ナレッジマネジメント
お役立ちガイド
ナレッジマネジメントのノウハウや、
効率化のポイントなど、
ビジネスで役立つ情報をご紹介します。
効率化のポイントなど、
ビジネスで役立つ情報をご紹介します。

最新記事
-
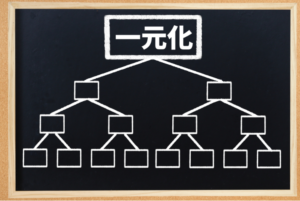 2025年03月27日情報の一元化とは?一元管理する方法やメリット、おすすめツールを紹介近年、インターネットの発達やAI技術の進歩によって、多くの情報が簡単に入手できるようになりました。企業においても社内情報のデータベースや顧客のビッグデータが積極的に活用されています。 一方で、「収集した情報を一元化したいが、どのように管理すれば良いかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、情報を一元化する方法やメリット、おすすめの情報管理ツールを中心にご紹介します。 社内情報を一元化するやり方を知りたい 情報を一元管理するメリットを把握したい 社内情報の一元管理に適したツールを探している という方はこの記事を参考にすると、社内に散在する情報を一元化して収集した情報をナレッジとして十分に活用できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 情報の一元化とは2 一元化すべき情報とは3 社内情報を一元化するメリット3.1 検索性が向上する3.2 業務の属人化を解消できる3.3 業務時間の短縮につながる4 【3ステップ】社内情報を一元管理する方法4.1 ステップ1|どこに何の情報があるのか整理する4.2 ステップ2|一元管理する情報を選定する4.3 ステップ3|ツールを選定する5 社内情報の一元化に最も適したツール5.1 社内のナレッジを一元管理して超高精度で検索できるツール「ナレカン」6 社内情報を一元管理するときの注意点7 社内情報を一元管理する方法やメリットまとめ 情報の一元化とは 情報の一元化とは、社内のあちこちに散らばっている情報を一箇所にまとめて管理することです。 顧客との商談記録や会議資料、マニュアルなど、社内情報は日々増えていきます。そのため、社員それぞれが自身のパソコンやストレージで業務情報を管理していると、担当者の不在時に対応が遅滞したり引き継ぎに時間がかかったりする恐れがあります。 また、情報を共有する場所を整備しておかないと業務ノウハウが属人化してしまい、ナレッジが社内に蓄積されていきません。したがって、社内情報を適切に管理・活用するためには情報を一元化して保管する場所を用意することが求められるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 一元化すべき情報とは 社内情報のなかでも、とくに一元化すべき情報には以下の3つがあります。 全社で共有するべき社内規定やお知らせ 社内規定の変更や社内行事のお知らせなどは、全社にすぐ共有し、常に全員が確認しやすいように管理しなくてはなりません。 顧客対応の記録や過去のトラブル事例 顧客との商談記録や過去のトラブル事例は、社内にナレッジとして蓄積し、必要なときに誰もが参考にできるようにしておきましょう。 業務に使うマニュアルや資料 頻繁に更新される業務マニュアルや社内資料は、一箇所にまとめて検索しやすいようにしておくべきです。 以上の3つを一元管理すれば、社内の情報に誰もが即アクセスできる状態になります。ただし、蓄積した情報は検索すれば確実に見つかるように「ナレカン」のような検索性に優れたツールで保管しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報を一元化するメリット 以下では、社内情報を一元化するメリットを解説します。社内情報の一元管理によって得られる効果を把握しきれていない担当者の方は必見です。 検索性が向上する 社内情報を一元化すると、検索性が向上します。 業務のマニュアルや会議資料が社内のあちこちに散在していると、どこに何を保存したかわからず、探すのに時間がかかります。また、そもそも業務ノウハウや手引書が共有されておらず、社員の頭の中や個人のパソコンの中にしか存在しない場合もあるのです。 そのため、社内の情報をまとめて保管しておく場所を決めておき、検索すれば必要な情報を必ず見つけられる状態を整備しましょう。 業務の属人化を解消できる 社内の情報を一元化すると、業務の属人化を解消できます。 社内で情報管理の方法が決まっていれば、共有や更新がしやすくなり、情報の属人化を防げるのです。ただし、ExcelやWordなどのファイル形式で共有すると、タイトルだけで中身を把握しづらくいちいちファイルを開く手間がかかります。 そのため、社内のマニュアルや過去事例などのナレッジは専用ツールで管理しましょう。たとえば、ナレッジ管理ツールの「ナレカン」は、AIによる添付ファイルの自動要約機能が備わっているので、既存のExcelファイルを貼り付けるだけで運用を始められます。 業務時間の短縮につながる 社内情報を一元管理すると、業務時間の短縮につながります。 社内文書や資料が複数のシステムやツールに分散していると、それぞれの場所をすべて検索しなくてはならず、煩わしいです。一方、社内情報を一元化して、「一箇所を検索すれば欲しい情報が必ず見つかる」という状態なら情報を探している時間を短縮できます。 そのため、本来の業務に時間をかけられるようになり、生産性が上がるのです。また、無駄な業務時間がなくなって社員の業務負担も減り、従業員満足度の向上も期待できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【3ステップ】社内情報を一元管理する方法 以下では、社内情報を一元管理する方法を3ステップでご紹介します。社内情報を一元化したいが、具体的な方法がわからないという担当者の方は必見です。 ステップ1|どこに何の情報があるのか整理する 社内情報を一元化する前に、まず「どこに何の情報があるのか」を整理しましょう。 たとえば、社内のファイルストレージや個人のパソコン、そもそもマニュアル化されていない暗黙知など、それぞれの場所にどんな情報が格納されているかを把握する必要があります。 社内に散在している情報を可視化することが、社内情報の一元化の最初のステップです。 ステップ2|一元管理する情報を選定する 次に、一元管理する情報を選定しましょう。 ステップ1で集めた社内情報にはさまざまな種類があるため、管理したい情報ごとにまとめます。たとえば、顧客データからグラフや表を作成したいのか、社内全体で活用する業務マニュアルやノウハウを蓄積したいのかによって、管理すべき情報が変わります。 また、重複していたり古くなっていたりする情報がないかも確認しておくことが重要です。 ステップ3|ツールを選定する 最後に、一元管理したい情報の種類と目的に合わせてツールを選定しましょう。 専用ツールがなくてもExcelなどで代用はできますが、運用ルールや使い方に工夫が必要です。とくに、ファイルでの管理は更新に手間がかかるうえ、タイトルからは内容を把握しづらく情報の検索性が低いので、社内でナレッジが活用されません。 そのため、顧客データの管理や売上予測にはCRMやSFAなどの専門ツール、社内全体で使うマニュアルや業務ノウハウの共有にはナレッジ管理専用ツールの利用が適しています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報の一元化に最も適したツール 以下では、社内情報の一元化に最も適したツールをご紹介します。 社内に散在する情報をナレッジ管理専用のツールで管理すれば、情報を探す時間が削減できて業務効率が上がります。また、共有ストレージや個人のパソコンに散在しているマニュアルやノウハウなどのナレッジを共有すれば、業務の属人化解消も期待できます。 ただし、ナレッジを一元管理しても社員が必要な情報に即アクセスできる検索性が備わっていなければ、「あるはずの情報が見つからない」という事態に陥ります。そこで、誰が検索しても欲しい情報へ確実にたどり着けるツールを導入しましょう。 結論、社内の情報を一元管理するなら、あらゆるファイル形式でナレッジを保管できてAIを活用したチャット形式の検索機能が備わった「ナレカン」が最適です。 ナレカンの「記事」には、ファイルやテキスト、画像などあらゆる形式の資料をまとめられ、検索すればナレカンAIが全ての資料から適切な情報を提示します。また、添付したファイルはAIが自動要約してくれるので、ファイルを開かずに内容を把握できるのです。 社内のナレッジを一元管理して超高精度で検索できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報を一元管理するときの注意点 社内情報を一元管理するときは、すでに社内に存在する情報を移管する手間がかかることに注意しましょう。 社内に散在しているマニュアルやノウハウを集めて、内容を精査・整理したうえでツールに移管しなくてはならないため、ある程度の手間と時間がかかります。そこで、既存の社内資料の移行支援をしてくれるなどのサポートがあるツールを選ぶと、導入がスムーズです。 たとえば、「ナレカン」は、社内の既存データの移行支援のほか、「メンバー登録」や「部署登録」などの初期設定支援やツールの利用状況レポートの利用が可能なので、導入・運用の負担を最小限に抑えられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報を一元管理する方法やメリットまとめ これまで、社内情報を一元管理する方法やメリットを中心にご紹介しました。 マニュアルや業務ノウハウなどの社内ナレッジを一元管理すると、社員が必要な情報を入手しやすくなり、業務効率の向上や属人化の解消に貢献します。また、社内情報の一元管理には専用ツールを使うと、管理や運用の手間が軽減されます。 ただし、大量の社内ナレッジから欲しい情報に即アクセスできるように、超高精度で検索できるツールを選びましょう。とくに、AIによるチャット形式での検索ができると、社員の検索スキルによらず思い通りの情報にたどり着けます。 したがって、社内情報を一元管理するなら、社内のあちこちに散らばったナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、スムーズに社内情報を一元化し、社内の業務効率を向上させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む
2025年03月27日情報の一元化とは?一元管理する方法やメリット、おすすめツールを紹介近年、インターネットの発達やAI技術の進歩によって、多くの情報が簡単に入手できるようになりました。企業においても社内情報のデータベースや顧客のビッグデータが積極的に活用されています。 一方で、「収集した情報を一元化したいが、どのように管理すれば良いかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、情報を一元化する方法やメリット、おすすめの情報管理ツールを中心にご紹介します。 社内情報を一元化するやり方を知りたい 情報を一元管理するメリットを把握したい 社内情報の一元管理に適したツールを探している という方はこの記事を参考にすると、社内に散在する情報を一元化して収集した情報をナレッジとして十分に活用できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 情報の一元化とは2 一元化すべき情報とは3 社内情報を一元化するメリット3.1 検索性が向上する3.2 業務の属人化を解消できる3.3 業務時間の短縮につながる4 【3ステップ】社内情報を一元管理する方法4.1 ステップ1|どこに何の情報があるのか整理する4.2 ステップ2|一元管理する情報を選定する4.3 ステップ3|ツールを選定する5 社内情報の一元化に最も適したツール5.1 社内のナレッジを一元管理して超高精度で検索できるツール「ナレカン」6 社内情報を一元管理するときの注意点7 社内情報を一元管理する方法やメリットまとめ 情報の一元化とは 情報の一元化とは、社内のあちこちに散らばっている情報を一箇所にまとめて管理することです。 顧客との商談記録や会議資料、マニュアルなど、社内情報は日々増えていきます。そのため、社員それぞれが自身のパソコンやストレージで業務情報を管理していると、担当者の不在時に対応が遅滞したり引き継ぎに時間がかかったりする恐れがあります。 また、情報を共有する場所を整備しておかないと業務ノウハウが属人化してしまい、ナレッジが社内に蓄積されていきません。したがって、社内情報を適切に管理・活用するためには情報を一元化して保管する場所を用意することが求められるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 一元化すべき情報とは 社内情報のなかでも、とくに一元化すべき情報には以下の3つがあります。 全社で共有するべき社内規定やお知らせ 社内規定の変更や社内行事のお知らせなどは、全社にすぐ共有し、常に全員が確認しやすいように管理しなくてはなりません。 顧客対応の記録や過去のトラブル事例 顧客との商談記録や過去のトラブル事例は、社内にナレッジとして蓄積し、必要なときに誰もが参考にできるようにしておきましょう。 業務に使うマニュアルや資料 頻繁に更新される業務マニュアルや社内資料は、一箇所にまとめて検索しやすいようにしておくべきです。 以上の3つを一元管理すれば、社内の情報に誰もが即アクセスできる状態になります。ただし、蓄積した情報は検索すれば確実に見つかるように「ナレカン」のような検索性に優れたツールで保管しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報を一元化するメリット 以下では、社内情報を一元化するメリットを解説します。社内情報の一元管理によって得られる効果を把握しきれていない担当者の方は必見です。 検索性が向上する 社内情報を一元化すると、検索性が向上します。 業務のマニュアルや会議資料が社内のあちこちに散在していると、どこに何を保存したかわからず、探すのに時間がかかります。また、そもそも業務ノウハウや手引書が共有されておらず、社員の頭の中や個人のパソコンの中にしか存在しない場合もあるのです。 そのため、社内の情報をまとめて保管しておく場所を決めておき、検索すれば必要な情報を必ず見つけられる状態を整備しましょう。 業務の属人化を解消できる 社内の情報を一元化すると、業務の属人化を解消できます。 社内で情報管理の方法が決まっていれば、共有や更新がしやすくなり、情報の属人化を防げるのです。ただし、ExcelやWordなどのファイル形式で共有すると、タイトルだけで中身を把握しづらくいちいちファイルを開く手間がかかります。 そのため、社内のマニュアルや過去事例などのナレッジは専用ツールで管理しましょう。たとえば、ナレッジ管理ツールの「ナレカン」は、AIによる添付ファイルの自動要約機能が備わっているので、既存のExcelファイルを貼り付けるだけで運用を始められます。 業務時間の短縮につながる 社内情報を一元管理すると、業務時間の短縮につながります。 社内文書や資料が複数のシステムやツールに分散していると、それぞれの場所をすべて検索しなくてはならず、煩わしいです。一方、社内情報を一元化して、「一箇所を検索すれば欲しい情報が必ず見つかる」という状態なら情報を探している時間を短縮できます。 そのため、本来の業務に時間をかけられるようになり、生産性が上がるのです。また、無駄な業務時間がなくなって社員の業務負担も減り、従業員満足度の向上も期待できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【3ステップ】社内情報を一元管理する方法 以下では、社内情報を一元管理する方法を3ステップでご紹介します。社内情報を一元化したいが、具体的な方法がわからないという担当者の方は必見です。 ステップ1|どこに何の情報があるのか整理する 社内情報を一元化する前に、まず「どこに何の情報があるのか」を整理しましょう。 たとえば、社内のファイルストレージや個人のパソコン、そもそもマニュアル化されていない暗黙知など、それぞれの場所にどんな情報が格納されているかを把握する必要があります。 社内に散在している情報を可視化することが、社内情報の一元化の最初のステップです。 ステップ2|一元管理する情報を選定する 次に、一元管理する情報を選定しましょう。 ステップ1で集めた社内情報にはさまざまな種類があるため、管理したい情報ごとにまとめます。たとえば、顧客データからグラフや表を作成したいのか、社内全体で活用する業務マニュアルやノウハウを蓄積したいのかによって、管理すべき情報が変わります。 また、重複していたり古くなっていたりする情報がないかも確認しておくことが重要です。 ステップ3|ツールを選定する 最後に、一元管理したい情報の種類と目的に合わせてツールを選定しましょう。 専用ツールがなくてもExcelなどで代用はできますが、運用ルールや使い方に工夫が必要です。とくに、ファイルでの管理は更新に手間がかかるうえ、タイトルからは内容を把握しづらく情報の検索性が低いので、社内でナレッジが活用されません。 そのため、顧客データの管理や売上予測にはCRMやSFAなどの専門ツール、社内全体で使うマニュアルや業務ノウハウの共有にはナレッジ管理専用ツールの利用が適しています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報の一元化に最も適したツール 以下では、社内情報の一元化に最も適したツールをご紹介します。 社内に散在する情報をナレッジ管理専用のツールで管理すれば、情報を探す時間が削減できて業務効率が上がります。また、共有ストレージや個人のパソコンに散在しているマニュアルやノウハウなどのナレッジを共有すれば、業務の属人化解消も期待できます。 ただし、ナレッジを一元管理しても社員が必要な情報に即アクセスできる検索性が備わっていなければ、「あるはずの情報が見つからない」という事態に陥ります。そこで、誰が検索しても欲しい情報へ確実にたどり着けるツールを導入しましょう。 結論、社内の情報を一元管理するなら、あらゆるファイル形式でナレッジを保管できてAIを活用したチャット形式の検索機能が備わった「ナレカン」が最適です。 ナレカンの「記事」には、ファイルやテキスト、画像などあらゆる形式の資料をまとめられ、検索すればナレカンAIが全ての資料から適切な情報を提示します。また、添付したファイルはAIが自動要約してくれるので、ファイルを開かずに内容を把握できるのです。 社内のナレッジを一元管理して超高精度で検索できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報を一元管理するときの注意点 社内情報を一元管理するときは、すでに社内に存在する情報を移管する手間がかかることに注意しましょう。 社内に散在しているマニュアルやノウハウを集めて、内容を精査・整理したうえでツールに移管しなくてはならないため、ある程度の手間と時間がかかります。そこで、既存の社内資料の移行支援をしてくれるなどのサポートがあるツールを選ぶと、導入がスムーズです。 たとえば、「ナレカン」は、社内の既存データの移行支援のほか、「メンバー登録」や「部署登録」などの初期設定支援やツールの利用状況レポートの利用が可能なので、導入・運用の負担を最小限に抑えられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報を一元管理する方法やメリットまとめ これまで、社内情報を一元管理する方法やメリットを中心にご紹介しました。 マニュアルや業務ノウハウなどの社内ナレッジを一元管理すると、社員が必要な情報を入手しやすくなり、業務効率の向上や属人化の解消に貢献します。また、社内情報の一元管理には専用ツールを使うと、管理や運用の手間が軽減されます。 ただし、大量の社内ナレッジから欲しい情報に即アクセスできるように、超高精度で検索できるツールを選びましょう。とくに、AIによるチャット形式での検索ができると、社員の検索スキルによらず思い通りの情報にたどり着けます。 したがって、社内情報を一元管理するなら、社内のあちこちに散らばったナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、スムーズに社内情報を一元化し、社内の業務効率を向上させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む -
 2025年03月27日社内システムとは?内製化のデメリットや解決策を紹介!DXが進む今日、業務の効率化やペーパーレス化などの目的で、あらゆる企業が社内システムを導入しています。 しかし、「社内システムを導入したいが、自社に適したものが分からず困っている」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内システムが使いづらい原因や解決策を中心にご紹介します。 新たに社内システムを導入して業務効率化を実現したい 社内システムが使いづらい原因と解決策を把握したい すぐに運用に乗せられるような社内システムを探している という方はこの記事を参考にすると、社内システムが使いづらい原因が分かるだけでなく、簡単に業務効率化をする方法までわかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 社内システムとは2 社内システムが使いづらい3つの原因2.1 (1)導入前の準備が不十分2.2 (2)システムが複雑化している2.3 (3)導入後のサポートができていない3 社内システムを内製化するデメリット3.1 (1)開発・運用コストがかかる3.2 (2)エンジニアの人員を確保する必要がある3.3 (3)システムの品質が低下する恐れがある4 【必見】開発不要で簡単に業務効率化を実現する方法4.1 誰でも簡単に社内情報を管理できるツール「ナレカン」5 社内システムの運用におけるポイント6 社内システムが使いづらい原因や解決策まとめ 社内システムとは 社内システムとは、社内で使用する業務システム全般のことです。 具体的には、販売管理システムや勤怠管理システム、顧客管理システムなどを指します。これらのシステムは利益に直結するものではありませんが、自社の業務を円滑かつ効率的に進め、生産性を向上させる点において重要な役割を果たすのです。 また、システム導入の選択肢としては、「既製品のツールを利用する」「社内でシステムを構築する」の2つが挙げられます。コストや社員のITスキルを考慮したうえで、自社に適した方を選択しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムが使いづらい3つの原因 以下では、社内システムが使いづらい3つの原因をご紹介します。社内システムが使いづらく悩んでいる方は必見です。 (1)導入前の準備が不十分 1つ目の原因は、導入前の準備が不十分である点です。 とくに準備不足になりやすい点として、必要な機能の選定が挙げられます。現場の業務を十分に理解せずに機能を選定すると、理想的なフローに合っていても実際には使いづらいシステムになってしまうのです。 また、内製する場合は開発計画が不十分であると、開発に過剰な時間がかかったりリソース不足になったりする可能性があります。したがって、システムの導入や内製にあたっては入念な準備を心掛けましょう。 (2)システムが複雑化している 2つ目の原因は、システムが複雑している点です。 システムの改良や修正を繰り返した結果、似たような機能が複数存在したり、機能が多すぎたりしてシステムが複雑化してしまう場合があります。そのため、かえって使いづらくなり、業務効率の低下を招いてしまうのです。 そのため、社員の意見を定期的に聞き、機能の重複や不要な機能を見直して必要な機能のみが搭載されたシステムを導入することが重要です。 (3)導入後のサポートができていない 3つ目の原因は、導入後のサポートができていない点です。 どれだけ高性能なシステムを導入しても、社内で定着しなければ意味がありません。システムの運用こそが本番であり、そのためにはサポートが欠かせないのです。 したがって、システムを内製する場合は社内の情報システム部や、各部署のITに強い人材を中心にサポート対応をしましょう。既存のシステムを利用する場合は、導入サポートが充実しているか十分確認しておく必要があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムを内製化するデメリット 以下では、社内システムを自社で構築するデメリットを3つご紹介します。社内システムの内製化を検討している方は、必ず確認しましょう。 (1)開発・運用コストがかかる デメリット1つ目は、開発・運用コストがかかる点です。 システム開発の場合、パソコン端末やサーバー、ネットワークなどのハードウェアや、業務管理を行うソフトウェアの準備が必要になります。また、作業場所の確保や備品の用意もしなければなりません。 そのため、「予想以上のコストが発生した」という事態を防ぐには、あらかじめ必要な設備や道具、その費用を試算しておくことが重要です。さらに、初期費用だけでなく、保守や運用にコストも考慮しておきましょう。 (2)エンジニアの人員を確保する必要がある デメリット2つ目は、エンジニアの人員確保が必要な点です。 システム開発の内製化において、必要なスキルを持つ人材を揃えることは必須です。そのためには、既存社員の育成するか、外部から人材を採用する必要があります。 しかし、外部委託が長期にわたると社内に知識を持つ人材が不足しやすく、育成に時間を要します。また、確保した人材が異動・退職するときには、引き継ぎが欠かせない点にも注意しましょう。 (3)システムの品質が低下する恐れがある デメリット3つ目は、システムの品質が低下する恐れがある点です。 内製化すると、システム開発を専門とする企業に依頼するよりも技術やノウハウが不足しやすく、システムの機能が求めていたレベルに届かない恐れがあります。結果として、システムエラーが発生したり改良・修正に手間がかかり、業務効率が下がってしまうのです。 そのため、内製化でシステムの品質を維持するには、十分なスキルを持つ人材を確保し、継続的な教育とサポート体制を整えなければなりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】開発不要で簡単に業務効率化を実現する方法 以下では、開発不要で簡単に業務効率化を実現できるITツールをご紹介します。 社内システムを導入すれば、円滑に業務を進められ業務効率の向上が期待できます。しかし、自社で開発をするとなると多大なコストがかかるうえ、検証や改修も自社で実施する必要があるため、かえって業務量が増え対応が追いつかなくなる恐れがあるのです。 そこで、「社内のあらゆる情報を一元管理できるITツール」を導入し、業務効率化を実現させましょう。しかし、多機能で複雑なツールでは使いこなせず、社内情報が散在してしまうため「シンプルな操作性で目的の情報へアクセスしやすいツール」を選ぶべきです。 結論、社内の業務効率化には、誰でも簡単に社内情報を管理でき、高精度の検索機能で目的の情報に即アクセス可能な「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、テキストやファイルを残してすばやく共有でき、「キーワード検索」やAIを活用した「自然言語検索」などの機能で欲しい情報をすぐに見つけられます。また、既存データの移行支援等のサポートによってすぐに運用に乗せられるのです。 誰でも簡単に社内情報を管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムの運用におけるポイント ここでは、社内システムの運用におけるポイントをご紹介します。システムの運用方法に不安がある方は、以下を参考にしましょう。 システムの導入目的を明確にする 社内システムの導入目的を明確にすることで、社員がその重要性を理解し、システムを活用しやすくなります。また、どの機能がどの分野の目標達成に役立つかを理解できるのです。 継続的なサポートを実施する システム導入後も、トラブルへの迅速な対応や定期的なメンテナンスなど、継続的なサポートを提供することが重要です。また、実際にシステムを使用する社員の意見も積極的に反映させましょう。 以上のように、効果的な社内システムの運用を目指しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムが使いづらい原因や解決策まとめ これまで、社内システムが使いづらい原因や内製化のデメリット、運用ポイントを中心にご紹介しました。 社内システムを活用することで、業務の効率化や生産性の向上につながります。しかし、内製化する場合、開発コストがかかるだけでなく、人材育成や定期的なサポートなどにより、業務負担が大きくなってしまうのです。 そこで、「社内のナレッジを一元管理できるITツール」を導入すれば、開発不要で業務効率化を実現できます。ただし、複雑なツールでは使いこなせず放置されてしまう恐れがあるため、「シンプルな操作性であるか」を確認しましょう。 結論、自社が導入すべきなのは、社内のあらゆる情報を一元管理でき、目的の情報がすぐに見つかる「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、社内の業務を円滑に進めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む
2025年03月27日社内システムとは?内製化のデメリットや解決策を紹介!DXが進む今日、業務の効率化やペーパーレス化などの目的で、あらゆる企業が社内システムを導入しています。 しかし、「社内システムを導入したいが、自社に適したものが分からず困っている」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内システムが使いづらい原因や解決策を中心にご紹介します。 新たに社内システムを導入して業務効率化を実現したい 社内システムが使いづらい原因と解決策を把握したい すぐに運用に乗せられるような社内システムを探している という方はこの記事を参考にすると、社内システムが使いづらい原因が分かるだけでなく、簡単に業務効率化をする方法までわかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 社内システムとは2 社内システムが使いづらい3つの原因2.1 (1)導入前の準備が不十分2.2 (2)システムが複雑化している2.3 (3)導入後のサポートができていない3 社内システムを内製化するデメリット3.1 (1)開発・運用コストがかかる3.2 (2)エンジニアの人員を確保する必要がある3.3 (3)システムの品質が低下する恐れがある4 【必見】開発不要で簡単に業務効率化を実現する方法4.1 誰でも簡単に社内情報を管理できるツール「ナレカン」5 社内システムの運用におけるポイント6 社内システムが使いづらい原因や解決策まとめ 社内システムとは 社内システムとは、社内で使用する業務システム全般のことです。 具体的には、販売管理システムや勤怠管理システム、顧客管理システムなどを指します。これらのシステムは利益に直結するものではありませんが、自社の業務を円滑かつ効率的に進め、生産性を向上させる点において重要な役割を果たすのです。 また、システム導入の選択肢としては、「既製品のツールを利用する」「社内でシステムを構築する」の2つが挙げられます。コストや社員のITスキルを考慮したうえで、自社に適した方を選択しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムが使いづらい3つの原因 以下では、社内システムが使いづらい3つの原因をご紹介します。社内システムが使いづらく悩んでいる方は必見です。 (1)導入前の準備が不十分 1つ目の原因は、導入前の準備が不十分である点です。 とくに準備不足になりやすい点として、必要な機能の選定が挙げられます。現場の業務を十分に理解せずに機能を選定すると、理想的なフローに合っていても実際には使いづらいシステムになってしまうのです。 また、内製する場合は開発計画が不十分であると、開発に過剰な時間がかかったりリソース不足になったりする可能性があります。したがって、システムの導入や内製にあたっては入念な準備を心掛けましょう。 (2)システムが複雑化している 2つ目の原因は、システムが複雑している点です。 システムの改良や修正を繰り返した結果、似たような機能が複数存在したり、機能が多すぎたりしてシステムが複雑化してしまう場合があります。そのため、かえって使いづらくなり、業務効率の低下を招いてしまうのです。 そのため、社員の意見を定期的に聞き、機能の重複や不要な機能を見直して必要な機能のみが搭載されたシステムを導入することが重要です。 (3)導入後のサポートができていない 3つ目の原因は、導入後のサポートができていない点です。 どれだけ高性能なシステムを導入しても、社内で定着しなければ意味がありません。システムの運用こそが本番であり、そのためにはサポートが欠かせないのです。 したがって、システムを内製する場合は社内の情報システム部や、各部署のITに強い人材を中心にサポート対応をしましょう。既存のシステムを利用する場合は、導入サポートが充実しているか十分確認しておく必要があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムを内製化するデメリット 以下では、社内システムを自社で構築するデメリットを3つご紹介します。社内システムの内製化を検討している方は、必ず確認しましょう。 (1)開発・運用コストがかかる デメリット1つ目は、開発・運用コストがかかる点です。 システム開発の場合、パソコン端末やサーバー、ネットワークなどのハードウェアや、業務管理を行うソフトウェアの準備が必要になります。また、作業場所の確保や備品の用意もしなければなりません。 そのため、「予想以上のコストが発生した」という事態を防ぐには、あらかじめ必要な設備や道具、その費用を試算しておくことが重要です。さらに、初期費用だけでなく、保守や運用にコストも考慮しておきましょう。 (2)エンジニアの人員を確保する必要がある デメリット2つ目は、エンジニアの人員確保が必要な点です。 システム開発の内製化において、必要なスキルを持つ人材を揃えることは必須です。そのためには、既存社員の育成するか、外部から人材を採用する必要があります。 しかし、外部委託が長期にわたると社内に知識を持つ人材が不足しやすく、育成に時間を要します。また、確保した人材が異動・退職するときには、引き継ぎが欠かせない点にも注意しましょう。 (3)システムの品質が低下する恐れがある デメリット3つ目は、システムの品質が低下する恐れがある点です。 内製化すると、システム開発を専門とする企業に依頼するよりも技術やノウハウが不足しやすく、システムの機能が求めていたレベルに届かない恐れがあります。結果として、システムエラーが発生したり改良・修正に手間がかかり、業務効率が下がってしまうのです。 そのため、内製化でシステムの品質を維持するには、十分なスキルを持つ人材を確保し、継続的な教育とサポート体制を整えなければなりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】開発不要で簡単に業務効率化を実現する方法 以下では、開発不要で簡単に業務効率化を実現できるITツールをご紹介します。 社内システムを導入すれば、円滑に業務を進められ業務効率の向上が期待できます。しかし、自社で開発をするとなると多大なコストがかかるうえ、検証や改修も自社で実施する必要があるため、かえって業務量が増え対応が追いつかなくなる恐れがあるのです。 そこで、「社内のあらゆる情報を一元管理できるITツール」を導入し、業務効率化を実現させましょう。しかし、多機能で複雑なツールでは使いこなせず、社内情報が散在してしまうため「シンプルな操作性で目的の情報へアクセスしやすいツール」を選ぶべきです。 結論、社内の業務効率化には、誰でも簡単に社内情報を管理でき、高精度の検索機能で目的の情報に即アクセス可能な「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、テキストやファイルを残してすばやく共有でき、「キーワード検索」やAIを活用した「自然言語検索」などの機能で欲しい情報をすぐに見つけられます。また、既存データの移行支援等のサポートによってすぐに運用に乗せられるのです。 誰でも簡単に社内情報を管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムの運用におけるポイント ここでは、社内システムの運用におけるポイントをご紹介します。システムの運用方法に不安がある方は、以下を参考にしましょう。 システムの導入目的を明確にする 社内システムの導入目的を明確にすることで、社員がその重要性を理解し、システムを活用しやすくなります。また、どの機能がどの分野の目標達成に役立つかを理解できるのです。 継続的なサポートを実施する システム導入後も、トラブルへの迅速な対応や定期的なメンテナンスなど、継続的なサポートを提供することが重要です。また、実際にシステムを使用する社員の意見も積極的に反映させましょう。 以上のように、効果的な社内システムの運用を目指しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムが使いづらい原因や解決策まとめ これまで、社内システムが使いづらい原因や内製化のデメリット、運用ポイントを中心にご紹介しました。 社内システムを活用することで、業務の効率化や生産性の向上につながります。しかし、内製化する場合、開発コストがかかるだけでなく、人材育成や定期的なサポートなどにより、業務負担が大きくなってしまうのです。 そこで、「社内のナレッジを一元管理できるITツール」を導入すれば、開発不要で業務効率化を実現できます。ただし、複雑なツールでは使いこなせず放置されてしまう恐れがあるため、「シンプルな操作性であるか」を確認しましょう。 結論、自社が導入すべきなのは、社内のあらゆる情報を一元管理でき、目的の情報がすぐに見つかる「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、社内の業務を円滑に進めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む -
 2025年03月27日基幹システムとは?ERPとの違いや選定ポイントをわかりやすく解説基幹システムとは、企業の主要部分となる業務を効率化するシステムです。ただし、企業によって主要となる業務は異なるので、基幹システムと一口に言っても種類は多岐にわたります。 そのため、「基幹システムを導入したいが、具体的にどのようなシステムがあるのかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、基幹システムの概要や選定ポイントを中心にご紹介します。 基幹システムの概要を把握したい 基幹システムとERPとの違いを知りたい 導入した基幹システムを社内に浸透させる方法を探している という方はこの記事を参考にすると、基幹システムにどのような種類があるかだけでなく、導入した基幹システムを社内に浸透させる方法までわかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 基幹システムとは1.1 ERPとの違い1.2 SAPとの違い2 基幹システムの主な機能3 基幹システムの選定ポイント3選3.1 (1)クラウド型かオンプレミス型か3.2 (2)自社の業務内容に合っているか3.3 (3)導入・運用のサポートが手厚いか4 社内の基幹システムの運用を円滑にするツール4.1 基幹システムの操作マニュアルを一元管理できるツール「ナレカン」5 基幹システムの概要や選定ポイントまとめ 基幹システムとは ここでは、基幹システムの概要についてわかりやすく解説します。基幹システムが具体的にどのようなものかわからないという方は必見です。 ERPとの違い 基幹システムは、労務部や経理部などの各部署で利用される、業務を円滑化するためのシステムを指すのに対し、ERPは各部門の基幹システムを連携し、データを一元管理するシステムを指します。 そもそも、ERPとはEnterprise Resource Planningの略で、日本語では「企業資源計画」と訳されるものです。しかし近年では、企業内の資源を適切に配置するためのシステムそのものをERPと呼称しています。 つまり、基幹システムをまとめて管理しているのがERPです。 SAPとの違い SAPは、基幹システムのうちの一つです。 SAPとは、ドイツのSAP社が提供する基幹システムの名称で、多くの日本企業に導入されています。 そのため、基幹システムという意味でSAPという言葉が使われる場合もあります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 基幹システムの主な機能 基幹システムの主な機能は、以下の6つです。 生産管理 生産管理システムは、製造計画を立てたり受注状況から材料の調達量を決定したりするのに必要な機能で、主に製造業で利用されます。在庫管理システムと連携して、無駄のない事業運営に貢献します。 在庫管理 在庫管理システムは、在庫数や棚卸し業務を支援するシステムで、在庫を抱えすぎたり欠品が発生したりするのを防ぎます。会社の利益に関わる重要な業務なので、システムの導入によって人為的なミスを軽減しましょう。 販売管理 販売管理システムは、受注や売上などを管理するシステムで、製造業や流通業の会社では必須です。在庫管理システムや生産管理システムと連携して、企業の一連の業務を円滑に進めます。 労務管理 労務管理システムは、社員の給与や就労時間の管理、採用活動の支援に利用されるシステムです。業種問わず必要な業務であるため、労務管理業務を適切に実施することで、社内の人的リソースの配分や人事評価の円滑な実施に役立ちます。 財務会計 財務会計システムは、会社の財務・会計を効率化するシステムです。会計帳票や決算書の作成の一部を自動化して、業務負荷を軽減できます。 情報管理 情報管理システムは、社内の情報を一元管理し、必要なデータに即座にアクセスできるようにするシステムです。社内システムのマニュアルや業務ノウハウなどの情報資産(ナレッジ)の管理は、企業の基盤になるのでシステムで効率化しましょう。 ただし、システムによって対応している業務範囲や利用方法が異なるので、システムを導入するときは各システムを比較して慎重に検討を進めることが重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 基幹システムの選定ポイント3選 ここでは、基幹システムの選定ポイントをご紹介します。自社に基幹システムを導入するときは以下の選定ポイントを参考にしましょう。 (1)クラウド型かオンプレミス型か 基幹システムの選定ポイントの1つ目は、クラウド型かオンプレミス型かです。 オンプレミス型は、自社のサーバを利用するためセキュリティが強固ですが、ピーク時の稼働量に合わせてストレージ容量を決めるので、稼働量が少ない最初のうちは費用対効果が低くなる恐れがあります。また、メンテナンスの手間がかかる点にも注意しましょう。 一方、クラウド型はオンラインで提供されているサービスを利用するので、自社でメンテナンスする必要がありません。また、現時点で必要なストレージ容量を確保すれば良いため、費用を抑えられるのです。 そのため、費用を抑えて自社の業務効率を向上させたい場合は、クラウド型のシステムを利用するのがおすすめです。 (2)自社の業務内容に合っているか 基幹システムの選定ポイントの2つ目は、自社の業務内容に合っているかです。 基幹システムは、同じ機能を持つものでもシステムによって対応している業務や操作方法が異なります。そのため、自社の業務内容に必要な機能を見極めなければ、かえって業務が遅滞したり不要な機能に利用料金を払ったりする恐れがあるのです。 したがって、基幹システムをどのように利用したいのかを明確にしたうえで導入するシステムを決定しましょう。 (3)導入・運用のサポートが手厚いか 基幹システムの選定ポイントの3つ目は、導入・運用のサポートが手厚いかです。 基幹システムを導入しても、操作が複雑すぎて社員が使いこなせなければ社内に浸透せず、システムが形骸化してしまいます。そのため、自社に新しいシステムやツールを導入するときは、導入・運用のサポートが充実しているかを必ず確認するべきです。 たとえば、社内情報の管理には既存の社内情報のデータ移管がある「ナレカン」のようなシステムを利用すると、導入から運用までがスムーズです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内の基幹システムの運用を円滑にするツール 以下では、社内の基幹システムの運用を円滑にするツールをご紹介します。 基幹システムは、財務管理や労務管理、在庫管理など企業が事業を運営するうえで必須の機能を備えています。しかし、システムの操作方法や業務での利用方法を社内で共有しなくては、導入したシステムが現場で使われず、形骸化する恐れがあるのです。 そのため、基幹システムの機能の中でも情報管理がとくに重要です。ただし、基幹システムのマニュアルなどの社内情報をファイルストレージや操作の複雑なシステム上で共有すると他のファイルに埋もれたり、探すのに時間がかかったりします。 したがって、社内情報は誰もが即アクセスできるよう、検索性に優れたツールで保管しましょう。結論、社内のあらゆるナレッジを一元管理するなら、格納した情報をAI検索によって必要なときにすぐ確認できるツール「ナレカン」が最適です。 ナレカンの「記事」に記載した情報は、”上司に話しかけるように”口語で検索できるので、誰が検索しても欲しい情報を確実に見つけられます。また、添付画像内の文章も検索可能なので、ファイルの中身をいちいち開いて確認する手間が一切かかりません。 基幹システムの操作マニュアルを一元管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 基幹システムの概要や選定ポイントまとめ これまで、基幹システムの概要や選定ポイントを中心にご紹介しました。 基幹システムは、企業の中心となる業務を円滑に進めるために必要です。とくに、社内の情報資産(ナレッジ)の管理は業種・業態問わず重要なので、検索性に優れたシステムで情報を一元管理しましょう。 なかでも、AIによるチャット形式での検索が可能なシステムであれば、検索したいキーワードを一字一句覚えていなくてもあいまい検索で欲しい情報にたどり着けます。 したがって、情報管理機能を備えた基幹システムを導入するなら、社内の情報資産を守りつつ、欲しい情報にストレスなく即アクセスできるシステム「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、誰もが必要なときに欲しい社内情報を見つけられるようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む
2025年03月27日基幹システムとは?ERPとの違いや選定ポイントをわかりやすく解説基幹システムとは、企業の主要部分となる業務を効率化するシステムです。ただし、企業によって主要となる業務は異なるので、基幹システムと一口に言っても種類は多岐にわたります。 そのため、「基幹システムを導入したいが、具体的にどのようなシステムがあるのかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、基幹システムの概要や選定ポイントを中心にご紹介します。 基幹システムの概要を把握したい 基幹システムとERPとの違いを知りたい 導入した基幹システムを社内に浸透させる方法を探している という方はこの記事を参考にすると、基幹システムにどのような種類があるかだけでなく、導入した基幹システムを社内に浸透させる方法までわかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 基幹システムとは1.1 ERPとの違い1.2 SAPとの違い2 基幹システムの主な機能3 基幹システムの選定ポイント3選3.1 (1)クラウド型かオンプレミス型か3.2 (2)自社の業務内容に合っているか3.3 (3)導入・運用のサポートが手厚いか4 社内の基幹システムの運用を円滑にするツール4.1 基幹システムの操作マニュアルを一元管理できるツール「ナレカン」5 基幹システムの概要や選定ポイントまとめ 基幹システムとは ここでは、基幹システムの概要についてわかりやすく解説します。基幹システムが具体的にどのようなものかわからないという方は必見です。 ERPとの違い 基幹システムは、労務部や経理部などの各部署で利用される、業務を円滑化するためのシステムを指すのに対し、ERPは各部門の基幹システムを連携し、データを一元管理するシステムを指します。 そもそも、ERPとはEnterprise Resource Planningの略で、日本語では「企業資源計画」と訳されるものです。しかし近年では、企業内の資源を適切に配置するためのシステムそのものをERPと呼称しています。 つまり、基幹システムをまとめて管理しているのがERPです。 SAPとの違い SAPは、基幹システムのうちの一つです。 SAPとは、ドイツのSAP社が提供する基幹システムの名称で、多くの日本企業に導入されています。 そのため、基幹システムという意味でSAPという言葉が使われる場合もあります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 基幹システムの主な機能 基幹システムの主な機能は、以下の6つです。 生産管理 生産管理システムは、製造計画を立てたり受注状況から材料の調達量を決定したりするのに必要な機能で、主に製造業で利用されます。在庫管理システムと連携して、無駄のない事業運営に貢献します。 在庫管理 在庫管理システムは、在庫数や棚卸し業務を支援するシステムで、在庫を抱えすぎたり欠品が発生したりするのを防ぎます。会社の利益に関わる重要な業務なので、システムの導入によって人為的なミスを軽減しましょう。 販売管理 販売管理システムは、受注や売上などを管理するシステムで、製造業や流通業の会社では必須です。在庫管理システムや生産管理システムと連携して、企業の一連の業務を円滑に進めます。 労務管理 労務管理システムは、社員の給与や就労時間の管理、採用活動の支援に利用されるシステムです。業種問わず必要な業務であるため、労務管理業務を適切に実施することで、社内の人的リソースの配分や人事評価の円滑な実施に役立ちます。 財務会計 財務会計システムは、会社の財務・会計を効率化するシステムです。会計帳票や決算書の作成の一部を自動化して、業務負荷を軽減できます。 情報管理 情報管理システムは、社内の情報を一元管理し、必要なデータに即座にアクセスできるようにするシステムです。社内システムのマニュアルや業務ノウハウなどの情報資産(ナレッジ)の管理は、企業の基盤になるのでシステムで効率化しましょう。 ただし、システムによって対応している業務範囲や利用方法が異なるので、システムを導入するときは各システムを比較して慎重に検討を進めることが重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 基幹システムの選定ポイント3選 ここでは、基幹システムの選定ポイントをご紹介します。自社に基幹システムを導入するときは以下の選定ポイントを参考にしましょう。 (1)クラウド型かオンプレミス型か 基幹システムの選定ポイントの1つ目は、クラウド型かオンプレミス型かです。 オンプレミス型は、自社のサーバを利用するためセキュリティが強固ですが、ピーク時の稼働量に合わせてストレージ容量を決めるので、稼働量が少ない最初のうちは費用対効果が低くなる恐れがあります。また、メンテナンスの手間がかかる点にも注意しましょう。 一方、クラウド型はオンラインで提供されているサービスを利用するので、自社でメンテナンスする必要がありません。また、現時点で必要なストレージ容量を確保すれば良いため、費用を抑えられるのです。 そのため、費用を抑えて自社の業務効率を向上させたい場合は、クラウド型のシステムを利用するのがおすすめです。 (2)自社の業務内容に合っているか 基幹システムの選定ポイントの2つ目は、自社の業務内容に合っているかです。 基幹システムは、同じ機能を持つものでもシステムによって対応している業務や操作方法が異なります。そのため、自社の業務内容に必要な機能を見極めなければ、かえって業務が遅滞したり不要な機能に利用料金を払ったりする恐れがあるのです。 したがって、基幹システムをどのように利用したいのかを明確にしたうえで導入するシステムを決定しましょう。 (3)導入・運用のサポートが手厚いか 基幹システムの選定ポイントの3つ目は、導入・運用のサポートが手厚いかです。 基幹システムを導入しても、操作が複雑すぎて社員が使いこなせなければ社内に浸透せず、システムが形骸化してしまいます。そのため、自社に新しいシステムやツールを導入するときは、導入・運用のサポートが充実しているかを必ず確認するべきです。 たとえば、社内情報の管理には既存の社内情報のデータ移管がある「ナレカン」のようなシステムを利用すると、導入から運用までがスムーズです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内の基幹システムの運用を円滑にするツール 以下では、社内の基幹システムの運用を円滑にするツールをご紹介します。 基幹システムは、財務管理や労務管理、在庫管理など企業が事業を運営するうえで必須の機能を備えています。しかし、システムの操作方法や業務での利用方法を社内で共有しなくては、導入したシステムが現場で使われず、形骸化する恐れがあるのです。 そのため、基幹システムの機能の中でも情報管理がとくに重要です。ただし、基幹システムのマニュアルなどの社内情報をファイルストレージや操作の複雑なシステム上で共有すると他のファイルに埋もれたり、探すのに時間がかかったりします。 したがって、社内情報は誰もが即アクセスできるよう、検索性に優れたツールで保管しましょう。結論、社内のあらゆるナレッジを一元管理するなら、格納した情報をAI検索によって必要なときにすぐ確認できるツール「ナレカン」が最適です。 ナレカンの「記事」に記載した情報は、”上司に話しかけるように”口語で検索できるので、誰が検索しても欲しい情報を確実に見つけられます。また、添付画像内の文章も検索可能なので、ファイルの中身をいちいち開いて確認する手間が一切かかりません。 基幹システムの操作マニュアルを一元管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 基幹システムの概要や選定ポイントまとめ これまで、基幹システムの概要や選定ポイントを中心にご紹介しました。 基幹システムは、企業の中心となる業務を円滑に進めるために必要です。とくに、社内の情報資産(ナレッジ)の管理は業種・業態問わず重要なので、検索性に優れたシステムで情報を一元管理しましょう。 なかでも、AIによるチャット形式での検索が可能なシステムであれば、検索したいキーワードを一字一句覚えていなくてもあいまい検索で欲しい情報にたどり着けます。 したがって、情報管理機能を備えた基幹システムを導入するなら、社内の情報資産を守りつつ、欲しい情報にストレスなく即アクセスできるシステム「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、誰もが必要なときに欲しい社内情報を見つけられるようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む -
 2025年03月27日【事例あり】社内イントラとは?導入する目的や作成方法を解説!社内イントラとは、「組織内の情報通信網」のことを指します。社内イントラを構築することで、迅速な情報共有が可能となり、業務効率化が実現できます。 とはいえ、「社内イントラをどのように構築すればいいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内イントラの目的や作成方法を中心にご紹介します。 社内イントラの作成方法を知りたい 事例を参考にして社内イントラを構築したい 業務を効率化できる社内イントラツールを探している という方はこの記事を参考にすると、社内イントラの構築方法が分かり、組織全体の生産性向上が期待できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 社内イントラとは1.1 社内イントラの概要1.2 社内イントラと社内ポータルサイトの違い2 社内イントラを作成するメリット2.1 (1)迅速な情報共有が実現できる2.2 (2)社内コミュニケーションが円滑になる2.3 (3)コストを削減できる3 社内イントラの作り方4 最も簡単に社内イントラを構築できるツール4.1 必要な社内情報が即見つかるようになるツール「ナレカン」5 社内イントラネットの活用事例6 社内イントラを導入する目的や作成方法まとめ 社内イントラとは ここでは、社内イントラの概要や社内ポータルサイトとの違いを解説します。「社内イントラが何か分からない」という方は必見です。 社内イントラの概要 社内イントラとは、社内イントラネット(intranet)の略語で、社内のみで使えるネットワークのことです。 社内イントラを活用すれば、社内文書やファイルを安全に共有できます。また、場所や時間を問わず作業が可能になるほか、社員同士の情報共有や連携がスムーズになるのです。 社内イントラと社内ポータルサイトの違い 社内イントラと社内ポータルサイトは、閲覧制限の厳しさが異なります。 社内ポータルサイトは、「URLを知っている社員なら誰でも社内向けのサービスや社内情報を検索・閲覧できる」のに対し、社内イントラは「社内の限られた空間、あるいは端末からのみアクセスできる情報通信網」です。 一方で、社内イントラも社内ポータルサイトも「社内の情報を一元管理してアクセスしやすくしている」点は同じです。 社内で情報が散在していると、必要な情報を探すのに手間がかかり、業務の対応漏れや作業効率の低下につながります。そのため、社内イントラを活用して、社内文書やマニュアルなどのナレッジに即アクセスできるようにしておきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラを作成するメリット ここでは、社内イントラを作成するメリットについて解説します。社内イントラを作成するかを悩んでいる方は必見です。 (1)迅速な情報共有が実現できる 1つ目のメリットは、迅速な情報共有が実現できる点です。 社内イントラにより、「ツールを見れば全ての社内情報を確認できる」といった環境を整えられます。そのため、特定の社員や個人に情報や業務が偏ってしまう課題を解消できます。 このように、社内イントラを作ると、迅速な情報共有が可能となり、業務の属人化防止につながるのです。 (2)社内コミュニケーションが円滑になる 2つ目のメリットは、社内コミュニケーションが円滑になる点です。 社内イントラを構築することで、部署を超えた情報共有が容易になります。そのため、業務連携が取りやすくなるほか、企業としての一体感も生まれます。 また、社内の情報共有がツール上で可能になれば、リモートワークやフレックスタイム制などの多様な働き方にも対応できます。以上のように、社内イントラを導入することで社内での業務連携がスムーズになるのです。 (3)コストを削減できる 3つ目のメリットは、費用や教育コストを削減できる点です。 社内イントラを構築すると、いちいち書類を印刷したりファイリングして保管したりする必要がなくなり、管理費用を抑えられます。また、マニュアルをツール内に共有すれば業務上の不明点を社員が自分で解消できるので、教育コストの削減も可能です。 このように社内イントラを作ることで、管理費用や教育コストの削減が実現します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラの作り方 ここでは、社内イントラの作り方を解説します。ポイントも解説しているので、社内イントラ作成に役立てましょう。 目的を明確化する まず、社内イントラの導入目的を明確にします。社内イントラ導入後の理想を掲げ、現在の課題を考えることで、ツール選定の方向性が定まります。 ツールを選定する 次に、現在の課題をカバーするのに必要な機能を検討し、ツールを選定します。無料トライアル期間を設けているツールでは、無料トライアルで使い勝手を確認してみましょう。 運用ルールを決める 続いて、運用ルールを決めていきます。多岐にわたる部署のメンバーがツールを適切に活用できるように、マニュアルを作成したり、ツールのカスタマイズや拡張性を検討する必要があります。 ツールを運用する 続いて、全社員に周知し、運用を開始します。とくに、導入して間もないうちは社員からフィードバックを収集し、改善をしていくことが重要です。 定期的に振り返る 最後に、ツールの運用においてはPDCAサイクルを回すことが重要です。定期的にツールの使用状況や効果を振り返り、必要に応じて運用ルールを改善をしていきます。 このように、社内イントラをより効果的に活用するために、適切な手順に則って導入していきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 最も簡単に社内イントラを構築できるツール 以下では、最も簡単に社内イントラを構築できるツールをご紹介します。 社内イントラとは、社員同士の情報共有を円滑にし、社内のコミュニケーションを促進する社内情報通信網です。社内イントラツールに、社内に散在しがちな業務マニュアルや共有事項などのナレッジを一元管理すれば、必要な情報をすぐ見つけられます。 ただし、社員全員が思い通りに情報を検索できるように検索機能の優れたツールを導入しましょう。とくに、生成AIによって口語での検索に対応していると欲しい情報を誰もが見つけられます。 結論、社内イントラの構築に最適なツールは、社内の情報を一元管理し、AIを活用した超高精度検索で簡単に情報へアクセスできる「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、あらゆる形式のファイルを添付して任意のメンバーと共有できます。また、生成AIを活用した超高精度の「自然言語検索」が備わっているので、検索スキルに依存せず、誰もが目的の情報にたどり着けます。 必要な社内情報が即見つかるようになるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラネットの活用事例 KOKUYOは、日本を代表する文具やオフィス家具メーカーの企業です。 同社では新規事業を立ち上げるにあたって、他部門との連携が取りづらい階層構造の組織体系が課題でした。多くの新規事業を円滑に進めるためには、部門を横断して情報を共有しながら業務に取り組むことが重要です。 そこで、部門を超えたコミュニケーションを取るためにITツールを導入したところ、自然に業務ノウハウが共有されるようになりました。結果として、上から言われたことをやるだけではなく、社員が主体性を持ってプロジェクトを進められるようになったのです。 参考:「自律的に動く組織へ。Slack 活用で目指すコクヨ式ハイブリッドワーク」│KOKUYO 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラを導入する目的や作成方法まとめ これまで、社内イントラの目的や作成方法を中心に解説してきました。 社内のノウハウやマニュアルなどのナレッジを適切に共有して活用するためには、社内に散在する情報を一元管理する社内イントラツールが必須です。また、社内イントラツールには、必要な情報を確実に見つけられる超高精度の機能が求められます。 そのため、「蓄積したナレッジを超高精度検索機能で簡単にアクセスできるITツール」を利用しましょう。とくに、生成AIによるチャット形式で検索できる検索機能があると便利です。 結論、社内イントラに利用すべきなのは、あらゆる情報を一元化し、生成AIを活用した「自然言語検索」が備わったツール「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、社内情報を共有・管理しやすい体制をつくりましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む
2025年03月27日【事例あり】社内イントラとは?導入する目的や作成方法を解説!社内イントラとは、「組織内の情報通信網」のことを指します。社内イントラを構築することで、迅速な情報共有が可能となり、業務効率化が実現できます。 とはいえ、「社内イントラをどのように構築すればいいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内イントラの目的や作成方法を中心にご紹介します。 社内イントラの作成方法を知りたい 事例を参考にして社内イントラを構築したい 業務を効率化できる社内イントラツールを探している という方はこの記事を参考にすると、社内イントラの構築方法が分かり、組織全体の生産性向上が期待できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 社内イントラとは1.1 社内イントラの概要1.2 社内イントラと社内ポータルサイトの違い2 社内イントラを作成するメリット2.1 (1)迅速な情報共有が実現できる2.2 (2)社内コミュニケーションが円滑になる2.3 (3)コストを削減できる3 社内イントラの作り方4 最も簡単に社内イントラを構築できるツール4.1 必要な社内情報が即見つかるようになるツール「ナレカン」5 社内イントラネットの活用事例6 社内イントラを導入する目的や作成方法まとめ 社内イントラとは ここでは、社内イントラの概要や社内ポータルサイトとの違いを解説します。「社内イントラが何か分からない」という方は必見です。 社内イントラの概要 社内イントラとは、社内イントラネット(intranet)の略語で、社内のみで使えるネットワークのことです。 社内イントラを活用すれば、社内文書やファイルを安全に共有できます。また、場所や時間を問わず作業が可能になるほか、社員同士の情報共有や連携がスムーズになるのです。 社内イントラと社内ポータルサイトの違い 社内イントラと社内ポータルサイトは、閲覧制限の厳しさが異なります。 社内ポータルサイトは、「URLを知っている社員なら誰でも社内向けのサービスや社内情報を検索・閲覧できる」のに対し、社内イントラは「社内の限られた空間、あるいは端末からのみアクセスできる情報通信網」です。 一方で、社内イントラも社内ポータルサイトも「社内の情報を一元管理してアクセスしやすくしている」点は同じです。 社内で情報が散在していると、必要な情報を探すのに手間がかかり、業務の対応漏れや作業効率の低下につながります。そのため、社内イントラを活用して、社内文書やマニュアルなどのナレッジに即アクセスできるようにしておきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラを作成するメリット ここでは、社内イントラを作成するメリットについて解説します。社内イントラを作成するかを悩んでいる方は必見です。 (1)迅速な情報共有が実現できる 1つ目のメリットは、迅速な情報共有が実現できる点です。 社内イントラにより、「ツールを見れば全ての社内情報を確認できる」といった環境を整えられます。そのため、特定の社員や個人に情報や業務が偏ってしまう課題を解消できます。 このように、社内イントラを作ると、迅速な情報共有が可能となり、業務の属人化防止につながるのです。 (2)社内コミュニケーションが円滑になる 2つ目のメリットは、社内コミュニケーションが円滑になる点です。 社内イントラを構築することで、部署を超えた情報共有が容易になります。そのため、業務連携が取りやすくなるほか、企業としての一体感も生まれます。 また、社内の情報共有がツール上で可能になれば、リモートワークやフレックスタイム制などの多様な働き方にも対応できます。以上のように、社内イントラを導入することで社内での業務連携がスムーズになるのです。 (3)コストを削減できる 3つ目のメリットは、費用や教育コストを削減できる点です。 社内イントラを構築すると、いちいち書類を印刷したりファイリングして保管したりする必要がなくなり、管理費用を抑えられます。また、マニュアルをツール内に共有すれば業務上の不明点を社員が自分で解消できるので、教育コストの削減も可能です。 このように社内イントラを作ることで、管理費用や教育コストの削減が実現します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラの作り方 ここでは、社内イントラの作り方を解説します。ポイントも解説しているので、社内イントラ作成に役立てましょう。 目的を明確化する まず、社内イントラの導入目的を明確にします。社内イントラ導入後の理想を掲げ、現在の課題を考えることで、ツール選定の方向性が定まります。 ツールを選定する 次に、現在の課題をカバーするのに必要な機能を検討し、ツールを選定します。無料トライアル期間を設けているツールでは、無料トライアルで使い勝手を確認してみましょう。 運用ルールを決める 続いて、運用ルールを決めていきます。多岐にわたる部署のメンバーがツールを適切に活用できるように、マニュアルを作成したり、ツールのカスタマイズや拡張性を検討する必要があります。 ツールを運用する 続いて、全社員に周知し、運用を開始します。とくに、導入して間もないうちは社員からフィードバックを収集し、改善をしていくことが重要です。 定期的に振り返る 最後に、ツールの運用においてはPDCAサイクルを回すことが重要です。定期的にツールの使用状況や効果を振り返り、必要に応じて運用ルールを改善をしていきます。 このように、社内イントラをより効果的に活用するために、適切な手順に則って導入していきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 最も簡単に社内イントラを構築できるツール 以下では、最も簡単に社内イントラを構築できるツールをご紹介します。 社内イントラとは、社員同士の情報共有を円滑にし、社内のコミュニケーションを促進する社内情報通信網です。社内イントラツールに、社内に散在しがちな業務マニュアルや共有事項などのナレッジを一元管理すれば、必要な情報をすぐ見つけられます。 ただし、社員全員が思い通りに情報を検索できるように検索機能の優れたツールを導入しましょう。とくに、生成AIによって口語での検索に対応していると欲しい情報を誰もが見つけられます。 結論、社内イントラの構築に最適なツールは、社内の情報を一元管理し、AIを活用した超高精度検索で簡単に情報へアクセスできる「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、あらゆる形式のファイルを添付して任意のメンバーと共有できます。また、生成AIを活用した超高精度の「自然言語検索」が備わっているので、検索スキルに依存せず、誰もが目的の情報にたどり着けます。 必要な社内情報が即見つかるようになるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラネットの活用事例 KOKUYOは、日本を代表する文具やオフィス家具メーカーの企業です。 同社では新規事業を立ち上げるにあたって、他部門との連携が取りづらい階層構造の組織体系が課題でした。多くの新規事業を円滑に進めるためには、部門を横断して情報を共有しながら業務に取り組むことが重要です。 そこで、部門を超えたコミュニケーションを取るためにITツールを導入したところ、自然に業務ノウハウが共有されるようになりました。結果として、上から言われたことをやるだけではなく、社員が主体性を持ってプロジェクトを進められるようになったのです。 参考:「自律的に動く組織へ。Slack 活用で目指すコクヨ式ハイブリッドワーク」│KOKUYO 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラを導入する目的や作成方法まとめ これまで、社内イントラの目的や作成方法を中心に解説してきました。 社内のノウハウやマニュアルなどのナレッジを適切に共有して活用するためには、社内に散在する情報を一元管理する社内イントラツールが必須です。また、社内イントラツールには、必要な情報を確実に見つけられる超高精度の機能が求められます。 そのため、「蓄積したナレッジを超高精度検索機能で簡単にアクセスできるITツール」を利用しましょう。とくに、生成AIによるチャット形式で検索できる検索機能があると便利です。 結論、社内イントラに利用すべきなのは、あらゆる情報を一元化し、生成AIを活用した「自然言語検索」が備わったツール「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、社内情報を共有・管理しやすい体制をつくりましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む -
 2025年03月27日【徹底ガイド】GigaCC(ギガシーシー)とは?機能や料金・評判も紹介あらゆる情報がデータ化している現代において、ファイル共有はビジネスで必須です。そのため、「インターネット上でデータを保存できるオンラインストレージ」が個人や法人問わず幅広く使われています。 なかでも、多くの利用者を抱えているのが「GigaCC(ギガシーシー)」です。しかし、「GigaCCの導入を検討しているが、自社に適しているのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、GigaCCの使い方や料金プラン、評判を中心に解説します。 GigaCCの機能や料金について詳しく知りたい 利用しているユーザーの評判を参考に、導入可否を検討したい GigaCCのデメリットを解消するツールがあれば知りたい という方はこの記事を参考にすると、GigaCCについて詳しく分かるので、自社にとって最適なツールかを検討できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 GigaCCとは1.1 GigaCCと他のオンラインストレージとの違い1.2 GigaCCの基本機能1.3 GigaCCの利用者向けの機能1.4 GigaCCの管理者向け機能2 GigaCCの料金プラン3 GigaCCを使うときの3つの注意点とは3.1 (1)フォルダ機能はない3.2 (2)容量制限に注意が必要4 【これで解消】GigaCCのデメリットをカバーするおすすめのツール4.1 あらゆる情報を簡単に一元管理できる「ナレカン」5 GigaCCの口コミ・評判5.1 GigaCCの良い口コミ・評判5.2 GigaCCの改善点に関する口コミ・評判6 導入実績!GigaCCを導入した事例2選6.1 (1)筑邦銀行6.2 (2)東京大学大学院 新領域創成科学研究科7 GigaCCの使い方や料金プラン・評判のまとめ GigaCCとは 以下では、GigaCCの特徴や機能をご紹介します。GigaCCの導入を検討している企業は必見です。 GigaCCと他のオンラインストレージとの違い 引用:GigaCCのサイトページ GigaCCは、 GigaCCは、日本ワムネット株式会社が提供する“純国産”法人向けのオンラインストレージです。加えて、データを共有したい企業間の「ファイル受取専用のポスト」として、大容量ファイルの安全な送受信やファイル共有に貢献しています。 また、GigaCCと他のオンラインストレージの違いは、安全性が担保されている点です。具体的には、サービスの開発から提供・サポート・データの保管まですべて国内で運用しており、2要素認証・2段階認証をはじめとするセキュリティ機能が挙げられます。 以上のように、充実したセキュリティ対策を実現していることから「多数の相手とのセキュアなファイル共有が必要な企業」に向いているサービスだと言えます。 ・GigaCCの公式サイトはこちら ・App Storeからのダウンロードはこちら GigaCCの基本機能 以下では、GigaCCの基本機能を3つご紹介します。 ファイル共有機能 取引先へのファイル送信だけでなく、データを受け取ることも可能です。また、アクセス権を管理することで、むやみやたらに情報が飛び交う事態を防ぎます。 共有ノート機能 アップロードされているファイルやフォルダに対して、アクセス権限のあるIDユーザーがコメントを書き込めます。社内外の関係者同士でスムーズな意見交換をしたり、コミュニケーションをとったりすることが可能です。 モバイル機能 PCだけでなく、スマホやタブレットからも使用できます。そのため、社外でもファイルの共有や転送が可能です。 以上のような機能は、スムーズな情報共有をするうえで欠かせません。とくに、職種によっては、オフィス外から情報を確認しなければならないケースもあるので、3つ目の「モバイル対応しているか」は重要なポイントとして認識しておきましょう。 GigaCCの利用者向けの機能 以下では、GigaCCの利用者向けの機能を3つご紹介します。 連携機能 「Microsoft Office for the web」と連携し、Officeファイルの新規作成・同時編集・保存がブラウザ上でできます。Officeソフトがない方でも追加料金なしで利用できるため、プロジェクトのスムーズな進行に役立ちます。 返信・アクセスURL機能 返信URLを発行すれば、外部ユーザーもGigaCCを通してファイルを送信できます。また、URLを通知すれば、外部ユーザーにファイルをダウンロードさせることも可能です。 CC通知機能 特定のメールアドレスに自動でCC通知が届くため、送信者が故意に情報漏えいするのを防ぎます。ファイル送信時に毎度メールアドレスをCCに入れる手間を省けるため、業務の効率化にも役立ちます。 以上が利用者向けの主要な機能です。ほかにも、ひな形機能や予約送信機能、収集用URL機能など便利な機能が豊富に備わっています。 GigaCCの管理者向け機能 以下では、GigaCCの管理者向けの機能を3つご紹介します。 制限管理機能 アカウントやアクセス権の管理ができるうえ、アカウントの登録などを一括設定できるため、管理者の工数削減につながります。 履歴ログ管理機能 200項目以上の検索項目でログ検索・出力できるため、ファイル共有の詳細を確認可能です。出力情報の一例としては、「ファイル送信・共有時のすべてのアクション」「ファイル容量」「URL情報」などが挙げられます。 証跡機能(全件バックアップ) 送信・共有されたファイルを別領域のアーカイブデータで保存します。また、ファイルは全件バックアップされるため、情報漏えいが発生した際に被害の特定や影響範囲の推測がしやすく、被害を最小限に抑えられます。 このように、GigaCCは利用者だけでなく管理者に対する機能も充実しています。しかし、機能が豊富な分、使いこなせない危険があることに注意しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ GigaCCの料金プラン GigaCCでは、以下3つのプランが用意されていて、いずれのプランも最低利用期間は3か月で、初期費用50,000円が必要となります。基本の月額料金は以下の通りです。 Standardプラン 12,000円~/10ID/月 280,000円~/1,000ID/月 ※要件に応じた見積りあり。 Advancedプラン 12,000円~/10ID/月+25,000円 280,000円~/1,000ID/月+25,000円 ※11種類あるオプションのうち、任意の機能を3種類選択できる。 Premiumプラン 12,000円~/10ID/月 280,000円~/1,000ID/月 プランごとに提供される機能が異なるので、注意しましょう。また、「独自ドメイン」「グローバルゲートウェイ」「コマンドラインツール」などの有料オプションもあるので、詳細はHPをご確認ください。 参考:GigaCCの料金プラン 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ GigaCCを使うときの3つの注意点とは GigaCCは、社外とのファイル共有に特化している反面、社内の情報管理には不向きな傾向にあります。以下では、利用する注意点を解説するので「何に気を付けるべきか」を事前に把握し、導入して問題ないか見極めましょう。 (1)フォルダ機能はない 1つ目に、GigaCCにはフォルダ機能がないことが挙げられます。 GigaCCでは、様々な相手先と「ファイル共有」ができ、「共有ノート」ではコメント機能を使ってコミュニケーションを図れるので便利です。しかし、取引先や案件ごとにファイル・ノートを管理する「フォルダ」機能はありません。 共有したいファイルや情報が散在した状態では、すぐに必要な情報を見つけられず非効率です。そのため、共有したファイルやノートを整理しながら管理できる「フォルダ」機能を備えた「ナレカン」ツールも検討しましょう。 (2)容量制限に注意が必要 2つ目に、容量制限に注意が必要な点が挙げられます。 GigaCCでは、ID課金型と利用量課金(利用容量に応じて料金が加算される)の掛け合わせで月額料金が決まります。どの契約プランでも契約範囲を超えた場合、従量課金制となるため、データの消し忘れなどで容量が超えると費用がかさむ危険があるのです。 とはいえ、情報化社会の現代において、日々管理すべき情報が増えていく状況は避けられません。そのため、GigaCCを使用する際には各社員が容量に注意して、定期的にデータを整理していきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【これで解消】GigaCCのデメリットをカバーするおすすめのツール ここでは、GigaCCのデメリットをカバーするおすすめのツールを紹介します。 GigaCCには情報を簡単に残せる共有ノートだけでなく、メンバーとやりとりできるコメント機能が備わっているので便利です。しかし、蓄積した情報を整理する「フォルダ」機能はないため、情報が散在しやすいです。 とくに、扱う情報が多くITスキルにばらつきのある大企業では、必要なファイルを探すのに時間がかかってしまいます。そこで、情報を適切に管理できる「フォルダ」機能と、個人の検索スキルに依存しない「検索」機能が備わったツールを導入しましょう。 結論、自社が導入すべきなのは、誰でも簡単に情報を残せる「記事」があり、多階層の「フォルダ」で情報を整理しながら管理できる「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」に残した情報は、「フォルダ」で“取引先”や“内容”ごとに分類して管理できます。また、生成AIを活用した「自然語検索」や「高度なキーワード検索」も備えているため、目的のファイルにいち早くたどり着けます。 あらゆる情報を簡単に一元管理できる「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード <ナレカンを使った「情報管理」の例> 以下は、ナレカンで情報管理をした例になります。 記事にファイルを添付 ナレカンの「記事」には、テキストだけでなくWordやExcelのファイルも添付できるので、情報共有に便利です。 フォルダでの情報管理 ナレカンでは、多階層の「フォルダ」によって“取引先”や“案件”ごとに情報を分類しながら管理できます。また、フォルダ単位で「記事」の閲覧・編集権限を付与できるのも特徴です。 コメント機能 ナレカンの「記事」には「コメント」を紐づけれられるので、メンバー間のコミュニケーションを図れます。記事ごとにやり取りすることで、会話の内容が混ざる心配もありません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ GigaCCの口コミ・評判 以下では、GigaCCを実際に利用しているユーザーからの口コミや評判を解説します。 利用者の声を知ることで、ツールの持つメリット・デメリットが把握できます。 ※こちらでご紹介する口コミ・評判はITreviewより引用しております。 GigaCCの良い口コミ・評判 まずは、GigaCCの良い口コミ・評判を解説します。 実際に利用しているユーザーからは「簡単な操作で大容量データの受け渡しができる」という点が評価されています。 非公開ユーザー 投稿日時:2023年11月06日 ・大容量メールを簡単な設定で即時に発信が可能です。 ・通常のメールのように送信箱、受信箱が設置されているので管理もしやすいです。 ・自身が会社全体で決められた全容量の内、どれだけ使用しているかも一元管理できます。 ・相手が添付ファイルを開封したら、開封されましたと受信メールが来るので、的確なタイミングで先方に電話フォローが可能になります。 非公開ユーザー 投稿日時:2023年03月03日 容量の大きいファイルや機密性の高いファイルを送るときに使用しています。 なかでも、登録したメールアドレスを発信元として、通常と同じメールスタイルでCC/BCCをつけて送ることができるので、便利です。 添付ファイルを受付ないだけでなく、ストレージからのメールを受付ない大企業でも、大容量ファイルのやり取りに重宝しています。 非公開ユーザー 投稿日時:2023年01月10日 ・メールで共有できない大容量のデータ(CADデータ等)のやりとりが楽にできる。 ・ドラッグ&ドロップで送信という簡単な作業で、誰でも簡単に使いこなすことができる。 非公開ユーザー 投稿日時:2022年12月27日 ・とにかくメールと同じような操作感で抵抗感なく使用できる。 ・動画や画像やCADデータ等の大容量になりがちなデータ受け渡しを安心して活用。 ・コメント機能でスムーズな相互やりとりができる。 GigaCCの改善点に関する口コミ・評判 良い評価・口コミがある一方で、改善点に関する口コミや評判も存在します。 実際に利用しているユーザーからは、「費用が高い」「管理画面のUIが使いづらい」といった評判があり、早急な対応が求められています。 非公開ユーザー 投稿日時:2023年03月03日 もうすこし費用が安いと良いと思います。 グーグルワークスペースの機能がアップした際に、グーグルのビジネスユースと迷った時もありました。 非公開ユーザー 投稿日時:2023年02月27日 ・シンプルな機能性と表裏一体なのかもしれないが、単にファイルを共有するだけでなく、リアルタイムに共同編集できる機能が欲しい。すでにそのような機能があるとしても自分は知らず、十分に浸透していないように感じる。 ・一定期間経った後に共有した/されたファイルをサイド確認したい際に有効期限切れとなることが多々ある 非公開ユーザー 投稿日時:2022年12月13日 費用がもう少し落とせると助かります。 また、セキュリティ強化のために、多要素認証の実装を早期にお願いしたい。 非公開ユーザー 投稿日時:2022年06月15日 ユーザーのUIは直感的に使いやすいが、管理者のUIが使いづらいため、もっと直感的に操作出来るようにわかりやすいUIにして欲しい 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 導入実績!GigaCCを導入した事例2選 ここでは、GigaCCを導入した2つの事例を紹介します。事例を把握しておけば、導入したときにスムーズな運用ができるようになるので必見です。 (1)筑邦銀行 引用:筑邦銀行のトップページ 筑邦銀行は、福岡県久留米市に本店を置く地方銀行です。 当社では、2021年4月より「ちくぎんDC企業型年金規約」の受け付けを開始したことで、不特定多数の顧客からファイルが届くようになりました。そのため、「メール以外で、安全にやりとりできる仕組み」が必要になったのです。 そこで、「不特定多数の顧客が安全かつ簡単に操作できること」「社内セキュリティ規定に問題がないこと」をクリアしたGigaCCを導入しました。 その結果、従来のメールによる誤送信や送信エラー、大量のメールに埋もれて見逃してしまう事態を解消できたのです。さらに、実務レベルでデジタル化による業務改革を実体験したことで、脱アナログの意識改革につながっているという声も挙がっています。 参考:導入事例:筑邦銀行-GigaCCー (2)東京大学大学院 新領域創成科学研究科 引用:東京大学大学院のトップページ 東京大学大学院の新領域創成科学研究科は、基盤化学、生命科学、環境学の3つの研究系で構成されている大学院です。 当研究科では、教職員の公募業務や運営する委員会など、重要な書類を取り扱うシーンが多くあります。そのため、「外部とのファイルの受け取り」「機密資料の安全な保管・共有」が実現できるシステムが必要でした。 そこで、GigaCCを導入して、写真や動画などの大容量データを安全にやりとりできる仕組みを整えたのです。 その結果、紙の資料で対応していたときに比べて、手間と時間の両方のコスト削減が実現できました。また、資料を各自のPCで閲覧できるので、ペーパーレスで会議を進められるようになり、紙資料の取り扱いによる情報漏えいや紛失のリスクも低減されました。 参考:導入事例:東京大学大学院 新領域創成科学研究科-GigaCCー 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ GigaCCの使い方や料金プラン・評判のまとめ ここまで、GigaCCの使い方や料金プラン・評判を中心に解説しました。 ビジネスをするうえで「情報共有」と「コミュニケーション」は、業界・業種問わず必須の要素です。しかし、GigaCCは、外部との”データ共有”に特化している反面、「フォルダ」機能がないため”情報の管理”には不向きなのです。 しかし、業務を効率よく進めていくうえで、社内の情報は適切に管理できていなければなりません。そのため、「共有したい情報や、やり取りを一元管理できるツール」が不可欠なのです。 結論、自社で導入すべきなのは、あらゆる情報を残せる「記事」があり、“取引先”や“内容”ごとの「フォルダ」で情報を整理しながら管理できる「ナレカン」一択です。ナレカンは国際セキュリティの資格を取得しており、大手企業でも安心して利用できます。 ぜひ「ナレカン」を使って、簡単に情報共有できる仕組みを整えましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【無料あり】仕事や職場で使える情報・スケジュール共有アプリ7選続きを読む
2025年03月27日【徹底ガイド】GigaCC(ギガシーシー)とは?機能や料金・評判も紹介あらゆる情報がデータ化している現代において、ファイル共有はビジネスで必須です。そのため、「インターネット上でデータを保存できるオンラインストレージ」が個人や法人問わず幅広く使われています。 なかでも、多くの利用者を抱えているのが「GigaCC(ギガシーシー)」です。しかし、「GigaCCの導入を検討しているが、自社に適しているのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、GigaCCの使い方や料金プラン、評判を中心に解説します。 GigaCCの機能や料金について詳しく知りたい 利用しているユーザーの評判を参考に、導入可否を検討したい GigaCCのデメリットを解消するツールがあれば知りたい という方はこの記事を参考にすると、GigaCCについて詳しく分かるので、自社にとって最適なツールかを検討できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 GigaCCとは1.1 GigaCCと他のオンラインストレージとの違い1.2 GigaCCの基本機能1.3 GigaCCの利用者向けの機能1.4 GigaCCの管理者向け機能2 GigaCCの料金プラン3 GigaCCを使うときの3つの注意点とは3.1 (1)フォルダ機能はない3.2 (2)容量制限に注意が必要4 【これで解消】GigaCCのデメリットをカバーするおすすめのツール4.1 あらゆる情報を簡単に一元管理できる「ナレカン」5 GigaCCの口コミ・評判5.1 GigaCCの良い口コミ・評判5.2 GigaCCの改善点に関する口コミ・評判6 導入実績!GigaCCを導入した事例2選6.1 (1)筑邦銀行6.2 (2)東京大学大学院 新領域創成科学研究科7 GigaCCの使い方や料金プラン・評判のまとめ GigaCCとは 以下では、GigaCCの特徴や機能をご紹介します。GigaCCの導入を検討している企業は必見です。 GigaCCと他のオンラインストレージとの違い 引用:GigaCCのサイトページ GigaCCは、 GigaCCは、日本ワムネット株式会社が提供する“純国産”法人向けのオンラインストレージです。加えて、データを共有したい企業間の「ファイル受取専用のポスト」として、大容量ファイルの安全な送受信やファイル共有に貢献しています。 また、GigaCCと他のオンラインストレージの違いは、安全性が担保されている点です。具体的には、サービスの開発から提供・サポート・データの保管まですべて国内で運用しており、2要素認証・2段階認証をはじめとするセキュリティ機能が挙げられます。 以上のように、充実したセキュリティ対策を実現していることから「多数の相手とのセキュアなファイル共有が必要な企業」に向いているサービスだと言えます。 ・GigaCCの公式サイトはこちら ・App Storeからのダウンロードはこちら GigaCCの基本機能 以下では、GigaCCの基本機能を3つご紹介します。 ファイル共有機能 取引先へのファイル送信だけでなく、データを受け取ることも可能です。また、アクセス権を管理することで、むやみやたらに情報が飛び交う事態を防ぎます。 共有ノート機能 アップロードされているファイルやフォルダに対して、アクセス権限のあるIDユーザーがコメントを書き込めます。社内外の関係者同士でスムーズな意見交換をしたり、コミュニケーションをとったりすることが可能です。 モバイル機能 PCだけでなく、スマホやタブレットからも使用できます。そのため、社外でもファイルの共有や転送が可能です。 以上のような機能は、スムーズな情報共有をするうえで欠かせません。とくに、職種によっては、オフィス外から情報を確認しなければならないケースもあるので、3つ目の「モバイル対応しているか」は重要なポイントとして認識しておきましょう。 GigaCCの利用者向けの機能 以下では、GigaCCの利用者向けの機能を3つご紹介します。 連携機能 「Microsoft Office for the web」と連携し、Officeファイルの新規作成・同時編集・保存がブラウザ上でできます。Officeソフトがない方でも追加料金なしで利用できるため、プロジェクトのスムーズな進行に役立ちます。 返信・アクセスURL機能 返信URLを発行すれば、外部ユーザーもGigaCCを通してファイルを送信できます。また、URLを通知すれば、外部ユーザーにファイルをダウンロードさせることも可能です。 CC通知機能 特定のメールアドレスに自動でCC通知が届くため、送信者が故意に情報漏えいするのを防ぎます。ファイル送信時に毎度メールアドレスをCCに入れる手間を省けるため、業務の効率化にも役立ちます。 以上が利用者向けの主要な機能です。ほかにも、ひな形機能や予約送信機能、収集用URL機能など便利な機能が豊富に備わっています。 GigaCCの管理者向け機能 以下では、GigaCCの管理者向けの機能を3つご紹介します。 制限管理機能 アカウントやアクセス権の管理ができるうえ、アカウントの登録などを一括設定できるため、管理者の工数削減につながります。 履歴ログ管理機能 200項目以上の検索項目でログ検索・出力できるため、ファイル共有の詳細を確認可能です。出力情報の一例としては、「ファイル送信・共有時のすべてのアクション」「ファイル容量」「URL情報」などが挙げられます。 証跡機能(全件バックアップ) 送信・共有されたファイルを別領域のアーカイブデータで保存します。また、ファイルは全件バックアップされるため、情報漏えいが発生した際に被害の特定や影響範囲の推測がしやすく、被害を最小限に抑えられます。 このように、GigaCCは利用者だけでなく管理者に対する機能も充実しています。しかし、機能が豊富な分、使いこなせない危険があることに注意しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ GigaCCの料金プラン GigaCCでは、以下3つのプランが用意されていて、いずれのプランも最低利用期間は3か月で、初期費用50,000円が必要となります。基本の月額料金は以下の通りです。 Standardプラン 12,000円~/10ID/月 280,000円~/1,000ID/月 ※要件に応じた見積りあり。 Advancedプラン 12,000円~/10ID/月+25,000円 280,000円~/1,000ID/月+25,000円 ※11種類あるオプションのうち、任意の機能を3種類選択できる。 Premiumプラン 12,000円~/10ID/月 280,000円~/1,000ID/月 プランごとに提供される機能が異なるので、注意しましょう。また、「独自ドメイン」「グローバルゲートウェイ」「コマンドラインツール」などの有料オプションもあるので、詳細はHPをご確認ください。 参考:GigaCCの料金プラン 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ GigaCCを使うときの3つの注意点とは GigaCCは、社外とのファイル共有に特化している反面、社内の情報管理には不向きな傾向にあります。以下では、利用する注意点を解説するので「何に気を付けるべきか」を事前に把握し、導入して問題ないか見極めましょう。 (1)フォルダ機能はない 1つ目に、GigaCCにはフォルダ機能がないことが挙げられます。 GigaCCでは、様々な相手先と「ファイル共有」ができ、「共有ノート」ではコメント機能を使ってコミュニケーションを図れるので便利です。しかし、取引先や案件ごとにファイル・ノートを管理する「フォルダ」機能はありません。 共有したいファイルや情報が散在した状態では、すぐに必要な情報を見つけられず非効率です。そのため、共有したファイルやノートを整理しながら管理できる「フォルダ」機能を備えた「ナレカン」ツールも検討しましょう。 (2)容量制限に注意が必要 2つ目に、容量制限に注意が必要な点が挙げられます。 GigaCCでは、ID課金型と利用量課金(利用容量に応じて料金が加算される)の掛け合わせで月額料金が決まります。どの契約プランでも契約範囲を超えた場合、従量課金制となるため、データの消し忘れなどで容量が超えると費用がかさむ危険があるのです。 とはいえ、情報化社会の現代において、日々管理すべき情報が増えていく状況は避けられません。そのため、GigaCCを使用する際には各社員が容量に注意して、定期的にデータを整理していきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【これで解消】GigaCCのデメリットをカバーするおすすめのツール ここでは、GigaCCのデメリットをカバーするおすすめのツールを紹介します。 GigaCCには情報を簡単に残せる共有ノートだけでなく、メンバーとやりとりできるコメント機能が備わっているので便利です。しかし、蓄積した情報を整理する「フォルダ」機能はないため、情報が散在しやすいです。 とくに、扱う情報が多くITスキルにばらつきのある大企業では、必要なファイルを探すのに時間がかかってしまいます。そこで、情報を適切に管理できる「フォルダ」機能と、個人の検索スキルに依存しない「検索」機能が備わったツールを導入しましょう。 結論、自社が導入すべきなのは、誰でも簡単に情報を残せる「記事」があり、多階層の「フォルダ」で情報を整理しながら管理できる「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」に残した情報は、「フォルダ」で“取引先”や“内容”ごとに分類して管理できます。また、生成AIを活用した「自然語検索」や「高度なキーワード検索」も備えているため、目的のファイルにいち早くたどり着けます。 あらゆる情報を簡単に一元管理できる「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード <ナレカンを使った「情報管理」の例> 以下は、ナレカンで情報管理をした例になります。 記事にファイルを添付 ナレカンの「記事」には、テキストだけでなくWordやExcelのファイルも添付できるので、情報共有に便利です。 フォルダでの情報管理 ナレカンでは、多階層の「フォルダ」によって“取引先”や“案件”ごとに情報を分類しながら管理できます。また、フォルダ単位で「記事」の閲覧・編集権限を付与できるのも特徴です。 コメント機能 ナレカンの「記事」には「コメント」を紐づけれられるので、メンバー間のコミュニケーションを図れます。記事ごとにやり取りすることで、会話の内容が混ざる心配もありません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ GigaCCの口コミ・評判 以下では、GigaCCを実際に利用しているユーザーからの口コミや評判を解説します。 利用者の声を知ることで、ツールの持つメリット・デメリットが把握できます。 ※こちらでご紹介する口コミ・評判はITreviewより引用しております。 GigaCCの良い口コミ・評判 まずは、GigaCCの良い口コミ・評判を解説します。 実際に利用しているユーザーからは「簡単な操作で大容量データの受け渡しができる」という点が評価されています。 非公開ユーザー 投稿日時:2023年11月06日 ・大容量メールを簡単な設定で即時に発信が可能です。 ・通常のメールのように送信箱、受信箱が設置されているので管理もしやすいです。 ・自身が会社全体で決められた全容量の内、どれだけ使用しているかも一元管理できます。 ・相手が添付ファイルを開封したら、開封されましたと受信メールが来るので、的確なタイミングで先方に電話フォローが可能になります。 非公開ユーザー 投稿日時:2023年03月03日 容量の大きいファイルや機密性の高いファイルを送るときに使用しています。 なかでも、登録したメールアドレスを発信元として、通常と同じメールスタイルでCC/BCCをつけて送ることができるので、便利です。 添付ファイルを受付ないだけでなく、ストレージからのメールを受付ない大企業でも、大容量ファイルのやり取りに重宝しています。 非公開ユーザー 投稿日時:2023年01月10日 ・メールで共有できない大容量のデータ(CADデータ等)のやりとりが楽にできる。 ・ドラッグ&ドロップで送信という簡単な作業で、誰でも簡単に使いこなすことができる。 非公開ユーザー 投稿日時:2022年12月27日 ・とにかくメールと同じような操作感で抵抗感なく使用できる。 ・動画や画像やCADデータ等の大容量になりがちなデータ受け渡しを安心して活用。 ・コメント機能でスムーズな相互やりとりができる。 GigaCCの改善点に関する口コミ・評判 良い評価・口コミがある一方で、改善点に関する口コミや評判も存在します。 実際に利用しているユーザーからは、「費用が高い」「管理画面のUIが使いづらい」といった評判があり、早急な対応が求められています。 非公開ユーザー 投稿日時:2023年03月03日 もうすこし費用が安いと良いと思います。 グーグルワークスペースの機能がアップした際に、グーグルのビジネスユースと迷った時もありました。 非公開ユーザー 投稿日時:2023年02月27日 ・シンプルな機能性と表裏一体なのかもしれないが、単にファイルを共有するだけでなく、リアルタイムに共同編集できる機能が欲しい。すでにそのような機能があるとしても自分は知らず、十分に浸透していないように感じる。 ・一定期間経った後に共有した/されたファイルをサイド確認したい際に有効期限切れとなることが多々ある 非公開ユーザー 投稿日時:2022年12月13日 費用がもう少し落とせると助かります。 また、セキュリティ強化のために、多要素認証の実装を早期にお願いしたい。 非公開ユーザー 投稿日時:2022年06月15日 ユーザーのUIは直感的に使いやすいが、管理者のUIが使いづらいため、もっと直感的に操作出来るようにわかりやすいUIにして欲しい 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 導入実績!GigaCCを導入した事例2選 ここでは、GigaCCを導入した2つの事例を紹介します。事例を把握しておけば、導入したときにスムーズな運用ができるようになるので必見です。 (1)筑邦銀行 引用:筑邦銀行のトップページ 筑邦銀行は、福岡県久留米市に本店を置く地方銀行です。 当社では、2021年4月より「ちくぎんDC企業型年金規約」の受け付けを開始したことで、不特定多数の顧客からファイルが届くようになりました。そのため、「メール以外で、安全にやりとりできる仕組み」が必要になったのです。 そこで、「不特定多数の顧客が安全かつ簡単に操作できること」「社内セキュリティ規定に問題がないこと」をクリアしたGigaCCを導入しました。 その結果、従来のメールによる誤送信や送信エラー、大量のメールに埋もれて見逃してしまう事態を解消できたのです。さらに、実務レベルでデジタル化による業務改革を実体験したことで、脱アナログの意識改革につながっているという声も挙がっています。 参考:導入事例:筑邦銀行-GigaCCー (2)東京大学大学院 新領域創成科学研究科 引用:東京大学大学院のトップページ 東京大学大学院の新領域創成科学研究科は、基盤化学、生命科学、環境学の3つの研究系で構成されている大学院です。 当研究科では、教職員の公募業務や運営する委員会など、重要な書類を取り扱うシーンが多くあります。そのため、「外部とのファイルの受け取り」「機密資料の安全な保管・共有」が実現できるシステムが必要でした。 そこで、GigaCCを導入して、写真や動画などの大容量データを安全にやりとりできる仕組みを整えたのです。 その結果、紙の資料で対応していたときに比べて、手間と時間の両方のコスト削減が実現できました。また、資料を各自のPCで閲覧できるので、ペーパーレスで会議を進められるようになり、紙資料の取り扱いによる情報漏えいや紛失のリスクも低減されました。 参考:導入事例:東京大学大学院 新領域創成科学研究科-GigaCCー 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ GigaCCの使い方や料金プラン・評判のまとめ ここまで、GigaCCの使い方や料金プラン・評判を中心に解説しました。 ビジネスをするうえで「情報共有」と「コミュニケーション」は、業界・業種問わず必須の要素です。しかし、GigaCCは、外部との”データ共有”に特化している反面、「フォルダ」機能がないため”情報の管理”には不向きなのです。 しかし、業務を効率よく進めていくうえで、社内の情報は適切に管理できていなければなりません。そのため、「共有したい情報や、やり取りを一元管理できるツール」が不可欠なのです。 結論、自社で導入すべきなのは、あらゆる情報を残せる「記事」があり、“取引先”や“内容”ごとの「フォルダ」で情報を整理しながら管理できる「ナレカン」一択です。ナレカンは国際セキュリティの資格を取得しており、大手企業でも安心して利用できます。 ぜひ「ナレカン」を使って、簡単に情報共有できる仕組みを整えましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【無料あり】仕事や職場で使える情報・スケジュール共有アプリ7選続きを読む -
 2025年10月03日【最新版】人気のクラウド型社内ポータルサイト7選を徹底比較!昨今、社内向けのWebサイトである「社内ポータルサイト」を介して情報共有をする企業が増えています。とくに、クラウド型は自社で開発したりサーバ等を管理したりする必要がないので、ITに関する知識がない企業でも手軽に使い始められる点が人気です。 しかし、「クラウド型の社内ポータルサイトを導入したいが、どのように選定したらよいか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、おすすめのクラウド型社内ポータルサイト7選と選定ポイントを中心に解説します。 自社に適した社内ポータルサイトを選定するポイントを知りたい 社内の総合ポータルサイトを作れるツールを比較検討したい 誰でも簡単に「社内お知らせ」ができるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、自社にマッチする社内ポータルサイトが見つかるだけでなく、運用のポイントまで押さえられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 クラウド型社内ポータルサイトの導入メリット2 社内ポータルサイトの選定ポイント4選2.1 (1)簡単に操作できるか2.2 (2)スムーズに導入できるか2.3 (3)セキュリティ対策が万全か2.4 (4)スマホからでも確認しやすいか3 人気あり!おすすめのクラウド型社内ポータルサイト7選3.1 【ナレカン】100人以上の大企業のナレッジ管理に特化したツール3.2 【Stock】100人以下の中小企業の情報管理・共有に最適のツール3.3 【Garoon】サイボウズが提供する大企業向けグループウェア3.4 【kintone】サイボウズが提供する多機能なクラウドサービス3.5 【Concrete CMS】オープンソースのポータルソフト3.6 【Notion】デザイン性の高い社内ポータルを作成できるツール3.7 【SharePoint】社内メンバーとの”情報共有”に使えるポータルサイト4 無料から試せる!クラウド型社内ポータルサイトの比較表5 社内ポータルサイトの基本的な使い方3選5.1 (1)社内掲示板にお知らせを掲載する5.2 (2)マニュアルや社内情報を検索する5.3 (3)コメントを残してコミュニケーションを取る6 社内ポータルサイトを導入すべき企業の特徴7 【解決策あり】ポータルサイトの運用が上手くいかない3つの原因7.1 (1)欲しい情報が見つからない7.2 (2)明確な運用ルールがない7.3 (3)設計が合っていない8 おすすめのクラウド型社内ポータルサイトまとめ クラウド型社内ポータルサイトの導入メリット クラウド型社内ポータルサイトの導入メリットは、おもに以下の2つです。 業務効率が上がる 社内ポータルサイトには、情報を整理できる「管理機能」や、欲しい情報がすぐに見つかる「検索機能」などが豊富に備わっています。そのため、社内ポータルで情報連携を改善することで、業務スピードの向上や業務品質の均一化が期待できるのです。 ナレッジ(知識・経験)が蓄積される 社内ポータルサイトは、あらゆるナレッジ(知識・経験)が蓄積される場所になります。社内ポータルを通して社内wikiや業務ノウハウを共有することで、ナレッジが蓄積され、属人化防止につながるのです。 開発・運用コストを抑えられる クラウド型のポータルサイトでは、サービスに不具合があった場合にベンダー(システム提供者)が対応します。そのため、ITに詳しい人材のいない「非IT企業」であっても、開発・運用コストを抑えてスムーズに導入できる点がメリットです。 以上のように、社内ポータルサイトはあらゆる情報を蓄積でき、属人化の防止や業務効率の向上につながります。有効活用するために、業務にどのような利益をもたらすのかを把握し、具体的なイメージを持っておきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルサイトの選定ポイント4選 以下では、社内ポータルサイトを選定するときに押さえるべきポイントを4つご紹介します。ポータルサイトの導入に失敗したくない方は必見です。 (1)簡単に操作できるか 1つ目のポイントは、「ITに詳しくないメンバーでも簡単に操作できるか」です。 社内ポータルサイトは全社員が利用するので、誰でも簡単に使いこなせるシンプルなツールが理想です。とくに、従業員数が多い企業では「年齢層」や「ITリテラシー」を考慮して選定しなければ、情報の更新や閲覧がされなくなってしまいます。 したがって、「便利そうだから」と多機能なツールを選ぶのではなく、必要な機能に過不足のないツールを選びましょう。 (2)スムーズに導入できるか 2つ目のポイントは、「スムーズに導入できるか」です。 社内ポータルサイトの導入には、様々な作業が伴います。具体的には、サイトの初期セットアップや運用ルールの制定、既存データの移行など、複雑で時間のかかる初期設定をしなければなりません。 また、運営元のサポート体制が手厚いかは、ツール運用の成功を左右するため、決裁者の承認を得るうえでも重要です。一方、サイト導入時に初期設定に関するサポートを受けられれば、担当者の負担を最小限に抑えつつ、スムーズな運用が開始できます。 (3)セキュリティ対策が万全か 3つ目のポイントは、「セキュリティ対策が万全であるか」です。 社内ポータルサイトは、自社が保有する様々な情報にアクセスすることができるサイトです。そのため、セキュリティ対策が不完全だと、不正アクセスによって社外秘の情報が漏えいしてしまう危険性もあります。 したがって、社内ポータルサイトを導入するときは、高セキュアなツールを選ぶようにしましょう。 (4)スマホからでも確認しやすいか 4つ目のポイントは、「スマホでも確認しやすいか」です。 職種によっては、オフィス外で社内ポータルサイトにアクセスする機会も少なくありません。たとえば、商談や営業で社外に出ている場合、スマホに対応していないツールでは社内ポータルサイトにアクセスするのに手間がかかってしまいます。 したがって、オフィス外でも快適に情報を参照できるよう、「ナレカン」のようにスマホでの利用にも最適化されたツールを選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 人気あり!おすすめのクラウド型社内ポータルサイト7選 以下では、おすすめのクラウド型社内ポータルサイトをご紹介します。 社内ポータルはあらゆる情報の入り口になるため、社内の重要なお知らせを常に掲示できなくてはなりません。また、社内で活用されるポータルサイトにするには、「知りたい情報に簡単にアクセスできること」を重視して構築しましょう。 そこで、「高精度の検索機能」を備えたサービスを選べば、情報を振り返りやすい体制が整います。とくに、どこに何の情報があるのかが分からなければ閲覧しないメンバーが出るため、「検索しやすい操作性やUI(画面デザイン)であるか」も重要なポイントです。 結論、社内ポータルサイトに最適なのは、社内のナレッジを簡単に一元管理でき、超高精度の検索機能で目的の情報に即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンでは「社内お知らせ」機能で全社へ簡単に情報を共有し、「ヒット率100%」の超高精度の検索機能で必要な情報をすぐに見つけられます。また、どのナレッジがどの程度活用されているかを把握できる機能もあり、効果的なナレッジ活用が実現可能です。 【ナレカン】100人以上の大企業のナレッジ管理に特化したツール 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンで社内ポータル(社内お知らせ)を作成する手順 ナレカンでは、下記のように、重要な情報をアナウンスできます。 また、管理画面から、社内お知らせの「レイアウト」や「公開/非公開」も簡単に調整できます。 そのため、わずかな工数で全社員向けにアナウンスできるので、担当者の負担を最小限に抑えられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Stock】100人以下の中小企業の情報管理・共有に最適のツール Stockは、非IT企業の65歳の方でも即日使いこなせるシンプルなツールです。 「Stock」の「ノート」にはあらゆる情報を残せるだけでなく、任意のメンバーにリアルタイムで共有できます。また、ノートには「メッセージ」や「タスク」を紐づけられるので、情報が分散する煩わしさを解消できるのです。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 <Stockをおすすめするポイント> ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 <Stockの口コミ・評判> 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ(栃木SC) 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 <Stockの料金> フリープラン :無料 ビジネスプラン :500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数:5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Garoon】サイボウズが提供する大企業向けグループウェア <Garoonの特徴> 社内ポータルを手軽に作成できる ドラッグ&ドロップやテンプレート機能で、誰でも手間をかけずに社内ポータルを作成できます。 大規模企業向け 同社が運営している「サイボウズOffice」と比較して、Garoonは、”企業規模が100名以上の企業向けツール”になっています。 <Garoonの機能・使用感> お知らせ機能が充実している 掲示板の”掲載期間設定”や”閲覧確認機能”を活用すれば、メールを使わずに全社へ周知できます。そのため、社員数が多い企業や掲示期間を設定して投稿したい場合に便利です。 kintoneと連携して使える Garoonのポータル上に、kintoneアプリで作成した案件管理や売上管理などのグラフを表示し、ダッシュボードのように利用できます。また、kintoneの通知や未処理アプリの一覧もGaroon上で表示できるため、必要な情報をすぐに確認するのに便利です。 <Garoonの注意点> スケジュールが外部サービスと連携できない Garoonには、スケジュール機能が備わっている一方、outlookやGoogleのカレンダーと連携できないため、予定が重複しない様に注意が必要です。 直感的に利用できない 利用しているユーザーからは「もう少し直感的な使い方が出来れば良い。若干昔のデザインや動作がある。特にデザインは今風に刷新してほしい。」との声があります。(引用:ITトレンド) <Garoonの料金> 以下は、クラウド版の価格です。 900円/ユーザー/月(1,000ユーザー以上の場合は、要問合せ) 以下は、パッケージ版の新規ライセンスの料金です。 ランクA:600,000円/50ユーザー ランクB:11,000円/1ユーザー(51~249ユーザー) ランクC:10,000円/1ユーザー(250~499ユーザー) ランクD:9,000円/1ユーザー(500~999ユーザー) ランクE:8,000円/1ユーザー(1,000~2,499ユーザー) ランクF:7,500円/1ユーザー(2,500~4,999ユーザー) ランクG:要問合わせ(5,000~9,999ユーザー) ランクH:要問合わせ(10,000ユーザー~) Garoonの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【kintone】サイボウズが提供する多機能なクラウドサービス <kintoneの特徴> 独自の業務アプリを作成できる プログラミングの知識を問わず、ノーコードで業務アプリを作ることが可能です。自社の業務内容や課題に合わせたアプリを作れるため、業務の効率化を図れます。 多言語に対応 表示言語は、日本語・英語・中国語・スペイン語・韓国語など、さまざまな言語に切り替えることができ、グローバル企業にも適しています。 <kintoneの機能・使用感> データをグラフ化できる 記入したデータをグラフ化する「レポート機能」が備わっています。リアルタイムでデータがグラフに反映されるため、更新の手間がかかりません。 全文検索ができる タイトルや条件、キーワードを絞り込んで全文検索が可能です。さらに、文字情報以外にも添付ファイルの中身まで検索対象となるため、必要な情報まで迅速にたどり着けます。 <kintoneの注意点> 一定以上のITリテラシーが必要 アプリを自由にカスタマイズできる一方、高いITリテラシーがないと上手く活用できない可能性があります。 バックアップが取りにくい ユーザーからは「もし間違えてデータを消してしまっても元に戻せない。データはcsvに出力することは可能だが、戻す場合、項目によってはそのまま戻せないものもあり、非常に手間がかかる。」といった声が寄せられています。(参考:ITreview) 直感的に使えない 「複雑なカスタマイズを行う際にもう少し直感的なUIが欲しいと感じました。特に、フォームの設計やフィールドの配置において、ドラッグ&ドロップ操作の精度や柔軟性が向上するとより使いやすくなります。」という声が寄せられています。(参考:ITトレンド) <kintoneの料金体系> ライトコース:1,000円/ユーザー/月 スタンダードコース:1,800円/ユーザー/月 ワイドコース:3,000円/ユーザー/月 kintoneの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Concrete CMS】オープンソースのポータルソフト <Concrete CMSの特徴> 誰でも無料で使える Concrete CMSは、誰でも簡単にHPの運用ができるCMS(コンテンツ・マネージメント・システム)です。オープンソースなので誰でも無料で使えます。 ページの編集がしやすい 編集したい部分をクリックするだけで編集できるので、ページを行き来する手間がかかりません。 <Concrete CMSの機能・使用感> 使い方が詳しく記載されている バージョンごとの勉強会の解説録画がアップロードされているため、難しい操作でも理解しやすいです。 セキュリティ対策が高い IPアドレスブロック機能の搭載や暗号化して復号できない形式のパスワード設定など、万全のセキュリティ対策によって大企業でも安心して利用できます。 <Concrete CMSの注意点> 運用に関する情報が少ない Concrete CMSは国内利用者が少ないため、ほかのツールに比べて情報が少なく、コミュニティーで情報を調べる必要があります。 インストールするのに手間がかかる Concrete CMSは、ホスティング環境もしくはローカル環境にインストール可能です。ただし、設定に手間がかかる点に注意しましょう。 動作が重くなることがある 利用しているユーザーからは「ドラッグ&ドロップで直感的に編集ができるというメリットが有る一方で、この機能を優先したため、読み込み速度が遅くなるケースが多々あります」との意見が挙がっています。(参考:ITreview) <Concrete CMSの料金> オープンソースのサービスなので、完全無料で利用できます。 Concrete CMSの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Notion】デザイン性の高い社内ポータルを作成できるツール Notionの特徴 かっこいいサイトを作れる Notionは画像やページの編集の自由度が高い点が特徴です。そのため、かっこいい社内ポータルサイトを作りたい場合に役立ちます。 ポータル以外の機能も充実している 社内ポータルを作るだけでなく、タスクやプロジェクト管理・データベース作成にも活用可能です。したがって、ひとつのツールであらゆる用途に活用したいという方に適しています。 Notionの機能・使用感 テンプレート機能が充実している Notionには豊富なテンプレートが用意されています。そのため、社内ポータルのトップページを作ったり、お知らせや社内wikiなどの体裁を整えたりするのに便利です。 動作が重くなる場合がある オリジナリティのあるページを自由に作成できる一方で、複雑な構造を作ると動作が重くなり、開くまでに時間がかかる点に注意が必要です。読み込みが遅いときは、履歴を削除すると解消できる場合があります。 Notionの注意点 直感的に使いこなせない Notionは構造化したサイトを作れるように、さまざまな編集機能が備わっています。一方で、「各機能がどのように使えるのかが分かりにくい」ため、ITに不慣れな場合は直感的に使いこなせない可能性があります。 検索機能が使いづらい ユーザーからは「まだページが増えてくると検索に時間がかかることがあり、タグやリンクの運用ルールをチームで統一する必要があります。AI機能による自動要約や検索補助がもう少し強化されると、大量情報でも迷わずアクセスできると思います。」という声があります。(参考:ITreview) Notionの料金体系 フリー:無料 プラス:2,000円/ユーザー/月 ビジネス:3,800円/ユーザー/月 エンタープライズ:要問合わせ Notionの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【SharePoint】社内メンバーとの”情報共有”に使えるポータルサイト SharePointの特徴 社内ポータルを自由に構築できる SharePointは、目的に応じて社内ポータルを自由に構築できます。たとえば、チームで完結するファイル共有には「チームサイト」、全社向けには掲示板のように使える「コミュニケーションサイト」と、利用用途に合わせて展開可能です。 Microsoft製品と連携できる SharePoint上でWordやExcelのファイルを編集したり、Outlookのスケジュールと連携させたりできるので、Microsoft社の製品を多用している会社に向いています。 SharePointの機能・使用感 サイトを簡単に作成できる SharePointはMicrosoft社の製品であるため、AIデジタルアシスタントである「Copilot」を連携して利用できます。Copilotを使えば、数個のプロンプトとクリック操作だけで目的のサイトを作成可能なため、手間がかからず便利です。 必要なファイルがすぐに見つかる 全文検索機能がついているので、ファイルの中身を開くことなく検索をかけることができます。そのため、スピーディーに情報へアクセスするのに役立ちます。 SharePointの注意点 教育コストがかかる SharePointでは、管理者が作成したサイト上にページを用意し、コンテンツを配置することで情報共有をします。つまり、情報共有のために自社独自の使い方を「全メンバーに教育する必要がある」のです。 自由度が低い 利用しているユーザーからは「ある程度フォーマット化されている分、自由度が高くないことが多い。」という声があります。(参考:ITreview) SharePointの料金体系 SharePoint (プラン 1):749円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Basic:899円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月 また、Microsoft 365 Copilot(4,497円/ユーザー/月)を追加すれば、 SharePointサイトやライブラリ、フォルダー内の情報を駆使して、簡単にエージェントを作成できるようになります。さまざまなエージェントを作ることで、生産性の向上が図れます。 SharePointの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 無料から試せる!クラウド型社内ポータルサイトの比較表 以下は、クラウド型社内ポータルサイトの比較表です。(左右にスクロールできます。)なかには、無料から利用できるものもあるので、担当者の方は必見です。 ナレカン【一番おすすめ】 Stock【おすすめ】 Garoon kintone Concrete CMS Notion SharePoint 特徴 100人以上の大企業のナレッジ管理に特化したツール 100人以下の中小企業の情報管理・共有に最適のツール サイボウズが提供する大企業向けグループウェア サイボウズが提供する多機能なクラウドサービス オープンソースのポータルソフト デザイン性の高い社内ポータルを作成できるツール 社内メンバーとの”情報共有”に使えるポータルサイト シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単(大手~中堅企業向け) シンプルで簡単(中小規模の企業向け) 多機能 多機能 多機能 多機能 多機能 既読機能 【〇】 【×】 【〇】 【〇】 【×】 【×】 【〇】 コメント機能 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】 【×】 【〇】 【〇】 注意点 法人利用が前提なので、個人利用は不可 5名以上での利用が前提 スケジュールが外部サービスと連携できない 一定以上のITリテラシーが必要 運用に関する情報が少ない 直感的に使いこなせない 教育コストがかかる 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料プランあり ・有料プランでも1人あたり500円/月〜 ・無料プランなし ・有料プラン(クラウド版)は900円/ユーザー/月~ ・無料プランなし ・有料プランは1,000円/ユーザー/月~ 完全無料で利用できます ・無料プランあり ・有料プランは2,000円/ユーザー/月~ ・無料プランなし ・有料プランは749円/ユーザー/月~ 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「Garoon」の詳細はこちら 「kintone」の詳細はこちら 「Concrete CMS」の詳細はこちら 「Notion」の詳細はこちら 「SharePoint」の詳細はこちら 以上のように、ツールによって機能性や価格帯が大きく異なる点に注意しましょう。また、社内ポータルサイトは全社で使われるものなので、「何名規模で使うか」を想定して導入を検討するのがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルサイトの基本的な使い方3選 以下では、社内ポータルサイトの使い方を3つ解説します。サイト導入後のイメージができていない方は、以下を参考にしましょう。 (1)社内掲示板にお知らせを掲載する 1つ目は、「社内掲示板へのお知らせ掲載」です。 社内ポータルサイトの「社内掲示板機能」を活用すると、共有したい情報を「お知らせ」として迅速に社員へ共有可能です。一般的には「企業情報」や「社内イベント」「社内FAQ」などが対象になります。 社内掲示板を通じて情報をリアルタイムで共有することで、情報共有のスピードが向上し、認識の齟齬も防げます。さらに、「お知らせ」として掲載した情報はサイト内に蓄積されて重要な社内資産となるため、「ナレッジ」として活用できるのです。 (2)マニュアルや社内情報を検索する 2つ目は、「マニュアルや社内情報の検索」です。 社内ポータルサイトには膨大な量の社内情報が保管されています。それらの情報を活用するためには、検索機能を使って目当ての情報を素早く抽出する必要があるのです。 しかし、精度の低い検索機能では、一度の検索で情報を絞りきることができない可能性があります。したがって、”複数キーワード検索”や”ファイル内検索”など、超高精度な検索機能が備わった「ナレカン」のようなサービスを選択しましょう。 (3)コメントを残してコミュニケーションを取る 3つ目は、「コメントを通じたコミュニケーション」です。 「コメント機能」があるポータルサイトでは、メールのように形式に縛られたやりとりではなく、対面に近い感覚でスピーディーに会話を進めることが可能です。一方で、他の話題と混ざって重要な情報が埋もれたり、確認漏れが生じたりするケースも少なくありません。 そこで、「共有したい情報」と「コメント機能」が紐づいたサービスを使えば、話題が入り乱れずにスムーズなコミュニケーションが実現します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルサイトを導入すべき企業の特徴 社内ポータルサイトを導入すべき企業の特徴は、以下の通りです。 社員数が多い企業 社員数が多いと、一人一人の質問や問合せへの対応に多くの時間と手間がかかってしまいます。そのため、社内ポータルサイトで社員が自ら調べ、疑問を解決できる体制を整える必要があるのです。 ナレッジやスキルが属人化している企業 業務に関するナレッジやスキルが属人化していると、「○○さんがいないからこの業務が進められない」という状況になりかねません。そのため、個人が有するナレッジやスキルをマニュアル化し、誰でも閲覧できる体制を整える必要があります。 上記の点を踏まえて、社内の情報共有に困っている場合は社内ポータルサイトの導入を検討しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【解決策あり】ポータルサイトの運用が上手くいかない3つの原因 社内ポータルの運用が上手くいかない原因として、以下が挙げられます。事前に原因と解決策を押さえて、迅速に対応できるようにしましょう。 (1)欲しい情報が見つからない 1つ目の原因として、「目的の情報がすぐに見つからない」ことが挙げられます。 社内ポータルサイトに蓄積した情報は、活用されなければ意味がありません。しかし、検索機能が乏しかったり、情報の整理ができていなかったりすると「どこに、何の情報があるのか分からない」という問題に直面するのです。 したがって、誰でも簡単に欲しい情報にアクセスできる体制に改善していきましょう。具体的には、高精度の検索機能やフォルダ機能が備わっているツールの導入が効果的です。 (2)明確な運用ルールがない 2つ目の原因として、「明確な運用ルールがない」ことが挙げられます。 運用ルールが明確でないと、メンバーによって情報の共有方法が異なったり、情報が散乱したりする事態につながります。したがって、ポータルサイトの作成や管理に関するルールを策定して、情報を見やすく管理しましょう。 また、運用ルールだけでなく、テンプレートを活用する方法も効果的です。社内ポータルで文書を共有する場合、テンプレートを使えば項目に従って情報を入力するだけで文書を作れるうえ、体裁も統一できます。 (3)設計が合っていない 3つ目の原因として、「自社に合った設計になっていない」ことが挙げられます。 たとえば、一から社内ポータルを構築した場合「情報がどこにあるのか分かりづらい」「情報にたどり着くのに工数がかかる」といったトラブルが起こりがちです。以上のように、情報へのアクセス性が悪ければ、サイトを構築しても使われなくなってしまいます。 したがって、自力で社内ポータルを構築するのに不安がある場合は、「自社に合わせたフォルダ・ルール設計」を支援する「ナレカン」のような、手厚いサポート体制が整ったサービスがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ おすすめのクラウド型社内ポータルサイトまとめ ここまで、おすすめのクラウド型社内ポータルサイトや選定ポイント、上手く運用できない原因をご紹介しました。 クラウド型社内ポータルサイトで社内情報を一元化すれば、格納場所が分散していた資料やデータを体系的にまとめられ、仕事で活用しやすくなります。また、全社共通で周知したい情報もスムーズに共有できるので、業務効率の向上が期待できるのです。 なかでも「検索性の高いサービス」であれば、共有した情報をあとから簡単に振り返ることができます。一方、多機能で複雑な操作性の社内ポータルを導入すると、社員が使いこなせないため「誰でも簡単に使える操作性やデザインのサービス」を選びましょう。 結論、社内ポータルサイトの構築には、シンプルな操作性で簡単に情報共有ができ、高精度の検索機能で欲しい情報がすぐに見つかるツール「ナレカン」が最適です 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、ナレッジ管理・共有のストレスを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む
2025年10月03日【最新版】人気のクラウド型社内ポータルサイト7選を徹底比較!昨今、社内向けのWebサイトである「社内ポータルサイト」を介して情報共有をする企業が増えています。とくに、クラウド型は自社で開発したりサーバ等を管理したりする必要がないので、ITに関する知識がない企業でも手軽に使い始められる点が人気です。 しかし、「クラウド型の社内ポータルサイトを導入したいが、どのように選定したらよいか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、おすすめのクラウド型社内ポータルサイト7選と選定ポイントを中心に解説します。 自社に適した社内ポータルサイトを選定するポイントを知りたい 社内の総合ポータルサイトを作れるツールを比較検討したい 誰でも簡単に「社内お知らせ」ができるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、自社にマッチする社内ポータルサイトが見つかるだけでなく、運用のポイントまで押さえられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 クラウド型社内ポータルサイトの導入メリット2 社内ポータルサイトの選定ポイント4選2.1 (1)簡単に操作できるか2.2 (2)スムーズに導入できるか2.3 (3)セキュリティ対策が万全か2.4 (4)スマホからでも確認しやすいか3 人気あり!おすすめのクラウド型社内ポータルサイト7選3.1 【ナレカン】100人以上の大企業のナレッジ管理に特化したツール3.2 【Stock】100人以下の中小企業の情報管理・共有に最適のツール3.3 【Garoon】サイボウズが提供する大企業向けグループウェア3.4 【kintone】サイボウズが提供する多機能なクラウドサービス3.5 【Concrete CMS】オープンソースのポータルソフト3.6 【Notion】デザイン性の高い社内ポータルを作成できるツール3.7 【SharePoint】社内メンバーとの”情報共有”に使えるポータルサイト4 無料から試せる!クラウド型社内ポータルサイトの比較表5 社内ポータルサイトの基本的な使い方3選5.1 (1)社内掲示板にお知らせを掲載する5.2 (2)マニュアルや社内情報を検索する5.3 (3)コメントを残してコミュニケーションを取る6 社内ポータルサイトを導入すべき企業の特徴7 【解決策あり】ポータルサイトの運用が上手くいかない3つの原因7.1 (1)欲しい情報が見つからない7.2 (2)明確な運用ルールがない7.3 (3)設計が合っていない8 おすすめのクラウド型社内ポータルサイトまとめ クラウド型社内ポータルサイトの導入メリット クラウド型社内ポータルサイトの導入メリットは、おもに以下の2つです。 業務効率が上がる 社内ポータルサイトには、情報を整理できる「管理機能」や、欲しい情報がすぐに見つかる「検索機能」などが豊富に備わっています。そのため、社内ポータルで情報連携を改善することで、業務スピードの向上や業務品質の均一化が期待できるのです。 ナレッジ(知識・経験)が蓄積される 社内ポータルサイトは、あらゆるナレッジ(知識・経験)が蓄積される場所になります。社内ポータルを通して社内wikiや業務ノウハウを共有することで、ナレッジが蓄積され、属人化防止につながるのです。 開発・運用コストを抑えられる クラウド型のポータルサイトでは、サービスに不具合があった場合にベンダー(システム提供者)が対応します。そのため、ITに詳しい人材のいない「非IT企業」であっても、開発・運用コストを抑えてスムーズに導入できる点がメリットです。 以上のように、社内ポータルサイトはあらゆる情報を蓄積でき、属人化の防止や業務効率の向上につながります。有効活用するために、業務にどのような利益をもたらすのかを把握し、具体的なイメージを持っておきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルサイトの選定ポイント4選 以下では、社内ポータルサイトを選定するときに押さえるべきポイントを4つご紹介します。ポータルサイトの導入に失敗したくない方は必見です。 (1)簡単に操作できるか 1つ目のポイントは、「ITに詳しくないメンバーでも簡単に操作できるか」です。 社内ポータルサイトは全社員が利用するので、誰でも簡単に使いこなせるシンプルなツールが理想です。とくに、従業員数が多い企業では「年齢層」や「ITリテラシー」を考慮して選定しなければ、情報の更新や閲覧がされなくなってしまいます。 したがって、「便利そうだから」と多機能なツールを選ぶのではなく、必要な機能に過不足のないツールを選びましょう。 (2)スムーズに導入できるか 2つ目のポイントは、「スムーズに導入できるか」です。 社内ポータルサイトの導入には、様々な作業が伴います。具体的には、サイトの初期セットアップや運用ルールの制定、既存データの移行など、複雑で時間のかかる初期設定をしなければなりません。 また、運営元のサポート体制が手厚いかは、ツール運用の成功を左右するため、決裁者の承認を得るうえでも重要です。一方、サイト導入時に初期設定に関するサポートを受けられれば、担当者の負担を最小限に抑えつつ、スムーズな運用が開始できます。 (3)セキュリティ対策が万全か 3つ目のポイントは、「セキュリティ対策が万全であるか」です。 社内ポータルサイトは、自社が保有する様々な情報にアクセスすることができるサイトです。そのため、セキュリティ対策が不完全だと、不正アクセスによって社外秘の情報が漏えいしてしまう危険性もあります。 したがって、社内ポータルサイトを導入するときは、高セキュアなツールを選ぶようにしましょう。 (4)スマホからでも確認しやすいか 4つ目のポイントは、「スマホでも確認しやすいか」です。 職種によっては、オフィス外で社内ポータルサイトにアクセスする機会も少なくありません。たとえば、商談や営業で社外に出ている場合、スマホに対応していないツールでは社内ポータルサイトにアクセスするのに手間がかかってしまいます。 したがって、オフィス外でも快適に情報を参照できるよう、「ナレカン」のようにスマホでの利用にも最適化されたツールを選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 人気あり!おすすめのクラウド型社内ポータルサイト7選 以下では、おすすめのクラウド型社内ポータルサイトをご紹介します。 社内ポータルはあらゆる情報の入り口になるため、社内の重要なお知らせを常に掲示できなくてはなりません。また、社内で活用されるポータルサイトにするには、「知りたい情報に簡単にアクセスできること」を重視して構築しましょう。 そこで、「高精度の検索機能」を備えたサービスを選べば、情報を振り返りやすい体制が整います。とくに、どこに何の情報があるのかが分からなければ閲覧しないメンバーが出るため、「検索しやすい操作性やUI(画面デザイン)であるか」も重要なポイントです。 結論、社内ポータルサイトに最適なのは、社内のナレッジを簡単に一元管理でき、超高精度の検索機能で目的の情報に即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンでは「社内お知らせ」機能で全社へ簡単に情報を共有し、「ヒット率100%」の超高精度の検索機能で必要な情報をすぐに見つけられます。また、どのナレッジがどの程度活用されているかを把握できる機能もあり、効果的なナレッジ活用が実現可能です。 【ナレカン】100人以上の大企業のナレッジ管理に特化したツール 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンで社内ポータル(社内お知らせ)を作成する手順 ナレカンでは、下記のように、重要な情報をアナウンスできます。 また、管理画面から、社内お知らせの「レイアウト」や「公開/非公開」も簡単に調整できます。 そのため、わずかな工数で全社員向けにアナウンスできるので、担当者の負担を最小限に抑えられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Stock】100人以下の中小企業の情報管理・共有に最適のツール Stockは、非IT企業の65歳の方でも即日使いこなせるシンプルなツールです。 「Stock」の「ノート」にはあらゆる情報を残せるだけでなく、任意のメンバーにリアルタイムで共有できます。また、ノートには「メッセージ」や「タスク」を紐づけられるので、情報が分散する煩わしさを解消できるのです。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 <Stockをおすすめするポイント> ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 <Stockの口コミ・評判> 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ(栃木SC) 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 <Stockの料金> フリープラン :無料 ビジネスプラン :500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数:5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Garoon】サイボウズが提供する大企業向けグループウェア <Garoonの特徴> 社内ポータルを手軽に作成できる ドラッグ&ドロップやテンプレート機能で、誰でも手間をかけずに社内ポータルを作成できます。 大規模企業向け 同社が運営している「サイボウズOffice」と比較して、Garoonは、”企業規模が100名以上の企業向けツール”になっています。 <Garoonの機能・使用感> お知らせ機能が充実している 掲示板の”掲載期間設定”や”閲覧確認機能”を活用すれば、メールを使わずに全社へ周知できます。そのため、社員数が多い企業や掲示期間を設定して投稿したい場合に便利です。 kintoneと連携して使える Garoonのポータル上に、kintoneアプリで作成した案件管理や売上管理などのグラフを表示し、ダッシュボードのように利用できます。また、kintoneの通知や未処理アプリの一覧もGaroon上で表示できるため、必要な情報をすぐに確認するのに便利です。 <Garoonの注意点> スケジュールが外部サービスと連携できない Garoonには、スケジュール機能が備わっている一方、outlookやGoogleのカレンダーと連携できないため、予定が重複しない様に注意が必要です。 直感的に利用できない 利用しているユーザーからは「もう少し直感的な使い方が出来れば良い。若干昔のデザインや動作がある。特にデザインは今風に刷新してほしい。」との声があります。(引用:ITトレンド) <Garoonの料金> 以下は、クラウド版の価格です。 900円/ユーザー/月(1,000ユーザー以上の場合は、要問合せ) 以下は、パッケージ版の新規ライセンスの料金です。 ランクA:600,000円/50ユーザー ランクB:11,000円/1ユーザー(51~249ユーザー) ランクC:10,000円/1ユーザー(250~499ユーザー) ランクD:9,000円/1ユーザー(500~999ユーザー) ランクE:8,000円/1ユーザー(1,000~2,499ユーザー) ランクF:7,500円/1ユーザー(2,500~4,999ユーザー) ランクG:要問合わせ(5,000~9,999ユーザー) ランクH:要問合わせ(10,000ユーザー~) Garoonの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【kintone】サイボウズが提供する多機能なクラウドサービス <kintoneの特徴> 独自の業務アプリを作成できる プログラミングの知識を問わず、ノーコードで業務アプリを作ることが可能です。自社の業務内容や課題に合わせたアプリを作れるため、業務の効率化を図れます。 多言語に対応 表示言語は、日本語・英語・中国語・スペイン語・韓国語など、さまざまな言語に切り替えることができ、グローバル企業にも適しています。 <kintoneの機能・使用感> データをグラフ化できる 記入したデータをグラフ化する「レポート機能」が備わっています。リアルタイムでデータがグラフに反映されるため、更新の手間がかかりません。 全文検索ができる タイトルや条件、キーワードを絞り込んで全文検索が可能です。さらに、文字情報以外にも添付ファイルの中身まで検索対象となるため、必要な情報まで迅速にたどり着けます。 <kintoneの注意点> 一定以上のITリテラシーが必要 アプリを自由にカスタマイズできる一方、高いITリテラシーがないと上手く活用できない可能性があります。 バックアップが取りにくい ユーザーからは「もし間違えてデータを消してしまっても元に戻せない。データはcsvに出力することは可能だが、戻す場合、項目によってはそのまま戻せないものもあり、非常に手間がかかる。」といった声が寄せられています。(参考:ITreview) 直感的に使えない 「複雑なカスタマイズを行う際にもう少し直感的なUIが欲しいと感じました。特に、フォームの設計やフィールドの配置において、ドラッグ&ドロップ操作の精度や柔軟性が向上するとより使いやすくなります。」という声が寄せられています。(参考:ITトレンド) <kintoneの料金体系> ライトコース:1,000円/ユーザー/月 スタンダードコース:1,800円/ユーザー/月 ワイドコース:3,000円/ユーザー/月 kintoneの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Concrete CMS】オープンソースのポータルソフト <Concrete CMSの特徴> 誰でも無料で使える Concrete CMSは、誰でも簡単にHPの運用ができるCMS(コンテンツ・マネージメント・システム)です。オープンソースなので誰でも無料で使えます。 ページの編集がしやすい 編集したい部分をクリックするだけで編集できるので、ページを行き来する手間がかかりません。 <Concrete CMSの機能・使用感> 使い方が詳しく記載されている バージョンごとの勉強会の解説録画がアップロードされているため、難しい操作でも理解しやすいです。 セキュリティ対策が高い IPアドレスブロック機能の搭載や暗号化して復号できない形式のパスワード設定など、万全のセキュリティ対策によって大企業でも安心して利用できます。 <Concrete CMSの注意点> 運用に関する情報が少ない Concrete CMSは国内利用者が少ないため、ほかのツールに比べて情報が少なく、コミュニティーで情報を調べる必要があります。 インストールするのに手間がかかる Concrete CMSは、ホスティング環境もしくはローカル環境にインストール可能です。ただし、設定に手間がかかる点に注意しましょう。 動作が重くなることがある 利用しているユーザーからは「ドラッグ&ドロップで直感的に編集ができるというメリットが有る一方で、この機能を優先したため、読み込み速度が遅くなるケースが多々あります」との意見が挙がっています。(参考:ITreview) <Concrete CMSの料金> オープンソースのサービスなので、完全無料で利用できます。 Concrete CMSの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Notion】デザイン性の高い社内ポータルを作成できるツール Notionの特徴 かっこいいサイトを作れる Notionは画像やページの編集の自由度が高い点が特徴です。そのため、かっこいい社内ポータルサイトを作りたい場合に役立ちます。 ポータル以外の機能も充実している 社内ポータルを作るだけでなく、タスクやプロジェクト管理・データベース作成にも活用可能です。したがって、ひとつのツールであらゆる用途に活用したいという方に適しています。 Notionの機能・使用感 テンプレート機能が充実している Notionには豊富なテンプレートが用意されています。そのため、社内ポータルのトップページを作ったり、お知らせや社内wikiなどの体裁を整えたりするのに便利です。 動作が重くなる場合がある オリジナリティのあるページを自由に作成できる一方で、複雑な構造を作ると動作が重くなり、開くまでに時間がかかる点に注意が必要です。読み込みが遅いときは、履歴を削除すると解消できる場合があります。 Notionの注意点 直感的に使いこなせない Notionは構造化したサイトを作れるように、さまざまな編集機能が備わっています。一方で、「各機能がどのように使えるのかが分かりにくい」ため、ITに不慣れな場合は直感的に使いこなせない可能性があります。 検索機能が使いづらい ユーザーからは「まだページが増えてくると検索に時間がかかることがあり、タグやリンクの運用ルールをチームで統一する必要があります。AI機能による自動要約や検索補助がもう少し強化されると、大量情報でも迷わずアクセスできると思います。」という声があります。(参考:ITreview) Notionの料金体系 フリー:無料 プラス:2,000円/ユーザー/月 ビジネス:3,800円/ユーザー/月 エンタープライズ:要問合わせ Notionの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【SharePoint】社内メンバーとの”情報共有”に使えるポータルサイト SharePointの特徴 社内ポータルを自由に構築できる SharePointは、目的に応じて社内ポータルを自由に構築できます。たとえば、チームで完結するファイル共有には「チームサイト」、全社向けには掲示板のように使える「コミュニケーションサイト」と、利用用途に合わせて展開可能です。 Microsoft製品と連携できる SharePoint上でWordやExcelのファイルを編集したり、Outlookのスケジュールと連携させたりできるので、Microsoft社の製品を多用している会社に向いています。 SharePointの機能・使用感 サイトを簡単に作成できる SharePointはMicrosoft社の製品であるため、AIデジタルアシスタントである「Copilot」を連携して利用できます。Copilotを使えば、数個のプロンプトとクリック操作だけで目的のサイトを作成可能なため、手間がかからず便利です。 必要なファイルがすぐに見つかる 全文検索機能がついているので、ファイルの中身を開くことなく検索をかけることができます。そのため、スピーディーに情報へアクセスするのに役立ちます。 SharePointの注意点 教育コストがかかる SharePointでは、管理者が作成したサイト上にページを用意し、コンテンツを配置することで情報共有をします。つまり、情報共有のために自社独自の使い方を「全メンバーに教育する必要がある」のです。 自由度が低い 利用しているユーザーからは「ある程度フォーマット化されている分、自由度が高くないことが多い。」という声があります。(参考:ITreview) SharePointの料金体系 SharePoint (プラン 1):749円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Basic:899円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月 また、Microsoft 365 Copilot(4,497円/ユーザー/月)を追加すれば、 SharePointサイトやライブラリ、フォルダー内の情報を駆使して、簡単にエージェントを作成できるようになります。さまざまなエージェントを作ることで、生産性の向上が図れます。 SharePointの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 無料から試せる!クラウド型社内ポータルサイトの比較表 以下は、クラウド型社内ポータルサイトの比較表です。(左右にスクロールできます。)なかには、無料から利用できるものもあるので、担当者の方は必見です。 ナレカン【一番おすすめ】 Stock【おすすめ】 Garoon kintone Concrete CMS Notion SharePoint 特徴 100人以上の大企業のナレッジ管理に特化したツール 100人以下の中小企業の情報管理・共有に最適のツール サイボウズが提供する大企業向けグループウェア サイボウズが提供する多機能なクラウドサービス オープンソースのポータルソフト デザイン性の高い社内ポータルを作成できるツール 社内メンバーとの”情報共有”に使えるポータルサイト シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単(大手~中堅企業向け) シンプルで簡単(中小規模の企業向け) 多機能 多機能 多機能 多機能 多機能 既読機能 【〇】 【×】 【〇】 【〇】 【×】 【×】 【〇】 コメント機能 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】 【×】 【〇】 【〇】 注意点 法人利用が前提なので、個人利用は不可 5名以上での利用が前提 スケジュールが外部サービスと連携できない 一定以上のITリテラシーが必要 運用に関する情報が少ない 直感的に使いこなせない 教育コストがかかる 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料プランあり ・有料プランでも1人あたり500円/月〜 ・無料プランなし ・有料プラン(クラウド版)は900円/ユーザー/月~ ・無料プランなし ・有料プランは1,000円/ユーザー/月~ 完全無料で利用できます ・無料プランあり ・有料プランは2,000円/ユーザー/月~ ・無料プランなし ・有料プランは749円/ユーザー/月~ 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「Garoon」の詳細はこちら 「kintone」の詳細はこちら 「Concrete CMS」の詳細はこちら 「Notion」の詳細はこちら 「SharePoint」の詳細はこちら 以上のように、ツールによって機能性や価格帯が大きく異なる点に注意しましょう。また、社内ポータルサイトは全社で使われるものなので、「何名規模で使うか」を想定して導入を検討するのがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルサイトの基本的な使い方3選 以下では、社内ポータルサイトの使い方を3つ解説します。サイト導入後のイメージができていない方は、以下を参考にしましょう。 (1)社内掲示板にお知らせを掲載する 1つ目は、「社内掲示板へのお知らせ掲載」です。 社内ポータルサイトの「社内掲示板機能」を活用すると、共有したい情報を「お知らせ」として迅速に社員へ共有可能です。一般的には「企業情報」や「社内イベント」「社内FAQ」などが対象になります。 社内掲示板を通じて情報をリアルタイムで共有することで、情報共有のスピードが向上し、認識の齟齬も防げます。さらに、「お知らせ」として掲載した情報はサイト内に蓄積されて重要な社内資産となるため、「ナレッジ」として活用できるのです。 (2)マニュアルや社内情報を検索する 2つ目は、「マニュアルや社内情報の検索」です。 社内ポータルサイトには膨大な量の社内情報が保管されています。それらの情報を活用するためには、検索機能を使って目当ての情報を素早く抽出する必要があるのです。 しかし、精度の低い検索機能では、一度の検索で情報を絞りきることができない可能性があります。したがって、”複数キーワード検索”や”ファイル内検索”など、超高精度な検索機能が備わった「ナレカン」のようなサービスを選択しましょう。 (3)コメントを残してコミュニケーションを取る 3つ目は、「コメントを通じたコミュニケーション」です。 「コメント機能」があるポータルサイトでは、メールのように形式に縛られたやりとりではなく、対面に近い感覚でスピーディーに会話を進めることが可能です。一方で、他の話題と混ざって重要な情報が埋もれたり、確認漏れが生じたりするケースも少なくありません。 そこで、「共有したい情報」と「コメント機能」が紐づいたサービスを使えば、話題が入り乱れずにスムーズなコミュニケーションが実現します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルサイトを導入すべき企業の特徴 社内ポータルサイトを導入すべき企業の特徴は、以下の通りです。 社員数が多い企業 社員数が多いと、一人一人の質問や問合せへの対応に多くの時間と手間がかかってしまいます。そのため、社内ポータルサイトで社員が自ら調べ、疑問を解決できる体制を整える必要があるのです。 ナレッジやスキルが属人化している企業 業務に関するナレッジやスキルが属人化していると、「○○さんがいないからこの業務が進められない」という状況になりかねません。そのため、個人が有するナレッジやスキルをマニュアル化し、誰でも閲覧できる体制を整える必要があります。 上記の点を踏まえて、社内の情報共有に困っている場合は社内ポータルサイトの導入を検討しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【解決策あり】ポータルサイトの運用が上手くいかない3つの原因 社内ポータルの運用が上手くいかない原因として、以下が挙げられます。事前に原因と解決策を押さえて、迅速に対応できるようにしましょう。 (1)欲しい情報が見つからない 1つ目の原因として、「目的の情報がすぐに見つからない」ことが挙げられます。 社内ポータルサイトに蓄積した情報は、活用されなければ意味がありません。しかし、検索機能が乏しかったり、情報の整理ができていなかったりすると「どこに、何の情報があるのか分からない」という問題に直面するのです。 したがって、誰でも簡単に欲しい情報にアクセスできる体制に改善していきましょう。具体的には、高精度の検索機能やフォルダ機能が備わっているツールの導入が効果的です。 (2)明確な運用ルールがない 2つ目の原因として、「明確な運用ルールがない」ことが挙げられます。 運用ルールが明確でないと、メンバーによって情報の共有方法が異なったり、情報が散乱したりする事態につながります。したがって、ポータルサイトの作成や管理に関するルールを策定して、情報を見やすく管理しましょう。 また、運用ルールだけでなく、テンプレートを活用する方法も効果的です。社内ポータルで文書を共有する場合、テンプレートを使えば項目に従って情報を入力するだけで文書を作れるうえ、体裁も統一できます。 (3)設計が合っていない 3つ目の原因として、「自社に合った設計になっていない」ことが挙げられます。 たとえば、一から社内ポータルを構築した場合「情報がどこにあるのか分かりづらい」「情報にたどり着くのに工数がかかる」といったトラブルが起こりがちです。以上のように、情報へのアクセス性が悪ければ、サイトを構築しても使われなくなってしまいます。 したがって、自力で社内ポータルを構築するのに不安がある場合は、「自社に合わせたフォルダ・ルール設計」を支援する「ナレカン」のような、手厚いサポート体制が整ったサービスがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ おすすめのクラウド型社内ポータルサイトまとめ ここまで、おすすめのクラウド型社内ポータルサイトや選定ポイント、上手く運用できない原因をご紹介しました。 クラウド型社内ポータルサイトで社内情報を一元化すれば、格納場所が分散していた資料やデータを体系的にまとめられ、仕事で活用しやすくなります。また、全社共通で周知したい情報もスムーズに共有できるので、業務効率の向上が期待できるのです。 なかでも「検索性の高いサービス」であれば、共有した情報をあとから簡単に振り返ることができます。一方、多機能で複雑な操作性の社内ポータルを導入すると、社員が使いこなせないため「誰でも簡単に使える操作性やデザインのサービス」を選びましょう。 結論、社内ポータルサイトの構築には、シンプルな操作性で簡単に情報共有ができ、高精度の検索機能で欲しい情報がすぐに見つかるツール「ナレカン」が最適です 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、ナレッジ管理・共有のストレスを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む -
 2025年09月25日【SharePoint】簡単!社内ポータルサイトの作り方や事例を徹底解説昨今、組織内の情報共有を活性化する手段として「社内ポータル」を整備する企業が増えています。とくに、Microsoft社が提供する「SharePoint」は、デザイン性の高い社内ポータルを簡単に作成できるので注目されているのです。 しかし、なかには「SharePointを利用したいが、社内ポータルサイトを作成するのが難しそう」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、SharePointを使った社内ポータルサイトの作り方や導入事例を中心に解説します。 SharePointでできることや機能を知りたい SharePointで社内ポータルを作る方法を学びたい 簡単に社内ポータルを作れるツールを探している という方はこの記事を参考にすれば、SharePointを使って、社内ポータルサイトを作成する方法が分かるほか、自社に最適なITツールが見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 SharePoint(シェアポイント)とは?1.1 SharePointの特徴1.2 SharePointで何ができる?1.3 SharePointとOneDriveとの違い1.4 SharePointの料金体系2 SharePointで社内ポータルサイトを作るメリット3 【口コミあり】SharePointで社内ポータルサイトをつくるデメリット3.1 SharePointユーザーからの口コミ3.2 SharePointを利用するときの注意点4 【必見】SharePointより簡単に社内ポータルをつくれるツール4.1 社内報などの全体アナウンスに最適なツール「ナレカン」4.2 ナレカンで「社内掲示板」を使用した例5 SharePointで社内ポータルを作るための基本機能6 【画像つき】SharePointで社内ポータルを作成する方法6.1 ステップ1|サイトを作成する6.2 ステップ2|ページを追加する6.3 ステップ3|ナビゲーションを設定する7 SharePointで社内ポータルサイトを作成するときのポイント3つ7.1 (1)ファイルのダウンロードを制御する7.2 (2)OneDriveに同期する7.3 (3)マニュアルを整備する8 SharePointでデザイン性の高い社内ポータルを作る方法8.1 カラーを統一する8.2 テンプレートを利用する9 SharePointの活用方法3選10 SharePointで構築した社内ポータルサイトの活用事例11 番外編|SharePointでテンプレートをカスタマイズする方法12 SharePointを活用した社内ポータルサイトの作り方まとめ SharePoint(シェアポイント)とは? 引用:SharePointのサインインページ はじめに、SharePointの特徴やできること、類似サービスであるOneDriveとの違いを解説します。SharePointの特徴を押さえ、自社に最適かどうか検討しましょう。 SharePointの特徴 SharePointとは、Microsoft社が提供する社内メンバーとの”ファイル共有”や”情報共有”に使えるポータルサイトを構築できるサービスです。SharePointの特徴は以下の4つが挙げられます。 自由な社内ポータルサイトの構築 SharePointは目的に応じて自由にカスタマイズできます。たとえば、チームで完結するファイル共有には「チームサイト」、全社向けには掲示板のように使える「コミュニケーションサイト」と、利用用途に合わせて展開できます。 マルチデバイス対応 SharePointで作成したデータは、クラウド(インターネット上の管理場所)へ保存され、社外のネットワークからもアクセスできます。したがって、時間や場所・デバイスを問わず必要な情報が手に入るのです。 ドキュメントの管理 作成・保存したドキュメントファイルをSharePoint上に保存できます。チーム全体で共有されるので、円滑なファイル管理が可能なうえ、ファイルのバージョン履歴が自動的に管理されるので、データの復元も可能です。 ワークフローの管理 煩雑な業務フローを自動化することで、申請者と承認者双方の手間や負担を軽減します。たとえば、「特定のユーザーが文書を作成したら、メンバーにメールが自動送信される」という条件を設定すると、共有の手間を省けるのです。 このように、SharePointは社内ポータルの運用を効率化するさまざまな特徴があります。 SharePointで何ができる? SharePointは運用次第であらゆる業務に使えるツールですが、基本的には以下のようなことができます。 <機能> <概要> 情報共有と共同編集 あらゆる情報をクラウド(インターネット上の管理場所)で保存するので、リアルタイムで情報共有と共同編集ができます。そのため、場所を問わずにアクセスでき、テレワークにも十分に対応可能です。 グループの作成 グループを作成して、ファイルにアクセスできるメンバーを制限できます。逆に、アクセス権を設定さえすれば、社外の人とも情報を共有できます。 ファイルの一括検索 全文検索機能がついているので、ファイルの中身を開くことなく検索をかけることができ、情報へのアクセスがスピーディーになります。 アンケートの作成・集計 SharePointではアンケートの作成機能があります。解答の字数制限や選択肢の設定も可能です。 Microsoft製品との連携 SharePoint上でWordやExcelのファイルを編集したり、Outlookのスケジュールと連携させたりできるので、Microsoft社の製品を多用している会社に向いています。 このように、SharePointはグループの作成によりアクセスできるメンバーを制限したり、アンケートを作成したりすることも可能です。 SharePointとOneDriveとの違い Microsoft社が提供する類似サービスにOneDriveがありますが、以下の表の通り、機能が一部SharePointとは異なります。 SharePoint OneDrive 主な役割 ・ポータルサイトの構築 ・書類の保管、ドキュメントの共有 ・業務プロセスの自動化 ・ファイル管理 社内ポータルサイトの作成 できる できない 検索機能 【〇】 全文検索機能で、ファイル内の情報を一括検索できる 【△】 ファイル名に書かれているワードのみヒットする このように、SharePointとOneDriveではメインの機能が異なるので、自社の課題に合わせてツールを選びましょう。 SharePointの料金体系 SharePoint Onlineには、以下の3つの料金プランがあります。 SharePoint (プラン 1):749円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Basic:899円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月 また、Microsoft 365 Copilot(4,497円/ユーザー/月)を追加すれば、 SharePointサイトやライブラリ、フォルダー内の情報を駆使して、簡単にエージェントを作成できるようになります。さまざまなエージェントを作ることで、生産性の向上が図れます。 引用1:SharePoint Online のオプションを比較 ▶ Microsoft365の公式サイト 引用2:Microsoft Teams ▶ ニーズに応じて最適な Microsoft Teams をお選びください 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointで社内ポータルサイトを作るメリット 以下では、SharePointで社内ポータルを作成する3つのメリットを解説します。 Office製品と連携ができる Teamsと連携させると、Teamsでのチーム作成に連動して自動的にSharePoint Onlineサイトが作成されます。作成されたサイトをコンテンツの格納場所として活用すれば、ファイルの保管先を探す手間が省けます。 コメント機能やいいね機能を搭載 SharePointには、コメントといいね機能が搭載されており、メールに比べて気軽にコミュニケーションがとれます。また、誰がコメントやいいねをしたのかも表示されるため、一方通行な情報共有ではなくなり、社員同士の連携強化にもつながります。 スマホでも閲覧できる SharePointはあらゆるデバイスでコンテンツが利用できるので、営業職など頻繁にパソコンを開かないメンバーにも浸透しやすい特徴があります。 このように、SharePointは、Microsoft製品と馴染みのある企業にとって、使いやすいです。しかし、格納した情報が見つからない恐れがあるので、散在する社内情報の一元化には「ナレカン」のようなシンプルなツールの方が適しているのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【口コミあり】SharePointで社内ポータルサイトをつくるデメリット 以下では、SharePointで社内ポータルサイトを作るデメリットや注意点をご紹介します。口コミで利用者の意見もわかるため、導入を検討している方は必見です。 SharePointユーザーからの口コミ ここでは、実際に利用しているユーザーからの口コミを紹介します。利用しているユーザーからは「初心者には難しく、直感的に使いこなせない」という声があります。 ご紹介する口コミはすべてITreviewより引用しています。 非公開ユーザー 投稿日:2025年9月11日 種類ごとにデスクトップ上にフォルダを作成するがやり方を間違うとちゃんと反映出来なかったり思っていたのと違うリンクに飛んだりするのでもっと直感的に作れると良い。 非公開ユーザー 投稿日:2025年9月1日 目的のファイルが見つけにくいので不要なファイルは削除できる機能があれば便利だと思います。 非公開ユーザー 投稿日:2025年8月27日 初心者には使い方がわかりづらい。 ボタンや設定項目が多く、「どこで何を設定すればいいか」が分かりにくい。 非公開ユーザー 投稿日:2025年7月27日 SharePointを利用している時に、容量がひっ迫するということがしばしば起こります。SharePoint上で、各ファイルの参照回数やファイル容量に基づいた、削減対象のサジェスチョン機能が提供されると嬉しいと感じます。 非公開ユーザー 投稿日:2025年7月21日 資料の共有の仕方が最初はわからなかったため、マニュアルもしくはガイダンスのようなものがあれば、より利用はスムーズに進むのではないかと思います。 上記は利用ユーザーのごく一部の声ですが、導入・操作のハードルの高さに関する意見が多く見られます。 SharePointを利用するときの注意点 以下では、SharePointを利用するときの注意点をご紹介します。 教育コストがかかる SharePointでは、管理者が作成したサイト上にページを用意し、コンテンツを配置することで情報共有をします。つまり、情報共有のために自社独自の使い方を「全メンバーに教育する必要がある」のです。 検索方法が複雑 SharePointでは、全文検索やフォルダ検索ができる一方、日本語だとヒットしないことがあるため工夫が必要です。しかし、社内ポータルサイトで欲しい情報やファイルが見つからないと、業務が滞ってしまうリスクがあります。 保守・運用のためにIT人材が必要になる 一般的なWebサイトに必要な”HTML”を知らなくても使える一方、大幅にカスタマイズすると保守・運用を続けられません。たとえば、担当者の異動や退職のタイミングで、管理ができなくなってしまうケースがあります。 このように、SharePointは教育コストやIT人材不足、検索性などの課題が懸念されます。一方、メールを使える方であれば簡単に情報を集約でき、超高度な検索機能を備えた「ナレカン」のようなツールなら、SharePointよりもスムーズに社内に浸透します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】SharePointより簡単に社内ポータルをつくれるツール 以下では、SharePointよりも簡単に社内ポータルサイトを作成できるツールをご紹介します。 SharePointは、多機能でデザイン性が高いですが、使いこなすのに時間がかかるというデメリットがあります。メンバーに利用を定着させるには、シンプルな操作性で教育コストをかけなくても利用できるツールが必要です。 また、ビジネスシーンで利用する場合には検索機能が優れていることも重要です。ファイル内まで検索できるツールを導入すれば、膨大な情報の中から欲しい情報にすぐアクセスできます。 結論、SharePointよりも簡単に社内ポータルサイトを作成できるのは、簡単でシンプルな操作性を備え、検索機能が超高精度なツール「ナレカン」が最適です。 ナレカンでは、簡単な操作で誰でもすぐに使いこなせるため、運用のためにIT人材に頼る必要もなく、教育コストも抑えられます。また、高精度な検索機能を備えているため、情報へのアクセス性が高く、業務を効率的に進められます。 社内報などの全体アナウンスに最適なツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンで「社内掲示板」を使用した例 ここでは、実際に「ナレカン」で社内ポータルとして使える「社内掲示板」を紹介します。以下は、ナレカンで作成した「社内お知らせ」が一覧表示されている画面です。 「2025年1月の健康診断のお知らせ」を押すと、以下のように内容が「プレビュー」で表示されます。投稿に添付してあるファイルも開かずに中身を確認可能です。 このように、ナレカンの「社内お知らせ」機能を使うと「社内掲示板」が作れます。また、ナレカンの「社内掲示板」は全メンバー向けの情報発信が前提なので、SharePointのように公開するメンバーを一人ずつ設定する手間がかかりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointで社内ポータルを作るための基本機能 以下は、SharePointに備わっている社内ポータルを作るための機能をまとめた表です。 <機能> <概要> サイトコレクション SharePointで作られた複数のサイトをまとめたグループのことです。サイトコレクションごとにアクセス権限を分けて設定することができます。 サイト 各サイトコレクション内にあるワークスペースやWebページを指します。SharePointのチームサイトでは、ドキュメント共有やタスク管理ができます。 ライブラリ SharePoint上のファイルの保管場所を意味します。クラウド上にファイルをアップロードすると他のメンバーも見られるため、共同作業が可能になります。 リスト SharePoint上のデータをExcelのような表で管理できるデータベース機能のことです。データの閲覧や共同編集の他、バージョン管理などさまざまな機能が備わっています。 ページ ポータルサイトのユーザーが閲覧できるWebページを指します。プログラミングの知識がなくても、テキストや画像、動画等を組み合わせることでWebページの作成が可能です。 以上の機能を使うことで、SharePointを社内ポータルとして活用できます。これからSharePointの導入を考えている方は、それぞれの単語の意味を理解した上で、どのように活用していくかを決めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【画像つき】SharePointで社内ポータルを作成する方法 以下では、SharePointを使った社内ポータルサイトの作り方を解説します。手順を押さえて自社に最適な社内ポータルサイトをつくりましょう。 ステップ1|サイトを作成する はじめに、以下の手順に沿って、社内ポータルの基盤を作成しましょう。 SharePointのアプリの[サイトの作成]をクリックする。 [コミュニケーションサイト]もしくは[チームサイト]のどちらかをクリックする。 サイトの作成に必要な情報を入力する。 プライバシー設定をする。 [所有者の追加]から共有先のメールアドレスを追加する。 以上の操作で、社内ポータルを作成する準備は完了です。 ステップ2|ページを追加する 次に、作成するコンテンツを選びましょう。以下では、新規ページを追加するための手順を紹介します。 [新規]をクリックする。 表示される選択肢から[ページ]を選ぶ。 ページのタイトルを入力する。 以上の操作で、新しいページがコンテンツとして追加できます。 ステップ3|ナビゲーションを設定する 画面右上の[編集]からは、リンク追加や名前・アドレスの変更ができます。 また、ナビゲーションのスタイルや色も変えられるので、利用ユーザーがサイトやページへすぐにアクセスできるように、ナビゲーションを適切にカスタマイズしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointで社内ポータルサイトを作成するときのポイント3つ ここからは、社内ポータルサイトをSharePointで作成する3つのポイントを紹介します。以下を実践すれば、より利便性の高い社内ポータルを作成できます。 (1)ファイルのダウンロードを制御する 1つ目のポイントは、ダウンロードの制御機能を活用することです。 SharePointにはダウンロードの制御機能があります。たとえば、特定のメンバーのみにデータのダウンロードを許可したい場合、ファイルのダウンロードが可能なメンバーを個別設定することができます。 このように、制御機能を使えば、情報流出のリスクが軽減し、安全に社内ポータルを運用できるようになるのです。 (2)OneDriveに同期する 2つ目に、OneDriveをすでに活用している場合は、SharePointとの同期も有効です。 OneDriveとSharePointを同期すれば、OneDriveで作成・編集したファイルがすぐにSharePointへ反映されます。結果として、編集後のファイルを都度コピーして保存する手間が省けるので、スムーズに業務を進められるのです。 一方、作成・編集だけでなく削除も同期の対象になるため、誤操作でOneDriveのファイルを削除しないように注意しましょう。 (3)マニュアルを整備する 3つ目に、マニュアルを整備することも運用のポイントとなります。 SharePointは多機能なツールなので、部署によってITリテラシーに差がある場合には、全社に浸透しない可能性があります。したがって、基本的な操作手順をまとめたマニュアルを整備して、SharePointが社内で広く利用されるようにしましょう。 また、社内にITの苦手なメンバーがいる場合には「簡単に社内情報を集約できるツール」を使うことも手法のひとつです。たとえば、社内に散らばる情報を一元化して高精度で検索できる「ナレカン」であれば、操作手順を教育する必要がありません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointでデザイン性の高い社内ポータルを作る方法 以下では、SharePointでデザイン性の高い社内ポータルを作る方法をご紹介します。見やすい社内ポータルにするために、デザインにも気を配るようにしましょう。 カラーを統一する SharePointで社内ポータルを作成するときには、カラーを統一するようにしましょう。 社内ポータルに使われる色がバラバラで、多くの色が使われていると見づらくなり、どれが重要な情報かわからなくなります。一目で情報が伝わるように色やデザインを工夫すると、従業員に活用してもらいやすい社内ポータルを作成できます。 自分の会社のイメージカラーで統一するなど、多くの色を使いすぎない工夫をしましょう。 テンプレートを利用する 見やすいポータルを作成するためには、テンプレートを利用することも有効です。 SharePointでは、サイトテンプレートを選択して、統一されたフォーマットで社内ポータルを作成できます。テンプレートに沿って作成することで、内容の抜けや漏れがなくなるほか、視覚的にわかりやすいポータルになります。 SharePointは多機能でデザイン性が高いため、一から社内ポータルを作成するのが難しいと感じた場合は、テンプレートを利用してみましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointの活用方法3選 SharePointにはさまざまな活用方法があります。具体的には、以下の活用方法が挙げられます。 ファイル共有 SharePoint内のライブラリの中にアップロードされたファイルは、共有権限を与えられた人の中で共有されます。Microsoftのアカウントを持っている人ならば社内外で他者とファイルを共有できるため、ファイル共有ツールとして使えるのです。 ファイル以外の情報共有 たとえば、「更新日」や「更新者」、「更新内容」などの更新履歴といった情報も共有が可能です。また、更新履歴を「リスト」にデータの表として保管できるため、ファイル以外の情報の共有にも便利です。 サイト 多様なテキストやメディア、コンテンツを挿入しながらWebページの作成ができます。そのため、業務ガイドやマニュアル、社内のお知らせサイト、社内ポータルサイトなどのあらゆる使い道のサイトを作れるのです。 以上のようにSharePointにはさまざまな活用方法がある一方、SharePointの導入目的が明確でないと、社員が使い道に迷う恐れがあります。そのため、導入時には、導入目的の周知に努めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointで構築した社内ポータルサイトの活用事例 出典:浅間商事株式会社サイトページ ITサポートサービスなどを提供する浅間商事株式会社では、ファイルサーバーでファイル管理をしていましたが、金銭的コストや人的コストに課題がありました。そこで、従来のファイルサーバーからSharePointへの移行を決定したのです。 現在は、全社共通のサイトに、チームやプロジェクト単位で権限を付与したライブラリを作成し、随時ファイルを追加する運用に変更しています。 その結果、コスト削減が実現したうえに、SharePointのほかの機能を活用することで、業務効率が向上しました。 ただし、浅間商事のように”ITに使い慣れている企業”でない場合、一からポータルサイトを構築・運用するのは困難な可能性もある点に注意しましょう。 参考:浅間公式サイト>ブログ>【第2回:SharePoint編】「Microsoft 365」で実現!中小企業の業務効率化 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 番外編|SharePointでテンプレートをカスタマイズする方法 ここでは、SharePoint内のテンプレートを使用・閲覧できるようにするための方法を解説します。 まず、「コミュニケーションサイト」または「チームサイト」を作成します。その後、サイトの名前・説明・ロゴ・プライバシーレベル・サイト分類・サービス制限・アクセス許可を変更可能です。 つぎに、[サイトの設定]に移動し、[サイトテンプレートの適用]を選択します。 つづいて、サイトテンプレートを選択して追加情報を表示します。組織のニーズを満たす場合は、[テンプレートの使用]を選択します。 新しいサイトを参照し、[サイトコンテンツ]の既存のコンテンツを確認し、以下のカスタマイズガイダンスを取得します。 最後に、サイトの編集を再発行して、新しいコンテンツを閲覧者が利用できるようにします。 以上の手順を踏むと、SharePointのさまざまなテンプレートを利用できるので、自社のコンテンツ作成の手間を軽減したい場合に役立ちます。 参照:Microsoftサポート|SharePointサイト>管理>SharePointサイトテンプレートを適用およびカスタマイズする 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointを活用した社内ポータルサイトの作り方まとめ これまで、SharePointで社内ポータルサイトをつくる方法や運用のメリット、デメリットを中心に解説しました。 SharePointは、多機能で自由度が高いがゆえに、導入方法や操作が難しい点がデメリットです。また、多くの情報を一元管理できる一方、目的の情報がすぐに見つからないことがあります。 とくに、情報共有で使用する場合、必要な情報がすぐに見つからないと迅速な対応ができません。そのため、「ITリテラシーの有無によらず誰でも使いこなせて、検索性に優れたツール」を導入すべきなのです。 したがって、自社での社内ポータル運用には、全社への情報共有を効率化し、目的の情報に即アクセスできる『ナレカン』が最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を社内ポータルとして活用し、自社のナレッジ管理におけるストレスを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む
2025年09月25日【SharePoint】簡単!社内ポータルサイトの作り方や事例を徹底解説昨今、組織内の情報共有を活性化する手段として「社内ポータル」を整備する企業が増えています。とくに、Microsoft社が提供する「SharePoint」は、デザイン性の高い社内ポータルを簡単に作成できるので注目されているのです。 しかし、なかには「SharePointを利用したいが、社内ポータルサイトを作成するのが難しそう」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、SharePointを使った社内ポータルサイトの作り方や導入事例を中心に解説します。 SharePointでできることや機能を知りたい SharePointで社内ポータルを作る方法を学びたい 簡単に社内ポータルを作れるツールを探している という方はこの記事を参考にすれば、SharePointを使って、社内ポータルサイトを作成する方法が分かるほか、自社に最適なITツールが見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 SharePoint(シェアポイント)とは?1.1 SharePointの特徴1.2 SharePointで何ができる?1.3 SharePointとOneDriveとの違い1.4 SharePointの料金体系2 SharePointで社内ポータルサイトを作るメリット3 【口コミあり】SharePointで社内ポータルサイトをつくるデメリット3.1 SharePointユーザーからの口コミ3.2 SharePointを利用するときの注意点4 【必見】SharePointより簡単に社内ポータルをつくれるツール4.1 社内報などの全体アナウンスに最適なツール「ナレカン」4.2 ナレカンで「社内掲示板」を使用した例5 SharePointで社内ポータルを作るための基本機能6 【画像つき】SharePointで社内ポータルを作成する方法6.1 ステップ1|サイトを作成する6.2 ステップ2|ページを追加する6.3 ステップ3|ナビゲーションを設定する7 SharePointで社内ポータルサイトを作成するときのポイント3つ7.1 (1)ファイルのダウンロードを制御する7.2 (2)OneDriveに同期する7.3 (3)マニュアルを整備する8 SharePointでデザイン性の高い社内ポータルを作る方法8.1 カラーを統一する8.2 テンプレートを利用する9 SharePointの活用方法3選10 SharePointで構築した社内ポータルサイトの活用事例11 番外編|SharePointでテンプレートをカスタマイズする方法12 SharePointを活用した社内ポータルサイトの作り方まとめ SharePoint(シェアポイント)とは? 引用:SharePointのサインインページ はじめに、SharePointの特徴やできること、類似サービスであるOneDriveとの違いを解説します。SharePointの特徴を押さえ、自社に最適かどうか検討しましょう。 SharePointの特徴 SharePointとは、Microsoft社が提供する社内メンバーとの”ファイル共有”や”情報共有”に使えるポータルサイトを構築できるサービスです。SharePointの特徴は以下の4つが挙げられます。 自由な社内ポータルサイトの構築 SharePointは目的に応じて自由にカスタマイズできます。たとえば、チームで完結するファイル共有には「チームサイト」、全社向けには掲示板のように使える「コミュニケーションサイト」と、利用用途に合わせて展開できます。 マルチデバイス対応 SharePointで作成したデータは、クラウド(インターネット上の管理場所)へ保存され、社外のネットワークからもアクセスできます。したがって、時間や場所・デバイスを問わず必要な情報が手に入るのです。 ドキュメントの管理 作成・保存したドキュメントファイルをSharePoint上に保存できます。チーム全体で共有されるので、円滑なファイル管理が可能なうえ、ファイルのバージョン履歴が自動的に管理されるので、データの復元も可能です。 ワークフローの管理 煩雑な業務フローを自動化することで、申請者と承認者双方の手間や負担を軽減します。たとえば、「特定のユーザーが文書を作成したら、メンバーにメールが自動送信される」という条件を設定すると、共有の手間を省けるのです。 このように、SharePointは社内ポータルの運用を効率化するさまざまな特徴があります。 SharePointで何ができる? SharePointは運用次第であらゆる業務に使えるツールですが、基本的には以下のようなことができます。 <機能> <概要> 情報共有と共同編集 あらゆる情報をクラウド(インターネット上の管理場所)で保存するので、リアルタイムで情報共有と共同編集ができます。そのため、場所を問わずにアクセスでき、テレワークにも十分に対応可能です。 グループの作成 グループを作成して、ファイルにアクセスできるメンバーを制限できます。逆に、アクセス権を設定さえすれば、社外の人とも情報を共有できます。 ファイルの一括検索 全文検索機能がついているので、ファイルの中身を開くことなく検索をかけることができ、情報へのアクセスがスピーディーになります。 アンケートの作成・集計 SharePointではアンケートの作成機能があります。解答の字数制限や選択肢の設定も可能です。 Microsoft製品との連携 SharePoint上でWordやExcelのファイルを編集したり、Outlookのスケジュールと連携させたりできるので、Microsoft社の製品を多用している会社に向いています。 このように、SharePointはグループの作成によりアクセスできるメンバーを制限したり、アンケートを作成したりすることも可能です。 SharePointとOneDriveとの違い Microsoft社が提供する類似サービスにOneDriveがありますが、以下の表の通り、機能が一部SharePointとは異なります。 SharePoint OneDrive 主な役割 ・ポータルサイトの構築 ・書類の保管、ドキュメントの共有 ・業務プロセスの自動化 ・ファイル管理 社内ポータルサイトの作成 できる できない 検索機能 【〇】 全文検索機能で、ファイル内の情報を一括検索できる 【△】 ファイル名に書かれているワードのみヒットする このように、SharePointとOneDriveではメインの機能が異なるので、自社の課題に合わせてツールを選びましょう。 SharePointの料金体系 SharePoint Onlineには、以下の3つの料金プランがあります。 SharePoint (プラン 1):749円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Basic:899円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月 また、Microsoft 365 Copilot(4,497円/ユーザー/月)を追加すれば、 SharePointサイトやライブラリ、フォルダー内の情報を駆使して、簡単にエージェントを作成できるようになります。さまざまなエージェントを作ることで、生産性の向上が図れます。 引用1:SharePoint Online のオプションを比較 ▶ Microsoft365の公式サイト 引用2:Microsoft Teams ▶ ニーズに応じて最適な Microsoft Teams をお選びください 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointで社内ポータルサイトを作るメリット 以下では、SharePointで社内ポータルを作成する3つのメリットを解説します。 Office製品と連携ができる Teamsと連携させると、Teamsでのチーム作成に連動して自動的にSharePoint Onlineサイトが作成されます。作成されたサイトをコンテンツの格納場所として活用すれば、ファイルの保管先を探す手間が省けます。 コメント機能やいいね機能を搭載 SharePointには、コメントといいね機能が搭載されており、メールに比べて気軽にコミュニケーションがとれます。また、誰がコメントやいいねをしたのかも表示されるため、一方通行な情報共有ではなくなり、社員同士の連携強化にもつながります。 スマホでも閲覧できる SharePointはあらゆるデバイスでコンテンツが利用できるので、営業職など頻繁にパソコンを開かないメンバーにも浸透しやすい特徴があります。 このように、SharePointは、Microsoft製品と馴染みのある企業にとって、使いやすいです。しかし、格納した情報が見つからない恐れがあるので、散在する社内情報の一元化には「ナレカン」のようなシンプルなツールの方が適しているのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【口コミあり】SharePointで社内ポータルサイトをつくるデメリット 以下では、SharePointで社内ポータルサイトを作るデメリットや注意点をご紹介します。口コミで利用者の意見もわかるため、導入を検討している方は必見です。 SharePointユーザーからの口コミ ここでは、実際に利用しているユーザーからの口コミを紹介します。利用しているユーザーからは「初心者には難しく、直感的に使いこなせない」という声があります。 ご紹介する口コミはすべてITreviewより引用しています。 非公開ユーザー 投稿日:2025年9月11日 種類ごとにデスクトップ上にフォルダを作成するがやり方を間違うとちゃんと反映出来なかったり思っていたのと違うリンクに飛んだりするのでもっと直感的に作れると良い。 非公開ユーザー 投稿日:2025年9月1日 目的のファイルが見つけにくいので不要なファイルは削除できる機能があれば便利だと思います。 非公開ユーザー 投稿日:2025年8月27日 初心者には使い方がわかりづらい。 ボタンや設定項目が多く、「どこで何を設定すればいいか」が分かりにくい。 非公開ユーザー 投稿日:2025年7月27日 SharePointを利用している時に、容量がひっ迫するということがしばしば起こります。SharePoint上で、各ファイルの参照回数やファイル容量に基づいた、削減対象のサジェスチョン機能が提供されると嬉しいと感じます。 非公開ユーザー 投稿日:2025年7月21日 資料の共有の仕方が最初はわからなかったため、マニュアルもしくはガイダンスのようなものがあれば、より利用はスムーズに進むのではないかと思います。 上記は利用ユーザーのごく一部の声ですが、導入・操作のハードルの高さに関する意見が多く見られます。 SharePointを利用するときの注意点 以下では、SharePointを利用するときの注意点をご紹介します。 教育コストがかかる SharePointでは、管理者が作成したサイト上にページを用意し、コンテンツを配置することで情報共有をします。つまり、情報共有のために自社独自の使い方を「全メンバーに教育する必要がある」のです。 検索方法が複雑 SharePointでは、全文検索やフォルダ検索ができる一方、日本語だとヒットしないことがあるため工夫が必要です。しかし、社内ポータルサイトで欲しい情報やファイルが見つからないと、業務が滞ってしまうリスクがあります。 保守・運用のためにIT人材が必要になる 一般的なWebサイトに必要な”HTML”を知らなくても使える一方、大幅にカスタマイズすると保守・運用を続けられません。たとえば、担当者の異動や退職のタイミングで、管理ができなくなってしまうケースがあります。 このように、SharePointは教育コストやIT人材不足、検索性などの課題が懸念されます。一方、メールを使える方であれば簡単に情報を集約でき、超高度な検索機能を備えた「ナレカン」のようなツールなら、SharePointよりもスムーズに社内に浸透します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】SharePointより簡単に社内ポータルをつくれるツール 以下では、SharePointよりも簡単に社内ポータルサイトを作成できるツールをご紹介します。 SharePointは、多機能でデザイン性が高いですが、使いこなすのに時間がかかるというデメリットがあります。メンバーに利用を定着させるには、シンプルな操作性で教育コストをかけなくても利用できるツールが必要です。 また、ビジネスシーンで利用する場合には検索機能が優れていることも重要です。ファイル内まで検索できるツールを導入すれば、膨大な情報の中から欲しい情報にすぐアクセスできます。 結論、SharePointよりも簡単に社内ポータルサイトを作成できるのは、簡単でシンプルな操作性を備え、検索機能が超高精度なツール「ナレカン」が最適です。 ナレカンでは、簡単な操作で誰でもすぐに使いこなせるため、運用のためにIT人材に頼る必要もなく、教育コストも抑えられます。また、高精度な検索機能を備えているため、情報へのアクセス性が高く、業務を効率的に進められます。 社内報などの全体アナウンスに最適なツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンで「社内掲示板」を使用した例 ここでは、実際に「ナレカン」で社内ポータルとして使える「社内掲示板」を紹介します。以下は、ナレカンで作成した「社内お知らせ」が一覧表示されている画面です。 「2025年1月の健康診断のお知らせ」を押すと、以下のように内容が「プレビュー」で表示されます。投稿に添付してあるファイルも開かずに中身を確認可能です。 このように、ナレカンの「社内お知らせ」機能を使うと「社内掲示板」が作れます。また、ナレカンの「社内掲示板」は全メンバー向けの情報発信が前提なので、SharePointのように公開するメンバーを一人ずつ設定する手間がかかりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointで社内ポータルを作るための基本機能 以下は、SharePointに備わっている社内ポータルを作るための機能をまとめた表です。 <機能> <概要> サイトコレクション SharePointで作られた複数のサイトをまとめたグループのことです。サイトコレクションごとにアクセス権限を分けて設定することができます。 サイト 各サイトコレクション内にあるワークスペースやWebページを指します。SharePointのチームサイトでは、ドキュメント共有やタスク管理ができます。 ライブラリ SharePoint上のファイルの保管場所を意味します。クラウド上にファイルをアップロードすると他のメンバーも見られるため、共同作業が可能になります。 リスト SharePoint上のデータをExcelのような表で管理できるデータベース機能のことです。データの閲覧や共同編集の他、バージョン管理などさまざまな機能が備わっています。 ページ ポータルサイトのユーザーが閲覧できるWebページを指します。プログラミングの知識がなくても、テキストや画像、動画等を組み合わせることでWebページの作成が可能です。 以上の機能を使うことで、SharePointを社内ポータルとして活用できます。これからSharePointの導入を考えている方は、それぞれの単語の意味を理解した上で、どのように活用していくかを決めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【画像つき】SharePointで社内ポータルを作成する方法 以下では、SharePointを使った社内ポータルサイトの作り方を解説します。手順を押さえて自社に最適な社内ポータルサイトをつくりましょう。 ステップ1|サイトを作成する はじめに、以下の手順に沿って、社内ポータルの基盤を作成しましょう。 SharePointのアプリの[サイトの作成]をクリックする。 [コミュニケーションサイト]もしくは[チームサイト]のどちらかをクリックする。 サイトの作成に必要な情報を入力する。 プライバシー設定をする。 [所有者の追加]から共有先のメールアドレスを追加する。 以上の操作で、社内ポータルを作成する準備は完了です。 ステップ2|ページを追加する 次に、作成するコンテンツを選びましょう。以下では、新規ページを追加するための手順を紹介します。 [新規]をクリックする。 表示される選択肢から[ページ]を選ぶ。 ページのタイトルを入力する。 以上の操作で、新しいページがコンテンツとして追加できます。 ステップ3|ナビゲーションを設定する 画面右上の[編集]からは、リンク追加や名前・アドレスの変更ができます。 また、ナビゲーションのスタイルや色も変えられるので、利用ユーザーがサイトやページへすぐにアクセスできるように、ナビゲーションを適切にカスタマイズしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointで社内ポータルサイトを作成するときのポイント3つ ここからは、社内ポータルサイトをSharePointで作成する3つのポイントを紹介します。以下を実践すれば、より利便性の高い社内ポータルを作成できます。 (1)ファイルのダウンロードを制御する 1つ目のポイントは、ダウンロードの制御機能を活用することです。 SharePointにはダウンロードの制御機能があります。たとえば、特定のメンバーのみにデータのダウンロードを許可したい場合、ファイルのダウンロードが可能なメンバーを個別設定することができます。 このように、制御機能を使えば、情報流出のリスクが軽減し、安全に社内ポータルを運用できるようになるのです。 (2)OneDriveに同期する 2つ目に、OneDriveをすでに活用している場合は、SharePointとの同期も有効です。 OneDriveとSharePointを同期すれば、OneDriveで作成・編集したファイルがすぐにSharePointへ反映されます。結果として、編集後のファイルを都度コピーして保存する手間が省けるので、スムーズに業務を進められるのです。 一方、作成・編集だけでなく削除も同期の対象になるため、誤操作でOneDriveのファイルを削除しないように注意しましょう。 (3)マニュアルを整備する 3つ目に、マニュアルを整備することも運用のポイントとなります。 SharePointは多機能なツールなので、部署によってITリテラシーに差がある場合には、全社に浸透しない可能性があります。したがって、基本的な操作手順をまとめたマニュアルを整備して、SharePointが社内で広く利用されるようにしましょう。 また、社内にITの苦手なメンバーがいる場合には「簡単に社内情報を集約できるツール」を使うことも手法のひとつです。たとえば、社内に散らばる情報を一元化して高精度で検索できる「ナレカン」であれば、操作手順を教育する必要がありません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointでデザイン性の高い社内ポータルを作る方法 以下では、SharePointでデザイン性の高い社内ポータルを作る方法をご紹介します。見やすい社内ポータルにするために、デザインにも気を配るようにしましょう。 カラーを統一する SharePointで社内ポータルを作成するときには、カラーを統一するようにしましょう。 社内ポータルに使われる色がバラバラで、多くの色が使われていると見づらくなり、どれが重要な情報かわからなくなります。一目で情報が伝わるように色やデザインを工夫すると、従業員に活用してもらいやすい社内ポータルを作成できます。 自分の会社のイメージカラーで統一するなど、多くの色を使いすぎない工夫をしましょう。 テンプレートを利用する 見やすいポータルを作成するためには、テンプレートを利用することも有効です。 SharePointでは、サイトテンプレートを選択して、統一されたフォーマットで社内ポータルを作成できます。テンプレートに沿って作成することで、内容の抜けや漏れがなくなるほか、視覚的にわかりやすいポータルになります。 SharePointは多機能でデザイン性が高いため、一から社内ポータルを作成するのが難しいと感じた場合は、テンプレートを利用してみましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointの活用方法3選 SharePointにはさまざまな活用方法があります。具体的には、以下の活用方法が挙げられます。 ファイル共有 SharePoint内のライブラリの中にアップロードされたファイルは、共有権限を与えられた人の中で共有されます。Microsoftのアカウントを持っている人ならば社内外で他者とファイルを共有できるため、ファイル共有ツールとして使えるのです。 ファイル以外の情報共有 たとえば、「更新日」や「更新者」、「更新内容」などの更新履歴といった情報も共有が可能です。また、更新履歴を「リスト」にデータの表として保管できるため、ファイル以外の情報の共有にも便利です。 サイト 多様なテキストやメディア、コンテンツを挿入しながらWebページの作成ができます。そのため、業務ガイドやマニュアル、社内のお知らせサイト、社内ポータルサイトなどのあらゆる使い道のサイトを作れるのです。 以上のようにSharePointにはさまざまな活用方法がある一方、SharePointの導入目的が明確でないと、社員が使い道に迷う恐れがあります。そのため、導入時には、導入目的の周知に努めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointで構築した社内ポータルサイトの活用事例 出典:浅間商事株式会社サイトページ ITサポートサービスなどを提供する浅間商事株式会社では、ファイルサーバーでファイル管理をしていましたが、金銭的コストや人的コストに課題がありました。そこで、従来のファイルサーバーからSharePointへの移行を決定したのです。 現在は、全社共通のサイトに、チームやプロジェクト単位で権限を付与したライブラリを作成し、随時ファイルを追加する運用に変更しています。 その結果、コスト削減が実現したうえに、SharePointのほかの機能を活用することで、業務効率が向上しました。 ただし、浅間商事のように”ITに使い慣れている企業”でない場合、一からポータルサイトを構築・運用するのは困難な可能性もある点に注意しましょう。 参考:浅間公式サイト>ブログ>【第2回:SharePoint編】「Microsoft 365」で実現!中小企業の業務効率化 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 番外編|SharePointでテンプレートをカスタマイズする方法 ここでは、SharePoint内のテンプレートを使用・閲覧できるようにするための方法を解説します。 まず、「コミュニケーションサイト」または「チームサイト」を作成します。その後、サイトの名前・説明・ロゴ・プライバシーレベル・サイト分類・サービス制限・アクセス許可を変更可能です。 つぎに、[サイトの設定]に移動し、[サイトテンプレートの適用]を選択します。 つづいて、サイトテンプレートを選択して追加情報を表示します。組織のニーズを満たす場合は、[テンプレートの使用]を選択します。 新しいサイトを参照し、[サイトコンテンツ]の既存のコンテンツを確認し、以下のカスタマイズガイダンスを取得します。 最後に、サイトの編集を再発行して、新しいコンテンツを閲覧者が利用できるようにします。 以上の手順を踏むと、SharePointのさまざまなテンプレートを利用できるので、自社のコンテンツ作成の手間を軽減したい場合に役立ちます。 参照:Microsoftサポート|SharePointサイト>管理>SharePointサイトテンプレートを適用およびカスタマイズする 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ SharePointを活用した社内ポータルサイトの作り方まとめ これまで、SharePointで社内ポータルサイトをつくる方法や運用のメリット、デメリットを中心に解説しました。 SharePointは、多機能で自由度が高いがゆえに、導入方法や操作が難しい点がデメリットです。また、多くの情報を一元管理できる一方、目的の情報がすぐに見つからないことがあります。 とくに、情報共有で使用する場合、必要な情報がすぐに見つからないと迅速な対応ができません。そのため、「ITリテラシーの有無によらず誰でも使いこなせて、検索性に優れたツール」を導入すべきなのです。 したがって、自社での社内ポータル運用には、全社への情報共有を効率化し、目的の情報に即アクセスできる『ナレカン』が最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を社内ポータルとして活用し、自社のナレッジ管理におけるストレスを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む -
 2025年10月22日Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!近年、社内情報を発信できる「社内ポータル」を導入する企業が増えています。とくに、Googleが提供する「Googleサイト」は、コストをかけずに社内ポータルの作成が可能なため、多くの企業に注目されているのです。 一方、「Googleサイトで社内ポータルを作る方法が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、Googleサイトで社内ポータルを作成する方法を中心に解説します。 Google サイトの社内ポータルについて知りたい Googleサイト社内ポータルの使い方を自社での参考にしたい 社内WIkiやナレッジを簡単・効率的にまとめて共有する方法を探している という方はこの記事を参考にすると、Googleサイトの使い方が分かり、自社に最適な社内ポータルを運用できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 社内ポータルとは1.1 社内ポータルサイトとホームページの違い1.2 社内ポータルの機能・活用例2 Googleサイトとは2.1 Googleサイトでできること2.2 Googleサイトの活用事例3 【画像付き】Googleサイトを使った社内ポータルの作り方3.1 ステップ1|Googleサイトにログインする3.2 ステップ2|テンプレートを選択する3.3 ステップ3|デザインを選択する3.4 ステップ4|ページを作成する3.5 ステップ5|Googleアプリと連携する3.6 ステップ6|サイトを公開する4 Googleサイトで社内ポータルを作るメリット5 Googleサイトで社内ポータルを作るデメリット5.1 (1)ページごとの細かな権限設定ができない5.2 (2)サイト内検索機能が乏しい5.3 (3)ページの階層設計が難しい6 Googleサイトのデメリットを解消できるおすすめのツール6.1 社内ポータルを簡単に作成・管理できるツール「ナレカン」6.2 ナレカンで作成した社内ポータル例7 社内ポータルに関するよくある質問8 Googleサイトで社内ポータルを作る方法まとめ 社内ポータルとは 以下では、社内ポータルサイトとホームページの違いや、社内ポータルの機能・活用例について説明します。自社で社内ポータルを活用したい方は必見です。 社内ポータルサイトとホームページの違い まず「社内ポータルサイト」と「ホームページ」の意味・目的・対象範囲は以下になります。 上記のように、社内ポータルサイトとホームページは、情報を公開する対象者や内容が大きく異なると言えます。社内ポータルに記載する内容は、業務に関係するものもあるため、社員全体への周知が重要です。 社内ポータルの機能・活用例 社内ポータルの機能や活用例は以下の通りとなります。 社内Wiki・社内掲示板 社内の情報を管理・共有したり、新しい情報を知らせたりします。社内全体へのお知らせや業務に必要な情報を記載すると簡単に周知できるのです。 FAQの作成 社内でよくある質問をまとめて記載すると、社員は担当者に直接質問をしなくても、不明点を解消できます。結果、業務効率化や担当者の負担軽減にもつながるのです。 社内チャット 社員ポータルで社員間でのやりとりが完結すれば、メールのような手間をかけず、スムーズな情報共有が可能です。また、コミュニケーションの活性化も図れます。 このように、社内ポータルには、社内情報の一元化やナレッジの共有に役立つ機能が集約されています。また質問した内容を社内FAQとしてそのままナレッジ化できる「ナレカン」のようなツールを使うと、質問をまとめる手間も省けるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイトとは 画像引用:Googleサイト Googleサイトとは、Google社が提供する、無料のホームページ作成ツールです。以下では、Googleサイトを使ってできることや活用事例を解説します。 Googleサイトでできること Googleサイトでは、プログラミングの知識なしで簡単にウェブサイトを作れます。活用方法として、以下の3つが代表的です。 社内掲示板 Googleサイトで、社内のイベントやお知らせを記載した「社内掲示板」を作れば、全社員へ一斉に情報を発信できます。また、Googleアプリと連携可能なので、カレンダーやドキュメントの情報を共有する手段としても使えるのです。 ナレッジスペース Googleサイトは、業務に必要なマニュアルやノウハウを集約した「ナレッジスペース」としても活用できます。ナレッジが見える化するため、業務の属人化防止に貢献するのです。 プロジェクト管理 プロジェクトの概要やスケジュール、進捗などの最新情報をまとめられます。Googleサイトは共同編集可能なので、プロジェクトメンバー全員で管理可能な点がメリットです。 以上のように、Googleサイトを上手く活用すると、社内情報のスムーズな共有・管理が実現します。 Googleサイトの活用事例 以下では、Googleサイトを活用してホームページを作成した事例をご紹介します。以下は、金属加工や溶接、塗装事業を展開する「株式会社ヒラノ」のホームページです。 引用:株式会社ヒラノのトップページ こちらのサイトには動画も埋め込まれており、内容が視覚的に分かりやすくなっています。Googleサイトの提供元であるGoogle社は、動画投稿サイト「YouTube」も運営しているので、動画との親和性が高いのが特徴です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【画像付き】Googleサイトを使った社内ポータルの作り方 ここでは、Googleサイトでの社内ポータルの作り方を解説します。以下の手順を押さえて、社内ポータルをスムーズに作成しましょう。 ステップ1|Googleサイトにログインする はじめに、Googleサイトにアクセスします。または、Googleアカウントでログインして、アプリ一覧から「Googleサイト」を選択します。 Googleアカウントでログインしなければ、Googleサイトを開けないので、注意しましょう。 ステップ2|テンプレートを選択する 次に、[テンプレートギャラリー]をクリックして、目的に合ったテンプレートを選択しましょう。 適切なテンプレートがなかった場合は、画面左上の [+] をクリックして、空白の状態から社内ポータルを作ります。 ステップ3|デザインを選択する 作成画面を開き、デザインを変更したい場合は、画面右側の [テーマ] をクリックして、下のデザイン例から適切なものを選択します。 以上の操作で、Googleサイト全体のデザインを設定できます。 ステップ4|ページを作成する デザインを設定したら、ページを作成していきます。 1.トップページのタイトルと、サイト名を入力しましょう。 2.ページタブから画面右下の [+] にカーソルを当てて、[新しいページ] をクリックします。 3.新しいページの名前を入力して、[完了] を選択します。 4.ページに情報を書き込むときは、[挿入] タブを開きます。「テキストボックス」から文字を入力したり、「コンテンツブロック」から画像を挿入したりできます。 以上の操作で、社内情報をページに記載して、社内ポータルを作成できます。 ステップ5|Googleアプリと連携する Googleアプリと連携すると、Googleサイト内に動画を挿入したり、マップを表示するといった使い方も可能です。 Googleアプリと連携するには、セクションの [+] または画面右側の [挿入] をクリックして、連携したいコンテンツを選択します。 連携したいツールを選ぶと、以下のようにサイト内にサムネイルが表示されます。 以上の操作で、簡単にGoogleサイトにほかのGoogleアプリの情報を埋め込めます。 ステップ6|サイトを公開する 社内ポータルの作成が完了したら、社員に公開します。 1.画面右上にある [公開] をクリックしましょう。 2.ウェブアドレスに任意のタイトルを入力して、[公開] をクリックしましょう。また、公開範囲に制限をかけたい場合は、青文字の [管理] から設定できます。 また、通常ドメインには「sites.google.com/」が含まれますが、Google Workspaceの管理者であれば、独自ドメインにカスタムできます。具体的な手順は、Google Workspace 管理者 ヘルプを参照ください。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイトで社内ポータルを作るメリット Googleサイトで社内ポータルを作るメリットとして、主に以下の点が挙げられます。 無料で利用可能 社内ポータルの作成を業者に依頼する場合、数万円~数十万円かかってしまいますが、Googleサイトは無料で利用可能です。また、月々のランニングコストもかからないため、料金コストを抑えられます。 共同編集が可能 Googleサイトは、スプレッドシートやドキュメントのように編集権限を付与できます。そのため、社内ポータルを複数人で同時編集が可能です。 他のGoogleのサービスと連携できる たとえば、Googleカレンダーと連携すれば、社内ポータルの情報が各社員のカレンダーに反映されます。また、スプレッドシートの共有も可能です。 このように、Googleサイトで社内ポータルを作成すると、料金コストをかけずに、他のGoogleサービスと連携して業務効率化を図れます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイトで社内ポータルを作るデメリット 以下では、Googleサイトの欠点を解説します。以下を把握しておかなければ、Googleサイトで社内ポータルを長期的に運用できなくなるので注意しましょう。 (1)ページごとの細かな権限設定ができない 1つ目のデメリットは、ページごとに閲覧権限を付与できない点です。 Googleサイトでは閲覧制限をかけられますが「サイトごと」になり、ページごとに細かく制限はできません。そのため、「この情報には特定のメンバーのみアクセスできるようにしたい」といった場合には、別のサイトを作成しなくてはならないのです。 しかし、社内に複数のポータルサイトがあると、サイトそのものの管理が煩雑化しかねません。したがって、多くの情報を扱う大企業では、サイト単位ではなく、フォルダやページごとに閲覧権限を付与できるツールを導入しましょう。 (2)サイト内検索機能が乏しい 2つ目のデメリットは、サイト内検索機能が乏しいことです。 Googleサイトは、デフォルトでページの右上に検索ボタンがありますが、見づらいうえサイト内に連携したスプレッドシートやファイル内までは検索対象になりません。そのため、社員が欲しい情報を見つけるのに時間がかかる恐れがあるのです。 以上のように、社内ポータルを作成しても情報が検索しづらければ、放置されてしまいます。そこで、社内情報をまとめるなら、ヒット率100%の検索機能が備わった「ナレカン」のようなツールを使いましょう。 (3)ページの階層設計が難しい 3つ目のデメリットは、ページの階層設計が難しいことです。 Googleサイトでは、任意のページの下部にサブページを追加して、情報を5階層まで階層化できます。ただし、各部署が自由に情報を投稿していくと、階層が深くなりすぎて何の情報がどこにあるかわからなくなるのです。 とはいえ、大企業での情報管理にはある程度の階層化は必要となります。分かりやすく階層をまとめることが社内ポータルの活用には必須のため、”自社に合ったフォルダ設計”をサポートしてくれるツールを検討しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイトのデメリットを解消できるおすすめのツール 以下では、社内ポータルを簡単に作成・管理できるおすすめのツールをご紹介します。 Googleサイトを使えば、社内の情報発信やナレッジの蓄積に便利なポータルサイトを作成可能です。ただし、サイト内検索機能はテキストのみが対象なので連携したファイル内までは検索できず、社員が欲しい情報を見つけられない恐れがあるのです。 したがって、「後から情報が振り返りやすいように管理・共有できるツール」を導入しましょう。また、公開範囲を限定したい場合にアクセス権を細く設定して情報共有可能な機能があれば、大企業で管理する情報の数が膨大にあっても、情報漏洩を未然に防げます。 結論、社内ポータルに利用すべきツールは、情報公開する範囲を適切にコントロールし、高度な検索機能で必要な情報に即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンでは、社内報などの全体アナウンスが簡単なので、迅速かつスムーズな全体周知が実現します。また作成した「記事」は、アクセス権を柔軟に設定できるうえ、ファイルや画像内のテキスト情報もすぐに見つけられるため、大企業の情報共有に貢献します。 社内ポータルを簡単に作成・管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレカンで作成した社内ポータル例 ナレカンでは、以下のように、見やすい社内ポータルを作成できます。 また、サムネイル画像は、あらかじめナレカン上にストックされている「ギャラリー」から選択することも可能です。たとえば、上図の青枠で囲われているような、サムネイルが用意されています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルに関するよくある質問 以下は、社内ポータルに関するよくある質問です。 質問1|社内ポータルに必要とされる機能は何ですか? 社内ポータルに必要な機能としては、「社内Wiki」や「ナレッジの蓄積」、「コミュニケーション」が挙げられます。多くの機能を集約することで、情報が一元化されて、社員間でスムーズに連携できるようになるのです。 質問2|社内ポータルサイトの運用のコツは何ですか? 社内ポータルサイトの運用のコツは、社員が必要な社内情報に即アクセスできるように設計することです。そのためには、情報の整理はもちろん、”100%ヒットする”超高精度の検索機能を備えた社内ポータルツールの利用が役立ちます。 質問3|Googleサイトの欠点は何ですか? Googleサイトの欠点のひとつに「細かな権限設定ができないこと」が挙げられます。一方、「ナレカン」では、メンバー権限を柔軟に設定可能なので、必要に応じて公開範囲を使い分けられます。 上記を参考に、社内ポータルに関する疑問を解消して、運用を円滑に進めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイトで社内ポータルを作る方法まとめ ここまで、Googleサイトで社内ポータルをつくる方法やGoogleサイトの欠点を中心に解説しました。 Googleサイトを使うと、社内ポータルを作成して、企業の情報が一元管理されます。しかし、Googleサイトには「閲覧制限をページごとにかけられない」や「検索機能が乏しい」といった問題があるため、社内ポータルを上手く運用できないリスクが高いです。 そこで、「全社向けの情報」と「一部のメンバーにのみ公開する情報」というように、シーンに応じて公開範囲を柔軟に指定できるツールを導入しましょう。また必要な情報をすぐに見つけられる検索機能があると、後から振り返るときに役立ちます。 したがって、自社が導入すべきは、添付ファイルの中身までヒットする超高精度な検索機能があり、社内ポータルに必要な機能に過不足がないツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、社内情報を一元管理しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジとは?ノウハウとの違いや社内のナレッジ運用の重要性を解説 【SharePoint】簡単!社内ポータルサイトの作り方や事例を徹底解説 【最新版】人気のクラウド型社内ポータルサイト7選を徹底比較! 【事例あり】社内イントラとは?導入する目的や作成方法を解説! 基幹システムとは?ERPとの違いや選定ポイントをわかりやすく解説 社内システムとは?内製化のデメリットや解決策を紹介! 情報の一元化とは?一元管理する方法やメリット、おすすめツールを紹介 【事例あり】社内ポータルサイトとは?活用されるためのポイントも解説! 【必見】社内ポータルの費用とは?コスパを高める方法も解説続きを読む
2025年10月22日Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!近年、社内情報を発信できる「社内ポータル」を導入する企業が増えています。とくに、Googleが提供する「Googleサイト」は、コストをかけずに社内ポータルの作成が可能なため、多くの企業に注目されているのです。 一方、「Googleサイトで社内ポータルを作る方法が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、Googleサイトで社内ポータルを作成する方法を中心に解説します。 Google サイトの社内ポータルについて知りたい Googleサイト社内ポータルの使い方を自社での参考にしたい 社内WIkiやナレッジを簡単・効率的にまとめて共有する方法を探している という方はこの記事を参考にすると、Googleサイトの使い方が分かり、自社に最適な社内ポータルを運用できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 社内ポータルとは1.1 社内ポータルサイトとホームページの違い1.2 社内ポータルの機能・活用例2 Googleサイトとは2.1 Googleサイトでできること2.2 Googleサイトの活用事例3 【画像付き】Googleサイトを使った社内ポータルの作り方3.1 ステップ1|Googleサイトにログインする3.2 ステップ2|テンプレートを選択する3.3 ステップ3|デザインを選択する3.4 ステップ4|ページを作成する3.5 ステップ5|Googleアプリと連携する3.6 ステップ6|サイトを公開する4 Googleサイトで社内ポータルを作るメリット5 Googleサイトで社内ポータルを作るデメリット5.1 (1)ページごとの細かな権限設定ができない5.2 (2)サイト内検索機能が乏しい5.3 (3)ページの階層設計が難しい6 Googleサイトのデメリットを解消できるおすすめのツール6.1 社内ポータルを簡単に作成・管理できるツール「ナレカン」6.2 ナレカンで作成した社内ポータル例7 社内ポータルに関するよくある質問8 Googleサイトで社内ポータルを作る方法まとめ 社内ポータルとは 以下では、社内ポータルサイトとホームページの違いや、社内ポータルの機能・活用例について説明します。自社で社内ポータルを活用したい方は必見です。 社内ポータルサイトとホームページの違い まず「社内ポータルサイト」と「ホームページ」の意味・目的・対象範囲は以下になります。 上記のように、社内ポータルサイトとホームページは、情報を公開する対象者や内容が大きく異なると言えます。社内ポータルに記載する内容は、業務に関係するものもあるため、社員全体への周知が重要です。 社内ポータルの機能・活用例 社内ポータルの機能や活用例は以下の通りとなります。 社内Wiki・社内掲示板 社内の情報を管理・共有したり、新しい情報を知らせたりします。社内全体へのお知らせや業務に必要な情報を記載すると簡単に周知できるのです。 FAQの作成 社内でよくある質問をまとめて記載すると、社員は担当者に直接質問をしなくても、不明点を解消できます。結果、業務効率化や担当者の負担軽減にもつながるのです。 社内チャット 社員ポータルで社員間でのやりとりが完結すれば、メールのような手間をかけず、スムーズな情報共有が可能です。また、コミュニケーションの活性化も図れます。 このように、社内ポータルには、社内情報の一元化やナレッジの共有に役立つ機能が集約されています。また質問した内容を社内FAQとしてそのままナレッジ化できる「ナレカン」のようなツールを使うと、質問をまとめる手間も省けるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイトとは 画像引用:Googleサイト Googleサイトとは、Google社が提供する、無料のホームページ作成ツールです。以下では、Googleサイトを使ってできることや活用事例を解説します。 Googleサイトでできること Googleサイトでは、プログラミングの知識なしで簡単にウェブサイトを作れます。活用方法として、以下の3つが代表的です。 社内掲示板 Googleサイトで、社内のイベントやお知らせを記載した「社内掲示板」を作れば、全社員へ一斉に情報を発信できます。また、Googleアプリと連携可能なので、カレンダーやドキュメントの情報を共有する手段としても使えるのです。 ナレッジスペース Googleサイトは、業務に必要なマニュアルやノウハウを集約した「ナレッジスペース」としても活用できます。ナレッジが見える化するため、業務の属人化防止に貢献するのです。 プロジェクト管理 プロジェクトの概要やスケジュール、進捗などの最新情報をまとめられます。Googleサイトは共同編集可能なので、プロジェクトメンバー全員で管理可能な点がメリットです。 以上のように、Googleサイトを上手く活用すると、社内情報のスムーズな共有・管理が実現します。 Googleサイトの活用事例 以下では、Googleサイトを活用してホームページを作成した事例をご紹介します。以下は、金属加工や溶接、塗装事業を展開する「株式会社ヒラノ」のホームページです。 引用:株式会社ヒラノのトップページ こちらのサイトには動画も埋め込まれており、内容が視覚的に分かりやすくなっています。Googleサイトの提供元であるGoogle社は、動画投稿サイト「YouTube」も運営しているので、動画との親和性が高いのが特徴です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【画像付き】Googleサイトを使った社内ポータルの作り方 ここでは、Googleサイトでの社内ポータルの作り方を解説します。以下の手順を押さえて、社内ポータルをスムーズに作成しましょう。 ステップ1|Googleサイトにログインする はじめに、Googleサイトにアクセスします。または、Googleアカウントでログインして、アプリ一覧から「Googleサイト」を選択します。 Googleアカウントでログインしなければ、Googleサイトを開けないので、注意しましょう。 ステップ2|テンプレートを選択する 次に、[テンプレートギャラリー]をクリックして、目的に合ったテンプレートを選択しましょう。 適切なテンプレートがなかった場合は、画面左上の [+] をクリックして、空白の状態から社内ポータルを作ります。 ステップ3|デザインを選択する 作成画面を開き、デザインを変更したい場合は、画面右側の [テーマ] をクリックして、下のデザイン例から適切なものを選択します。 以上の操作で、Googleサイト全体のデザインを設定できます。 ステップ4|ページを作成する デザインを設定したら、ページを作成していきます。 1.トップページのタイトルと、サイト名を入力しましょう。 2.ページタブから画面右下の [+] にカーソルを当てて、[新しいページ] をクリックします。 3.新しいページの名前を入力して、[完了] を選択します。 4.ページに情報を書き込むときは、[挿入] タブを開きます。「テキストボックス」から文字を入力したり、「コンテンツブロック」から画像を挿入したりできます。 以上の操作で、社内情報をページに記載して、社内ポータルを作成できます。 ステップ5|Googleアプリと連携する Googleアプリと連携すると、Googleサイト内に動画を挿入したり、マップを表示するといった使い方も可能です。 Googleアプリと連携するには、セクションの [+] または画面右側の [挿入] をクリックして、連携したいコンテンツを選択します。 連携したいツールを選ぶと、以下のようにサイト内にサムネイルが表示されます。 以上の操作で、簡単にGoogleサイトにほかのGoogleアプリの情報を埋め込めます。 ステップ6|サイトを公開する 社内ポータルの作成が完了したら、社員に公開します。 1.画面右上にある [公開] をクリックしましょう。 2.ウェブアドレスに任意のタイトルを入力して、[公開] をクリックしましょう。また、公開範囲に制限をかけたい場合は、青文字の [管理] から設定できます。 また、通常ドメインには「sites.google.com/」が含まれますが、Google Workspaceの管理者であれば、独自ドメインにカスタムできます。具体的な手順は、Google Workspace 管理者 ヘルプを参照ください。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイトで社内ポータルを作るメリット Googleサイトで社内ポータルを作るメリットとして、主に以下の点が挙げられます。 無料で利用可能 社内ポータルの作成を業者に依頼する場合、数万円~数十万円かかってしまいますが、Googleサイトは無料で利用可能です。また、月々のランニングコストもかからないため、料金コストを抑えられます。 共同編集が可能 Googleサイトは、スプレッドシートやドキュメントのように編集権限を付与できます。そのため、社内ポータルを複数人で同時編集が可能です。 他のGoogleのサービスと連携できる たとえば、Googleカレンダーと連携すれば、社内ポータルの情報が各社員のカレンダーに反映されます。また、スプレッドシートの共有も可能です。 このように、Googleサイトで社内ポータルを作成すると、料金コストをかけずに、他のGoogleサービスと連携して業務効率化を図れます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイトで社内ポータルを作るデメリット 以下では、Googleサイトの欠点を解説します。以下を把握しておかなければ、Googleサイトで社内ポータルを長期的に運用できなくなるので注意しましょう。 (1)ページごとの細かな権限設定ができない 1つ目のデメリットは、ページごとに閲覧権限を付与できない点です。 Googleサイトでは閲覧制限をかけられますが「サイトごと」になり、ページごとに細かく制限はできません。そのため、「この情報には特定のメンバーのみアクセスできるようにしたい」といった場合には、別のサイトを作成しなくてはならないのです。 しかし、社内に複数のポータルサイトがあると、サイトそのものの管理が煩雑化しかねません。したがって、多くの情報を扱う大企業では、サイト単位ではなく、フォルダやページごとに閲覧権限を付与できるツールを導入しましょう。 (2)サイト内検索機能が乏しい 2つ目のデメリットは、サイト内検索機能が乏しいことです。 Googleサイトは、デフォルトでページの右上に検索ボタンがありますが、見づらいうえサイト内に連携したスプレッドシートやファイル内までは検索対象になりません。そのため、社員が欲しい情報を見つけるのに時間がかかる恐れがあるのです。 以上のように、社内ポータルを作成しても情報が検索しづらければ、放置されてしまいます。そこで、社内情報をまとめるなら、ヒット率100%の検索機能が備わった「ナレカン」のようなツールを使いましょう。 (3)ページの階層設計が難しい 3つ目のデメリットは、ページの階層設計が難しいことです。 Googleサイトでは、任意のページの下部にサブページを追加して、情報を5階層まで階層化できます。ただし、各部署が自由に情報を投稿していくと、階層が深くなりすぎて何の情報がどこにあるかわからなくなるのです。 とはいえ、大企業での情報管理にはある程度の階層化は必要となります。分かりやすく階層をまとめることが社内ポータルの活用には必須のため、”自社に合ったフォルダ設計”をサポートしてくれるツールを検討しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイトのデメリットを解消できるおすすめのツール 以下では、社内ポータルを簡単に作成・管理できるおすすめのツールをご紹介します。 Googleサイトを使えば、社内の情報発信やナレッジの蓄積に便利なポータルサイトを作成可能です。ただし、サイト内検索機能はテキストのみが対象なので連携したファイル内までは検索できず、社員が欲しい情報を見つけられない恐れがあるのです。 したがって、「後から情報が振り返りやすいように管理・共有できるツール」を導入しましょう。また、公開範囲を限定したい場合にアクセス権を細く設定して情報共有可能な機能があれば、大企業で管理する情報の数が膨大にあっても、情報漏洩を未然に防げます。 結論、社内ポータルに利用すべきツールは、情報公開する範囲を適切にコントロールし、高度な検索機能で必要な情報に即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンでは、社内報などの全体アナウンスが簡単なので、迅速かつスムーズな全体周知が実現します。また作成した「記事」は、アクセス権を柔軟に設定できるうえ、ファイルや画像内のテキスト情報もすぐに見つけられるため、大企業の情報共有に貢献します。 社内ポータルを簡単に作成・管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレカンで作成した社内ポータル例 ナレカンでは、以下のように、見やすい社内ポータルを作成できます。 また、サムネイル画像は、あらかじめナレカン上にストックされている「ギャラリー」から選択することも可能です。たとえば、上図の青枠で囲われているような、サムネイルが用意されています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルに関するよくある質問 以下は、社内ポータルに関するよくある質問です。 質問1|社内ポータルに必要とされる機能は何ですか? 社内ポータルに必要な機能としては、「社内Wiki」や「ナレッジの蓄積」、「コミュニケーション」が挙げられます。多くの機能を集約することで、情報が一元化されて、社員間でスムーズに連携できるようになるのです。 質問2|社内ポータルサイトの運用のコツは何ですか? 社内ポータルサイトの運用のコツは、社員が必要な社内情報に即アクセスできるように設計することです。そのためには、情報の整理はもちろん、”100%ヒットする”超高精度の検索機能を備えた社内ポータルツールの利用が役立ちます。 質問3|Googleサイトの欠点は何ですか? Googleサイトの欠点のひとつに「細かな権限設定ができないこと」が挙げられます。一方、「ナレカン」では、メンバー権限を柔軟に設定可能なので、必要に応じて公開範囲を使い分けられます。 上記を参考に、社内ポータルに関する疑問を解消して、運用を円滑に進めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイトで社内ポータルを作る方法まとめ ここまで、Googleサイトで社内ポータルをつくる方法やGoogleサイトの欠点を中心に解説しました。 Googleサイトを使うと、社内ポータルを作成して、企業の情報が一元管理されます。しかし、Googleサイトには「閲覧制限をページごとにかけられない」や「検索機能が乏しい」といった問題があるため、社内ポータルを上手く運用できないリスクが高いです。 そこで、「全社向けの情報」と「一部のメンバーにのみ公開する情報」というように、シーンに応じて公開範囲を柔軟に指定できるツールを導入しましょう。また必要な情報をすぐに見つけられる検索機能があると、後から振り返るときに役立ちます。 したがって、自社が導入すべきは、添付ファイルの中身までヒットする超高精度な検索機能があり、社内ポータルに必要な機能に過不足がないツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、社内情報を一元管理しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジとは?ノウハウとの違いや社内のナレッジ運用の重要性を解説 【SharePoint】簡単!社内ポータルサイトの作り方や事例を徹底解説 【最新版】人気のクラウド型社内ポータルサイト7選を徹底比較! 【事例あり】社内イントラとは?導入する目的や作成方法を解説! 基幹システムとは?ERPとの違いや選定ポイントをわかりやすく解説 社内システムとは?内製化のデメリットや解決策を紹介! 情報の一元化とは?一元管理する方法やメリット、おすすめツールを紹介 【事例あり】社内ポータルサイトとは?活用されるためのポイントも解説! 【必見】社内ポータルの費用とは?コスパを高める方法も解説続きを読む -
 2025年03月26日RPAとは?意味や背景、ビジネスでの導入事例をわかりやすく紹介近年、急速にAIが普及し、従来は人間が担ってきた仕事をAIが代わって実行する様子を目にする機会も増えています。こうした状況下で、RPAという言葉がしばしば話題に上がります。 一方で「RPAとは何かわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、RPAの意味や背景、導入事例を中心にご紹介します。 RPAを簡単に説明してほしい RPAの意味や背景、導入事例など詳しく知りたい RPAツールよりも簡単に運用に乗せられるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、RPAの意味を正確に理解し、自社でRPAを進めるべきか判断できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 RPAとは1.1 RPAの意味1.2 RPAが注目される背景1.3 「AI」や「Excelのマクロ機能」との違い2 RPAの導入事例3 【比較表】RPAツール3選4 【意味がない?】RPAの導入に失敗する理由4.1 (1)対象業務がRPAの利用に不向き4.2 (2)RPAの運用体制が構築されていない4.3 (3)社内に浸透しない5 RPAツールよりも簡単に運用できるツール5.1 手厚い支援体制で知識の有無を問わず運用できるアプリ「ナレカン」6 RPAの意味や導入事例、失敗理由のまとめ RPAとは ここでは、RPAの意味や背景、よく混同されるものとの違いをご説明します。RPAの概要をしっかりと押さえたい方は必見です。 RPAの意味 RPAとは、Robotic Process Automation(ロボティックプロセスオートメーション)の略称で、従来人間がパソコン上で実行してきた作業をロボットが自動化することを指します。 RPAにおけるロボットは登録された仕事の一連の流れを実行するため、一定の規則で繰り返されるタスクやルーティン作業で使用されます。また、休むことなく業務を遂行し人為的なミスを起こさないため、生産性や品質の向上が期待できるのです。 さらに、少ない人員であってもロボットによって補完されるため、人件費の削減にもつながります。そのため、RPAの実施は会社全体に大きな利益があると言えます。 一方で、RPAの効果を最大限引き出すためには、活用される業務や運用体制がポイントになるため、導入の際には慎重に準備を進める必要があります。 RPAが注目される背景 近年、少子高齢化の進行により労働者不足の問題が表面化するなかで、少ない人材でも生産性を上昇させられるRPAが注目を集めるようになりました。 たとえば、RPAは勤務時間の集計、有給休暇の残り日数などを自動で表示し、データを元に給与計算したり、振り込みをしたりできます。そのため、給与の支払いにおいて必要な人員を減らしても滞りのない業務が実現されます。 このように、人手不足であってもロボットが人間の仕事を肩代わりすれば、他の業務に人員が割けて生産性を上げられます。したがって、今後ますますRPAの必要性が高まると考えられます。 「AI」や「Excelのマクロ機能」との違い 以下の表は「RPA」「AI」「Excelのマクロ機能」の意味についてです。3つを比較し、それぞれの違いを掴みましょう。 意味 RPA ロボットがパソコン上の規則性のある単純作業を自動化する AI 大量のデータを学習することで推論して事象を識別・判断する Excelのマクロ機能 ExcelなどのOfficeドキュメント内でのみ事務的な業務を自動化する 以上より、「RPA」と「AI」の違いは、あらかじめ決められた作業のみ実行するか、データから学習して推論できるかであり、「RPA」と「Excelのマクロ機能」の違いは、業務を自動化する範囲の広さです。ぜひ使い分けられるようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ RPAの導入事例 RPAの導入事例として、大手都市銀行が煩雑な事務処理作業を効率化するためにRPAを活用したことが挙げられます。 銀行業務のうち、20種類の事務処理にRPAを適用したところ、年間8,000時間を削減することに成功しました。また、本来なら事務を担当していた社員が他の業務をできるようになりました。 今後の展望として、複数システムを使う事務処理にRPAを適用することで、システム連携による業務の単純化も視野に入れているようです。以上のように、RPAは導入後の運用に成功すると仕事の効率性を大きく上げることが可能なのです。 参考:大手都市銀行のRPAの導入事例 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【比較表】RPAツール3選 以下の表は、有名なRPAツールであるUniPath、WinActor、Blue Prismの3つをまとめたものです。(左右にスクロール可) UiPath WinActor Blue Prism 特徴 ルーマニア発の多くのツールやプラットフォームで多種多様な業務の効率化ができるツール 純国産のソフトウェアでWindows端末のあらゆる操作を学習し、自動化できるツール イギリス発の自動化する業務の拡張を前提に作られたため管理機能と拡張性に優れたツール できること ・「発見」:業務を自動化するためのタスクを見つける ・「自動化」:ワークフローを構築、実行する ・「運用」:複数のロボットを統合して利用する ・「記録」:パソコン上の操作を記録する ・「編集」:記録された操作を編集、作成する ・「実行」:作成された操作を実行する ・「学習」:AIが機械学習する ・「実行」:計画されたスケジュールやアクションによって処理が実行される ・「管理」:稼働状況やアクセス管理、エラーの処理などができる 日本語対応 【○】 【○】 【○】 以上のように、同じRPAツールであっても特徴等が異なるため、注意して選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【意味がない?】RPAの導入に失敗する理由 RPAは導入に成功すると大きな恩恵が得られる一方で、RPAの導入がうまくいかず意味がないと感じてしまう人もいます。これからRPAの導入を検討している方は以下に注意しましょう。 (1)対象業務がRPAの利用に不向き RPAの導入に失敗する1つ目の理由に、対象業務がRPAの利用に不向きであることが挙げられます。 RPAは伝票処理などの単純定型作業や反復作業は得意とする一方で、発案や判断を必要とする作業や規則が複雑すぎる業務にはあまり向いていません。仮に、RPAが苦手とする業務をやらせようとすると開発に時間がかかったり、エラーが出てしまったりします。 このように、RPAの対象業務が不向きなものであると逆に非効率になり、本来の効果を得られないので気をつけましょう。 (2)RPAの運用体制が構築されていない RPAの導入に失敗する2つ目の理由に、RPAの運用体制が構築されていないことがあります。 RPAは基本的なプログラミングの知識が必要とされるため、運用には専門的な知識を持った人材が十分にいることが望ましいです。しかし、人材育成が進んでいない会社では担当者の異動や退職の際に、RPAの使用が頓挫してしまいます。 そこで、RPAの運用体制を強固なものにするために、社員教育を実施したり、マニュアルを作成したりして、RPAの運用が属人化してしまわないように努めましょう。 (3)社内に浸透しない RPAの導入に失敗する3つ目の理由に、社内に浸透しないことがあります。 RPAは大規模に利用されるようになって初めて大きな効果を得られます。しかし、社内に浸透せず一部の業務でしか使われていないと導入コストに見合った利益を生み出すことができません。 そこでRPA導入直後は、社内で導入目的を明確にし、具体的な方針を示していくことが重要なのです。社員のRPA導入に対する理解が進めば、自然と社内に浸透していくようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ RPAツールよりも簡単に運用できるツール 以下ではRPAツールよりも簡単に運用できるツールをご紹介します。 RPAとは、人が対応してきた作業をロボットが代わりに実行するというもので、昨今では広く普及しています。しかし、いくつかの企業ではRPAを導入したものの、高度な技術を持つ人材不足が原因で導入後の運用がうまくいかないといった問題を抱えています。 そこで、まずはRPAツールのような専門的知識が必要なツールではなく、導入直後から使いこなせるITツールを導入しましょう。とくに、業務マニュアルやノウハウなどのナレッジを全社に共有することで、作業効率が大幅に上がるのです。 また、手厚い初期導入支援が受けられるツールを選べば、ツール導入の負担が最小限に抑えられます。結論、自社が導入すべきなのは、初期導入支援や既存データの移行支援といった手厚いサポートが受けられるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンでは、「フォルダ設計」や「メンバー登録」などのセットアップをしてくれる初期導入支援や社内の既存データの移行支援が受けられます。また高度なAIが搭載されていながらも、複雑な知識は要らず誰でも簡単に使いこなせます。 手厚い支援体制で知識の有無を問わず運用できるアプリ「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ RPAの意味や導入事例、失敗理由のまとめ これまで、RPAの意味や導入事例、導入に失敗する理由を中心にご紹介しました。 RPAを導入すれば、人間がすべき仕事の負担が減り、大幅な生産性の向上が期待できます。一方で、RPAを円滑に運用していくためにはプログラミングなどの専門的な知識が必要とされるため、IT人材が少ない企業ではRPAの導入に懸念もあります。 そこで、ITに関する専門知識を持っていない会社であってもすぐに運用に乗せられて仕事のパフォーマンスの上昇が見込まれるツールを導入しましょう。そのためには、しっかりしたサポート体制と業務効率化につながる機能があるかを軸にツールを選ぶべきです。 結論、徹底した初期導入支援がありながら、社内情報の管理がしやすくなる高度なAIによる検索機能を備えたツール「ナレカン」一択です。 無料の導入相談も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、社内の業務をスムーズにこなしていきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 自然言語処理とは?4つのステップや活用事例をわかりやすく解説続きを読む
2025年03月26日RPAとは?意味や背景、ビジネスでの導入事例をわかりやすく紹介近年、急速にAIが普及し、従来は人間が担ってきた仕事をAIが代わって実行する様子を目にする機会も増えています。こうした状況下で、RPAという言葉がしばしば話題に上がります。 一方で「RPAとは何かわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、RPAの意味や背景、導入事例を中心にご紹介します。 RPAを簡単に説明してほしい RPAの意味や背景、導入事例など詳しく知りたい RPAツールよりも簡単に運用に乗せられるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、RPAの意味を正確に理解し、自社でRPAを進めるべきか判断できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 RPAとは1.1 RPAの意味1.2 RPAが注目される背景1.3 「AI」や「Excelのマクロ機能」との違い2 RPAの導入事例3 【比較表】RPAツール3選4 【意味がない?】RPAの導入に失敗する理由4.1 (1)対象業務がRPAの利用に不向き4.2 (2)RPAの運用体制が構築されていない4.3 (3)社内に浸透しない5 RPAツールよりも簡単に運用できるツール5.1 手厚い支援体制で知識の有無を問わず運用できるアプリ「ナレカン」6 RPAの意味や導入事例、失敗理由のまとめ RPAとは ここでは、RPAの意味や背景、よく混同されるものとの違いをご説明します。RPAの概要をしっかりと押さえたい方は必見です。 RPAの意味 RPAとは、Robotic Process Automation(ロボティックプロセスオートメーション)の略称で、従来人間がパソコン上で実行してきた作業をロボットが自動化することを指します。 RPAにおけるロボットは登録された仕事の一連の流れを実行するため、一定の規則で繰り返されるタスクやルーティン作業で使用されます。また、休むことなく業務を遂行し人為的なミスを起こさないため、生産性や品質の向上が期待できるのです。 さらに、少ない人員であってもロボットによって補完されるため、人件費の削減にもつながります。そのため、RPAの実施は会社全体に大きな利益があると言えます。 一方で、RPAの効果を最大限引き出すためには、活用される業務や運用体制がポイントになるため、導入の際には慎重に準備を進める必要があります。 RPAが注目される背景 近年、少子高齢化の進行により労働者不足の問題が表面化するなかで、少ない人材でも生産性を上昇させられるRPAが注目を集めるようになりました。 たとえば、RPAは勤務時間の集計、有給休暇の残り日数などを自動で表示し、データを元に給与計算したり、振り込みをしたりできます。そのため、給与の支払いにおいて必要な人員を減らしても滞りのない業務が実現されます。 このように、人手不足であってもロボットが人間の仕事を肩代わりすれば、他の業務に人員が割けて生産性を上げられます。したがって、今後ますますRPAの必要性が高まると考えられます。 「AI」や「Excelのマクロ機能」との違い 以下の表は「RPA」「AI」「Excelのマクロ機能」の意味についてです。3つを比較し、それぞれの違いを掴みましょう。 意味 RPA ロボットがパソコン上の規則性のある単純作業を自動化する AI 大量のデータを学習することで推論して事象を識別・判断する Excelのマクロ機能 ExcelなどのOfficeドキュメント内でのみ事務的な業務を自動化する 以上より、「RPA」と「AI」の違いは、あらかじめ決められた作業のみ実行するか、データから学習して推論できるかであり、「RPA」と「Excelのマクロ機能」の違いは、業務を自動化する範囲の広さです。ぜひ使い分けられるようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ RPAの導入事例 RPAの導入事例として、大手都市銀行が煩雑な事務処理作業を効率化するためにRPAを活用したことが挙げられます。 銀行業務のうち、20種類の事務処理にRPAを適用したところ、年間8,000時間を削減することに成功しました。また、本来なら事務を担当していた社員が他の業務をできるようになりました。 今後の展望として、複数システムを使う事務処理にRPAを適用することで、システム連携による業務の単純化も視野に入れているようです。以上のように、RPAは導入後の運用に成功すると仕事の効率性を大きく上げることが可能なのです。 参考:大手都市銀行のRPAの導入事例 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【比較表】RPAツール3選 以下の表は、有名なRPAツールであるUniPath、WinActor、Blue Prismの3つをまとめたものです。(左右にスクロール可) UiPath WinActor Blue Prism 特徴 ルーマニア発の多くのツールやプラットフォームで多種多様な業務の効率化ができるツール 純国産のソフトウェアでWindows端末のあらゆる操作を学習し、自動化できるツール イギリス発の自動化する業務の拡張を前提に作られたため管理機能と拡張性に優れたツール できること ・「発見」:業務を自動化するためのタスクを見つける ・「自動化」:ワークフローを構築、実行する ・「運用」:複数のロボットを統合して利用する ・「記録」:パソコン上の操作を記録する ・「編集」:記録された操作を編集、作成する ・「実行」:作成された操作を実行する ・「学習」:AIが機械学習する ・「実行」:計画されたスケジュールやアクションによって処理が実行される ・「管理」:稼働状況やアクセス管理、エラーの処理などができる 日本語対応 【○】 【○】 【○】 以上のように、同じRPAツールであっても特徴等が異なるため、注意して選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【意味がない?】RPAの導入に失敗する理由 RPAは導入に成功すると大きな恩恵が得られる一方で、RPAの導入がうまくいかず意味がないと感じてしまう人もいます。これからRPAの導入を検討している方は以下に注意しましょう。 (1)対象業務がRPAの利用に不向き RPAの導入に失敗する1つ目の理由に、対象業務がRPAの利用に不向きであることが挙げられます。 RPAは伝票処理などの単純定型作業や反復作業は得意とする一方で、発案や判断を必要とする作業や規則が複雑すぎる業務にはあまり向いていません。仮に、RPAが苦手とする業務をやらせようとすると開発に時間がかかったり、エラーが出てしまったりします。 このように、RPAの対象業務が不向きなものであると逆に非効率になり、本来の効果を得られないので気をつけましょう。 (2)RPAの運用体制が構築されていない RPAの導入に失敗する2つ目の理由に、RPAの運用体制が構築されていないことがあります。 RPAは基本的なプログラミングの知識が必要とされるため、運用には専門的な知識を持った人材が十分にいることが望ましいです。しかし、人材育成が進んでいない会社では担当者の異動や退職の際に、RPAの使用が頓挫してしまいます。 そこで、RPAの運用体制を強固なものにするために、社員教育を実施したり、マニュアルを作成したりして、RPAの運用が属人化してしまわないように努めましょう。 (3)社内に浸透しない RPAの導入に失敗する3つ目の理由に、社内に浸透しないことがあります。 RPAは大規模に利用されるようになって初めて大きな効果を得られます。しかし、社内に浸透せず一部の業務でしか使われていないと導入コストに見合った利益を生み出すことができません。 そこでRPA導入直後は、社内で導入目的を明確にし、具体的な方針を示していくことが重要なのです。社員のRPA導入に対する理解が進めば、自然と社内に浸透していくようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ RPAツールよりも簡単に運用できるツール 以下ではRPAツールよりも簡単に運用できるツールをご紹介します。 RPAとは、人が対応してきた作業をロボットが代わりに実行するというもので、昨今では広く普及しています。しかし、いくつかの企業ではRPAを導入したものの、高度な技術を持つ人材不足が原因で導入後の運用がうまくいかないといった問題を抱えています。 そこで、まずはRPAツールのような専門的知識が必要なツールではなく、導入直後から使いこなせるITツールを導入しましょう。とくに、業務マニュアルやノウハウなどのナレッジを全社に共有することで、作業効率が大幅に上がるのです。 また、手厚い初期導入支援が受けられるツールを選べば、ツール導入の負担が最小限に抑えられます。結論、自社が導入すべきなのは、初期導入支援や既存データの移行支援といった手厚いサポートが受けられるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンでは、「フォルダ設計」や「メンバー登録」などのセットアップをしてくれる初期導入支援や社内の既存データの移行支援が受けられます。また高度なAIが搭載されていながらも、複雑な知識は要らず誰でも簡単に使いこなせます。 手厚い支援体制で知識の有無を問わず運用できるアプリ「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ RPAの意味や導入事例、失敗理由のまとめ これまで、RPAの意味や導入事例、導入に失敗する理由を中心にご紹介しました。 RPAを導入すれば、人間がすべき仕事の負担が減り、大幅な生産性の向上が期待できます。一方で、RPAを円滑に運用していくためにはプログラミングなどの専門的な知識が必要とされるため、IT人材が少ない企業ではRPAの導入に懸念もあります。 そこで、ITに関する専門知識を持っていない会社であってもすぐに運用に乗せられて仕事のパフォーマンスの上昇が見込まれるツールを導入しましょう。そのためには、しっかりしたサポート体制と業務効率化につながる機能があるかを軸にツールを選ぶべきです。 結論、徹底した初期導入支援がありながら、社内情報の管理がしやすくなる高度なAIによる検索機能を備えたツール「ナレカン」一択です。 無料の導入相談も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、社内の業務をスムーズにこなしていきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 自然言語処理とは?4つのステップや活用事例をわかりやすく解説続きを読む -
 2025年08月20日OneDrive for Businessとは?OneDriveとの違いや使い方を解説Microsoft社が提供するクラウドストレージのひとつに「OneDrive for Business」があります。通常のOneDriveと異なり、法人向けに特化したサービスです。 しかし、なかには「個人向けと法人向けで、何が違うのか分からない」と混乱している方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、OneDrive for Businessの使い方や料金、個人向けのOneDriveとの違いを網羅的に解説します。 OneDrive Business がどのようなツールか知りたい OneDrive Business とOneDriveの違いを把握したい OneDrive Businessから新しいツールへの移行を検討している という方はこの記事を参考にすると、OneDrive for Businessの特徴や機能が分かるほか、ファイル管理の手間も解消できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 OneDrive for Businessとは1.1 OneDrive for Businessの特徴1.2 OneDrive for Businessの機能1.3 OneDrive for businessの使い方2 「OneDrive for Business」と「OneDrive(個人利用)」の違い2.1 (1)管理機能を使える2.2 (2)無料プランがない2.3 (3)アカウントが異なる3 OneDrive for Businessのアクセス権限を設定する方法4 OneDrive for Businessを使うメリットは?5 要注意!OneDrive for Businessのデメリットとは6 【必見】OneDrive for Businessのデメリットを解消するツール6.1 誰でもストレスなくファイル管理できるツール「ナレカン」7 OneDrive for Businessの料金/容量プラン8 OneDrive for Businessの口コミ・評判8.1 OneDrive for Businessの良い口コミ・評判8.2 OneDrive for Businessの改善点に関する口コミ・評判9 OneDrive for BusinessとOneDriveの違いまとめ OneDrive for Businessとは 以下では、OneDrive for Businessの特徴をご紹介します。「有名だから」という理由で導入してしまうと、トラブルを招きかねないため、まずは詳細を押さえましょう。 OneDrive for Businessの特徴 引用:OneDrive for Businessの公式サイト OneDrive for Businessは、Microsoft社が提供するクラウドストレージです。 通常のOneDriveと同じく、ビジネスで多用されるWordやExcel、PowerPointだけでなく、モバイルアプリを用いればスマホで撮影した画像も手軽に残せます。また、TeamsやSharePointで共有したファイルを、そのままOneDriveに保存することも可能です。 加えて、「従業員のアカウントを管理する機能」によってセキュリティも強化されているため、ビジネス利用がしやすい点もメリットです。以上のように、ビジネスで利用頻度の高いMicrosoft製品とシームレスに連携でき、安全性の高い点が大きな特徴です。 ・OneDrive for Businessの公式サイトはこちら ・App Storeからダウンロードはこちら ・Google Play ストアからダウンロードはこちら OneDrive for Businessの機能 OneDrive for Businessでは、以下の機能がメインになります。 ファイル管理機能 ファイルや写真の保存、アクセス、編集、共有がどこからでも可能です。また、データはバックアップされるので、利用するデバイスに不備が生じた場合にも心配いりません。 また、Business BasicもしくはBusiness Standardプランにグレードアップすることで、以下の機能も利用できます。 メールと予定表 Exchange(業務用メール)を活用できるので、50GBまでの法人メールをサーバーで管理が可能です。また、メールを共有できるだけでなく、スケジュールを管理するための予定表もチームで使えます。 チャット機能 有料プランにはTeamsも含まれており、音声やビデオでのコミュニケーションもできます。また、重要なメッセージはピン留めして残すことも可能です。 このように、OneDrive for Businessで使える機能は加入するプランにもよりますが、「チームでファイル管理するための機能」が充実しているのです。 OneDrive for businessの使い方 以下ではOneDrive for businessの使い方をご紹介します。ビジネスシーンで想定される利用例や、サインアップの方法を確認できます。 想定される利用例 OneDrive for businessが役立つ利用例として、以下の2つが挙げられます。 外回りが必要な営業職 外回りが必要な営業職の方は、OneDrive for businessの利用に適しているといえます。 OneDrive for businessにはAndroidやiOSなどに対応したモバイルアプリがあります。そのため外出先などでも情報を簡単に確認できるのです。 また、ファイルはアプリ上でオフラインでも開けるため、アクセスが不安定な場所でも、ファイルを見ることができます。 社外の組織との情報共有が必要な職 OneDrive for businessは組織外のユーザーと情報共有が必要な場合にも便利です。 組織内だけではなく組織外のユーザーとも安全に情報共有ができるため、外部との情報共有が頻繁な方には実用的です。 アクセス権限の設定やパスワードを利用して、セキュリティの高い情報共有が可能です。また、データの転送中や保管中も常に暗号化されているため、情報を安全に管理できます。 以上のように、ビジネスシーンでの情報共有に幅広く利用できます。 サインアップ方法 OneDrive for businessにサインアップするには以下の手順を踏みましょう。 公式ページにアクセスして[購入はこちら]をクリック まず、OneDrive for businessの公式ページにアクセスしましょう。[一般法人向け]を選択すると、3つのプランが出てくるので、購入したいプランをクリックします。 サブスクリプションを設定する 次に、サブスクリプションについての設定を行います。利用するユーザー数や、期間、請求頻度を設定して、[次へ]をクリックします。 アカウントを入力し支払い情報を追加 最後にサブスクリプションを登録したいアカウントの詳細を入力します。支払い情報を入力すると、購入が完了します。 OneDrive for businessの詳細はこちら 以上の手順でサインアップが完了します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 「OneDrive for Business」と「OneDrive(個人利用)」の違い ここでは、OneDrive for Businessと通常のOneDriveの違いを解説します。法人向けと個人向けでは、料金やセキュリティが大きく異なるので必見です。 (1)管理機能を使える 1つ目の違いは管理機能を使えることです。 OneDrive for Businessには、管理者の権限でアカウントを追加・削除する機能があります。そのため、退職した従業員のアカウントを簡単に削除でき、情報漏えいを未然に防げるのです。 一方、通常のOneDriveではほかのアカウントを管理できません。したがって、セキュリティを重視するならOneDrive for Businessを選びましょう。 (2)無料プランがない 2つ目の違いは無料プランがないことです。 OneDrive for Businessには、1ヶ月の試用期間があるものの、その後は有料プランへの加入が求められます。一方、通常OneDriveには無料プランがあるため、コストを抑えたい場合におすすめです。 ただし、無料版のOneDriveでは、ストレージ容量が5GBまでとなっているので注意しなければなりません。 (3)アカウントが異なる 3つ目の違いはアカウントが異なることです。 OneDrive for Businessでは「法人専用のアカウント」を使います。そのため、個人で持っているMicrosoftアカウントからは、OneDrive for Businessへのサインインができません。 したがって、OneDrive for Businessを利用する場合は「OneDrive for Business」としての有料契約が必要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ OneDrive for Businessのアクセス権限を設定する方法 OneDrive for Businessは、アクセス権を制御できます。ただし、”何を制限するのか”によって手順は変わるので、以下で確認しましょう。 参照:Microsoft365相談センター:どこまで設定すれば安心?OneDrive for Businessの安全対策~どんな事ができる?どうやって設定する?~ OneDriveへアクセスできるデバイスを制限する OneDrive for Businessは、多人数での利用が想定されるため、なかには退職するメンバーもでてきます。そのため、退職者が出たときには、速やかに以下の対応をしましょう Microsoft365管理センターにアクセスする まず、Microsoft365の管理者のアカウントで、Microsoft365にサインインします。[Microsoft365管理センター] > [すべての管理センター] > [Share Point管理センター]を開きましょう。 ユーザープロファイル画面を開く 次に、[その他の機能]のなかから[ユーザープロファイル]を選択し、開きます。 アカウントやグループを追加する 最後に、[ユーザー権限の管理]をクリックし、アクセス権を制限したいアカウントを追加します。[OK]ボタンをクリックすれば完了です。 以上のステップで、情報を公開する範囲を適切に管理し、情報漏えいのリスクになくしましょう。 OneDrive自体へのアクセスを制限する 各デバイスから、インターネットにアクセスするときは「IPアドレス」が必要になります。OneDrive for Businessでは、以下の手順で「指定されたIPアドレスでのみアクセスを許可する」ことが可能です。 まず、「ShreaPoint 管理センター」を開きましょう。 次に、[ポリシー] > [アクセスの制御] >[アクセスの制御]の順に画面を開きます。 最後に、[ネットワーク上の場所]から、”特定のIPアドレスからのアクセスのみ許可する”設定します。 以上の手順で、より厳格に外部からの不正アクセスを防げます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ OneDrive for Businessを使うメリットは? 以下では、無料版のOneDriveと比較して、OneDrive for Businessを使うメリットを紹介します。メリットを把握した上で自社に適したツールか判断しましょう。 高度なセキュリティを備えている 無料版と比較して「Microsoft 365 Business Basic」と「Microsoft 365 Business Standard」は安全性が高く、会社での利用に適しています。 ファイル共有時に役立つ 無料版にはないファイル共有の機能が備わっています。アクセス権を取り消したり、ダウンロードを禁止したりできるので、情報漏えいの防止に役立ちます。 以上のようなメリットがあるため、OneDrive for BusinessはOneDrive(個人利用)と比べて、高いセキュリティを要する企業や、小規模~大規模チームでの利用に適していると言えます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 要注意!OneDrive for Businessのデメリットとは OneDrive for Businessには、共有に時間がかかるデメリットがあります。 結局のところ、OneDrive for Businessに添付した資料を読むには、ファイルをひとつずつ開かなければなりません。また、ファイル形式でのデータ管理する場合、「見つけやすい情報構造」「キーワード単位でヒットする検索機能」がなければ、使いづらいです。 一方、「ノート形式に直接情報を書き込めるITツール」であれば、ファイルを開く手間を省けます。なかでも、「ファイル内検索」や「ファイル要約」も可能な「ナレカン」であれば、ExcelやWord、PowerPointもそのまま管理・共有できて便利です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】OneDrive for Businessのデメリットを解消するツール 以下では、OneDrive for Businessのデメリットを解消するツールをご紹介します。 OneDrive for Businessはクラウド上で情報を管理するツールであるため、情報を確認するにはファイルを一つずつ開かなければならず、手間がかかります。そのため、社内の情報を一元管理して、すぐに欲しい情報を取り出せる環境を作る必要があるのです。 また社内のナレッジが膨大になると、必要なファイルをすぐに見つけ出すことができません。そこで、検索機能が優れているツールを使用すれば、簡単に情報を見つけ出せるため、業務にかかる時間を大幅に短縮できます。 結論、OneDrive for Businessのデメリットを解消するには、あらゆる情報を一元管理でき、欲しい情報をすぐに探し出せる「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事機能」を使えば、テキストはもちろん、画像やファイルも直接添付してわかりやすく情報を保存できます。さらに、検索機能が優れているため多くの情報の中から必要な情報をすぐに取り出すことが可能です。 誰でもストレスなくファイル管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ OneDrive for Businessの料金/容量プラン 以下は、OneDrive for Businessの料金と容量のプラン表です。 OneDrive for Business (Plan 1) Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard 料金 (年払い) 749円(税抜)/ユーザー/月 899円(税抜)/ユーザー/月 1,874円(税抜)/ユーザー/月 容量 1TB 1TB 1TB 法人メール ✕ 〇 〇 標準のセキュリティ ✕ 〇 〇 チャット機能(Microsoft Teams) ✕ 〇 〇 上記のうち、OneDrive for Business (Plan 1)では、1か月の無料試用ができません。また、全てのプランで容量が定められており、無制限ではない点に注意しましょう。 参照:OneDrive for Businessの料金ページ 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ OneDrive for Businessの口コミ・評判 以下では、OneDrive for Businessの口コミ・評判をご紹介します。自社で導入するにあたり、具体的な運用イメージを持ちたい方は必見です。 ※こちらでご紹介する口コミ・評判は、すべてITreviewより引用しています。 OneDrive for Businessの良い口コミ・評判 OneDrive for Businessの良い口コミ・評判は以下の通りです。 非公開ユーザー 投稿日:2025年07月30日 PCのデータバックアップだけでなく、PCのリプレイスの負荷軽減に役立つサービスです。 非公開ユーザー 投稿日:2025年03月03日 Microsoft 365との連携がシームレスでスムーズ。特に、Microsoft Officeアプリ間でのオンライン/オフラインアプリでの連携・作成・共有が一体化していて365組織内のユーザー間でのファイル共有管理においては非常に便利。 非公開ユーザー 投稿日:2025年02月20日 この製品の機能にはファイル共有とドキュメント格納がありますが、容量がTeamsと比べても非常に大きいのがメリットです。 上記のように、Microsoft365との連携がスムーズな点や、容量が大きいことが評価されています。 OneDrive for Businessの改善点に関する口コミ・評判 OneDrive for Businessの改善点に関する口コミ・評判は以下の通りです。 非公開ユーザー 投稿日:2025年07月30日 クラウド同期を取っても、別PCから見た時にタイムラグが長く感じる事がある。 非公開ユーザー 投稿日:2025年03月03日 ローカルアプリケーションにおいての挙動が時々不安定な時がある。 非公開ユーザー 投稿日:2025年02月20日 ファイルの容量によりますが、格納まで時間がかかる点が改善点です。SharePointと比べてファイルや画像の格納に時間がかかります。 上記のように、タイムラグが生じる点や、動作が不安定である点に改善を求める声が寄せられています。使い勝手の悪いツールは形骸化してしまうため、高度な検索機能を有し、誰でも利用できるほどシンプルな「ナレカン」のようなツールを導入しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ OneDrive for BusinessとOneDriveの違いまとめ これまで、OneDrive for Businessの概要や個人向けOneDriveとの違いを中心に解説しました。 OneDrive for Businessは通常のOneDriveと異なり、従業員のアカウントを追加・削除できる「管理機能」を使える点がメリットです。一方、ファイルを開くのに手間がかかったり、検索性に使いづらかったりするデメリットがあります。 そこで、ファイル内の情報にもヒットしたり、ゆらぎ表記に対応していたりする「検索性に優れたツール」を使えば、スピーディな情報共有が実現します。加えて、シンプルなUIであれば、ITに不慣れなメンバーでも迷わず情報にたどり着けるのです。 結論、上記の検索機能を備えつつ、分かりやすい構造で情報を管理できる「ナレカン」が最適です。また、ナレカンでは、既存データの移行支援も実施しているので、すでに利用するアプリがあっても乗り換えの負担がかかりません。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、OneDrive for Businessよりも円滑なファイル共有をしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 初心者向け|OneDrive(ワンドライブ)とは?使い方や必要性、価格を紹介続きを読む
2025年08月20日OneDrive for Businessとは?OneDriveとの違いや使い方を解説Microsoft社が提供するクラウドストレージのひとつに「OneDrive for Business」があります。通常のOneDriveと異なり、法人向けに特化したサービスです。 しかし、なかには「個人向けと法人向けで、何が違うのか分からない」と混乱している方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、OneDrive for Businessの使い方や料金、個人向けのOneDriveとの違いを網羅的に解説します。 OneDrive Business がどのようなツールか知りたい OneDrive Business とOneDriveの違いを把握したい OneDrive Businessから新しいツールへの移行を検討している という方はこの記事を参考にすると、OneDrive for Businessの特徴や機能が分かるほか、ファイル管理の手間も解消できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 OneDrive for Businessとは1.1 OneDrive for Businessの特徴1.2 OneDrive for Businessの機能1.3 OneDrive for businessの使い方2 「OneDrive for Business」と「OneDrive(個人利用)」の違い2.1 (1)管理機能を使える2.2 (2)無料プランがない2.3 (3)アカウントが異なる3 OneDrive for Businessのアクセス権限を設定する方法4 OneDrive for Businessを使うメリットは?5 要注意!OneDrive for Businessのデメリットとは6 【必見】OneDrive for Businessのデメリットを解消するツール6.1 誰でもストレスなくファイル管理できるツール「ナレカン」7 OneDrive for Businessの料金/容量プラン8 OneDrive for Businessの口コミ・評判8.1 OneDrive for Businessの良い口コミ・評判8.2 OneDrive for Businessの改善点に関する口コミ・評判9 OneDrive for BusinessとOneDriveの違いまとめ OneDrive for Businessとは 以下では、OneDrive for Businessの特徴をご紹介します。「有名だから」という理由で導入してしまうと、トラブルを招きかねないため、まずは詳細を押さえましょう。 OneDrive for Businessの特徴 引用:OneDrive for Businessの公式サイト OneDrive for Businessは、Microsoft社が提供するクラウドストレージです。 通常のOneDriveと同じく、ビジネスで多用されるWordやExcel、PowerPointだけでなく、モバイルアプリを用いればスマホで撮影した画像も手軽に残せます。また、TeamsやSharePointで共有したファイルを、そのままOneDriveに保存することも可能です。 加えて、「従業員のアカウントを管理する機能」によってセキュリティも強化されているため、ビジネス利用がしやすい点もメリットです。以上のように、ビジネスで利用頻度の高いMicrosoft製品とシームレスに連携でき、安全性の高い点が大きな特徴です。 ・OneDrive for Businessの公式サイトはこちら ・App Storeからダウンロードはこちら ・Google Play ストアからダウンロードはこちら OneDrive for Businessの機能 OneDrive for Businessでは、以下の機能がメインになります。 ファイル管理機能 ファイルや写真の保存、アクセス、編集、共有がどこからでも可能です。また、データはバックアップされるので、利用するデバイスに不備が生じた場合にも心配いりません。 また、Business BasicもしくはBusiness Standardプランにグレードアップすることで、以下の機能も利用できます。 メールと予定表 Exchange(業務用メール)を活用できるので、50GBまでの法人メールをサーバーで管理が可能です。また、メールを共有できるだけでなく、スケジュールを管理するための予定表もチームで使えます。 チャット機能 有料プランにはTeamsも含まれており、音声やビデオでのコミュニケーションもできます。また、重要なメッセージはピン留めして残すことも可能です。 このように、OneDrive for Businessで使える機能は加入するプランにもよりますが、「チームでファイル管理するための機能」が充実しているのです。 OneDrive for businessの使い方 以下ではOneDrive for businessの使い方をご紹介します。ビジネスシーンで想定される利用例や、サインアップの方法を確認できます。 想定される利用例 OneDrive for businessが役立つ利用例として、以下の2つが挙げられます。 外回りが必要な営業職 外回りが必要な営業職の方は、OneDrive for businessの利用に適しているといえます。 OneDrive for businessにはAndroidやiOSなどに対応したモバイルアプリがあります。そのため外出先などでも情報を簡単に確認できるのです。 また、ファイルはアプリ上でオフラインでも開けるため、アクセスが不安定な場所でも、ファイルを見ることができます。 社外の組織との情報共有が必要な職 OneDrive for businessは組織外のユーザーと情報共有が必要な場合にも便利です。 組織内だけではなく組織外のユーザーとも安全に情報共有ができるため、外部との情報共有が頻繁な方には実用的です。 アクセス権限の設定やパスワードを利用して、セキュリティの高い情報共有が可能です。また、データの転送中や保管中も常に暗号化されているため、情報を安全に管理できます。 以上のように、ビジネスシーンでの情報共有に幅広く利用できます。 サインアップ方法 OneDrive for businessにサインアップするには以下の手順を踏みましょう。 公式ページにアクセスして[購入はこちら]をクリック まず、OneDrive for businessの公式ページにアクセスしましょう。[一般法人向け]を選択すると、3つのプランが出てくるので、購入したいプランをクリックします。 サブスクリプションを設定する 次に、サブスクリプションについての設定を行います。利用するユーザー数や、期間、請求頻度を設定して、[次へ]をクリックします。 アカウントを入力し支払い情報を追加 最後にサブスクリプションを登録したいアカウントの詳細を入力します。支払い情報を入力すると、購入が完了します。 OneDrive for businessの詳細はこちら 以上の手順でサインアップが完了します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 「OneDrive for Business」と「OneDrive(個人利用)」の違い ここでは、OneDrive for Businessと通常のOneDriveの違いを解説します。法人向けと個人向けでは、料金やセキュリティが大きく異なるので必見です。 (1)管理機能を使える 1つ目の違いは管理機能を使えることです。 OneDrive for Businessには、管理者の権限でアカウントを追加・削除する機能があります。そのため、退職した従業員のアカウントを簡単に削除でき、情報漏えいを未然に防げるのです。 一方、通常のOneDriveではほかのアカウントを管理できません。したがって、セキュリティを重視するならOneDrive for Businessを選びましょう。 (2)無料プランがない 2つ目の違いは無料プランがないことです。 OneDrive for Businessには、1ヶ月の試用期間があるものの、その後は有料プランへの加入が求められます。一方、通常OneDriveには無料プランがあるため、コストを抑えたい場合におすすめです。 ただし、無料版のOneDriveでは、ストレージ容量が5GBまでとなっているので注意しなければなりません。 (3)アカウントが異なる 3つ目の違いはアカウントが異なることです。 OneDrive for Businessでは「法人専用のアカウント」を使います。そのため、個人で持っているMicrosoftアカウントからは、OneDrive for Businessへのサインインができません。 したがって、OneDrive for Businessを利用する場合は「OneDrive for Business」としての有料契約が必要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ OneDrive for Businessのアクセス権限を設定する方法 OneDrive for Businessは、アクセス権を制御できます。ただし、”何を制限するのか”によって手順は変わるので、以下で確認しましょう。 参照:Microsoft365相談センター:どこまで設定すれば安心?OneDrive for Businessの安全対策~どんな事ができる?どうやって設定する?~ OneDriveへアクセスできるデバイスを制限する OneDrive for Businessは、多人数での利用が想定されるため、なかには退職するメンバーもでてきます。そのため、退職者が出たときには、速やかに以下の対応をしましょう Microsoft365管理センターにアクセスする まず、Microsoft365の管理者のアカウントで、Microsoft365にサインインします。[Microsoft365管理センター] > [すべての管理センター] > [Share Point管理センター]を開きましょう。 ユーザープロファイル画面を開く 次に、[その他の機能]のなかから[ユーザープロファイル]を選択し、開きます。 アカウントやグループを追加する 最後に、[ユーザー権限の管理]をクリックし、アクセス権を制限したいアカウントを追加します。[OK]ボタンをクリックすれば完了です。 以上のステップで、情報を公開する範囲を適切に管理し、情報漏えいのリスクになくしましょう。 OneDrive自体へのアクセスを制限する 各デバイスから、インターネットにアクセスするときは「IPアドレス」が必要になります。OneDrive for Businessでは、以下の手順で「指定されたIPアドレスでのみアクセスを許可する」ことが可能です。 まず、「ShreaPoint 管理センター」を開きましょう。 次に、[ポリシー] > [アクセスの制御] >[アクセスの制御]の順に画面を開きます。 最後に、[ネットワーク上の場所]から、”特定のIPアドレスからのアクセスのみ許可する”設定します。 以上の手順で、より厳格に外部からの不正アクセスを防げます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ OneDrive for Businessを使うメリットは? 以下では、無料版のOneDriveと比較して、OneDrive for Businessを使うメリットを紹介します。メリットを把握した上で自社に適したツールか判断しましょう。 高度なセキュリティを備えている 無料版と比較して「Microsoft 365 Business Basic」と「Microsoft 365 Business Standard」は安全性が高く、会社での利用に適しています。 ファイル共有時に役立つ 無料版にはないファイル共有の機能が備わっています。アクセス権を取り消したり、ダウンロードを禁止したりできるので、情報漏えいの防止に役立ちます。 以上のようなメリットがあるため、OneDrive for BusinessはOneDrive(個人利用)と比べて、高いセキュリティを要する企業や、小規模~大規模チームでの利用に適していると言えます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 要注意!OneDrive for Businessのデメリットとは OneDrive for Businessには、共有に時間がかかるデメリットがあります。 結局のところ、OneDrive for Businessに添付した資料を読むには、ファイルをひとつずつ開かなければなりません。また、ファイル形式でのデータ管理する場合、「見つけやすい情報構造」「キーワード単位でヒットする検索機能」がなければ、使いづらいです。 一方、「ノート形式に直接情報を書き込めるITツール」であれば、ファイルを開く手間を省けます。なかでも、「ファイル内検索」や「ファイル要約」も可能な「ナレカン」であれば、ExcelやWord、PowerPointもそのまま管理・共有できて便利です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】OneDrive for Businessのデメリットを解消するツール 以下では、OneDrive for Businessのデメリットを解消するツールをご紹介します。 OneDrive for Businessはクラウド上で情報を管理するツールであるため、情報を確認するにはファイルを一つずつ開かなければならず、手間がかかります。そのため、社内の情報を一元管理して、すぐに欲しい情報を取り出せる環境を作る必要があるのです。 また社内のナレッジが膨大になると、必要なファイルをすぐに見つけ出すことができません。そこで、検索機能が優れているツールを使用すれば、簡単に情報を見つけ出せるため、業務にかかる時間を大幅に短縮できます。 結論、OneDrive for Businessのデメリットを解消するには、あらゆる情報を一元管理でき、欲しい情報をすぐに探し出せる「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事機能」を使えば、テキストはもちろん、画像やファイルも直接添付してわかりやすく情報を保存できます。さらに、検索機能が優れているため多くの情報の中から必要な情報をすぐに取り出すことが可能です。 誰でもストレスなくファイル管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ OneDrive for Businessの料金/容量プラン 以下は、OneDrive for Businessの料金と容量のプラン表です。 OneDrive for Business (Plan 1) Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard 料金 (年払い) 749円(税抜)/ユーザー/月 899円(税抜)/ユーザー/月 1,874円(税抜)/ユーザー/月 容量 1TB 1TB 1TB 法人メール ✕ 〇 〇 標準のセキュリティ ✕ 〇 〇 チャット機能(Microsoft Teams) ✕ 〇 〇 上記のうち、OneDrive for Business (Plan 1)では、1か月の無料試用ができません。また、全てのプランで容量が定められており、無制限ではない点に注意しましょう。 参照:OneDrive for Businessの料金ページ 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ OneDrive for Businessの口コミ・評判 以下では、OneDrive for Businessの口コミ・評判をご紹介します。自社で導入するにあたり、具体的な運用イメージを持ちたい方は必見です。 ※こちらでご紹介する口コミ・評判は、すべてITreviewより引用しています。 OneDrive for Businessの良い口コミ・評判 OneDrive for Businessの良い口コミ・評判は以下の通りです。 非公開ユーザー 投稿日:2025年07月30日 PCのデータバックアップだけでなく、PCのリプレイスの負荷軽減に役立つサービスです。 非公開ユーザー 投稿日:2025年03月03日 Microsoft 365との連携がシームレスでスムーズ。特に、Microsoft Officeアプリ間でのオンライン/オフラインアプリでの連携・作成・共有が一体化していて365組織内のユーザー間でのファイル共有管理においては非常に便利。 非公開ユーザー 投稿日:2025年02月20日 この製品の機能にはファイル共有とドキュメント格納がありますが、容量がTeamsと比べても非常に大きいのがメリットです。 上記のように、Microsoft365との連携がスムーズな点や、容量が大きいことが評価されています。 OneDrive for Businessの改善点に関する口コミ・評判 OneDrive for Businessの改善点に関する口コミ・評判は以下の通りです。 非公開ユーザー 投稿日:2025年07月30日 クラウド同期を取っても、別PCから見た時にタイムラグが長く感じる事がある。 非公開ユーザー 投稿日:2025年03月03日 ローカルアプリケーションにおいての挙動が時々不安定な時がある。 非公開ユーザー 投稿日:2025年02月20日 ファイルの容量によりますが、格納まで時間がかかる点が改善点です。SharePointと比べてファイルや画像の格納に時間がかかります。 上記のように、タイムラグが生じる点や、動作が不安定である点に改善を求める声が寄せられています。使い勝手の悪いツールは形骸化してしまうため、高度な検索機能を有し、誰でも利用できるほどシンプルな「ナレカン」のようなツールを導入しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ OneDrive for BusinessとOneDriveの違いまとめ これまで、OneDrive for Businessの概要や個人向けOneDriveとの違いを中心に解説しました。 OneDrive for Businessは通常のOneDriveと異なり、従業員のアカウントを追加・削除できる「管理機能」を使える点がメリットです。一方、ファイルを開くのに手間がかかったり、検索性に使いづらかったりするデメリットがあります。 そこで、ファイル内の情報にもヒットしたり、ゆらぎ表記に対応していたりする「検索性に優れたツール」を使えば、スピーディな情報共有が実現します。加えて、シンプルなUIであれば、ITに不慣れなメンバーでも迷わず情報にたどり着けるのです。 結論、上記の検索機能を備えつつ、分かりやすい構造で情報を管理できる「ナレカン」が最適です。また、ナレカンでは、既存データの移行支援も実施しているので、すでに利用するアプリがあっても乗り換えの負担がかかりません。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、OneDrive for Businessよりも円滑なファイル共有をしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 初心者向け|OneDrive(ワンドライブ)とは?使い方や必要性、価格を紹介続きを読む
最新の投稿
おすすめ記事

