ナレッジマネジメント
お役立ちガイド
ナレッジマネジメントのノウハウや、
効率化のポイントなど、
ビジネスで役立つ情報をご紹介します。
効率化のポイントなど、
ビジネスで役立つ情報をご紹介します。

ナレッジ管理
-
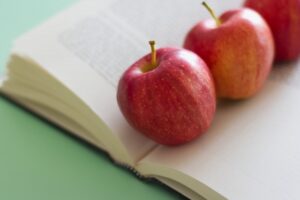 2026年01月14日【例文あり】ナレッジシェアとは?重要性や方法を解説近年、情報の属人化・ノウハウの偏りを防ぐために、「ナレッジシェア」に取り組む企業が増えています。ナレッジシェアができれば、社内メンバー内で知識が共有され、業務品質の向上も期待できるのです。 しかし、「ナレッジシェアとはなにか、概要や具体的なやり方が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ナレッジシェアの意味や重要性、方法を中心にご紹介します。 ナレッジシェアはどんなものか概要が知りたい ナレッジシェアに取り組みたいが、具体的な方法が分からない 社内でナレッジシェアを円滑に進められるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、自社でのナレッジシェアどのように進めるべきかが分かります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ナレッジシェア(ナレッジシェアリング)とは?1.1 「ナレッジシェア」とは何か1.2 「ナレッジシェア」の例文1.3 「ナレッジ共有」との違い2 ナレッジシェアの重要性・注目される背景3 ナレッジの種類|暗黙知と形式知とは4 ナレッジシェアのメリット4.1 属人化の解消4.2 社員のスキルアップ4.3 成功事例や失敗事例の蓄積による改善5 【3ステップ】ナレッジシェアの方法5.1 ステップ1|推進メンバーを決める5.2 ステップ2|ナレッジシェアのやり方を明文化する5.3 ステップ3|メンバーに習慣化を促す6 【必見】ナレッジシェアにおすすめのツール6.1 社内のナレッジシェアの推進に役立つツール「ナレカン」7 ナレッジシェアの概要や方法まとめ ナレッジシェア(ナレッジシェアリング)とは? 以下では、ナレッジシェア(ナレッジシェアリング)の意味や例文、類語との違いを紹介します。ナレッジシェアの概要が知りたい方は必見です。 「ナレッジシェア」とは何か 「ナレッジシェア(Knowledge Share)」とは、個人やチームが持つ業務知識・ノウハウ・経験などの情報を、他者や組織内で共有する取り組みを指します。 特定の社員にしかわからない「暗黙知」や、「失敗から得た教訓」など、形式知化されていない知識も含まれます。近年では、リモートワークや人材の流動化が進む中で、企業が継続的に価値を創出していくための重要な基盤として注目されています。 したがって、ナレッジシェアは単なる情報共有ではなく、「誰かのために知識を役立てる」という視点が求められる行為です。 「ナレッジシェア」の例文 以下は、職場における「ナレッジシェア」の実用例文です。 「今朝の会議で挙がった提案内容は、ナレッジシェアの観点からも資料にまとめて部門全体へ共有しましょう。」 「この業務はミスが起こりやすいので、再発防止のためにメンバーへナレッジシェアしてください。」 「新人研修で得られたフィードバックを、ナレッジシェアの一環として社内Wikiに記録しました。」 このように、「ナレッジシェア」は業務における情報共有・改善といったシーンで使われることが多いです。 「ナレッジ共有」との違い 「ナレッジシェア」と「ナレッジ共有」は、情報の伝え方において違いがあると言えます。 「ナレッジ共有」は、共有する側が一方向に情報発信する意味合いで使われることが多くあります。一方、「ナレッジシェア」は、相互的・能動的な知識のやり取りを前提としています。 属人化防止を実現するには、共有するだけではなく、相互に知識を活かし合う「シェア」の姿勢を浸透させることが重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジシェアの重要性・注目される背景 ナレッジシェアは、社会状況の変化により実施の重要性が高まっています。 近年はリモートワークの普及や人材不足により、知識が個人ごとに分散しやすく、属人化が加速しています。こうした中で、ナレッジシェアを推し進めて知識やノウハウを組織内で共有することは、業務の円滑な進行や、業務水準の底上げに効果的です。 一方で、ナレッジや知識が偏っている企業では、「同じ失敗の繰り返し」や「特定の人に聞かないと仕事が進められない」事態に陥ってしまいます。そのため、社内でナレッジシェアの文化を構築し、組織全体の成長を促すべきなのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジの種類|暗黙知と形式知とは ナレッジには大きく分けて「暗黙知」と「形式知」があります。 暗黙知とは、経験や勘、感覚に基づいた言語化しにくい知識で、現場の判断やスキルに含まれます。一方、形式知は文書やマニュアルなど、共有しやすく整備された知識を指します。 とくに、すぐには分かりにくい暗黙知を形式知へと変換することが、ナレッジシェアの鍵となります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジシェアのメリット ナレッジシェアに取り組むと、「属人化の解消」「社員のスキルアップ」「成功事例や失敗事例の蓄積による改善」のメリットが得られます。以下では、各メリットの具体的な効果について解説します。 属人化の解消 ナレッジシェアは、業務の属人化を解消する効果があります。 特定の個人に依存していたノウハウを共有・蓄積することで、不在時や退職時の業務停滞を防げます。また、誰が業務に携わっても同じ品質で対応できる体制を整えられるので、急な異動・退職リスク対策にもつながります。 ナレッジシェアは、業務を持続的に進めるうえで重要なのです。 社員のスキルアップ ナレッジシェアは社員のスキルアップを促進します。 ほかのメンバーの経験や他部署のノウハウから学ぶことで、自分の担当業務以外の視点やスキルが身につきます。さらに、自ら情報発信すれば自身の考えも整理され、学びが深まります。 社内でナレッジシェアし、学び合う文化が定着すれば、社員の働くモチベーションやエンゲージメント(企業への愛着)も自然に向上していきます。 成功事例や失敗事例の蓄積による改善 ナレッジシェアは、成功・失敗の事例を資産化するうえでも重要です。 業務で得た知見を組織で共有すると、同じミスの再発防止になります。また、成功事例もノウハウとして残せば、似たような状況のときに再現性が高まるのです。 ナレッジの蓄積と活用が習慣化されると、将来的に競争力の高い組織へと成長することが期待できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【3ステップ】ナレッジシェアの方法 以下では、ナレッジシェアの方法を3ステップに分けて紹介します。社内でナレッジシェアを始めようとしている方は必見です。 ステップ1|推進メンバーを決める まずはナレッジシェアのプロジェクトを牽引する「推進メンバー」を選任しましょう。 推進メンバーを決めることで、ナレッジの管理や共有の促進がスムーズに進みます。メンバーを選定するときは、ナレッジが共有されないことで実際に困っている社員や、社内で影響力のある社員・情報発信が得意な社員が適任です。 推進メンバーは少人数のチームとして組むと、チーム内でナレッジシェアの仮運用もしやすくなります。 ステップ2|ナレッジシェアのやり方を明文化する 次に、ナレッジシェアのやり方を明文化しましょう。 どのような情報を、いつ、どこで、どのように共有するかを定めることで、関係者が迷わず行動できます。明文化された運用ルールがあれば、ナレッジシェアの仕組みを安定的に運用する基盤となるのです。 したがって、ナレッジシェアのやり方はマニュアルや社内掲示板・社内wiki等にまとめておきましょう。 ステップ3|メンバーに習慣化を促す 最後に、ナレッジシェアを社内メンバーに習慣化するよう促します。 重要なのは、各社員に「ナレッジを共有すること」が日常業務の一部として定着するように、習慣化を促すことです。そのためには、業務の中にナレッジシェアを組み込んだり、ナレッジ共有を評価・称賛する仕組みをつくったりする方法が効果的です。 たとえば、会議での共有時間の確保や、「○○社の事例をナレッジとして記録しました」と社内告知したメンバーにリアクションを送る文化を作ると、習慣化につながります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】ナレッジシェアにおすすめのツール 以下では、ナレッジシェアにおすすめのツールをご紹介します。 ナレッジシェアを成功させるには、社内メンバーにナレッジの記録・共有を習慣づける必要があります。しかし、ナレッジのまとめ方がルール化されていないと結局ナレッジを残すハードルが高く、定着しなくなってしまいます。 そこで、「社内メンバーが気軽に使えるナレッジ管理専用ツール」を導入すると、ナレッジシェアのハードルが下げられます。また、ナレッジシェアがうまく進んでいるか、メンバーの利用状況が確かめられるツールを導入すると改善にもつなげやすいのです。 結論、ナレッジシェアには社内のあらゆる情報を簡単に共有・確認できるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンはメモを残すように気軽にナレッジを残せるうえ、不明点を社内メンバーに質問することでナレッジを蓄積することも可能です。また、「利用状況レポート」でメンバーのナレッジシェアの取り組み状況も分かるので、ナレッジシェアの定着に向け改善点を見つけられるのです。 社内のナレッジシェアの推進に役立つツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジシェアの概要や方法まとめ これまで、ナレッジシェア(ナレッジシェアリング)の意味や例文、方法を中心にご紹介しました。 ナレッジシェアは、企業が円滑かつ高品質な業務を進めていくうえで欠かせません。そのため、ナレッジシェアが社内に根付くように推進していく必要があるのです。 一方で、ナレッジのまとめ方や共有方法が決まっていない・やり方が複雑だと、社内メンバーがナレッジシェアに対するハードルが高く実行しなくなってしまいます。したがって、「誰でも気軽にナレッジシェアができるITツール」を導入しましょう。 結論、直感的かつメモ・質問ベースでナレッジシェアができるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、活発なナレッジシェアを実現しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2026年01月14日【例文あり】ナレッジシェアとは?重要性や方法を解説近年、情報の属人化・ノウハウの偏りを防ぐために、「ナレッジシェア」に取り組む企業が増えています。ナレッジシェアができれば、社内メンバー内で知識が共有され、業務品質の向上も期待できるのです。 しかし、「ナレッジシェアとはなにか、概要や具体的なやり方が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ナレッジシェアの意味や重要性、方法を中心にご紹介します。 ナレッジシェアはどんなものか概要が知りたい ナレッジシェアに取り組みたいが、具体的な方法が分からない 社内でナレッジシェアを円滑に進められるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、自社でのナレッジシェアどのように進めるべきかが分かります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ナレッジシェア(ナレッジシェアリング)とは?1.1 「ナレッジシェア」とは何か1.2 「ナレッジシェア」の例文1.3 「ナレッジ共有」との違い2 ナレッジシェアの重要性・注目される背景3 ナレッジの種類|暗黙知と形式知とは4 ナレッジシェアのメリット4.1 属人化の解消4.2 社員のスキルアップ4.3 成功事例や失敗事例の蓄積による改善5 【3ステップ】ナレッジシェアの方法5.1 ステップ1|推進メンバーを決める5.2 ステップ2|ナレッジシェアのやり方を明文化する5.3 ステップ3|メンバーに習慣化を促す6 【必見】ナレッジシェアにおすすめのツール6.1 社内のナレッジシェアの推進に役立つツール「ナレカン」7 ナレッジシェアの概要や方法まとめ ナレッジシェア(ナレッジシェアリング)とは? 以下では、ナレッジシェア(ナレッジシェアリング)の意味や例文、類語との違いを紹介します。ナレッジシェアの概要が知りたい方は必見です。 「ナレッジシェア」とは何か 「ナレッジシェア(Knowledge Share)」とは、個人やチームが持つ業務知識・ノウハウ・経験などの情報を、他者や組織内で共有する取り組みを指します。 特定の社員にしかわからない「暗黙知」や、「失敗から得た教訓」など、形式知化されていない知識も含まれます。近年では、リモートワークや人材の流動化が進む中で、企業が継続的に価値を創出していくための重要な基盤として注目されています。 したがって、ナレッジシェアは単なる情報共有ではなく、「誰かのために知識を役立てる」という視点が求められる行為です。 「ナレッジシェア」の例文 以下は、職場における「ナレッジシェア」の実用例文です。 「今朝の会議で挙がった提案内容は、ナレッジシェアの観点からも資料にまとめて部門全体へ共有しましょう。」 「この業務はミスが起こりやすいので、再発防止のためにメンバーへナレッジシェアしてください。」 「新人研修で得られたフィードバックを、ナレッジシェアの一環として社内Wikiに記録しました。」 このように、「ナレッジシェア」は業務における情報共有・改善といったシーンで使われることが多いです。 「ナレッジ共有」との違い 「ナレッジシェア」と「ナレッジ共有」は、情報の伝え方において違いがあると言えます。 「ナレッジ共有」は、共有する側が一方向に情報発信する意味合いで使われることが多くあります。一方、「ナレッジシェア」は、相互的・能動的な知識のやり取りを前提としています。 属人化防止を実現するには、共有するだけではなく、相互に知識を活かし合う「シェア」の姿勢を浸透させることが重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジシェアの重要性・注目される背景 ナレッジシェアは、社会状況の変化により実施の重要性が高まっています。 近年はリモートワークの普及や人材不足により、知識が個人ごとに分散しやすく、属人化が加速しています。こうした中で、ナレッジシェアを推し進めて知識やノウハウを組織内で共有することは、業務の円滑な進行や、業務水準の底上げに効果的です。 一方で、ナレッジや知識が偏っている企業では、「同じ失敗の繰り返し」や「特定の人に聞かないと仕事が進められない」事態に陥ってしまいます。そのため、社内でナレッジシェアの文化を構築し、組織全体の成長を促すべきなのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジの種類|暗黙知と形式知とは ナレッジには大きく分けて「暗黙知」と「形式知」があります。 暗黙知とは、経験や勘、感覚に基づいた言語化しにくい知識で、現場の判断やスキルに含まれます。一方、形式知は文書やマニュアルなど、共有しやすく整備された知識を指します。 とくに、すぐには分かりにくい暗黙知を形式知へと変換することが、ナレッジシェアの鍵となります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジシェアのメリット ナレッジシェアに取り組むと、「属人化の解消」「社員のスキルアップ」「成功事例や失敗事例の蓄積による改善」のメリットが得られます。以下では、各メリットの具体的な効果について解説します。 属人化の解消 ナレッジシェアは、業務の属人化を解消する効果があります。 特定の個人に依存していたノウハウを共有・蓄積することで、不在時や退職時の業務停滞を防げます。また、誰が業務に携わっても同じ品質で対応できる体制を整えられるので、急な異動・退職リスク対策にもつながります。 ナレッジシェアは、業務を持続的に進めるうえで重要なのです。 社員のスキルアップ ナレッジシェアは社員のスキルアップを促進します。 ほかのメンバーの経験や他部署のノウハウから学ぶことで、自分の担当業務以外の視点やスキルが身につきます。さらに、自ら情報発信すれば自身の考えも整理され、学びが深まります。 社内でナレッジシェアし、学び合う文化が定着すれば、社員の働くモチベーションやエンゲージメント(企業への愛着)も自然に向上していきます。 成功事例や失敗事例の蓄積による改善 ナレッジシェアは、成功・失敗の事例を資産化するうえでも重要です。 業務で得た知見を組織で共有すると、同じミスの再発防止になります。また、成功事例もノウハウとして残せば、似たような状況のときに再現性が高まるのです。 ナレッジの蓄積と活用が習慣化されると、将来的に競争力の高い組織へと成長することが期待できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【3ステップ】ナレッジシェアの方法 以下では、ナレッジシェアの方法を3ステップに分けて紹介します。社内でナレッジシェアを始めようとしている方は必見です。 ステップ1|推進メンバーを決める まずはナレッジシェアのプロジェクトを牽引する「推進メンバー」を選任しましょう。 推進メンバーを決めることで、ナレッジの管理や共有の促進がスムーズに進みます。メンバーを選定するときは、ナレッジが共有されないことで実際に困っている社員や、社内で影響力のある社員・情報発信が得意な社員が適任です。 推進メンバーは少人数のチームとして組むと、チーム内でナレッジシェアの仮運用もしやすくなります。 ステップ2|ナレッジシェアのやり方を明文化する 次に、ナレッジシェアのやり方を明文化しましょう。 どのような情報を、いつ、どこで、どのように共有するかを定めることで、関係者が迷わず行動できます。明文化された運用ルールがあれば、ナレッジシェアの仕組みを安定的に運用する基盤となるのです。 したがって、ナレッジシェアのやり方はマニュアルや社内掲示板・社内wiki等にまとめておきましょう。 ステップ3|メンバーに習慣化を促す 最後に、ナレッジシェアを社内メンバーに習慣化するよう促します。 重要なのは、各社員に「ナレッジを共有すること」が日常業務の一部として定着するように、習慣化を促すことです。そのためには、業務の中にナレッジシェアを組み込んだり、ナレッジ共有を評価・称賛する仕組みをつくったりする方法が効果的です。 たとえば、会議での共有時間の確保や、「○○社の事例をナレッジとして記録しました」と社内告知したメンバーにリアクションを送る文化を作ると、習慣化につながります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】ナレッジシェアにおすすめのツール 以下では、ナレッジシェアにおすすめのツールをご紹介します。 ナレッジシェアを成功させるには、社内メンバーにナレッジの記録・共有を習慣づける必要があります。しかし、ナレッジのまとめ方がルール化されていないと結局ナレッジを残すハードルが高く、定着しなくなってしまいます。 そこで、「社内メンバーが気軽に使えるナレッジ管理専用ツール」を導入すると、ナレッジシェアのハードルが下げられます。また、ナレッジシェアがうまく進んでいるか、メンバーの利用状況が確かめられるツールを導入すると改善にもつなげやすいのです。 結論、ナレッジシェアには社内のあらゆる情報を簡単に共有・確認できるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンはメモを残すように気軽にナレッジを残せるうえ、不明点を社内メンバーに質問することでナレッジを蓄積することも可能です。また、「利用状況レポート」でメンバーのナレッジシェアの取り組み状況も分かるので、ナレッジシェアの定着に向け改善点を見つけられるのです。 社内のナレッジシェアの推進に役立つツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジシェアの概要や方法まとめ これまで、ナレッジシェア(ナレッジシェアリング)の意味や例文、方法を中心にご紹介しました。 ナレッジシェアは、企業が円滑かつ高品質な業務を進めていくうえで欠かせません。そのため、ナレッジシェアが社内に根付くように推進していく必要があるのです。 一方で、ナレッジのまとめ方や共有方法が決まっていない・やり方が複雑だと、社内メンバーがナレッジシェアに対するハードルが高く実行しなくなってしまいます。したがって、「誰でも気軽にナレッジシェアができるITツール」を導入しましょう。 結論、直感的かつメモ・質問ベースでナレッジシェアができるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、活発なナレッジシェアを実現しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年07月31日【分かりやすく解説】ノウハウの類義語とは?チームで共有するメリットも解説!日々の業務において「ノウハウ」はあらゆる場面で使用される言葉です。ノウハウを活用すれば、企業は生産力向上などのメリットが得られるようになります。 しかし、ノウハウは利用シーンによって意味が変わる言葉であり、正しく意味を理解していないと社内で認識相違が生じる原因になります。 そこで今回は、ノウハウが持つ言葉の意味や、類義語との違いを中心にご紹介します。 「ノウハウ」の意味や使い方がよく分からない ノウハウとその類義語を区別して正しく理解したい ノウハウの共有・蓄積を容易にするツールを探している という方はこの記事を読むと、ノウハウの正しい意味や類義語との使い分けができ、ノウハウ共有に関する社内教育の促進に役立てられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ノウハウとは1.1 ノウハウの意味1.2 ビジネスにおけるノウハウの意味2 ノウハウの類義語とは2.1 要領2.2 ハウツー2.3 スキル2.4 ナレッジ2.5 知見3 ノウハウを使った例文4 企業がノウハウの蓄積・共有を行うメリットとは4.1 知識の属人化防止4.2 業務効率の向上4.3 社内の財産になる5 【必見】身につけたノウハウの蓄積・共有におすすめのツール5.1 最も簡単にノウハウの蓄積・共有ができるツール「ナレカン」6 ノウハウの意味と類義語のまとめ ノウハウとは 以下では、ノウハウが持つ意味を一般的な使い方とビジネスでの使い方の2つの視点から解説します。 ノウハウの意味をチームメンバー全員が正確に把握できていなければ、認識齟齬などのトラブルに発展する可能性があるので、あらかじめ周知しておきましょう。 ノウハウの意味 ノウハウとは「物事における方法や手順、順番、コツなどの知識」を指します。 ノウハウは、英語の「know-how」が語源で「know=知る」「how=方法」という2つの単語が組み合わさっています。失敗や成功を重ねるうちに得られる「こうすれば上手くいく」といった知恵の言い換えとしているケースも多いです。 つまり、ノウハウは「過去の経験から得た知恵」とも言い換えられます。 ビジネスにおけるノウハウの意味 ビジネスにおける「ノウハウ」は単なる知識ではなく、ビジネスに関連する行為や作業に関する具体的な技術的知識を指します。 こうした知識は「手続き的知識」とも言われ、作業に対して直接適用される具体的な知識や技術を意味します。あくまでも直接適用できる知識なので、抽象的な思想や考え方、心構えなどはノウハウになりません。 また、ビジネスにおけるノウハウには「製品や開発の技術的な知識」という意味もあり、コンピューターや機械の開発・製造における「特殊な技術や知識」などが該当します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウの類義語とは 以下では、ノウハウの類義語を紹介します。同じような言葉でもそれぞれ意味に違いがあるため、類義語との違いを正しく理解しておく必要があります。 要領 要領とは「物事の要旨や要点、物事に対する方針や目的などの大事な点」を意味する言葉です。たとえば、学校教育で利用される学習指導要領では、どの学年でどのようなことを指導するかといった方針が記されています。 また、要領は本来の意味から発展して「物事を上手く処理する方法」という意味で用いられる場合もあります。「要領よく進める」や「要領を得る」などの表現がこの使い方に当たります。 ノウハウとの違いは範囲です。要領はあくまでもポイントを指す言葉であり「物事を処理する方法や手順に関する知恵」を意味するノウハウと比べて制限的に利用されます。 ハウツー ハウツーは英語の「how-to」を語源にもつ言葉で 「作業をする際の方法や手順・やり方」を指します。 ハウツーはノウハウと同じく方法や手順を表しますが、両者の大きな違いは専門性を持つかどうかです。ハウツーは一般に初心者のサポートを目的としており、専門家が必要とするような詳細な情報は含まれません。 また、手順も簡易的で分かりやすく、誰でもできるやり方が特徴です。専門性がないので、ハウツーでこなした作業は誰がやっても同じ結果になる傾向があります。 一方で、ノウハウは知的財産としての意味合いをもつように「専門性の高いやり方」です。そのため、専門的な知識が足りていない場合「成功者のノウハウと同じようにしたが、思うような結果が出せなかった」という結末になります。 スキル スキルとは、技量や手腕を意味する言葉であり「何らかの物事を行うために必要とされている能力」を意味します。 日本語では「技能」と表現される場合もありますが、技能は「筋肉や神経系統の働きに関する能力」といった意味合いが強いです。 スキルはノウハウと同様に技術や能力を表す言葉ですが、ノウハウよりも専門性の高い技術を意味します。つまり、両者はノウハウをさらに実践することでそれがテクニックとなり、そのテクニックがスキルになるという関係にあるのです。 ナレッジ ナレッジとは、英語の「knowledge」を語源にもつ言葉で、知識や情報といった意味を持つ言葉です。 一般的にナレッジは、新聞や書籍などのテキスト情報から得られるもの全般を指します。一方で、ビジネスシーンにおいては「有益性の高い情報」や「付加価値のある経験や体系的な知識」を意味するのです。 企業はナレッジを活用することで、生産性の向上や有効的な経営手法を実行できるようになります。 知見 知見とは、ナレッジと同様に英語の「knowledge」を語源にもつ言葉ではありますが、ビジネスシーンでは意味が多少異なります。 ナレッジが「付加価値のある知識」を示すのに対し、知見とは「経験や実践を通じて得られる知識」を意味します。 また、知見の方には「ある特定の分野に関する専門的な知識」の意味合いが込められているため、場面に合わせて言葉を使い分けるのが大切です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウを使った例文 以下は、「ノウハウ」を使った例文です。 今回のプロジェクトを通じてノウハウを身につけた チーム内でマーケティングのノウハウを共有する 先輩から教わったノウハウを生かす 営業活動でノウハウを得る 社内で製品開発に関するノウハウを培う このように、ノウハウは個人が持つ知識や経験を教えてもらったり業務に役立てたりした際に使うことが多い言葉です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 企業がノウハウの蓄積・共有を行うメリットとは ここからは、企業がノウハウを蓄積・共有するメリットを解説します。以下の内容を周知しておけば、ノウハウの活用をスムーズに進められます。 知識の属人化防止 ノウハウを蓄積・共有するメリットのひとつとして、特定の従業員のみが知る情報が存在している「知識の属人化」を防止できることが挙げられます。 ノウハウが社内で共有されていれば、誰でも同じ業務ができるようになります。そのため、ベテラン従業員の離職によってノウハウが失われたり、経験豊富な従業員に業務負担が偏ったりする事態を防げるのです。 このように、ノウハウの蓄積・共有によって知識の属人化が解消されれば、業務を円滑に進められるようになります。 業務効率の向上 業務効率の向上も、ノウハウの蓄積・共有によって得られるメリットと言えます。 社内でノウハウが共有されていると作業方法を簡単に確認できるようになります。そのため、「同じ質問に何度も対応する」「作業のやり方が分からず一から調べる」などの時間を削減でき、作業を効率的に進められるのです。 このように、業務が滞るのを防いで効率的に作業ができるようにするには、ノウハウを蓄積・共有できる環境が必須です。そこで、「ナレカン」のように誰でも簡単にノウハウを蓄積できるツールを使うと、情報を共有しやすくなります。 社内の財産になる ノウハウを蓄積・共有するメリットの中には、社内の財産になる点もあります。 これから行う業務に関する過去の成功事例・失敗事例の情報があれば、それぞれの内容を参考に最適なアプローチで取り組めます。 実際の経験から得られる知識や技術は、属人化しやすい傾向にあります。したがって、ノウハウを社内の財産として蓄積し、業務に生かせる環境をつくることが大切です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】身につけたノウハウの蓄積・共有におすすめのツール 以下では、身につけたノウハウの蓄積・共有におすすめのツールをご紹介します。 従業員のノウハウは正しく管理しておかないと失われてしまい、属人化を加速させる要因になってしまいます。そのため、業務で得られたノウハウは各従業員が個別に管理するのではなく、社内で共有する体制づくりが必要です。 そこで、「ノウハウの蓄積・共有に役立つITツール」を導入すれば、情報を一か所に集めることが可能なので、口頭やメモでの情報共有で起こりうる後から情報を探すのに時間がかかることを防げます。 結論、ノウハウの情報を適切に管理し、蓄積・共有するには社内の情報に、即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは社内のノウハウを一括管理できるうえ、「超高精度な検索機能」で添付ファイル内や画像内もキーワード検索できます。そのため、情報の探索を最適化した労働環境を提供するのです。 最も簡単にノウハウの蓄積・共有ができるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウの意味と類義語のまとめ これまで、ノウハウの意味と類義語との違いを中心に解説しました。 ビジネスにおけるノウハウは「技術的な知識」という意味で使われ、スキルやナレッジとは異なる意味を持っています。個人が持つノウハウの共有を進めれば、知識の属人化を防ぎながら円滑に業務を遂行できます。 しかし、共有されたノウハウが社内に分散していると従業員が必要な情報をすぐに見つけるのが困難になり、スムーズな業務進行の妨げになります。そのため、「情報の蓄積や共有、情報の検索性に優れたITツール」が必要なのです。 結論、ノウハウを適切に管理・活用するにはファイル内検索や画像内検索にも対応した、あらゆる情報の共有に最適なツール「ナレカン」一択と言えます。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」で社内のノウハウ共有を活性化させ、業務を滞りなく進めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年07月31日【分かりやすく解説】ノウハウの類義語とは?チームで共有するメリットも解説!日々の業務において「ノウハウ」はあらゆる場面で使用される言葉です。ノウハウを活用すれば、企業は生産力向上などのメリットが得られるようになります。 しかし、ノウハウは利用シーンによって意味が変わる言葉であり、正しく意味を理解していないと社内で認識相違が生じる原因になります。 そこで今回は、ノウハウが持つ言葉の意味や、類義語との違いを中心にご紹介します。 「ノウハウ」の意味や使い方がよく分からない ノウハウとその類義語を区別して正しく理解したい ノウハウの共有・蓄積を容易にするツールを探している という方はこの記事を読むと、ノウハウの正しい意味や類義語との使い分けができ、ノウハウ共有に関する社内教育の促進に役立てられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ノウハウとは1.1 ノウハウの意味1.2 ビジネスにおけるノウハウの意味2 ノウハウの類義語とは2.1 要領2.2 ハウツー2.3 スキル2.4 ナレッジ2.5 知見3 ノウハウを使った例文4 企業がノウハウの蓄積・共有を行うメリットとは4.1 知識の属人化防止4.2 業務効率の向上4.3 社内の財産になる5 【必見】身につけたノウハウの蓄積・共有におすすめのツール5.1 最も簡単にノウハウの蓄積・共有ができるツール「ナレカン」6 ノウハウの意味と類義語のまとめ ノウハウとは 以下では、ノウハウが持つ意味を一般的な使い方とビジネスでの使い方の2つの視点から解説します。 ノウハウの意味をチームメンバー全員が正確に把握できていなければ、認識齟齬などのトラブルに発展する可能性があるので、あらかじめ周知しておきましょう。 ノウハウの意味 ノウハウとは「物事における方法や手順、順番、コツなどの知識」を指します。 ノウハウは、英語の「know-how」が語源で「know=知る」「how=方法」という2つの単語が組み合わさっています。失敗や成功を重ねるうちに得られる「こうすれば上手くいく」といった知恵の言い換えとしているケースも多いです。 つまり、ノウハウは「過去の経験から得た知恵」とも言い換えられます。 ビジネスにおけるノウハウの意味 ビジネスにおける「ノウハウ」は単なる知識ではなく、ビジネスに関連する行為や作業に関する具体的な技術的知識を指します。 こうした知識は「手続き的知識」とも言われ、作業に対して直接適用される具体的な知識や技術を意味します。あくまでも直接適用できる知識なので、抽象的な思想や考え方、心構えなどはノウハウになりません。 また、ビジネスにおけるノウハウには「製品や開発の技術的な知識」という意味もあり、コンピューターや機械の開発・製造における「特殊な技術や知識」などが該当します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウの類義語とは 以下では、ノウハウの類義語を紹介します。同じような言葉でもそれぞれ意味に違いがあるため、類義語との違いを正しく理解しておく必要があります。 要領 要領とは「物事の要旨や要点、物事に対する方針や目的などの大事な点」を意味する言葉です。たとえば、学校教育で利用される学習指導要領では、どの学年でどのようなことを指導するかといった方針が記されています。 また、要領は本来の意味から発展して「物事を上手く処理する方法」という意味で用いられる場合もあります。「要領よく進める」や「要領を得る」などの表現がこの使い方に当たります。 ノウハウとの違いは範囲です。要領はあくまでもポイントを指す言葉であり「物事を処理する方法や手順に関する知恵」を意味するノウハウと比べて制限的に利用されます。 ハウツー ハウツーは英語の「how-to」を語源にもつ言葉で 「作業をする際の方法や手順・やり方」を指します。 ハウツーはノウハウと同じく方法や手順を表しますが、両者の大きな違いは専門性を持つかどうかです。ハウツーは一般に初心者のサポートを目的としており、専門家が必要とするような詳細な情報は含まれません。 また、手順も簡易的で分かりやすく、誰でもできるやり方が特徴です。専門性がないので、ハウツーでこなした作業は誰がやっても同じ結果になる傾向があります。 一方で、ノウハウは知的財産としての意味合いをもつように「専門性の高いやり方」です。そのため、専門的な知識が足りていない場合「成功者のノウハウと同じようにしたが、思うような結果が出せなかった」という結末になります。 スキル スキルとは、技量や手腕を意味する言葉であり「何らかの物事を行うために必要とされている能力」を意味します。 日本語では「技能」と表現される場合もありますが、技能は「筋肉や神経系統の働きに関する能力」といった意味合いが強いです。 スキルはノウハウと同様に技術や能力を表す言葉ですが、ノウハウよりも専門性の高い技術を意味します。つまり、両者はノウハウをさらに実践することでそれがテクニックとなり、そのテクニックがスキルになるという関係にあるのです。 ナレッジ ナレッジとは、英語の「knowledge」を語源にもつ言葉で、知識や情報といった意味を持つ言葉です。 一般的にナレッジは、新聞や書籍などのテキスト情報から得られるもの全般を指します。一方で、ビジネスシーンにおいては「有益性の高い情報」や「付加価値のある経験や体系的な知識」を意味するのです。 企業はナレッジを活用することで、生産性の向上や有効的な経営手法を実行できるようになります。 知見 知見とは、ナレッジと同様に英語の「knowledge」を語源にもつ言葉ではありますが、ビジネスシーンでは意味が多少異なります。 ナレッジが「付加価値のある知識」を示すのに対し、知見とは「経験や実践を通じて得られる知識」を意味します。 また、知見の方には「ある特定の分野に関する専門的な知識」の意味合いが込められているため、場面に合わせて言葉を使い分けるのが大切です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウを使った例文 以下は、「ノウハウ」を使った例文です。 今回のプロジェクトを通じてノウハウを身につけた チーム内でマーケティングのノウハウを共有する 先輩から教わったノウハウを生かす 営業活動でノウハウを得る 社内で製品開発に関するノウハウを培う このように、ノウハウは個人が持つ知識や経験を教えてもらったり業務に役立てたりした際に使うことが多い言葉です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 企業がノウハウの蓄積・共有を行うメリットとは ここからは、企業がノウハウを蓄積・共有するメリットを解説します。以下の内容を周知しておけば、ノウハウの活用をスムーズに進められます。 知識の属人化防止 ノウハウを蓄積・共有するメリットのひとつとして、特定の従業員のみが知る情報が存在している「知識の属人化」を防止できることが挙げられます。 ノウハウが社内で共有されていれば、誰でも同じ業務ができるようになります。そのため、ベテラン従業員の離職によってノウハウが失われたり、経験豊富な従業員に業務負担が偏ったりする事態を防げるのです。 このように、ノウハウの蓄積・共有によって知識の属人化が解消されれば、業務を円滑に進められるようになります。 業務効率の向上 業務効率の向上も、ノウハウの蓄積・共有によって得られるメリットと言えます。 社内でノウハウが共有されていると作業方法を簡単に確認できるようになります。そのため、「同じ質問に何度も対応する」「作業のやり方が分からず一から調べる」などの時間を削減でき、作業を効率的に進められるのです。 このように、業務が滞るのを防いで効率的に作業ができるようにするには、ノウハウを蓄積・共有できる環境が必須です。そこで、「ナレカン」のように誰でも簡単にノウハウを蓄積できるツールを使うと、情報を共有しやすくなります。 社内の財産になる ノウハウを蓄積・共有するメリットの中には、社内の財産になる点もあります。 これから行う業務に関する過去の成功事例・失敗事例の情報があれば、それぞれの内容を参考に最適なアプローチで取り組めます。 実際の経験から得られる知識や技術は、属人化しやすい傾向にあります。したがって、ノウハウを社内の財産として蓄積し、業務に生かせる環境をつくることが大切です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】身につけたノウハウの蓄積・共有におすすめのツール 以下では、身につけたノウハウの蓄積・共有におすすめのツールをご紹介します。 従業員のノウハウは正しく管理しておかないと失われてしまい、属人化を加速させる要因になってしまいます。そのため、業務で得られたノウハウは各従業員が個別に管理するのではなく、社内で共有する体制づくりが必要です。 そこで、「ノウハウの蓄積・共有に役立つITツール」を導入すれば、情報を一か所に集めることが可能なので、口頭やメモでの情報共有で起こりうる後から情報を探すのに時間がかかることを防げます。 結論、ノウハウの情報を適切に管理し、蓄積・共有するには社内の情報に、即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは社内のノウハウを一括管理できるうえ、「超高精度な検索機能」で添付ファイル内や画像内もキーワード検索できます。そのため、情報の探索を最適化した労働環境を提供するのです。 最も簡単にノウハウの蓄積・共有ができるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウの意味と類義語のまとめ これまで、ノウハウの意味と類義語との違いを中心に解説しました。 ビジネスにおけるノウハウは「技術的な知識」という意味で使われ、スキルやナレッジとは異なる意味を持っています。個人が持つノウハウの共有を進めれば、知識の属人化を防ぎながら円滑に業務を遂行できます。 しかし、共有されたノウハウが社内に分散していると従業員が必要な情報をすぐに見つけるのが困難になり、スムーズな業務進行の妨げになります。そのため、「情報の蓄積や共有、情報の検索性に優れたITツール」が必要なのです。 結論、ノウハウを適切に管理・活用するにはファイル内検索や画像内検索にも対応した、あらゆる情報の共有に最適なツール「ナレカン」一択と言えます。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」で社内のノウハウ共有を活性化させ、業務を滞りなく進めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年12月05日DokuWiki(ドクウィキ) とは?使い方や料金・評判まで紹介昨今では、無料で手軽に社内用Webページを作成する手段として、オープンソースのWikiソフトウェアが多く活用されています。たとえば、世界中で使われている「DokuWiki(ドクウィキ)」も社内Wikiツールのひとつです。 DokuWikiは、閲覧者が自由にページを編集できるので、社内情報の蓄積に役立ちます。しかし、「DokuWikiの使い方がわからず、導入するか迷っている」という方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、DokuWikiの使い方や料金・評判を中心にご紹介します。 Dokuwikiの基本機能や使い方を知りたい Dokuwikiの評判や注意点を参考にして、導入を検討したい Dokuwikiよりも簡単に社内wikiの作成・運用ができるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、DokuWikiの活用方法が分かり、社内情報を効率的に管理できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 DokuWiki(ドクウィキ)とは1.1 DokuWikiと他の社内wikiツールとの違い1.2 DokuWikiの特徴1.3 DokuWikiの機能2 DokuWiki(ドクウィキ)の使い方2.1 (1)ページを作る2.2 (2)ページ名を日本語にする2.3 (3)Wikiを拡張する3 DokuWiki(ドクウィキ)の注意点4 DokuWiki(ドクウィキ)の評判4.1 DokuWikiの良い口コミ・評判4.2 DokuWikiの改善点に関する口コミ・評判5 Dokuwikiよりも簡単に社内wikiの作成・運用ができるツール5.1 あらゆる情報を一元管理して高精度検索ができる「ナレカン」6 DokuWiki(ドクウィキ)の使い方や料金・評判まとめ DokuWiki(ドクウィキ)とは 以下では、DokuWikiと他ツールの違いや、DokuWikiの特徴・機能についてご紹介します。DokuWikiの導入を検討している方は必見です。 DokuWikiと他の社内wikiツールとの違い 引用:DokuWiki|公式ホームページ DokuWikiとは、データベースを必要とせず、汎用性の高いオープンソースのWikiソフトウェアです。多種の拡張機能が備わっており、社内Wikiをはじめとした幅広い活用方法があります。 DokuWikiと他社内wikiツールとの違いは、以下の4点が挙げられます。 データベースやアプリのダウンロードが必要ない サイト内や複数ページの全文検索ができる 「誰がどのような編集をしたか」といったことが分かる オープンソースのソフトウェアなため、無料で使える DokuWikiは専用のアプリではなく、ブラウザから使用できるため、導入に手間がかかりません。また、変更を加えた編集者が明確になっているため、記載された情報の中に不明点があった場合、すぐに編集者に確かめられます。 DokuWikiの特徴 引用:DokuWiki|メイン画面 DokuWikiの特徴は、大きく分けて2つあります。 1つ目は、豊富な機能があることです。DokuWikiには、多くの拡張機能があり、レイアウトやテーマも好きなように変更できます。したがって、自社の環境に合わせて自由に社内Wikiを作成可能なのです。 2つ目は、情報を安全に管理できることです。DokuWikiは、アクセス制御リストを作成してページの閲覧者を制限する機能があります。そのため、社外秘や顧客の情報を扱う企業の利用にも適しており、社内情報を安全に集約できます。 DokuWikiの機能 DokuWikiの機能は、以下の3つがあります。 Wikiページ 情報を残せるページを作成・編集する機能です。 テンプレート ページのレイアウトを変更可能な機能です。現時点で190種類以上のテンプレートが利用可能です。 プラグイン DokuWikiのオリジナルのコードを変更せずに、機能を拡張できる機能です。現時点で1400種類以上のコードが利用可能です。 以上の機能により、社内Wikiを自社にあった形にカスタマイズして活用できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ DokuWiki(ドクウィキ)の使い方 以下では、DokuWikiの使い方を解説します。以下の使用方法を押さえ、自社での活用イメージを深めましょう。 (1)ページを作る 引用:DokuWiki|編集画面 以下の手順で、Wikiの中核となるページを作成できます。 存在するページのURLを書き換えて、存在しないページ(後の新規ページ)のリンクを作成をする 作成したリンクにとび、画面左うえの[文書の作成]ボタンをクリックする 新規ページが作成されるのでタイトルを記述・記事作成をする 以上は、一般的に推奨されている新規ページの作成方法なので、代替方法を知りたい方は、ページのライフサイクルをご確認ください。 参照:DokuWiki|ページの作成 (2)ページ名を日本語にする まずは、インストール画面を表示します。 次に、画面右上にある「Choose your language:」を「Ja」に変更すると、ページの言語を 日本語に設定できます。 引用:DokuWikiのインストール|日本語化 (3)Wikiを拡張する プラグインをインストールする場合は、以下のプラグイン管理画面に移動します。 はじめに、Wiki上で全ての権限を持つ「スーパーユーザー」としてログインし、[管理]をクリックし、[プラグイン管理]を選択します。 引用:DokuWiki|Plugin Manager プラグイン リスト表示されているのは、既に導入済みのプラグインです。 左端のチェックボックスから有効・無効を選択でき、[delete]をクリックすると削除も可能です。ただし、薄赤色で塗りつぶされているプラグインは無効化や削除はできません。 また、新規プラグインをインストールするには、まずプラグインページから欲しいプラグインを選び、詳細を開きます。そして、表示されたページのURLをコピーし、プラグイン管理画面にあるURL記入欄にペーストして[ダウンロード]をクリックします。 引用:DokuWiki|プラグイン プラグインをダウンロードしたら、[インストール]をクリックすれば終了です。ただし、そのときにWebサーバーがDokuWikiの「lib/plugin」ディレクトリへの書き込み権限を持っている必要があります。 そのため、プラグインのインストールに失敗した場合は、ファイルの書き込み権限を設定するか、手動でダウンロードして「lib/plugin」に展開する必要があります。許可設定の方法は、ファイル権限の設定ページを参照しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ DokuWiki(ドクウィキ)の注意点 DokuWikiの注意点は以下の2つがあります。 十分なサポートを受けられない DokuWikは、個人的なサポートはできないことを明らかにしているため、トラブルや緊急で確認したいことがある場合でも、十分なサポートを受けることができません。 参考:DokuWiki|サポートを受ける方法 操作が難しい テンプレートはあるものの、コードを使ってwikiを作成する必要があるため、初心者には難しいです。そのため、ITリテラシーが低い社員が使いこなせず、業務が属人化する恐れがあります。 以上のように、DokuWikiは無料で社内wikiを作れますが、十分なサポートが受けられず、操作が難しい点に注意する必要があります。そこで、「ナレカン」のような、手厚いサポートを受けられ、誰でも簡単に操作できる情報共有ツールを導入すれば、社内wikiの作成が簡単になり、運用もスムーズです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ DokuWiki(ドクウィキ)の評判 ここでは、DokuWikiを導入したユーザーの評判をご紹介します。自社への導入を検討するときは、実際にDokuWikiを利用しているユーザーの声を参考にしましょう。 DokuWikiの良い口コミ・評判 ユーザーの良い口コミとして「マークダウン式で書ける」や「自動更新ができる」ことが挙げられます。 Markdownで書けるWikiで #DokuWiki がいいかんじ🤗PHPのオンラインマニュアルもDokuWikiで作られていると知って、少し驚きました!DokuWikiを利用しているサイト、利用例 [DokuWikiで情報発信]https://t.co/gBAmchgBw2— Saga Site (@sagasite_info) October 3, 2025 あれ、Visual Studio Code の拡張「Markdown All in One」、目次の作成が出来るのは知っていましたが、自動で更新されるの…。すごすぎる。Dokuwiki や自作スニペットアプリを活用してメモを管理してきましたが、VSC があれば、テキストベースでさくさく書ける上、GitHub で管理→バックアップ完備。— 安曇野レイ (@Web_akira) September 15, 2023 DokuWikiの改善点に関する口コミ・評判 DokuWikiの改善点に関する口コミとして、コードの記述が未経験のユーザーが「使用が難しい」というものが挙げられます。 DokuWiki難しすぎるだろ。?: にたどり着くまでにめっちゃ時間かかった。 pic.twitter.com/O371hpT6ho— 琴音ふぁみ⧸🍊 (@fami_kotone) March 18, 2025 dokuwikiはローカルで記事やらを管理できるから、そこがやりたいことに適していたんだけど、コーディングできない自分には色々難しいことが多かったNotionはクラウド?だから自分の日記用(外部秘匿)としては、要件満たしてないけど、中々面白そう— 社外人 一生暮らせるだけの100円big当たってくれ (@Kame_akatori) March 13, 2021 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Dokuwikiよりも簡単に社内wikiの作成・運用ができるツール 以下では、Dokuwikiよりも簡単に社内wikiの作成・運用ができるツールをご紹介します。 Dokuwikiは無料で社内wikiを作成できますが、操作が複雑なため、ITリテラシーが低い社員が使いこなせず、形骸化してしまう恐れがあります。そこで、「直感的にノウハウを集約できるツール」を選べば、誰でも簡単に社内wikiを運用できるようになるため、業務の属人化を防げます。 とくに、社内マニュアルやノウハウを誰でも簡単に共有できると、業務がスムーズに進みます。ただし、目的の情報をすぐに見つけられなければ、あらゆる情報を社内wikiにまとめても、ナレッジとして活用されません。 結論、社内wikiの作成・運用に最適なのは、あらゆる情報をまとめられ、充実した検索機能ですぐに情報が見つかるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「社内お知らせ」を活用すれば、社員全員に共有しておきたい連絡事項をニュースサイトのようにホーム画面に表示できます。 また、記事上のテキストのほか、ファイル・画像内検索も可能なので、蓄積されたナレッジから目的の情報を簡単に見つけられるのです。 あらゆる情報を一元管理して高精度検索ができる「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード <ナレカンで社内wikiを作成した例> ナレカンの社内お知らせを活用すれば、社内で共有しておきたいことがホーム画面に分かりやすく表示されるため、お知らせされた情報を見逃す心配がありません。 また、詳細を確認したいものは、クリックして以下の画像のように内容を参照できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ DokuWiki(ドクウィキ)の使い方や料金・評判まとめ これまで、DokuWikiの使い方や料金・評判を中心にご紹介しました。 DokuWikiは、豊富な拡張機能を揃えたカスタマイズ性の高いWikiソフトウェアです。しかし、自社に合った社内Wikiに情報を蓄積できる一方で、コードや記法に疎い従業員にとっては難しく、社内に浸透するのに時間がかかります。 また、欲しい情報がすぐに見つからないと、情報の共有にも手間がかかります。そのため「充実した検索機能があり、社員のITスキルに関係なく、情報を共有・管理ができるツール」を活用しましょう。 したがって、社内Wikiに最適なのは、あらゆる情報を自社のスタイルに合わせてまとめられ、充実した機能で欲しい情報が素早く見つかるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を利用して、社内Wikiを利用しやすくし、社内情報を効率よく管理しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【初心者向け】PukiWikiとは?使い方や料金・評判まで紹介続きを読む
2025年12月05日DokuWiki(ドクウィキ) とは?使い方や料金・評判まで紹介昨今では、無料で手軽に社内用Webページを作成する手段として、オープンソースのWikiソフトウェアが多く活用されています。たとえば、世界中で使われている「DokuWiki(ドクウィキ)」も社内Wikiツールのひとつです。 DokuWikiは、閲覧者が自由にページを編集できるので、社内情報の蓄積に役立ちます。しかし、「DokuWikiの使い方がわからず、導入するか迷っている」という方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、DokuWikiの使い方や料金・評判を中心にご紹介します。 Dokuwikiの基本機能や使い方を知りたい Dokuwikiの評判や注意点を参考にして、導入を検討したい Dokuwikiよりも簡単に社内wikiの作成・運用ができるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、DokuWikiの活用方法が分かり、社内情報を効率的に管理できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 DokuWiki(ドクウィキ)とは1.1 DokuWikiと他の社内wikiツールとの違い1.2 DokuWikiの特徴1.3 DokuWikiの機能2 DokuWiki(ドクウィキ)の使い方2.1 (1)ページを作る2.2 (2)ページ名を日本語にする2.3 (3)Wikiを拡張する3 DokuWiki(ドクウィキ)の注意点4 DokuWiki(ドクウィキ)の評判4.1 DokuWikiの良い口コミ・評判4.2 DokuWikiの改善点に関する口コミ・評判5 Dokuwikiよりも簡単に社内wikiの作成・運用ができるツール5.1 あらゆる情報を一元管理して高精度検索ができる「ナレカン」6 DokuWiki(ドクウィキ)の使い方や料金・評判まとめ DokuWiki(ドクウィキ)とは 以下では、DokuWikiと他ツールの違いや、DokuWikiの特徴・機能についてご紹介します。DokuWikiの導入を検討している方は必見です。 DokuWikiと他の社内wikiツールとの違い 引用:DokuWiki|公式ホームページ DokuWikiとは、データベースを必要とせず、汎用性の高いオープンソースのWikiソフトウェアです。多種の拡張機能が備わっており、社内Wikiをはじめとした幅広い活用方法があります。 DokuWikiと他社内wikiツールとの違いは、以下の4点が挙げられます。 データベースやアプリのダウンロードが必要ない サイト内や複数ページの全文検索ができる 「誰がどのような編集をしたか」といったことが分かる オープンソースのソフトウェアなため、無料で使える DokuWikiは専用のアプリではなく、ブラウザから使用できるため、導入に手間がかかりません。また、変更を加えた編集者が明確になっているため、記載された情報の中に不明点があった場合、すぐに編集者に確かめられます。 DokuWikiの特徴 引用:DokuWiki|メイン画面 DokuWikiの特徴は、大きく分けて2つあります。 1つ目は、豊富な機能があることです。DokuWikiには、多くの拡張機能があり、レイアウトやテーマも好きなように変更できます。したがって、自社の環境に合わせて自由に社内Wikiを作成可能なのです。 2つ目は、情報を安全に管理できることです。DokuWikiは、アクセス制御リストを作成してページの閲覧者を制限する機能があります。そのため、社外秘や顧客の情報を扱う企業の利用にも適しており、社内情報を安全に集約できます。 DokuWikiの機能 DokuWikiの機能は、以下の3つがあります。 Wikiページ 情報を残せるページを作成・編集する機能です。 テンプレート ページのレイアウトを変更可能な機能です。現時点で190種類以上のテンプレートが利用可能です。 プラグイン DokuWikiのオリジナルのコードを変更せずに、機能を拡張できる機能です。現時点で1400種類以上のコードが利用可能です。 以上の機能により、社内Wikiを自社にあった形にカスタマイズして活用できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ DokuWiki(ドクウィキ)の使い方 以下では、DokuWikiの使い方を解説します。以下の使用方法を押さえ、自社での活用イメージを深めましょう。 (1)ページを作る 引用:DokuWiki|編集画面 以下の手順で、Wikiの中核となるページを作成できます。 存在するページのURLを書き換えて、存在しないページ(後の新規ページ)のリンクを作成をする 作成したリンクにとび、画面左うえの[文書の作成]ボタンをクリックする 新規ページが作成されるのでタイトルを記述・記事作成をする 以上は、一般的に推奨されている新規ページの作成方法なので、代替方法を知りたい方は、ページのライフサイクルをご確認ください。 参照:DokuWiki|ページの作成 (2)ページ名を日本語にする まずは、インストール画面を表示します。 次に、画面右上にある「Choose your language:」を「Ja」に変更すると、ページの言語を 日本語に設定できます。 引用:DokuWikiのインストール|日本語化 (3)Wikiを拡張する プラグインをインストールする場合は、以下のプラグイン管理画面に移動します。 はじめに、Wiki上で全ての権限を持つ「スーパーユーザー」としてログインし、[管理]をクリックし、[プラグイン管理]を選択します。 引用:DokuWiki|Plugin Manager プラグイン リスト表示されているのは、既に導入済みのプラグインです。 左端のチェックボックスから有効・無効を選択でき、[delete]をクリックすると削除も可能です。ただし、薄赤色で塗りつぶされているプラグインは無効化や削除はできません。 また、新規プラグインをインストールするには、まずプラグインページから欲しいプラグインを選び、詳細を開きます。そして、表示されたページのURLをコピーし、プラグイン管理画面にあるURL記入欄にペーストして[ダウンロード]をクリックします。 引用:DokuWiki|プラグイン プラグインをダウンロードしたら、[インストール]をクリックすれば終了です。ただし、そのときにWebサーバーがDokuWikiの「lib/plugin」ディレクトリへの書き込み権限を持っている必要があります。 そのため、プラグインのインストールに失敗した場合は、ファイルの書き込み権限を設定するか、手動でダウンロードして「lib/plugin」に展開する必要があります。許可設定の方法は、ファイル権限の設定ページを参照しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ DokuWiki(ドクウィキ)の注意点 DokuWikiの注意点は以下の2つがあります。 十分なサポートを受けられない DokuWikは、個人的なサポートはできないことを明らかにしているため、トラブルや緊急で確認したいことがある場合でも、十分なサポートを受けることができません。 参考:DokuWiki|サポートを受ける方法 操作が難しい テンプレートはあるものの、コードを使ってwikiを作成する必要があるため、初心者には難しいです。そのため、ITリテラシーが低い社員が使いこなせず、業務が属人化する恐れがあります。 以上のように、DokuWikiは無料で社内wikiを作れますが、十分なサポートが受けられず、操作が難しい点に注意する必要があります。そこで、「ナレカン」のような、手厚いサポートを受けられ、誰でも簡単に操作できる情報共有ツールを導入すれば、社内wikiの作成が簡単になり、運用もスムーズです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ DokuWiki(ドクウィキ)の評判 ここでは、DokuWikiを導入したユーザーの評判をご紹介します。自社への導入を検討するときは、実際にDokuWikiを利用しているユーザーの声を参考にしましょう。 DokuWikiの良い口コミ・評判 ユーザーの良い口コミとして「マークダウン式で書ける」や「自動更新ができる」ことが挙げられます。 Markdownで書けるWikiで #DokuWiki がいいかんじ🤗PHPのオンラインマニュアルもDokuWikiで作られていると知って、少し驚きました!DokuWikiを利用しているサイト、利用例 [DokuWikiで情報発信]https://t.co/gBAmchgBw2— Saga Site (@sagasite_info) October 3, 2025 あれ、Visual Studio Code の拡張「Markdown All in One」、目次の作成が出来るのは知っていましたが、自動で更新されるの…。すごすぎる。Dokuwiki や自作スニペットアプリを活用してメモを管理してきましたが、VSC があれば、テキストベースでさくさく書ける上、GitHub で管理→バックアップ完備。— 安曇野レイ (@Web_akira) September 15, 2023 DokuWikiの改善点に関する口コミ・評判 DokuWikiの改善点に関する口コミとして、コードの記述が未経験のユーザーが「使用が難しい」というものが挙げられます。 DokuWiki難しすぎるだろ。?: にたどり着くまでにめっちゃ時間かかった。 pic.twitter.com/O371hpT6ho— 琴音ふぁみ⧸🍊 (@fami_kotone) March 18, 2025 dokuwikiはローカルで記事やらを管理できるから、そこがやりたいことに適していたんだけど、コーディングできない自分には色々難しいことが多かったNotionはクラウド?だから自分の日記用(外部秘匿)としては、要件満たしてないけど、中々面白そう— 社外人 一生暮らせるだけの100円big当たってくれ (@Kame_akatori) March 13, 2021 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Dokuwikiよりも簡単に社内wikiの作成・運用ができるツール 以下では、Dokuwikiよりも簡単に社内wikiの作成・運用ができるツールをご紹介します。 Dokuwikiは無料で社内wikiを作成できますが、操作が複雑なため、ITリテラシーが低い社員が使いこなせず、形骸化してしまう恐れがあります。そこで、「直感的にノウハウを集約できるツール」を選べば、誰でも簡単に社内wikiを運用できるようになるため、業務の属人化を防げます。 とくに、社内マニュアルやノウハウを誰でも簡単に共有できると、業務がスムーズに進みます。ただし、目的の情報をすぐに見つけられなければ、あらゆる情報を社内wikiにまとめても、ナレッジとして活用されません。 結論、社内wikiの作成・運用に最適なのは、あらゆる情報をまとめられ、充実した検索機能ですぐに情報が見つかるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「社内お知らせ」を活用すれば、社員全員に共有しておきたい連絡事項をニュースサイトのようにホーム画面に表示できます。 また、記事上のテキストのほか、ファイル・画像内検索も可能なので、蓄積されたナレッジから目的の情報を簡単に見つけられるのです。 あらゆる情報を一元管理して高精度検索ができる「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード <ナレカンで社内wikiを作成した例> ナレカンの社内お知らせを活用すれば、社内で共有しておきたいことがホーム画面に分かりやすく表示されるため、お知らせされた情報を見逃す心配がありません。 また、詳細を確認したいものは、クリックして以下の画像のように内容を参照できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ DokuWiki(ドクウィキ)の使い方や料金・評判まとめ これまで、DokuWikiの使い方や料金・評判を中心にご紹介しました。 DokuWikiは、豊富な拡張機能を揃えたカスタマイズ性の高いWikiソフトウェアです。しかし、自社に合った社内Wikiに情報を蓄積できる一方で、コードや記法に疎い従業員にとっては難しく、社内に浸透するのに時間がかかります。 また、欲しい情報がすぐに見つからないと、情報の共有にも手間がかかります。そのため「充実した検索機能があり、社員のITスキルに関係なく、情報を共有・管理ができるツール」を活用しましょう。 したがって、社内Wikiに最適なのは、あらゆる情報を自社のスタイルに合わせてまとめられ、充実した機能で欲しい情報が素早く見つかるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を利用して、社内Wikiを利用しやすくし、社内情報を効率よく管理しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【初心者向け】PukiWikiとは?使い方や料金・評判まで紹介続きを読む -
 2025年07月08日【非IT企業必見】見える化するべき4つの情報とおすすめシステム6選近年、働き手不足による社員の過重労働は解決すべき重要な課題となっています。そこで企業は、業務プロセスや社員の働く実態の「見える化」によって、不必要な業務や過剰な残業が発生していないかを把握し、改善策を講じる必要があるのです。 ただし、業務の見える化を手作業で実施するのは、通常業務がひっ迫する要因になるので、システムの導入がおすすめです。しかし、「どのような要素を見える化したらよいか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、見える化するべき要素とおすすめシステムを6選ご紹介します。 自社の課題にマッチしたシステムを導入し、業務を効率化したい 不必要な業務を抽出して、コスト削減を図りたい 見える化によって、社員の労働負担を減らしたい という方はこの記事を参考にすると、見える化するべき要素や自社の課題にマッチしたシステムも導入できるので、不必要なコストの軽減につなげられるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 業務の見える化とは2 見える化にシステムを導入するメリットとは3 見える化するべき情報とは4 業務の見える化におすすめのシステム6選4.1 【ナレカン】業務ノウハウを簡単に共有できるシステム4.2 【Stock】65歳以上のメンバーも操作できるシステム4.3 【LANSCOPE】サイバーセキュリティに特化したシステム4.4 【kaonavi】記憶頼りなマネジメントからの脱却を実現4.5 【backlog】あらゆるチームのプロジェクトを一元管理4.6 【TimeCrowd】業務時間の見える化に特化5 業務の見える化におすすめのシステム6選の比較表6 業務を見える化するシステムを導入する注意点とは6.1 (1)全社で浸透する操作性か6.2 (2)セキュリティは安全か7 見える化するべき情報とおすすめシステム6選まとめ 業務の見える化とは 業務の見える化とは、業務フローやスケジュール、進捗などを可視化して一目で把握できる環境を整えることです。 業務の見える化ができていなければ、不必要な業務プロセスに時間や労力を費やし続けることになり、各社員の負担やストレスが増加します。そのため、業務のムダを明らかにして、「不必要な業務や工数の抽出・削減」につなげましょう。 また、社内のナレッジを適切に管理すれば、ノウハウが見える化するので、情報を効果的に活用できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 見える化にシステムを導入するメリットとは 業務の「見える化」には、システムを導入して実践する方法が一般的です。 日々増加する情報を手作業で処理するのは、人手や時間的コストがかかるうえ、人為的ミスの要因となります。そこで、システムを活用すると、業務フローが簡単に可視化され、運用フローの改善が効率化するのです。 また、企業活動において「見える化」するべき要素は数多く存在し、日々情報は更新されます。そこで、システムを使うとシステム内に情報が残るため、常に運用フローを最適化できているかの振り返りも可能となるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 見える化するべき情報とは ここでは、業務フローのなかで見える化するべき4つの情報を紹介します。 業務プロセス 業務プロセスの見える化により、不必要な作業が浮き彫りになるので、業務負担やリソースが削減できます。さらに、業務プロセスをチーム内で共有すると、業務の属人化や担当者不在による未対応も防げます。 顧客情報 商品やサービスの購入履歴や問い合わせ履歴を見える化すると、顧客一人ひとりへの最適なアプローチが可能になります。 ナレッジ 社内に分散するナレッジは蓄積し、共有することでマニュアルとして活用できます。また、マニュアルとして活用すれば、教育コストの削減になるだけでなく、メンバーのスキルや業務の質を高めることにも繋がります。 勤怠状況 社員の勤怠状況の見える化によって、残業の常態化や休日出勤が発生していないかの管理が可能になります。そのため、長時間労働といった労務リスクの回避や職場環境の改善が見込めるのです。 以上の要素を見える化すると、業界職種問わず業務プロセスの効率化ができるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 業務の見える化におすすめのシステム6選 以下では、業務の見える化におすすめのシステムを6選紹介します。 業務内容が可視化されることで、無駄や非効率な手順が明らかになり、改善に役立てられます。とくに、属人化しがちな業務や、暗黙知として個人にとどまっていたノウハウも、ナレッジ管理ツールを使えば全社で共有・蓄積が可能になるので、業務効率の向上が見込めるのです。 ただし、ナレッジを蓄積してもスムーズに検索できなければ、ナレッジを十分に活用できません。そのため、高精度の検索機能が備わったツールを選びましょう。 結論、業務の見える化には、属人化しやすいナレッジを引き出して蓄積できるうえ、超高精度の検索機能が実装されたナレッジ管理ツール「ナレカン」一択です。 ナレカンには、社内知恵袋のように使える質問機能があるので、「今不足しているナレッジ」や「現場ニーズ」を把握でき、“誰かが知っている情報”を引き出しやすくなります。また、蓄積したナレッジは“ヒット率100%”の検索機能で誰もが活用できる状態で管理できるのです。 【ナレカン】業務ノウハウを簡単に共有できるシステム 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Stock】65歳以上のメンバーも操作できるシステム Stockは、即日使える情報共有ツールです。顧客情報や業務マニュアルの共有・管理に活用することで、業務が見える化し、進捗報告を簡略化できます。 とくに、「Stock」には、「ノート」とノートに紐づけられる「メッセージ」「タスク機能」があるので、複数の案件に関するやりとりを並行しても情報が入り乱れません。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 <Stockをおすすめするポイント> ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 <Stockの口コミ・評判> 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ(栃木SC) 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 <Stockの料金> フリープラン :無料 ビジネスプラン :500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数:5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【LANSCOPE】サイバーセキュリティに特化したシステム LANSCOPEの特徴 サイバーセキュリティに特化したシステム 社員の業務実態を見える化し、情報漏洩や外的からの攻撃を防げるサイバーセキュリティに特化しています。 社内の機密情報や個人情報の取り扱い状況を管理できる 社員のPCの利用状況だけでなく、「アプリの利用」「Webサイトの閲覧/アップロード/書き込み」「ファイル操作」などの操作ログを記録します。 LANSCOPEの機能・使用感 充実したPC管理機能 充実したPC管理機能で、資産管理や記録メディアの制御、操作ログを見える化します。そのため、情報漏洩や改ざんのリスクを最小限に抑えたいという企業も安心して利用できます。 モバイル管理機能 モバイルデバイス管理機能で、従業員が使用している端末の利用状況を把握できるなど、社員の私物化を防げる点もポイントです。 LANSCOPEの注意点 自社の課題と機能性の親和性を見定める必要あり 自社の課題に応じて必要な機能だけを追加できますが、その分コストがかかるので、課題と機能性の親和性を見定める必要があります。 機能が豊富な分、使いこなすのが難しい 利用しているユーザーからは「機能が豊富だが使いこなすのが難しい」という声があります。(参考:ITreview) LANSCOPEの料金体系 詳細な料金は問い合わせが必要です。 LANSCOPEの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【kaonavi】記憶頼りなマネジメントからの脱却を実現 kaonaviの特徴 社員の情報の一元管理機能 社員情報の一元管理によって、スキルに基づいた人材配置・育成の最適化だけでなく、搭載されたアンケート機能で社員のコンディション管理も可能になります。 充実したサポート体制 課題ごとのセミナーや専任スタッフによる支援といったサポート体制も充実しています。 kaonaviの機能・使用感 社員タイプ分析機能 個人の特性を性格診断によって分類し、関わり方や成長するためのアドバイスも記載されているので、円滑なコミュニケーションを促進します。 スキルの可視化・管理機能 スキル関連のあらゆる情報を一元化し、スキルマップを作成できるので、社員の資格取得情報などを簡単に可視化できます。 kaonaviの注意点 費用対効果の検討が必須 人事業務に特化したシステムであり、業界によっては効果が薄い可能性もあるので費用対効果の検討が必須です。 データの深い分析をしたいときは物足りない 利用しているユーザーからは「人材分析機能はあるものの、深い分析やビジュアライズに物足りなさを感じる。導入後に「形だけの人材管理ツール」になっている気がする」という声があります。(参考:ITreview) kaonaviの料金体系 詳細な料金は問い合わせが必要です。 kaonaviの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【backlog】あらゆるチームのプロジェクトを一元管理 backlogの特徴 課題の進捗管理を見える化できる プロジェクトにおける課題はカンバンボード上で「カード」として管理され、進捗状況に応じて、未対応・処理中・処理済み・完了の4つのフォルダに振り分けられます。 課題の担当者や期限を細かく設定できる 課題の担当者や期限、優先度は個別に設定も可能なので、対応漏れや二重対応を防ぎます。 backlogの機能・使用感 ガントチャート機能 プロジェクトを見える化でき、直感的に全体像を把握したい場合に便利です。 カンバンボード機能 課題のカードをドラッグ&ドロップすることで課題の状態を変更でき、リアルタイムで更新できます。 backlogの注意点 やりとりが流れないように管理が必要 課題はテーマごとに分けて管理しなければ、ほかの課題とまぎれてしまい課題を確認するのに手間がかかるので注意が必要です。 backlogの料金 スタータープラン:2,970円/月(月払い) スタンダードプラン:17,600円/月(月払い) プレミアムプラン:29,700円/月(月払い) プラチナプラン:82,500円/月(月払い) それぞれ30日間無料で利用可能です。 backlogの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【TimeCrowd】業務時間の見える化に特化 TimeCrowdの特徴 シンプルな時間管理ツール タスクの時間を記録して見える化することに特化したツールで、簡単に操作ができます。 メンバーの動きも見える化 チームメンバーの時間の記録を見える化し共有できるので、業務のブラックボックス化を防ぎます。 TimeCrowdの機能・使用感 メンバー機能 稼働しているメンバーをリアルタイムで確認出来るため、チームの状況を見える化したい場合に便利です。 単価計算機能 チーム、ユーザーごとに単価を設定でき、その月の金額やタスクごとの金額を確認したい場合に適しています。 TimeCrowdの注意点 プランごとに価格や搭載機能が異なる プランによって、料金設定、無料お試しの有無、機能性が異なるので注意する必要があります。 チームへの招待の工数が多い 利用しているユーザーからは「チームへの招待の仕方が、チームごとにURLを送ってそこから入ってもらう、という形なので、 複数招待する場合に、面倒に感じている。」という声があります。(参考:ITreview) TimeCrowdの料金体系 詳細な料金については問い合わせが必要です。 TimeCrowdの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 業務の見える化におすすめのシステム6選の比較表 以下は、業務の見える化におすすめのシステム6選の比較表です。 ナレカン【一番おすすめ】 Stock【おすすめ】 LANSCOPE kaonavi backlog TimeCrowd 特徴 業務ノウハウを簡単に共有できるシステム 65歳以上のメンバーも操作できるシステム サイバーセキュリティに特化したシステム 記憶頼りなマネジメントからの脱却を実現 あらゆるチームのプロジェクトを一元管理 業務時間の見える化に特化 シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単(大手~中堅企業向け) シンプルで簡単(中小規模の企業向け) 多機能 多機能 多機能 多機能 注意点 法人利用が前提なので、個人利用は不可 5名以上での利用が前提 自社の課題と機能性の親和性を見定める必要がある 費用対効果の検討が必須である やりとりが流れないように管理が必要である プランごとに価格や搭載機能が異なる 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料 ・有料プランでも1人あたり500円/月〜 ・無料プランなし ・有料プランは問い合わせが必要 ・無料プランなし ・有料プランは問い合わせが必要 ・無料プランあり(30日間) ・有料プランは2,970円/月〜 ・無料プランなし ・有料プランは問い合わせが必要 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「LANSCOPE」の詳細はこちら 「kaonavi」の詳細はこちら 「backlog」の詳細はこちら 「TimeCrowd」の詳細はこちら また、チームで業務に取り組むのであれば、各々のタスクを把握しておくことはもちろん、必要なときにすぐにやりとりできることが大切です。そのため、「タスク管理」だけでなく「メッセージ」機能を兼ね備えたシステムを選定しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 業務を見える化するシステムを導入する注意点とは 以下では、業務を見える化するシステムを導入するときの注意点を解説していきます。担当者の方は、システムを導入する際に以下の点に注意しましょう。 (1)全社で浸透する操作性か 1つ目は、全社で浸透する操作性かという点です。 業務効率化を目的にしているにも関わらず、社内のITリテラシーを考慮せずに「操作が難しいシステム」や「自社に見合っていない多機能なツール」を導入しては、社内に浸透しないリスクがあります。 社内にITの苦手な社員がいる場合、操作の難しいシステムを導入すると、教育コストがかかってしまいます。導入してすぐに全メンバーが使えなければ業務の見える化の意味がありません。 また、多機能・高機能なシステムでは、自社では不要な機能がついていて費用対効果が高くなってしまう場合もあるため、必要な機能が過不足ないツールを導入しましょう。 (2)セキュリティは安全か 2つ目に、セキュリティは安全かという点に注意してツール選びをしましょう。 業務の見える化するシステムを導入すると、社内のセキュリティの一元管理ができ、機密データの改ざんや誤送信をはじめとする情報漏洩の防止に有効です。 たとえば、業務を可視化するシステムの中には、社員のPCの操作ログを記録することで「内部不正を抑止する」「問題発生時には操作ログから検証できる」といったセキュリティ機能を備えたツールもあります。 たとえば、「ISO27017」というクラウドサービスに特化した国際セキュリティ規格を取得している「Stock」なら、安心してビジネス上の情報を残すことができます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 見える化するべき情報とおすすめシステム6選まとめ ここまで、見える化するべき情報とおすすめシステム6選について紹介しました。 どの業界職種においても「業務プロセス・ナレッジ・顧客管理・勤怠状況」は、業務効率化を図るための見える化すべき情報だと言えます。とはいえ、情報は日々増加していくので、見える化した「情報」をアナログで管理していては、更新に時間がかかり面倒です。 そこで、システムを使って、簡単に情報を管理・共有しましょう。ただし、操作が難しいシステムでは、現場に馴染まないので「誰でも使えるシステムであるか」は大前提です。 結論、ITに不慣れでも「誰でも簡単に」情報を見える化でき、社内での活用が可能になるシステム『ナレカン』が最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って見える化した「情報」を正しく管理・共有し、業務プロセスの最適化を図りましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 管理職のためのナレッジマネジメント設計ガイド|古い手法は卒業!続きを読む
2025年07月08日【非IT企業必見】見える化するべき4つの情報とおすすめシステム6選近年、働き手不足による社員の過重労働は解決すべき重要な課題となっています。そこで企業は、業務プロセスや社員の働く実態の「見える化」によって、不必要な業務や過剰な残業が発生していないかを把握し、改善策を講じる必要があるのです。 ただし、業務の見える化を手作業で実施するのは、通常業務がひっ迫する要因になるので、システムの導入がおすすめです。しかし、「どのような要素を見える化したらよいか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、見える化するべき要素とおすすめシステムを6選ご紹介します。 自社の課題にマッチしたシステムを導入し、業務を効率化したい 不必要な業務を抽出して、コスト削減を図りたい 見える化によって、社員の労働負担を減らしたい という方はこの記事を参考にすると、見える化するべき要素や自社の課題にマッチしたシステムも導入できるので、不必要なコストの軽減につなげられるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 業務の見える化とは2 見える化にシステムを導入するメリットとは3 見える化するべき情報とは4 業務の見える化におすすめのシステム6選4.1 【ナレカン】業務ノウハウを簡単に共有できるシステム4.2 【Stock】65歳以上のメンバーも操作できるシステム4.3 【LANSCOPE】サイバーセキュリティに特化したシステム4.4 【kaonavi】記憶頼りなマネジメントからの脱却を実現4.5 【backlog】あらゆるチームのプロジェクトを一元管理4.6 【TimeCrowd】業務時間の見える化に特化5 業務の見える化におすすめのシステム6選の比較表6 業務を見える化するシステムを導入する注意点とは6.1 (1)全社で浸透する操作性か6.2 (2)セキュリティは安全か7 見える化するべき情報とおすすめシステム6選まとめ 業務の見える化とは 業務の見える化とは、業務フローやスケジュール、進捗などを可視化して一目で把握できる環境を整えることです。 業務の見える化ができていなければ、不必要な業務プロセスに時間や労力を費やし続けることになり、各社員の負担やストレスが増加します。そのため、業務のムダを明らかにして、「不必要な業務や工数の抽出・削減」につなげましょう。 また、社内のナレッジを適切に管理すれば、ノウハウが見える化するので、情報を効果的に活用できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 見える化にシステムを導入するメリットとは 業務の「見える化」には、システムを導入して実践する方法が一般的です。 日々増加する情報を手作業で処理するのは、人手や時間的コストがかかるうえ、人為的ミスの要因となります。そこで、システムを活用すると、業務フローが簡単に可視化され、運用フローの改善が効率化するのです。 また、企業活動において「見える化」するべき要素は数多く存在し、日々情報は更新されます。そこで、システムを使うとシステム内に情報が残るため、常に運用フローを最適化できているかの振り返りも可能となるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 見える化するべき情報とは ここでは、業務フローのなかで見える化するべき4つの情報を紹介します。 業務プロセス 業務プロセスの見える化により、不必要な作業が浮き彫りになるので、業務負担やリソースが削減できます。さらに、業務プロセスをチーム内で共有すると、業務の属人化や担当者不在による未対応も防げます。 顧客情報 商品やサービスの購入履歴や問い合わせ履歴を見える化すると、顧客一人ひとりへの最適なアプローチが可能になります。 ナレッジ 社内に分散するナレッジは蓄積し、共有することでマニュアルとして活用できます。また、マニュアルとして活用すれば、教育コストの削減になるだけでなく、メンバーのスキルや業務の質を高めることにも繋がります。 勤怠状況 社員の勤怠状況の見える化によって、残業の常態化や休日出勤が発生していないかの管理が可能になります。そのため、長時間労働といった労務リスクの回避や職場環境の改善が見込めるのです。 以上の要素を見える化すると、業界職種問わず業務プロセスの効率化ができるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 業務の見える化におすすめのシステム6選 以下では、業務の見える化におすすめのシステムを6選紹介します。 業務内容が可視化されることで、無駄や非効率な手順が明らかになり、改善に役立てられます。とくに、属人化しがちな業務や、暗黙知として個人にとどまっていたノウハウも、ナレッジ管理ツールを使えば全社で共有・蓄積が可能になるので、業務効率の向上が見込めるのです。 ただし、ナレッジを蓄積してもスムーズに検索できなければ、ナレッジを十分に活用できません。そのため、高精度の検索機能が備わったツールを選びましょう。 結論、業務の見える化には、属人化しやすいナレッジを引き出して蓄積できるうえ、超高精度の検索機能が実装されたナレッジ管理ツール「ナレカン」一択です。 ナレカンには、社内知恵袋のように使える質問機能があるので、「今不足しているナレッジ」や「現場ニーズ」を把握でき、“誰かが知っている情報”を引き出しやすくなります。また、蓄積したナレッジは“ヒット率100%”の検索機能で誰もが活用できる状態で管理できるのです。 【ナレカン】業務ノウハウを簡単に共有できるシステム 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Stock】65歳以上のメンバーも操作できるシステム Stockは、即日使える情報共有ツールです。顧客情報や業務マニュアルの共有・管理に活用することで、業務が見える化し、進捗報告を簡略化できます。 とくに、「Stock」には、「ノート」とノートに紐づけられる「メッセージ」「タスク機能」があるので、複数の案件に関するやりとりを並行しても情報が入り乱れません。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 <Stockをおすすめするポイント> ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 <Stockの口コミ・評判> 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ(栃木SC) 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 <Stockの料金> フリープラン :無料 ビジネスプラン :500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数:5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【LANSCOPE】サイバーセキュリティに特化したシステム LANSCOPEの特徴 サイバーセキュリティに特化したシステム 社員の業務実態を見える化し、情報漏洩や外的からの攻撃を防げるサイバーセキュリティに特化しています。 社内の機密情報や個人情報の取り扱い状況を管理できる 社員のPCの利用状況だけでなく、「アプリの利用」「Webサイトの閲覧/アップロード/書き込み」「ファイル操作」などの操作ログを記録します。 LANSCOPEの機能・使用感 充実したPC管理機能 充実したPC管理機能で、資産管理や記録メディアの制御、操作ログを見える化します。そのため、情報漏洩や改ざんのリスクを最小限に抑えたいという企業も安心して利用できます。 モバイル管理機能 モバイルデバイス管理機能で、従業員が使用している端末の利用状況を把握できるなど、社員の私物化を防げる点もポイントです。 LANSCOPEの注意点 自社の課題と機能性の親和性を見定める必要あり 自社の課題に応じて必要な機能だけを追加できますが、その分コストがかかるので、課題と機能性の親和性を見定める必要があります。 機能が豊富な分、使いこなすのが難しい 利用しているユーザーからは「機能が豊富だが使いこなすのが難しい」という声があります。(参考:ITreview) LANSCOPEの料金体系 詳細な料金は問い合わせが必要です。 LANSCOPEの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【kaonavi】記憶頼りなマネジメントからの脱却を実現 kaonaviの特徴 社員の情報の一元管理機能 社員情報の一元管理によって、スキルに基づいた人材配置・育成の最適化だけでなく、搭載されたアンケート機能で社員のコンディション管理も可能になります。 充実したサポート体制 課題ごとのセミナーや専任スタッフによる支援といったサポート体制も充実しています。 kaonaviの機能・使用感 社員タイプ分析機能 個人の特性を性格診断によって分類し、関わり方や成長するためのアドバイスも記載されているので、円滑なコミュニケーションを促進します。 スキルの可視化・管理機能 スキル関連のあらゆる情報を一元化し、スキルマップを作成できるので、社員の資格取得情報などを簡単に可視化できます。 kaonaviの注意点 費用対効果の検討が必須 人事業務に特化したシステムであり、業界によっては効果が薄い可能性もあるので費用対効果の検討が必須です。 データの深い分析をしたいときは物足りない 利用しているユーザーからは「人材分析機能はあるものの、深い分析やビジュアライズに物足りなさを感じる。導入後に「形だけの人材管理ツール」になっている気がする」という声があります。(参考:ITreview) kaonaviの料金体系 詳細な料金は問い合わせが必要です。 kaonaviの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【backlog】あらゆるチームのプロジェクトを一元管理 backlogの特徴 課題の進捗管理を見える化できる プロジェクトにおける課題はカンバンボード上で「カード」として管理され、進捗状況に応じて、未対応・処理中・処理済み・完了の4つのフォルダに振り分けられます。 課題の担当者や期限を細かく設定できる 課題の担当者や期限、優先度は個別に設定も可能なので、対応漏れや二重対応を防ぎます。 backlogの機能・使用感 ガントチャート機能 プロジェクトを見える化でき、直感的に全体像を把握したい場合に便利です。 カンバンボード機能 課題のカードをドラッグ&ドロップすることで課題の状態を変更でき、リアルタイムで更新できます。 backlogの注意点 やりとりが流れないように管理が必要 課題はテーマごとに分けて管理しなければ、ほかの課題とまぎれてしまい課題を確認するのに手間がかかるので注意が必要です。 backlogの料金 スタータープラン:2,970円/月(月払い) スタンダードプラン:17,600円/月(月払い) プレミアムプラン:29,700円/月(月払い) プラチナプラン:82,500円/月(月払い) それぞれ30日間無料で利用可能です。 backlogの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【TimeCrowd】業務時間の見える化に特化 TimeCrowdの特徴 シンプルな時間管理ツール タスクの時間を記録して見える化することに特化したツールで、簡単に操作ができます。 メンバーの動きも見える化 チームメンバーの時間の記録を見える化し共有できるので、業務のブラックボックス化を防ぎます。 TimeCrowdの機能・使用感 メンバー機能 稼働しているメンバーをリアルタイムで確認出来るため、チームの状況を見える化したい場合に便利です。 単価計算機能 チーム、ユーザーごとに単価を設定でき、その月の金額やタスクごとの金額を確認したい場合に適しています。 TimeCrowdの注意点 プランごとに価格や搭載機能が異なる プランによって、料金設定、無料お試しの有無、機能性が異なるので注意する必要があります。 チームへの招待の工数が多い 利用しているユーザーからは「チームへの招待の仕方が、チームごとにURLを送ってそこから入ってもらう、という形なので、 複数招待する場合に、面倒に感じている。」という声があります。(参考:ITreview) TimeCrowdの料金体系 詳細な料金については問い合わせが必要です。 TimeCrowdの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 業務の見える化におすすめのシステム6選の比較表 以下は、業務の見える化におすすめのシステム6選の比較表です。 ナレカン【一番おすすめ】 Stock【おすすめ】 LANSCOPE kaonavi backlog TimeCrowd 特徴 業務ノウハウを簡単に共有できるシステム 65歳以上のメンバーも操作できるシステム サイバーセキュリティに特化したシステム 記憶頼りなマネジメントからの脱却を実現 あらゆるチームのプロジェクトを一元管理 業務時間の見える化に特化 シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単(大手~中堅企業向け) シンプルで簡単(中小規模の企業向け) 多機能 多機能 多機能 多機能 注意点 法人利用が前提なので、個人利用は不可 5名以上での利用が前提 自社の課題と機能性の親和性を見定める必要がある 費用対効果の検討が必須である やりとりが流れないように管理が必要である プランごとに価格や搭載機能が異なる 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料 ・有料プランでも1人あたり500円/月〜 ・無料プランなし ・有料プランは問い合わせが必要 ・無料プランなし ・有料プランは問い合わせが必要 ・無料プランあり(30日間) ・有料プランは2,970円/月〜 ・無料プランなし ・有料プランは問い合わせが必要 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「LANSCOPE」の詳細はこちら 「kaonavi」の詳細はこちら 「backlog」の詳細はこちら 「TimeCrowd」の詳細はこちら また、チームで業務に取り組むのであれば、各々のタスクを把握しておくことはもちろん、必要なときにすぐにやりとりできることが大切です。そのため、「タスク管理」だけでなく「メッセージ」機能を兼ね備えたシステムを選定しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 業務を見える化するシステムを導入する注意点とは 以下では、業務を見える化するシステムを導入するときの注意点を解説していきます。担当者の方は、システムを導入する際に以下の点に注意しましょう。 (1)全社で浸透する操作性か 1つ目は、全社で浸透する操作性かという点です。 業務効率化を目的にしているにも関わらず、社内のITリテラシーを考慮せずに「操作が難しいシステム」や「自社に見合っていない多機能なツール」を導入しては、社内に浸透しないリスクがあります。 社内にITの苦手な社員がいる場合、操作の難しいシステムを導入すると、教育コストがかかってしまいます。導入してすぐに全メンバーが使えなければ業務の見える化の意味がありません。 また、多機能・高機能なシステムでは、自社では不要な機能がついていて費用対効果が高くなってしまう場合もあるため、必要な機能が過不足ないツールを導入しましょう。 (2)セキュリティは安全か 2つ目に、セキュリティは安全かという点に注意してツール選びをしましょう。 業務の見える化するシステムを導入すると、社内のセキュリティの一元管理ができ、機密データの改ざんや誤送信をはじめとする情報漏洩の防止に有効です。 たとえば、業務を可視化するシステムの中には、社員のPCの操作ログを記録することで「内部不正を抑止する」「問題発生時には操作ログから検証できる」といったセキュリティ機能を備えたツールもあります。 たとえば、「ISO27017」というクラウドサービスに特化した国際セキュリティ規格を取得している「Stock」なら、安心してビジネス上の情報を残すことができます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 見える化するべき情報とおすすめシステム6選まとめ ここまで、見える化するべき情報とおすすめシステム6選について紹介しました。 どの業界職種においても「業務プロセス・ナレッジ・顧客管理・勤怠状況」は、業務効率化を図るための見える化すべき情報だと言えます。とはいえ、情報は日々増加していくので、見える化した「情報」をアナログで管理していては、更新に時間がかかり面倒です。 そこで、システムを使って、簡単に情報を管理・共有しましょう。ただし、操作が難しいシステムでは、現場に馴染まないので「誰でも使えるシステムであるか」は大前提です。 結論、ITに不慣れでも「誰でも簡単に」情報を見える化でき、社内での活用が可能になるシステム『ナレカン』が最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って見える化した「情報」を正しく管理・共有し、業務プロセスの最適化を図りましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 管理職のためのナレッジマネジメント設計ガイド|古い手法は卒業!続きを読む -
 2025年09月19日Excelで業務を見える化するやり方は?メリット・デメリットも解説チーム全体でスムーズに仕事を進めるには、メンバーごとの業務内容や進捗を見える化して共有する必要があります。そこで、Excelを使って業務を見える化する企業は少なくありません。 しかし、「Excelを使って効果的に業務を見える化する方法が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、Excelで見える化するメリット・デメリットを中心にご紹介します。 メンバーの進捗がわからず、作業を円滑に薄められていない Excelで「業務の見える化」をするメリット・デメリットを知りたい 業務の見える化におすすめのツールを導入したい という方はこの記事を参考にすると、業務を見える化する最適な方法が分かり、業務進行の効率化に役立てられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 業務を見える化・可視化とは2 業務を見える化する重要性とは2.1 作業を適切に配分できる2.2 進捗を把握できる2.3 業務ノウハウを共有できる3 Excelを活用して業務の見える化をするやり方3.1 業務一覧表を作成する3.2 ガントチャートを作成する4 <ポイントあり>業務の見える化・可視化する手順4.1 (1)現状の業務内容を洗い出す4.2 (2)改善点を抽出する4.3 (3)定期的な見直しを実施する5 Excelで業務を見える化する2つのメリット5.1 (1)導入コストが低い5.2 (2)カスタマイズ性が高い6 Excelで業務を見える化する3つのデメリット6.1 (1)編集・閲覧に手間がかかる6.2 (2)Excelファイルの共有がしづらい6.3 (3)スマホやタブレットでは使いづらい7 【必見】業務の見える化に最もおすすめのツール7.1 情報を作成・管理ができ充実した検索機能がある「ナレカン」8 Excelで業務を見える化するまとめ 業務を見える化・可視化とは 業務の見える化・可視化とは、プロジェクトの全体像や進捗状況を担当者でなくても把握できるようにすることです。 メンバー全員が全体進捗を把握しておくことで、業務の問題点や課題を発見しやすくなります。その結果、進捗に遅れがでていたり対応が漏れたりしていた場合に、すぐにメンバーのフォローに回れます。 このように、業務の見える化・可視化が実現されると、メンバー内でのコミュニケーションも活性化され、業務の効率化や生産性向上につなげることができるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 業務を見える化する重要性とは ここでは、業務を見える化する重要性を紹介します。チームの作業を円滑に進めるには、以下の重要性を把握して、適切に業務を見える化しなければなりません。 作業を適切に配分できる 業務が見える化すると、メンバーへの適切な作業配分も実現します。 たとえば、プロジェクトを円滑に進めるには、業務ごとの作業量を見える化して、メンバーに適切に振り分ける必要があります。業務全体が明確になっていることで、メンバーの作業負担の偏りがなくなるのです。 その結果として、負担が大きいメンバーの作業の質が低下したり、納期に遅れてしまったりすることがなくなり、業務効率も良くなります。以上のことから、メンバーに適切に作業を配分するうえで、業務の見える化は不可欠だと言えます。 進捗を把握できる メンバーの進捗を把握できる点でも、業務の見える化は重要です。 仕事を円滑に進めるには、メンバーの進捗を共有して、チームで連携を取らなければなりません。具体的には、作業がスムーズに進んでいるメンバーと遅れているメンバーを把握して、サポートし合う体制が必要なのです。 とくに、プロジェクトチームを組む場合、メンバーの作業が1人でも遅れてしまうと、プロジェクト全体の遅延につながります。したがって、メンバー同士で助け合い、チームの足並みをそろえるためにも、業務の見える化は重要なのです。 業務ノウハウを共有できる 業務の見える化によって、ノウハウの共有が可能になります。 業務の見える化によって、マニュアルや社内wikiなどが共有されれば、一から指導する手間を軽減できるので、教育コストの軽減につながります。また、業務の属人化も防止され、「担当者でなければ対処できない」といった事態も回避できるのです。 さらに、ノウハウが共有されると、経験の有無による業務の質のばらつきを抑えられます。そのため、経験の浅いメンバーでも一定の質を保ちながら業務に取り組めるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Excelを活用して業務の見える化をするやり方 ここでは、Excelで業務を可視化する方法を2つ紹介します。どちらのやり方も進捗をまとめて管理できる点が便利です。 業務一覧表を作成する 1つ目は、業務を一覧表にして見える化するやり方です。 個人でタスク管理していると、情報が属人化してしまい、誰がどの作業を進めているのかがわかりません。そのため、一か所に作業内容を洗い出し、完了しているかが一目でわかるようなチェックボックスを使って管理するのが効果的です。 このとき、作業内容だけでなく「作業着手日」や「期限」を項目に追加すれば、タスク漏れを未然に防げるのです。また、自社に合わせて「部署」も記入したり、定期的に発生するタスクは上部に固定したりする工夫もできます。 ガントチャートを作成する 2つ目は、ガントチャートを作成し、「どのタスクがどれくらい進んでいるか」を確認する方法です。 上記のように、Excelには、プロジェクト計画の進捗を視覚的にまとめられるテンプレートが備わっています。タスク名や進捗度をカスタマイズするだけなので、「一から作成するのは面倒」という方におすすめです。 ただし、ガントチャートは作業が進むたびに更新する必要があるため、すぐに取り出せる状態で保管するようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ <ポイントあり>業務の見える化・可視化する手順 ここでは、業務の見える化・可視化のやり方について説明します。「業務の見える化・可視化をどのように進めれば良いか分からない」という方は必見です。 (1)現状の業務内容を洗い出す まず、現状の業務内容を洗い出しましょう。 業務の見える化・可視化する目的は「業務内容の改善により、業務の効率化や生産性の向上を目指すこと」です。不必要な業務や形骸化した業務があれば目的の妨げになるため、「継続すべきかどうか」を一度見直すことが大切です。 また、現場の社員から業務の様子をヒアリングし、業務内容を整理していくのも有効な手段だと言えます。このとき、担当者や業務時間、場所などの細かいところまで調査し、一元的にまとめるようにしましょう。 (2)改善点を抽出する 現状の業務内容を把握できたら、改善点を抽出しましょう。 まず、業務についてまとめた資料やヒアリングから、現状の問題を分析します。なぜなら、課題解決を急ぎ、いきなり新しいシステムを導入しても浸透せず無駄になってしまうからです。 次に、改善点が明確になったら、課題を解決することでどのような効果・メリットがあるのかを全体で共有することが重要です。認識が揃ったら解決策を提示し、今後の業務に活かせる状態にブラッシュアップしましょう。 (3)定期的な見直しを実施する 最後に、作成後は定期的な見直しをこころがけましょう。 ガントチャートや一覧表で業務を可視化したあとも、進捗に合わせて都度更新し、最新の状態を保つ必要があります。ただし、編集したいときにすぐに目的のファイルを取り出せなければスムーズに対応できません。 そこで、「ナレカン」のようなファイル・画像内にまで検索をかけられるツールで管理すれば、定期的な振り返りや情報の更新も簡単に進められます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Excelで業務を見える化する2つのメリット 業務の見える化にExcelを使用する企業は少なくありません。以下では、Excelで業務を見える化する2つのメリットを紹介します。 (1)導入コストが低い 導入コストが低く、手軽に利用できる点はExcelを使うメリットのひとつです。 Excelは元々パソコンに備わっていることが多く、追加費用をかけずに運用を始められます。また、専門知識も不要であり、誰でも簡単に作成できます。 とくに、ITに詳しいメンバーが多くない企業にとって、ツールを使いこなせないまま形骸化してしまうケースは少なくありません。したがって、教育コストをかけずに使い始められる点は大きなメリットといえます。 (2)カスタマイズ性が高い カスタマイズ性が高く、様々な使い方ができる点もExcelのメリットです。 Excelは汎用性が高く、カスタマイズ次第でさまざまな用途に対応可能です。また、Excelは簡単なデータ管理から高度な分析までできるため、自社の運用スタイルに合わせた使い方が実現します また、専門知識を持つメンバーがいれば、関数やマクロ機能を使って入力の手間を省いたり、グラフを使って見やすく管理したりできるため、業務時間の短縮にも繋がります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Excelで業務を見える化する3つのデメリット ここでは、Excelを使って業務を見える化する3つのデメリットを紹介します。Excelの利用を検討する場合は、メリットだけでなくデメリットも把握しなくてはなりません。 (1)編集・閲覧に手間がかかる Excelのデメリットのひとつは、編集や閲覧に手間がかかる点です。 Excelで管理する場合、編集や閲覧のたびにファイルを開かなければならず不便です。とくに、進捗共有など頻繁に内容を更新する場合、ファイルを開く手間は大きなストレスとなります。 さらに、情報が増えてファイル数が膨大になると、管理が困難となり目的の情報にスムーズにアクセスできません。そのため、「Excelで一覧表を作成したが、放置されたままである」という恐れがある点に注意しましょう。 (2)Excelファイルの共有がしづらい スムーズな共有ができない点もExcelのデメリットです。 Excelは十分なメッセージ機能が備わっていないので、メンバーに共有するには別のツールを使う必要があります。しかし、共有のたびに別のツールを開き、ファイルを添付しなければならず面倒です。 また、メールやチャットツールを使って情報を共有する場合、他のメッセージで流れてしまうリスクもあります。情報の共有漏れは、納期の遅れや重大なミスにつながるので、ツールを導入する場合は慎重に選択しましょう。 (3)スマホやタブレットでは使いづらい Excelのデメリットには、スマホやタブレットでは使いづらい点も挙げられます。 ExcelはPC向けのツールのため、スマホやタブレットなどの画面の小さいデバイスでは閲覧や編集が難しいです。それゆえ、入力ミスや重要情報の見落としも起こりやすく、仕事に支障が出る可能性があります。 また、営業や現場仕事などオフィスを離れる場面が多い場合、スマホで簡単に情報の確認ができないと、最新の情報をすぐに業務に反映させることができません。 一方、スマホやタブレットでも手軽に編集・閲覧ができる「ナレカン」のようなツールなら、情報共有と管理が一か所で完結しまするので便利です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】業務の見える化に最もおすすめのツール 以下では、業務の見える化におすすめのツールをご紹介します。 業務を見える化するためには、業務に関する最新の情報を簡単に共有・管理するべきです。Excelはファイルを開く手間を要するほか、スマホからでは編集しにくいというデメリットがあり、簡単に共有・管理ができません。 そのため、「業務に関する情報を直接書き込んで簡単に更新ができるツール」を導入しましょう。また、膨大な情報から更新したい情報をすぐに見つけられるように、充実した検索機能も必須です。 結論、業務の見える化に最適なのは、テキストやファイルを一元化でき、充実した検索機能で即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは、パソコンだけでなくスマホからも簡単に情報を更新・確認することができます。また超高精度の「キーワード検索」により、欲しい情報をすぐに見つけられるので、可視化した業務の分担を振り返りたいときに、探す手間がかかりません。 情報を作成・管理ができ充実した検索機能がある「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Excelで業務を見える化するまとめ これまで、業務を見える化する重要性や方法、Excelを使うメリット、デメリットを中心にご紹介しました。 チームで仕事をスムーズに進めるためには、業務を見える化して「適切な作業配分」や「進捗の把握」、「業務ノウハウの共有」をする必要があります。そこで、導入コストが低くカスタマイズ性が高いExcelを使って業務を見える化する企業は少なくありません。 しかし、Excelは編集や閲覧のたびにファイルを開く手間がかかるうえ、スマホやタブレットからは使いづらいのが難点です。したがって、Excelのデメリットを解消する、「情報を簡単に共有・管理でき、充実した検索機能があるツール」を導入しましょう。 結論、業務の見える化に最適なのは、デバイスを問わずにあらゆる情報を簡単に共有・管理でき、超高精度な検索機能があるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入し、業務の見える化を実現しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年09月19日Excelで業務を見える化するやり方は?メリット・デメリットも解説チーム全体でスムーズに仕事を進めるには、メンバーごとの業務内容や進捗を見える化して共有する必要があります。そこで、Excelを使って業務を見える化する企業は少なくありません。 しかし、「Excelを使って効果的に業務を見える化する方法が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、Excelで見える化するメリット・デメリットを中心にご紹介します。 メンバーの進捗がわからず、作業を円滑に薄められていない Excelで「業務の見える化」をするメリット・デメリットを知りたい 業務の見える化におすすめのツールを導入したい という方はこの記事を参考にすると、業務を見える化する最適な方法が分かり、業務進行の効率化に役立てられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 業務を見える化・可視化とは2 業務を見える化する重要性とは2.1 作業を適切に配分できる2.2 進捗を把握できる2.3 業務ノウハウを共有できる3 Excelを活用して業務の見える化をするやり方3.1 業務一覧表を作成する3.2 ガントチャートを作成する4 <ポイントあり>業務の見える化・可視化する手順4.1 (1)現状の業務内容を洗い出す4.2 (2)改善点を抽出する4.3 (3)定期的な見直しを実施する5 Excelで業務を見える化する2つのメリット5.1 (1)導入コストが低い5.2 (2)カスタマイズ性が高い6 Excelで業務を見える化する3つのデメリット6.1 (1)編集・閲覧に手間がかかる6.2 (2)Excelファイルの共有がしづらい6.3 (3)スマホやタブレットでは使いづらい7 【必見】業務の見える化に最もおすすめのツール7.1 情報を作成・管理ができ充実した検索機能がある「ナレカン」8 Excelで業務を見える化するまとめ 業務を見える化・可視化とは 業務の見える化・可視化とは、プロジェクトの全体像や進捗状況を担当者でなくても把握できるようにすることです。 メンバー全員が全体進捗を把握しておくことで、業務の問題点や課題を発見しやすくなります。その結果、進捗に遅れがでていたり対応が漏れたりしていた場合に、すぐにメンバーのフォローに回れます。 このように、業務の見える化・可視化が実現されると、メンバー内でのコミュニケーションも活性化され、業務の効率化や生産性向上につなげることができるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 業務を見える化する重要性とは ここでは、業務を見える化する重要性を紹介します。チームの作業を円滑に進めるには、以下の重要性を把握して、適切に業務を見える化しなければなりません。 作業を適切に配分できる 業務が見える化すると、メンバーへの適切な作業配分も実現します。 たとえば、プロジェクトを円滑に進めるには、業務ごとの作業量を見える化して、メンバーに適切に振り分ける必要があります。業務全体が明確になっていることで、メンバーの作業負担の偏りがなくなるのです。 その結果として、負担が大きいメンバーの作業の質が低下したり、納期に遅れてしまったりすることがなくなり、業務効率も良くなります。以上のことから、メンバーに適切に作業を配分するうえで、業務の見える化は不可欠だと言えます。 進捗を把握できる メンバーの進捗を把握できる点でも、業務の見える化は重要です。 仕事を円滑に進めるには、メンバーの進捗を共有して、チームで連携を取らなければなりません。具体的には、作業がスムーズに進んでいるメンバーと遅れているメンバーを把握して、サポートし合う体制が必要なのです。 とくに、プロジェクトチームを組む場合、メンバーの作業が1人でも遅れてしまうと、プロジェクト全体の遅延につながります。したがって、メンバー同士で助け合い、チームの足並みをそろえるためにも、業務の見える化は重要なのです。 業務ノウハウを共有できる 業務の見える化によって、ノウハウの共有が可能になります。 業務の見える化によって、マニュアルや社内wikiなどが共有されれば、一から指導する手間を軽減できるので、教育コストの軽減につながります。また、業務の属人化も防止され、「担当者でなければ対処できない」といった事態も回避できるのです。 さらに、ノウハウが共有されると、経験の有無による業務の質のばらつきを抑えられます。そのため、経験の浅いメンバーでも一定の質を保ちながら業務に取り組めるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Excelを活用して業務の見える化をするやり方 ここでは、Excelで業務を可視化する方法を2つ紹介します。どちらのやり方も進捗をまとめて管理できる点が便利です。 業務一覧表を作成する 1つ目は、業務を一覧表にして見える化するやり方です。 個人でタスク管理していると、情報が属人化してしまい、誰がどの作業を進めているのかがわかりません。そのため、一か所に作業内容を洗い出し、完了しているかが一目でわかるようなチェックボックスを使って管理するのが効果的です。 このとき、作業内容だけでなく「作業着手日」や「期限」を項目に追加すれば、タスク漏れを未然に防げるのです。また、自社に合わせて「部署」も記入したり、定期的に発生するタスクは上部に固定したりする工夫もできます。 ガントチャートを作成する 2つ目は、ガントチャートを作成し、「どのタスクがどれくらい進んでいるか」を確認する方法です。 上記のように、Excelには、プロジェクト計画の進捗を視覚的にまとめられるテンプレートが備わっています。タスク名や進捗度をカスタマイズするだけなので、「一から作成するのは面倒」という方におすすめです。 ただし、ガントチャートは作業が進むたびに更新する必要があるため、すぐに取り出せる状態で保管するようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ <ポイントあり>業務の見える化・可視化する手順 ここでは、業務の見える化・可視化のやり方について説明します。「業務の見える化・可視化をどのように進めれば良いか分からない」という方は必見です。 (1)現状の業務内容を洗い出す まず、現状の業務内容を洗い出しましょう。 業務の見える化・可視化する目的は「業務内容の改善により、業務の効率化や生産性の向上を目指すこと」です。不必要な業務や形骸化した業務があれば目的の妨げになるため、「継続すべきかどうか」を一度見直すことが大切です。 また、現場の社員から業務の様子をヒアリングし、業務内容を整理していくのも有効な手段だと言えます。このとき、担当者や業務時間、場所などの細かいところまで調査し、一元的にまとめるようにしましょう。 (2)改善点を抽出する 現状の業務内容を把握できたら、改善点を抽出しましょう。 まず、業務についてまとめた資料やヒアリングから、現状の問題を分析します。なぜなら、課題解決を急ぎ、いきなり新しいシステムを導入しても浸透せず無駄になってしまうからです。 次に、改善点が明確になったら、課題を解決することでどのような効果・メリットがあるのかを全体で共有することが重要です。認識が揃ったら解決策を提示し、今後の業務に活かせる状態にブラッシュアップしましょう。 (3)定期的な見直しを実施する 最後に、作成後は定期的な見直しをこころがけましょう。 ガントチャートや一覧表で業務を可視化したあとも、進捗に合わせて都度更新し、最新の状態を保つ必要があります。ただし、編集したいときにすぐに目的のファイルを取り出せなければスムーズに対応できません。 そこで、「ナレカン」のようなファイル・画像内にまで検索をかけられるツールで管理すれば、定期的な振り返りや情報の更新も簡単に進められます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Excelで業務を見える化する2つのメリット 業務の見える化にExcelを使用する企業は少なくありません。以下では、Excelで業務を見える化する2つのメリットを紹介します。 (1)導入コストが低い 導入コストが低く、手軽に利用できる点はExcelを使うメリットのひとつです。 Excelは元々パソコンに備わっていることが多く、追加費用をかけずに運用を始められます。また、専門知識も不要であり、誰でも簡単に作成できます。 とくに、ITに詳しいメンバーが多くない企業にとって、ツールを使いこなせないまま形骸化してしまうケースは少なくありません。したがって、教育コストをかけずに使い始められる点は大きなメリットといえます。 (2)カスタマイズ性が高い カスタマイズ性が高く、様々な使い方ができる点もExcelのメリットです。 Excelは汎用性が高く、カスタマイズ次第でさまざまな用途に対応可能です。また、Excelは簡単なデータ管理から高度な分析までできるため、自社の運用スタイルに合わせた使い方が実現します また、専門知識を持つメンバーがいれば、関数やマクロ機能を使って入力の手間を省いたり、グラフを使って見やすく管理したりできるため、業務時間の短縮にも繋がります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Excelで業務を見える化する3つのデメリット ここでは、Excelを使って業務を見える化する3つのデメリットを紹介します。Excelの利用を検討する場合は、メリットだけでなくデメリットも把握しなくてはなりません。 (1)編集・閲覧に手間がかかる Excelのデメリットのひとつは、編集や閲覧に手間がかかる点です。 Excelで管理する場合、編集や閲覧のたびにファイルを開かなければならず不便です。とくに、進捗共有など頻繁に内容を更新する場合、ファイルを開く手間は大きなストレスとなります。 さらに、情報が増えてファイル数が膨大になると、管理が困難となり目的の情報にスムーズにアクセスできません。そのため、「Excelで一覧表を作成したが、放置されたままである」という恐れがある点に注意しましょう。 (2)Excelファイルの共有がしづらい スムーズな共有ができない点もExcelのデメリットです。 Excelは十分なメッセージ機能が備わっていないので、メンバーに共有するには別のツールを使う必要があります。しかし、共有のたびに別のツールを開き、ファイルを添付しなければならず面倒です。 また、メールやチャットツールを使って情報を共有する場合、他のメッセージで流れてしまうリスクもあります。情報の共有漏れは、納期の遅れや重大なミスにつながるので、ツールを導入する場合は慎重に選択しましょう。 (3)スマホやタブレットでは使いづらい Excelのデメリットには、スマホやタブレットでは使いづらい点も挙げられます。 ExcelはPC向けのツールのため、スマホやタブレットなどの画面の小さいデバイスでは閲覧や編集が難しいです。それゆえ、入力ミスや重要情報の見落としも起こりやすく、仕事に支障が出る可能性があります。 また、営業や現場仕事などオフィスを離れる場面が多い場合、スマホで簡単に情報の確認ができないと、最新の情報をすぐに業務に反映させることができません。 一方、スマホやタブレットでも手軽に編集・閲覧ができる「ナレカン」のようなツールなら、情報共有と管理が一か所で完結しまするので便利です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】業務の見える化に最もおすすめのツール 以下では、業務の見える化におすすめのツールをご紹介します。 業務を見える化するためには、業務に関する最新の情報を簡単に共有・管理するべきです。Excelはファイルを開く手間を要するほか、スマホからでは編集しにくいというデメリットがあり、簡単に共有・管理ができません。 そのため、「業務に関する情報を直接書き込んで簡単に更新ができるツール」を導入しましょう。また、膨大な情報から更新したい情報をすぐに見つけられるように、充実した検索機能も必須です。 結論、業務の見える化に最適なのは、テキストやファイルを一元化でき、充実した検索機能で即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは、パソコンだけでなくスマホからも簡単に情報を更新・確認することができます。また超高精度の「キーワード検索」により、欲しい情報をすぐに見つけられるので、可視化した業務の分担を振り返りたいときに、探す手間がかかりません。 情報を作成・管理ができ充実した検索機能がある「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Excelで業務を見える化するまとめ これまで、業務を見える化する重要性や方法、Excelを使うメリット、デメリットを中心にご紹介しました。 チームで仕事をスムーズに進めるためには、業務を見える化して「適切な作業配分」や「進捗の把握」、「業務ノウハウの共有」をする必要があります。そこで、導入コストが低くカスタマイズ性が高いExcelを使って業務を見える化する企業は少なくありません。 しかし、Excelは編集や閲覧のたびにファイルを開く手間がかかるうえ、スマホやタブレットからは使いづらいのが難点です。したがって、Excelのデメリットを解消する、「情報を簡単に共有・管理でき、充実した検索機能があるツール」を導入しましょう。 結論、業務の見える化に最適なのは、デバイスを問わずにあらゆる情報を簡単に共有・管理でき、超高精度な検索機能があるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入し、業務の見える化を実現しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年09月22日【サービス終了】COTOHA Meeting Assistとは?代替ツールや評判を紹介近年、リモートワークの普及に伴いWeb会議も一般的になりつつあります。そこで、会議内容の整理を効率化させるために、「議事録作成支援ツール」を使う企業が増えています。 たとえば、「COTOHA Meeting Assist(コトハミーティングアシスト)」は議事録作成に役立つツールのひとつでした。しかし、COTOHA Meeting Assistのサービスが終了したことで「どのツールを使えば良いか分からない」と悩む方が多いのではないでしょうか。 そこで今回は、COTOHA Meeting Assistの機能や使い方・料金・評判と他の議事録ツールとの比較まで網羅的にご紹介します。 COTOHA Meeting Assistの機能や料金、使い方を知りたい COTOHA Meeting Assistのサービス終了により、代替ツールを比較検討したい 作成した議事録を適切に管理・共有できるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、COTOHA Meeting Assistの概要だけでなく、議事録にかける業務の手間を軽減する方法が分かります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 COTOHA Meeting Assist(コトハミーティングアシスト)とは2 COTOHA Meeting Assistに代わる!AI議事録作成ツール3選2.1 スマート書記2.2 AmiVoice Cloud Platform2.3 Notta3 【必見】議事録の共有・管理に役立つITツール3.1 議事録の共有・バージョン管理を最も簡単にできるツール「ナレカン」4 COTOHA Meeting Assistの機能/料金5 COTOHA Meeting Assistの使い方5.1 ミーティングルームの作成5.2 会話の記録6 COTOHA Meeting Assistの代替ツールや評判まとめ COTOHA Meeting Assist(コトハミーティングアシスト)とは 引用: COTOHA Meeting Assistのトップページ COTOHA Meeting Assist(コトハミーティングアシスト)とは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供するAI議事録自動作成ツールです。 他の議事録作成ツールとの違いとしては、「確認したい部分のみ音声を聞き直し、文章を修正できること」が挙げられます。これにより、AIで作成した議事録の確認/手直しを容易に実施できるのです。 また、会議中はリアルタイムで文字起こしがおこなわれるため、外出やリモートワーク中で会議に参加できずともテキストを読むだけで内容が把握できます。 ただし、COTOHA Meeting Assist(コトハミーティングアシスト)は2024年9月30日(月)でサービスが終了しているため、議事録作成ツールを探している場合は、他のツールの利用を検討しなければなりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ COTOHA Meeting Assistに代わる!AI議事録作成ツール3選 COTOHA Meeting Assistは2024年9月30日でサービス終了となりました。そこで、以下では代替となるAI議事録作成ツールをご紹介します。 スマート書記 スマート書記の特徴 使えば使うほどAIの精度が上がる 独自アルゴリズムでAIに学習させることなく、AIの精度を向上させる仕組みを構築しています。そのため、使えば使うほどAIの精度が向上します。 あらゆるWeb会議ツールと連携可能 ZoomやMicrosoft Teams、Google Meet、Cisco Webexなど、あらゆるWeb会議ツールと連携して使えます。 スマート書記の機能・使用感 自動話者分離機能 最大20名までの発話者を認識し、誰がどのような発言をしたのか可視化することができます。そのため、活発に意見交換がおこなわれる会議において役立ちます。 フィラー除去機能 「あー」「えー」などの発話の間に挟み込む意味を持たない言葉を自動で削除できます。そのため、文章校正をスムーズに実施したいときに便利です。 要約機能・要点抽出機能 会議の概要をAIが自動でまとめてくれる機能や、会議の要点共有に役立つ「要点抽出機能」があります。指定した議題ごとの要点整理も可能なため、会議の概要をすぐに把握したいときに便利です。 スマート書記の注意点 最初の設定が複雑 利用しているユーザーからは「最初の設定が少し複雑なので、この様なツールに慣れていない人にはハードルが高いかもしれません。」という声があります。(参考:ITreview) 専門用語学習の自動化ができない 利用しているユーザーからは「特定の業界の単語リストを自動で提案したり、頻繁に使用される用語をAIが自動的にピックアップして学習候補として提示する機能があれば、ユーザーの手間が省けます。」という声があります。(参考:ITreview) スマート書記の料金体系 料金は利用人数に合わせて変わるため、問い合わせる必要があります。 ライセンス料:10,000円/月 スマート書記の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ AmiVoice Cloud Platform AmiVoice Cloud Platformの特徴 日本語の認識精度が高い AmiVoiceは、25年以上のノウハウ・データが蓄積された音声認識エンジンです。そのため、日本語に対する高い認識精度に定評があります。 ノイズ対策技術に優れている AmiVoiceはノイズ対策技術により街の中はもとより、工場、自動車・電車・飛行機などの騒音が多い場所での音声や、電話などの聞き取りづらい音声もクリアに認識できます。 AmiVoice Cloud Platformの機能・使用感 専門用語に強い 業務に不適切な用語を省き、製品名や固有名詞などの登録・認識も可能です。各業界特有の用語を認識できるため、幅広い業界で活用できます。 認識言語が複数ある 国内で開発・運用されているサービスですが、認識言語は日本語以外に英語、中国語、韓国語にも対応しています。そのため、海外の方との会議での文字起こしにも便利です。 AmiVoice Cloud Platformの注意点 スマホでは操作しにくい 利用しているユーザーからは「モバイル版(携帯版)ですと、操作しにくいです。パソコンですとGoogleに劣らない!と思うのですが・・・今後に期待しています。」という声があります。(参考:ITreview) 誤認識が多い 利用しているユーザーからは「言い方などにより誤認識になることも多いので、その部分を成長させていただければなおさら使い勝手が向上すると思います。」という声があります。(参考:ITreview) AmiVoice Cloud Platformの料金体系 利用料金は、利用した音声時間をもとにして、月ごとに計算・請求されます。毎月60分までは無料で利用できます。 99円(税込み)/1時間 AmiVoice Cloud Platformの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Notta Nottaの特徴 シンプルで直感的に操作できる NottaのUI/UXは、直感的に操作できるわかりやすい設計になっています。そのため、ITツールが苦手な方でも簡単に使えます。 音声認識の精度が高い 最先端の音声認識AI技術を用いて、常にNottaの文字起こしの認識精度は向上し続けており、98.86%という高精度な音声認識を実現しています。 Nottaの機能・使用感 引用:Nottaのホームページ フォルダ機能 作成したファイルは2階層のフォルダで管理可能なため、必要なファイルへスムーズにアクセスでき、業務効率化に役立ちます。 翻訳機能 42言語に対応した翻訳機能が搭載されています。翻訳したテキストは「原文」と「訳文」を同時に表示させられるので、国際会議や海外研修でのサポート、語学学習などのシーンで役立ちます。 Nottaの注意点 無料プランは1回につき3分までしか文字起こしできない 無料プランでは1回につき3分まで、1ヶ月で120分までしか文字起こしできないため、ビジネスで使用するには有料プランを選択する必要があります。 誤字修正に手間取る 利用しているユーザーからは「文字起こしされた文章は、句読点や改行が不自然な場合があります。手動で修正する際、もう少しスムーズに編集できる機能があると嬉しいです。」という声があります。(参考:ITreview) Nottaの料金体系 フリー:0円 プレミアム:1,980円/ユーザー/月(月払い) ビジネス:4,180円/ユーザー/月(月払い) エンタープライズ:要問合せ Nottaの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】議事録の共有・管理に役立つITツール ここでは、議事録の共有・管理に役立つITツールをご紹介します。 議事録は業務を進めるうえで必須のため、作成して終わりではなく、すぐに社内で共有するべきです。しかし、メールやチャットだと情報が流れてしまい、ストレージでの保管だとほかのファイルに議事録データが埋もれてしまいます。 したがって、議事録作成ツールのほかに「議事録の共有・バージョン管理が簡単にできるツール」を併用しましょう。また、過去の議事録を必要なときにすぐに見つけられるよう、充実した「検索機能」も必須です。 結論、議事録の管理・共有に最適なのは、議事録ファイルの共有・管理が簡単にできて、充実した検索機能があるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは、議事録のファイルをそのまま添付できるうえ、共有の連絡も可能なので、複数のツールをまたぐ必要がありません。さらに、「ファイル内検索機能」により、添付ファイルの中身まで検索できるため、会議の内容も振り返りやすいのです。 議事録の共有・バージョン管理を最も簡単にできるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ COTOHA Meeting Assistの機能/料金 COTOHA Meeting Assistには、主に以下の機能がありました。 多言語対応 自動翻訳機能で、異なる言語も翻訳された状態でテキストに表示されます。 ラベル付機能 発言内容に応じて、AIが「重要」「タスク」などのラベル付けをします。 Web会議サービスとの併用 Zoom、Google MeetなどのWeb会議サービスと同時に立ち上げることで、Web会議の発言もテキスト化できます。 また、COTOHA Meeting Assistが提供されていたときの料金価格は以下の通りです。 基本契約 APIパック 月額料金 税込38,500円 税込16,500円 内容 CPU1コア/メモリー8GB/ディスク100GBを含む。 1カ月あたり約50時間分の音声認識や翻訳ができ、最大50パックまで追加可能。 契約単位 1契約毎 1パック毎 「どれがいいか分からない」という場合は、上記を参考に代替ツールを探しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ COTOHA Meeting Assistの使い方 ここでは、COTOHA Meeting Assistの「ミーティングルームの作成」「会話の記録」の使い方を解説します。 ミーティングルームの作成 メニューバー上の「ミーティング」をクリックします。 「新規作成」をクリックします。 ルーム名やルームメンバーなどを設定して、画面下部の「作成」をクリックします。 ルーム一覧に表示されたらミーティングルームの作成は完了です。 会話の記録 会議が始まったら「議事メモの記録を開始」をクリックします。 「記録開始」をクリックすると、議題を入力する画面が表示されます。議題を入力した後、「開始」をクリックすると、会議メモの記録が開始されます。 記録が始まると「●記録中」と表示されます。 「記事メモの記録を終了」をクリックすると、会話の記録がメモとして残ります。 参考および画像引用: COTOHA Meeting Assist利用者マニュアル 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ COTOHA Meeting Assistの代替ツールや評判まとめ ここまで、COTOHA Meeting Assistの代替ツールや評判などをご紹介しました。 COTOHA Meeting Assistは、2024年9月30日にサービスが終了しました。議事録作成の代替ツールとしてスマート書記やAmiVoice、Nottaなどが挙げられますが、議事録は作成するだけではなく、簡単に社内で管理・共有できるかも重要です。 そのため、「議事録の共有・管理を簡単にできるツール」も併用しましょう。また、過去の議事録が必要なときにすぐ見つけられるよう、充実した検索機能も必須です。 結論、議事録の管理・共有に最適なのは、議事録ファイルの共有・管理が簡単なうえに、ファイルの中身まで検索可能なツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、議事録の共有・管理を円滑に実施しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年09月22日【サービス終了】COTOHA Meeting Assistとは?代替ツールや評判を紹介近年、リモートワークの普及に伴いWeb会議も一般的になりつつあります。そこで、会議内容の整理を効率化させるために、「議事録作成支援ツール」を使う企業が増えています。 たとえば、「COTOHA Meeting Assist(コトハミーティングアシスト)」は議事録作成に役立つツールのひとつでした。しかし、COTOHA Meeting Assistのサービスが終了したことで「どのツールを使えば良いか分からない」と悩む方が多いのではないでしょうか。 そこで今回は、COTOHA Meeting Assistの機能や使い方・料金・評判と他の議事録ツールとの比較まで網羅的にご紹介します。 COTOHA Meeting Assistの機能や料金、使い方を知りたい COTOHA Meeting Assistのサービス終了により、代替ツールを比較検討したい 作成した議事録を適切に管理・共有できるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、COTOHA Meeting Assistの概要だけでなく、議事録にかける業務の手間を軽減する方法が分かります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 COTOHA Meeting Assist(コトハミーティングアシスト)とは2 COTOHA Meeting Assistに代わる!AI議事録作成ツール3選2.1 スマート書記2.2 AmiVoice Cloud Platform2.3 Notta3 【必見】議事録の共有・管理に役立つITツール3.1 議事録の共有・バージョン管理を最も簡単にできるツール「ナレカン」4 COTOHA Meeting Assistの機能/料金5 COTOHA Meeting Assistの使い方5.1 ミーティングルームの作成5.2 会話の記録6 COTOHA Meeting Assistの代替ツールや評判まとめ COTOHA Meeting Assist(コトハミーティングアシスト)とは 引用: COTOHA Meeting Assistのトップページ COTOHA Meeting Assist(コトハミーティングアシスト)とは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供するAI議事録自動作成ツールです。 他の議事録作成ツールとの違いとしては、「確認したい部分のみ音声を聞き直し、文章を修正できること」が挙げられます。これにより、AIで作成した議事録の確認/手直しを容易に実施できるのです。 また、会議中はリアルタイムで文字起こしがおこなわれるため、外出やリモートワーク中で会議に参加できずともテキストを読むだけで内容が把握できます。 ただし、COTOHA Meeting Assist(コトハミーティングアシスト)は2024年9月30日(月)でサービスが終了しているため、議事録作成ツールを探している場合は、他のツールの利用を検討しなければなりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ COTOHA Meeting Assistに代わる!AI議事録作成ツール3選 COTOHA Meeting Assistは2024年9月30日でサービス終了となりました。そこで、以下では代替となるAI議事録作成ツールをご紹介します。 スマート書記 スマート書記の特徴 使えば使うほどAIの精度が上がる 独自アルゴリズムでAIに学習させることなく、AIの精度を向上させる仕組みを構築しています。そのため、使えば使うほどAIの精度が向上します。 あらゆるWeb会議ツールと連携可能 ZoomやMicrosoft Teams、Google Meet、Cisco Webexなど、あらゆるWeb会議ツールと連携して使えます。 スマート書記の機能・使用感 自動話者分離機能 最大20名までの発話者を認識し、誰がどのような発言をしたのか可視化することができます。そのため、活発に意見交換がおこなわれる会議において役立ちます。 フィラー除去機能 「あー」「えー」などの発話の間に挟み込む意味を持たない言葉を自動で削除できます。そのため、文章校正をスムーズに実施したいときに便利です。 要約機能・要点抽出機能 会議の概要をAIが自動でまとめてくれる機能や、会議の要点共有に役立つ「要点抽出機能」があります。指定した議題ごとの要点整理も可能なため、会議の概要をすぐに把握したいときに便利です。 スマート書記の注意点 最初の設定が複雑 利用しているユーザーからは「最初の設定が少し複雑なので、この様なツールに慣れていない人にはハードルが高いかもしれません。」という声があります。(参考:ITreview) 専門用語学習の自動化ができない 利用しているユーザーからは「特定の業界の単語リストを自動で提案したり、頻繁に使用される用語をAIが自動的にピックアップして学習候補として提示する機能があれば、ユーザーの手間が省けます。」という声があります。(参考:ITreview) スマート書記の料金体系 料金は利用人数に合わせて変わるため、問い合わせる必要があります。 ライセンス料:10,000円/月 スマート書記の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ AmiVoice Cloud Platform AmiVoice Cloud Platformの特徴 日本語の認識精度が高い AmiVoiceは、25年以上のノウハウ・データが蓄積された音声認識エンジンです。そのため、日本語に対する高い認識精度に定評があります。 ノイズ対策技術に優れている AmiVoiceはノイズ対策技術により街の中はもとより、工場、自動車・電車・飛行機などの騒音が多い場所での音声や、電話などの聞き取りづらい音声もクリアに認識できます。 AmiVoice Cloud Platformの機能・使用感 専門用語に強い 業務に不適切な用語を省き、製品名や固有名詞などの登録・認識も可能です。各業界特有の用語を認識できるため、幅広い業界で活用できます。 認識言語が複数ある 国内で開発・運用されているサービスですが、認識言語は日本語以外に英語、中国語、韓国語にも対応しています。そのため、海外の方との会議での文字起こしにも便利です。 AmiVoice Cloud Platformの注意点 スマホでは操作しにくい 利用しているユーザーからは「モバイル版(携帯版)ですと、操作しにくいです。パソコンですとGoogleに劣らない!と思うのですが・・・今後に期待しています。」という声があります。(参考:ITreview) 誤認識が多い 利用しているユーザーからは「言い方などにより誤認識になることも多いので、その部分を成長させていただければなおさら使い勝手が向上すると思います。」という声があります。(参考:ITreview) AmiVoice Cloud Platformの料金体系 利用料金は、利用した音声時間をもとにして、月ごとに計算・請求されます。毎月60分までは無料で利用できます。 99円(税込み)/1時間 AmiVoice Cloud Platformの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Notta Nottaの特徴 シンプルで直感的に操作できる NottaのUI/UXは、直感的に操作できるわかりやすい設計になっています。そのため、ITツールが苦手な方でも簡単に使えます。 音声認識の精度が高い 最先端の音声認識AI技術を用いて、常にNottaの文字起こしの認識精度は向上し続けており、98.86%という高精度な音声認識を実現しています。 Nottaの機能・使用感 引用:Nottaのホームページ フォルダ機能 作成したファイルは2階層のフォルダで管理可能なため、必要なファイルへスムーズにアクセスでき、業務効率化に役立ちます。 翻訳機能 42言語に対応した翻訳機能が搭載されています。翻訳したテキストは「原文」と「訳文」を同時に表示させられるので、国際会議や海外研修でのサポート、語学学習などのシーンで役立ちます。 Nottaの注意点 無料プランは1回につき3分までしか文字起こしできない 無料プランでは1回につき3分まで、1ヶ月で120分までしか文字起こしできないため、ビジネスで使用するには有料プランを選択する必要があります。 誤字修正に手間取る 利用しているユーザーからは「文字起こしされた文章は、句読点や改行が不自然な場合があります。手動で修正する際、もう少しスムーズに編集できる機能があると嬉しいです。」という声があります。(参考:ITreview) Nottaの料金体系 フリー:0円 プレミアム:1,980円/ユーザー/月(月払い) ビジネス:4,180円/ユーザー/月(月払い) エンタープライズ:要問合せ Nottaの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】議事録の共有・管理に役立つITツール ここでは、議事録の共有・管理に役立つITツールをご紹介します。 議事録は業務を進めるうえで必須のため、作成して終わりではなく、すぐに社内で共有するべきです。しかし、メールやチャットだと情報が流れてしまい、ストレージでの保管だとほかのファイルに議事録データが埋もれてしまいます。 したがって、議事録作成ツールのほかに「議事録の共有・バージョン管理が簡単にできるツール」を併用しましょう。また、過去の議事録を必要なときにすぐに見つけられるよう、充実した「検索機能」も必須です。 結論、議事録の管理・共有に最適なのは、議事録ファイルの共有・管理が簡単にできて、充実した検索機能があるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは、議事録のファイルをそのまま添付できるうえ、共有の連絡も可能なので、複数のツールをまたぐ必要がありません。さらに、「ファイル内検索機能」により、添付ファイルの中身まで検索できるため、会議の内容も振り返りやすいのです。 議事録の共有・バージョン管理を最も簡単にできるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ COTOHA Meeting Assistの機能/料金 COTOHA Meeting Assistには、主に以下の機能がありました。 多言語対応 自動翻訳機能で、異なる言語も翻訳された状態でテキストに表示されます。 ラベル付機能 発言内容に応じて、AIが「重要」「タスク」などのラベル付けをします。 Web会議サービスとの併用 Zoom、Google MeetなどのWeb会議サービスと同時に立ち上げることで、Web会議の発言もテキスト化できます。 また、COTOHA Meeting Assistが提供されていたときの料金価格は以下の通りです。 基本契約 APIパック 月額料金 税込38,500円 税込16,500円 内容 CPU1コア/メモリー8GB/ディスク100GBを含む。 1カ月あたり約50時間分の音声認識や翻訳ができ、最大50パックまで追加可能。 契約単位 1契約毎 1パック毎 「どれがいいか分からない」という場合は、上記を参考に代替ツールを探しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ COTOHA Meeting Assistの使い方 ここでは、COTOHA Meeting Assistの「ミーティングルームの作成」「会話の記録」の使い方を解説します。 ミーティングルームの作成 メニューバー上の「ミーティング」をクリックします。 「新規作成」をクリックします。 ルーム名やルームメンバーなどを設定して、画面下部の「作成」をクリックします。 ルーム一覧に表示されたらミーティングルームの作成は完了です。 会話の記録 会議が始まったら「議事メモの記録を開始」をクリックします。 「記録開始」をクリックすると、議題を入力する画面が表示されます。議題を入力した後、「開始」をクリックすると、会議メモの記録が開始されます。 記録が始まると「●記録中」と表示されます。 「記事メモの記録を終了」をクリックすると、会話の記録がメモとして残ります。 参考および画像引用: COTOHA Meeting Assist利用者マニュアル 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ COTOHA Meeting Assistの代替ツールや評判まとめ ここまで、COTOHA Meeting Assistの代替ツールや評判などをご紹介しました。 COTOHA Meeting Assistは、2024年9月30日にサービスが終了しました。議事録作成の代替ツールとしてスマート書記やAmiVoice、Nottaなどが挙げられますが、議事録は作成するだけではなく、簡単に社内で管理・共有できるかも重要です。 そのため、「議事録の共有・管理を簡単にできるツール」も併用しましょう。また、過去の議事録が必要なときにすぐ見つけられるよう、充実した検索機能も必須です。 結論、議事録の管理・共有に最適なのは、議事録ファイルの共有・管理が簡単なうえに、ファイルの中身まで検索可能なツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、議事録の共有・管理を円滑に実施しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年06月26日PDCAサイクルは古い?理由と新たなフレームワークも紹介PDCAは、業務を効率化するために多くの企業で利用されています。しかし昨今は、PDCAに代わる新しいフレームワークが注目を集めるようになり、「PDCAは古い」と言われることもあります。 しかし、「PDCAに代わる新しいフレームワークがわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、PDCAが古いと言われる理由や、今注目されているフレームワークを中心にご紹介します。 なぜPDCAが古いとされているのか知りたい PDCAに代わるフレームワークを教えてほしい フレームワーク活用に最適なツールがあれば使いたい という方はこの記事を参考にすると、PDCAが古いと言われる理由やPDCAの代わりになるフレームワークがわかるだけでなく、業務効率化におすすめのツールも見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 PDCAとは?2 【時代遅れ?】PDCAが古いとされる理由3 PDCAの代わりになるフレームワークとは3.1 OODA3.2 STPD3.3 PDR4 【ビジネスマン必見】フレームワーク活用に最適なツール4.1 業務の見える化におすすめのツール「ナレカン」5 PDCAが古い理由と新たなフレームワークまとめ PDCAとは? PDCAは、業務改善が目的のフレームワークであり、組織や個人のマネジメントに使用されています。 特徴として、結果とプロセスに重きが置かれており、計画を綿密に立てられることが挙げられます。そのため、改善サイクルが回しやすく、既存の業務に合わせて柔軟に取り組みことができます。 PDCAサイクルは、以下の4段階で成り立っています。 Plan(計画) Do(実行) Check(評価) Action(改善) 以上の4つのプロセスを意識してらせん状にPDCAサイクルを回せば、課題が明確になり、やるべきことが具体的にわかるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【時代遅れ?】PDCAが古いとされる理由 PDCAが古いと言われる理由は、「改善までのプロセスに時間がかかるため」です。 近年、市場や顧客のニーズは変化し続けています。しかし、PDCAサイクルでは計画に時間がかかるため、実行する段階ではすでに流行が変わっていたという事態になりかねません。 そのため、新しいアイデアをすぐに取り入れることのできないPDCAサイクルは、こうした近年のビジネスモデルには合わず、古いと言われるようになったのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ PDCAの代わりになるフレームワークとは 以下では、今注目されている効果的なフレームワークについてご紹介します。フレームワークを活用して、業務を効率化したいという方は必見です。 OODA まずは、OODAというフレームワークをご紹介します。OODAは「意思決定のためのフレームワーク」で、以下の4つの英単語の頭文字から取っています。 Observe(観察) Orient(状況判断) Decide(意思決定) Act(行動) OODAは、情報に基づき即応的に動くことを重視するため、顧客のニーズに合わせられる点が特徴です。また、現場で意思決定し実行する前提で作られているため、課題に対して最短で解決できます。 以上のように、PDCAと比べて改善までのサイクルが短くスピード感があるため、変化する市場に適している点がメリットです。 STPD 次に、STPDというフレームワークをご紹介します。STPDは、課題解決や業務改善の場面で活用される思考のプロセスで、以下の4つのステップで構成されています。 See (見る) Think (考える) Plan (計画) Do (実行) STPDでは、現場観察から入るため、表面的でなく「根本的な課題」に気づきやすいです。そのため、製造現場・カスタマー対応・ヘルプデスク・店舗業務など、「現場を起点とした改善活動」に適しているといえます。 以上のように、STPDは計画よりも「現状観察」や「本質的な問題把握」を重視するため、じっくりと状況を見極めたうえで改善に向かう点が特徴的です。 PDR 最後に、PDRというフレームワークをご紹介します。PDRの大きな特徴は「計画を立てない」ことにあり、以下の3つの英単語の頭文字を取っています。 Prep(準備) Do(実行) Review(評価) PDCAとは異なり、いち早く行動し、客観的な評価を取り入れて改善するというのがPDRの考え方です。また、一回のスパンが短いため、サイクルをスピーディーに効率よく回すことができます。 そのため、PDRはIT化した現代の変化しやすいビジネスモデルに有効です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【ビジネスマン必見】フレームワーク活用に最適なツール 以下では、フレームワーク活用に最適なツールをご紹介します。 PDCAなどのフレームワークは組織や個人のマネジメントにおいて非常に重要です。ただし、フレームワークを活用するには、過去のプロセスと結果、意思決定の背景などの情報を組織内で適切に管理しておくことが重要です。 また、実施したサイクルを情報として記録し共有することは、上司からのフィードバックや部下へのノウハウ共有にもつながります。そのため、フレームワーク活用の過程で得られた情報やノウハウなどを、社内の情報資産として必要なときに瞬時に探し出せる状況で管理できるツールを利用しましょう。 結論、自社が導入すべきなのは、フレームワークの過程や結果の記録、組織内での共有・活用に最適なツール「ナレカン」一択です。 ナレカンには、社内のあらゆる情報が蓄積できるので、社内の意思決定の基準や判断の背景が共有されます。またAIを活用した超高精度な検索機能により、大量の情報のなかから必要な情報を瞬時にピックアップし、活用することが可能です。 業務の見える化におすすめのツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ PDCAが古い理由と新たなフレームワークまとめ これまで、PDCAが古いと言われる理由や、ビジネスに効果的なフレームワークを中心にご紹介しました。 近年では、変化するニーズに合わせて、PDCAに代わり高速でサイクルを回せるフレームワークが注目されています。フレームワークを活用してやるべきことを明確化すれば、業務を滞りなく進められるのです。 ただし、フレームワークを取り入れるには、社内にある情報をいつでも活用できるように管理しなくてはなりません。そこで、「社内のノウハウを一元化し、高精度に検索できるツール」を導入すれば、業務改善サイクルのスピードが上がります。 結論、フレームワークの効果を最大化するなら、ファイル形式問わず、業務情報をまとめて管理できて、常に最新の情報を入手できる体制を作るナレッジ管理ツール『ナレカン』一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、フレームワークによる業務改善の効果を最大化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年06月26日PDCAサイクルは古い?理由と新たなフレームワークも紹介PDCAは、業務を効率化するために多くの企業で利用されています。しかし昨今は、PDCAに代わる新しいフレームワークが注目を集めるようになり、「PDCAは古い」と言われることもあります。 しかし、「PDCAに代わる新しいフレームワークがわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、PDCAが古いと言われる理由や、今注目されているフレームワークを中心にご紹介します。 なぜPDCAが古いとされているのか知りたい PDCAに代わるフレームワークを教えてほしい フレームワーク活用に最適なツールがあれば使いたい という方はこの記事を参考にすると、PDCAが古いと言われる理由やPDCAの代わりになるフレームワークがわかるだけでなく、業務効率化におすすめのツールも見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 PDCAとは?2 【時代遅れ?】PDCAが古いとされる理由3 PDCAの代わりになるフレームワークとは3.1 OODA3.2 STPD3.3 PDR4 【ビジネスマン必見】フレームワーク活用に最適なツール4.1 業務の見える化におすすめのツール「ナレカン」5 PDCAが古い理由と新たなフレームワークまとめ PDCAとは? PDCAは、業務改善が目的のフレームワークであり、組織や個人のマネジメントに使用されています。 特徴として、結果とプロセスに重きが置かれており、計画を綿密に立てられることが挙げられます。そのため、改善サイクルが回しやすく、既存の業務に合わせて柔軟に取り組みことができます。 PDCAサイクルは、以下の4段階で成り立っています。 Plan(計画) Do(実行) Check(評価) Action(改善) 以上の4つのプロセスを意識してらせん状にPDCAサイクルを回せば、課題が明確になり、やるべきことが具体的にわかるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【時代遅れ?】PDCAが古いとされる理由 PDCAが古いと言われる理由は、「改善までのプロセスに時間がかかるため」です。 近年、市場や顧客のニーズは変化し続けています。しかし、PDCAサイクルでは計画に時間がかかるため、実行する段階ではすでに流行が変わっていたという事態になりかねません。 そのため、新しいアイデアをすぐに取り入れることのできないPDCAサイクルは、こうした近年のビジネスモデルには合わず、古いと言われるようになったのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ PDCAの代わりになるフレームワークとは 以下では、今注目されている効果的なフレームワークについてご紹介します。フレームワークを活用して、業務を効率化したいという方は必見です。 OODA まずは、OODAというフレームワークをご紹介します。OODAは「意思決定のためのフレームワーク」で、以下の4つの英単語の頭文字から取っています。 Observe(観察) Orient(状況判断) Decide(意思決定) Act(行動) OODAは、情報に基づき即応的に動くことを重視するため、顧客のニーズに合わせられる点が特徴です。また、現場で意思決定し実行する前提で作られているため、課題に対して最短で解決できます。 以上のように、PDCAと比べて改善までのサイクルが短くスピード感があるため、変化する市場に適している点がメリットです。 STPD 次に、STPDというフレームワークをご紹介します。STPDは、課題解決や業務改善の場面で活用される思考のプロセスで、以下の4つのステップで構成されています。 See (見る) Think (考える) Plan (計画) Do (実行) STPDでは、現場観察から入るため、表面的でなく「根本的な課題」に気づきやすいです。そのため、製造現場・カスタマー対応・ヘルプデスク・店舗業務など、「現場を起点とした改善活動」に適しているといえます。 以上のように、STPDは計画よりも「現状観察」や「本質的な問題把握」を重視するため、じっくりと状況を見極めたうえで改善に向かう点が特徴的です。 PDR 最後に、PDRというフレームワークをご紹介します。PDRの大きな特徴は「計画を立てない」ことにあり、以下の3つの英単語の頭文字を取っています。 Prep(準備) Do(実行) Review(評価) PDCAとは異なり、いち早く行動し、客観的な評価を取り入れて改善するというのがPDRの考え方です。また、一回のスパンが短いため、サイクルをスピーディーに効率よく回すことができます。 そのため、PDRはIT化した現代の変化しやすいビジネスモデルに有効です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【ビジネスマン必見】フレームワーク活用に最適なツール 以下では、フレームワーク活用に最適なツールをご紹介します。 PDCAなどのフレームワークは組織や個人のマネジメントにおいて非常に重要です。ただし、フレームワークを活用するには、過去のプロセスと結果、意思決定の背景などの情報を組織内で適切に管理しておくことが重要です。 また、実施したサイクルを情報として記録し共有することは、上司からのフィードバックや部下へのノウハウ共有にもつながります。そのため、フレームワーク活用の過程で得られた情報やノウハウなどを、社内の情報資産として必要なときに瞬時に探し出せる状況で管理できるツールを利用しましょう。 結論、自社が導入すべきなのは、フレームワークの過程や結果の記録、組織内での共有・活用に最適なツール「ナレカン」一択です。 ナレカンには、社内のあらゆる情報が蓄積できるので、社内の意思決定の基準や判断の背景が共有されます。またAIを活用した超高精度な検索機能により、大量の情報のなかから必要な情報を瞬時にピックアップし、活用することが可能です。 業務の見える化におすすめのツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ PDCAが古い理由と新たなフレームワークまとめ これまで、PDCAが古いと言われる理由や、ビジネスに効果的なフレームワークを中心にご紹介しました。 近年では、変化するニーズに合わせて、PDCAに代わり高速でサイクルを回せるフレームワークが注目されています。フレームワークを活用してやるべきことを明確化すれば、業務を滞りなく進められるのです。 ただし、フレームワークを取り入れるには、社内にある情報をいつでも活用できるように管理しなくてはなりません。そこで、「社内のノウハウを一元化し、高精度に検索できるツール」を導入すれば、業務改善サイクルのスピードが上がります。 結論、フレームワークの効果を最大化するなら、ファイル形式問わず、業務情報をまとめて管理できて、常に最新の情報を入手できる体制を作るナレッジ管理ツール『ナレカン』一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、フレームワークによる業務改善の効果を最大化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年06月26日【徹底解説】KPT法とは?振り返りの進め方やコツも紹介ビジネスを進めていくにあたり、プロジェクト終了時に振り返りをすることは重要です。とくに、KPT法を用いて振り返りを実施すると、前回の反省を生かしつつ新しいプロジェクトに入れるため、より良い成果が期待できます。 しかし、「KPTという名称は知ってはいるものの、KPT法の具体的な進め方は分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、KPT法の具体的な進め方や導入時のコツを中心にご紹介します。 KPT法の概要や取り入れるメリットを知りたい KPT法の具体的な進め方について把握したい KPT法を簡単かつ効率的に進める方法が知りたい という方はこの記事を参考にすると、KPT法が企業にどのように役立つのか理解を深めつつ、実践できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 KPT法とは2 KPT法の3つのメリット2.1 (1)課題を早期発見できる2.2 (2)コミュニケーションが活性化する2.3 (3)認識を統一できる3 4ステップ|KPT法の進め方4 KPT法の3つのコツとは4.1 (1)テーマを絞り込む4.2 (2)誰でも発言しやすい環境を作る4.3 (3)KPT法を継続的に実施する5 KPT法で話し合った情報を蓄積するツール5.1 エクセルよりも簡単に情報を記録・蓄積できる「ナレカン」6 KPT法の概要や注意点まとめ KPT法とは KPT法とは振り返り手法の1つであり、業務内容の改善を促進するために用いられる方法です。具体的には、プロジェクトの全容を以下の3つに分類して振り返り、改善点や今後の施策を考えていきます。 Keep:継続すべき良かった点 Problem:解決すべき課題 Try:解決に向けて取り組むべき施策 KPT法を用いて振り返りを実施することで、プロジェクトの良かった点や反省点を分析できます。その結果、次のアクションにつながり、プロジェクトを効率よく進めていけるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ KPT法の3つのメリット ここでは、KPT法を活用することで得られるメリットを3つご紹介します。KPT法を用いて業務改善を図りたい方は必見です。 (1)課題を早期発見できる KPT法の1つ目のメリットは、課題を可視化し、早期発見できる点です。 KPTは、反省点だけでなく良かった点も整理するため、客観的な視点で課題を洗い出すことができます。その結果、課題解決に素早く取り組むことができ、後に大きな問題へと発展するリスクも抑えられるのです。 さらに、KPT法を取り入れることで、自身や組織の行動を客観的に分析して課題を見つけ出す習慣が身に付きます。以上のように、仕事内容に向き合う機会が多くなる分、課題の早期発見にもつながるのです。 (2)コミュニケーションが活性化する KPT法の2つ目のメリットは、意見交換の機会が増え、職場内のコミュニケーションが活発になる点です。 さまざまな意見が交わされることで、自身では気がつかなかった点が見つかり、あらゆる視点から解決策を見出せるようになります。また、共通の課題に対してお互いの意見を尊重しながら話し合うことで、一体感を持って課題解決に取り組めるのです。 以上のように、KPTの実施はコミュニケーションを活発化させ、組織の向上力増進が期待できます。 (3)認識を統一できる KPT法の3つ目のメリットは、物事に対しての認識を組織内で統一できる点です。 人によって課題に対する解釈が異なる可能性があるため、課題や問題は正確に共有することが大切です。そこで、KPIを通じて振り返りをすれば同じタイミングで共通認識をもてるため、今後やるべきタスクが明確になり、迅速に行動へ移すことができます。 このように、KPT法を用いると組織内での認識を統一しやすくなり、効率的に課題解決を進めることができます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 4ステップ|KPT法の進め方 ここでは、KPT法を実施するときの具体的な進め方について、表を用いて解説します。 ステップ1|振り返り用のフォーマットを作成する KPTをはじめる準備として、下図のように左上に「Keep」、左下に「Problem」、右側に「Try」と書いた表を用意します。 ステップ2|KeepとProblemを書き出す 「Keep」の欄にうまくいったこと、「Problem」の欄に課題や問題点を記載します。このとき、他人の考えに影響を受けないよう自身の意見を書き出していきましょう。 ステップ3|KeepとProblemについて話し合う ステップ2で書き出した内容について、「Problem」を中心にディスカッションします。問題とした理由や要因を突き詰めて、真相を明確にすることが大切です。 ステップ4|Tryする内容を具体的に考える 話し合いを通して明らかになった要因に対して、どのような改善策をとるのか具体的に考え、実施していきます。ここで決定したTry内容は、次回の振り返りのときに検証ポイントとして役立つため、いつでも確認できるようにしましょう。 このように、KPT法ではKeep→Problem→Tryの順にプロジェクト内容を書き出していき、良かった点や反省点を振り返っていきます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ KPT法の3つのコツとは KPT法による振り返りにはコツがあります。以下では3つのコツを解説するので、KPT法を効果的に実施したい方は必見です。 (1)テーマを絞り込む KPT法を用いた話し合いでは、テーマを絞り込むことが大切です。 たとえば、「上半期の売上実績」といった抽象的なテーマではなく、「今月のテレアポ件数」や「組織体制」など、具体的なテーマを設定しましょう。また、決定したテーマは事前に共有しておけば、会議でより活発な意見交換が期待できます。 以上のように、明確なテーマを決めてKPTを実施することで、思考を整理しやすくなり、議論の効率化も図れます。 (2)誰でも発言しやすい環境を作る KPTでは、各自が些細なことでもすぐに発言できる環境づくりが非常に大切です。 しかし、大人数の会議では、なかなか自分の意見を言いづらい場合も少なくありません。そこで、参加者を複数のグループに分けたり、進行役を設けたりすることで、さまざまな意見が出るうえ、議論も整理しやすくなるのです。 したがって、誰もが活発に意見を言える環境をつくることが、KPTを成功させるためには欠かせません。 (3)KPT法を継続的に実施する KPTを正しく機能させるためには、定期的に継続することが必須です。 前回のTry結果の振り返りによって連続性が生まれ、課題が徐々に改善されていく実感が湧きやすくなります。また、KPTを繰り返す中で新たな発見や学びがあり、自身や組織が成長していく実感を得られることは、継続していく上で大きな原動力となります。 このように、KPT法を継続的に実施することは、業務を改善していくのに効果的です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ KPT法で話し合った情報を蓄積するツール 以下では、KPT法を用いた振り返りの情報を蓄積・活用できるツールをご紹介します。 KPT法は1度きりで終わりではなく、定期的に繰り返し実施することで効果を発揮します。そして、業務を継続的に改善していくには、振り返った内容を記録して適切に管理し、会議の都度見返して次のアクションに活かしていくことが大切です。 そのため、会議で話し合った情報を簡単に記録・共有でき、必要なときにすぐ見返せる情報管理ツールを導入すべきです。しかし、検索性の低いツールでは、目的の情報を探すのに時間がかかるため、「高精度の検索機能」を備えたツールを選びましょう。 結論、効果的なKPT法の実践には、社内のあらゆる情報を一元管理でき、優れた検索性で必要な情報がすぐに見つかる「ナレカン」が最適です。 ナレカンでは、KPT法を用いた振り返りの内容を「記事」形式で簡単に記録・共有できます。また、ヒット率100%の「キーワード検索」によって、過去の内容やノウハウをすぐに見返して活用することが可能です。 エクセルよりも簡単に情報を記録・蓄積できる「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ KPT法の概要や注意点まとめ これまで、KPT法の詳細やメリット、進め方を中心にご紹介しました。 KPT法は課題の早期発見や組織力の向上につながりますが、効果を発揮するためには継続的に実施することが重要です。そのためには、会議の内容をしっかりと記録・管理し、次の会議で確認することで、次の行動につなげていく必要があります。 そこで、「情報管理ツール」を活用すると、会議内容をいつでも見返せる状態で管理でき、議論の質も向上します。とくに、検索性に優れたツールであれば、情報量が増えても必要なデータに素早くアクセスでき、より効率的に会議を進めることが可能です。 結論、KPT法を用いた会議での情報管理には、社内情報を一元的に管理・共有でき、高精度の検索機能で情報活用もしやすい「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入してKPTを継続的に実践し、業務改善を促進させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年06月26日【徹底解説】KPT法とは?振り返りの進め方やコツも紹介ビジネスを進めていくにあたり、プロジェクト終了時に振り返りをすることは重要です。とくに、KPT法を用いて振り返りを実施すると、前回の反省を生かしつつ新しいプロジェクトに入れるため、より良い成果が期待できます。 しかし、「KPTという名称は知ってはいるものの、KPT法の具体的な進め方は分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、KPT法の具体的な進め方や導入時のコツを中心にご紹介します。 KPT法の概要や取り入れるメリットを知りたい KPT法の具体的な進め方について把握したい KPT法を簡単かつ効率的に進める方法が知りたい という方はこの記事を参考にすると、KPT法が企業にどのように役立つのか理解を深めつつ、実践できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 KPT法とは2 KPT法の3つのメリット2.1 (1)課題を早期発見できる2.2 (2)コミュニケーションが活性化する2.3 (3)認識を統一できる3 4ステップ|KPT法の進め方4 KPT法の3つのコツとは4.1 (1)テーマを絞り込む4.2 (2)誰でも発言しやすい環境を作る4.3 (3)KPT法を継続的に実施する5 KPT法で話し合った情報を蓄積するツール5.1 エクセルよりも簡単に情報を記録・蓄積できる「ナレカン」6 KPT法の概要や注意点まとめ KPT法とは KPT法とは振り返り手法の1つであり、業務内容の改善を促進するために用いられる方法です。具体的には、プロジェクトの全容を以下の3つに分類して振り返り、改善点や今後の施策を考えていきます。 Keep:継続すべき良かった点 Problem:解決すべき課題 Try:解決に向けて取り組むべき施策 KPT法を用いて振り返りを実施することで、プロジェクトの良かった点や反省点を分析できます。その結果、次のアクションにつながり、プロジェクトを効率よく進めていけるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ KPT法の3つのメリット ここでは、KPT法を活用することで得られるメリットを3つご紹介します。KPT法を用いて業務改善を図りたい方は必見です。 (1)課題を早期発見できる KPT法の1つ目のメリットは、課題を可視化し、早期発見できる点です。 KPTは、反省点だけでなく良かった点も整理するため、客観的な視点で課題を洗い出すことができます。その結果、課題解決に素早く取り組むことができ、後に大きな問題へと発展するリスクも抑えられるのです。 さらに、KPT法を取り入れることで、自身や組織の行動を客観的に分析して課題を見つけ出す習慣が身に付きます。以上のように、仕事内容に向き合う機会が多くなる分、課題の早期発見にもつながるのです。 (2)コミュニケーションが活性化する KPT法の2つ目のメリットは、意見交換の機会が増え、職場内のコミュニケーションが活発になる点です。 さまざまな意見が交わされることで、自身では気がつかなかった点が見つかり、あらゆる視点から解決策を見出せるようになります。また、共通の課題に対してお互いの意見を尊重しながら話し合うことで、一体感を持って課題解決に取り組めるのです。 以上のように、KPTの実施はコミュニケーションを活発化させ、組織の向上力増進が期待できます。 (3)認識を統一できる KPT法の3つ目のメリットは、物事に対しての認識を組織内で統一できる点です。 人によって課題に対する解釈が異なる可能性があるため、課題や問題は正確に共有することが大切です。そこで、KPIを通じて振り返りをすれば同じタイミングで共通認識をもてるため、今後やるべきタスクが明確になり、迅速に行動へ移すことができます。 このように、KPT法を用いると組織内での認識を統一しやすくなり、効率的に課題解決を進めることができます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 4ステップ|KPT法の進め方 ここでは、KPT法を実施するときの具体的な進め方について、表を用いて解説します。 ステップ1|振り返り用のフォーマットを作成する KPTをはじめる準備として、下図のように左上に「Keep」、左下に「Problem」、右側に「Try」と書いた表を用意します。 ステップ2|KeepとProblemを書き出す 「Keep」の欄にうまくいったこと、「Problem」の欄に課題や問題点を記載します。このとき、他人の考えに影響を受けないよう自身の意見を書き出していきましょう。 ステップ3|KeepとProblemについて話し合う ステップ2で書き出した内容について、「Problem」を中心にディスカッションします。問題とした理由や要因を突き詰めて、真相を明確にすることが大切です。 ステップ4|Tryする内容を具体的に考える 話し合いを通して明らかになった要因に対して、どのような改善策をとるのか具体的に考え、実施していきます。ここで決定したTry内容は、次回の振り返りのときに検証ポイントとして役立つため、いつでも確認できるようにしましょう。 このように、KPT法ではKeep→Problem→Tryの順にプロジェクト内容を書き出していき、良かった点や反省点を振り返っていきます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ KPT法の3つのコツとは KPT法による振り返りにはコツがあります。以下では3つのコツを解説するので、KPT法を効果的に実施したい方は必見です。 (1)テーマを絞り込む KPT法を用いた話し合いでは、テーマを絞り込むことが大切です。 たとえば、「上半期の売上実績」といった抽象的なテーマではなく、「今月のテレアポ件数」や「組織体制」など、具体的なテーマを設定しましょう。また、決定したテーマは事前に共有しておけば、会議でより活発な意見交換が期待できます。 以上のように、明確なテーマを決めてKPTを実施することで、思考を整理しやすくなり、議論の効率化も図れます。 (2)誰でも発言しやすい環境を作る KPTでは、各自が些細なことでもすぐに発言できる環境づくりが非常に大切です。 しかし、大人数の会議では、なかなか自分の意見を言いづらい場合も少なくありません。そこで、参加者を複数のグループに分けたり、進行役を設けたりすることで、さまざまな意見が出るうえ、議論も整理しやすくなるのです。 したがって、誰もが活発に意見を言える環境をつくることが、KPTを成功させるためには欠かせません。 (3)KPT法を継続的に実施する KPTを正しく機能させるためには、定期的に継続することが必須です。 前回のTry結果の振り返りによって連続性が生まれ、課題が徐々に改善されていく実感が湧きやすくなります。また、KPTを繰り返す中で新たな発見や学びがあり、自身や組織が成長していく実感を得られることは、継続していく上で大きな原動力となります。 このように、KPT法を継続的に実施することは、業務を改善していくのに効果的です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ KPT法で話し合った情報を蓄積するツール 以下では、KPT法を用いた振り返りの情報を蓄積・活用できるツールをご紹介します。 KPT法は1度きりで終わりではなく、定期的に繰り返し実施することで効果を発揮します。そして、業務を継続的に改善していくには、振り返った内容を記録して適切に管理し、会議の都度見返して次のアクションに活かしていくことが大切です。 そのため、会議で話し合った情報を簡単に記録・共有でき、必要なときにすぐ見返せる情報管理ツールを導入すべきです。しかし、検索性の低いツールでは、目的の情報を探すのに時間がかかるため、「高精度の検索機能」を備えたツールを選びましょう。 結論、効果的なKPT法の実践には、社内のあらゆる情報を一元管理でき、優れた検索性で必要な情報がすぐに見つかる「ナレカン」が最適です。 ナレカンでは、KPT法を用いた振り返りの内容を「記事」形式で簡単に記録・共有できます。また、ヒット率100%の「キーワード検索」によって、過去の内容やノウハウをすぐに見返して活用することが可能です。 エクセルよりも簡単に情報を記録・蓄積できる「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ KPT法の概要や注意点まとめ これまで、KPT法の詳細やメリット、進め方を中心にご紹介しました。 KPT法は課題の早期発見や組織力の向上につながりますが、効果を発揮するためには継続的に実施することが重要です。そのためには、会議の内容をしっかりと記録・管理し、次の会議で確認することで、次の行動につなげていく必要があります。 そこで、「情報管理ツール」を活用すると、会議内容をいつでも見返せる状態で管理でき、議論の質も向上します。とくに、検索性に優れたツールであれば、情報量が増えても必要なデータに素早くアクセスでき、より効率的に会議を進めることが可能です。 結論、KPT法を用いた会議での情報管理には、社内情報を一元的に管理・共有でき、高精度の検索機能で情報活用もしやすい「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入してKPTを継続的に実践し、業務改善を促進させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年06月26日業務改善に欠かせないシステム化とは?意味や手順も紹介会社を運営していく上で、利益を最大限出すためには、業務の効率化は欠かせません。そこで、業務効率化を最も簡単かつ早期に実現できるのが「業務のシステム化」です。 しかし、「どのようにシステム化を進めていけば良いのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、システム化の手順や方法を中心にご紹介します。 システム化のメリット・デメリットを明らかにした上で、取り組みを進めたい システム化の具体的な進め方を把握し、今後の参考にしたい 業務のシステム化に役立つツールを知りたい という方はこの記事を参考にすると、システム化の円滑な進め方が分かり、会社の生産性を向上させられるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 システム化とは1.1 システム化の意味1.2 システム化できる業務2 システム化の3つのメリット2.1 (1)データを柔軟に管理できる2.2 (2)業務の効率化につながる2.3 (3)属人化を防げる3 【対処法あり】システム化の3つのデメリット3.1 (1)専門知識を持つ人材が必要となる3.2 (2)不正アクセスのリスクが生じる3.3 (3)導入にコストがかかる4 【マニュアル化・ルール化編】システム化の手順5 【ITシステムの導入編】システム化の手順6 【必見】業務のシステム化に役立つITツール6.1 充実した支援のもと安全にナレッジを蓄積できるツール「ナレカン」7 システム化のメリットや手順まとめ システム化とは ここでは、システム化の意味やシステム化できる業務を説明します。システム化とは具体的に何のことなのか知りたい方は必見です。 システム化の意味 システム化とは、企業が継続して一定の成果を出すために、誰がやっても同じ成果を生み出せる仕組みづくりのことです。 システム化は以下2種類に分類されます。 マニュアル・ルール化 誰が業務を担当しても業務の質を均一に保つ手法です。ITの知識がなくても簡単に導入できます。 ITシステムの導入 ITシステムを活用して定型業務を自動化し、作業効率を上昇させる手法です。ある程度のITの知識やスキルが求められます。 以上より、誰でも一定数の成果を出せる仕組みを構築するためには、マニュアルの作成やITシステムの導入による業務のシステム化が欠かせません。 システム化できる業務 システム化できる業務には以下のものが挙げられます。 勤怠管理 生産管理 在庫管理 経理 コールセンター など 以上のように、定型業務はシステム化できることが多くあります。まずは、各業務のワークフローや作業内容を見直し、システム化できるかどうかを見極めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ システム化の3つのメリット ここでは、業務をシステム化するメリットを3つご紹介します。システム化を検討している方は必見です。 (1)データを柔軟に管理できる ITツールを活用したシステム化によって、データの柔軟な管理ができるようになります。 業務をシステム化すると、今まで部署ごとでバラバラに管理されていたデータの保存先が基幹システムに統一されます。それにより、情報は基幹システムに入力させるようになるため、どの部署でもリアルタイムで同一のデータを取得することが可能となるのです。 したがって、システム化によりデータのアクセス先が統一されるため、一元管理ができるようになり、柔軟なデータ管理がしやすくなります。 (2)業務の効率化につながる システム化によって、業務工程が最適化されることで、業務の効率化につながります。 従来では、会議をするために全員が同じ場所に集まる必要がありましたが、リモートワークが普及したことで、時間や場所を問わず、仕事ができるようになりました。また、移動時間が短縮された分、他の業務に割ける時間も増えました。 結果、業務をシステム化することで、無駄な作業や時間を削減でき、業務の効率化を図れます。 (3)属人化を防げる マニュアルを整備して、誰でも同一の業務に取り組める環境を整えることで、属人化を防げるというメリットがあります。 たとえば、担当者が緊急で休んだり、退職した場合に、業務が属人化していると業務の遂行に大きな支障がでてしまいます。しかし、マニュアル化やルール化を進めて業務手順を定義しておけば、担当者以外でも業務をスムーズに進めることが可能です。 そのため、業務のシステム化を進めて、誰でも同じ作業ができるようにすると、属人化を避けられるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【対処法あり】システム化の3つのデメリット 業務をシステム化(ITシステムの導入)するデメリットと対処法を3つご紹介します。システム化にはリスクもあるため、内容をよく理解してから導入しましょう。 (1)専門知識を持つ人材が必要となる ITを活用してシステム化するには、専門知識を持つ人材が必要となりす。 ITシステムを導入すると、継続的な運用や保守をしていかなければなりません。そのため、導入にばかり目が向き、運用後にシステムを管理できる専門人材がいなければ、問題発生時に対処できず、システムの継続的な使用が困難になります。 そこで、ITシステムを導入に伴い、社内研修や外部研修を通して社員を教育しましょう。社内での人材育成が難しい場合は、専門知識を有する人材の採用や外部委託を検討しましょう。 (2)不正アクセスのリスクが生じる ITシステムを使用して情報をデータ化すると、不正アクセスされるリスクが高まります。 紙媒体と異なり、情報をデータ化して管理すると、不正アクセスによって情報漏えいするリスクが生じます。また、外部からの不正アクセスだけでなく、人為的ミスによっても情報が漏えいする可能性もあります。 したがって、外部からの不正アクセスにより情報漏洩を防ぐために、万全のセキュリティ対策をするのが大切です。また、人的ミスをなくすために、ITリテラシー教育を徹底しましょう。 (3)導入にコストがかかる ITシステムの導入には、様々なコストがかかります。 ITシステム自体の費用に加えて、システムの設定や管理をする人の人件費がかかります。さらに、社員がITシステムを安全に使えるようにするための研修や勉強会の開催など、教育コストも上乗せされるのです。 そこで、誰でも簡単に使えて、導入後にすばやく運用できるようなシステムを選ぶと、人件費や教育コストを削減できます。たとえば、「ナレカン」のように、初期設定を全て任せられるほか、ITに不慣れな人でも使いやすいものを選択しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【マニュアル化・ルール化編】システム化の手順 以下では、マニュアル化・ルール化の手順について、ステップ別に解説します。これを理解すれば、マニュアル化・ルール化をするときに、スムーズに作業を進められます。 ステップ1|システム化の対象業務を整理する 全体の業務を整理して、システム化できる工程や対象範囲を分析しましょう。これにより、開発の手間や費用などの見立てを立てやすくなります。 ステップ2|マニュアルを作成する システム化の対象となる業務が決定したら、誰でも簡単に理解して使用できるよう、その業務に関するマニュアルを作成します。マニュアルには、緊急時に現場で対応できるように、手順の解説のほか、システムの運用方法も記載しましょう。 ステップ3|業務を実行・修正する 作成したマニュアルを実際に試してみて、現場の声を聞き、わかりやすい記載かどうか確認します。また、マニュアルを使っているうちに不備やミスが見つかった場合は、速やかに修正しましょう。 以上のように、マニュアルを作成した後、実務の中で必要に応じて修正していくことが重要です。そのため、いつでもマニュアルを検索して更新できるよう、超高精度な検索機能を備えた「ナレカン」のようなツールでマニュアルを管理しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【ITシステムの導入編】システム化の手順 以下では、ITシステムの導入の手順について、ステップ別に解説します。これを理解すれば、ITシステムを導入する時は以下の順序を意識しましょう。 ステップ1|目的や課題の明確化 システムを導入する目的や現状の課題を明確化しましょう。目的と課題がはっきりすると、必要なシステムの選定が容易になるほか、社員からもシステムの導入を受け入れてもらいやすくなります。 ステップ2|他社事例の調査やヒアリングをする 他社におけるシステムの導入事例に関する情報を収集したり、専門家からのアドバイスをもらったりしましょう。導入後の活用イメージが掴めるため、参考になります。 ステップ3|システム化の対象業務を洗い出す システム化したい業務を洗い出します。このとき、目的や課題から逆算して、システム化する優先順位を決めると、スムーズにシステム化を進められます。 ステップ4|システムを導入する システム化の対象業や自社のニーズをもとにシステムを選定し、導入します。システム導入後の運用まで見据えて、「ナレカン」のように誰でも使いやすいシステムを選ぶのも一つのポイントです。 ステップ5|効果検証を実施する システム導入後は、定期的に効果検証を実施しましょう。効果検証で想定通りの成果が出ていない場合は、問題点を抽出し、システムに改良を加えるといったように、PDCAを回していくことが大切です。 以上のように、ITツールの導入においては、システム導入前の確認や調査を徹底するだけでなく、導入後にも繰り返し改善していくことが求められます。 【必見】業務のシステム化に役立つITツール 以下では、業務のシステム化(マニュアル化・ルール化)に役立つツールをご紹介します。 システム化は、業務効率の向上や社内情報の蓄積に欠かせない施策です。しかし、ITに不慣れな社員が多い職場では、導入後の設定ミスや誤操作による情報漏えいのリスクが懸念されるうえ、運用定着に時間がかかるという課題もあります。 そこで「高度なセキュリティ対策」と「導入後のサポート体制」が整ったITツールの選定が重要です。とくに、導入時には現場はトラブルが発生しやすいため、ヘルプデスクなどで「現場をしっかり支援してくれるナレッジ管理ツール」を導入が最適です。 結論、自社のシステム化に最適なのは、高セキュアかつ充実したサポートでシステム化を推進できるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」では、情報セキュリティの国際規格認証を取得したほどの高いセキュリティで、記事内に記載されたマニュアルやルールの情報を安全に管理します。また、既存データ移行支援や初期導入支援で、導入時のコストを軽減し、円滑な運用につなげます。 充実した支援のもと安全にナレッジを蓄積できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ システム化のメリットや手順まとめ これまで、システム化のメリットやデメリット、手順を中心にご紹介しました。 ITの導入によるシステム化は、会社全体の効率を上げて、属人化を防ぐためにも欠かせません。そのためには、マニュアルを作成して、誰でも同じように作業できる仕組み作りが必要です。 しかし、マニュアルを作成しても適切に管理されていないと、使われなくなったり探すのに手間取ったりと、かえって非効率になる可能性があります。そのため、必要なマニュアルをすぐに見つけ出せるよう、優れた検索性を持つITツールで管理しましょう。 結論、業務のシステム化には、マニュアルを整理して管理し、必要な情報に即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、システム化を図りましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年06月26日業務改善に欠かせないシステム化とは?意味や手順も紹介会社を運営していく上で、利益を最大限出すためには、業務の効率化は欠かせません。そこで、業務効率化を最も簡単かつ早期に実現できるのが「業務のシステム化」です。 しかし、「どのようにシステム化を進めていけば良いのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、システム化の手順や方法を中心にご紹介します。 システム化のメリット・デメリットを明らかにした上で、取り組みを進めたい システム化の具体的な進め方を把握し、今後の参考にしたい 業務のシステム化に役立つツールを知りたい という方はこの記事を参考にすると、システム化の円滑な進め方が分かり、会社の生産性を向上させられるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 システム化とは1.1 システム化の意味1.2 システム化できる業務2 システム化の3つのメリット2.1 (1)データを柔軟に管理できる2.2 (2)業務の効率化につながる2.3 (3)属人化を防げる3 【対処法あり】システム化の3つのデメリット3.1 (1)専門知識を持つ人材が必要となる3.2 (2)不正アクセスのリスクが生じる3.3 (3)導入にコストがかかる4 【マニュアル化・ルール化編】システム化の手順5 【ITシステムの導入編】システム化の手順6 【必見】業務のシステム化に役立つITツール6.1 充実した支援のもと安全にナレッジを蓄積できるツール「ナレカン」7 システム化のメリットや手順まとめ システム化とは ここでは、システム化の意味やシステム化できる業務を説明します。システム化とは具体的に何のことなのか知りたい方は必見です。 システム化の意味 システム化とは、企業が継続して一定の成果を出すために、誰がやっても同じ成果を生み出せる仕組みづくりのことです。 システム化は以下2種類に分類されます。 マニュアル・ルール化 誰が業務を担当しても業務の質を均一に保つ手法です。ITの知識がなくても簡単に導入できます。 ITシステムの導入 ITシステムを活用して定型業務を自動化し、作業効率を上昇させる手法です。ある程度のITの知識やスキルが求められます。 以上より、誰でも一定数の成果を出せる仕組みを構築するためには、マニュアルの作成やITシステムの導入による業務のシステム化が欠かせません。 システム化できる業務 システム化できる業務には以下のものが挙げられます。 勤怠管理 生産管理 在庫管理 経理 コールセンター など 以上のように、定型業務はシステム化できることが多くあります。まずは、各業務のワークフローや作業内容を見直し、システム化できるかどうかを見極めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ システム化の3つのメリット ここでは、業務をシステム化するメリットを3つご紹介します。システム化を検討している方は必見です。 (1)データを柔軟に管理できる ITツールを活用したシステム化によって、データの柔軟な管理ができるようになります。 業務をシステム化すると、今まで部署ごとでバラバラに管理されていたデータの保存先が基幹システムに統一されます。それにより、情報は基幹システムに入力させるようになるため、どの部署でもリアルタイムで同一のデータを取得することが可能となるのです。 したがって、システム化によりデータのアクセス先が統一されるため、一元管理ができるようになり、柔軟なデータ管理がしやすくなります。 (2)業務の効率化につながる システム化によって、業務工程が最適化されることで、業務の効率化につながります。 従来では、会議をするために全員が同じ場所に集まる必要がありましたが、リモートワークが普及したことで、時間や場所を問わず、仕事ができるようになりました。また、移動時間が短縮された分、他の業務に割ける時間も増えました。 結果、業務をシステム化することで、無駄な作業や時間を削減でき、業務の効率化を図れます。 (3)属人化を防げる マニュアルを整備して、誰でも同一の業務に取り組める環境を整えることで、属人化を防げるというメリットがあります。 たとえば、担当者が緊急で休んだり、退職した場合に、業務が属人化していると業務の遂行に大きな支障がでてしまいます。しかし、マニュアル化やルール化を進めて業務手順を定義しておけば、担当者以外でも業務をスムーズに進めることが可能です。 そのため、業務のシステム化を進めて、誰でも同じ作業ができるようにすると、属人化を避けられるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【対処法あり】システム化の3つのデメリット 業務をシステム化(ITシステムの導入)するデメリットと対処法を3つご紹介します。システム化にはリスクもあるため、内容をよく理解してから導入しましょう。 (1)専門知識を持つ人材が必要となる ITを活用してシステム化するには、専門知識を持つ人材が必要となりす。 ITシステムを導入すると、継続的な運用や保守をしていかなければなりません。そのため、導入にばかり目が向き、運用後にシステムを管理できる専門人材がいなければ、問題発生時に対処できず、システムの継続的な使用が困難になります。 そこで、ITシステムを導入に伴い、社内研修や外部研修を通して社員を教育しましょう。社内での人材育成が難しい場合は、専門知識を有する人材の採用や外部委託を検討しましょう。 (2)不正アクセスのリスクが生じる ITシステムを使用して情報をデータ化すると、不正アクセスされるリスクが高まります。 紙媒体と異なり、情報をデータ化して管理すると、不正アクセスによって情報漏えいするリスクが生じます。また、外部からの不正アクセスだけでなく、人為的ミスによっても情報が漏えいする可能性もあります。 したがって、外部からの不正アクセスにより情報漏洩を防ぐために、万全のセキュリティ対策をするのが大切です。また、人的ミスをなくすために、ITリテラシー教育を徹底しましょう。 (3)導入にコストがかかる ITシステムの導入には、様々なコストがかかります。 ITシステム自体の費用に加えて、システムの設定や管理をする人の人件費がかかります。さらに、社員がITシステムを安全に使えるようにするための研修や勉強会の開催など、教育コストも上乗せされるのです。 そこで、誰でも簡単に使えて、導入後にすばやく運用できるようなシステムを選ぶと、人件費や教育コストを削減できます。たとえば、「ナレカン」のように、初期設定を全て任せられるほか、ITに不慣れな人でも使いやすいものを選択しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【マニュアル化・ルール化編】システム化の手順 以下では、マニュアル化・ルール化の手順について、ステップ別に解説します。これを理解すれば、マニュアル化・ルール化をするときに、スムーズに作業を進められます。 ステップ1|システム化の対象業務を整理する 全体の業務を整理して、システム化できる工程や対象範囲を分析しましょう。これにより、開発の手間や費用などの見立てを立てやすくなります。 ステップ2|マニュアルを作成する システム化の対象となる業務が決定したら、誰でも簡単に理解して使用できるよう、その業務に関するマニュアルを作成します。マニュアルには、緊急時に現場で対応できるように、手順の解説のほか、システムの運用方法も記載しましょう。 ステップ3|業務を実行・修正する 作成したマニュアルを実際に試してみて、現場の声を聞き、わかりやすい記載かどうか確認します。また、マニュアルを使っているうちに不備やミスが見つかった場合は、速やかに修正しましょう。 以上のように、マニュアルを作成した後、実務の中で必要に応じて修正していくことが重要です。そのため、いつでもマニュアルを検索して更新できるよう、超高精度な検索機能を備えた「ナレカン」のようなツールでマニュアルを管理しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【ITシステムの導入編】システム化の手順 以下では、ITシステムの導入の手順について、ステップ別に解説します。これを理解すれば、ITシステムを導入する時は以下の順序を意識しましょう。 ステップ1|目的や課題の明確化 システムを導入する目的や現状の課題を明確化しましょう。目的と課題がはっきりすると、必要なシステムの選定が容易になるほか、社員からもシステムの導入を受け入れてもらいやすくなります。 ステップ2|他社事例の調査やヒアリングをする 他社におけるシステムの導入事例に関する情報を収集したり、専門家からのアドバイスをもらったりしましょう。導入後の活用イメージが掴めるため、参考になります。 ステップ3|システム化の対象業務を洗い出す システム化したい業務を洗い出します。このとき、目的や課題から逆算して、システム化する優先順位を決めると、スムーズにシステム化を進められます。 ステップ4|システムを導入する システム化の対象業や自社のニーズをもとにシステムを選定し、導入します。システム導入後の運用まで見据えて、「ナレカン」のように誰でも使いやすいシステムを選ぶのも一つのポイントです。 ステップ5|効果検証を実施する システム導入後は、定期的に効果検証を実施しましょう。効果検証で想定通りの成果が出ていない場合は、問題点を抽出し、システムに改良を加えるといったように、PDCAを回していくことが大切です。 以上のように、ITツールの導入においては、システム導入前の確認や調査を徹底するだけでなく、導入後にも繰り返し改善していくことが求められます。 【必見】業務のシステム化に役立つITツール 以下では、業務のシステム化(マニュアル化・ルール化)に役立つツールをご紹介します。 システム化は、業務効率の向上や社内情報の蓄積に欠かせない施策です。しかし、ITに不慣れな社員が多い職場では、導入後の設定ミスや誤操作による情報漏えいのリスクが懸念されるうえ、運用定着に時間がかかるという課題もあります。 そこで「高度なセキュリティ対策」と「導入後のサポート体制」が整ったITツールの選定が重要です。とくに、導入時には現場はトラブルが発生しやすいため、ヘルプデスクなどで「現場をしっかり支援してくれるナレッジ管理ツール」を導入が最適です。 結論、自社のシステム化に最適なのは、高セキュアかつ充実したサポートでシステム化を推進できるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」では、情報セキュリティの国際規格認証を取得したほどの高いセキュリティで、記事内に記載されたマニュアルやルールの情報を安全に管理します。また、既存データ移行支援や初期導入支援で、導入時のコストを軽減し、円滑な運用につなげます。 充実した支援のもと安全にナレッジを蓄積できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ システム化のメリットや手順まとめ これまで、システム化のメリットやデメリット、手順を中心にご紹介しました。 ITの導入によるシステム化は、会社全体の効率を上げて、属人化を防ぐためにも欠かせません。そのためには、マニュアルを作成して、誰でも同じように作業できる仕組み作りが必要です。 しかし、マニュアルを作成しても適切に管理されていないと、使われなくなったり探すのに手間取ったりと、かえって非効率になる可能性があります。そのため、必要なマニュアルをすぐに見つけ出せるよう、優れた検索性を持つITツールで管理しましょう。 結論、業務のシステム化には、マニュアルを整理して管理し、必要な情報に即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、システム化を図りましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年06月26日Data Knowledgeとは?価格や機能・評判を紹介ビジネス活動を通して得たデータは、単純に蓄積しているだけでは、業務に活かすことができません。そのため、多くの企業ではBI(ビジネスインテリジェンス)ツールによってデータを分析し、生産性向上に役立てているのです。 たとえば、「Data Knowledge(データナレッジ)」も高性能なBIツールのひとつです。しかし、「Data Knowledgeの特徴や機能がわからず、自社への導入に踏み切れない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、Data Knowledgeの使い方や料金・評判を中心にご紹介します。 Data Knowledgeの特徴や価格について知りたい Data Knowledgeの機能が自社に合うか検討したい 自社に最適な社内データの管理ツールを教えてほしい という方はこの記事を参考にすると、Data Knowledgeの具体的な活用方法がわかり、社内のデータ活用が効率化します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 Data Knowledgeとは1.1 「Data Knowledge」と「Power BI」との違いとは1.2 Data Knowledgeの機能2 Data Knowledgeの使い方2.1 データ作成・出力2.2 ナレッジ共有3 Data Knowledgeの料金プラン一覧4 Data Knowledgeの口コミ・評判4.1 良い口コミ・評判4.2 改善点に関する口コミ・評判5 社内のあらゆるデータを一元管理できるおすすめツール5.1 社内の情報を最も簡単に管理・共有できるツール「ナレカン」6 Data Knowledgeの使い方や料金・評判まとめ Data Knowledgeとは Data Knowledgeとは、全社的なデータ活用を実現するナレッジ共有型BIツールです。部署を問わずに高品質なデータ分析ができるので、経営が可視化され、そして業務効率の向上に貢献します。 「Data Knowledge」と「Power BI」との違いとは 引用:Data Knowledge|公式ページ 「Data Knowledge」と「Power BI」の大きな違いは、「Data Knowledge」が「ナレッジ共有機能」による社内ノウハウの蓄積と活用に強みを持つ点です。 「Power BI」はMicrosoftエコシステムとの親和性、AIやビッグデータ分析への対応力を強みとしています。一方、「Data Knowledge」はデータの分析に加え、分析ノウハウや検索画面を含めたナレッジを共有でき、評価が付けられるため、有益な情報を簡単に把握することが可能です。 そのため、AIを活用しデータを抽出できる機能を持つ「Power BI」は効率的なデータ分析が可能ですが、「Data Knowledge」では、ナレッジ・ノウハウの共有での組織全体のデータリテラシー向上による、業務の効率化が期待できます。 ・Data Knowledgeの公式サイトはこちら Data Knowledgeの機能 Data Knowledgeの機能は、以下の4つがあります。 「データ作成・出力」機能 蓄積データを統合・加工して、出力してレポートを作成できます。 「ナレッジ共有」機能 社内で作成された分析ノウハウを公開・共有できます。 「権限・ログ管理」機能 サーバー管理者が各データの閲覧権限を細かく設定できます。 「外部アプリケーション連携」機能 Data Knowledgeの持つ分析機能を外部のツールでも利用可能にします。 以上の機能が備わっているので、Data Knowledgeはビジネスを支える基幹システムとして役立つのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Data Knowledgeの使い方 ここでは、Data Knowledgeの使い方を解説します。以下の使用方法を押さえ、自社での活用イメージを深めましょう。 データ作成・出力 引用:Data Knowledge|「データ作成・出力」機能 Data Knowledgeでは、社内に散在するデータを統合でき、データベースとして活用可能です。 たとえば、データベースからドラッグ&ドロップの簡単な操作でデータを抽出すると、レポート作成に活用できます。また、関数や数式の指定や結合実績のあるファイルの自動的な結合など、データを円滑に出力する機能も盛り込まれています。 以上の機能から、週次レポートのような定期的な資料作成にも手間がかかりません。 ナレッジ共有 引用:Data Knowledge|「ナレッジ共有」機能 Data Knowledgeは、ユーザーのデータ集計や分析手法をナレッジとして共有します。 異なるデータベースの結合や特定条件でのデータ抽出など、データの分析ノウハウに加え、検索画面やレポートを含めたナレッジを共有できます。さらに、各ナレッジは評価をつけられるので、評価の高い有益なナレッジを把握可能です。 そのため、ナレッジの共有により分析作業を短縮できるだけでなく、データ分析の属人化予防や従業員の分析力向上につながります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Data Knowledgeの料金プラン一覧 Data Knowledgeは、ユーザーライセンス種別の料金体系を用意しています。 1サーバーあたりの基本利用料金は500,000円(標準ユーザーライセンス1つ含む)です。 標準 閲覧・実行限定 閲覧限定 料金/ユーザー 12,000円 8,400円 6,000円 デザイン作成 あり なし なし 共有 あり なし なし 処理実行 あり あり なし 結果閲覧 あり あり デザインは制限 また、Data Knowledgeでは用途によって、以下のオプションを付与できます。 Webサービス ファイル出力 認証API 機能 外部アプリケーションとの連携 サーバーディスクへのファイル出力 別サイトからのシングルサインオン 料金/サーバー 300,000円 300,000円 100,000円 さらに、以上の料金の15%が保守基本サービス料の年間費用としてかかります。 上記の1ユーザーあたりのライセンス料は、追加ライセンス数が51以上の場合には、割引を適用できます。また、30日間の無料トライアルも利用可能なので、自社への導入を検討する場合は、サービスの運営会社まで問い合わせましょう。 参照:Data Knowledge|Data Knowledgeの価格 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Data Knowledgeの口コミ・評判 ここでは、「良い口コミ・評判」と「改善点に関する口コミ・評判」をご紹介します。自社への導入を検討するときは、実際にツールを活用したユーザーの声を参考にしましょう。 ※以下の口コミ・評判はITトレンドから引用しています。 良い口コミ・評判 以下では、Data Knowledgeの良い口コミ・評判をご紹介します。ユーザーからは「資料を自由に作成できる」「資料の質を高められる」といった声があがっています。 非公開ユーザー(投稿日:2022年7月16日) 自分たちで好きな様に最新のデータをアウトプット・加工し、任意のレポートを比較的簡単に作成できるのが魅力です。複雑なデータ加工処理や任意項目の追加も容易に可能であり、よくデザインされていると思います。(参考:ITトレンド) 非公開ユーザー(投稿日:2021年4月12日) 膨大なデータの分析作業と図表の作成に際して、アプリケーションの機能に則って作業をすることでいつの間にかそれなりな仕上がりの資料が出来ている。どういった資料を作るべきか迷っているときのヒントにもなるようなアプリケーションだと感じている。(参考:ITトレンド) 非公開ユーザー(投稿日:2021年3月31日) 必要なデータ・日付のみ大量の元データから抽出することができる。また、CSV・エクセル・表など自分の思い描くとおりに作成することができる。(参考:ITトレンド) 改善点に関する口コミ・評判 以下では、Data Knowledgeの改善点に関する口コミ・評判をご紹介します。ユーザーからは、「専門的である」「使いこなすのが難しい」といった声が寄せられています。 非公開ユーザー(投稿日:2022年7月16日) 例えば事務所内に設置されているプリントへのアクセス・印刷など、外部ソフトウェア・システムとの連携がよりスムーズになると使い勝手が向上します。(参考:ITトレンド) 非公開ユーザー(投稿日:2021年4月12日) 自社ではこのアプリケーションの使用方法を説明するための研修を実施しているが、実際そういった研修なしには上手く使いこなせないような少々専門的で操作の複雑なサービスで、この難しさがある程度簡便になればいいなとは思う。(参考:ITトレンド) 非公開ユーザー(投稿日:2021年3月31日) 抽出元のデータがどれを選べばよいかわかりにくい。私以外にも使いこなせていない人がたくさんいるので説明会を開いてほしい。(参考:ITトレンド) 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内のあらゆるデータを一元管理できるおすすめツール 以下では、社内のあらゆるデータを一元管理できるおすすめツールをご紹介します。 Data Knowledgeはデータの分析機能が豊富なBIツールであり、社内に蓄積された膨大なデータを可視化・分析し、意思決定を支えます。しかし、「データから読み取った示唆」や「現場の解釈・判断・施策案」などは、BIツールだけでは記録・共有しづらいという課題があります。 たとえば、分析担当者が出した考察が、担当部署内だけにとどまってしまったり、数値の変化に対する現場の対応や背景情報が“個人の頭の中”に埋もれてしまったりするリスクがあるのです。そのため、BIで可視化された数値は、背景情報や施策、施策の効果などを含めてナレッジとして共有しなくてはなりません。 結論、自社でBIツールと併用するべきなのは、BIツールで可視化したデータをもとに分析~改善のサイクルのナレッジを管理できるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは、分析結果や施策の背景を記録・共有できるので、データを再現性ある知見へ昇華可能です。また、共有したナレッジは、超高精度な検索機能により、すばやく検索可能なので、組織の意思決定が円滑化します。 社内の情報を最も簡単に管理・共有できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Data Knowledgeの使い方や料金・評判まとめ これまで、Data Knowledgeの使い方や料金・評判を中心にご紹介しました。 全社的なデータ活用とナレッジ共有に役立つ「Data Knowledge」を活用すると、高度なデータ分析や自由度の高いレポートによって、社内の生産性を高められます。しかし、BIツールでは「データ解析で得られた洞察」や「現場での判断・対策提案」の記録・共有が困難という問題があります。 例として、解析者の見解が担当チーム内に限定されたり、数値変動への現場対応や背景が”担当者の記憶”に留まるリスクが存在します。そこで、BIで表示された数値は、背景や対策、対策結果を含むノウハウとして共有する必要があります。 結論、自社が導入すべきなのは、BIツールで分析データのナレッジを最大限活用できる状態で管理できるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、社内のデータ活用の悩みを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年06月26日Data Knowledgeとは?価格や機能・評判を紹介ビジネス活動を通して得たデータは、単純に蓄積しているだけでは、業務に活かすことができません。そのため、多くの企業ではBI(ビジネスインテリジェンス)ツールによってデータを分析し、生産性向上に役立てているのです。 たとえば、「Data Knowledge(データナレッジ)」も高性能なBIツールのひとつです。しかし、「Data Knowledgeの特徴や機能がわからず、自社への導入に踏み切れない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、Data Knowledgeの使い方や料金・評判を中心にご紹介します。 Data Knowledgeの特徴や価格について知りたい Data Knowledgeの機能が自社に合うか検討したい 自社に最適な社内データの管理ツールを教えてほしい という方はこの記事を参考にすると、Data Knowledgeの具体的な活用方法がわかり、社内のデータ活用が効率化します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 Data Knowledgeとは1.1 「Data Knowledge」と「Power BI」との違いとは1.2 Data Knowledgeの機能2 Data Knowledgeの使い方2.1 データ作成・出力2.2 ナレッジ共有3 Data Knowledgeの料金プラン一覧4 Data Knowledgeの口コミ・評判4.1 良い口コミ・評判4.2 改善点に関する口コミ・評判5 社内のあらゆるデータを一元管理できるおすすめツール5.1 社内の情報を最も簡単に管理・共有できるツール「ナレカン」6 Data Knowledgeの使い方や料金・評判まとめ Data Knowledgeとは Data Knowledgeとは、全社的なデータ活用を実現するナレッジ共有型BIツールです。部署を問わずに高品質なデータ分析ができるので、経営が可視化され、そして業務効率の向上に貢献します。 「Data Knowledge」と「Power BI」との違いとは 引用:Data Knowledge|公式ページ 「Data Knowledge」と「Power BI」の大きな違いは、「Data Knowledge」が「ナレッジ共有機能」による社内ノウハウの蓄積と活用に強みを持つ点です。 「Power BI」はMicrosoftエコシステムとの親和性、AIやビッグデータ分析への対応力を強みとしています。一方、「Data Knowledge」はデータの分析に加え、分析ノウハウや検索画面を含めたナレッジを共有でき、評価が付けられるため、有益な情報を簡単に把握することが可能です。 そのため、AIを活用しデータを抽出できる機能を持つ「Power BI」は効率的なデータ分析が可能ですが、「Data Knowledge」では、ナレッジ・ノウハウの共有での組織全体のデータリテラシー向上による、業務の効率化が期待できます。 ・Data Knowledgeの公式サイトはこちら Data Knowledgeの機能 Data Knowledgeの機能は、以下の4つがあります。 「データ作成・出力」機能 蓄積データを統合・加工して、出力してレポートを作成できます。 「ナレッジ共有」機能 社内で作成された分析ノウハウを公開・共有できます。 「権限・ログ管理」機能 サーバー管理者が各データの閲覧権限を細かく設定できます。 「外部アプリケーション連携」機能 Data Knowledgeの持つ分析機能を外部のツールでも利用可能にします。 以上の機能が備わっているので、Data Knowledgeはビジネスを支える基幹システムとして役立つのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Data Knowledgeの使い方 ここでは、Data Knowledgeの使い方を解説します。以下の使用方法を押さえ、自社での活用イメージを深めましょう。 データ作成・出力 引用:Data Knowledge|「データ作成・出力」機能 Data Knowledgeでは、社内に散在するデータを統合でき、データベースとして活用可能です。 たとえば、データベースからドラッグ&ドロップの簡単な操作でデータを抽出すると、レポート作成に活用できます。また、関数や数式の指定や結合実績のあるファイルの自動的な結合など、データを円滑に出力する機能も盛り込まれています。 以上の機能から、週次レポートのような定期的な資料作成にも手間がかかりません。 ナレッジ共有 引用:Data Knowledge|「ナレッジ共有」機能 Data Knowledgeは、ユーザーのデータ集計や分析手法をナレッジとして共有します。 異なるデータベースの結合や特定条件でのデータ抽出など、データの分析ノウハウに加え、検索画面やレポートを含めたナレッジを共有できます。さらに、各ナレッジは評価をつけられるので、評価の高い有益なナレッジを把握可能です。 そのため、ナレッジの共有により分析作業を短縮できるだけでなく、データ分析の属人化予防や従業員の分析力向上につながります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Data Knowledgeの料金プラン一覧 Data Knowledgeは、ユーザーライセンス種別の料金体系を用意しています。 1サーバーあたりの基本利用料金は500,000円(標準ユーザーライセンス1つ含む)です。 標準 閲覧・実行限定 閲覧限定 料金/ユーザー 12,000円 8,400円 6,000円 デザイン作成 あり なし なし 共有 あり なし なし 処理実行 あり あり なし 結果閲覧 あり あり デザインは制限 また、Data Knowledgeでは用途によって、以下のオプションを付与できます。 Webサービス ファイル出力 認証API 機能 外部アプリケーションとの連携 サーバーディスクへのファイル出力 別サイトからのシングルサインオン 料金/サーバー 300,000円 300,000円 100,000円 さらに、以上の料金の15%が保守基本サービス料の年間費用としてかかります。 上記の1ユーザーあたりのライセンス料は、追加ライセンス数が51以上の場合には、割引を適用できます。また、30日間の無料トライアルも利用可能なので、自社への導入を検討する場合は、サービスの運営会社まで問い合わせましょう。 参照:Data Knowledge|Data Knowledgeの価格 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Data Knowledgeの口コミ・評判 ここでは、「良い口コミ・評判」と「改善点に関する口コミ・評判」をご紹介します。自社への導入を検討するときは、実際にツールを活用したユーザーの声を参考にしましょう。 ※以下の口コミ・評判はITトレンドから引用しています。 良い口コミ・評判 以下では、Data Knowledgeの良い口コミ・評判をご紹介します。ユーザーからは「資料を自由に作成できる」「資料の質を高められる」といった声があがっています。 非公開ユーザー(投稿日:2022年7月16日) 自分たちで好きな様に最新のデータをアウトプット・加工し、任意のレポートを比較的簡単に作成できるのが魅力です。複雑なデータ加工処理や任意項目の追加も容易に可能であり、よくデザインされていると思います。(参考:ITトレンド) 非公開ユーザー(投稿日:2021年4月12日) 膨大なデータの分析作業と図表の作成に際して、アプリケーションの機能に則って作業をすることでいつの間にかそれなりな仕上がりの資料が出来ている。どういった資料を作るべきか迷っているときのヒントにもなるようなアプリケーションだと感じている。(参考:ITトレンド) 非公開ユーザー(投稿日:2021年3月31日) 必要なデータ・日付のみ大量の元データから抽出することができる。また、CSV・エクセル・表など自分の思い描くとおりに作成することができる。(参考:ITトレンド) 改善点に関する口コミ・評判 以下では、Data Knowledgeの改善点に関する口コミ・評判をご紹介します。ユーザーからは、「専門的である」「使いこなすのが難しい」といった声が寄せられています。 非公開ユーザー(投稿日:2022年7月16日) 例えば事務所内に設置されているプリントへのアクセス・印刷など、外部ソフトウェア・システムとの連携がよりスムーズになると使い勝手が向上します。(参考:ITトレンド) 非公開ユーザー(投稿日:2021年4月12日) 自社ではこのアプリケーションの使用方法を説明するための研修を実施しているが、実際そういった研修なしには上手く使いこなせないような少々専門的で操作の複雑なサービスで、この難しさがある程度簡便になればいいなとは思う。(参考:ITトレンド) 非公開ユーザー(投稿日:2021年3月31日) 抽出元のデータがどれを選べばよいかわかりにくい。私以外にも使いこなせていない人がたくさんいるので説明会を開いてほしい。(参考:ITトレンド) 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内のあらゆるデータを一元管理できるおすすめツール 以下では、社内のあらゆるデータを一元管理できるおすすめツールをご紹介します。 Data Knowledgeはデータの分析機能が豊富なBIツールであり、社内に蓄積された膨大なデータを可視化・分析し、意思決定を支えます。しかし、「データから読み取った示唆」や「現場の解釈・判断・施策案」などは、BIツールだけでは記録・共有しづらいという課題があります。 たとえば、分析担当者が出した考察が、担当部署内だけにとどまってしまったり、数値の変化に対する現場の対応や背景情報が“個人の頭の中”に埋もれてしまったりするリスクがあるのです。そのため、BIで可視化された数値は、背景情報や施策、施策の効果などを含めてナレッジとして共有しなくてはなりません。 結論、自社でBIツールと併用するべきなのは、BIツールで可視化したデータをもとに分析~改善のサイクルのナレッジを管理できるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは、分析結果や施策の背景を記録・共有できるので、データを再現性ある知見へ昇華可能です。また、共有したナレッジは、超高精度な検索機能により、すばやく検索可能なので、組織の意思決定が円滑化します。 社内の情報を最も簡単に管理・共有できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Data Knowledgeの使い方や料金・評判まとめ これまで、Data Knowledgeの使い方や料金・評判を中心にご紹介しました。 全社的なデータ活用とナレッジ共有に役立つ「Data Knowledge」を活用すると、高度なデータ分析や自由度の高いレポートによって、社内の生産性を高められます。しかし、BIツールでは「データ解析で得られた洞察」や「現場での判断・対策提案」の記録・共有が困難という問題があります。 例として、解析者の見解が担当チーム内に限定されたり、数値変動への現場対応や背景が”担当者の記憶”に留まるリスクが存在します。そこで、BIで表示された数値は、背景や対策、対策結果を含むノウハウとして共有する必要があります。 結論、自社が導入すべきなのは、BIツールで分析データのナレッジを最大限活用できる状態で管理できるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、社内のデータ活用の悩みを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
最新の投稿
おすすめ記事

