ナレッジマネジメント
お役立ちガイド
ナレッジマネジメントのノウハウや、
効率化のポイントなど、
ビジネスで役立つ情報をご紹介します。
効率化のポイントなど、
ビジネスで役立つ情報をご紹介します。

最新記事
-
 2025年03月26日「すごい」と言われる議事録の取り方は?フォーマットや作成例も紹介!会議内容の共有には、概要が記載された「議事録」が使われます。すなわち、議事録は、欠席者に会議内容を把握させる重要な役割を担っているのです。 しかし、良い議事録を作成できていないために、社員間で認識のずれが生じて困っている方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、「すごい」と言われる議事録の取り方や、フォーマット例を紹介します。 議事録の具体例やダメな例を踏まえて取り方を改善したい コツをもとにわかりやすい議事録を取れるようになりたい 簡単に議事録を作成・共有できるツールがあれば活用したい という方はこの記事を参考にすると、議事録が上手い人の取り方が分かるほか、すぐに使えるテンプレートも見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 議事録の作成目的2 ダメな議事録の例3 【見本】議事録の取り方例3.1 議事録の具体例3.2 7つの必要項目4 3ステップ|議事録の作成手順4.1 (1)事前に準備する4.2 (2)メモを取る4.3 (3)議事録を執筆する5 議事録を上手くとる方法は?コツ5選5.1 (1)テンプレートを利用する5.2 (2)FOCEPを使いこなす5.3 (3)主語述語を明記する5.4 (4)定量的な情報を記載する5.5 (5)ツールを活用する6 【必見】非IT企業の社員でもすぐに使えるツール6.1 必要な機能に過不足がないシンプルなツール「ナレカン」6.2 ナレカンを使った議事録の作成例7 すごい議事録の取り方・コツ・フォーマットまとめ 議事録の作成目的 議事録を作成する際には、以下で紹介する3つの目的を正しく理解する必要があります。 決定事項やタスクを記録するため 議事録は、会議で決定した事項やタスクを可視化する役割を果たしています。 正確な情報を共有するため 議事録を使えば、会議の欠席者に正確な情報を届けられるので、認識のずれを防げます。 責任の所在を明確にするため それぞれの発言をした社員名が記録されていれば、責任の所在が明確になるので「言った・言わない」のトラブルを防げます。 上記の目的を理解して、必要な情報が漏れなく記載された議事録を作成しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ダメな議事録の例 以下では、ダメ出しを受けてしまうような議事録の例を3つ紹介します。 結論が不明瞭 会議中の情報をできるだけ詰め込んだ結果として、最終的な結論が分かりづらい・あいまいになってしまう議事録があります。他の作業で忙しく、「結論のみ知りたい」という社員もいるため、まず結論は明確にしましょう。 会議に参加していない社員が理解できない 会議に参加した社員しか内容が理解できない議事録では、「情報共有」という議事録の作成目的が果たせません。会議に参加していない社員でもスムーズに理解できるか、読み手の立場に立って作成しましょう。 意思決定の過程が分からない 結論は記載されているものの、決定するまでの過程が記載されていないと、どのような議論がなされたのか・誰が発言したのか分かりません。会議の過程も残すことで、議論の経緯を正確に把握できるのです。 上記の3つを意識するだけで、議事録の読みやすさは大きく変わります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【見本】議事録の取り方例 以下では、議事録の具体例と作成に必要な項目を紹介します。上手く議事録が取れずに悩んでいる方は必見です。 議事録の具体例 以下は、株主総会議事録です。株主総会議事録とは、株主総会を開催した際に会社法によって作成が義務付けられている資料で、会社法施行規則によって記載事項が定められています。 会社法第318条議事録 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 下記のサンプルを参考に、正式な様式に則った議事録を作成しましょう。 定時株主総会 1. 日時 令和○年○月○日○時○分〜○時○分 2. 場所 当社会議室 3. 出席者 議決権のある総株主数 ○名 この議決権の総数 ○個 出席株主数 ○名 この議決権の総数 ○個 4. 出席役員 代表取締役 ○○ 取締役 ○○ 監査役 ○○ 5. 議事の結果の要領及びその結果 以上の通り株主の出席があり、定款の定めにより本定時総会は適法に成立したので、議長は開会する旨を宣し、議事に入った。 第1号議案:決算報告書の承認に関する件 … 第2号議案:取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件 … 6. 閉会 議長は以上をもって本日の議事が終了した旨を述べ、○時○分閉会した。 上記の決議を明確にするため、この議事をつくり、議長及び役員がこれに記名する。 令和○年○月○日 ○○株式会社 定時株主総会 代表取締役 ○○ 取締役 ○○ 監査役 ○○ 参考: 定時・臨時株主総会議事録 書き方・書式 雛形(ひな形) テンプレート01 【添付書面】01_取締役会設置会社・全員重任 7つの必要項目 以下では、議事録作成時に必要な項目を7つ紹介します。項目を踏まえてよりわかりやすい議事録にしましょう。 タイトル 日付 参加者 議題・目的 会議の発言内容 決定事項・保留事項 次回までのToDo また、以上7つの項目を記載したテンプレートを事前に用意しておくことで、フォーマットを統一できます。そのため、書き方に悩むことなく、誰でもわかりやすい議事録を作成できるようになるので便利です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 3ステップ|議事録の作成手順 見やすい議事録を作成するには、3つのステップを踏む必要があります。以下を参考に、分かりやすい議事録を短時間で仕上げましょう。 (1)事前に準備する 会議中に必要な情報を聞き分けるために、事前の準備が求められます。 たとえば、議題を事前に把握しておけば、会議の流れを予測したうえで議事録の構成を決められます。また、参加者を把握しておくと決裁権の所在が明確になるので、重要な発言の聞き漏らしを減らせるのです。 以上のように、事前に準備して会議の属性を把握しておけば、要旨を捉えた議事録を作成できます。 (2)メモを取る 会議が開始したら発言を聞き分けてメモを取る必要があります。 すべての発言を記録すると時間がかかってしまい聞き漏らしにもつながるので、要点を抑えながら箇条書きで記載する方法がおすすめです。 また、指示語でのやりとりは主語・述語を明確にしたうえでメモする必要があります。さらに、数値は発言の根拠として大切なため、正しく記録しなければなりません。 このように、要点を抑えながら正確にメモをして、良い議事録の作成につなげましょう。 (3)議事録を執筆する 議事録は、会議終了後すぐに執筆を開始しなければなりません。 会議内容を迅速に共有すれば、社員は最新の決定事項に沿って業務を進められるようになります。言い換えれば、社員間で認識の相違を生まないために、議事録の早急な作成が求められるのです。 また、議事録は、会議中のメモを清書するのではなく「どのようにまとめれば読みやすくなるか」を意識しながら執筆しましょう。会議の要旨が一目で理解できるように、5W1Hに即して結論ファーストで記載するのがポイントです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録を上手くとる方法は?コツ5選 以下では、議事録を上手くとる方法を紹介します。議事録の作成時間が短くなればほかの業務に集中できるので、以下の方法を試して業務効率を上げましょう。 (1)テンプレートを利用する テンプレートを使えば社内で議事録の様式を統一できるので、項目の漏れを防げます。 形式を統一することで、書き手は重要な項目を確実に残すことができます。また、フォーマットが決まっていれば「欲しい情報がどこに載っているか」が分かるので、あとから見返したときに素早く目的の箇所を見つけられるのです。 したがって、テンプレートは、作り手と読み手の双方にメリットがあるので積極的に活用しましょう。ただし、自社で一から作るのが難しい場合は、ExcelやWordのテンプレートをダウンロードして使うのがおすすめです。 (2)FOCEPを使いこなす 議事録を作成する際に大切なのは、FOCEPを使って重要な発言を聞き分けることです。FOCEPは、以下の5単語の頭文字を取ったものであり、発言を分析する際の切り口として活用できます。 Fact:事実 Opinion:意見 Cause:原因 Evaluation:評価 Plan:計画 会議中の発言を上記に当てはめれば、すぐに分類できます。注意点として、Fact(事実)とPlan(計画)に分類されたものは会議のなかでもとくに重要な発言なので、聞き漏らし/書き漏らしが起こらないようにしましょう。 (3)主語述語を明記する 主語述語の明記も議事録の取り方・コツのひとつです。 会議中は会話が交わされているため、そのまま文字起こししても、読み手はスムーズに理解できません。たとえば、「いいですね」や「あの時はどうしたの?」といった言葉をそのまま書いても、主語述語が分からないため、振り返りづらいです。 発言者・内容が変わることはあってはなりませんが、適切に主語や述語を補って読みやすい文章にすることを心がけましょう。 (4)定量的な情報を記載する 議事録を取るときは、定量的な情報を記載しましょう。 定性的な情報では、人によって解釈が変わってくるため、定量的な情報の記載を心がけるべきです。また、人数や日時が発言に含まれていた際は、確実に書き入れましょう。 このように、具体的な数字が示されていると、読みやすい議事録になります。 (5)ツールを活用する 議事録を振り返りやすくしたい場合は、情報共有ツールを活用しましょう。 手書きによる議事録は、発言を聞き逃さないように素早く書き留めなければならないので雑になりがちです。そのため、あとから振り返るときに、他の人が読みづらいと感じてしまいます。 そこで、情報共有ツールを導入すると、議事録を見やすく整理できるうえ、紙と違ってかさばることもありません。また、検索機能のあるツールであれば、簡単に目的の資料を見つけることができるので、重要な情報をすぐに振り返れるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】非IT企業の社員でもすぐに使えるツール 以下では、非IT企業の社員でもすぐに使えるツールを紹介します。 ExcelやWordで議事録を作成は、始めやすい反面、共有にメールやチャットを使う必要があります。そこで、簡単に議事録を作成・共有できる「情報共有ツール」を使えば、わざわざメールで共有する必要がないため便利です。 また、ExcelやWordはファイルの管理が煩雑になりやすく、必要な情報をさがすために都度ファイルを開かなければなりません。そこで、いちいちファイルを開かなくても欲しい情報がヒットする検索性に優れたツールの導入がおすすめです。 結論、議事録の作成・管理には、社内の情報を一元化し、目的の議事録に即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは「ヒット率100%」の超高精度検索ができるため、欲しい情報をすぐに取り出せます。また、生成AIによる「自然言語検索」機能も備わっているため、検索スキルを問わず、最適な回答を導き出せるのです。 必要な機能に過不足がないシンプルなツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンを使った議事録の作成例 ここからは、ナレカンを使った議事録の作成手順を紹介します。 自社の議事録に合わせてあらかじめ登録しておいた「テンプレート」を呼び出します。 テンプレートに沿って、議事録を作成します。議事録は、紙のノートに書くように直感的に記載でき、画像・ファイルの添付も可能です。 コメント機能を活用すれば、簡単に会議内容を共有できます。 上記のように「ナレカン」を利用すれば、誰でも簡単に議事録の作成・共有ができます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ すごい議事録の取り方・コツ・フォーマットまとめ これまで、すごい議事録の取り方やコツ、フォーマット例を紹介しました。分かりやすい議事録を完成させるには、以下の3点に取り組む必要があります。 議事録の様式を統一して項目の漏れを防ぐために、テンプレートを活用する 論点と重要事項を正確に理解するためにFOCEP(分類のフレームワーク)を用いる 読み手のスムーズな理解のために、主語述語を補う 誰にとっても分かりやすくするために、定量的な情報を記載する 議事録の作成時間を短縮するために、情報共有ツールを活用する とくに、5点目の「情報共有ツールを活用する」は重要です。手書きの議事録は他の人が読みづらく、目的の箇所を探すのに時間がかかってしまいます。そこで、わかりやすい議事録を作成し、振り返りやすくするためにもツールの導入は不可欠です。 したがって、議事録の作成・管理には、社内の文書を一元管理し、検索性に優れたツール「ナレカン」が最適です。 ぜひ「ナレカン」を活用して議事録の運用にかかる負担を減らし、業務効率を改善しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年03月26日「すごい」と言われる議事録の取り方は?フォーマットや作成例も紹介!会議内容の共有には、概要が記載された「議事録」が使われます。すなわち、議事録は、欠席者に会議内容を把握させる重要な役割を担っているのです。 しかし、良い議事録を作成できていないために、社員間で認識のずれが生じて困っている方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、「すごい」と言われる議事録の取り方や、フォーマット例を紹介します。 議事録の具体例やダメな例を踏まえて取り方を改善したい コツをもとにわかりやすい議事録を取れるようになりたい 簡単に議事録を作成・共有できるツールがあれば活用したい という方はこの記事を参考にすると、議事録が上手い人の取り方が分かるほか、すぐに使えるテンプレートも見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 議事録の作成目的2 ダメな議事録の例3 【見本】議事録の取り方例3.1 議事録の具体例3.2 7つの必要項目4 3ステップ|議事録の作成手順4.1 (1)事前に準備する4.2 (2)メモを取る4.3 (3)議事録を執筆する5 議事録を上手くとる方法は?コツ5選5.1 (1)テンプレートを利用する5.2 (2)FOCEPを使いこなす5.3 (3)主語述語を明記する5.4 (4)定量的な情報を記載する5.5 (5)ツールを活用する6 【必見】非IT企業の社員でもすぐに使えるツール6.1 必要な機能に過不足がないシンプルなツール「ナレカン」6.2 ナレカンを使った議事録の作成例7 すごい議事録の取り方・コツ・フォーマットまとめ 議事録の作成目的 議事録を作成する際には、以下で紹介する3つの目的を正しく理解する必要があります。 決定事項やタスクを記録するため 議事録は、会議で決定した事項やタスクを可視化する役割を果たしています。 正確な情報を共有するため 議事録を使えば、会議の欠席者に正確な情報を届けられるので、認識のずれを防げます。 責任の所在を明確にするため それぞれの発言をした社員名が記録されていれば、責任の所在が明確になるので「言った・言わない」のトラブルを防げます。 上記の目的を理解して、必要な情報が漏れなく記載された議事録を作成しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ダメな議事録の例 以下では、ダメ出しを受けてしまうような議事録の例を3つ紹介します。 結論が不明瞭 会議中の情報をできるだけ詰め込んだ結果として、最終的な結論が分かりづらい・あいまいになってしまう議事録があります。他の作業で忙しく、「結論のみ知りたい」という社員もいるため、まず結論は明確にしましょう。 会議に参加していない社員が理解できない 会議に参加した社員しか内容が理解できない議事録では、「情報共有」という議事録の作成目的が果たせません。会議に参加していない社員でもスムーズに理解できるか、読み手の立場に立って作成しましょう。 意思決定の過程が分からない 結論は記載されているものの、決定するまでの過程が記載されていないと、どのような議論がなされたのか・誰が発言したのか分かりません。会議の過程も残すことで、議論の経緯を正確に把握できるのです。 上記の3つを意識するだけで、議事録の読みやすさは大きく変わります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【見本】議事録の取り方例 以下では、議事録の具体例と作成に必要な項目を紹介します。上手く議事録が取れずに悩んでいる方は必見です。 議事録の具体例 以下は、株主総会議事録です。株主総会議事録とは、株主総会を開催した際に会社法によって作成が義務付けられている資料で、会社法施行規則によって記載事項が定められています。 会社法第318条議事録 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 下記のサンプルを参考に、正式な様式に則った議事録を作成しましょう。 定時株主総会 1. 日時 令和○年○月○日○時○分〜○時○分 2. 場所 当社会議室 3. 出席者 議決権のある総株主数 ○名 この議決権の総数 ○個 出席株主数 ○名 この議決権の総数 ○個 4. 出席役員 代表取締役 ○○ 取締役 ○○ 監査役 ○○ 5. 議事の結果の要領及びその結果 以上の通り株主の出席があり、定款の定めにより本定時総会は適法に成立したので、議長は開会する旨を宣し、議事に入った。 第1号議案:決算報告書の承認に関する件 … 第2号議案:取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件 … 6. 閉会 議長は以上をもって本日の議事が終了した旨を述べ、○時○分閉会した。 上記の決議を明確にするため、この議事をつくり、議長及び役員がこれに記名する。 令和○年○月○日 ○○株式会社 定時株主総会 代表取締役 ○○ 取締役 ○○ 監査役 ○○ 参考: 定時・臨時株主総会議事録 書き方・書式 雛形(ひな形) テンプレート01 【添付書面】01_取締役会設置会社・全員重任 7つの必要項目 以下では、議事録作成時に必要な項目を7つ紹介します。項目を踏まえてよりわかりやすい議事録にしましょう。 タイトル 日付 参加者 議題・目的 会議の発言内容 決定事項・保留事項 次回までのToDo また、以上7つの項目を記載したテンプレートを事前に用意しておくことで、フォーマットを統一できます。そのため、書き方に悩むことなく、誰でもわかりやすい議事録を作成できるようになるので便利です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 3ステップ|議事録の作成手順 見やすい議事録を作成するには、3つのステップを踏む必要があります。以下を参考に、分かりやすい議事録を短時間で仕上げましょう。 (1)事前に準備する 会議中に必要な情報を聞き分けるために、事前の準備が求められます。 たとえば、議題を事前に把握しておけば、会議の流れを予測したうえで議事録の構成を決められます。また、参加者を把握しておくと決裁権の所在が明確になるので、重要な発言の聞き漏らしを減らせるのです。 以上のように、事前に準備して会議の属性を把握しておけば、要旨を捉えた議事録を作成できます。 (2)メモを取る 会議が開始したら発言を聞き分けてメモを取る必要があります。 すべての発言を記録すると時間がかかってしまい聞き漏らしにもつながるので、要点を抑えながら箇条書きで記載する方法がおすすめです。 また、指示語でのやりとりは主語・述語を明確にしたうえでメモする必要があります。さらに、数値は発言の根拠として大切なため、正しく記録しなければなりません。 このように、要点を抑えながら正確にメモをして、良い議事録の作成につなげましょう。 (3)議事録を執筆する 議事録は、会議終了後すぐに執筆を開始しなければなりません。 会議内容を迅速に共有すれば、社員は最新の決定事項に沿って業務を進められるようになります。言い換えれば、社員間で認識の相違を生まないために、議事録の早急な作成が求められるのです。 また、議事録は、会議中のメモを清書するのではなく「どのようにまとめれば読みやすくなるか」を意識しながら執筆しましょう。会議の要旨が一目で理解できるように、5W1Hに即して結論ファーストで記載するのがポイントです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録を上手くとる方法は?コツ5選 以下では、議事録を上手くとる方法を紹介します。議事録の作成時間が短くなればほかの業務に集中できるので、以下の方法を試して業務効率を上げましょう。 (1)テンプレートを利用する テンプレートを使えば社内で議事録の様式を統一できるので、項目の漏れを防げます。 形式を統一することで、書き手は重要な項目を確実に残すことができます。また、フォーマットが決まっていれば「欲しい情報がどこに載っているか」が分かるので、あとから見返したときに素早く目的の箇所を見つけられるのです。 したがって、テンプレートは、作り手と読み手の双方にメリットがあるので積極的に活用しましょう。ただし、自社で一から作るのが難しい場合は、ExcelやWordのテンプレートをダウンロードして使うのがおすすめです。 (2)FOCEPを使いこなす 議事録を作成する際に大切なのは、FOCEPを使って重要な発言を聞き分けることです。FOCEPは、以下の5単語の頭文字を取ったものであり、発言を分析する際の切り口として活用できます。 Fact:事実 Opinion:意見 Cause:原因 Evaluation:評価 Plan:計画 会議中の発言を上記に当てはめれば、すぐに分類できます。注意点として、Fact(事実)とPlan(計画)に分類されたものは会議のなかでもとくに重要な発言なので、聞き漏らし/書き漏らしが起こらないようにしましょう。 (3)主語述語を明記する 主語述語の明記も議事録の取り方・コツのひとつです。 会議中は会話が交わされているため、そのまま文字起こししても、読み手はスムーズに理解できません。たとえば、「いいですね」や「あの時はどうしたの?」といった言葉をそのまま書いても、主語述語が分からないため、振り返りづらいです。 発言者・内容が変わることはあってはなりませんが、適切に主語や述語を補って読みやすい文章にすることを心がけましょう。 (4)定量的な情報を記載する 議事録を取るときは、定量的な情報を記載しましょう。 定性的な情報では、人によって解釈が変わってくるため、定量的な情報の記載を心がけるべきです。また、人数や日時が発言に含まれていた際は、確実に書き入れましょう。 このように、具体的な数字が示されていると、読みやすい議事録になります。 (5)ツールを活用する 議事録を振り返りやすくしたい場合は、情報共有ツールを活用しましょう。 手書きによる議事録は、発言を聞き逃さないように素早く書き留めなければならないので雑になりがちです。そのため、あとから振り返るときに、他の人が読みづらいと感じてしまいます。 そこで、情報共有ツールを導入すると、議事録を見やすく整理できるうえ、紙と違ってかさばることもありません。また、検索機能のあるツールであれば、簡単に目的の資料を見つけることができるので、重要な情報をすぐに振り返れるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】非IT企業の社員でもすぐに使えるツール 以下では、非IT企業の社員でもすぐに使えるツールを紹介します。 ExcelやWordで議事録を作成は、始めやすい反面、共有にメールやチャットを使う必要があります。そこで、簡単に議事録を作成・共有できる「情報共有ツール」を使えば、わざわざメールで共有する必要がないため便利です。 また、ExcelやWordはファイルの管理が煩雑になりやすく、必要な情報をさがすために都度ファイルを開かなければなりません。そこで、いちいちファイルを開かなくても欲しい情報がヒットする検索性に優れたツールの導入がおすすめです。 結論、議事録の作成・管理には、社内の情報を一元化し、目的の議事録に即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは「ヒット率100%」の超高精度検索ができるため、欲しい情報をすぐに取り出せます。また、生成AIによる「自然言語検索」機能も備わっているため、検索スキルを問わず、最適な回答を導き出せるのです。 必要な機能に過不足がないシンプルなツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンを使った議事録の作成例 ここからは、ナレカンを使った議事録の作成手順を紹介します。 自社の議事録に合わせてあらかじめ登録しておいた「テンプレート」を呼び出します。 テンプレートに沿って、議事録を作成します。議事録は、紙のノートに書くように直感的に記載でき、画像・ファイルの添付も可能です。 コメント機能を活用すれば、簡単に会議内容を共有できます。 上記のように「ナレカン」を利用すれば、誰でも簡単に議事録の作成・共有ができます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ すごい議事録の取り方・コツ・フォーマットまとめ これまで、すごい議事録の取り方やコツ、フォーマット例を紹介しました。分かりやすい議事録を完成させるには、以下の3点に取り組む必要があります。 議事録の様式を統一して項目の漏れを防ぐために、テンプレートを活用する 論点と重要事項を正確に理解するためにFOCEP(分類のフレームワーク)を用いる 読み手のスムーズな理解のために、主語述語を補う 誰にとっても分かりやすくするために、定量的な情報を記載する 議事録の作成時間を短縮するために、情報共有ツールを活用する とくに、5点目の「情報共有ツールを活用する」は重要です。手書きの議事録は他の人が読みづらく、目的の箇所を探すのに時間がかかってしまいます。そこで、わかりやすい議事録を作成し、振り返りやすくするためにもツールの導入は不可欠です。 したがって、議事録の作成・管理には、社内の文書を一元管理し、検索性に優れたツール「ナレカン」が最適です。 ぜひ「ナレカン」を活用して議事録の運用にかかる負担を減らし、業務効率を改善しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年03月26日会議における議事録の書き方とは?サンプルも紹介!会議の決定事項を全社に共有するには「議事録」が有効です。また、議事録はナレッジやノウハウの蓄積にも役立つため、あとから読み返しても理解できるようにしておくのが重要です。 一方、「社内で共有される議事録が、誰が読んでも分かるようになっておらず困っている」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、会議における議事録の書き方やサンプルを中心にご紹介します。 見やすい議事録を簡単に書く方法が知りたい 新入社員でも簡単に議事録がつくれるように教育したい 社内の議事録をすぐに業務に活かしたい という担当者の方はこの記事を参考にすると、分かりやすい議事録を書くためのポイントだけでなく、議事録の適切な管理法まで理解できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 会議・ミーティングにおける議事録とは1.1 会議やミーティングで議事録をつくる目的1.2 議事録と議事メモの違い2 見やすい議事録を書くコツ4選2.1 (1)情報を整理する2.2 (2)5W1Hを意識2.3 (3)当日中に完了させることを重視する2.4 (4)テンプレートを使う3 議事録のサンプル例4 【必見】会議の議事録を作成・管理するのに最適なツール4.1 最も簡単に議事録を作成できる「ナレカン」5 議事録メモが追いつかない?実践すべきコツとは6 ミーティングの議事録を作成する目的や書き方まとめ 会議・ミーティングにおける議事録とは 議事録とは、会議で議論された内容や決定事項をまとめ、ほかのメンバーに伝えるための報告書類を指します。また、議事録は目的を明らかにしたうえで、議事メモとの違いも把握しておく必要があります。 会議やミーティングで議事録をつくる目的 以下は、議事録を作成する3つの目的です。 会議内容の共有 会議内容を議事録に残して共有すると、参加できなかったメンバーに概要を周知させられます。また、会議の備忘録としての役割も持ち合わせているため、会議に参加していたメンバーのためにも役立つのです。 決定事項の可視化 会議で決定したことを明確に記載することで、タスクの進捗管理もできます。具体的には、タスクの担当者や期限も書き残しておけば、メンバー同士で認識の齟齬が起こることがありません。 責任の所在を明確化 参加者の発言を議事録に残して、責任の所在を明らかにします。誰が発言したのかが明確になっていないと、責任の押し付け合いになる可能性があるのです。 このように、議事録は重要な役割を担っているため蔑ろにせず、適切な書き方を身につける必要があるのです。 議事録と議事メモの違い 議事録は「誰が、いつ、何を発言したのか」と会議の全体像を書き残す一方、議事メモは「会議の要旨」のみに絞って作成する違いがあります。 社内での打ち合わせやミーティングなど詳細な議事録が不要な場合、議事メモを議事録の代替として作成するのも有効です。しかし、総会など取締役が参加するフォーマルな会議の場合は、議事メモではなく議事録が必要になります。 このように、会議の属性によって議事録と議事メモを使い分けて、適切な方法で情報を共有しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 見やすい議事録を書くコツ4選 以下では、見やすい議事録を書く4つのポイントをご紹介します。見やすい議事録は自然と活用されるようになるため必見です。 (1)情報を整理する 見やすい議事録を作成するためには、情報を整理することが必要不可欠です。 会議に参加していないメンバーにも周知させるためにも、会議の内容を一目で理解できるようにする必要があります。そのため、会議でとったメモをそのまま転記していくのではなく、主語や目的語を補ったり、時系列順に整理したりしましょう。 とくに、決定事項や未決事項といった会議の要点を過不足なく記載すると、会議の結論が明確になり、次回に持ち越した事項も分かりやすくなります。そのため、議事録を作成するときには内容を整理したうえで、要点を端的に示すのがおすすめです。 (2)5W1Hを意識 次に、議事録を作成するときには5W1Hを意識して、必要事項を漏れなく記載することが重要です。 When(いつ)=日時 Where(どこで)=場所 Who(誰が)=参加者 What(何を)=議題 Why(なぜ)=目的 How(どのように)=内容 5W1Hに即して記載すると議事録に必要な項目を盛り込めるので、会議の内容を抜け漏れなく共有できます。 (3)当日中に完了させることを重視する 次に、議事録は会議の当日中に完成させて、すぐに共有するのもポイントのひとつです。 会議の記憶が鮮明なうちに作成すれば正確に議事録をつくれるので、会議があった当日中に対応しましょう。また、議事録をすぐに共有すれば、決まったことを忘れないうちに対応できるのです。 しかし、スピードを意識するあまり誤った内容を共有しては意味がないので、共有する前には同僚などに事実誤認や誤字脱字がないかをチェックしてもらうのもおすすめです。 (4)テンプレートを使う 最後に、見やすい議事録を作成するためにテンプレートを使いましょう。 テンプレートがあれば一からつくる必要がないので、ほかの業務に時間を割くことができます。また、記載すべき項目が決まっているので抜け漏れがなくなるのも重要なポイントです。 ただし、ファイル形式の議事録は管理が面倒なうえに、フォルダから探し出すのに手間がかかります。そのため、WordやExcelなどのファイルを用意しなくても議事録を作成できる「ナレカン」のようなノート形式のツールを活用すべきです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録のサンプル例 以下では、議事録のサンプル例をご紹介します。 企業認知拡大プロジェクト キックオフミーティング 日時:2022年9月8日(木) 13時30分から14時30分 場所:本社会議室B 参加者:営業企画部 大道課長、田中係長、柴田 / 広報部 山田、西野 議題:新規顧客獲得の施策について 決定事項 (1)Facebookアカウントの開設と投稿 ・無料で実施でき、工数も小さい ・利用者層の年齢層が他のSNSよりも高く、既存顧客と属性が似ている (2)オンラインセミナーの開催 ・定期的に実施することで、企業認知度の高まりが期待できる ・過去の開催事例があり、ノウハウがある To Do ・アカウント開設 ・セミナーの日程調整 会議内容のメモ ・認知を拡大するうえでSNSの利用は必須 ・Instagram、Xの利用者層は既存顧客の年齢層と合わない ・他のSNSと比較してFacebookは既存顧客と属性が近い ・過去のオンラインセミナーは満足度が高かった 次回の議題:上記で決定した(1)(2)についてチームを組み、担当者やタスクを決定する このように、議事録には日時・場所・参加者といった会議の基本情報から、議題・決定事項・未決事項といった要点まで漏れなく簡潔に記載する必要があります。とくに、決定事項は箇条書きで書き、一目で内容が把握できるようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】会議の議事録を作成・管理するのに最適なツール 以下では、会議議事録の作成・運用を効率化するツールをご紹介します。 紙の議事録は、印刷や収納スペースのコストがかかり非効率です。そこで、ITツールで議事録を作成・管理すれば、情報を一元化できるうえに、時間や場所を問わずに議事録にアクセスすることも可能です。 具体的には、「議事録の作成・共有・管理に必要な機能が過不足なく備わったツール」を導入しましょう。ただし、多機能すぎるITツールの場合、現場社員が使いこなせない可能性が高く、議事録の管理がかえって煩雑になってしまいます。 したがって、自社が導入すべきなのは、議事録の作成・運用に必要な機能を備えつつも、シンプルな操作性で使いやすいツール「ナレカン」一択です。 ナレカンには、議事録の作成に役立つ「テンプレート」や共有時にやりとりできる「メッセージ機能」が備わっています。また、高精度の「検索機能」も備えているため、ナレカンひとつで議事録の円滑な作成・共有・管理が実現します。 最も簡単に議事録を作成できる「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録メモが追いつかない?実践すべきコツとは ここでは、メモが追い付かない悩みを抱える方向けに、議事録をとるときのコツを解説します。以下を参考に、正確なメモを素早くとりましょう。 数字を押さえる 会議中に出てきた数字は必ず押さえましょう。議事録に数字が記載されていると、会議に参加できなかったメンバーの理解も深まりやすくなります。 記号を効果的に使う 重要なポイントを目立たせるときは色を使うケースが多いですが、会議中は逐一色分けする時間がないため「〇」「△」「×」などの記号を使うのがおすすめです。また、自分の中で記号の役割を整理しておくと、あとからまとめるときにスムーズになります。 因果関係を明確にする 議題に対してのアンサーは「矢印でつなぐ」「近くに配置する」など、因果関係を明確にしておきましょう。各議題の決定事項・今後の方針が可視化され、会議の全容が把握しやすくなります。 以上のように、あとから議事録を作成するために、メモは必要な情報を過不足なくとりましょう。また、メモは議事録を作成するときだけ使うので、書いた本人が分かるようにするのもポイントです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ミーティングの議事録を作成する目的や書き方まとめ ここまで、議事録の作成目的や押さえるべきポイントを中心に紹介しました。 見やすい議事録を作成するためには「5W1Hを意識しながらスピード重視で作成する」「テンプレートを使用する」などのポイントを押さえる必要があります。しかし、議事録の作成と共有をそれぞれ別のツールでするのは面倒です。 したがって、議事録を素早く作成・共有するには、一連の作業を集約できるITツールの活用が必須なのです。ただし、選定するツールはシンプルでなければ、導入しても一部のメンバーしか使えない状況に陥ってしまうので注意しましょう。 そこで、議事録の作成から共有・管理を一元化するには、議事録に必要な機能を過不足なく備え、非IT企業の方でも簡単に使いこなせるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、ストレスなく議事録の運用を効率化させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年03月26日会議における議事録の書き方とは?サンプルも紹介!会議の決定事項を全社に共有するには「議事録」が有効です。また、議事録はナレッジやノウハウの蓄積にも役立つため、あとから読み返しても理解できるようにしておくのが重要です。 一方、「社内で共有される議事録が、誰が読んでも分かるようになっておらず困っている」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、会議における議事録の書き方やサンプルを中心にご紹介します。 見やすい議事録を簡単に書く方法が知りたい 新入社員でも簡単に議事録がつくれるように教育したい 社内の議事録をすぐに業務に活かしたい という担当者の方はこの記事を参考にすると、分かりやすい議事録を書くためのポイントだけでなく、議事録の適切な管理法まで理解できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 会議・ミーティングにおける議事録とは1.1 会議やミーティングで議事録をつくる目的1.2 議事録と議事メモの違い2 見やすい議事録を書くコツ4選2.1 (1)情報を整理する2.2 (2)5W1Hを意識2.3 (3)当日中に完了させることを重視する2.4 (4)テンプレートを使う3 議事録のサンプル例4 【必見】会議の議事録を作成・管理するのに最適なツール4.1 最も簡単に議事録を作成できる「ナレカン」5 議事録メモが追いつかない?実践すべきコツとは6 ミーティングの議事録を作成する目的や書き方まとめ 会議・ミーティングにおける議事録とは 議事録とは、会議で議論された内容や決定事項をまとめ、ほかのメンバーに伝えるための報告書類を指します。また、議事録は目的を明らかにしたうえで、議事メモとの違いも把握しておく必要があります。 会議やミーティングで議事録をつくる目的 以下は、議事録を作成する3つの目的です。 会議内容の共有 会議内容を議事録に残して共有すると、参加できなかったメンバーに概要を周知させられます。また、会議の備忘録としての役割も持ち合わせているため、会議に参加していたメンバーのためにも役立つのです。 決定事項の可視化 会議で決定したことを明確に記載することで、タスクの進捗管理もできます。具体的には、タスクの担当者や期限も書き残しておけば、メンバー同士で認識の齟齬が起こることがありません。 責任の所在を明確化 参加者の発言を議事録に残して、責任の所在を明らかにします。誰が発言したのかが明確になっていないと、責任の押し付け合いになる可能性があるのです。 このように、議事録は重要な役割を担っているため蔑ろにせず、適切な書き方を身につける必要があるのです。 議事録と議事メモの違い 議事録は「誰が、いつ、何を発言したのか」と会議の全体像を書き残す一方、議事メモは「会議の要旨」のみに絞って作成する違いがあります。 社内での打ち合わせやミーティングなど詳細な議事録が不要な場合、議事メモを議事録の代替として作成するのも有効です。しかし、総会など取締役が参加するフォーマルな会議の場合は、議事メモではなく議事録が必要になります。 このように、会議の属性によって議事録と議事メモを使い分けて、適切な方法で情報を共有しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 見やすい議事録を書くコツ4選 以下では、見やすい議事録を書く4つのポイントをご紹介します。見やすい議事録は自然と活用されるようになるため必見です。 (1)情報を整理する 見やすい議事録を作成するためには、情報を整理することが必要不可欠です。 会議に参加していないメンバーにも周知させるためにも、会議の内容を一目で理解できるようにする必要があります。そのため、会議でとったメモをそのまま転記していくのではなく、主語や目的語を補ったり、時系列順に整理したりしましょう。 とくに、決定事項や未決事項といった会議の要点を過不足なく記載すると、会議の結論が明確になり、次回に持ち越した事項も分かりやすくなります。そのため、議事録を作成するときには内容を整理したうえで、要点を端的に示すのがおすすめです。 (2)5W1Hを意識 次に、議事録を作成するときには5W1Hを意識して、必要事項を漏れなく記載することが重要です。 When(いつ)=日時 Where(どこで)=場所 Who(誰が)=参加者 What(何を)=議題 Why(なぜ)=目的 How(どのように)=内容 5W1Hに即して記載すると議事録に必要な項目を盛り込めるので、会議の内容を抜け漏れなく共有できます。 (3)当日中に完了させることを重視する 次に、議事録は会議の当日中に完成させて、すぐに共有するのもポイントのひとつです。 会議の記憶が鮮明なうちに作成すれば正確に議事録をつくれるので、会議があった当日中に対応しましょう。また、議事録をすぐに共有すれば、決まったことを忘れないうちに対応できるのです。 しかし、スピードを意識するあまり誤った内容を共有しては意味がないので、共有する前には同僚などに事実誤認や誤字脱字がないかをチェックしてもらうのもおすすめです。 (4)テンプレートを使う 最後に、見やすい議事録を作成するためにテンプレートを使いましょう。 テンプレートがあれば一からつくる必要がないので、ほかの業務に時間を割くことができます。また、記載すべき項目が決まっているので抜け漏れがなくなるのも重要なポイントです。 ただし、ファイル形式の議事録は管理が面倒なうえに、フォルダから探し出すのに手間がかかります。そのため、WordやExcelなどのファイルを用意しなくても議事録を作成できる「ナレカン」のようなノート形式のツールを活用すべきです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録のサンプル例 以下では、議事録のサンプル例をご紹介します。 企業認知拡大プロジェクト キックオフミーティング 日時:2022年9月8日(木) 13時30分から14時30分 場所:本社会議室B 参加者:営業企画部 大道課長、田中係長、柴田 / 広報部 山田、西野 議題:新規顧客獲得の施策について 決定事項 (1)Facebookアカウントの開設と投稿 ・無料で実施でき、工数も小さい ・利用者層の年齢層が他のSNSよりも高く、既存顧客と属性が似ている (2)オンラインセミナーの開催 ・定期的に実施することで、企業認知度の高まりが期待できる ・過去の開催事例があり、ノウハウがある To Do ・アカウント開設 ・セミナーの日程調整 会議内容のメモ ・認知を拡大するうえでSNSの利用は必須 ・Instagram、Xの利用者層は既存顧客の年齢層と合わない ・他のSNSと比較してFacebookは既存顧客と属性が近い ・過去のオンラインセミナーは満足度が高かった 次回の議題:上記で決定した(1)(2)についてチームを組み、担当者やタスクを決定する このように、議事録には日時・場所・参加者といった会議の基本情報から、議題・決定事項・未決事項といった要点まで漏れなく簡潔に記載する必要があります。とくに、決定事項は箇条書きで書き、一目で内容が把握できるようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】会議の議事録を作成・管理するのに最適なツール 以下では、会議議事録の作成・運用を効率化するツールをご紹介します。 紙の議事録は、印刷や収納スペースのコストがかかり非効率です。そこで、ITツールで議事録を作成・管理すれば、情報を一元化できるうえに、時間や場所を問わずに議事録にアクセスすることも可能です。 具体的には、「議事録の作成・共有・管理に必要な機能が過不足なく備わったツール」を導入しましょう。ただし、多機能すぎるITツールの場合、現場社員が使いこなせない可能性が高く、議事録の管理がかえって煩雑になってしまいます。 したがって、自社が導入すべきなのは、議事録の作成・運用に必要な機能を備えつつも、シンプルな操作性で使いやすいツール「ナレカン」一択です。 ナレカンには、議事録の作成に役立つ「テンプレート」や共有時にやりとりできる「メッセージ機能」が備わっています。また、高精度の「検索機能」も備えているため、ナレカンひとつで議事録の円滑な作成・共有・管理が実現します。 最も簡単に議事録を作成できる「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録メモが追いつかない?実践すべきコツとは ここでは、メモが追い付かない悩みを抱える方向けに、議事録をとるときのコツを解説します。以下を参考に、正確なメモを素早くとりましょう。 数字を押さえる 会議中に出てきた数字は必ず押さえましょう。議事録に数字が記載されていると、会議に参加できなかったメンバーの理解も深まりやすくなります。 記号を効果的に使う 重要なポイントを目立たせるときは色を使うケースが多いですが、会議中は逐一色分けする時間がないため「〇」「△」「×」などの記号を使うのがおすすめです。また、自分の中で記号の役割を整理しておくと、あとからまとめるときにスムーズになります。 因果関係を明確にする 議題に対してのアンサーは「矢印でつなぐ」「近くに配置する」など、因果関係を明確にしておきましょう。各議題の決定事項・今後の方針が可視化され、会議の全容が把握しやすくなります。 以上のように、あとから議事録を作成するために、メモは必要な情報を過不足なくとりましょう。また、メモは議事録を作成するときだけ使うので、書いた本人が分かるようにするのもポイントです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ミーティングの議事録を作成する目的や書き方まとめ ここまで、議事録の作成目的や押さえるべきポイントを中心に紹介しました。 見やすい議事録を作成するためには「5W1Hを意識しながらスピード重視で作成する」「テンプレートを使用する」などのポイントを押さえる必要があります。しかし、議事録の作成と共有をそれぞれ別のツールでするのは面倒です。 したがって、議事録を素早く作成・共有するには、一連の作業を集約できるITツールの活用が必須なのです。ただし、選定するツールはシンプルでなければ、導入しても一部のメンバーしか使えない状況に陥ってしまうので注意しましょう。 そこで、議事録の作成から共有・管理を一元化するには、議事録に必要な機能を過不足なく備え、非IT企業の方でも簡単に使いこなせるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、ストレスなく議事録の運用を効率化させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年11月18日【無料】Word/Excelの議事録テンプレート6選!見やすい書き方も紹介議事録を作成すると、会議の議題や決定事項を正確に共有できるほか、社内のノウハウとして今後の業務にも役立ちます。また、テンプレートを活用すれば、手間をかけることなく簡単に議事録を書けるのです。 しかし、「議事録の見やすい書き方が分からない」という方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、すぐに使える議事録のテンプレートや見やすい書き方を中心にご紹介します。 テンプレート・フォーマットを活用して、簡単に議事録を作成したい 見やすい議事録の書き方やポイントを確認したい 議事録の作成・共有・管理を一元的にできるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、分かりやすい議事録の作り方が分かるだけでなく、ビジネス向きの管理方法も見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 【無料】見やすい議事録フォーマット・テンプレート6選1.1 Word|シンプルな議事録のテンプレート1.2 Word|議題をまとめられる議事録のひな形1.3 Word|株主総会の議事録フォーマット1.4 Word|おしゃれなミーティング議事録テンプレート1.5 Excel|打ち合わせの議事録フォーマット1.6 Excel|総会で使える議案書のテンプレート2 【必見】Word・Excelでの議事録管理が抱える課題とは2.1 最も簡単に議事録を作成・共有・管理できるツール「ナレカン」3 <見本あり>簡単解説!分かりやすい議事録の作り方は?3.1 議事録の基本項目3.2 見やすい議事録のサンプル4 議事録の目的5 読みづらい!議事録でダメな例と改善策6 見やすい議事録を書くためのポイント6.1 (1)事前準備をする6.2 (2)要点を中心にメモをとる6.3 (3)5W1Hを意識する6.4 (4)共有・管理しやすいツールを使う7 Word/Excelの議事録テンプレート・雛形まとめ 【無料】見やすい議事録フォーマット・テンプレート6選 以下では、無料で使えるWord・Excelの議事録テンプレート6選をご紹介します。テンプレートを使うと、一から記載する手間が無くなり、スムーズに議事録を書けるのです。 Word|シンプルな議事録のテンプレート こちらは、「[文書]テンプレートの無料ダウンロード」が提供する、シンプルな議事録のテンプレートです。 「議題」「議論の過程」「結果」などの基本項目が記載されており、さまざまな場面で汎用的に使えます。また、「結果」と「保留事項」の記入欄が分かれているので、会議の決定事項と次回に持ち越す内容を整理できます。 [文書]テンプレートの無料ダウンロードの詳細はこちら Word|議題をまとめられる議事録のひな形 こちらは、「Microsoft」が提供する、議題をまとめられる議事録のひな形です。 会議の議題を包括的にまとめるのに最適なテンプレートとなっています。会議の全体像を一目で確認できるので、円滑に議論を進められるのです。 Microsoftのテンプレートの詳細はこちら Word|株主総会の議事録フォーマット こちらは、「[文書]テンプレートの無料ダウンロード」が提供する、株主総会の議事録フォーマットです。 株主総会向けに特化したテンプレートです。議案の例文が記載されているので、初心者の方でも「何をどのように書けばいいのか」が分かります。 [文書]テンプレートの無料ダウンロードの詳細はこちら Word|おしゃれなミーティング議事録テンプレート こちらは、「Microsoft」が提供する、デザイン性の高い議事録のテンプレートです。 フォントの色や背景が設定されているため、見やすくおしゃれなミーティング議事録が作れます。また、項目を自社の用途に合わせて変更できるので、様々な会議の議事録に利用可能です。 Microsoftのテンプレートの詳細はこちら Excel|打ち合わせの議事録フォーマット こちらは、「[文書]テンプレートの無料ダウンロード」が提供する、打ち合わせの議事録テンプレートです。 打ち合わせの要点を箇条書きで記載できる、表形式の議事録となっています。ただし、「決定事項」「次回のタスク」などの記入欄はないので、適宜項目を追加しましょう。 [文書]テンプレートの無料ダウンロードの詳細はこちら Excel|総会で使える議案書のテンプレート こちらは、「[文書]テンプレートの無料ダウンロード」が提供する、総会で使える議案書のテンプレートです。 定期総会議案書のひとつとして、1年間で実施した事業をまとめられます。時系列に沿って記載できるので、内容を理解しやすいです。 [文書]テンプレートの無料ダウンロードの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】Word・Excelでの議事録管理が抱える課題とは 以下では、Word・Excelでの議事録管理が抱える課題をご紹介します。 議事録は、社員の知識やノウハウも記載される重要な情報資産なので、作成後は適切に管理しなければなりません。しかし、WordやExcelの場合、似た名前のファイルが乱立して目的のファイルが見つけづらかったり、都度ファイルを開く手間がかかったりしてしまいます。 そこで、「情報が更新と同時に共有されるツール」を導入して、ファイル管理の手間を最小限にしましょう。また、議事録は会議の度に増えていくので、目的の情報を素早く見つけるには「検索機能が充実している」ことも重視すべきです。 結論、議事録の作成・共有に最適なのは、超高精度の検索機能を備えた、ノート型情報管理ツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、テキストだけでなく画像・ファイルを格納できるうえに、登録した「テンプレート」を呼び起こせば、手間をかけることなく議事録を作成できます。また、「ヒット率100%」の超高精度検索によって、目的の情報へ即アクセス可能です。 最も簡単に議事録を作成・共有・管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンの機能 テンプレート機能 ナレカンでは、以下のようにテンプレートを登録できます。登録した「テンプレート」を呼び起こせば、議事録の作成にかかる手間を大幅に削減可能です。 自然言語検索機能 ナレカンには、“上司に質問するように探せる”生成AIを活用した「自然言語検索機能」があります。ナレカン内の記事をすべて横断して、最も適切な回答を返してくれるため、目的の議事録をすぐに見つけられるのです。 また上のように、ナレカンのAIは生成した情報の根拠となる記事を添付してくれるため、情報の正確性が高いといえます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ <見本あり>簡単解説!分かりやすい議事録の作り方は? ここでは、議事録に書くべき項目や、見やすい例文をご紹介します。「議事録の書き方が分からない」という方は、以下を参考にしましょう。 議事録の基本項目 議事録に書くべき内容として、以下の項目が挙げられます。 <項目> <概要> 会議名 会議の「タイトル」や「目的」を記載します。 日時・場所 会議の「開催日時」や「開催場所」を記載します。 参加者 会議に参加したメンバーの「部署」や「名前」を記載します。 議題 会議で議論した項目を記載します。 決定事項 会議を通して決定した項目を記載します。 今後のタスク 会議で決定した「タスク」や「担当者」、「期限」を記載します。 参考資料 会議で配布された「資料」を添付します。 上記の項目を記載することで、会議の概要を正確に共有できます。また、テンプレートを簡単に自作できる「ナレカン」ようなツールを使えば、自社に合った項目で議事録を作れるのです。 見やすい議事録のサンプル 以下は、見やすい議事録の作成例です。 23/6/29木 企業認知拡大プロジェクト キックオフミーティング <概要> ・会議名;企業認知拡大プロジェクト キックオフミーティング ・開始/終了日時と場所:24/8/29木 13:00~14:00@本社会議室A ・参加者:渡辺、石原、小橋、大道 <議題> ・企業認知拡大プロジェクトの施策 →現在、既存顧客からの満足度・再受注率ともに高いが、新規顧客獲得数が伸び悩んでいるために売り上げが停滞している。前回のブレインストーミングをもとに施策を決定し、具体的な施策に落としたい。 <決定事項> 1. Instagramアカウントの開設と運用 ・無料で使えて、工数も少ない ・高級感のあるWebページを制作しているので、写真で視覚的に訴求するInstagramと相性が良さそう ・大道がInstagramで1,000人のフォロワーを獲得しており、知見がある 2. オンラインセミナーの開催 ・定期的に実施することで、企業認知度が一気に高くなる可能性がある ・既存顧客のなかに、共催できそうな顧客が複数いる <補足事項> ・なし <次回の課題> 上記の決定事項について、今週中にチームを発足する 上記のように、読み手が内容を把握しやすくなるよう、基本項目を設けたうえで数字や箇条書きを使いましょう。また、下図のように参考資料をプレビューで参照できるツールで管理すれば、会議に関する情報の共有が一つのツールで完結します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録の目的 議事録を作成する目的として、以下の2つが挙げられます。 会議の概要を共有する 議論の「過程」や「決定事項」を議事録に記載すると、会議に参加していないメンバーでも会議の全容を把握できます。また、会議の要点を見返せるため、参加したメンバーの認識のズレも防げるのです。 今後の会議をスムーズに進める 議事録を作成しておけば、過去の会議の内容を簡単に振り返れるようになり、同じ議論を繰り返したり、欠席者に向けて再度説明したりする手間を省けます。 議事録を作成するときは、上記の目的を踏まえて、意味のある議事録にすることを意識しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 読みづらい!議事録でダメな例と改善策 ここでは、ダメな議事録の例と改善策をご紹介します。 会議参加者しか内容を把握できない 議事録は「会議の内容を残す」だけでなく、「会議に参加していない人への情報共有」という重要な目的があります。そのため、略称には注釈をつけて説明するなど、会議に参加していない人もスムーズに理解できるよう意識しましょう。 結論に至る過程が不明確 議事録に結論が記載されていても、そこに至るまでのプロセスが明確でなければ、読み手にとって納得感のある議事録になりません。そのため、誰が提案し、どのような議論がおこなわれ、誰の判断で結論となったのか、明確に記載すべきです。 このように、議事録を作成するときは読み手の視点に立つことを必ず意識しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 見やすい議事録を書くためのポイント ここでは、議事録を書くときの4つのポイントをご紹介します。見やすい議事録を作成するために、以下のポイントを確実に押さえましょう。 (1)事前準備をする 議事録作成の事前準備をしておくと、会議中にスムーズにメモを取れます。 “日時”や”参加者”のような事前に分かる情報を会議前に記入しておけば、「議論のスピードが速くてメモが追い付かない」といった状況を防げます。また、議論の展開を予想して、議事録の構成を決めておくことも効果的です。 以上のように、単純にフォーマットを用意するだけでなく「記入できるところを埋めておく」「議論の流れを予測してメモの準備をする」などの備えをしておきましょう。 (2)要点を中心にメモをとる 会議中はすべてを書き起こそうとせずに、要点をメモするようにしましょう。 「完璧なメモを取ること」「一言一句書き起こすこと」に固執すると、メモを取ること自体が目的化してしまい、会議の要点を掴めません。そのため、会議中は要点を中心とした、簡潔なメモをとるように意識することが重要です。 また、太字や下線で文字を装飾すると、視覚的に分かりやすい議事録になります。 (3)5W1Hを意識する 議事録の作成時に5W1Hを意識すると、情報の抜け漏れを防げます。5W1Hとは、以下の6項目です。 Who:誰が What:何を Why:なぜ When:いつ Where:どこで How:どのように 山田が提案書類を作成中、3/5までに提出。 伊藤が休暇のため、3/10に顧客面談を変更。株式会社〇〇第3会議室。 このように、5W1Hを意識した文章にすることで、必要な情報を正確に伝えられます。 (4)共有・管理しやすいツールを使う 議事録の作成だけでなく、共有・管理がしやすいツールを使うこともポイントです。 議事録は、作成して終わりではなく、メンバーに共有したり振り返ったりする必要があります。しかし、WordやExcelでは、共有のたびにメールやチャットに添付する手間がかかるほか、ファイル数が増えて管理が煩雑になりやすいです。 一方、社内のあらゆる情報を集約して、”即アクセス”できる「ナレカン」のように検索性に優れたツールであれば、共有や振り返りもスムーズです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Word/Excelの議事録テンプレート・雛形まとめ ここまで、議事録の書き方や、作成におすすめのテンプレートを中心にご紹介しました。 テンプレートを活用すれば、効率よく議事録を作成できるうえ、「作成者によって内容が違う」といった問題を解消できます。ただし、WordやExcelで作成する場合、作成後の共有・管理に手間がかかってしまいます。 そこで、「自作のテンプレートを使って議事録の作成と蓄積を一元化できる情報共有ツール」を活用しましょう。また、過去の議事録を見返しやすく管理するためには、「検索機能が優れているか」にも注意して検討すべきです。 結論、自社が導入すべきなのは、探している情報に即アクセスでき、議事録を簡単に作成・共有・管理できるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、議事録の作成・共有・管理を効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年11月18日【無料】Word/Excelの議事録テンプレート6選!見やすい書き方も紹介議事録を作成すると、会議の議題や決定事項を正確に共有できるほか、社内のノウハウとして今後の業務にも役立ちます。また、テンプレートを活用すれば、手間をかけることなく簡単に議事録を書けるのです。 しかし、「議事録の見やすい書き方が分からない」という方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、すぐに使える議事録のテンプレートや見やすい書き方を中心にご紹介します。 テンプレート・フォーマットを活用して、簡単に議事録を作成したい 見やすい議事録の書き方やポイントを確認したい 議事録の作成・共有・管理を一元的にできるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、分かりやすい議事録の作り方が分かるだけでなく、ビジネス向きの管理方法も見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 【無料】見やすい議事録フォーマット・テンプレート6選1.1 Word|シンプルな議事録のテンプレート1.2 Word|議題をまとめられる議事録のひな形1.3 Word|株主総会の議事録フォーマット1.4 Word|おしゃれなミーティング議事録テンプレート1.5 Excel|打ち合わせの議事録フォーマット1.6 Excel|総会で使える議案書のテンプレート2 【必見】Word・Excelでの議事録管理が抱える課題とは2.1 最も簡単に議事録を作成・共有・管理できるツール「ナレカン」3 <見本あり>簡単解説!分かりやすい議事録の作り方は?3.1 議事録の基本項目3.2 見やすい議事録のサンプル4 議事録の目的5 読みづらい!議事録でダメな例と改善策6 見やすい議事録を書くためのポイント6.1 (1)事前準備をする6.2 (2)要点を中心にメモをとる6.3 (3)5W1Hを意識する6.4 (4)共有・管理しやすいツールを使う7 Word/Excelの議事録テンプレート・雛形まとめ 【無料】見やすい議事録フォーマット・テンプレート6選 以下では、無料で使えるWord・Excelの議事録テンプレート6選をご紹介します。テンプレートを使うと、一から記載する手間が無くなり、スムーズに議事録を書けるのです。 Word|シンプルな議事録のテンプレート こちらは、「[文書]テンプレートの無料ダウンロード」が提供する、シンプルな議事録のテンプレートです。 「議題」「議論の過程」「結果」などの基本項目が記載されており、さまざまな場面で汎用的に使えます。また、「結果」と「保留事項」の記入欄が分かれているので、会議の決定事項と次回に持ち越す内容を整理できます。 [文書]テンプレートの無料ダウンロードの詳細はこちら Word|議題をまとめられる議事録のひな形 こちらは、「Microsoft」が提供する、議題をまとめられる議事録のひな形です。 会議の議題を包括的にまとめるのに最適なテンプレートとなっています。会議の全体像を一目で確認できるので、円滑に議論を進められるのです。 Microsoftのテンプレートの詳細はこちら Word|株主総会の議事録フォーマット こちらは、「[文書]テンプレートの無料ダウンロード」が提供する、株主総会の議事録フォーマットです。 株主総会向けに特化したテンプレートです。議案の例文が記載されているので、初心者の方でも「何をどのように書けばいいのか」が分かります。 [文書]テンプレートの無料ダウンロードの詳細はこちら Word|おしゃれなミーティング議事録テンプレート こちらは、「Microsoft」が提供する、デザイン性の高い議事録のテンプレートです。 フォントの色や背景が設定されているため、見やすくおしゃれなミーティング議事録が作れます。また、項目を自社の用途に合わせて変更できるので、様々な会議の議事録に利用可能です。 Microsoftのテンプレートの詳細はこちら Excel|打ち合わせの議事録フォーマット こちらは、「[文書]テンプレートの無料ダウンロード」が提供する、打ち合わせの議事録テンプレートです。 打ち合わせの要点を箇条書きで記載できる、表形式の議事録となっています。ただし、「決定事項」「次回のタスク」などの記入欄はないので、適宜項目を追加しましょう。 [文書]テンプレートの無料ダウンロードの詳細はこちら Excel|総会で使える議案書のテンプレート こちらは、「[文書]テンプレートの無料ダウンロード」が提供する、総会で使える議案書のテンプレートです。 定期総会議案書のひとつとして、1年間で実施した事業をまとめられます。時系列に沿って記載できるので、内容を理解しやすいです。 [文書]テンプレートの無料ダウンロードの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】Word・Excelでの議事録管理が抱える課題とは 以下では、Word・Excelでの議事録管理が抱える課題をご紹介します。 議事録は、社員の知識やノウハウも記載される重要な情報資産なので、作成後は適切に管理しなければなりません。しかし、WordやExcelの場合、似た名前のファイルが乱立して目的のファイルが見つけづらかったり、都度ファイルを開く手間がかかったりしてしまいます。 そこで、「情報が更新と同時に共有されるツール」を導入して、ファイル管理の手間を最小限にしましょう。また、議事録は会議の度に増えていくので、目的の情報を素早く見つけるには「検索機能が充実している」ことも重視すべきです。 結論、議事録の作成・共有に最適なのは、超高精度の検索機能を備えた、ノート型情報管理ツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、テキストだけでなく画像・ファイルを格納できるうえに、登録した「テンプレート」を呼び起こせば、手間をかけることなく議事録を作成できます。また、「ヒット率100%」の超高精度検索によって、目的の情報へ即アクセス可能です。 最も簡単に議事録を作成・共有・管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンの機能 テンプレート機能 ナレカンでは、以下のようにテンプレートを登録できます。登録した「テンプレート」を呼び起こせば、議事録の作成にかかる手間を大幅に削減可能です。 自然言語検索機能 ナレカンには、“上司に質問するように探せる”生成AIを活用した「自然言語検索機能」があります。ナレカン内の記事をすべて横断して、最も適切な回答を返してくれるため、目的の議事録をすぐに見つけられるのです。 また上のように、ナレカンのAIは生成した情報の根拠となる記事を添付してくれるため、情報の正確性が高いといえます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ <見本あり>簡単解説!分かりやすい議事録の作り方は? ここでは、議事録に書くべき項目や、見やすい例文をご紹介します。「議事録の書き方が分からない」という方は、以下を参考にしましょう。 議事録の基本項目 議事録に書くべき内容として、以下の項目が挙げられます。 <項目> <概要> 会議名 会議の「タイトル」や「目的」を記載します。 日時・場所 会議の「開催日時」や「開催場所」を記載します。 参加者 会議に参加したメンバーの「部署」や「名前」を記載します。 議題 会議で議論した項目を記載します。 決定事項 会議を通して決定した項目を記載します。 今後のタスク 会議で決定した「タスク」や「担当者」、「期限」を記載します。 参考資料 会議で配布された「資料」を添付します。 上記の項目を記載することで、会議の概要を正確に共有できます。また、テンプレートを簡単に自作できる「ナレカン」ようなツールを使えば、自社に合った項目で議事録を作れるのです。 見やすい議事録のサンプル 以下は、見やすい議事録の作成例です。 23/6/29木 企業認知拡大プロジェクト キックオフミーティング <概要> ・会議名;企業認知拡大プロジェクト キックオフミーティング ・開始/終了日時と場所:24/8/29木 13:00~14:00@本社会議室A ・参加者:渡辺、石原、小橋、大道 <議題> ・企業認知拡大プロジェクトの施策 →現在、既存顧客からの満足度・再受注率ともに高いが、新規顧客獲得数が伸び悩んでいるために売り上げが停滞している。前回のブレインストーミングをもとに施策を決定し、具体的な施策に落としたい。 <決定事項> 1. Instagramアカウントの開設と運用 ・無料で使えて、工数も少ない ・高級感のあるWebページを制作しているので、写真で視覚的に訴求するInstagramと相性が良さそう ・大道がInstagramで1,000人のフォロワーを獲得しており、知見がある 2. オンラインセミナーの開催 ・定期的に実施することで、企業認知度が一気に高くなる可能性がある ・既存顧客のなかに、共催できそうな顧客が複数いる <補足事項> ・なし <次回の課題> 上記の決定事項について、今週中にチームを発足する 上記のように、読み手が内容を把握しやすくなるよう、基本項目を設けたうえで数字や箇条書きを使いましょう。また、下図のように参考資料をプレビューで参照できるツールで管理すれば、会議に関する情報の共有が一つのツールで完結します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録の目的 議事録を作成する目的として、以下の2つが挙げられます。 会議の概要を共有する 議論の「過程」や「決定事項」を議事録に記載すると、会議に参加していないメンバーでも会議の全容を把握できます。また、会議の要点を見返せるため、参加したメンバーの認識のズレも防げるのです。 今後の会議をスムーズに進める 議事録を作成しておけば、過去の会議の内容を簡単に振り返れるようになり、同じ議論を繰り返したり、欠席者に向けて再度説明したりする手間を省けます。 議事録を作成するときは、上記の目的を踏まえて、意味のある議事録にすることを意識しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 読みづらい!議事録でダメな例と改善策 ここでは、ダメな議事録の例と改善策をご紹介します。 会議参加者しか内容を把握できない 議事録は「会議の内容を残す」だけでなく、「会議に参加していない人への情報共有」という重要な目的があります。そのため、略称には注釈をつけて説明するなど、会議に参加していない人もスムーズに理解できるよう意識しましょう。 結論に至る過程が不明確 議事録に結論が記載されていても、そこに至るまでのプロセスが明確でなければ、読み手にとって納得感のある議事録になりません。そのため、誰が提案し、どのような議論がおこなわれ、誰の判断で結論となったのか、明確に記載すべきです。 このように、議事録を作成するときは読み手の視点に立つことを必ず意識しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 見やすい議事録を書くためのポイント ここでは、議事録を書くときの4つのポイントをご紹介します。見やすい議事録を作成するために、以下のポイントを確実に押さえましょう。 (1)事前準備をする 議事録作成の事前準備をしておくと、会議中にスムーズにメモを取れます。 “日時”や”参加者”のような事前に分かる情報を会議前に記入しておけば、「議論のスピードが速くてメモが追い付かない」といった状況を防げます。また、議論の展開を予想して、議事録の構成を決めておくことも効果的です。 以上のように、単純にフォーマットを用意するだけでなく「記入できるところを埋めておく」「議論の流れを予測してメモの準備をする」などの備えをしておきましょう。 (2)要点を中心にメモをとる 会議中はすべてを書き起こそうとせずに、要点をメモするようにしましょう。 「完璧なメモを取ること」「一言一句書き起こすこと」に固執すると、メモを取ること自体が目的化してしまい、会議の要点を掴めません。そのため、会議中は要点を中心とした、簡潔なメモをとるように意識することが重要です。 また、太字や下線で文字を装飾すると、視覚的に分かりやすい議事録になります。 (3)5W1Hを意識する 議事録の作成時に5W1Hを意識すると、情報の抜け漏れを防げます。5W1Hとは、以下の6項目です。 Who:誰が What:何を Why:なぜ When:いつ Where:どこで How:どのように 山田が提案書類を作成中、3/5までに提出。 伊藤が休暇のため、3/10に顧客面談を変更。株式会社〇〇第3会議室。 このように、5W1Hを意識した文章にすることで、必要な情報を正確に伝えられます。 (4)共有・管理しやすいツールを使う 議事録の作成だけでなく、共有・管理がしやすいツールを使うこともポイントです。 議事録は、作成して終わりではなく、メンバーに共有したり振り返ったりする必要があります。しかし、WordやExcelでは、共有のたびにメールやチャットに添付する手間がかかるほか、ファイル数が増えて管理が煩雑になりやすいです。 一方、社内のあらゆる情報を集約して、”即アクセス”できる「ナレカン」のように検索性に優れたツールであれば、共有や振り返りもスムーズです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Word/Excelの議事録テンプレート・雛形まとめ ここまで、議事録の書き方や、作成におすすめのテンプレートを中心にご紹介しました。 テンプレートを活用すれば、効率よく議事録を作成できるうえ、「作成者によって内容が違う」といった問題を解消できます。ただし、WordやExcelで作成する場合、作成後の共有・管理に手間がかかってしまいます。 そこで、「自作のテンプレートを使って議事録の作成と蓄積を一元化できる情報共有ツール」を活用しましょう。また、過去の議事録を見返しやすく管理するためには、「検索機能が優れているか」にも注意して検討すべきです。 結論、自社が導入すべきなのは、探している情報に即アクセスでき、議事録を簡単に作成・共有・管理できるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、議事録の作成・共有・管理を効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年10月29日【無料フォーマットあり】見やすい議事録の書き方とは?会議やミーティングを実施するときに、議事録を作成しておけば、不参加だったメンバーに共有できるうえ、備忘録として後から振り返るのにも役立ちます。そのため、ビジネスにおいて、議事録の作成を求められるシーンは多いです。 一方で、「議事録の書き方が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、議事録の書き方のコツやWord/Excelフォーマットを紹介します。 議事録の作成に便利なおすすめのフォーマットを知りたい 会議の議事録を上手に活用するポイントを学びたい 議事録の作成・運用がスムーズにできるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、見やすい議事録のフォーマットが見つかるだけでなく、作成後の共有・管理を効率化する方法も分かります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 議事録を作成する目的とは2 【基本フォーマット付き】議事録に記載するべき項目3 即実践!見やすい議事録の書き方のコツとは3.1 コツ1|5W2Hを意識する3.2 コツ2|事実と所感を区別する3.3 コツ3|社内で共通のフォーマットを使う4 無料|見やすいWord/Excelのフォーマット・テンプレート7選4.1 【Word】シンプルな議事録フォーマット4.2 【Word】表形式の議事録フォーマット4.3 【Word】社外向け議事録に使えるフォーマット4.4 【Word】打ち合わせメモに便利な議事録フォーマット4.5 【Word】定時・臨時で使える株主総会議事録4.6 【Excel】自由に書き込める議事録フォーマット4.7 【Excel】議事と宿題を記入できる議事録フォーマット5 Word・Excelで議事録を作成する問題点とは6 最も簡単に議事録を作成・運用する方法6.1 Excelより簡単!見やすい議事録の作成・管理に最適な「ナレカン」7 ChatGPTで議事録を作るコツ7.1 コツ1|具体的かつ明確な指示をする7.2 コツ2|フォーマットや項目を指定する7.3 コツ3|回答をブラッシュアップする8 会議後に役立つ!議事録を上手に活用するポイント9 【徹底比較】議事録のダメな例/良い例10 見やすい議事録を作れるフォーマットやコツまとめ 議事録を作成する目的とは 議事録を作成するおもな目的として、以下の3点が挙げられます。 会議の内容を共有するため 議事録を作成すると、会議に参加していないメンバーへ「議論の内容」や「決定事項」を共有できます。議事録には会議の概要が簡潔にまとめられているので、口頭よりも正確に会議の内容を伝えられるのです。 認識を統一するため 議事録があれば、「会議でどのような課題が挙がったか」「次回までのタスクは何か」が明確になり、参加者間の認識を統一できます。また、口頭の情報共有で起きがちな、「言った・言わない」のトラブル防止にもつながるのです。 備忘録として残すため 議事録を作成すれば、備忘録として後から振り返りやすくなります。また、議事録に記載された社員の知識やノウハウは、今後の業務に活用できる情報資産となるので、適切に管理する必要があるのです。 このように、議事録を作成すると、口頭よりも正確に会議の内容を共有できるうえ、今後の業務にも役立たられます。したがって、会議や打ち合わせを実施するときは、議事録を忘れずに作成しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【基本フォーマット付き】議事録に記載するべき項目 議事録に記載するべき項目は以下の通りです。 項目 概要 会議の基本情報 日時、開催場所、参加者、欠席者、議長、書記 議題 会議で話す項目、アジェンダ 議論の内容 会議内容の要約、決定に至るまでの経緯、賛成意見や反対意見 決定事項 会議で決まったこと アクションプラン 誰が何をいつまでに実行するのか 次回の会議 次会議の日時、議題 その他 添付資料、参考資料、注意事項 以上の項目を入れると、必要な情報がそろった議事録を作成することができます。また、以下は会議議事録の作成に慣れていない方向けの基本フォーマットです。 作成日:〇月〇日(〇) 会議名:〇〇〇〇会議 場所:〇〇会議室 出席者:〇〇、〇〇、〇〇、〇〇(議事録作成者) 欠席者:〇〇、〇〇 議題:〇〇〇〇 議論内容:(決定に至るまでの経緯、賛成意見や反対意見) 決定事項を受けてやるべきこと: 保留事項:(今回は保留した議題) 次回会議の日時:〇月〇日(〇) 次回会議の議題:〇〇〇〇 その他連絡事項: 以上はコピペしてそのまま使えるフォーマットです。しかし、あくまで最低限の項目を示したフォーマットなため、会議の内容に応じて、必要な項目は適宜追加するようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 即実践!見やすい議事録の書き方のコツとは 以下では、見やすい議事録を作成するコツを3つご紹介します。読み手に正確に情報を伝えるためにも、以下の項目を意識しましょう。 コツ1|5W2Hを意識する 1つ目のコツは、「5W2H」を意識することです。5W2Hとは、以下の7項目を指します。 When(いつ) Where(どこで) Who(誰が) What(何を) Why(なぜ) How(どのように) How much(どのくらい) 上記を意識することで、冗長な文章を避けられるため、要点を正確に読み手に伝えられます。また、議事録に記載すべき内容が明確になり、作成者側もスムーズに議事録を書けるようになるのです。 さらに、文章だけでは表現が難しい場合は、記号や図を活用することで視覚的に分かりやすい議事録になります。 コツ2|事実と所感を区別する 2つ目のコツは、事実と所感を区別して書くことです。 客観的な事実と主観的な所感が混在すると、内容が分かりづらくなるうえ、読み手に誤解を与えてしまう恐れがあります。たとえば、「~と思われる」「~くらい」といった曖昧な表現は避けましょう。 したがって、事実ベースで必要事項を書いてから、最後に「所感」の項目を別で設けておくと情報が混在しません。ただし、議事録の目的によっては所感が必要ない場合もあるため、項目は適宜追加していく方法をとるべきです。 コツ3|社内で共通のフォーマットを使う 3つ目のコツは、社内で共有のフォーマットを使うことです。 議事録の作成者によって項目が違ったり、情報量にばらつきがあったりすると、読み手の混乱を招く恐れがあります。そこで、社内で共通のフォーマットを用意しておけば、議事録の書式を統一でき、後から振り返るときも見やすいです。 たとえば、テンプレートを自作できる「ナレカン」を使えば、自社に合ったテンプレートを作成して、数クリックで呼び起こせます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 無料|見やすいWord/Excelのフォーマット・テンプレート7選 以下は、見やすいWord・Excelの議事録フォーマットを7つご紹介します。以下のフォーマットを活用すると、基本項目を押さえた議事録をすぐに作成できます。 【Word】シンプルな議事録フォーマット ビジネス文書形式のシンプルな議事録です。 議事の経過や結果を示す欄があるので、内容を過不足なく伝えられます。 [文書]テンプレート|シンプルな議事録フォーマットの詳細はこちら 【Word】表形式の議事録フォーマット 議題ごとに内容や決定事項をまとめられる表形式のフォーマットです。 表の幅は字数によって広げられるので、情報量が多かったり複数の議題があったりする場合に便利です。 ビズ研|表形式の議事録フォーマットの詳細はこちら 【Word】社外向け議事録に使えるフォーマット 会議の概要を大まかに記載できるフォーマットです。 社外向けとしても使えるうえ、自由にカスタマイズ可能なので、用途に合わせて適宜項目を追加できます。 [文書]テンプレート|社外向け議事録に使えるフォーマットの詳細はこちら 【Word】打ち合わせメモに便利な議事録フォーマット 打ち合わせ中にメモもできるフォーマットです。 本フォーマットを印刷しておけば、手書きでメモができます。また、打ち合わせ内容を記録する表の「行の高さ」「罫線の種類」は、自由にカスタマイズ可能です。 [文書]テンプレート|打ち合わせメモに便利な議事録フォーマットの詳細はこちら 【Word】定時・臨時で使える株主総会議事録 定時・臨時いずれの株主総会にも使えるフォーマットです。 「出席者」「議長」「議事録作成者」といった『会社法施行規則 第72条』で法定されている株主総会議事録の記載事項を、抜け漏れなく記入できます。 参考:会社法施行規則>e-GOV法令検索 [文書]テンプレート|定時・臨時で使える株主総会議事録の詳細はこちら 【Excel】自由に書き込める議事録フォーマット 情報量や書き方の自由度が高いフォーマットです。 枠が広く確保されているうえ、「日時」「議題」などの基本項目のほかに「次回予定」も漏れなく記載できます。 [文書]テンプレート|自由に書き込める議事録フォーマットの詳細はこちら 【Excel】議事と宿題を記入できる議事録フォーマット 宿題の欄があるため、次回までのタスクを記載できるフォーマットです。 そのため、「誰が何をいつまでにやるか」が明確になります。加えて、会議で配布した参考資料を添付すれば、分かりやすい議事録を作成できます。 業務用テンプレート|議事と宿題を記入できる議事録フォーマットの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Word・Excelで議事録を作成する問題点とは Word・Excelで議事録を作成する問題点は以下の通りです。 共有しづらい ExcelやWordで作成した議事録を共有するには、メールやチャットなどの別のツールを使う必要があります。議事録は会議に参加していないメンバーに共有することで効果を発揮するため、共有しづらいことは大きなストレスになる可能性があります。 過去の議事録をすぐに見返せない WordやExcelで作成した議事録のファイルは、開くまで内容や詳細が分からないため過去の議事録を見返すときに時間がかかってしまいます。 管理が面倒 作成した議事録を適切に管理しておかなければ、情報が散在してしまいます。しかし、WordやExcelのファイルでは管理が煩雑になりがちで、とくにファイルが膨大な量になるとまとめて管理するのが難しいです。 WordやExcelのテンプレートを活用すれば簡単に議事録を作成できますが、上記のような問題点もあるため、導入を検討している方は注意が必要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 最も簡単に議事録を作成・運用する方法 以下では、最も簡単に議事録を作成・運用する方法をご紹介します。 見やすい議事録を手軽に作成したい人は「テンプレート機能を備えたツール」を導入しましょう。テンプレート機能を使えば、あらかじめ設定した議事録のフォーマットをWordやExcelよりも素早く呼び出せて、体裁の整った議事録を作成できます。 しかし、議事録にはその後のTodoも記載するので、会議後にも見返す点も考慮しなくてはいけません。そこで、あとから振り返るときにも必要な情報にすぐにアクセスできるように、「検索機能が充実しているツール」を選ぶことが大切です。 結論、議事録の作成・管理に最適なのは、テンプレート機能を備えているうえ、超高精度の検索が可能なノート型情報共有ツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは、あらかじめ作成したフォーマットを瞬時に呼び出せるうえ、ヒット率100%の「超高精度検索」によって欲しい情報を即座に取り出すことができます。そのため、議事録の作成・管理がひとつのツールで完結するのです。 Excelより簡単!見やすい議事録の作成・管理に最適な「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ChatGPTで議事録を作るコツ 以下では、ChatGPTで議事録を作るコツを3つご紹介します。ChatGPTを活用して、会議内容のメモや文字起こしから簡単に議事録を作成したい方は必見です。 コツ1|具体的かつ明確な指示をする 1つ目のコツは具体的かつ明確な指示をすることです。 正確な議事録を作成するには、生成AIによる推測力を減らす必要があるため、曖昧で抽象的な表現は避けましょう。たとえば、「どんな目的で誰に対する議事録なのか」を指定すると、目的や対象者に合った議事録を作成できます。 しかし、AIは事実と異なる内容を生成することがあるため、生成された議事録は必ず人間の目で確認する必要があります。 コツ2|フォーマットや項目を指定する 2つ目のコツは、フォーマットや項目を指定することです。 内容が正確であることだけでなく、見やすく整理された形式で出力させることも重要です。フォーマットや、記載してほしい項目をあらかじめ指定しておけば、読者が素早く内容を把握できる議事録を作成できます。 また、文体や表現ルールも指定しておくと、後から手作業で修正する手間を省けるため便利です。 コツ3|回答をブラッシュアップする 3つ目のコツは、回答をブラッシュアップすることです。 1回の指示だけでは理想の議事録を作成できない場合があるため、出力された議事録に対して指示を追加し、議事録をブラッシュアップしていく方法が効果的です。 たとえば、出力された議事録が客観的でなかった場合、主観を排除し、事実に基づいた出力を促すことで客観的な議事録を作成することができます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 会議後に役立つ!議事録を上手に活用するポイント 議事録を上手に活用するポイントは以下の通りです。 なるべく早く共有する 議事録を作成したら、なるべく早く共有することが重要です。決定事項やアクションプランを素早く共有することで、スピード感をもって業務を進められます。 定期的に振り返りをする 定期的に前回議事録を振り返り、「前回の決定事項は守られたか?」「決定した期日までにアクションプランを完了できたか?」などを確認しましょう。こうすることで、会議での決定事項が口先だけになるのを防げます。 ナレッジ化する 議事録をナレッジ化し、社内の情報として蓄積することで、新入社員が過去の意思決定や検討の経緯などを学び、会社に対しての理解度を高めるのに役立ちます。 以上のポイントを踏まえ、議事録を上手に活用し業務に役立てましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【徹底比較】議事録のダメな例/良い例 ここでは、議事録のダメな例とよい例をご紹介します。適切な情報共有のためにも事前に確認しておきましょう。 <ダメな議事録の例> 上記の議事録には「敬語が混ざっている」「打合せ内容の各発信者が明記されていない」「数字などの客観性に欠ける」などの改善点があります。そこで、改善点をもとに議事録を作成すると以下のようになります。 <良い議事録の例> 議事録は、あとから読み返すことを前提に作成すべき文書です。したがって、フォーマットや文末を整えたり、誰の発言かがわかる書き方を心がけましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 見やすい議事録を作れるフォーマットやコツまとめ ここまで、見やすい議事録を作れるフォーマットやコツを中心に紹介しました。 事前に項目をフォーマット化しておけば、議事録の書式を統一できるうえ、「認識のズレ」や「情報の抜け漏れ」を防げます。また、見やすい議事録にするためには、5W2Hを意識したり、箇条書きで簡潔にまとめたりすることも重要です。 ただし、WordやExcelのフォーマットで議事録を作成すると、「メールで共有する手間がかかる」「増えた議事録ファイルの管理が面倒になる」などのデメリットがあります。そのため、”議事録の作成から管理までの負担を解消するツール”が必須なのです。 結論、議事録の作成に最適なのは、議事録の作成・共有・管理を一元化するノート型ツール「ナレカン」一択です。ナレカンでは、独自の社内用語を「辞書登録」すること、議事録を作成するときに起こりがちな”表記揺れ”も考慮して、情報を振り返れます。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、議事録の悩みを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年10月29日【無料フォーマットあり】見やすい議事録の書き方とは?会議やミーティングを実施するときに、議事録を作成しておけば、不参加だったメンバーに共有できるうえ、備忘録として後から振り返るのにも役立ちます。そのため、ビジネスにおいて、議事録の作成を求められるシーンは多いです。 一方で、「議事録の書き方が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、議事録の書き方のコツやWord/Excelフォーマットを紹介します。 議事録の作成に便利なおすすめのフォーマットを知りたい 会議の議事録を上手に活用するポイントを学びたい 議事録の作成・運用がスムーズにできるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、見やすい議事録のフォーマットが見つかるだけでなく、作成後の共有・管理を効率化する方法も分かります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 議事録を作成する目的とは2 【基本フォーマット付き】議事録に記載するべき項目3 即実践!見やすい議事録の書き方のコツとは3.1 コツ1|5W2Hを意識する3.2 コツ2|事実と所感を区別する3.3 コツ3|社内で共通のフォーマットを使う4 無料|見やすいWord/Excelのフォーマット・テンプレート7選4.1 【Word】シンプルな議事録フォーマット4.2 【Word】表形式の議事録フォーマット4.3 【Word】社外向け議事録に使えるフォーマット4.4 【Word】打ち合わせメモに便利な議事録フォーマット4.5 【Word】定時・臨時で使える株主総会議事録4.6 【Excel】自由に書き込める議事録フォーマット4.7 【Excel】議事と宿題を記入できる議事録フォーマット5 Word・Excelで議事録を作成する問題点とは6 最も簡単に議事録を作成・運用する方法6.1 Excelより簡単!見やすい議事録の作成・管理に最適な「ナレカン」7 ChatGPTで議事録を作るコツ7.1 コツ1|具体的かつ明確な指示をする7.2 コツ2|フォーマットや項目を指定する7.3 コツ3|回答をブラッシュアップする8 会議後に役立つ!議事録を上手に活用するポイント9 【徹底比較】議事録のダメな例/良い例10 見やすい議事録を作れるフォーマットやコツまとめ 議事録を作成する目的とは 議事録を作成するおもな目的として、以下の3点が挙げられます。 会議の内容を共有するため 議事録を作成すると、会議に参加していないメンバーへ「議論の内容」や「決定事項」を共有できます。議事録には会議の概要が簡潔にまとめられているので、口頭よりも正確に会議の内容を伝えられるのです。 認識を統一するため 議事録があれば、「会議でどのような課題が挙がったか」「次回までのタスクは何か」が明確になり、参加者間の認識を統一できます。また、口頭の情報共有で起きがちな、「言った・言わない」のトラブル防止にもつながるのです。 備忘録として残すため 議事録を作成すれば、備忘録として後から振り返りやすくなります。また、議事録に記載された社員の知識やノウハウは、今後の業務に活用できる情報資産となるので、適切に管理する必要があるのです。 このように、議事録を作成すると、口頭よりも正確に会議の内容を共有できるうえ、今後の業務にも役立たられます。したがって、会議や打ち合わせを実施するときは、議事録を忘れずに作成しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【基本フォーマット付き】議事録に記載するべき項目 議事録に記載するべき項目は以下の通りです。 項目 概要 会議の基本情報 日時、開催場所、参加者、欠席者、議長、書記 議題 会議で話す項目、アジェンダ 議論の内容 会議内容の要約、決定に至るまでの経緯、賛成意見や反対意見 決定事項 会議で決まったこと アクションプラン 誰が何をいつまでに実行するのか 次回の会議 次会議の日時、議題 その他 添付資料、参考資料、注意事項 以上の項目を入れると、必要な情報がそろった議事録を作成することができます。また、以下は会議議事録の作成に慣れていない方向けの基本フォーマットです。 作成日:〇月〇日(〇) 会議名:〇〇〇〇会議 場所:〇〇会議室 出席者:〇〇、〇〇、〇〇、〇〇(議事録作成者) 欠席者:〇〇、〇〇 議題:〇〇〇〇 議論内容:(決定に至るまでの経緯、賛成意見や反対意見) 決定事項を受けてやるべきこと: 保留事項:(今回は保留した議題) 次回会議の日時:〇月〇日(〇) 次回会議の議題:〇〇〇〇 その他連絡事項: 以上はコピペしてそのまま使えるフォーマットです。しかし、あくまで最低限の項目を示したフォーマットなため、会議の内容に応じて、必要な項目は適宜追加するようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 即実践!見やすい議事録の書き方のコツとは 以下では、見やすい議事録を作成するコツを3つご紹介します。読み手に正確に情報を伝えるためにも、以下の項目を意識しましょう。 コツ1|5W2Hを意識する 1つ目のコツは、「5W2H」を意識することです。5W2Hとは、以下の7項目を指します。 When(いつ) Where(どこで) Who(誰が) What(何を) Why(なぜ) How(どのように) How much(どのくらい) 上記を意識することで、冗長な文章を避けられるため、要点を正確に読み手に伝えられます。また、議事録に記載すべき内容が明確になり、作成者側もスムーズに議事録を書けるようになるのです。 さらに、文章だけでは表現が難しい場合は、記号や図を活用することで視覚的に分かりやすい議事録になります。 コツ2|事実と所感を区別する 2つ目のコツは、事実と所感を区別して書くことです。 客観的な事実と主観的な所感が混在すると、内容が分かりづらくなるうえ、読み手に誤解を与えてしまう恐れがあります。たとえば、「~と思われる」「~くらい」といった曖昧な表現は避けましょう。 したがって、事実ベースで必要事項を書いてから、最後に「所感」の項目を別で設けておくと情報が混在しません。ただし、議事録の目的によっては所感が必要ない場合もあるため、項目は適宜追加していく方法をとるべきです。 コツ3|社内で共通のフォーマットを使う 3つ目のコツは、社内で共有のフォーマットを使うことです。 議事録の作成者によって項目が違ったり、情報量にばらつきがあったりすると、読み手の混乱を招く恐れがあります。そこで、社内で共通のフォーマットを用意しておけば、議事録の書式を統一でき、後から振り返るときも見やすいです。 たとえば、テンプレートを自作できる「ナレカン」を使えば、自社に合ったテンプレートを作成して、数クリックで呼び起こせます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 無料|見やすいWord/Excelのフォーマット・テンプレート7選 以下は、見やすいWord・Excelの議事録フォーマットを7つご紹介します。以下のフォーマットを活用すると、基本項目を押さえた議事録をすぐに作成できます。 【Word】シンプルな議事録フォーマット ビジネス文書形式のシンプルな議事録です。 議事の経過や結果を示す欄があるので、内容を過不足なく伝えられます。 [文書]テンプレート|シンプルな議事録フォーマットの詳細はこちら 【Word】表形式の議事録フォーマット 議題ごとに内容や決定事項をまとめられる表形式のフォーマットです。 表の幅は字数によって広げられるので、情報量が多かったり複数の議題があったりする場合に便利です。 ビズ研|表形式の議事録フォーマットの詳細はこちら 【Word】社外向け議事録に使えるフォーマット 会議の概要を大まかに記載できるフォーマットです。 社外向けとしても使えるうえ、自由にカスタマイズ可能なので、用途に合わせて適宜項目を追加できます。 [文書]テンプレート|社外向け議事録に使えるフォーマットの詳細はこちら 【Word】打ち合わせメモに便利な議事録フォーマット 打ち合わせ中にメモもできるフォーマットです。 本フォーマットを印刷しておけば、手書きでメモができます。また、打ち合わせ内容を記録する表の「行の高さ」「罫線の種類」は、自由にカスタマイズ可能です。 [文書]テンプレート|打ち合わせメモに便利な議事録フォーマットの詳細はこちら 【Word】定時・臨時で使える株主総会議事録 定時・臨時いずれの株主総会にも使えるフォーマットです。 「出席者」「議長」「議事録作成者」といった『会社法施行規則 第72条』で法定されている株主総会議事録の記載事項を、抜け漏れなく記入できます。 参考:会社法施行規則>e-GOV法令検索 [文書]テンプレート|定時・臨時で使える株主総会議事録の詳細はこちら 【Excel】自由に書き込める議事録フォーマット 情報量や書き方の自由度が高いフォーマットです。 枠が広く確保されているうえ、「日時」「議題」などの基本項目のほかに「次回予定」も漏れなく記載できます。 [文書]テンプレート|自由に書き込める議事録フォーマットの詳細はこちら 【Excel】議事と宿題を記入できる議事録フォーマット 宿題の欄があるため、次回までのタスクを記載できるフォーマットです。 そのため、「誰が何をいつまでにやるか」が明確になります。加えて、会議で配布した参考資料を添付すれば、分かりやすい議事録を作成できます。 業務用テンプレート|議事と宿題を記入できる議事録フォーマットの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Word・Excelで議事録を作成する問題点とは Word・Excelで議事録を作成する問題点は以下の通りです。 共有しづらい ExcelやWordで作成した議事録を共有するには、メールやチャットなどの別のツールを使う必要があります。議事録は会議に参加していないメンバーに共有することで効果を発揮するため、共有しづらいことは大きなストレスになる可能性があります。 過去の議事録をすぐに見返せない WordやExcelで作成した議事録のファイルは、開くまで内容や詳細が分からないため過去の議事録を見返すときに時間がかかってしまいます。 管理が面倒 作成した議事録を適切に管理しておかなければ、情報が散在してしまいます。しかし、WordやExcelのファイルでは管理が煩雑になりがちで、とくにファイルが膨大な量になるとまとめて管理するのが難しいです。 WordやExcelのテンプレートを活用すれば簡単に議事録を作成できますが、上記のような問題点もあるため、導入を検討している方は注意が必要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 最も簡単に議事録を作成・運用する方法 以下では、最も簡単に議事録を作成・運用する方法をご紹介します。 見やすい議事録を手軽に作成したい人は「テンプレート機能を備えたツール」を導入しましょう。テンプレート機能を使えば、あらかじめ設定した議事録のフォーマットをWordやExcelよりも素早く呼び出せて、体裁の整った議事録を作成できます。 しかし、議事録にはその後のTodoも記載するので、会議後にも見返す点も考慮しなくてはいけません。そこで、あとから振り返るときにも必要な情報にすぐにアクセスできるように、「検索機能が充実しているツール」を選ぶことが大切です。 結論、議事録の作成・管理に最適なのは、テンプレート機能を備えているうえ、超高精度の検索が可能なノート型情報共有ツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは、あらかじめ作成したフォーマットを瞬時に呼び出せるうえ、ヒット率100%の「超高精度検索」によって欲しい情報を即座に取り出すことができます。そのため、議事録の作成・管理がひとつのツールで完結するのです。 Excelより簡単!見やすい議事録の作成・管理に最適な「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ChatGPTで議事録を作るコツ 以下では、ChatGPTで議事録を作るコツを3つご紹介します。ChatGPTを活用して、会議内容のメモや文字起こしから簡単に議事録を作成したい方は必見です。 コツ1|具体的かつ明確な指示をする 1つ目のコツは具体的かつ明確な指示をすることです。 正確な議事録を作成するには、生成AIによる推測力を減らす必要があるため、曖昧で抽象的な表現は避けましょう。たとえば、「どんな目的で誰に対する議事録なのか」を指定すると、目的や対象者に合った議事録を作成できます。 しかし、AIは事実と異なる内容を生成することがあるため、生成された議事録は必ず人間の目で確認する必要があります。 コツ2|フォーマットや項目を指定する 2つ目のコツは、フォーマットや項目を指定することです。 内容が正確であることだけでなく、見やすく整理された形式で出力させることも重要です。フォーマットや、記載してほしい項目をあらかじめ指定しておけば、読者が素早く内容を把握できる議事録を作成できます。 また、文体や表現ルールも指定しておくと、後から手作業で修正する手間を省けるため便利です。 コツ3|回答をブラッシュアップする 3つ目のコツは、回答をブラッシュアップすることです。 1回の指示だけでは理想の議事録を作成できない場合があるため、出力された議事録に対して指示を追加し、議事録をブラッシュアップしていく方法が効果的です。 たとえば、出力された議事録が客観的でなかった場合、主観を排除し、事実に基づいた出力を促すことで客観的な議事録を作成することができます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 会議後に役立つ!議事録を上手に活用するポイント 議事録を上手に活用するポイントは以下の通りです。 なるべく早く共有する 議事録を作成したら、なるべく早く共有することが重要です。決定事項やアクションプランを素早く共有することで、スピード感をもって業務を進められます。 定期的に振り返りをする 定期的に前回議事録を振り返り、「前回の決定事項は守られたか?」「決定した期日までにアクションプランを完了できたか?」などを確認しましょう。こうすることで、会議での決定事項が口先だけになるのを防げます。 ナレッジ化する 議事録をナレッジ化し、社内の情報として蓄積することで、新入社員が過去の意思決定や検討の経緯などを学び、会社に対しての理解度を高めるのに役立ちます。 以上のポイントを踏まえ、議事録を上手に活用し業務に役立てましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【徹底比較】議事録のダメな例/良い例 ここでは、議事録のダメな例とよい例をご紹介します。適切な情報共有のためにも事前に確認しておきましょう。 <ダメな議事録の例> 上記の議事録には「敬語が混ざっている」「打合せ内容の各発信者が明記されていない」「数字などの客観性に欠ける」などの改善点があります。そこで、改善点をもとに議事録を作成すると以下のようになります。 <良い議事録の例> 議事録は、あとから読み返すことを前提に作成すべき文書です。したがって、フォーマットや文末を整えたり、誰の発言かがわかる書き方を心がけましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 見やすい議事録を作れるフォーマットやコツまとめ ここまで、見やすい議事録を作れるフォーマットやコツを中心に紹介しました。 事前に項目をフォーマット化しておけば、議事録の書式を統一できるうえ、「認識のズレ」や「情報の抜け漏れ」を防げます。また、見やすい議事録にするためには、5W2Hを意識したり、箇条書きで簡潔にまとめたりすることも重要です。 ただし、WordやExcelのフォーマットで議事録を作成すると、「メールで共有する手間がかかる」「増えた議事録ファイルの管理が面倒になる」などのデメリットがあります。そのため、”議事録の作成から管理までの負担を解消するツール”が必須なのです。 結論、議事録の作成に最適なのは、議事録の作成・共有・管理を一元化するノート型ツール「ナレカン」一択です。ナレカンでは、独自の社内用語を「辞書登録」すること、議事録を作成するときに起こりがちな”表記揺れ”も考慮して、情報を振り返れます。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、議事録の悩みを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年03月26日【見本あり】分かりやすい議事録に必要な項目や書き方のコツとは?ビジネスにおいて、会議や商談の備忘録として欠かせない議事録は、社内で取り扱う重要な情報のひとつです。 しかし、入社したばかりの新入社員や若手の場合、議事録を書いても作成・共有がスムーズにいかず悩む方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、分かりやすい議事録の書き方のポイントやコツを中心にご紹介します。 議事録の正しい書き方が分からない 分かりやすい議事録の書き方を知って作成時に活かしたい 議事録の作成を効率化したい という方はこの記事を参考にすると、正しい議事録の書き方が分かり、社内における情報共有の質が向上できるヒントを得られます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 【簡単】分かりやすい議事録の書き方2 議事録に必要な項目3 【見本あり】議事メモの例3.1 基本的な議事メモ3.2 会話形式の議事メモの書き方例4 議事録を素早く綺麗に書くコツ3選4.1 要点を押さえながらメモを取る4.2 アジェンダを作っておく4.3 作成後に整合性があるか確認する5 議事録が上手い人に共通する3つのポイントとは5.1 会議の目的が一目でわかる5.2 次のアクションが明確になっている5.3 内容が簡潔にまとめられている6 【やってはいけない】分かりづらい議事録の共通点とは6.1 会議の流れに沿って記載されていない6.2 情報に過不足がある6.3 体裁のみにこだわっている7 議事録のメモを残す手法8 【非IT企業向け】効率的に議事録を分かりやすく作成できるツール8.1 議事録の作成・管理を最も簡単に行えるツール「ナレカン」9 議事録作成に関するよくある質問10 分かりやすい議事録の取り方まとめ 【簡単】分かりやすい議事録の書き方 以下の3ステップが議事録の簡単な書き方です。 必要な項目を記載しておく 決定事項やToDoなどの項目は事前に設けておきます。会議中に決まる可能性が高く、重要度の高い項目はあらかじめ記載しておくことで時短に繋がるのです。 あらかじめ分かっている情報を記載する 会議の目的や参加者、場所などの事前に分かっている情報は記載しておきましょう。会議中は議論の内容を記録することだけに集中できるので、メモが追いつかない、抜け漏れるといった問題が生じづらいです。 項目内容をメモして整理する 会議中は、事前に設置した項目に沿って、議論を記録します。メモをそのまま提出するのではなく、相手に伝わりやすいように整理すれば、議事録は完成です。 上記の大まかな流れを押さえて、分かりやすい議事録を作成しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録に必要な項目 分かりやすい議事録を作成するには、次に挙げる7点の項目を盛り込むことが重要です。 会議名 会議名は議事録のタイトルである重要な部分です。議事録の内容をすぐに振り返るためにも、どのような内容であるのか一目でわかるように記載する必要があります。 日時 会議が行われた「証拠」を示す要素として、議事録には必ず会議の開始と終了の日時を記載しましょう。あらかじめ会議の日時が決まっている場合、先に入力しておくと記載漏れの心配がありません。 場所 場所は、会社名から実際に会議を行った会議室の場所までを正確に記載します。議事録は社内だけでなく、社外の人に対して共有するケースもあるので、場所の記載の仕方に注意しましょう。 出席者 出席者はクライアント側から「部署の序列順」に「役職の高い方から」記載しましょう。役職まで記載する必要があるため、出席者がどのような役職だったかメモに残さなくてはなりません。 議題 議題を記載する際には、箇条書きにするのがポイントです。議題の具体的な内容を指す一文を併せて記載すると、過去の議事録を見返した際に理解しやすくなります。 議論内容 議論内容は、具体的かつ簡潔に記載しましょう。たとえば、見出しを使うと文章にメリハリがつき、会議の内容が理解しやすくなります。 決定事項 会議における決定事項は、議事録を社外に共有する場合に相互認識のズレがないかどうか確認できるほか、次に行うべきことが把握しやすくなるので漏れなく記載しましょう。 上記を記載すると「いつどこで誰が何を議論したのか」が明確になり、決定事項に至る経緯がすぐに分かります。また、議事録の冒頭では書記の氏名を記載し、作成者を明らかにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【見本あり】議事メモの例 ここでは、項目ごとにコピペして使える「基本的な議事メモ」と「会話形式の議事メモ」の書き方サンプルをご紹介します。 基本的な議事メモ 以下は、基本的な議事録の書き方のサンプルです。以下の例文は幅広い業種で応用可能なので、議事録作成時に活用しましょう。 第1回新商品開発会議 文責:大道 日付:2021年12月6日(月) 場所:第1会議室 参加者:商品企画部 田中部長、浅井課長、林 営業部 西田係長、大道 議題:新商品開発の進め方 決定事項 ・今週までに商品企画部で新商品案を20個提出 ・営業部はニーズ調査として顧客へのアンケートを実施 議論内容 ・データが不十分で、顧客のニーズを正確に把握できない(田中部長) ・顧客のニーズを把握するためにアンケートを実施してはどうか(西田係長) 次回の予定 ・アンケートの結果をもとに商品案を絞り込む 次回会議日程:2023年9月7日(水)9時30分ー11時30分 このように、議事録には決定事項を端的に記載し、会議の不参加者でもすぐに要旨を把握できるようにしておく必要があります。 会話形式の議事メモの書き方例 会話形式の議事メモは、議論の内容を時系列に記載し、誰がどのような発言をしたのか明確に記す方式でメモを取ることが重要です。 会話形式で記録するメリットは、会議の流れが分かりやすく、参加者の発言が詳細に記載される点です。一方で、重要な内容がひと目で判別しづらくなる傾向にあるため、議事メモの最後に必ず決定事項を箇条書きでまとめておきましょう。 また、会話形式の議事メモを作成する際には「話し言葉を書き言葉に直す」「内容を要約して発言の要旨を明確化する」必要があります。そこで以下では、議論の発言を議事録に要約する具体例をご紹介します。 ケーススタディ:新入社員研修に関する議論 山中課長「新入社員向けの研修はどのような形式にしますか?昨年は社内でOJTを行いましたが、リソースが足りず通常業務にも影響が出てしまいました。」 大道部長「そうだな。昨年は研修の準備で忙しく、他の業務に手が回らなかったな。今年はOff-JTで外部講師に研修を依頼しよう。誰か費用の見積もりを出してくれないか。」 佐藤係長「わかりました。今月末までに外部研修にかかる費用を見積もります。」 上記の会話を踏まえた議事録 新入社員研修に関する議論 文責:佐藤 日付:2023年1月20日(金) 場所:第2会議室 参加者:大道部長、山中課長、佐藤 山中課長:新入社員向けの研修についてです。昨年は社内でOJTを行いましたが、リソースが足りず通常業務に影響がありました。 大道部長:昨年は研修で忙しく、ほかの業務に手が回らなかったので、今年はOff-JTで外部講師に研修を依頼しましょう。費用の見積もりをお願いします。 佐藤係長:承知しました。今月末までに外部研修にかかる費用を見積もります。 決定事項 ・新入社員研修はOff-JT形式で実施 ・Off-JTは外部講師に研修を依頼 ・1月末までにOff-JTの費用を見積もる(佐藤) 会話形式の議事メモでは、時系列に沿って各参加者がどのような発言をしたのかを要約して記載し、会議のフローを可視化することが重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録を素早く綺麗に書くコツ3選 ここでは、議事録を素早く綺麗に書く3つのコツを紹介します。見やすい議事録が作れなかったり、作成に時間がかかってしまったりする場合は、以下のポイントを参考にしましょう。 要点を押さえながらメモを取る 素早く綺麗な議事録を書くには、内容の要点を押さえながらメモに残しましょう。 会議中の質問・回答、発言者などの情報をメモとして簡潔にまとめておけば、効率的に議事録を作成できます。とくに、長時間の会議や参加者の多い会議であれば、内容をすべて記録することは困難なので、重要な情報のみピックアップしてメモを取りましょう。 また、メモを取る際にはテキストだけではなく、簡単な図やイラストを使うこともポイントです。視覚的に分かりやすく記録を残しておくと、見返したときに会議の内容が思い出しやすくなります。 アジェンダを作っておく 前もって「アジェンダ(話す予定の議題)」を作成しておくことも正確な議事録づくりに効果的です。 たとえば、新規の課題についてクライアントと検討する会議でも、会話が予想される内容をアジェンダとして議事録に落とし込んでおけば、会議に対する理解度も深まります。また、アジェンダを書いておくと議題がひと目で分かり、記録が取りやすくなるのです。 つまり、会議開始前にアジェンダを作成しておけば、素早く議事録が作れるうえに、議題に対する情報の記録漏れを防げるのです。 作成後に整合性があるか確認する 議事録作成後、出席者のもとで内容を確認すると、正確に記録が残せます。 議事録は、誰が読んでも会議の内容が理解できるように書く必要があります。そのため、自身が出席する会議で部下に議事録を依頼する際は、作成後に「端的に事実を述べられているか」「会議の内容が正しく反映されているか」を確認しましょう。 ほかの会議参加者に確認作業を依頼すれば、記載した情報の正確性が担保され、スムーズに文章を読み進められる議事録になります。ただし、会議から時間が経つと作成者・出席者ともに記憶が曖昧になるので、作成した議事録は素早く共有・確認しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録が上手い人に共通する3つのポイントとは 上手い人が作成する、共有した際に分かりやすい議事録には共通点があります。以下で紹介するポイントを押さえて、分かりやすい議事録の作成に役立てましょう。 会議の目的が一目でわかる 分かりやすい議事録は、会議の目的がひと目で分かります。 議事録は「備忘録として情報を書き留める」「情報共有により関係者同士の認識齟齬をなくす」目的で残すものです。そのため、会議の不参加者も対象とした情報共有が前提になるので、誰が見ても文章の意図を読み取れるように正確にまとめる必要があるのです。 そこで、たとえば「会議のテーマや課題に関する目的を端的にまとめる」と、会議の前提が共有出来て情報共有がスムーズになります。 次のアクションが明確になっている 分かりやすい議事録の共通点として、次のアクションが明確になっていることが挙げられます。 議事録には、打ち合わせやミーティングで「決定した内容」「タスク」の2つを明確にする役割があります。そのため、次の会議までに「誰が・何を・いつまでにするか」を洗い出して記載しておかなければなりません。 決定した内容に対して、明確に次のタスクが記載されていると、次にとるべきアクションがスムーズに理解できます。議事録作成の際には、次に対応するべきタスクを示すことを考慮しながら作業を進めましょう。 内容が簡潔にまとめられている 議事録が上手な人は、会議の内容が簡潔にまとめられています。 議事録は、短時間で内容を把握できるように簡潔に記載することが重要です。そのため、どこまで詳しく書くか悩むときには重要な情報のみを抜き出してまとめましょう。 また、冗長な文章で書かれていると読みづらく、読み手が知りたい情報にたどり着くまでに時間がかかってしまいます。そこで、「箇条書き」を用いて要点を示し、後ろに短く補足文を付け加える形で記載していくと、情報が視覚的に分かりやすくなります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【やってはいけない】分かりづらい議事録の共通点とは ここでは、分かりづらい議事録の共通点を紹介します。作成した議事録が読みにくい場合、以下のケースに当てはまっている可能性があるのです。 会議の流れに沿って記載されていない 分かりづらい議事録は、会議の流れに沿って記載されていません。 たとえば、複数の議題がある会議の場合、会議の流れに沿って記録が残されていなければ、あとから出席者が見返したときに混乱を招きます。 したがって、議事録は会議の流れに沿って作成しましょう。情報を正しく残せるように、5W1Hを意識することも重要です。 とくに、決定事項は各項目ごとに記載しなければ、その後のタスク対応が漏れる恐れがあるので注意しましょう。 情報に過不足がある 議事録に記載された情報に過不足があることも、分かりづらい議事録に共通するポイントのひとつです。 議事録は、会議の備忘録だけでなく関係各所との情報共有も兼ねています。そのため、議事録には共有内容を過不足なく記載し、共有された側がひと目で会議の内容を把握できるようにする必要があるのです。 そのほかにも、決定事項だけでなく会議中に共有された資料や参照元も正確に記載すると、不参加メンバーも議事録と会議資料を照らし合わせて確認できるので、情報の連携がスムーズになります。 体裁のみにこだわっている 綺麗に書こうとするあまり、議事録の体裁だけにこだわると分かりづらい議事録になってしまいます。 議事録の提出・共有に時間がかかれば、情報の記載漏れが発生するリスクが高まります。議事録は綺麗に書くことも重要な一方、情報を漏れなく共有するためにも、スピード感を持って作成しなければなりません。 たとえば、事前にフォーマットを用意し、必要事項を入力するだけで議事録が完成する状態にしておくと、作成時間を短縮しながら綺麗で分かりやすい議事録が残せます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録のメモを残す手法 議事録のメモを残す手法は主に以下の3つがあります。 手書き ノートやメモ帳に手書きで残す手法は、誰でもできる最も簡単な方法です。しかし、時間がかかるうえに、社員ごとに読みやすさのばらつきが大きいです。 PCのメモアプリ PCであれば、簡単かつ早く議論内容をメモできます。しかし、作成した議事録はメールなどを介して共有する必要があり、管理方法によってはデータ管理が煩雑になりがちです。 ITツール ITツールであれば、スムーズに議論内容を記録できるだけではなく、作成後の共有・管理まで一元化できます。ただし、ITツールは多機能すぎるものも多いため、社員が使いこなせるシンプルなツールを選択するべきです。 それぞれの特徴を踏まえて、自社に適した手法を選択しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【非IT企業向け】効率的に議事録を分かりやすく作成できるツール 以下では、効率的に議事録を分かりやすく作成できるツールを紹介します。 分かりやすい議事録を作るには、基本的な書き方を把握したうえで、コツを押さえることが重要です。また、過去の議事録を参考にしながら作成するのも、分かりやすい議事録に作成する方法のひとつです。 そこで、ITツールを使って議事録を作成・管理することで、過去の議事録を簡単に振り返れる環境を整えましょう。ただし、検索機能の不十分なITツールでは、必要な議事録がなかなか見つからず、議事録の作成に時間がかかります。 そのため、検索機能の充実したITツールを使って、議事録は管理するべきなのです。結論、自社の議事録作成に利用するべきツールは、高精度の検索機能で欲しい議事録がすぐに見つかるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンには、「ヒット率100%」の検索機能に加えて、わずかな手順でテンプレートを呼び出せる機能があります。そのため、過去の議事録を参考にする場合も、テンプレートを使う場合も、簡単に議事録を作成できます。 議事録の作成・管理を最も簡単に行えるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録作成に関するよくある質問 議事録作成に関するよくある質問は、以下の2つです。 議事録を訂正する場合はどうする? 会議の参加者に共有する前であれば速やかに修正して、共有後の場合は修正箇所が分かるようにして再共有します。このとき、ITツールであれば、訂正作業が簡単なうえ、メッセージ機能が付いていれば連絡も素早く実施できます。 議事録作成後はどうする? 議事録を作成した後は、先輩社員・上司の確認をとります。議論の内容や決定事項は迅速に共有する必要があるため、会議終了後できるだけ速く提出しましょう。 自社の業務に合わせて、訂正時や作成後のルールはあらかじめ定めておきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 分かりやすい議事録の取り方まとめ ここまで、分かりやすい議事録の書き方を中心に解説しました。 議事録は、会議の内容をひと目で把握できるように、要点を押さえながらスピード感を持って作成することが重要です。とくに、議論内容や決定事項など議事録に必要な項目は確実に記載して、迅速に提出・共有しなければなりません。 しかし、紙やメールのアナログな手法を用いて議事録を作成すると、共有に手間がかかるうえに管理が難しく、必要なときに目的の情報が見つからない可能性があるのです。したがって、ITツールを用いて議事録の作成から管理までを効率化させるべきです。 そこで、簡単に社内の情報共有を活性化できるツール「ナレカン」を使うと、議事録の作成管理はもちろん、全社の情報蓄積にも最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入し、議事録をはじめとした社内の情報共有・管理のストレスを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年03月26日【見本あり】分かりやすい議事録に必要な項目や書き方のコツとは?ビジネスにおいて、会議や商談の備忘録として欠かせない議事録は、社内で取り扱う重要な情報のひとつです。 しかし、入社したばかりの新入社員や若手の場合、議事録を書いても作成・共有がスムーズにいかず悩む方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、分かりやすい議事録の書き方のポイントやコツを中心にご紹介します。 議事録の正しい書き方が分からない 分かりやすい議事録の書き方を知って作成時に活かしたい 議事録の作成を効率化したい という方はこの記事を参考にすると、正しい議事録の書き方が分かり、社内における情報共有の質が向上できるヒントを得られます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 【簡単】分かりやすい議事録の書き方2 議事録に必要な項目3 【見本あり】議事メモの例3.1 基本的な議事メモ3.2 会話形式の議事メモの書き方例4 議事録を素早く綺麗に書くコツ3選4.1 要点を押さえながらメモを取る4.2 アジェンダを作っておく4.3 作成後に整合性があるか確認する5 議事録が上手い人に共通する3つのポイントとは5.1 会議の目的が一目でわかる5.2 次のアクションが明確になっている5.3 内容が簡潔にまとめられている6 【やってはいけない】分かりづらい議事録の共通点とは6.1 会議の流れに沿って記載されていない6.2 情報に過不足がある6.3 体裁のみにこだわっている7 議事録のメモを残す手法8 【非IT企業向け】効率的に議事録を分かりやすく作成できるツール8.1 議事録の作成・管理を最も簡単に行えるツール「ナレカン」9 議事録作成に関するよくある質問10 分かりやすい議事録の取り方まとめ 【簡単】分かりやすい議事録の書き方 以下の3ステップが議事録の簡単な書き方です。 必要な項目を記載しておく 決定事項やToDoなどの項目は事前に設けておきます。会議中に決まる可能性が高く、重要度の高い項目はあらかじめ記載しておくことで時短に繋がるのです。 あらかじめ分かっている情報を記載する 会議の目的や参加者、場所などの事前に分かっている情報は記載しておきましょう。会議中は議論の内容を記録することだけに集中できるので、メモが追いつかない、抜け漏れるといった問題が生じづらいです。 項目内容をメモして整理する 会議中は、事前に設置した項目に沿って、議論を記録します。メモをそのまま提出するのではなく、相手に伝わりやすいように整理すれば、議事録は完成です。 上記の大まかな流れを押さえて、分かりやすい議事録を作成しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録に必要な項目 分かりやすい議事録を作成するには、次に挙げる7点の項目を盛り込むことが重要です。 会議名 会議名は議事録のタイトルである重要な部分です。議事録の内容をすぐに振り返るためにも、どのような内容であるのか一目でわかるように記載する必要があります。 日時 会議が行われた「証拠」を示す要素として、議事録には必ず会議の開始と終了の日時を記載しましょう。あらかじめ会議の日時が決まっている場合、先に入力しておくと記載漏れの心配がありません。 場所 場所は、会社名から実際に会議を行った会議室の場所までを正確に記載します。議事録は社内だけでなく、社外の人に対して共有するケースもあるので、場所の記載の仕方に注意しましょう。 出席者 出席者はクライアント側から「部署の序列順」に「役職の高い方から」記載しましょう。役職まで記載する必要があるため、出席者がどのような役職だったかメモに残さなくてはなりません。 議題 議題を記載する際には、箇条書きにするのがポイントです。議題の具体的な内容を指す一文を併せて記載すると、過去の議事録を見返した際に理解しやすくなります。 議論内容 議論内容は、具体的かつ簡潔に記載しましょう。たとえば、見出しを使うと文章にメリハリがつき、会議の内容が理解しやすくなります。 決定事項 会議における決定事項は、議事録を社外に共有する場合に相互認識のズレがないかどうか確認できるほか、次に行うべきことが把握しやすくなるので漏れなく記載しましょう。 上記を記載すると「いつどこで誰が何を議論したのか」が明確になり、決定事項に至る経緯がすぐに分かります。また、議事録の冒頭では書記の氏名を記載し、作成者を明らかにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【見本あり】議事メモの例 ここでは、項目ごとにコピペして使える「基本的な議事メモ」と「会話形式の議事メモ」の書き方サンプルをご紹介します。 基本的な議事メモ 以下は、基本的な議事録の書き方のサンプルです。以下の例文は幅広い業種で応用可能なので、議事録作成時に活用しましょう。 第1回新商品開発会議 文責:大道 日付:2021年12月6日(月) 場所:第1会議室 参加者:商品企画部 田中部長、浅井課長、林 営業部 西田係長、大道 議題:新商品開発の進め方 決定事項 ・今週までに商品企画部で新商品案を20個提出 ・営業部はニーズ調査として顧客へのアンケートを実施 議論内容 ・データが不十分で、顧客のニーズを正確に把握できない(田中部長) ・顧客のニーズを把握するためにアンケートを実施してはどうか(西田係長) 次回の予定 ・アンケートの結果をもとに商品案を絞り込む 次回会議日程:2023年9月7日(水)9時30分ー11時30分 このように、議事録には決定事項を端的に記載し、会議の不参加者でもすぐに要旨を把握できるようにしておく必要があります。 会話形式の議事メモの書き方例 会話形式の議事メモは、議論の内容を時系列に記載し、誰がどのような発言をしたのか明確に記す方式でメモを取ることが重要です。 会話形式で記録するメリットは、会議の流れが分かりやすく、参加者の発言が詳細に記載される点です。一方で、重要な内容がひと目で判別しづらくなる傾向にあるため、議事メモの最後に必ず決定事項を箇条書きでまとめておきましょう。 また、会話形式の議事メモを作成する際には「話し言葉を書き言葉に直す」「内容を要約して発言の要旨を明確化する」必要があります。そこで以下では、議論の発言を議事録に要約する具体例をご紹介します。 ケーススタディ:新入社員研修に関する議論 山中課長「新入社員向けの研修はどのような形式にしますか?昨年は社内でOJTを行いましたが、リソースが足りず通常業務にも影響が出てしまいました。」 大道部長「そうだな。昨年は研修の準備で忙しく、他の業務に手が回らなかったな。今年はOff-JTで外部講師に研修を依頼しよう。誰か費用の見積もりを出してくれないか。」 佐藤係長「わかりました。今月末までに外部研修にかかる費用を見積もります。」 上記の会話を踏まえた議事録 新入社員研修に関する議論 文責:佐藤 日付:2023年1月20日(金) 場所:第2会議室 参加者:大道部長、山中課長、佐藤 山中課長:新入社員向けの研修についてです。昨年は社内でOJTを行いましたが、リソースが足りず通常業務に影響がありました。 大道部長:昨年は研修で忙しく、ほかの業務に手が回らなかったので、今年はOff-JTで外部講師に研修を依頼しましょう。費用の見積もりをお願いします。 佐藤係長:承知しました。今月末までに外部研修にかかる費用を見積もります。 決定事項 ・新入社員研修はOff-JT形式で実施 ・Off-JTは外部講師に研修を依頼 ・1月末までにOff-JTの費用を見積もる(佐藤) 会話形式の議事メモでは、時系列に沿って各参加者がどのような発言をしたのかを要約して記載し、会議のフローを可視化することが重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録を素早く綺麗に書くコツ3選 ここでは、議事録を素早く綺麗に書く3つのコツを紹介します。見やすい議事録が作れなかったり、作成に時間がかかってしまったりする場合は、以下のポイントを参考にしましょう。 要点を押さえながらメモを取る 素早く綺麗な議事録を書くには、内容の要点を押さえながらメモに残しましょう。 会議中の質問・回答、発言者などの情報をメモとして簡潔にまとめておけば、効率的に議事録を作成できます。とくに、長時間の会議や参加者の多い会議であれば、内容をすべて記録することは困難なので、重要な情報のみピックアップしてメモを取りましょう。 また、メモを取る際にはテキストだけではなく、簡単な図やイラストを使うこともポイントです。視覚的に分かりやすく記録を残しておくと、見返したときに会議の内容が思い出しやすくなります。 アジェンダを作っておく 前もって「アジェンダ(話す予定の議題)」を作成しておくことも正確な議事録づくりに効果的です。 たとえば、新規の課題についてクライアントと検討する会議でも、会話が予想される内容をアジェンダとして議事録に落とし込んでおけば、会議に対する理解度も深まります。また、アジェンダを書いておくと議題がひと目で分かり、記録が取りやすくなるのです。 つまり、会議開始前にアジェンダを作成しておけば、素早く議事録が作れるうえに、議題に対する情報の記録漏れを防げるのです。 作成後に整合性があるか確認する 議事録作成後、出席者のもとで内容を確認すると、正確に記録が残せます。 議事録は、誰が読んでも会議の内容が理解できるように書く必要があります。そのため、自身が出席する会議で部下に議事録を依頼する際は、作成後に「端的に事実を述べられているか」「会議の内容が正しく反映されているか」を確認しましょう。 ほかの会議参加者に確認作業を依頼すれば、記載した情報の正確性が担保され、スムーズに文章を読み進められる議事録になります。ただし、会議から時間が経つと作成者・出席者ともに記憶が曖昧になるので、作成した議事録は素早く共有・確認しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録が上手い人に共通する3つのポイントとは 上手い人が作成する、共有した際に分かりやすい議事録には共通点があります。以下で紹介するポイントを押さえて、分かりやすい議事録の作成に役立てましょう。 会議の目的が一目でわかる 分かりやすい議事録は、会議の目的がひと目で分かります。 議事録は「備忘録として情報を書き留める」「情報共有により関係者同士の認識齟齬をなくす」目的で残すものです。そのため、会議の不参加者も対象とした情報共有が前提になるので、誰が見ても文章の意図を読み取れるように正確にまとめる必要があるのです。 そこで、たとえば「会議のテーマや課題に関する目的を端的にまとめる」と、会議の前提が共有出来て情報共有がスムーズになります。 次のアクションが明確になっている 分かりやすい議事録の共通点として、次のアクションが明確になっていることが挙げられます。 議事録には、打ち合わせやミーティングで「決定した内容」「タスク」の2つを明確にする役割があります。そのため、次の会議までに「誰が・何を・いつまでにするか」を洗い出して記載しておかなければなりません。 決定した内容に対して、明確に次のタスクが記載されていると、次にとるべきアクションがスムーズに理解できます。議事録作成の際には、次に対応するべきタスクを示すことを考慮しながら作業を進めましょう。 内容が簡潔にまとめられている 議事録が上手な人は、会議の内容が簡潔にまとめられています。 議事録は、短時間で内容を把握できるように簡潔に記載することが重要です。そのため、どこまで詳しく書くか悩むときには重要な情報のみを抜き出してまとめましょう。 また、冗長な文章で書かれていると読みづらく、読み手が知りたい情報にたどり着くまでに時間がかかってしまいます。そこで、「箇条書き」を用いて要点を示し、後ろに短く補足文を付け加える形で記載していくと、情報が視覚的に分かりやすくなります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【やってはいけない】分かりづらい議事録の共通点とは ここでは、分かりづらい議事録の共通点を紹介します。作成した議事録が読みにくい場合、以下のケースに当てはまっている可能性があるのです。 会議の流れに沿って記載されていない 分かりづらい議事録は、会議の流れに沿って記載されていません。 たとえば、複数の議題がある会議の場合、会議の流れに沿って記録が残されていなければ、あとから出席者が見返したときに混乱を招きます。 したがって、議事録は会議の流れに沿って作成しましょう。情報を正しく残せるように、5W1Hを意識することも重要です。 とくに、決定事項は各項目ごとに記載しなければ、その後のタスク対応が漏れる恐れがあるので注意しましょう。 情報に過不足がある 議事録に記載された情報に過不足があることも、分かりづらい議事録に共通するポイントのひとつです。 議事録は、会議の備忘録だけでなく関係各所との情報共有も兼ねています。そのため、議事録には共有内容を過不足なく記載し、共有された側がひと目で会議の内容を把握できるようにする必要があるのです。 そのほかにも、決定事項だけでなく会議中に共有された資料や参照元も正確に記載すると、不参加メンバーも議事録と会議資料を照らし合わせて確認できるので、情報の連携がスムーズになります。 体裁のみにこだわっている 綺麗に書こうとするあまり、議事録の体裁だけにこだわると分かりづらい議事録になってしまいます。 議事録の提出・共有に時間がかかれば、情報の記載漏れが発生するリスクが高まります。議事録は綺麗に書くことも重要な一方、情報を漏れなく共有するためにも、スピード感を持って作成しなければなりません。 たとえば、事前にフォーマットを用意し、必要事項を入力するだけで議事録が完成する状態にしておくと、作成時間を短縮しながら綺麗で分かりやすい議事録が残せます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録のメモを残す手法 議事録のメモを残す手法は主に以下の3つがあります。 手書き ノートやメモ帳に手書きで残す手法は、誰でもできる最も簡単な方法です。しかし、時間がかかるうえに、社員ごとに読みやすさのばらつきが大きいです。 PCのメモアプリ PCであれば、簡単かつ早く議論内容をメモできます。しかし、作成した議事録はメールなどを介して共有する必要があり、管理方法によってはデータ管理が煩雑になりがちです。 ITツール ITツールであれば、スムーズに議論内容を記録できるだけではなく、作成後の共有・管理まで一元化できます。ただし、ITツールは多機能すぎるものも多いため、社員が使いこなせるシンプルなツールを選択するべきです。 それぞれの特徴を踏まえて、自社に適した手法を選択しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【非IT企業向け】効率的に議事録を分かりやすく作成できるツール 以下では、効率的に議事録を分かりやすく作成できるツールを紹介します。 分かりやすい議事録を作るには、基本的な書き方を把握したうえで、コツを押さえることが重要です。また、過去の議事録を参考にしながら作成するのも、分かりやすい議事録に作成する方法のひとつです。 そこで、ITツールを使って議事録を作成・管理することで、過去の議事録を簡単に振り返れる環境を整えましょう。ただし、検索機能の不十分なITツールでは、必要な議事録がなかなか見つからず、議事録の作成に時間がかかります。 そのため、検索機能の充実したITツールを使って、議事録は管理するべきなのです。結論、自社の議事録作成に利用するべきツールは、高精度の検索機能で欲しい議事録がすぐに見つかるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンには、「ヒット率100%」の検索機能に加えて、わずかな手順でテンプレートを呼び出せる機能があります。そのため、過去の議事録を参考にする場合も、テンプレートを使う場合も、簡単に議事録を作成できます。 議事録の作成・管理を最も簡単に行えるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録作成に関するよくある質問 議事録作成に関するよくある質問は、以下の2つです。 議事録を訂正する場合はどうする? 会議の参加者に共有する前であれば速やかに修正して、共有後の場合は修正箇所が分かるようにして再共有します。このとき、ITツールであれば、訂正作業が簡単なうえ、メッセージ機能が付いていれば連絡も素早く実施できます。 議事録作成後はどうする? 議事録を作成した後は、先輩社員・上司の確認をとります。議論の内容や決定事項は迅速に共有する必要があるため、会議終了後できるだけ速く提出しましょう。 自社の業務に合わせて、訂正時や作成後のルールはあらかじめ定めておきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 分かりやすい議事録の取り方まとめ ここまで、分かりやすい議事録の書き方を中心に解説しました。 議事録は、会議の内容をひと目で把握できるように、要点を押さえながらスピード感を持って作成することが重要です。とくに、議論内容や決定事項など議事録に必要な項目は確実に記載して、迅速に提出・共有しなければなりません。 しかし、紙やメールのアナログな手法を用いて議事録を作成すると、共有に手間がかかるうえに管理が難しく、必要なときに目的の情報が見つからない可能性があるのです。したがって、ITツールを用いて議事録の作成から管理までを効率化させるべきです。 そこで、簡単に社内の情報共有を活性化できるツール「ナレカン」を使うと、議事録の作成管理はもちろん、全社の情報蓄積にも最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入し、議事録をはじめとした社内の情報共有・管理のストレスを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年10月01日【例文あり】議事録とは?分かりやすい書き方の特徴や目的も解説!会議や定例会で必ず作成される資料として「議事録」があります。議事録は、会議を振り返ったり欠席のメンバーへ情報を共有したりするときに不可欠な資料です。 しかし、書記として議事録を作成したいが「どう書けば良いのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、議事録の分かりやすい書き方や目的を中心にご紹介します。 議事録を作成する目的を知りたい 分かりやすい議事録の書き方を自社で導入したい 議事録の共有・管理までスムーズに行いたい という方はこの記事を参考にすると、分かりやすい議事録が書けるようになるほか、議事録を簡単に共有する方法も分かります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 議事録とは2 議事録を書く3つの目的2.1 目的1|会議の備忘録を残す2.2 目的2|会議の決定事項を共有する2.3 目的3|社内メンバーの認識をすり合わせる3 分かりやすい議事録の書き方3.1 (1)事前準備を徹底する3.2 (2)要点を箇条書きにする3.3 (3)冗長な表現を避ける3.4 (4)5W2Hを意識する3.5 (5)迅速に共有する3.6 (6)フォーマットを統一する3.7 (7)ITツールを活用する3.8 (8)資料も添付する4 【必見】議事録を最も簡単に作成・共有・確認できるITツール4.1 社内の議事録をナレッジ化して見やすく管理するツール「ナレカン」5 【例文あり】ナレカンでそのまま使える議事録の書き方見本6 議事録の書き方に関するQ&A7 議事録のダメな例8 メモが追い付かない?議事録作成が上手い人/早い人の特徴3選8.1 (1)記号を使う8.2 (2)テンプレートを活用する8.3 (3)議事録を作成しやすいツールを活用する9 【無料で使える】議事録のフォーマット・テンプレート3選9.1 (1)進捗共有会議に使える議事録9.2 (2)シンプルな会議議事録9.3 (3)議事録・会議報告書10 議事録は、WordとExcelのどっちでまとめるべきか?11 議事録の書き方や目的まとめ 議事録とは 議事録とは、会議の内容を記録するための文書を指します。 議事録があれば「どのような意見が交わされて、最終的に何が決まったのか」の事実確認がとれます。さらに、チームメンバーに会議の内容を共有する目的もあるので、抜け漏れなく記載しなければなりません。 このように、会議の決定事項を確実に記録・共有するうえで、議事録は必須です。また、議事録には会社の重要な決定事項が記載されているので、ナレッジとして確実に保管しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録を書く3つの目的 ここでは、議事録を書く3つの目的をご紹介します。議事録の作成には、会社の経営判断にもつながる重要な役割があるので必見です。 目的1|会議の備忘録を残す 1つ目に、議事録の目的として、会議の備忘録を残すことが挙げられます。 議事録を記載すれば、業務進捗をはじめとした事実確認がとれます。そのため、口頭でのやりとりにありがちな「言った・言わない」のトラブルを防げるのです。 したがって、あとから正確な情報を振り返れるように、議事録は項目の抜け漏れがないように記載しなければなりません。 目的2|会議の決定事項を共有する 2つ目に、会議の決定事項を共有することも、議事録の目的です。 会議によっては、責任者や主要メンバーなど、一部の関係者のみで開催されるケースもあります。このような場合に、議事録を作成すれば、会議に参加していないメンバーにも決定事項を伝えられるのです。 そのため、社内メンバー全員が「どのような議論があったのか」を把握できるように、共有するときは要点を明確にしましょう。 目的3|社内メンバーの認識をすり合わせる 3つ目に、社内メンバーの認識をすり合わせる目的もあります。 たとえば、会議の場で共有した情報が、正確に相手へ伝わっていないと認識のズレが生じてしまいます。認識がずれていると、その後の業務に支障をきたす場合もあるのです。 そこで、会議後の議事録の共有をルール化しておけば、全員が正しい情報を参照できるので、議論に関する認識齟齬を防げます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 分かりやすい議事録の書き方 ここでは、分かりやすい議事録の書き方をご紹介します。議事録を作成するにあたり、押さえるべき点を知りたい方は必見です。 (1)事前準備を徹底する 議事録を書く1つ目のルールは、事前準備を徹底することです。 日時や場所、参加者、会議内容などの情報は、会議の前に分かっているケースが大半です。そのため、このような項目をあらかじめ設定しておくと、会議中に慌てて構成を考える必要がありません。 また、過去の議事録から「どのような項目があるのか」を確認するのも、事前準備として取り入れましょう。 (2)要点を箇条書きにする 2つ目に、議事録では、要点を箇条書きにすることが大切です。 会議の内容をそのまま議事録へ羅列しただけでは、メリハリがなく、情報が相手へ伝わりづらくなってしまいます。しかし、要点を箇条書きにすれば、重要事項が明確になり、全体の内容もスムーズに理解できるのです。 加えて、箇条書きであれば情報を少なく絞れるので、議事録の作成に無駄な時間がかかりません。 (3)冗長な表現を避ける 3つ目に、相手に分かりやすくするには、冗長な表現を避け、簡潔に記載しましょう。 議事録で冗長な文章が多ければ、内容を理解するのに時間がかかり、読むだけでもストレスになってしまいます。その結果、「議事録を見たが、会議でどのような決定があったか分からなかった」ともなりかねません。 したがって、議事録では平易な文章を心がけ、内容の過不足がないように記載すべきなのです。たとえば、敬語の「です・ます調」ではなく「だ・である調」を使ったり「一文に一要素」を意識したりすることが有効です。 (4)5W2Hを意識する 4つ目に、5W2Hを明確に記載することも重要です。具体的には、以下の要素を指します。 When(いつ) Where(どこで) Who(誰が) What(何を) Why(なぜ) How(どのように) How Much(いくらで) 上記のフレームワークを押さえれば、文章が曖昧になるのを防いだり、記載漏れがないかを確かめたりするのに役立ちます。 (5)迅速に共有する 5つ目に、会議内容の振り返りに役立てるためにも、迅速な共有が求められます。 議事録の共有に時間がかかると、一部の社員が会議内容を把握できない状態になり、業務の遅れにつながってしまいます。そのため、議事録は遅くとも翌営業日までに仕上げて共有するのが望ましいです。 ただし、スピードを意識するあまり内容に不備があっては意味がありません。したがって、一度議事録を作成したら添削を受けて、精度の高い状態で共有しましょう。 (6)フォーマットを統一する 6つ目に、議事録のフォーマットを社内で統一することも効果的です。 議事録の作り方が属人化している場合、情報が抜け漏れる恐れがあります。しかし、フォーマットがあれば記録すべき項目が明確になるため、全員が正確に情報を残せるようになるのです。 また、社内でフォーマットが統一されていれば、各々で構成を考える必要がないので、作成時間の短縮にもつながります。 (7)ITツールを活用する 7つ目に、分かりやすい議事録を書くうえでは、ITツールも欠かせません。 紙で議事録を作成している場合、修正が重なって見づらくなるケースも多いです。一方、ITツールを活用すれば、クリック操作だけで議事録の記載や修正ができるので、常に分かりやすい状態に保てます。 ただし、ツールの機能が多機能すぎると、ITが苦手なメンバーが使いこなせません。そのため、操作がシンプル・簡単な「ナレカン」のようなツールを導入して、ツールが形骸化しないようにしましょう。 (8)資料も添付する 8つ目に、会議で共有された資料の添付も重要です。 議事録に資料を添付すると、会議で決定された企画・施策がどのようなデータをもとにしていたか、といったことが振り返りやすくなるのです。また会議に出席していない人が、会議の内容を理解するのにも役立ちます。 以上のように、出席者もそうでない人も会議の内容について共通認識を持てるよう、資料共有まで行うようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】議事録を最も簡単に作成・共有・確認できるITツール 以下では、議事録を最も簡単に作成・共有・確認できるITツールをご紹介します。 会議の内容は、後から振り返れるように議事録としてまとめて社員に共有するべきです。しかしWordやExcelは、内容を確認するのに都度ファイルを開かなければならないうえ、他のファイルに埋もれて見つからなくなりがちです。 そこで、「誰でも簡単に議事録を作成・共有可能なツール」を導入しましょう。また、作成した議事録をツール上でそのまま共有できると、情報を探す際に逐一ファイルを開封する手間もかかりません。 結論、議事録の作成・共有・確認に最適なのは、直感的な操作で直接記事に書き込んで簡単に議事録を作成でき、超高精度な検索機能で必要な情報がすぐに見つかるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは、作成した議事録をファイル形式にする必要がなく、直接記載~共有まで一元的に行えるほか、一度作成した議事録はテンプレート化できるため、議事録の作成にかかる時間が短縮されます。また、社内用語も「超高精度な検索機能」でヒットするため、後から振り返る際に必要な情報をすぐに見つけられるのです。 社内の議事録をナレッジ化して見やすく管理するツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【例文あり】ナレカンでそのまま使える議事録の書き方見本 以下では、すぐに使える議事録のフォーマット例をご紹介します。 <会議名/開始・終了日時/開催場所> 20〇〇年〇月〇日16時〜17時〇〇株式会社第3会議室 <参加者> 〇〇株式会社:〜部長、〜課長、〜係長、〜様/自社:△△、□□ <会議の目的> 製品〇〇に関する原材料の高騰における価格調整および決定 <決定事項> 協力会社T社との意思決定も反映させたうえで詳細レンジを確定させる <補足事項> T社の資材調達責任者が出張により〇月〇日まで不在 <次回の議題> 最終的な価格調整にあたっての懸念点解消 <参考資料> 価格高騰の推移レポートと価格レンジの傾向 上記の例をコピー&ペーストして、短時間で議事録を作成しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録の書き方に関するQ&A 以下では、議事録の書き方に関するよくある質問と回答をご紹介します。とくに、議事録の書き方に不安がある担当者の方は必見です。 質問1|議事録の上手な取り方は? 会議の内容の全てをメモするのではなく、重要な部分のみをメモすると、要点がまとまった議事録になります。具体的には、「会議内容を事前に把握する」「日時や数値は確実に記載する」「略語や記号を使う」と効率よくメモがとれます。 質問2|議事録は誰が書くべきか? 一般的には役職の低い社員や若手社員に任される場合が多いです。しかし年齢・役職にとらわれず情報整理能力が高い社員が作成すると、分かりやすい議事録となり、会議内容の認識の齟齬がなくなります。 以上のように、議事録の書き方や作成者の設定を工夫すると、時間をかけずに分かりやすい議事録を作成できるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録のダメな例 議事録を作成する際に、無意識のうちに「ダメな議事録」になってしまっている場合があります。以下の表で自分が作成した議事録が「ダメな例」に当てはまっていないか確認しましょう。 ダメな例 理由 ・専門用語の多用あるいは補足説明がない 新入社員や業務経験が浅い社員から理解を得るのに時間がかかるため ・意見と事実が混合して記載されている 結論が分かりづらく、認識の違いが生まれやすくなるため ・作成・共有に時間をかけている 会議の記憶が曖昧になり、会議の内容の定着・振り返りが不十分になるため 作成した議事録を有効活用するためにも、ダメな例に当てはまっていないか、再度確認することが必要です。また十分な確認作業を行うと、上記の例以外にも、誤字脱字や情報の不備など基本的なミスも防げます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ メモが追い付かない?議事録作成が上手い人/早い人の特徴3選 ここでは、議事録作成が上手い人/早い人の特徴を3つご紹介します。会議での発言内容をすべて書き残すのは難しいものの、以下を押さえると、議事録の作成がスムーズになります。 (1)記号を使う 1つ目の特徴は、文章とともに記号を使うことです。 たとえば、因果関係には「→」、不明点には「?」、決定事項には「☆」などの記号をつける方法が挙げられます。このような工夫をすれば、要点・流れが見やすく伝わりやすい議事録になるのです。 ただし、記号に補足説明をつけなければ、人によっては「何を意味する記号なのか」が分からないため注意しましょう。 (2)テンプレートを活用する 2つ目の特徴として、テンプレートの活用が挙げられます。 重要な項目があらかじめ記載されたテンプレートを活用すれば、構成をいちいちゼロから考える手間がいりません。そのため、議事録作成者は発言に集中してメモがとれるうえに、フォーマットに沿って項目を埋めるだけで抜け漏れのない議事録を作成できます。 そこで、テンプレートをすぐに呼び出せるITツールがあると便利です。 (3)議事録を作成しやすいツールを活用する 3つ目の特徴は、議事録を作成しやすいITツールを活用することです。 手書きで議事録を作成すると、記載や修正に多大な時間がかかってしまいます。一方、記事形式で議事録を残せる「ITツール」であれば、修正に手間がかからず、テンプレートを瞬時に呼び出す使い方もできるのです。 ただし、「何となく便利そうだから」と多機能なITツールを選ぶと、ITが苦手なメンバーは使いこなせない可能性が高いです。したがって、メールを使える方ならば誰でも使えるほど簡単な「ナレカン」のようなツールで議事録を作成しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【無料で使える】議事録のフォーマット・テンプレート3選 ここでは、議事録作成にそのまま使えるサンプルを3つご紹介します。以下のサンプルを使って、短時間で議事録を完成させましょう。 (1)進捗共有会議に使える議事録 こちらは、進捗共有会議に使える議事録のサンプルです。 Wordでダウンロードでき、「対応中の案件」「新規案件」など、案件の進捗共有に即した項目が記載されています。また、シンプルな構成ゆえに、会議内容を自由に書けるのも特徴です。 Microsoftのテンプレートサイト|ダウンロードはこちら (2)シンプルな会議議事録 こちらは、シンプルな会議議事録サンプルです。 Wordでダウンロードでき、一般的な会議や部門内会議などで使えるテンプレートです。会議内容を決定事項と分けてシンプルにまとめられるほか、次回予定を記載する欄があるので、定例会議などにも適しています。 文例書式テンプレート集|ダウンロードはこちら (3)議事録・会議報告書 こちらは、議事録・会議報告書のサンプルです。 「要望」「処置内容」「担当者」「完了日」などの項目があり、開発に特化した構成になっています。 [文書]テンプレートの無料ダウンロード|ダウンロードはこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録は、WordとExcelのどっちでまとめるべきか? 議事録をWordとExcelのどちらをを用いてをまとめるべきかは、目的に合わせてどちらを使うか選択することが重要です。具体的な使い分けについては以下の表を参考にしましょう。 Word Excel ・文章メインで会議の流れなどをまとめるとき ・数値やデータをまとめて表に活用したいとき ・レイアウトやデザインを細かく調整したいとき ・表計算や関数を利用したいとき 以上のように、会議の内容や目的に合わせて使い分けると、分かりやすい議事録となるのです。また、各ツールの機能を使いこなすと、議事録作成が効率的になります。 一方、WordやExcelだと体裁を整えるのに時間がかかる場合があります。そこで、簡単に情報を残せて目次も自動で作成可能な「ナレカン」のようなツールを使うと、議事録作成に手間がかかりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録の書き方や目的まとめ ここまで、議事録の分かりやすい書き方や目的を中心にご紹介しました。 議事録の作成・共有は会議内容の定着や振り返りのために、迅速に行うべきです。しかし、ファイル形式では内容を確認するのに都度ファイルを開かなければならず、ファイルを共有する手間もかかります。 そこで、「直接議事録の情報を記録・共有できるツール」を導入すると、素早い情報共有につながります。また、充実した検索機能があると、後から議事録を振り返る際にも情報を探す手間が省けるため、便利です。 結論、議事録の作成・共有・確認に最適なのは、シンプルな操作性で記事の作成共有まで一元的にでき、超高精度な検索機能で社内用語まで検索にヒットするツール「ナレカン」が一択です。 無料の導入支援も受けられるので、「ナレカン」を導入して、議事録の作成と管理を効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジとは?ノウハウとの違いや社内のナレッジ運用の重要性を解説 【見本あり】分かりやすい議事録に必要な項目や書き方のコツとは? 【無料フォーマットあり】見やすい議事録の書き方とは? 【無料】Word/Excelの議事録テンプレート6選!見やすい書き方も紹介 会議における議事録の書き方とは?サンプルも紹介! 「すごい」と言われる議事録の取り方は?フォーマットや作成例も紹介! 【即解決】議事録を作成する意味は?社内で活用される書き方の例も紹介 【社会人必見】議事録のメモが追いつかない?取り方のコツを紹介 【会議効率化】議事録作成・管理を楽にするコツ!おすすめツール9選も紹介 【無料あり】AIを活用した人気の議事録自動作成ツール5選 【最新版】無料あり!iPhone/Android対応の議事録作成アプリ8選続きを読む
2025年10月01日【例文あり】議事録とは?分かりやすい書き方の特徴や目的も解説!会議や定例会で必ず作成される資料として「議事録」があります。議事録は、会議を振り返ったり欠席のメンバーへ情報を共有したりするときに不可欠な資料です。 しかし、書記として議事録を作成したいが「どう書けば良いのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、議事録の分かりやすい書き方や目的を中心にご紹介します。 議事録を作成する目的を知りたい 分かりやすい議事録の書き方を自社で導入したい 議事録の共有・管理までスムーズに行いたい という方はこの記事を参考にすると、分かりやすい議事録が書けるようになるほか、議事録を簡単に共有する方法も分かります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 議事録とは2 議事録を書く3つの目的2.1 目的1|会議の備忘録を残す2.2 目的2|会議の決定事項を共有する2.3 目的3|社内メンバーの認識をすり合わせる3 分かりやすい議事録の書き方3.1 (1)事前準備を徹底する3.2 (2)要点を箇条書きにする3.3 (3)冗長な表現を避ける3.4 (4)5W2Hを意識する3.5 (5)迅速に共有する3.6 (6)フォーマットを統一する3.7 (7)ITツールを活用する3.8 (8)資料も添付する4 【必見】議事録を最も簡単に作成・共有・確認できるITツール4.1 社内の議事録をナレッジ化して見やすく管理するツール「ナレカン」5 【例文あり】ナレカンでそのまま使える議事録の書き方見本6 議事録の書き方に関するQ&A7 議事録のダメな例8 メモが追い付かない?議事録作成が上手い人/早い人の特徴3選8.1 (1)記号を使う8.2 (2)テンプレートを活用する8.3 (3)議事録を作成しやすいツールを活用する9 【無料で使える】議事録のフォーマット・テンプレート3選9.1 (1)進捗共有会議に使える議事録9.2 (2)シンプルな会議議事録9.3 (3)議事録・会議報告書10 議事録は、WordとExcelのどっちでまとめるべきか?11 議事録の書き方や目的まとめ 議事録とは 議事録とは、会議の内容を記録するための文書を指します。 議事録があれば「どのような意見が交わされて、最終的に何が決まったのか」の事実確認がとれます。さらに、チームメンバーに会議の内容を共有する目的もあるので、抜け漏れなく記載しなければなりません。 このように、会議の決定事項を確実に記録・共有するうえで、議事録は必須です。また、議事録には会社の重要な決定事項が記載されているので、ナレッジとして確実に保管しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録を書く3つの目的 ここでは、議事録を書く3つの目的をご紹介します。議事録の作成には、会社の経営判断にもつながる重要な役割があるので必見です。 目的1|会議の備忘録を残す 1つ目に、議事録の目的として、会議の備忘録を残すことが挙げられます。 議事録を記載すれば、業務進捗をはじめとした事実確認がとれます。そのため、口頭でのやりとりにありがちな「言った・言わない」のトラブルを防げるのです。 したがって、あとから正確な情報を振り返れるように、議事録は項目の抜け漏れがないように記載しなければなりません。 目的2|会議の決定事項を共有する 2つ目に、会議の決定事項を共有することも、議事録の目的です。 会議によっては、責任者や主要メンバーなど、一部の関係者のみで開催されるケースもあります。このような場合に、議事録を作成すれば、会議に参加していないメンバーにも決定事項を伝えられるのです。 そのため、社内メンバー全員が「どのような議論があったのか」を把握できるように、共有するときは要点を明確にしましょう。 目的3|社内メンバーの認識をすり合わせる 3つ目に、社内メンバーの認識をすり合わせる目的もあります。 たとえば、会議の場で共有した情報が、正確に相手へ伝わっていないと認識のズレが生じてしまいます。認識がずれていると、その後の業務に支障をきたす場合もあるのです。 そこで、会議後の議事録の共有をルール化しておけば、全員が正しい情報を参照できるので、議論に関する認識齟齬を防げます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 分かりやすい議事録の書き方 ここでは、分かりやすい議事録の書き方をご紹介します。議事録を作成するにあたり、押さえるべき点を知りたい方は必見です。 (1)事前準備を徹底する 議事録を書く1つ目のルールは、事前準備を徹底することです。 日時や場所、参加者、会議内容などの情報は、会議の前に分かっているケースが大半です。そのため、このような項目をあらかじめ設定しておくと、会議中に慌てて構成を考える必要がありません。 また、過去の議事録から「どのような項目があるのか」を確認するのも、事前準備として取り入れましょう。 (2)要点を箇条書きにする 2つ目に、議事録では、要点を箇条書きにすることが大切です。 会議の内容をそのまま議事録へ羅列しただけでは、メリハリがなく、情報が相手へ伝わりづらくなってしまいます。しかし、要点を箇条書きにすれば、重要事項が明確になり、全体の内容もスムーズに理解できるのです。 加えて、箇条書きであれば情報を少なく絞れるので、議事録の作成に無駄な時間がかかりません。 (3)冗長な表現を避ける 3つ目に、相手に分かりやすくするには、冗長な表現を避け、簡潔に記載しましょう。 議事録で冗長な文章が多ければ、内容を理解するのに時間がかかり、読むだけでもストレスになってしまいます。その結果、「議事録を見たが、会議でどのような決定があったか分からなかった」ともなりかねません。 したがって、議事録では平易な文章を心がけ、内容の過不足がないように記載すべきなのです。たとえば、敬語の「です・ます調」ではなく「だ・である調」を使ったり「一文に一要素」を意識したりすることが有効です。 (4)5W2Hを意識する 4つ目に、5W2Hを明確に記載することも重要です。具体的には、以下の要素を指します。 When(いつ) Where(どこで) Who(誰が) What(何を) Why(なぜ) How(どのように) How Much(いくらで) 上記のフレームワークを押さえれば、文章が曖昧になるのを防いだり、記載漏れがないかを確かめたりするのに役立ちます。 (5)迅速に共有する 5つ目に、会議内容の振り返りに役立てるためにも、迅速な共有が求められます。 議事録の共有に時間がかかると、一部の社員が会議内容を把握できない状態になり、業務の遅れにつながってしまいます。そのため、議事録は遅くとも翌営業日までに仕上げて共有するのが望ましいです。 ただし、スピードを意識するあまり内容に不備があっては意味がありません。したがって、一度議事録を作成したら添削を受けて、精度の高い状態で共有しましょう。 (6)フォーマットを統一する 6つ目に、議事録のフォーマットを社内で統一することも効果的です。 議事録の作り方が属人化している場合、情報が抜け漏れる恐れがあります。しかし、フォーマットがあれば記録すべき項目が明確になるため、全員が正確に情報を残せるようになるのです。 また、社内でフォーマットが統一されていれば、各々で構成を考える必要がないので、作成時間の短縮にもつながります。 (7)ITツールを活用する 7つ目に、分かりやすい議事録を書くうえでは、ITツールも欠かせません。 紙で議事録を作成している場合、修正が重なって見づらくなるケースも多いです。一方、ITツールを活用すれば、クリック操作だけで議事録の記載や修正ができるので、常に分かりやすい状態に保てます。 ただし、ツールの機能が多機能すぎると、ITが苦手なメンバーが使いこなせません。そのため、操作がシンプル・簡単な「ナレカン」のようなツールを導入して、ツールが形骸化しないようにしましょう。 (8)資料も添付する 8つ目に、会議で共有された資料の添付も重要です。 議事録に資料を添付すると、会議で決定された企画・施策がどのようなデータをもとにしていたか、といったことが振り返りやすくなるのです。また会議に出席していない人が、会議の内容を理解するのにも役立ちます。 以上のように、出席者もそうでない人も会議の内容について共通認識を持てるよう、資料共有まで行うようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】議事録を最も簡単に作成・共有・確認できるITツール 以下では、議事録を最も簡単に作成・共有・確認できるITツールをご紹介します。 会議の内容は、後から振り返れるように議事録としてまとめて社員に共有するべきです。しかしWordやExcelは、内容を確認するのに都度ファイルを開かなければならないうえ、他のファイルに埋もれて見つからなくなりがちです。 そこで、「誰でも簡単に議事録を作成・共有可能なツール」を導入しましょう。また、作成した議事録をツール上でそのまま共有できると、情報を探す際に逐一ファイルを開封する手間もかかりません。 結論、議事録の作成・共有・確認に最適なのは、直感的な操作で直接記事に書き込んで簡単に議事録を作成でき、超高精度な検索機能で必要な情報がすぐに見つかるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンは、作成した議事録をファイル形式にする必要がなく、直接記載~共有まで一元的に行えるほか、一度作成した議事録はテンプレート化できるため、議事録の作成にかかる時間が短縮されます。また、社内用語も「超高精度な検索機能」でヒットするため、後から振り返る際に必要な情報をすぐに見つけられるのです。 社内の議事録をナレッジ化して見やすく管理するツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【例文あり】ナレカンでそのまま使える議事録の書き方見本 以下では、すぐに使える議事録のフォーマット例をご紹介します。 <会議名/開始・終了日時/開催場所> 20〇〇年〇月〇日16時〜17時〇〇株式会社第3会議室 <参加者> 〇〇株式会社:〜部長、〜課長、〜係長、〜様/自社:△△、□□ <会議の目的> 製品〇〇に関する原材料の高騰における価格調整および決定 <決定事項> 協力会社T社との意思決定も反映させたうえで詳細レンジを確定させる <補足事項> T社の資材調達責任者が出張により〇月〇日まで不在 <次回の議題> 最終的な価格調整にあたっての懸念点解消 <参考資料> 価格高騰の推移レポートと価格レンジの傾向 上記の例をコピー&ペーストして、短時間で議事録を作成しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録の書き方に関するQ&A 以下では、議事録の書き方に関するよくある質問と回答をご紹介します。とくに、議事録の書き方に不安がある担当者の方は必見です。 質問1|議事録の上手な取り方は? 会議の内容の全てをメモするのではなく、重要な部分のみをメモすると、要点がまとまった議事録になります。具体的には、「会議内容を事前に把握する」「日時や数値は確実に記載する」「略語や記号を使う」と効率よくメモがとれます。 質問2|議事録は誰が書くべきか? 一般的には役職の低い社員や若手社員に任される場合が多いです。しかし年齢・役職にとらわれず情報整理能力が高い社員が作成すると、分かりやすい議事録となり、会議内容の認識の齟齬がなくなります。 以上のように、議事録の書き方や作成者の設定を工夫すると、時間をかけずに分かりやすい議事録を作成できるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録のダメな例 議事録を作成する際に、無意識のうちに「ダメな議事録」になってしまっている場合があります。以下の表で自分が作成した議事録が「ダメな例」に当てはまっていないか確認しましょう。 ダメな例 理由 ・専門用語の多用あるいは補足説明がない 新入社員や業務経験が浅い社員から理解を得るのに時間がかかるため ・意見と事実が混合して記載されている 結論が分かりづらく、認識の違いが生まれやすくなるため ・作成・共有に時間をかけている 会議の記憶が曖昧になり、会議の内容の定着・振り返りが不十分になるため 作成した議事録を有効活用するためにも、ダメな例に当てはまっていないか、再度確認することが必要です。また十分な確認作業を行うと、上記の例以外にも、誤字脱字や情報の不備など基本的なミスも防げます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ メモが追い付かない?議事録作成が上手い人/早い人の特徴3選 ここでは、議事録作成が上手い人/早い人の特徴を3つご紹介します。会議での発言内容をすべて書き残すのは難しいものの、以下を押さえると、議事録の作成がスムーズになります。 (1)記号を使う 1つ目の特徴は、文章とともに記号を使うことです。 たとえば、因果関係には「→」、不明点には「?」、決定事項には「☆」などの記号をつける方法が挙げられます。このような工夫をすれば、要点・流れが見やすく伝わりやすい議事録になるのです。 ただし、記号に補足説明をつけなければ、人によっては「何を意味する記号なのか」が分からないため注意しましょう。 (2)テンプレートを活用する 2つ目の特徴として、テンプレートの活用が挙げられます。 重要な項目があらかじめ記載されたテンプレートを活用すれば、構成をいちいちゼロから考える手間がいりません。そのため、議事録作成者は発言に集中してメモがとれるうえに、フォーマットに沿って項目を埋めるだけで抜け漏れのない議事録を作成できます。 そこで、テンプレートをすぐに呼び出せるITツールがあると便利です。 (3)議事録を作成しやすいツールを活用する 3つ目の特徴は、議事録を作成しやすいITツールを活用することです。 手書きで議事録を作成すると、記載や修正に多大な時間がかかってしまいます。一方、記事形式で議事録を残せる「ITツール」であれば、修正に手間がかからず、テンプレートを瞬時に呼び出す使い方もできるのです。 ただし、「何となく便利そうだから」と多機能なITツールを選ぶと、ITが苦手なメンバーは使いこなせない可能性が高いです。したがって、メールを使える方ならば誰でも使えるほど簡単な「ナレカン」のようなツールで議事録を作成しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【無料で使える】議事録のフォーマット・テンプレート3選 ここでは、議事録作成にそのまま使えるサンプルを3つご紹介します。以下のサンプルを使って、短時間で議事録を完成させましょう。 (1)進捗共有会議に使える議事録 こちらは、進捗共有会議に使える議事録のサンプルです。 Wordでダウンロードでき、「対応中の案件」「新規案件」など、案件の進捗共有に即した項目が記載されています。また、シンプルな構成ゆえに、会議内容を自由に書けるのも特徴です。 Microsoftのテンプレートサイト|ダウンロードはこちら (2)シンプルな会議議事録 こちらは、シンプルな会議議事録サンプルです。 Wordでダウンロードでき、一般的な会議や部門内会議などで使えるテンプレートです。会議内容を決定事項と分けてシンプルにまとめられるほか、次回予定を記載する欄があるので、定例会議などにも適しています。 文例書式テンプレート集|ダウンロードはこちら (3)議事録・会議報告書 こちらは、議事録・会議報告書のサンプルです。 「要望」「処置内容」「担当者」「完了日」などの項目があり、開発に特化した構成になっています。 [文書]テンプレートの無料ダウンロード|ダウンロードはこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録は、WordとExcelのどっちでまとめるべきか? 議事録をWordとExcelのどちらをを用いてをまとめるべきかは、目的に合わせてどちらを使うか選択することが重要です。具体的な使い分けについては以下の表を参考にしましょう。 Word Excel ・文章メインで会議の流れなどをまとめるとき ・数値やデータをまとめて表に活用したいとき ・レイアウトやデザインを細かく調整したいとき ・表計算や関数を利用したいとき 以上のように、会議の内容や目的に合わせて使い分けると、分かりやすい議事録となるのです。また、各ツールの機能を使いこなすと、議事録作成が効率的になります。 一方、WordやExcelだと体裁を整えるのに時間がかかる場合があります。そこで、簡単に情報を残せて目次も自動で作成可能な「ナレカン」のようなツールを使うと、議事録作成に手間がかかりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 議事録の書き方や目的まとめ ここまで、議事録の分かりやすい書き方や目的を中心にご紹介しました。 議事録の作成・共有は会議内容の定着や振り返りのために、迅速に行うべきです。しかし、ファイル形式では内容を確認するのに都度ファイルを開かなければならず、ファイルを共有する手間もかかります。 そこで、「直接議事録の情報を記録・共有できるツール」を導入すると、素早い情報共有につながります。また、充実した検索機能があると、後から議事録を振り返る際にも情報を探す手間が省けるため、便利です。 結論、議事録の作成・共有・確認に最適なのは、シンプルな操作性で記事の作成共有まで一元的にでき、超高精度な検索機能で社内用語まで検索にヒットするツール「ナレカン」が一択です。 無料の導入支援も受けられるので、「ナレカン」を導入して、議事録の作成と管理を効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジとは?ノウハウとの違いや社内のナレッジ運用の重要性を解説 【見本あり】分かりやすい議事録に必要な項目や書き方のコツとは? 【無料フォーマットあり】見やすい議事録の書き方とは? 【無料】Word/Excelの議事録テンプレート6選!見やすい書き方も紹介 会議における議事録の書き方とは?サンプルも紹介! 「すごい」と言われる議事録の取り方は?フォーマットや作成例も紹介! 【即解決】議事録を作成する意味は?社内で活用される書き方の例も紹介 【社会人必見】議事録のメモが追いつかない?取り方のコツを紹介 【会議効率化】議事録作成・管理を楽にするコツ!おすすめツール9選も紹介 【無料あり】AIを活用した人気の議事録自動作成ツール5選 【最新版】無料あり!iPhone/Android対応の議事録作成アプリ8選続きを読む -
 2025年03月26日【事例あり】ビジネスリスクとは?リスク管理の方法も解説!ビジネスリスクは、日常のさまざまな業務に内在しています。健全な企業経営を行うにはビジネスリスクを正しく把握し、対処しなければなりません。 しかし、ビジネスにおけるリスクに対して具体的なイメージが持てず、リスク管理に悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ビジネスで発生するリスクの事例や管理方法を中心に解説します。 ビジネス上のリスクについて理解を深めたい ビジネスリスクの事例を把握して、リスク管理を徹底したい 適切にリスクを管理して、企業経営を安定させたい という方は本記事を参考にすると、企業が対処すべきビジネスのリスクを把握しながら、企業経営の安定性を高めることにもつなげられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ビジネスリスクとは2 ビジネスリスクの7つの事例一覧2.1 1.経営戦略上のリスク2.2 2.コンプライアンスリスク2.3 3.セキュリティリスク2.4 4.運用上のリスク2.5 5.財務リスク2.6 6.レピュテーションリスク2.7 7.競争リスク3 業務リスクの事例4 ビジネスにおけるリスクマネジメントの方法とは4.1 保険の利用4.2 マニュアルの整備4.3 社内教育の徹底5 ビジネスリスクの管理に最適なツール5.1 最も簡単にビジネスリスクの管理を効率化できるツール「ナレカン」6 ビジネスリスクの事例やリスク管理の方法まとめ ビジネスリスクとは ビジネスリスクとは、企業経営において起こり得るリスク全般を指します。 ビジネスにおけるリスクの要因は、企業の内部環境と外部環境、いずれにも存在しています。また、近年、情報通信技術の進化や経営環境の変化に伴い、ビジネスでのリスクは複雑化しているのです。 安定した事業の継続には、リスク管理によるビジネスリスクの回避・軽減が求められます。そのためには、想定されるビジネスリスクを事前に把握し、分析しておかなければなりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ビジネスリスクの7つの事例一覧 以下では、ビジネスリスクの7つの事例について解説します。自社の経営状況に合わせて、優先的に対処すべきリスクを抽出し解決する必要があります。 1.経営戦略上のリスク 経営戦略上のリスクとは、経営者の判断によって経営戦略を実行する場合に生じるリスクです。例として、以下のリスクが挙げられます。 事業規模の拡大 新商品開発 海外進出 経営戦略では企業の将来に関わる重要な判断が行われるため、経営戦略上のリスクは企業経営に多大な影響を及ぼします。したがって、発生するリスクとリターンのバランスを考慮して、利益の最大化を追求する必要があるのです。 2.コンプライアンスリスク コンプライアンスリスクとは、企業の評判に関わるリスクです。例として、以下のリスクが挙げられます。 着服・横領・粉飾決算 ハラスメント 長時間労働 製品の不備による法令違反 コンプライアンスリスクによる損失は、企業のイメージや社会的信用に深刻な影響を及ぼします。そのため、定期的な規制の確認や、監視システムの導入が重要なのです。 3.セキュリティリスク セキュリティリスクでは、情報漏えいが代表的です。情報漏えいが発生する要因として、以下の内容が挙げられます。 不正アクセスによるサイバー攻撃・ウイルス感染 フィッシング詐欺 社員による情報の持ち出し メールの誤送信 顧客情報や機密情報の漏えいは企業だけでなく、取引先や顧客に対しても損失が発生するため、厳格な対策が求められます。したがって、セキュリティリスクに関する社内教育や、安心して情報を管理できる体制づくりが重要です。 そして、セキュリティリスクの管理が浸透しているチームは「ナレカン」のように「強固なセキュリティ下で情報を適切に管理できるツール」を使っている点もポイントです。 4.運用上のリスク 運用上のリスクとは、自然災害や事故によって実際の事業運用に影響を及ぼすリスクです。例として、以下のリスクが挙げられます。 建物の損壊・停電 商品の出荷遅延 データ消失 労働災害 このように完全な回避が難しいリスクでは、データバックアップやサーバーの外部委託によって被害を最小限に抑えられます。リスクの発生時に、迅速にトラブルを収束して事業を継続できる仕組みづくりが重要です。 5.財務リスク 財務リスクとは、経営不振や売上減少といった企業やその利益に直接影響を及ぼすリスクです。財務リスクが発生する要因として、以下の内容が挙げられます。 無計画な経営 大きな事業の失敗 景気の変化 財務リスクに対処するためには、事業計画を調整して支出と債務を最小限に抑える必要があります。また、融資の返済や財務状況を正確に把握し、管理しておく点が重要です。 さらに、特定の顧客に依存するビジネスも、顧客を失った場合の損失が増大するため、リスクが発生します。そのため、積極的にマーケティングを行い、多様な顧客を獲得しておく必要があります。 6.レピュテーションリスク レピュテーションリスクとは、企業イメージの低下によって企業経営に損失が与えられるリスクです。 ソーシャルメディアの普及によって、顧客が商品やサービスに関する感想を自由に発信できるようになりました。企業に対する評判は業績に直結するため、真摯な対応を行って顧客満足度を向上させる点が重要です。 レピュテーションリスクの対策としては、例としてレビューの監視による迅速な対応が挙げられます。万が一問題が発生した場合は、課題を早急に解決し、謝罪や返金などの対応が必要です。 7.競争リスク 競争リスクとは競合他社との競争において、優位性を失ってしまうリスクです。 企業の収益性を向上させるためにも、競争リスクを考慮して現状維持の状態にある場合は打破していく必要があります。また、競争が激しいなかでも既存ノウハウの陳腐化を防止するには、社会状況の変化に対する柔軟な対応が求められます。 そのため、マーケティングの専門家を採用したり市場動向を監視するソフトウェアを導入したりして、市場ニーズを把握したうえで適切な事業戦略を策定する必要があります。また、最新の技術や業界動向を確認し、生産性の向上やサービスの改善に努める点もポイントです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 業務リスクの事例 業務中、発生し得るリスクとして以下のようなものがあります。 顧客情報の漏えい サイバー攻撃やメールの誤送信により、顧客情報の流出は起こってしまいます。企業としての信頼を大きく失うため、対策を徹底するべきです。 現場仕事における墜落・転落 現場仕事において、墜落・転落などの落下事故のリスクは考慮しなければなりません。建設業における死傷事故の原因として、高所からの落下は多くを占めるため、リスクマネジメントは必須です。 業務内容によって、直面するリスクは異なるため、それぞれに合わせて適切にリスクマネジメントしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ビジネスにおけるリスクマネジメントの方法とは 以下では、ビジネスにおけるリスク管理の方法について解説します。ビジネスリスクの対策では管理体制を整備して、組織的にリスク管理をしていかなければなりません。 保険の利用 保険を利用してリスクを移転しておけば、万が一損害が発生した場合でも事業を継続できます。例として、以下の保険が挙げられます。 損害保険 生命保険 労災保険 損害賠償責任保険 そのほかにも、特定の業種に特化した保険や、訴訟費用を補償する保険があるため、自社のニーズに合わせて保険を検討する必要があります。 ただし、保険の利用にはコストが発生するため、リスクの対応策を十分に検討したうえで利用する点が重要です。 マニュアルの整備 リスク管理では、業務はもちろんセキュリティに関するマニュアルの整備が有効です。 たとえば、情報セキュリティに関して注意すべき点をまとめておけば、ヒューマンエラーによる情報漏えいのリスクを対策できます。また、セキュリティリスクに関するマニュアルに記載すべき項目として、以下の内容が挙げられます。 パスワード管理 ウイルス対策 バックアップ ただし、マニュアルを作成しても活用されなければリスク管理は不十分です。マニュアルの整備が完了したら周知を徹底し、定期的な更新を行って社内に浸透させる必要があるのです。 社内教育の徹底 リスク管理では、社内教育の徹底が不可欠です。特にコンプライアンスリスクやセキュリティリスクの管理では、全社員のリスク意識を高める必要があります。 社内教育で扱うべきテーマとして、以下の内容が挙げられます。 情報セキュリティ ハラスメント 著作権・特許権の侵害 社内教育は企業の信頼性を高め、企業価値を向上させます。リスクについての社内教育は一度で終わりではなく、定期的に取り組むべきです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ビジネスリスクの管理に最適なツール 以下では、ビジネスリスクの管理に最適なツールをご紹介します。 ビジネスリスクの管理は、管理体制を整えて、組織的に取り組む必要があります。たとえば、マニュアルや社内教育が充実していると、社員の意識を高めつつ全社でリスク管理を徹底できます。 そこで、「情報共有ツール」を使うとリスク対策のマニュアルや社内教育の確認事項、過去の研修内容を共有しやすくなります。ただし、操作が複雑では社員が使いこなせないので、簡単に使えるツールを選びましょう。 そのため、ビジネスリスクの管理には、簡単に使えてマニュアルや社内教育資料ををすぐに確認できるツール「ナレカン」を導入するべきです。 ナレカンは、簡単にマニュアルや社内教育で使う資料をまとめられるうえ、ヒット率100%の「検索機能」で必要な情報に確実にアクセスできます。そのため、マニュアル運用や社内教育が進めやすく、リスク管理に最適なのです。 最も簡単にビジネスリスクの管理を効率化できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ビジネスリスクの事例やリスク管理の方法まとめ ここまで、ビジネスでのリスク事例・リスク管理の方法を中心に解説しました。 ビジネスリスクの事例には経営戦略や財務といった経営者の判断によって生じるリスクのほかに、コンプライアンスリスクやセキュリティリスクなど、全社員が管理すべきリスクもあります。とくに、現場レベルでは「情報漏えいのリスク」が身近に潜んでいるという認識を全社で統一させる必要があります。 また、さまざまなリスクに対し保険や社内教育の徹底、マニュアルの管理で対策ができますが、このような情報は「情報管理ツール」を使うと、社内情報を安全に蓄積しつつ、リスク管理における情報共有を効率化できるのです。 したがって、ビジネスリスク管理で扱う大切な情報をシンプルかつ厳格に管理できる情報管理ツール「ナレカン」が必須です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」で情報管理を効率化し、ビジネスリスクの管理に全社で取り組みましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年03月26日【事例あり】ビジネスリスクとは?リスク管理の方法も解説!ビジネスリスクは、日常のさまざまな業務に内在しています。健全な企業経営を行うにはビジネスリスクを正しく把握し、対処しなければなりません。 しかし、ビジネスにおけるリスクに対して具体的なイメージが持てず、リスク管理に悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ビジネスで発生するリスクの事例や管理方法を中心に解説します。 ビジネス上のリスクについて理解を深めたい ビジネスリスクの事例を把握して、リスク管理を徹底したい 適切にリスクを管理して、企業経営を安定させたい という方は本記事を参考にすると、企業が対処すべきビジネスのリスクを把握しながら、企業経営の安定性を高めることにもつなげられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ビジネスリスクとは2 ビジネスリスクの7つの事例一覧2.1 1.経営戦略上のリスク2.2 2.コンプライアンスリスク2.3 3.セキュリティリスク2.4 4.運用上のリスク2.5 5.財務リスク2.6 6.レピュテーションリスク2.7 7.競争リスク3 業務リスクの事例4 ビジネスにおけるリスクマネジメントの方法とは4.1 保険の利用4.2 マニュアルの整備4.3 社内教育の徹底5 ビジネスリスクの管理に最適なツール5.1 最も簡単にビジネスリスクの管理を効率化できるツール「ナレカン」6 ビジネスリスクの事例やリスク管理の方法まとめ ビジネスリスクとは ビジネスリスクとは、企業経営において起こり得るリスク全般を指します。 ビジネスにおけるリスクの要因は、企業の内部環境と外部環境、いずれにも存在しています。また、近年、情報通信技術の進化や経営環境の変化に伴い、ビジネスでのリスクは複雑化しているのです。 安定した事業の継続には、リスク管理によるビジネスリスクの回避・軽減が求められます。そのためには、想定されるビジネスリスクを事前に把握し、分析しておかなければなりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ビジネスリスクの7つの事例一覧 以下では、ビジネスリスクの7つの事例について解説します。自社の経営状況に合わせて、優先的に対処すべきリスクを抽出し解決する必要があります。 1.経営戦略上のリスク 経営戦略上のリスクとは、経営者の判断によって経営戦略を実行する場合に生じるリスクです。例として、以下のリスクが挙げられます。 事業規模の拡大 新商品開発 海外進出 経営戦略では企業の将来に関わる重要な判断が行われるため、経営戦略上のリスクは企業経営に多大な影響を及ぼします。したがって、発生するリスクとリターンのバランスを考慮して、利益の最大化を追求する必要があるのです。 2.コンプライアンスリスク コンプライアンスリスクとは、企業の評判に関わるリスクです。例として、以下のリスクが挙げられます。 着服・横領・粉飾決算 ハラスメント 長時間労働 製品の不備による法令違反 コンプライアンスリスクによる損失は、企業のイメージや社会的信用に深刻な影響を及ぼします。そのため、定期的な規制の確認や、監視システムの導入が重要なのです。 3.セキュリティリスク セキュリティリスクでは、情報漏えいが代表的です。情報漏えいが発生する要因として、以下の内容が挙げられます。 不正アクセスによるサイバー攻撃・ウイルス感染 フィッシング詐欺 社員による情報の持ち出し メールの誤送信 顧客情報や機密情報の漏えいは企業だけでなく、取引先や顧客に対しても損失が発生するため、厳格な対策が求められます。したがって、セキュリティリスクに関する社内教育や、安心して情報を管理できる体制づくりが重要です。 そして、セキュリティリスクの管理が浸透しているチームは「ナレカン」のように「強固なセキュリティ下で情報を適切に管理できるツール」を使っている点もポイントです。 4.運用上のリスク 運用上のリスクとは、自然災害や事故によって実際の事業運用に影響を及ぼすリスクです。例として、以下のリスクが挙げられます。 建物の損壊・停電 商品の出荷遅延 データ消失 労働災害 このように完全な回避が難しいリスクでは、データバックアップやサーバーの外部委託によって被害を最小限に抑えられます。リスクの発生時に、迅速にトラブルを収束して事業を継続できる仕組みづくりが重要です。 5.財務リスク 財務リスクとは、経営不振や売上減少といった企業やその利益に直接影響を及ぼすリスクです。財務リスクが発生する要因として、以下の内容が挙げられます。 無計画な経営 大きな事業の失敗 景気の変化 財務リスクに対処するためには、事業計画を調整して支出と債務を最小限に抑える必要があります。また、融資の返済や財務状況を正確に把握し、管理しておく点が重要です。 さらに、特定の顧客に依存するビジネスも、顧客を失った場合の損失が増大するため、リスクが発生します。そのため、積極的にマーケティングを行い、多様な顧客を獲得しておく必要があります。 6.レピュテーションリスク レピュテーションリスクとは、企業イメージの低下によって企業経営に損失が与えられるリスクです。 ソーシャルメディアの普及によって、顧客が商品やサービスに関する感想を自由に発信できるようになりました。企業に対する評判は業績に直結するため、真摯な対応を行って顧客満足度を向上させる点が重要です。 レピュテーションリスクの対策としては、例としてレビューの監視による迅速な対応が挙げられます。万が一問題が発生した場合は、課題を早急に解決し、謝罪や返金などの対応が必要です。 7.競争リスク 競争リスクとは競合他社との競争において、優位性を失ってしまうリスクです。 企業の収益性を向上させるためにも、競争リスクを考慮して現状維持の状態にある場合は打破していく必要があります。また、競争が激しいなかでも既存ノウハウの陳腐化を防止するには、社会状況の変化に対する柔軟な対応が求められます。 そのため、マーケティングの専門家を採用したり市場動向を監視するソフトウェアを導入したりして、市場ニーズを把握したうえで適切な事業戦略を策定する必要があります。また、最新の技術や業界動向を確認し、生産性の向上やサービスの改善に努める点もポイントです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 業務リスクの事例 業務中、発生し得るリスクとして以下のようなものがあります。 顧客情報の漏えい サイバー攻撃やメールの誤送信により、顧客情報の流出は起こってしまいます。企業としての信頼を大きく失うため、対策を徹底するべきです。 現場仕事における墜落・転落 現場仕事において、墜落・転落などの落下事故のリスクは考慮しなければなりません。建設業における死傷事故の原因として、高所からの落下は多くを占めるため、リスクマネジメントは必須です。 業務内容によって、直面するリスクは異なるため、それぞれに合わせて適切にリスクマネジメントしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ビジネスにおけるリスクマネジメントの方法とは 以下では、ビジネスにおけるリスク管理の方法について解説します。ビジネスリスクの対策では管理体制を整備して、組織的にリスク管理をしていかなければなりません。 保険の利用 保険を利用してリスクを移転しておけば、万が一損害が発生した場合でも事業を継続できます。例として、以下の保険が挙げられます。 損害保険 生命保険 労災保険 損害賠償責任保険 そのほかにも、特定の業種に特化した保険や、訴訟費用を補償する保険があるため、自社のニーズに合わせて保険を検討する必要があります。 ただし、保険の利用にはコストが発生するため、リスクの対応策を十分に検討したうえで利用する点が重要です。 マニュアルの整備 リスク管理では、業務はもちろんセキュリティに関するマニュアルの整備が有効です。 たとえば、情報セキュリティに関して注意すべき点をまとめておけば、ヒューマンエラーによる情報漏えいのリスクを対策できます。また、セキュリティリスクに関するマニュアルに記載すべき項目として、以下の内容が挙げられます。 パスワード管理 ウイルス対策 バックアップ ただし、マニュアルを作成しても活用されなければリスク管理は不十分です。マニュアルの整備が完了したら周知を徹底し、定期的な更新を行って社内に浸透させる必要があるのです。 社内教育の徹底 リスク管理では、社内教育の徹底が不可欠です。特にコンプライアンスリスクやセキュリティリスクの管理では、全社員のリスク意識を高める必要があります。 社内教育で扱うべきテーマとして、以下の内容が挙げられます。 情報セキュリティ ハラスメント 著作権・特許権の侵害 社内教育は企業の信頼性を高め、企業価値を向上させます。リスクについての社内教育は一度で終わりではなく、定期的に取り組むべきです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ビジネスリスクの管理に最適なツール 以下では、ビジネスリスクの管理に最適なツールをご紹介します。 ビジネスリスクの管理は、管理体制を整えて、組織的に取り組む必要があります。たとえば、マニュアルや社内教育が充実していると、社員の意識を高めつつ全社でリスク管理を徹底できます。 そこで、「情報共有ツール」を使うとリスク対策のマニュアルや社内教育の確認事項、過去の研修内容を共有しやすくなります。ただし、操作が複雑では社員が使いこなせないので、簡単に使えるツールを選びましょう。 そのため、ビジネスリスクの管理には、簡単に使えてマニュアルや社内教育資料ををすぐに確認できるツール「ナレカン」を導入するべきです。 ナレカンは、簡単にマニュアルや社内教育で使う資料をまとめられるうえ、ヒット率100%の「検索機能」で必要な情報に確実にアクセスできます。そのため、マニュアル運用や社内教育が進めやすく、リスク管理に最適なのです。 最も簡単にビジネスリスクの管理を効率化できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ビジネスリスクの事例やリスク管理の方法まとめ ここまで、ビジネスでのリスク事例・リスク管理の方法を中心に解説しました。 ビジネスリスクの事例には経営戦略や財務といった経営者の判断によって生じるリスクのほかに、コンプライアンスリスクやセキュリティリスクなど、全社員が管理すべきリスクもあります。とくに、現場レベルでは「情報漏えいのリスク」が身近に潜んでいるという認識を全社で統一させる必要があります。 また、さまざまなリスクに対し保険や社内教育の徹底、マニュアルの管理で対策ができますが、このような情報は「情報管理ツール」を使うと、社内情報を安全に蓄積しつつ、リスク管理における情報共有を効率化できるのです。 したがって、ビジネスリスク管理で扱う大切な情報をシンプルかつ厳格に管理できる情報管理ツール「ナレカン」が必須です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」で情報管理を効率化し、ビジネスリスクの管理に全社で取り組みましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年03月26日リスクヘッジの意味とは?企業が実施すべき対策やポイントを紹介!ビジネスにおけるリスクヘッジ(risk hedge)とは、企業に対する危険の予測・対策を意味します。企業が継続して成長していくためには、適切なリスクヘッジが欠かせません。 しかし、リスクヘッジを実施すべき意味や具体的な対策内容が社内に浸透しておらず「リスクヘッジの正しい対策が分からない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、リスクヘッジの意味や企業が実施すべき対策・ポイントを中心に解説します。 リスクヘッジの意味や使い方を理解したい 企業が実施すべきリスクヘッジの手法とポイントを知りたい 社内に散在する情報を集約し、情報管理のリスクを軽減したい という担当者の方は本記事を参考にすると、企業が実施すべきリスクヘッジ対策を把握しながら、事業の安定性を高められます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 リスクヘッジの意味や類語との違いとは1.1 リスクヘッジとは1.2 リスクマネジメントとの違い1.3 リスクテイクとの違い2 企業が実施すべきリスクヘッジとは?2.1 人事・労務の見直し2.2 コンプライアンスの徹底2.3 経営状況の可視化2.4 情報漏洩の防止3 リスクヘッジを実施するときのポイント3選3.1 論理的に思考する癖づけをする3.2 社内の課題を蓄積する体制を整える3.3 正しく情報共有をする4 【必見】情報漏えいのリスクヘッジに最適なツール4.1 社内のあらゆる情報を一元管理し即共有できるツール「ナレカン」5 企業が実施すべきリスクヘッジ対策とポイントまとめ リスクヘッジの意味や類語との違いとは 以下では、リスクヘッジを実施すべき意味について解説します。混同しやすい用語との違いを確認して、リスクヘッジの使い方や重要性を把握しましょう。 リスクヘッジとは リスクヘッジとは、あらかじめ予測されるリスクに対して対策を立てて備えることを指します。 リスクヘッジは、元々金融業界において用いられる言葉であり「危機管理」や「保険」といった類語があります。為替の変動などで想定される損失のリスクに対し、対策をとることを「リスクヘッジをする」という表現で使います。 とはいえ、業界業種問わず、企業の営業活動には「ヒト・モノ・カネ・情報」に関わるリスクが潜んでいます。そのため、トラブルが発生する前にリスクヘッジを実施して、チーム全体でリスクに対する認識をすり合わせておく必要があるのです。 リスクマネジメントとの違い リスクマネジメントとは、発生する可能性のあるリスクに対する危機管理を指します。 リスクヘッジがリスクを軽減する方法論である一方で、リスクマネジメントはリスク対策のプロセス全体を意味します。そのため、リスクヘッジはリスクマネジメントのプロセスの一環であると言えるのです。 適切なリスクマネジメントには、的確なリスクヘッジが欠かせません。そのため、効果的なリスクヘッジを実施しつつ、組織的にリスクマネジメントをする体制を整えましょう。 リスクテイクとの違い リスクテイクとは、危険性を理解したうえでリターンを期待して実行される行動であり、リスクを回避するリスクヘッジとは相反する意味を持つ用語です。 あえてリスクを引き受けた行動によって、大きなリターンを期待できる場合があります。そのため、利益を得るには、適切なリスクテイクが不可欠なのです。 したがって、リスクテイクを適切に判断するには、リスクヘッジによって不確定要素のリスクを把握・軽減しておく必要があるのです。以上のように、リスクテイクとリスクヘッジをバランス良く実施し、企業の発展を目指しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 企業が実施すべきリスクヘッジとは? 以下では、企業が実施すべきリスクヘッジについて解説します。適切なリスクヘッジによって、企業にもたらされるダメージを最小限に抑えられます。 人事・労務の見直し 企業のリスクヘッジはもちろん持続的な成長には、人事・労務の見直しが不可欠です。 適切な人材育成を通して、社員それぞれが能力を向上させ発揮できるようになると、モチベーションの低下や人材不足のリスクを軽減します。また、人材育成のシステムを上手く構築できれば、業務の属人化を防ぎ、組織全体の成長を促進できるのです。 また、社会保険手続や給与計算に関する従業員とのトラブルを防ぐためにも、「働く環境」の整備・管理のリスクヘッジも適切に実施しましょう。 コンプライアンスの徹底 「コンプライアンス」とは、企業が法令や社会的ルールを遵守することを意味します。 各企業は、「労働基準法」や「独占禁止法」などの自社に適用される法令を守らなければなりません。法令に違反した企業は、行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。 また、企業は明文化された法令だけでなく、社会的な規範も十分に意識する必要があります。社会的なモラルやルールに反すると、世間から会社の信頼を失う事態になりかねないため、批判を受ける可能性がある行動は避けましょう。 経営状況の可視化 企業が損失や不利益を回避するために、自社はもちろん、取引先の経営状況を可視化しておきましょう。 経営面において危惧される要素には、”為替変動による損失”や”取引先の倒産リスク”などが挙げられます。とくに、昨今では原材料価格の高騰が頻発しているため、複数の取引先を確保しておくなどの対策が必要になるのです。 以上のように目先の問題だけでなく、将来的に起こり得るリスクを把握して対策を講じていきましょう。 情報漏洩の防止 情報漏洩の防止は、現代の企業にとって必須の課題です。 自社が保有する機密情報や顧客情報、個人情報の漏洩は、企業の社会的信用を失墜させ、ブランドイメージにダメージを与えかねません。損害賠償金や業務停止による機会損失が発生するだけでなく、法的責任が問われるリスクもあるのです。 そして、情報漏洩の原因としては、以下の理由が挙げられます。 外部からのサイバー攻撃 内部不正 社員の人為的ミス 管理ミス 以上のように、社内外問わず情報漏洩に関わるリスクがあります。そのため、情報漏洩に対するリスクヘッジには、情報セキュリティに関する国際規格「ISO27001」を取得している「ナレカン」のようなツールで、安全に社内情報を管理する必要があるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ リスクヘッジを実施するときのポイント3選 以下では、リスクヘッジを実施するときのポイント3選をご紹介します。リスクヘッジが不十分では、プロジェクトの進行が妨げられる場合があるため、以下のポイントを踏まえたうえで、リスクヘッジを実施しましょう。 論理的に思考する癖づけをする リスクヘッジには、客観的な根拠から論理的に考えられる思考能力が求められます。 たとえば、トラブルを引き起こすリスク要因を整理して因果関係を明らかにすれば、対応すべきタスクがすぐにわかるので、課題をスムーズに解決できます。また、物事を多角的な視点で捉え、原因と結果を予測すれば、より適切なリスクヘッジが可能です。 さらに、リスクヘッジは主観的な立場から実施してしまうと、固定観念にとらわれ、リスクを見逃したりアプローチが限定されたりする可能性があります。そのため、リスクの規模や影響を事実ベースで客観的に判断することを心がけましょう。 社内の課題を蓄積する体制を整える リスクヘッジを実施する前に、社内の課題を蓄積する体制を整えましょう。 社内には大小さまざまな課題が存在しています。しかし、社内の課題として認知されているだけで、放置されている状態であれば、誰も対策を講じようとせず、適切なリスクヘッジを実施できません。 そこで、社内のあらゆる情報を一元管理できる「ナレカン」のようなツールを導入すれば、社内の全ての課題を認識でき、優先順位を設定したうえでリスクヘッジを実施できます。 正しく情報共有をする 正しい情報共有が実践できていれば、社内全体でリスクヘッジ能力を高められます。 担当者のみがリスクに対する意識が高くても、社内全体で意識醸成がされていなければ、トラブルが発生したときに適切な対応ができません。しかし、リスクに関する情報共有ができていると、危機意識が生まれるので、トラブルが起きても冷静に対処できるのです。 また、情報共有を実践するには、メールや口頭では非効率なうえ、セキュリティ面で不安が残ります。そのため、セキュリティ性に優れているITツールを活用して、効率的かつ安全にコミュニケーションをとる企業が多いです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】情報漏えいのリスクヘッジに最適なツール 以下では、情報のリスクヘッジに最適なツールをご紹介します。 IT化が進むなか、業界業種問わず利用される「情報」は企業が保護すべき財産であり、リスクヘッジは欠かせません。とくに、情報に関するリスクヘッジがされてなければ、人材流出によってノウハウを失ったり、意図せず情報が漏えいしたりするトラブルに発展してしまいます。 ただし、情報のリスクヘッジを実施するには、社内のあらゆる情報を管理・共有する体制が必要です。そこで、「情報共有ツール」を使うと、貴重なノウハウを簡単に蓄積できるだけでなく、アナログな管理にはない高度なセキュリティ下で安心して情報を守れます。 結論、情報漏えいのリスクヘッジには、社内に散在するリスクを一元管理し社員に即共有できるツール「ナレカン」が必須です。 ナレカンの「記事」に残した情報は、任意のメンバーにのみ共有されるほか、資料DLの可否も操作できるので、不正アクセスや情報漏えいのリスクがありません。また、全ての通信・情報は暗号化されるなど、強固なセキュリティを誇るので大企業でも安心して情報を残せます。 社内のあらゆる情報を一元管理し即共有できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 企業が実施すべきリスクヘッジ対策とポイントまとめ ここまで、企業が実施すべきリスクヘッジ対策や、リスクヘッジを実施するときのポイントを中心に解説しました。 企業を継続的に成長させるには、人材育成の強化やコンプライアンスの徹底、情報漏洩の防止などのリスクヘッジを実施する必要があります。また、効果的なリスクヘッジを実施するためには、社内で適切に情報を共有・管理する体制を整えなければなりません。 ただし、紙をはじめとしたアナログな情報管理では「情報に関するリスク」をなくせません。そこで、「強固なセキュリティで社内情報を安全に管理できるツール」を導入すべきなのです。 したがって、リスクヘッジを実施するには、社内のあらゆる情報を一元管理し、強固なセキュリティ対策が備わったツール「ナレカン」が必須です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、リスクヘッジの問題を解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年03月26日リスクヘッジの意味とは?企業が実施すべき対策やポイントを紹介!ビジネスにおけるリスクヘッジ(risk hedge)とは、企業に対する危険の予測・対策を意味します。企業が継続して成長していくためには、適切なリスクヘッジが欠かせません。 しかし、リスクヘッジを実施すべき意味や具体的な対策内容が社内に浸透しておらず「リスクヘッジの正しい対策が分からない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、リスクヘッジの意味や企業が実施すべき対策・ポイントを中心に解説します。 リスクヘッジの意味や使い方を理解したい 企業が実施すべきリスクヘッジの手法とポイントを知りたい 社内に散在する情報を集約し、情報管理のリスクを軽減したい という担当者の方は本記事を参考にすると、企業が実施すべきリスクヘッジ対策を把握しながら、事業の安定性を高められます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 リスクヘッジの意味や類語との違いとは1.1 リスクヘッジとは1.2 リスクマネジメントとの違い1.3 リスクテイクとの違い2 企業が実施すべきリスクヘッジとは?2.1 人事・労務の見直し2.2 コンプライアンスの徹底2.3 経営状況の可視化2.4 情報漏洩の防止3 リスクヘッジを実施するときのポイント3選3.1 論理的に思考する癖づけをする3.2 社内の課題を蓄積する体制を整える3.3 正しく情報共有をする4 【必見】情報漏えいのリスクヘッジに最適なツール4.1 社内のあらゆる情報を一元管理し即共有できるツール「ナレカン」5 企業が実施すべきリスクヘッジ対策とポイントまとめ リスクヘッジの意味や類語との違いとは 以下では、リスクヘッジを実施すべき意味について解説します。混同しやすい用語との違いを確認して、リスクヘッジの使い方や重要性を把握しましょう。 リスクヘッジとは リスクヘッジとは、あらかじめ予測されるリスクに対して対策を立てて備えることを指します。 リスクヘッジは、元々金融業界において用いられる言葉であり「危機管理」や「保険」といった類語があります。為替の変動などで想定される損失のリスクに対し、対策をとることを「リスクヘッジをする」という表現で使います。 とはいえ、業界業種問わず、企業の営業活動には「ヒト・モノ・カネ・情報」に関わるリスクが潜んでいます。そのため、トラブルが発生する前にリスクヘッジを実施して、チーム全体でリスクに対する認識をすり合わせておく必要があるのです。 リスクマネジメントとの違い リスクマネジメントとは、発生する可能性のあるリスクに対する危機管理を指します。 リスクヘッジがリスクを軽減する方法論である一方で、リスクマネジメントはリスク対策のプロセス全体を意味します。そのため、リスクヘッジはリスクマネジメントのプロセスの一環であると言えるのです。 適切なリスクマネジメントには、的確なリスクヘッジが欠かせません。そのため、効果的なリスクヘッジを実施しつつ、組織的にリスクマネジメントをする体制を整えましょう。 リスクテイクとの違い リスクテイクとは、危険性を理解したうえでリターンを期待して実行される行動であり、リスクを回避するリスクヘッジとは相反する意味を持つ用語です。 あえてリスクを引き受けた行動によって、大きなリターンを期待できる場合があります。そのため、利益を得るには、適切なリスクテイクが不可欠なのです。 したがって、リスクテイクを適切に判断するには、リスクヘッジによって不確定要素のリスクを把握・軽減しておく必要があるのです。以上のように、リスクテイクとリスクヘッジをバランス良く実施し、企業の発展を目指しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 企業が実施すべきリスクヘッジとは? 以下では、企業が実施すべきリスクヘッジについて解説します。適切なリスクヘッジによって、企業にもたらされるダメージを最小限に抑えられます。 人事・労務の見直し 企業のリスクヘッジはもちろん持続的な成長には、人事・労務の見直しが不可欠です。 適切な人材育成を通して、社員それぞれが能力を向上させ発揮できるようになると、モチベーションの低下や人材不足のリスクを軽減します。また、人材育成のシステムを上手く構築できれば、業務の属人化を防ぎ、組織全体の成長を促進できるのです。 また、社会保険手続や給与計算に関する従業員とのトラブルを防ぐためにも、「働く環境」の整備・管理のリスクヘッジも適切に実施しましょう。 コンプライアンスの徹底 「コンプライアンス」とは、企業が法令や社会的ルールを遵守することを意味します。 各企業は、「労働基準法」や「独占禁止法」などの自社に適用される法令を守らなければなりません。法令に違反した企業は、行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。 また、企業は明文化された法令だけでなく、社会的な規範も十分に意識する必要があります。社会的なモラルやルールに反すると、世間から会社の信頼を失う事態になりかねないため、批判を受ける可能性がある行動は避けましょう。 経営状況の可視化 企業が損失や不利益を回避するために、自社はもちろん、取引先の経営状況を可視化しておきましょう。 経営面において危惧される要素には、”為替変動による損失”や”取引先の倒産リスク”などが挙げられます。とくに、昨今では原材料価格の高騰が頻発しているため、複数の取引先を確保しておくなどの対策が必要になるのです。 以上のように目先の問題だけでなく、将来的に起こり得るリスクを把握して対策を講じていきましょう。 情報漏洩の防止 情報漏洩の防止は、現代の企業にとって必須の課題です。 自社が保有する機密情報や顧客情報、個人情報の漏洩は、企業の社会的信用を失墜させ、ブランドイメージにダメージを与えかねません。損害賠償金や業務停止による機会損失が発生するだけでなく、法的責任が問われるリスクもあるのです。 そして、情報漏洩の原因としては、以下の理由が挙げられます。 外部からのサイバー攻撃 内部不正 社員の人為的ミス 管理ミス 以上のように、社内外問わず情報漏洩に関わるリスクがあります。そのため、情報漏洩に対するリスクヘッジには、情報セキュリティに関する国際規格「ISO27001」を取得している「ナレカン」のようなツールで、安全に社内情報を管理する必要があるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ リスクヘッジを実施するときのポイント3選 以下では、リスクヘッジを実施するときのポイント3選をご紹介します。リスクヘッジが不十分では、プロジェクトの進行が妨げられる場合があるため、以下のポイントを踏まえたうえで、リスクヘッジを実施しましょう。 論理的に思考する癖づけをする リスクヘッジには、客観的な根拠から論理的に考えられる思考能力が求められます。 たとえば、トラブルを引き起こすリスク要因を整理して因果関係を明らかにすれば、対応すべきタスクがすぐにわかるので、課題をスムーズに解決できます。また、物事を多角的な視点で捉え、原因と結果を予測すれば、より適切なリスクヘッジが可能です。 さらに、リスクヘッジは主観的な立場から実施してしまうと、固定観念にとらわれ、リスクを見逃したりアプローチが限定されたりする可能性があります。そのため、リスクの規模や影響を事実ベースで客観的に判断することを心がけましょう。 社内の課題を蓄積する体制を整える リスクヘッジを実施する前に、社内の課題を蓄積する体制を整えましょう。 社内には大小さまざまな課題が存在しています。しかし、社内の課題として認知されているだけで、放置されている状態であれば、誰も対策を講じようとせず、適切なリスクヘッジを実施できません。 そこで、社内のあらゆる情報を一元管理できる「ナレカン」のようなツールを導入すれば、社内の全ての課題を認識でき、優先順位を設定したうえでリスクヘッジを実施できます。 正しく情報共有をする 正しい情報共有が実践できていれば、社内全体でリスクヘッジ能力を高められます。 担当者のみがリスクに対する意識が高くても、社内全体で意識醸成がされていなければ、トラブルが発生したときに適切な対応ができません。しかし、リスクに関する情報共有ができていると、危機意識が生まれるので、トラブルが起きても冷静に対処できるのです。 また、情報共有を実践するには、メールや口頭では非効率なうえ、セキュリティ面で不安が残ります。そのため、セキュリティ性に優れているITツールを活用して、効率的かつ安全にコミュニケーションをとる企業が多いです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】情報漏えいのリスクヘッジに最適なツール 以下では、情報のリスクヘッジに最適なツールをご紹介します。 IT化が進むなか、業界業種問わず利用される「情報」は企業が保護すべき財産であり、リスクヘッジは欠かせません。とくに、情報に関するリスクヘッジがされてなければ、人材流出によってノウハウを失ったり、意図せず情報が漏えいしたりするトラブルに発展してしまいます。 ただし、情報のリスクヘッジを実施するには、社内のあらゆる情報を管理・共有する体制が必要です。そこで、「情報共有ツール」を使うと、貴重なノウハウを簡単に蓄積できるだけでなく、アナログな管理にはない高度なセキュリティ下で安心して情報を守れます。 結論、情報漏えいのリスクヘッジには、社内に散在するリスクを一元管理し社員に即共有できるツール「ナレカン」が必須です。 ナレカンの「記事」に残した情報は、任意のメンバーにのみ共有されるほか、資料DLの可否も操作できるので、不正アクセスや情報漏えいのリスクがありません。また、全ての通信・情報は暗号化されるなど、強固なセキュリティを誇るので大企業でも安心して情報を残せます。 社内のあらゆる情報を一元管理し即共有できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 企業が実施すべきリスクヘッジ対策とポイントまとめ ここまで、企業が実施すべきリスクヘッジ対策や、リスクヘッジを実施するときのポイントを中心に解説しました。 企業を継続的に成長させるには、人材育成の強化やコンプライアンスの徹底、情報漏洩の防止などのリスクヘッジを実施する必要があります。また、効果的なリスクヘッジを実施するためには、社内で適切に情報を共有・管理する体制を整えなければなりません。 ただし、紙をはじめとしたアナログな情報管理では「情報に関するリスク」をなくせません。そこで、「強固なセキュリティで社内情報を安全に管理できるツール」を導入すべきなのです。 したがって、リスクヘッジを実施するには、社内のあらゆる情報を一元管理し、強固なセキュリティ対策が備わったツール「ナレカン」が必須です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、リスクヘッジの問題を解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年03月26日【必見】コストダウン・削減に成功した企業事例7選!コストダウン・削減には、リソースの適切な分配や利益の拡大につながるメリットがあり、業界業種を問わず企業が積極的に推し進めている施策です。 しかし、コスト削減を実現したいが、具体的な方法がわからないと悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。自社でコスト削減を行うにあたり、企業事例を参考にすると施策実施から成功までのイメージがしやすくなります。 そこで今回は、コストダウン・削減に成功した企業事例を中心にご紹介します。 コスト削減に成功した事例を参考にしたい 自社のコスト削減に役立つ方法が知りたい コスト削減におすすめの手段があれば教えて欲しい という方はこの記事を参考にすると、実際に企業が行ったコストダウン・削減の取り組み方と効果を確認しながら、自社に必要な施策が取れるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 コスト削減とは2 コストダウン・削減の効果とは3 コストダウン・削減に成功した企業事例7選3.1 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン|会計システムのデジタル化3.2 ClipLine株式会社|オフィス縮小化3.3 株式会社フジテックス|営業ツールの導入3.4 株式会社半谷製作所|デジタル化促進3.5 株式会社石崎電機製作所|ドキュメントツールの利用3.6 株式会社ゴッタライド|情報共有ツールの導入3.7 株式会社LIVEUP|情報ストックツールの導入4 情報共有を円滑化しコスト削減にも役立つツール4.1 コスト削減に最適な情報共有ツール「ナレカン」5 コスト削減の手順6 コストダウン・削減の成功事例と理由まとめ コスト削減とは 企業におけるコスト削減とは、「企業活動のなかで発生する費用を削減すること」を指します。 コストは、商品の製造にかかる原価だけでなく、オフィスの維持費や従業員の給与など、企業が利益を生むために必要な費用すべてを含みます。 そのため、「コスト削減」といっても、大量仕入れで原材料費を削減したり、従業員の定着率を高めて採用コストを削減したりするなど様々な方法があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ コストダウン・削減の効果とは コストダウン・削減には、「企業利益を向上させる効果」があります。 コスト削減が企業にとって利益拡大に結び付く根拠として、利益が「企業利益=売上-コスト」の図式で表せることが挙げられます。 つまり、利益拡大を図るには「売り上げを向上する」もしくは「コストを抑える」のいずれかに絞られるのです。ただし、利益の拡大を目指して、新商品の発売やサービスの拡大などの取り組みを行っても、すぐに効果は表れません。 コスト削減は、消耗品費や水道光熱費といった取り組みやすい施策も多く存在し、削減効果が数値で比較できるため継続しやすいメリットもあります。そのため、利益拡大を目標に施策を実行するには、まずコスト削減から着手することがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ コストダウン・削減に成功した企業事例7選 以下では、コストダウン・削減に成功した企業事例を紹介します。コストダウン施策の効果や規模がイメージできない場合には、他社事例を参考にし、より自社に適した施策を選択しましょう。 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン|会計システムのデジタル化 引用:https://www.sej.co.jp/company/ 従来のセブン‐イレブン・ジャパンでは、伝票や帳票などの会計処理を全て紙媒体で行っており、用紙代だけでなく保管コストも企業にとって大きな負担となっていました。 そこで、事務処理コストを削減するために、会計システムをデジタル化しました。すると、伝票や帳票のペーパーレス化を推し進め年間でおよそ14億円ものコスト削減に成功したのです。 また、コスト削減政策の1つとして電力代削減にも取り組み、店内照明のLED化や空調温度の設定温度上昇といった施策で、月間の電気使用料をおよそ27%もの削減を達成しています。 参考:株式会社セブン‐イレブン・ジャパンのコスト削減事例詳細はこちら ClipLine株式会社|オフィス縮小化 引用:https://corp.clipline.com/ ClipLine株式会社は、コロナ渦により対面での出勤が少なくなっていた情勢に対し、オフィス縮小化という手段でコスト削減に成功しました。 もともと同社は、JR田町駅にほど近いオフィスビルの1フロアを月額家賃500万ほどで借りていました。しかしコロナ渦の情勢と緊急事態宣言を鑑みて全社員を在宅勤務制に移行させたため、オフィススペースに余裕ができていたのです。 そこで、さまざまな観点から社内で検討を繰り返し、オフィス移転による規模の縮小を決定しました。そのコスト削減効果は年間で6,000万円にも及ぶ試算であり、当時の情勢にマッチさせたコスト削減政策だといえます。 参考:ClipLineのコスト削減事例詳細はこちら 株式会社フジテックス|営業ツールの導入 引用:https://fjtex.co.jp/ 株式会社フジテックスは、受注確度が曖昧なまま顧客のもとへ訪問し、一泊かけて訪ねても何の成果も生まれなかったと振り返ることもしばしばありました。 そこで、クロージング時以外はオンライン営業ツールを用いて営業を行う、というシステム作りに着手しコスト削減に成功しました。 オンライン営業ツールの導入により、交通費や宿泊費といった金銭コストはもちろん、移動に要する時間的コストも大幅に削減されました。そして、より多くの商談を行えるようになり、確かな業務効率化とコスト削減効果を実感しています。 参考:株式会社フジテックスのコスト削減の事例詳細はこちら 株式会社半谷製作所|デジタル化促進 引用:http://www.hanya-net.co.jp/ 株式会社半谷製作所は、間接部門の業務効率を改善できないか検討し、デジタル化を選択しました。 システムの導入時に重視していた項目は、使い勝手と単純作業の合理化でした。徹底した現場とのヒアリングの甲斐もあり、スムーズにシステムは浸透し、従来業務の人為的ミスを大幅削減に成功したのです。 また、社長のデジタル化に対する姿勢が社員にも浸透し、「この業務もデジタル化により合理化できないか」と社員自ら考え業務効率化を推し進める環境構築も実現しました。 参考:株式会社半谷製作所 株式会社石崎電機製作所|ドキュメントツールの利用 引用:https://www.sure-ishizaki.co.jp/ 「男前アイロン」などの商品で知られる株式会社石崎電機製作所では、必要な情報にすぐにアクセスできないという課題を抱えていました。 そこで、課題解決のためにオンライン上でドキュメントを管理可能な「Evernote(エバーノート)」を全社で導入しました。すると、議事録、日報、名刺など社内の情報を一元管理できるようになり、従来の紙媒体で頻発していた必要な資料が見つからないという問題を解決しました。 全社で導入を図るために、社員1人あたり4時間ほどの個人レクチャーを行い、全員が使いこなせる環境を作り上げました。そして、従来の情報共有の無駄を省きリソースを過不足なく分配できるようになったのです。 参考:株式会社石崎電機製作所のコスト削減事例詳細はこちら 株式会社ゴッタライド|情報共有ツールの導入 引用:https://www.gotta-ride.com/ 株式会社ゴッタライドは、住宅リフォーム会社のウェブマーケティングや、不動産仲介への参入支援を主な事業として行っています。同社は日頃から情報共有の不便さを感じていました。 そこで、新たに情報共有ツールである「Chatwork」の導入によってコストを抑え、より細やかな情報共有を実現しました。具体的には、ゴッタライドのミーティングは「Chatwork Live」を用いて画面を共有し、オンライン上で完結させることで交通費や日程調整のコストを削減しているのです。 離れた場所でもオンラインデバイスを活用しながら、顧客と綿密なコミュニケーションを図り、サービスの質を落とさずコスト削減に成功した事例のひとつです。 参考:株式会社ゴッタライドのコスト削減事例詳細はこちら 株式会社LIVEUP|情報ストックツールの導入 引用:https://live-up.co.jp/ 『映像』に関連するソリューションサービスを提供している株式会社LIVEUPでは、常時70~80の案件を平行して行っていました。そのような状況の中、利用していたチャットツールでは、情報が流れてしまい業務に支障をきたしていたのです。 そこで、情報を流さずにストックでき、案件ごとに「ノート」で管理可能な情報共有ツールの「Stock」を導入しました。 結果として、導入以前の運用であった「複数ツールを併用」せずにStockですべての情報を一元管理可能になったため、業務コストが5分の1以下に削減されました。また、必要な情報を探し出す検索性も向上しており、業務効率化の実現にも成功しています。 参考:株式会社LIVEUPのコスト削減事例詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 情報共有を円滑化しコスト削減にも役立つツール 以下では、情報共有を円滑化し、コスト削減にも役立つツールを紹介します。 自社のコスト削減を実現したいが、具体的な方法がわからない場合には、「情報共有を円滑化するITツール」の導入がおすすめです。業務の基本となる情報共有の円滑化は、ノウハウ共有による新入社員の教育コスト削減や、欲しい情報を探す無駄な時間的コスト削減の効果も期待できるのです。 したがって、社内の情報共有を最適化し、コストを削減できるITツールを導入しましょう。ただし、多機能で操作が難しいツールでは社員が使いこなすまでに時間がかかるので、「社員全員が簡単に使えるか」も選定ポイントとして重視しなければなりません。 結論、社内のコスト削減には社内の情報共有を円滑化し、コスト削減に役立つツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」にはテキストや画像を使って、マニュル作成やノウハウ共有が簡単にできるので、教育コスト削減に役立ちます。さらに、まとめた社内情報から必要な情報だけを探し出す「検索機能」で、情報を見つけ出す際にかかる時間的コストも削減できます。 コスト削減に最適な情報共有ツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ コスト削減の手順 社内のコスト削減を実施する際の手順は以下の通りです。 現状分析と削減計画の作成 まずは、現状のコストを把握し、課題を設定します。課題をふまえたうえで、コスト削減の計画を立てましょう。 計画の実行 立てた計画を社内に共有し、実行します。削減目標や計画実施の必要性を社員に伝えたうえで進めることが重要です。 結果の分析と改善 取り組みを振り返り、どのコストが削減できた・できなかったのかを分析しましょう。結果をもとに、その後のコスト削減計画における改善点を見つけることも大切です。 以上の手順で分析、実行、改善を繰り返し、社内のコスト削減を定着させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ コストダウン・削減の成功事例と理由まとめ ここまでコストダウン・削減の成功事例と理由をご紹介しました。 コスト削減の成功事例に見られる共通点として、自社の課題解決にマッチしたITツールを正しく導入していることが挙げられます。とくに、オフィスの縮小や大規模なデジタル化に取り組むには、工数がかかり施策規模も大きくなるので、業務の基本である「情報共有」をITツールで円滑化しコスト削減を達成しましょう。 ただし、情報共有ツールは全社で運用されなければ効果が最大化できません。そこで、ITリテラシーの高さに関わらず、誰でも使えるツールが大前提となるのです。 そこで社内のコストダウンにはコスト削減を情報共有の側面から実現するツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、自社のコストに関する悩みを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年03月26日【必見】コストダウン・削減に成功した企業事例7選!コストダウン・削減には、リソースの適切な分配や利益の拡大につながるメリットがあり、業界業種を問わず企業が積極的に推し進めている施策です。 しかし、コスト削減を実現したいが、具体的な方法がわからないと悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。自社でコスト削減を行うにあたり、企業事例を参考にすると施策実施から成功までのイメージがしやすくなります。 そこで今回は、コストダウン・削減に成功した企業事例を中心にご紹介します。 コスト削減に成功した事例を参考にしたい 自社のコスト削減に役立つ方法が知りたい コスト削減におすすめの手段があれば教えて欲しい という方はこの記事を参考にすると、実際に企業が行ったコストダウン・削減の取り組み方と効果を確認しながら、自社に必要な施策が取れるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 コスト削減とは2 コストダウン・削減の効果とは3 コストダウン・削減に成功した企業事例7選3.1 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン|会計システムのデジタル化3.2 ClipLine株式会社|オフィス縮小化3.3 株式会社フジテックス|営業ツールの導入3.4 株式会社半谷製作所|デジタル化促進3.5 株式会社石崎電機製作所|ドキュメントツールの利用3.6 株式会社ゴッタライド|情報共有ツールの導入3.7 株式会社LIVEUP|情報ストックツールの導入4 情報共有を円滑化しコスト削減にも役立つツール4.1 コスト削減に最適な情報共有ツール「ナレカン」5 コスト削減の手順6 コストダウン・削減の成功事例と理由まとめ コスト削減とは 企業におけるコスト削減とは、「企業活動のなかで発生する費用を削減すること」を指します。 コストは、商品の製造にかかる原価だけでなく、オフィスの維持費や従業員の給与など、企業が利益を生むために必要な費用すべてを含みます。 そのため、「コスト削減」といっても、大量仕入れで原材料費を削減したり、従業員の定着率を高めて採用コストを削減したりするなど様々な方法があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ コストダウン・削減の効果とは コストダウン・削減には、「企業利益を向上させる効果」があります。 コスト削減が企業にとって利益拡大に結び付く根拠として、利益が「企業利益=売上-コスト」の図式で表せることが挙げられます。 つまり、利益拡大を図るには「売り上げを向上する」もしくは「コストを抑える」のいずれかに絞られるのです。ただし、利益の拡大を目指して、新商品の発売やサービスの拡大などの取り組みを行っても、すぐに効果は表れません。 コスト削減は、消耗品費や水道光熱費といった取り組みやすい施策も多く存在し、削減効果が数値で比較できるため継続しやすいメリットもあります。そのため、利益拡大を目標に施策を実行するには、まずコスト削減から着手することがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ コストダウン・削減に成功した企業事例7選 以下では、コストダウン・削減に成功した企業事例を紹介します。コストダウン施策の効果や規模がイメージできない場合には、他社事例を参考にし、より自社に適した施策を選択しましょう。 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン|会計システムのデジタル化 引用:https://www.sej.co.jp/company/ 従来のセブン‐イレブン・ジャパンでは、伝票や帳票などの会計処理を全て紙媒体で行っており、用紙代だけでなく保管コストも企業にとって大きな負担となっていました。 そこで、事務処理コストを削減するために、会計システムをデジタル化しました。すると、伝票や帳票のペーパーレス化を推し進め年間でおよそ14億円ものコスト削減に成功したのです。 また、コスト削減政策の1つとして電力代削減にも取り組み、店内照明のLED化や空調温度の設定温度上昇といった施策で、月間の電気使用料をおよそ27%もの削減を達成しています。 参考:株式会社セブン‐イレブン・ジャパンのコスト削減事例詳細はこちら ClipLine株式会社|オフィス縮小化 引用:https://corp.clipline.com/ ClipLine株式会社は、コロナ渦により対面での出勤が少なくなっていた情勢に対し、オフィス縮小化という手段でコスト削減に成功しました。 もともと同社は、JR田町駅にほど近いオフィスビルの1フロアを月額家賃500万ほどで借りていました。しかしコロナ渦の情勢と緊急事態宣言を鑑みて全社員を在宅勤務制に移行させたため、オフィススペースに余裕ができていたのです。 そこで、さまざまな観点から社内で検討を繰り返し、オフィス移転による規模の縮小を決定しました。そのコスト削減効果は年間で6,000万円にも及ぶ試算であり、当時の情勢にマッチさせたコスト削減政策だといえます。 参考:ClipLineのコスト削減事例詳細はこちら 株式会社フジテックス|営業ツールの導入 引用:https://fjtex.co.jp/ 株式会社フジテックスは、受注確度が曖昧なまま顧客のもとへ訪問し、一泊かけて訪ねても何の成果も生まれなかったと振り返ることもしばしばありました。 そこで、クロージング時以外はオンライン営業ツールを用いて営業を行う、というシステム作りに着手しコスト削減に成功しました。 オンライン営業ツールの導入により、交通費や宿泊費といった金銭コストはもちろん、移動に要する時間的コストも大幅に削減されました。そして、より多くの商談を行えるようになり、確かな業務効率化とコスト削減効果を実感しています。 参考:株式会社フジテックスのコスト削減の事例詳細はこちら 株式会社半谷製作所|デジタル化促進 引用:http://www.hanya-net.co.jp/ 株式会社半谷製作所は、間接部門の業務効率を改善できないか検討し、デジタル化を選択しました。 システムの導入時に重視していた項目は、使い勝手と単純作業の合理化でした。徹底した現場とのヒアリングの甲斐もあり、スムーズにシステムは浸透し、従来業務の人為的ミスを大幅削減に成功したのです。 また、社長のデジタル化に対する姿勢が社員にも浸透し、「この業務もデジタル化により合理化できないか」と社員自ら考え業務効率化を推し進める環境構築も実現しました。 参考:株式会社半谷製作所 株式会社石崎電機製作所|ドキュメントツールの利用 引用:https://www.sure-ishizaki.co.jp/ 「男前アイロン」などの商品で知られる株式会社石崎電機製作所では、必要な情報にすぐにアクセスできないという課題を抱えていました。 そこで、課題解決のためにオンライン上でドキュメントを管理可能な「Evernote(エバーノート)」を全社で導入しました。すると、議事録、日報、名刺など社内の情報を一元管理できるようになり、従来の紙媒体で頻発していた必要な資料が見つからないという問題を解決しました。 全社で導入を図るために、社員1人あたり4時間ほどの個人レクチャーを行い、全員が使いこなせる環境を作り上げました。そして、従来の情報共有の無駄を省きリソースを過不足なく分配できるようになったのです。 参考:株式会社石崎電機製作所のコスト削減事例詳細はこちら 株式会社ゴッタライド|情報共有ツールの導入 引用:https://www.gotta-ride.com/ 株式会社ゴッタライドは、住宅リフォーム会社のウェブマーケティングや、不動産仲介への参入支援を主な事業として行っています。同社は日頃から情報共有の不便さを感じていました。 そこで、新たに情報共有ツールである「Chatwork」の導入によってコストを抑え、より細やかな情報共有を実現しました。具体的には、ゴッタライドのミーティングは「Chatwork Live」を用いて画面を共有し、オンライン上で完結させることで交通費や日程調整のコストを削減しているのです。 離れた場所でもオンラインデバイスを活用しながら、顧客と綿密なコミュニケーションを図り、サービスの質を落とさずコスト削減に成功した事例のひとつです。 参考:株式会社ゴッタライドのコスト削減事例詳細はこちら 株式会社LIVEUP|情報ストックツールの導入 引用:https://live-up.co.jp/ 『映像』に関連するソリューションサービスを提供している株式会社LIVEUPでは、常時70~80の案件を平行して行っていました。そのような状況の中、利用していたチャットツールでは、情報が流れてしまい業務に支障をきたしていたのです。 そこで、情報を流さずにストックでき、案件ごとに「ノート」で管理可能な情報共有ツールの「Stock」を導入しました。 結果として、導入以前の運用であった「複数ツールを併用」せずにStockですべての情報を一元管理可能になったため、業務コストが5分の1以下に削減されました。また、必要な情報を探し出す検索性も向上しており、業務効率化の実現にも成功しています。 参考:株式会社LIVEUPのコスト削減事例詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 情報共有を円滑化しコスト削減にも役立つツール 以下では、情報共有を円滑化し、コスト削減にも役立つツールを紹介します。 自社のコスト削減を実現したいが、具体的な方法がわからない場合には、「情報共有を円滑化するITツール」の導入がおすすめです。業務の基本となる情報共有の円滑化は、ノウハウ共有による新入社員の教育コスト削減や、欲しい情報を探す無駄な時間的コスト削減の効果も期待できるのです。 したがって、社内の情報共有を最適化し、コストを削減できるITツールを導入しましょう。ただし、多機能で操作が難しいツールでは社員が使いこなすまでに時間がかかるので、「社員全員が簡単に使えるか」も選定ポイントとして重視しなければなりません。 結論、社内のコスト削減には社内の情報共有を円滑化し、コスト削減に役立つツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」にはテキストや画像を使って、マニュル作成やノウハウ共有が簡単にできるので、教育コスト削減に役立ちます。さらに、まとめた社内情報から必要な情報だけを探し出す「検索機能」で、情報を見つけ出す際にかかる時間的コストも削減できます。 コスト削減に最適な情報共有ツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ コスト削減の手順 社内のコスト削減を実施する際の手順は以下の通りです。 現状分析と削減計画の作成 まずは、現状のコストを把握し、課題を設定します。課題をふまえたうえで、コスト削減の計画を立てましょう。 計画の実行 立てた計画を社内に共有し、実行します。削減目標や計画実施の必要性を社員に伝えたうえで進めることが重要です。 結果の分析と改善 取り組みを振り返り、どのコストが削減できた・できなかったのかを分析しましょう。結果をもとに、その後のコスト削減計画における改善点を見つけることも大切です。 以上の手順で分析、実行、改善を繰り返し、社内のコスト削減を定着させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ コストダウン・削減の成功事例と理由まとめ ここまでコストダウン・削減の成功事例と理由をご紹介しました。 コスト削減の成功事例に見られる共通点として、自社の課題解決にマッチしたITツールを正しく導入していることが挙げられます。とくに、オフィスの縮小や大規模なデジタル化に取り組むには、工数がかかり施策規模も大きくなるので、業務の基本である「情報共有」をITツールで円滑化しコスト削減を達成しましょう。 ただし、情報共有ツールは全社で運用されなければ効果が最大化できません。そこで、ITリテラシーの高さに関わらず、誰でも使えるツールが大前提となるのです。 そこで社内のコストダウンにはコスト削減を情報共有の側面から実現するツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、自社のコストに関する悩みを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
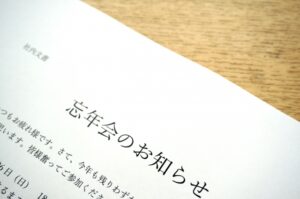 2025年10月27日【無料あり】社内・自治会で使える便利なおすすめ電子回覧板アプリ6選!情報を共有する手段として「回覧板」が挙げられます。そして、今日では紙ではなく「電子回覧板アプリ」を使って、情報共有を効率化する企業や自治会が増えているのです。 一方、「電子回覧板アプリを導入したいが、どれが自社に最適なのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリ6選を中心にご紹介します。 電子回覧板のメリットやアプリの選定ポイントを知りたい 各アプリの特徴を比較して、導入するアプリを決めたい 情報が自然と目に入りやすい情報共有ツールを探している という方はこの記事を参考にすると、自社でストレスなく運用できる電子回覧板アプリが分かり、情報共有の負担を取り除けるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 電子回覧板アプリ・デジタル回覧板のメリットは?1.1 企業が電子回覧板を導入するメリット1.2 自治会・町内会が電子回覧板を導入するメリット2 電子回覧板アプリを選ぶポイント2.1 企業が電子回覧板アプリを選ぶポイント2.2 自治会・町内会が電子回覧板アプリを選ぶポイント3 無料あり|社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリ6選3.1 【ナレカン】回覧板の作成からやりとりまでできる社内向けアプリ3.2 【Stock】最も簡単に回覧板を共有できる社内・町内会向けアプリ3.3 【LINE WORKS】LINEのように使える社内向けチャットアプリ3.4 【デジタル回覧板】写真を撮るだけで回覧板を回せる自治会向けアプリ3.5 【回覧板アプリ】Microsoftツールと連携できる社内向けアプリ3.6 【NI Collabo 360】回覧板にコメントを残せる社内向けアプリ4 <比較表>社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリ一覧5 社内電子回覧板アプリに必要な4つの機能5.1 (1)情報共有機能5.2 (2)確認機能5.3 (3)検索機能5.4 (4)編集・更新機能6 社内回覧板を電子化するときの2つの注意点7 社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリまとめ 電子回覧板アプリ・デジタル回覧板のメリットは? 電子回覧板アプリとは、インターネット上で簡単に回覧板を作成・共有できるアプリのことです。以下では、物理的な書類のやりとりが不要な電子回覧板のメリットを「企業」「自治会・町内会」ごとに紹介します。 企業が電子回覧板を導入するメリット 電子回覧板アプリは、社内情報を正確かつ円滑に共有・確認するのに重要なツールです。 アプリを使えば、社員に手渡しで回覧板を回す手間が省けるため、情報共有におけるタイムラグを解消できます。また、一度共有された情報はいつでも何度でも確認できるので、認識齟齬が生じにくくなるのです。 さらに、最近では「メッセージ機能」が搭載された回覧板アプリが増えています。これにより、回覧板に関するやりとりや担当者への質問も、メールやチャットツールを使わずに電子回覧板で完結します。 自治会・町内会が電子回覧板を導入するメリット 自治会や町内会で回覧板アプリを導入すれば、情報は「閲覧するだけ」で済むため、回覧板を回す手間や順番待ちの時間が一切かかりません。 さらに、地域の回覧板でよく見られる「不在の場合、回覧板が止まる」「不特定多数の人が触れるため、感染症のリスクが気になる」といった問題も解決できるのです。 とくに、セキュリティ対策が万全な回覧板アプリを導入すれば、地域の方が安心して利用できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 電子回覧板アプリを選ぶポイント ここでは、電子回覧板アプリを選ぶポイントを「企業」「自治会・町内会」別で紹介します。電子回覧板アプリを導入しても、合わないサービスを選んでしまうとかえって情報共有が滞ってしまうので、以下の内容を軸に選定しましょう。 企業が電子回覧板アプリを選ぶポイント 企業が電子回覧板アプリを選ぶときには、以下3点を軸に選びましょう。 自社の企業規模に合ったアプリか 大手~中堅企業は、セキュリティ対策が強固で、数万人規模でもスムーズに利用できるか確認しましょう。とくに大規模の企業は、「回覧板をはじめ、あらゆる社内のお知らせを共有できるアプリ」を選ぶと、ほかの業務の情報管理としても活用できます。 情報を振り返りやすいか 社内回覧板の情報は、見返せないと認識齟齬を引き起こすので「簡単に目的の情報を振り返れる」アプリを選ぶことが重要です。また、高性能な検索機能が搭載されていれば、必要な情報にすぐアクセスできます。 誰が見たか分かるか とくに人数が多い大規模な企業の場合、回覧板を回すたびに閲覧状況を確認するのは手間がかかります。そこで、誰が回覧板を見たかまで特定できる「既読機能」や「リアクション機能」があると便利です。 たとえば、上記3点を満たした「ナレカン」のようなツールを選ぶと、大企業でもスムーズな情報共有が実現します。 自治会・町内会が電子回覧板アプリを選ぶポイント 自治会・町内会が電子回覧板アプリを選ぶときには、「あらゆる年代が簡単に使えるツールか」を重視して選定しましょう。 自治会・町内会員によってITツールへの抵抗感は異なるので、操作が難しい電子回覧板アプリを選ぶと使いこなせず放置されてしまいます。したがって、ITツールに馴染みがない人でも直感的に使えることが大前提として必要なのです。 たとえば、「Stock」のような60代~70代でも説明なしで使えるほど簡単なツールを選べば、ITに詳しくなくても直感的に操作でき、導入後も安心して使い続けられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 無料あり|社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリ6選 以下では、社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリを6つ紹介します。 回覧板で情報を共有していると、一人ずつ内容を確認する必要があり、手間と時間がかかるため、アプリを導入して回覧板をデジタル化しましょう。また、情報の伝達漏れを防ぐために「共有した内容を誰が読んだか確認できるか」も重視すべきです。 さらに、ITに詳しくない人がいる場合は、複雑な操作をしなくても直感的に情報を受け取れる仕組みが必要です。誰でも迷わず大事な内容を確認できるようにするために「情報が自然と目に入るような機能」は欠かせません。 結論、企業・自治体が導入すべきアプリは、一目で必要な情報を確認でき、既読機能で閲覧状況を把握しやすい「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」で作成した回覧板は、既読表示があるうえ、「コメント」でやり取りができるので円滑な情報共有が実現します。また、ホーム画面の「お知らせ」に確認すべき情報をまとめられるので、直感的に情報にアクセスできます。 【ナレカン】回覧板の作成からやりとりまでできる社内向けアプリ 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード <重要な情報を周知できるホーム画面> ここでは、重要な情報を周知するのに便利なナレカンの機能を紹介します。 以下の画像は、ナレカンのホーム画面です。ナレカンのホーム画面では「社内お知らせ」で社員に周知したい記事を上部に大きく表示したり、最新の記事やよく閲覧されている記事を確認したりできます。 「社内お知らせ」機能を活用することで、社員が見るべき情報が自然と目に入るようになるため、社内の情報共有の手間を軽減できるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Stock】最も簡単に回覧板を共有できる社内・町内会向けアプリ Stockは、中小規模の企業や自治会・町内会に最適な情報共有アプリです。 「Stock」の「ノート」には、テキストをはじめ画像やファイルも記録でき、画像には直接文字を書き込むことができます。そのため、単なる回覧板としての利用だけでなく、社内や地域の情報共有ツールとして活用できる点が特徴です。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 <Stockをおすすめするポイント> ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 <Stockの口コミ・評判> 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ(栃木SC) 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 <Stockの料金> フリープラン :無料 ビジネスプラン :500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数:5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【LINE WORKS】LINEのように使える社内向けチャットアプリ LINE WORKSの特徴 さまざまな業務に役立つ機能がある 「掲示板機能」の他にも「カレンダー機能」や「タスク機能」、プライベート版LINEにもあるような「出欠確認」などの機能を使えます。そのため、回覧板としてだけでなく、あらゆる業務に活用可能です。 メッセージが送りやすい プライベート版LINEと同じような使用感のため、気軽にやりとりできます。また、グループトークでは「ノート」や「フォルダ」機能を活用して、円滑な情報共有が可能です。 LINE WORKSの機能・使用感 メンバーに回覧板の確認を促せる 「掲示板」で作成した回覧板を必読表示にすると、掲示板のトップページ上部に固定されるので、メンバーに確認されやすくなります。 回覧板へのコメントもできる 掲示板の画面下部にある「コメントを許可」にチェックを入れれば、回覧板に対するメンバーの声を受け取れます。そのため、掲示した情報に対する「質問事項」をその場で解決できるのです。 LINE WORKSの注意点 情報が流れやすい LINE WORKSはチャットツールなので、共有事項が多いと情報が流れて見つけづらくなる恐れがあります。そのため、あとから情報を振り返りにくかったり、重要な情報を見逃してしまったりする点に注意が必要です。 アプリ版ではダウンロードできないときがある ユーザーの口コミでは「時々、少し重たい添付など(PDF)がダウンロードできない、その場合はブラウザ版で開くと解消される」との声もあります。(参考:ITreview) LINE WORKSの料金体系 フリー:0円 スタンダード:540円/ユーザー/月(月払い) アドバンスト:960円/ユーザー/月(月払い) LINE WORKSの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【デジタル回覧板】写真を撮るだけで回覧板を回せる自治会向けアプリ デジタル回覧板の特徴 写真を撮ってすぐに回覧板を回せる 配布物を写真に撮ってすぐに共有する仕組みなので、紙の回覧板のように次の人へ手渡ししたり、順番待ちをしたりする必要はありません。 配信対象をグループ分けできる 全員への一斉配信はもちろん、対象者をグループ分けして、特定のメンバーに向けて情報を配信することもできます。 デジタル回覧板の機能 画像引用:DX推進支援アプリ「デジタル回覧板」リーフレット わずかな工数で回覧板を送れる 回覧板を写真に撮り、上図のように「タイトル、組織名、公開期間」を設定するだけで、すぐに情報を回覧できます。 回覧板の配布通知が来る 回覧板が配布されると、端末に配布通知が来るので確認漏れを防げます。 デジタル回覧板の注意点 行政(自治会)向けのツール 回覧板機能の他にも「防災放送の配信機能」や「避難場所の確認機能」が備えられています。そのため、ビジネスでの利用もできますが、地域の回覧板としての利用が想定されたツールという点に注意しましょう。 アプリ上で回覧板の作成はできない デジタル回覧板は、紙の書類を撮影することを前提に作られているので、文章を直接入力したり、情報をツールへ蓄積したりするには向いていない可能性があります。 デジタル回覧板の料金体系 料金の詳細はお問い合わせください。 デジタル回覧板の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【回覧板アプリ】Microsoftツールと連携できる社内向けアプリ 回覧板アプリの特徴 確認状況を表示できる 登録した回覧内容に対する、確認状況(%)の表示が出来ます。 回覧板を一覧表示できる アプリに登録した回覧板を一覧表示できるので、目的の情報を見つけやすいです。 回覧板アプリの機能 回覧期限を設定できる すぐに確認してほしい内容がある場合は、回覧期限を設定できるため安心です。 重要度を設定できる ステータスを「重要」に設定すれば、重要な情報を太字で一覧表示できます。そのため、必ず確認してほしい情報の確認漏れを減らせるのです。 回覧板アプリの注意点 回覧者を最大5名までしか指定できない 回覧者の指定を最大5名までしか指定できないため、大規模チームでは使いづらい恐れがあります。 Microsoft SharePointをインストールしなければ使えない 回覧板アプリを利用するには、有料ツールのMicrosoft SharePointをインストールしなければなりません。 回覧板アプリの料金体系 「回覧板アプリ」はMicrosoft SharePointをインストールすれば無料で使えます。以下は、他のアプリも使えるMicrosoft 365の一般法人向けプランを含んだ、Microsoft SharePointの料金体系です。各プランの詳細はSharePoint Onlineの料金ページを参照してください。 SharePoint(プラン 1):749円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Standard (Teams なし):1,536円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月 回覧板アプリの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【NI Collabo 360】回覧板にコメントを残せる社内向けアプリ NI Collabo 360の特徴 情報共有だけでなくワークフローにも利用できる 社内回覧板だけでなく、経費精算や稟議に関するワークフローにも利用できます。 多言語に対応している 日本語、英語以外にも、各企業で言語の辞書登録や設定が可能です。また、タイムゾーンの切り替えもできるため、グローバルな事業にも使えます。 NI Collabo 360の機能 確認状況が一覧表示される 画像引用:NI Collabo 360|回覧板 投稿した回覧板を「誰がいつ確認したのか」が一覧表示されるので、情報の伝え漏れを防げます。また、閲覧者は一言コメントを残せます。 社内SNS機能 画像引用:NI Collabo 360|UP! 「UP!」は、NI Collabo 360における社内SNSです。この機能を使って社内情報を気軽に共有することもできますが、チャット形式なので情報が流れやすい点に注意が必要です。 NI Collabo 360の注意点 個々の機能の専門性はない 一部のユーザーからは「様々な機能があり大変便利ですが、特化したサービス、システムには劣り、痒いところに手が届かないことも事実です」との声もあります。(参考:ITreview) ワークフローの設定が難しい 一部のユーザーからは「ワークフローのフロー図の作成が難しく、何度かテストを実施し対応をしています」という声が見られます。(参考:ITreview) NI Collabo 360の料金体系 クラウドタイプ:328円~/ユーザー/月 ライセンスタイプ:58,000円~/10ユーザー NI Collabo 360の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ <比較表>社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリ一覧 以下は、おすすめの電子回覧板アプリ6選の比較表です。(左右にスクロール可) ナレカン【一番おすすめ】 Stock【おすすめ】 LINE WORKS デジタル回覧板 回覧板アプリ NI Collabo 360 特徴 回覧板の作成からやりとりまでできる社内向けアプリ 最も簡単に回覧板を作成・共有できる・自治会向けアプリ LINEのように使える社内向けチャットアプリ 写真を撮るだけで回覧板を回せる自治会向けアプリ Microsoftツールと連携できる社内向けアプリ 回覧板にコメントを残せる社内向けアプリ おすすめの利用用途 ・社内利用(大手~中堅企業向け) ・社内利用(中小規模企業向け) ・自治会利用 ・社内利用 ・自治会利用 ・社内利用(小規模企業向け) ・社内利用 シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単 シンプルで簡単 多機能 シンプルで簡単 多機能 多機能 メッセージ機能 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】※ただし、音声チャットでのやりとり 【×】 【×】※閲覧者がコメントを残すことは可 既読機能 【〇】 【×】 【〇】 【×】 【〇】 【〇】 注意点 法人利用が前提 5名以上での利用が前提 大切な情報が流れやすい アプリ本体では回覧板を作成できない(紙の書類を撮影することが前提) 回覧者は最大5名までしか指定できない 個々の機能の専門性はない 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料プランあり ・有料プランは500円~/ユーザー/月 ・無料プランあり ・有料プランは540円~/ユーザー/月(月払い) ・要問い合わせ ・無料プランあり ・ただし、SharePoint(749円/ユーザー/月~)の導入が必須 ・無料プランなし ・有料プランは328円/ユーザー/月~ 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「LINE WORKS」の詳細はこちら 「デジタル回覧板」の詳細はこちら 「回覧板アプリ」の詳細はこちら 「NI Collabo 360」の詳細はこちら 上記のように、電子回覧板アプリによって機能性が異なるので「必要な機能に過不足ないアプリ」を選定しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内電子回覧板アプリに必要な4つの機能 ここでは、社内電子回覧板アプリに必要な4つの機能を解説します。以下の機能を備えたアプリを選べば、情報共有の負担を迅速に解消できます。 (1)情報共有機能 まず、社内電子回覧板には「情報共有機能」が欠かせません。 電子回覧板の本来の目的は、全社員に必要な情報を正確に、すばやく共有することです。情報共有機能があれば、社内情報が一貫して伝えられるので、伝達漏れを防げます。 たとえば、部署内の会議資料や社内イベントの案内など、関係者がリアルタイムで情報を確認しやすくなることで、不要な連絡の手間が省けます。そのため、情報をタイムリーに共有できる機能は、円滑なコミュニケーションの実現のために必須です。 (2)確認機能 次に、回覧板の閲覧や確認を記録できる「確認機能」も大切です。 情報を発信しただけでは、相手が内容を確認したかわかりません。そこで、確認機能があれば、社員が内容を読んだかをリアクションやチェック機能で記録でき、重要な通知が確実に伝わったことが把握できます。 たとえば、社内の緊急告知を発信したときに、確認ボタンがあると、閲覧していない社員を特定できます。そのため、社員の確認状況がわかる確認機能は、情報の伝達漏れを防ぐために欠かせない要素です。 (3)検索機能 次に、「検索機能」も、回覧板アプリの利用効率を高めるために重要です。 過去の回覧情報を確認したいとき、高性能な検索機能があると、キーワードや日時で過去の回覧情報をすぐに見つけられます。たとえば、以前共有されたプロジェクト資料や会議の要点をすぐに探し出せるので、社員は情報の振り返りに時間がかかりません。 たとえば、高性能な検索機能を備えている「ナレカン」のようなアプリでは、生成AIを活用した「自然言語検索」で、上司に質問するように知りたい情報を検索できます。 (4)編集・更新機能 最後に、内容の修正が簡単にできる「編集・更新機能」も重要な要素です。 一度公開した情報に変更が生じた場合に、再度同じ内容を回覧するのは手間です。編集機能があれば、公開後の内容もすぐに修正できるため、最新の情報が正確に共有されます。 たとえば、全社会議の日時変更が起こった場合、回覧板を作り直すことなく情報を修正でき、スピーディな情報共有が可能です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内回覧板を電子化するときの2つの注意点 ITツールを使って社内回覧板をデジタル化すれば、社内共有を効率化できます。一方で、電子回覧板を使い始めるときには以下の2つの注意点があります。 情報が流れにくいツールを選ぶ 社員の投稿が「チャット形式」や「タイムライン形式」で表示されるツールでは、投稿が増えるにつれて重要な情報が埋もれてしまいます。また、投稿内容を整理して保管できないので、過去の投稿を振り返るのに手間がかかるのです。 誰でも使いやすいツールを選ぶ 様々な業務に応用できる多機能な掲示板ツールもありますが、機能が多すぎたり使い方が複雑すぎると、社員にとって扱いづらく利用が定着しません。ツールの利用を社内に浸透させるために、「社員の誰でも簡単に使えるツール」を選びましょう。 以上のように、社内掲示板を電子化する場合は、「情報が流れないか」「誰でも簡単につかえるか」を必ず確認すべきです。たとえば、連絡事項を全メンバーにすばやく情報共有できて、シンプルな操作で使える「ナレカン」のようなアプリを選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリまとめ ここまで、社内や自治会・町内会で使えるおすすめの電子回覧板アプリ6選を中心に解説しました。 アプリを導入して回覧板をデジタル化することで、効率的な情報共有が実現します。ただし、電子回覧板アプリは情報が流れてしまったり、重要な情報が埋もれたりして、必要な情報を見つけづらくなる恐れがあるのです。 そこで、重要な情報を見やすく表示できるアプリを導入しましょう。また、情報を発信しただけでは誰が読んだのかを把握できないため、閲覧状況を簡単に確認できるアプリが最適です。 結論、導入すべきは、超高精度な検索機能で必要な情報に即アクセスでき、閲覧状況も把握しやすい「ナレカン」一択です。ナレカンは、専属担当者がアプリの導入から定着までを手厚くサポートするので、導入後も形骸化する心配がありません。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、回覧板をはじめとした情報をストレスなく社内共有しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年10月27日【無料あり】社内・自治会で使える便利なおすすめ電子回覧板アプリ6選!情報を共有する手段として「回覧板」が挙げられます。そして、今日では紙ではなく「電子回覧板アプリ」を使って、情報共有を効率化する企業や自治会が増えているのです。 一方、「電子回覧板アプリを導入したいが、どれが自社に最適なのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリ6選を中心にご紹介します。 電子回覧板のメリットやアプリの選定ポイントを知りたい 各アプリの特徴を比較して、導入するアプリを決めたい 情報が自然と目に入りやすい情報共有ツールを探している という方はこの記事を参考にすると、自社でストレスなく運用できる電子回覧板アプリが分かり、情報共有の負担を取り除けるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 電子回覧板アプリ・デジタル回覧板のメリットは?1.1 企業が電子回覧板を導入するメリット1.2 自治会・町内会が電子回覧板を導入するメリット2 電子回覧板アプリを選ぶポイント2.1 企業が電子回覧板アプリを選ぶポイント2.2 自治会・町内会が電子回覧板アプリを選ぶポイント3 無料あり|社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリ6選3.1 【ナレカン】回覧板の作成からやりとりまでできる社内向けアプリ3.2 【Stock】最も簡単に回覧板を共有できる社内・町内会向けアプリ3.3 【LINE WORKS】LINEのように使える社内向けチャットアプリ3.4 【デジタル回覧板】写真を撮るだけで回覧板を回せる自治会向けアプリ3.5 【回覧板アプリ】Microsoftツールと連携できる社内向けアプリ3.6 【NI Collabo 360】回覧板にコメントを残せる社内向けアプリ4 <比較表>社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリ一覧5 社内電子回覧板アプリに必要な4つの機能5.1 (1)情報共有機能5.2 (2)確認機能5.3 (3)検索機能5.4 (4)編集・更新機能6 社内回覧板を電子化するときの2つの注意点7 社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリまとめ 電子回覧板アプリ・デジタル回覧板のメリットは? 電子回覧板アプリとは、インターネット上で簡単に回覧板を作成・共有できるアプリのことです。以下では、物理的な書類のやりとりが不要な電子回覧板のメリットを「企業」「自治会・町内会」ごとに紹介します。 企業が電子回覧板を導入するメリット 電子回覧板アプリは、社内情報を正確かつ円滑に共有・確認するのに重要なツールです。 アプリを使えば、社員に手渡しで回覧板を回す手間が省けるため、情報共有におけるタイムラグを解消できます。また、一度共有された情報はいつでも何度でも確認できるので、認識齟齬が生じにくくなるのです。 さらに、最近では「メッセージ機能」が搭載された回覧板アプリが増えています。これにより、回覧板に関するやりとりや担当者への質問も、メールやチャットツールを使わずに電子回覧板で完結します。 自治会・町内会が電子回覧板を導入するメリット 自治会や町内会で回覧板アプリを導入すれば、情報は「閲覧するだけ」で済むため、回覧板を回す手間や順番待ちの時間が一切かかりません。 さらに、地域の回覧板でよく見られる「不在の場合、回覧板が止まる」「不特定多数の人が触れるため、感染症のリスクが気になる」といった問題も解決できるのです。 とくに、セキュリティ対策が万全な回覧板アプリを導入すれば、地域の方が安心して利用できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 電子回覧板アプリを選ぶポイント ここでは、電子回覧板アプリを選ぶポイントを「企業」「自治会・町内会」別で紹介します。電子回覧板アプリを導入しても、合わないサービスを選んでしまうとかえって情報共有が滞ってしまうので、以下の内容を軸に選定しましょう。 企業が電子回覧板アプリを選ぶポイント 企業が電子回覧板アプリを選ぶときには、以下3点を軸に選びましょう。 自社の企業規模に合ったアプリか 大手~中堅企業は、セキュリティ対策が強固で、数万人規模でもスムーズに利用できるか確認しましょう。とくに大規模の企業は、「回覧板をはじめ、あらゆる社内のお知らせを共有できるアプリ」を選ぶと、ほかの業務の情報管理としても活用できます。 情報を振り返りやすいか 社内回覧板の情報は、見返せないと認識齟齬を引き起こすので「簡単に目的の情報を振り返れる」アプリを選ぶことが重要です。また、高性能な検索機能が搭載されていれば、必要な情報にすぐアクセスできます。 誰が見たか分かるか とくに人数が多い大規模な企業の場合、回覧板を回すたびに閲覧状況を確認するのは手間がかかります。そこで、誰が回覧板を見たかまで特定できる「既読機能」や「リアクション機能」があると便利です。 たとえば、上記3点を満たした「ナレカン」のようなツールを選ぶと、大企業でもスムーズな情報共有が実現します。 自治会・町内会が電子回覧板アプリを選ぶポイント 自治会・町内会が電子回覧板アプリを選ぶときには、「あらゆる年代が簡単に使えるツールか」を重視して選定しましょう。 自治会・町内会員によってITツールへの抵抗感は異なるので、操作が難しい電子回覧板アプリを選ぶと使いこなせず放置されてしまいます。したがって、ITツールに馴染みがない人でも直感的に使えることが大前提として必要なのです。 たとえば、「Stock」のような60代~70代でも説明なしで使えるほど簡単なツールを選べば、ITに詳しくなくても直感的に操作でき、導入後も安心して使い続けられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 無料あり|社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリ6選 以下では、社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリを6つ紹介します。 回覧板で情報を共有していると、一人ずつ内容を確認する必要があり、手間と時間がかかるため、アプリを導入して回覧板をデジタル化しましょう。また、情報の伝達漏れを防ぐために「共有した内容を誰が読んだか確認できるか」も重視すべきです。 さらに、ITに詳しくない人がいる場合は、複雑な操作をしなくても直感的に情報を受け取れる仕組みが必要です。誰でも迷わず大事な内容を確認できるようにするために「情報が自然と目に入るような機能」は欠かせません。 結論、企業・自治体が導入すべきアプリは、一目で必要な情報を確認でき、既読機能で閲覧状況を把握しやすい「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」で作成した回覧板は、既読表示があるうえ、「コメント」でやり取りができるので円滑な情報共有が実現します。また、ホーム画面の「お知らせ」に確認すべき情報をまとめられるので、直感的に情報にアクセスできます。 【ナレカン】回覧板の作成からやりとりまでできる社内向けアプリ 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード <重要な情報を周知できるホーム画面> ここでは、重要な情報を周知するのに便利なナレカンの機能を紹介します。 以下の画像は、ナレカンのホーム画面です。ナレカンのホーム画面では「社内お知らせ」で社員に周知したい記事を上部に大きく表示したり、最新の記事やよく閲覧されている記事を確認したりできます。 「社内お知らせ」機能を活用することで、社員が見るべき情報が自然と目に入るようになるため、社内の情報共有の手間を軽減できるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Stock】最も簡単に回覧板を共有できる社内・町内会向けアプリ Stockは、中小規模の企業や自治会・町内会に最適な情報共有アプリです。 「Stock」の「ノート」には、テキストをはじめ画像やファイルも記録でき、画像には直接文字を書き込むことができます。そのため、単なる回覧板としての利用だけでなく、社内や地域の情報共有ツールとして活用できる点が特徴です。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 <Stockをおすすめするポイント> ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 <Stockの口コミ・評判> 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ(栃木SC) 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 <Stockの料金> フリープラン :無料 ビジネスプラン :500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数:5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【LINE WORKS】LINEのように使える社内向けチャットアプリ LINE WORKSの特徴 さまざまな業務に役立つ機能がある 「掲示板機能」の他にも「カレンダー機能」や「タスク機能」、プライベート版LINEにもあるような「出欠確認」などの機能を使えます。そのため、回覧板としてだけでなく、あらゆる業務に活用可能です。 メッセージが送りやすい プライベート版LINEと同じような使用感のため、気軽にやりとりできます。また、グループトークでは「ノート」や「フォルダ」機能を活用して、円滑な情報共有が可能です。 LINE WORKSの機能・使用感 メンバーに回覧板の確認を促せる 「掲示板」で作成した回覧板を必読表示にすると、掲示板のトップページ上部に固定されるので、メンバーに確認されやすくなります。 回覧板へのコメントもできる 掲示板の画面下部にある「コメントを許可」にチェックを入れれば、回覧板に対するメンバーの声を受け取れます。そのため、掲示した情報に対する「質問事項」をその場で解決できるのです。 LINE WORKSの注意点 情報が流れやすい LINE WORKSはチャットツールなので、共有事項が多いと情報が流れて見つけづらくなる恐れがあります。そのため、あとから情報を振り返りにくかったり、重要な情報を見逃してしまったりする点に注意が必要です。 アプリ版ではダウンロードできないときがある ユーザーの口コミでは「時々、少し重たい添付など(PDF)がダウンロードできない、その場合はブラウザ版で開くと解消される」との声もあります。(参考:ITreview) LINE WORKSの料金体系 フリー:0円 スタンダード:540円/ユーザー/月(月払い) アドバンスト:960円/ユーザー/月(月払い) LINE WORKSの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【デジタル回覧板】写真を撮るだけで回覧板を回せる自治会向けアプリ デジタル回覧板の特徴 写真を撮ってすぐに回覧板を回せる 配布物を写真に撮ってすぐに共有する仕組みなので、紙の回覧板のように次の人へ手渡ししたり、順番待ちをしたりする必要はありません。 配信対象をグループ分けできる 全員への一斉配信はもちろん、対象者をグループ分けして、特定のメンバーに向けて情報を配信することもできます。 デジタル回覧板の機能 画像引用:DX推進支援アプリ「デジタル回覧板」リーフレット わずかな工数で回覧板を送れる 回覧板を写真に撮り、上図のように「タイトル、組織名、公開期間」を設定するだけで、すぐに情報を回覧できます。 回覧板の配布通知が来る 回覧板が配布されると、端末に配布通知が来るので確認漏れを防げます。 デジタル回覧板の注意点 行政(自治会)向けのツール 回覧板機能の他にも「防災放送の配信機能」や「避難場所の確認機能」が備えられています。そのため、ビジネスでの利用もできますが、地域の回覧板としての利用が想定されたツールという点に注意しましょう。 アプリ上で回覧板の作成はできない デジタル回覧板は、紙の書類を撮影することを前提に作られているので、文章を直接入力したり、情報をツールへ蓄積したりするには向いていない可能性があります。 デジタル回覧板の料金体系 料金の詳細はお問い合わせください。 デジタル回覧板の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【回覧板アプリ】Microsoftツールと連携できる社内向けアプリ 回覧板アプリの特徴 確認状況を表示できる 登録した回覧内容に対する、確認状況(%)の表示が出来ます。 回覧板を一覧表示できる アプリに登録した回覧板を一覧表示できるので、目的の情報を見つけやすいです。 回覧板アプリの機能 回覧期限を設定できる すぐに確認してほしい内容がある場合は、回覧期限を設定できるため安心です。 重要度を設定できる ステータスを「重要」に設定すれば、重要な情報を太字で一覧表示できます。そのため、必ず確認してほしい情報の確認漏れを減らせるのです。 回覧板アプリの注意点 回覧者を最大5名までしか指定できない 回覧者の指定を最大5名までしか指定できないため、大規模チームでは使いづらい恐れがあります。 Microsoft SharePointをインストールしなければ使えない 回覧板アプリを利用するには、有料ツールのMicrosoft SharePointをインストールしなければなりません。 回覧板アプリの料金体系 「回覧板アプリ」はMicrosoft SharePointをインストールすれば無料で使えます。以下は、他のアプリも使えるMicrosoft 365の一般法人向けプランを含んだ、Microsoft SharePointの料金体系です。各プランの詳細はSharePoint Onlineの料金ページを参照してください。 SharePoint(プラン 1):749円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Standard (Teams なし):1,536円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月 回覧板アプリの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【NI Collabo 360】回覧板にコメントを残せる社内向けアプリ NI Collabo 360の特徴 情報共有だけでなくワークフローにも利用できる 社内回覧板だけでなく、経費精算や稟議に関するワークフローにも利用できます。 多言語に対応している 日本語、英語以外にも、各企業で言語の辞書登録や設定が可能です。また、タイムゾーンの切り替えもできるため、グローバルな事業にも使えます。 NI Collabo 360の機能 確認状況が一覧表示される 画像引用:NI Collabo 360|回覧板 投稿した回覧板を「誰がいつ確認したのか」が一覧表示されるので、情報の伝え漏れを防げます。また、閲覧者は一言コメントを残せます。 社内SNS機能 画像引用:NI Collabo 360|UP! 「UP!」は、NI Collabo 360における社内SNSです。この機能を使って社内情報を気軽に共有することもできますが、チャット形式なので情報が流れやすい点に注意が必要です。 NI Collabo 360の注意点 個々の機能の専門性はない 一部のユーザーからは「様々な機能があり大変便利ですが、特化したサービス、システムには劣り、痒いところに手が届かないことも事実です」との声もあります。(参考:ITreview) ワークフローの設定が難しい 一部のユーザーからは「ワークフローのフロー図の作成が難しく、何度かテストを実施し対応をしています」という声が見られます。(参考:ITreview) NI Collabo 360の料金体系 クラウドタイプ:328円~/ユーザー/月 ライセンスタイプ:58,000円~/10ユーザー NI Collabo 360の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ <比較表>社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリ一覧 以下は、おすすめの電子回覧板アプリ6選の比較表です。(左右にスクロール可) ナレカン【一番おすすめ】 Stock【おすすめ】 LINE WORKS デジタル回覧板 回覧板アプリ NI Collabo 360 特徴 回覧板の作成からやりとりまでできる社内向けアプリ 最も簡単に回覧板を作成・共有できる・自治会向けアプリ LINEのように使える社内向けチャットアプリ 写真を撮るだけで回覧板を回せる自治会向けアプリ Microsoftツールと連携できる社内向けアプリ 回覧板にコメントを残せる社内向けアプリ おすすめの利用用途 ・社内利用(大手~中堅企業向け) ・社内利用(中小規模企業向け) ・自治会利用 ・社内利用 ・自治会利用 ・社内利用(小規模企業向け) ・社内利用 シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単 シンプルで簡単 多機能 シンプルで簡単 多機能 多機能 メッセージ機能 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】※ただし、音声チャットでのやりとり 【×】 【×】※閲覧者がコメントを残すことは可 既読機能 【〇】 【×】 【〇】 【×】 【〇】 【〇】 注意点 法人利用が前提 5名以上での利用が前提 大切な情報が流れやすい アプリ本体では回覧板を作成できない(紙の書類を撮影することが前提) 回覧者は最大5名までしか指定できない 個々の機能の専門性はない 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料プランあり ・有料プランは500円~/ユーザー/月 ・無料プランあり ・有料プランは540円~/ユーザー/月(月払い) ・要問い合わせ ・無料プランあり ・ただし、SharePoint(749円/ユーザー/月~)の導入が必須 ・無料プランなし ・有料プランは328円/ユーザー/月~ 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「LINE WORKS」の詳細はこちら 「デジタル回覧板」の詳細はこちら 「回覧板アプリ」の詳細はこちら 「NI Collabo 360」の詳細はこちら 上記のように、電子回覧板アプリによって機能性が異なるので「必要な機能に過不足ないアプリ」を選定しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内電子回覧板アプリに必要な4つの機能 ここでは、社内電子回覧板アプリに必要な4つの機能を解説します。以下の機能を備えたアプリを選べば、情報共有の負担を迅速に解消できます。 (1)情報共有機能 まず、社内電子回覧板には「情報共有機能」が欠かせません。 電子回覧板の本来の目的は、全社員に必要な情報を正確に、すばやく共有することです。情報共有機能があれば、社内情報が一貫して伝えられるので、伝達漏れを防げます。 たとえば、部署内の会議資料や社内イベントの案内など、関係者がリアルタイムで情報を確認しやすくなることで、不要な連絡の手間が省けます。そのため、情報をタイムリーに共有できる機能は、円滑なコミュニケーションの実現のために必須です。 (2)確認機能 次に、回覧板の閲覧や確認を記録できる「確認機能」も大切です。 情報を発信しただけでは、相手が内容を確認したかわかりません。そこで、確認機能があれば、社員が内容を読んだかをリアクションやチェック機能で記録でき、重要な通知が確実に伝わったことが把握できます。 たとえば、社内の緊急告知を発信したときに、確認ボタンがあると、閲覧していない社員を特定できます。そのため、社員の確認状況がわかる確認機能は、情報の伝達漏れを防ぐために欠かせない要素です。 (3)検索機能 次に、「検索機能」も、回覧板アプリの利用効率を高めるために重要です。 過去の回覧情報を確認したいとき、高性能な検索機能があると、キーワードや日時で過去の回覧情報をすぐに見つけられます。たとえば、以前共有されたプロジェクト資料や会議の要点をすぐに探し出せるので、社員は情報の振り返りに時間がかかりません。 たとえば、高性能な検索機能を備えている「ナレカン」のようなアプリでは、生成AIを活用した「自然言語検索」で、上司に質問するように知りたい情報を検索できます。 (4)編集・更新機能 最後に、内容の修正が簡単にできる「編集・更新機能」も重要な要素です。 一度公開した情報に変更が生じた場合に、再度同じ内容を回覧するのは手間です。編集機能があれば、公開後の内容もすぐに修正できるため、最新の情報が正確に共有されます。 たとえば、全社会議の日時変更が起こった場合、回覧板を作り直すことなく情報を修正でき、スピーディな情報共有が可能です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内回覧板を電子化するときの2つの注意点 ITツールを使って社内回覧板をデジタル化すれば、社内共有を効率化できます。一方で、電子回覧板を使い始めるときには以下の2つの注意点があります。 情報が流れにくいツールを選ぶ 社員の投稿が「チャット形式」や「タイムライン形式」で表示されるツールでは、投稿が増えるにつれて重要な情報が埋もれてしまいます。また、投稿内容を整理して保管できないので、過去の投稿を振り返るのに手間がかかるのです。 誰でも使いやすいツールを選ぶ 様々な業務に応用できる多機能な掲示板ツールもありますが、機能が多すぎたり使い方が複雑すぎると、社員にとって扱いづらく利用が定着しません。ツールの利用を社内に浸透させるために、「社員の誰でも簡単に使えるツール」を選びましょう。 以上のように、社内掲示板を電子化する場合は、「情報が流れないか」「誰でも簡単につかえるか」を必ず確認すべきです。たとえば、連絡事項を全メンバーにすばやく情報共有できて、シンプルな操作で使える「ナレカン」のようなアプリを選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内・自治会で使えるおすすめの電子回覧板アプリまとめ ここまで、社内や自治会・町内会で使えるおすすめの電子回覧板アプリ6選を中心に解説しました。 アプリを導入して回覧板をデジタル化することで、効率的な情報共有が実現します。ただし、電子回覧板アプリは情報が流れてしまったり、重要な情報が埋もれたりして、必要な情報を見つけづらくなる恐れがあるのです。 そこで、重要な情報を見やすく表示できるアプリを導入しましょう。また、情報を発信しただけでは誰が読んだのかを把握できないため、閲覧状況を簡単に確認できるアプリが最適です。 結論、導入すべきは、超高精度な検索機能で必要な情報に即アクセスでき、閲覧状況も把握しやすい「ナレカン」一択です。ナレカンは、専属担当者がアプリの導入から定着までを手厚くサポートするので、導入後も形骸化する心配がありません。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、回覧板をはじめとした情報をストレスなく社内共有しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
最新の投稿
おすすめ記事

