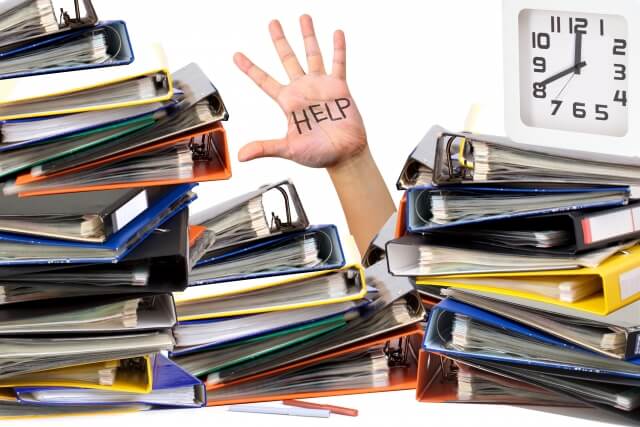ビックデータをビジネスで活用するには?成功事例や企業のメリットも解説

近年、情報化社会は加速しており、社内で管理すべき「データ」は膨大に増えています。一方で、データを上手く活用すれば企業の利益向上につながります。
とはいえ、「アナログな方法に慣れており、データ活用の明確なイメージが掴めない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、データを活用するメリットや成功事例を中心に解説します。
- 社内データがより活用されるような職場環境を作りたい
- 社内のデータを上手く活用している企業事例を参考にしたい
- 社内に大量にあるデータを簡単に管理・活用できるツールを探している
という方はこの記事を参考にすると、企業でのデータ活用法が分かり、自社の業務を効率化が可能になります。
目次
ビジネスにおけるビックデータとは
ビッグデータとは、巨大で多種多様なデータ群のことを言います。明確な定義はないものの、以下「5つの特性」を有しています。
| Volume(量) | 従来のシステムでは処理するのが難しいほど、膨大なデータ量 |
|---|---|
| Velocity(速度) | データの生成・処理・分析の速度が速く、リアルタイムで更新されるスピード感 |
| Variety(多様性) | 文書・画像・音声・動画のほか検索履歴など、さまざまなデータの種類 |
| Veracity(正確性) | 誤ったデータを適切に管理し、正確性や信頼性が担保された状態 |
| Value(価値) | 含有するデータを活用し、企業に利益や価値を与えられる状態 |
このような特徴のあるビッグデータを上手く活用できれば、企業が受ける恩恵は多岐に渡ります。ただし、すべての情報管理ツールがビックデータを適当に管理・活用できるわけではないので、ツール選びは慎重におこないましょう。
企業がビックデータ活用をする4つのメリット
ここでは、企業がデータ活用をする4つのメリットを解説します。これまで、アナログな方法で情報を扱っていた企業の担当者は必見です。
(1)現状を正確に把握できる
データ活用のメリットの1つ目に、現状を正確に把握できる点が挙げられます。
紙や口頭でやりとりをしていると、情報が属人化されるので企業の現状把握が困難になります。しかし、データとして管理すれば定量的な視点を持てるため、現状を正確に把握できるのです。
また、現状を分析できれば「新規顧客を獲得するにはどうすべきか」なども議論しやすくなるので、企業の売り上げアップにも大きく貢献します。
(2)コストを削減できる
データ活用のメリットの2つ目に、コストを削減できるメリットがあります。
たとえば、過去のデータから経費の推移などを算出すれば、無駄な業務や出費が一目で分かります。また、仕入れや人件費など、将来的なコストへの対策もしやすくなるのです。
以上のことから、データを活用すればコストの大幅な削減につながると言えます。
(3)ビジネスのアイデアが得られる
データ活用のメリットの3つ目に、ビジネスのアイデアが得られるメリットがあります。
自社のデータを活用することで、顧客の行動や市場の動向をより深く理解できます。そのため、膨大なデータから潜在ニーズを把握し、革新的な商品やサービスの開発が可能になるでしょ。
つまり、データ活用は新たなビジネスチャンスの創出が期待できるのです。
(4)仕事のスピードが上がる
データ活用のメリットの4つ目に、仕事のスピードが向上するのもデータ活用のメリットです。
企業の現状がデータとして分かれば、定量的な分析ができるので意思決定のスピードが向上します。さらに、社員の勘や経験といった定性的な情報も、データ化すれば逐一本人に聞く必要がありません。
ただし、蓄積したデータをすぐに探し出せなければ、次第に活用されなくなる恐れがあるため注意です。したがって、「記事」に残した情報を高精度検索できる「ナレカン」のようなツールが適しています。
企業が抱えるビックデータの課題と解決策
ビックデータは、企業が上手く活用できれば貴重な情報源になりますが、必ずしもプラスの面とは限りません。ここでは、企業が抱えるビックデータの課題と解決策について、二つほど解説します。
管理や維持にコストがかさむ
一つ目に、管理や維持にコストがかさむことが課題として挙げられます。
ビックデータのような膨大な量のデータを保存・活用できるシステムを自社で構築するには、時間的・人的に費用が掛かります。そのため、情報管理に特化した他社が運用しているツールを活用するのがおすすめです。
外部のクラウドツールを活用すれば、サーバー機器の購入などの初期費用が不要です。また、システムの管理・維持やセキュリティ対策を社内で行う必要がないため、人件費や維持費も削減できます。
データが陳腐化しやすい
二つ目に、データの取捨選択が難しいという課題もあります。
ただ情報を蓄積していくだけでは、陳腐化した情報まで残り続けてしまうので、せっかく時間をかけて記載した情報も有効活用しきれません。そのため、定期的に情報を更新したり、不要なデータを整理したりして、必要なデータだけを残し続けましょう。
そこで、似た内容の文章を指摘してくれる「重複判定機能」や一定期間、閲覧されていないナレッジを検出できる「断捨離機能」が備わった「ナレカン」のようなツールがあれば、使われ続ける有益な情報のみをツール上に残せます。
ビッグデータを上手く活用している企業事例6選
以下では、データを有効活用している企業事例を6つご紹介します。自社でどのようにデータを活用すべきか悩む方は、具体的なイメージを持てるので必見です。
事例1|城崎温泉

画像引用:城崎温泉のトップページ
城崎温泉は、きのさき温泉観光協会が運営する観光施設です。
当社では、紙の外湯券がない観光客は外湯に入浴できず、送客の機会を失っている課題がありました。そこで、スマートフォンのICカード機能を使った外湯券を発行したのです。
その結果、複数枚の外湯券を持ち運ぶ手間が省けて客数が増えただけでなく、ICカードの利用履歴をもとに定量的な分析もできるようになりました。
事例2|ダイドードリンコ株式会社

画像引用:ダイドードリンコ株式会社のトップページ
ダイドードリンコ株式会社は、自動販売機を軸にサービスを展開する飲料メーカーです。
当社では自動販売機でドリンクを買うときに、顧客はどこに視線を向けるのかを調べるため「アイトラッキング」という装置を活用しました。その結果、下段を見る傾向が強いというデータを得られたのです。
また、パッケージに関しても、顧客は左上を見てから右下を見ることがデータから分かりました。そのため、商品パッケージや陳列の仕方を変えたところ、売り上げの2割アップに成功したのです。
事例3|株式会社カイエンシステム開発

株式会社カイエンシステム開発は、ポケットタクシー営業とシステム請負開発事業を展開する企業です。
当社では、乗務員不足と配車センターの負担を軽減して、コストを抑えるために「ポケットタクシー」というアプリを開発しました。その結果、GPSデータが蓄積されて「どの時間帯にどの場所が混んでいるのか」が簡単に分かるようになったのです。
また、データから”一番近くを走っている乗務員”を割り出せるようになったので、配車センターのコスト削減も実現しました。
事例4|岡山大学

画像引用:岡山大学のトップページ
岡山大学は、岡山県にキャンパスを持つ国立大学です。
当大学では、eラーニングシステムで学生にアンケートをさせて、自主学習態度と成績の相関関係を可視化しました。また、アンケートの結果で学習が不十分だと分かった学生には、個別でフィードバックを実施したのです。
その結果、フィードバックの回数が自主学習態度と成績に比例することが分かり、より良いアプローチへのきっかけにもなりました。
事例5|大阪ガス株式会社

画像引用:大阪ガス株式会社のトップページ
大阪ガス株式会社は、近畿地方を販売エリアとするガス会社です。
同社では、長年のガス設備稼働データと独自分析で故障予測システムを構築しました。これにより交換が必要な部品の自動抽出や、ガス設備が壊れる前に修理する「予防保全活動」が可能となったのです。
その結果、一度の訪問で修理が完了するケースが増え、業務効率と顧客満足度が向上しました。
事例6|株式会社TGK

画像引用:株式会社TGKのトップページ
株式会社TGKは、オムライス専門店「神田たまごけん」を運営する企業です。
当社ではグループチャットの「LINE」でデータを扱っていましたが、チャット形式ゆえに情報が次々に流れてしまい、データを活用できない課題がありました。そこで、あらゆる情報を「ノート」で確実に蓄積できる「Stock」を導入したのです。
その結果、営業日報やシフト情報といったデータへすぐにアクセスできるようになり、情報管理のストレスが解消されました。また、カテゴリに応じて「フォルダ」で振り分けているので、情報が入り乱れることもなくなっています。
【ビジネスパーソン必見】企業のデータ管理・活用に最適なツール
以下では、企業のデータ管理・活用に最適なツールをご紹介します。
営業活動で得たデータを活用すれば、スムーズな意思決定やコスト削減につながります。しかし、情報がアナログで管理されていたり、メンバーが属人的にデータを保持したりしていては、蓄積されたデータも十分に活用されません。
そのため、「あらゆる情報を一元管理できるツール」にデータを集約して、必要な情報をすぐに探し出せるようにしましょう。ただし、収集したデータには機密性の高い情報が含まれるため、「誰がどの情報にアクセスできるか」を細かく設定できるツールを選ぶことが大切です。
結論、企業のデータ管理・活用には、必要な情報を瞬時に探しだせて、かつチームやメンバーごとにアクセス権を設定できるツール「ナレカン」が最適です。
ナレカンは「記事」にファイルやテキストで自由に情報をまとめられるうえ、生成AIを活用した「超高精度の検索機能」で目的の情報に即アクセスできます。また、データの閲覧権限を設定でき、生成AIは検索内容を学習しないので、外部に漏れる心配もありません。
社内のデータを最も簡単に管理・活用できるツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
<ナレカンをおすすめするポイント>
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。
ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
【6ステップ】データを活用する手順
企業でデータを活用するときは、以下の手順を踏みます。
- 目標の設定
- 分析課題の設定
- データ収集
- 可視化
- データ分析
- 解決モデルの作成と効果検証
「売上の向上」や「新規事業の立案」など、明確な目標を設定します。
問題点を抽出するのはもちろん、原因を特定して解決策まで導きましょう。
目標と分析課題をもとに必要なデータを収集します。すでに自社に格納している情報だけでなく、新しい情報も過不足なく集めましょう。
収集したデータをグラフや表で可視化します。視覚的に分かりやすくすれば複雑なデータでも分析がスムーズになります。
可視化したデータをもとに、規則性や異常値を見つけます。規則性が分かれば将来的な予測ができ、異常値が見つかれば分析のヒントにもつなげられます。
データ分析の結果をもとに、実際に解決モデルを作成します。また、予実差をなくすために、作成後は定期的に効果検証をしましょう。
上記の手順を踏めば、誰でも有効なデータを蓄積・活用できます。また、データはいつでもアクセスできるように分かりやすく管理しておくのが大切です。
企業におけるデータ活用のメリット・成功事例まとめ
これまで、企業がデータ活用するメリットや成功事例を中心にご紹介しました。
企業がデータを活用すれば、現状を正確に把握できるだけでなく、無駄な出費も分かるのでコストの削減にもつながります。そのため「社内の情報を一元管理が可能なツール」を導入し、いつでもデータを活用できる環境を整備しましょう。
ただし、企業の収集したデータには機密性の高い情報が含まれるため、取り扱いには注意が必要です。そこで、アクセスできる情報を細かく設定できるツールを選択しましょう。
結論、自社が導入すべきは、あらゆるデータを高セキュアな環境で管理でき、必要な情報にすぐにアクセスできるツール「ナレカン」一択です。
無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、企業のデータ活用の悩みを解消しましょう。