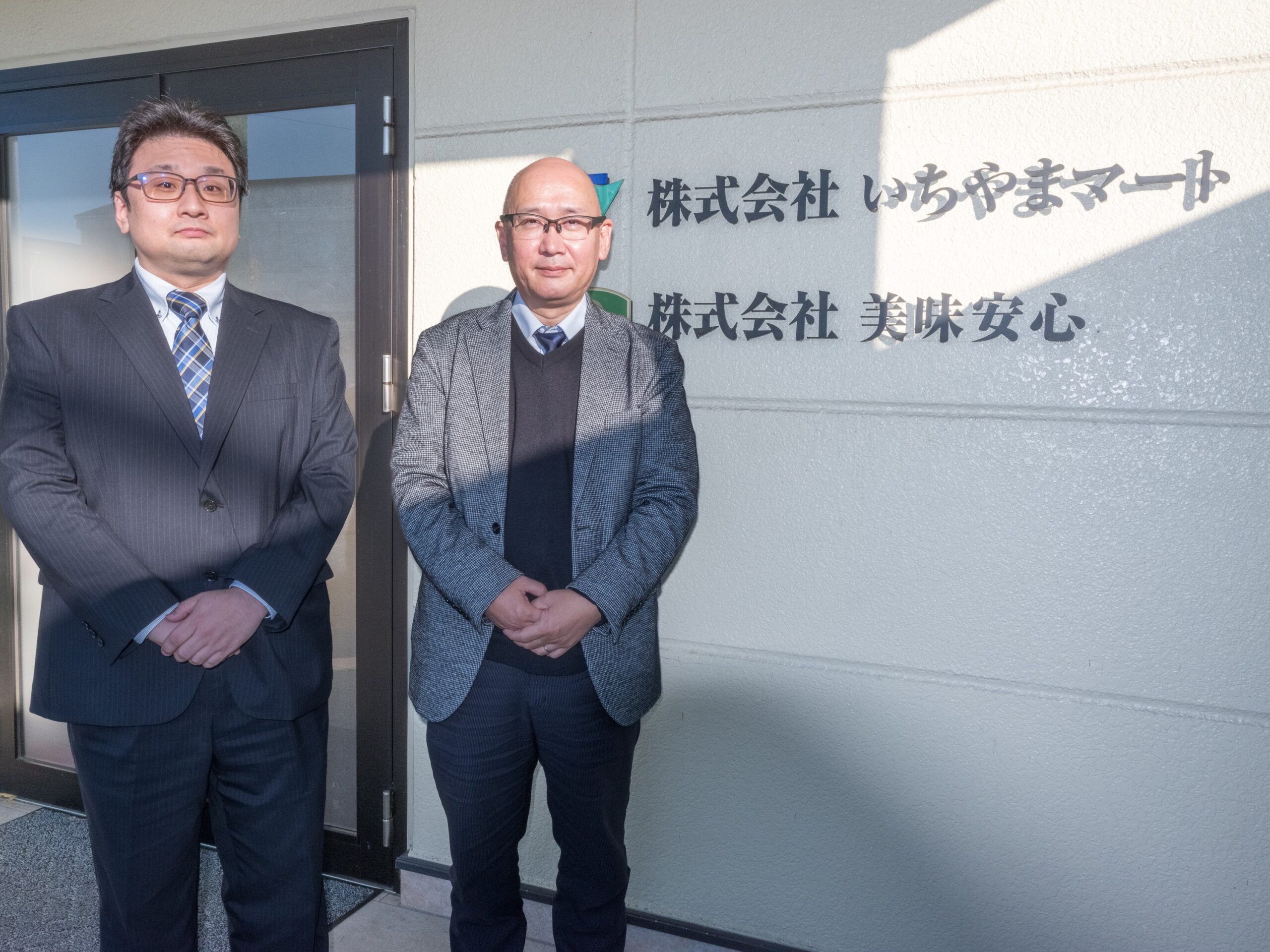ナレカンを導入し、拠点間のナレッジを共有できる体制にしたことで、情報検索にかかる時間が最大90%削減されました!

目次
「ナレカンを導入し、拠点間のナレッジを共有できる体制にしたことで、情報検索にかかる時間が最大90%削減されました!」

全国の製造拠点間での人事労務情報の共有に課題を感じていた古河電気工業(株) 平塚事業所 総務課様。
古河電気工業(株) 平塚事業所 総務課
業種:非鉄金属製造業
従業員:古河電気工業(単体) 約4,400名
ナレカンを活用して、属人的な情報管理やナレッジの散在を解消した平塚事業所 総務課の宇都宮様・畠山様・伊藤様に、ナレカン導入の背景や、実際の活用方法についてお話をお伺いしました。
“情報通信・エネルギーインフラを支える非鉄金属メーカーの現場を支える総務チーム”
— 貴社の事業内容について教えてください。
宇都宮様:
「非鉄金属の製造業です。具体的には、光ファイバーなどの情報通信関連製品や電力ケーブルなどのエネルギー分野のインフラを支える製品を提供しています。」
— 皆様のご担当業務について教えてください。
宇都宮様:
「我々は平塚事業所の総務課で、庶務・厚生業務のほか、人事労務業務も担っています。
私は総務課の課長として全体の統括を担当しています。人事労務関係の実務は畠山と伊藤が担当しています。」
“散在する情報を一元化し、誰もが迷わずナレッジにたどり着ける環境を実現できました”
— ナレカン導入前に感じていた課題はどのようなものでしたか。
畠山様:
「大きく以下の3つの課題がありました。
- 情報が分散し、検索に手間取る
- ナレッジ習得に時間を要する
- 拠点間でイレギュラー事例を共有できていない
従業員からの問い合わせが多い中で、回答に必要な情報がTeams、メール、共有フォルダなどに散在していて、探すのに時間がかかっていました。
人事労務の知識は専門的かつ複雑であるため、新入社員やキャリア採用の社員が業務の中で疑問を抱く場面が少なくありません。しかし、そうした際に忙しい上司や先輩に声をかけづらく、必要な情報にすぐアクセスできていませんでした。
複数拠点にそれぞれに人事労務担当が配置されていますが、『判断が難しいグレーゾーンの対応』は個別対応にとどまり、他拠点へ展開されていませんでした。結果として、イレギュラーが発生するたびにそれぞれでゼロから判断を検討する非効率さがありました。」
— ナレカン導入のきっかけについて教えてください。
畠山様:
「2024年の4月にその年の『チャレンジ目標』として、『DXを活用したナレッジ共有基盤の構築』を掲げたのが始まりです。
もともと人事労務業務の効率化に課題を感じており、情報への“アクセスのしづらさ”を何とかしたいと考えていました。」
宇都宮様:
「目標を立ててもらった後、私自身もAIやナレッジマネジメントの本を8冊ほど読んで勉強しました。
要件定義を行い、『FAQ的にナレッジを検索できる』『誰でも使いやすいUI』という条件で13社を比較検討した結果、ナレカンが最もフィットしていると感じ導入を決定しました。」
— 13社からナレカンにした決め手は何でしたか?
畠山様:
「決め手は、ナレカンに搭載されている『RAG機能(あらかじめ登録されたナレッジデータからAIが検索して、それをもとに自然な回答を生成してくれる仕組み)』のクオリティとユーザー体験です。
ラフに質問するだけで、事前に登録されたナレッジの中から適切な情報をピックアップしてくれます。この『検索精度の高さと手軽さ』が、非常に魅力的だと感じました。
実際に使い始めてからも、『どこに何があるか』が一目でわかるので、必要なナレッジにすぐアクセスできるのは大きなメリットです。
さらに、自分でイレギュラー事例などを登録する際も、記事作成の操作がシンプルで、特別なレクチャーがなくても直感的に使える点は、現場にとって非常にありがたいポイントでした。」

“情報がナレカンに自然と集まるようになり、業務パフォーマンスが格段に向上しました”
— 実際の活用方法について教えてください。
宇都宮様:
「ナレカンは、他の事業所を含めた人事労務担当者約10名と、本社の人事労務担当者約50名、あわせて約60名で活用しています。」
畠山様:
「管理しているナレッジの内容は主に、人事労務関連の情報と庶務・厚生関連の情報です。具体的には以下のような情報を蓄積しています。
- 就業規則・給与規則などの社内規程
- 各拠点での対応事例
- 庶務・厚生関連の実務事例
- 他部門理解を促す業務資料
それぞれのカテゴリごとに、「基礎知識」と「イレギュラー事例」の2つに分類してフォルダを作成しています。」
宇都宮様:
「特に、基礎知識だけでは判断が難しいイレギュラーケースの背景や対応内容を共有することで、同じような事例が発生した際の参考になっています。
例えば、『社員寮の利用条件を通勤2時間以上から1.5時間以上に緩和した』ケースでは、その検討背景や理由をナレカンに記録しておくことで、制度を見直す時の判断根拠として活用できます。
また、ナレカンに情報を集約したことで、新入社員であってもAI検索機能を活用して自ら情報を探し、問い合わせ対応ができるようになった点も大きな効果のひとつです。」
— ナレカン導入後、どのような変化がありましたか。
畠山様:
「情報を検索する時間が大幅に短縮されました。
ナレカン導入前は、必要な情報を探すために長いときはメールやTeamsを30分〜1時間も確認し、それでも見つからないということが度々ありました。
しかし、導入後はナレカンを検索するだけで、欲しい情報にすぐアクセスできるようになりました。」
宇都宮様:
「加えて、ナレッジを『後世に残す』文化が自然に生まれました。
『これ、ナレカンに入れておいて』と声をかけるだけで、自然と情報を共有する仕組みがあるので、ナレッジを残すことが当たり前になり、組織全体の情報資産が着実に積み上がっています。」
伊藤様:
「現場でも、検索のしやすさと回答の即時性から、『ナレカンにまずは聞いてみよう』という文化が定着しました。
その結果、『ナレッジ登録→検索→活用→新たなナレッジを登録』という、理想的なナレッジ活用のサイクルが自然と回っています。
例えば、問い合わせ対応で『賞与の支給日は?』といった質問が来た際、ナレカンにキーワードを入力するだけで即座に回答が見つかります。新入社員やキャリア採用の社員でも迷うことなく対応できる環境が整いました。」
畠山様:
「さらに、各拠点で発生したイレギュラーな対応事例を、他拠点でも簡単に参照できるようになったことで、人事労務担当者の間での横展開・情報共有がスムーズになっています。
副次的な効果として、対応事例をナレッジとして登録する過程で、自分の判断や対応の背景を振り返ることができ、自身の理解がより深まるというメリットも生まれています。
また、ナレカンは現在進行形で機能アップデートが非常に活発である点も魅力ですね。機能の改善や新しい機能が次々と実装されていて、今後、より便利になっていくと思います。」
— ナレカン導入後、社内展開はどのように進められましたか。

畠山様:
「振り返ってみても、立ち上げ時に大きな苦労はほとんどありませんでした。
というのも、ナレカンの導入にあたっては、簡単な操作説明やフォローのみでナレッジ登録作業をスタートすることができたからです。
とくに、ナレカンの操作感は、Wordなどの一般的なツールとほとんど変わらず、ユーザーが直感的に扱える設計になっているのでスムーズに導入が進みました。
また、テンプレートを活用して『この項目に沿って書いてください』とフォーマットの型を提示できるので、指示や依頼も非常に簡単でした。」
宇都宮様:
「実際、導入初日に1つ記事を公開してみて『これは簡単にできる』と手応えを感じたので、その日のうちに20〜30個ほどの『記事タイトル』だけを先に作成し、関係者に割り振って、期日までの執筆を依頼しました。
現在では、トータルで600弱の記事が登録されており、人事労務業務に必要なナレッジは一通りカバーできていると感じています。権限設定や新規ユーザーの招待もスムーズなため、スピーディーに社内展開が進みました。」
畠山様:
「今では、新入社員もどんどん記事を作成してくれています。
ナレカンのホーム画面にランキングが出ると思うのですが、積極的にナレッジを活用しているメンバーが分かるので、管理側としても嬉しいですね。コミュニケーションのきっかけにもなっています。」
“我々の要望に真摯に向き合うサポートと現場の声を反映する頻繁な機能アップデートによって、想定以上の成果をもたらしました”
— ナレカンのサポート体制はいかがですか。
宇都宮様:
「メールのレスポンスも早く、内容も丁寧で、全く不満はありません。とても快適にサポートを受けられています。
月に1回の定例会では、新機能のリリース情報を共有いただいたり、こちらからの要望や相談に耳を傾けていただいたりと、非常にタイムリーかつ丁寧に対応していただいています。
実際、こちらから出したフィードバックや要望が、新機能という形で反映されていると感じる場面が多くあり、『ちゃんと現場の声を聞いてくれているな』という安心感があります。
直近では、『ユーザーごとに登録されるナレッジの正確性をどう担保するか』という課題について相談していたのですが、まさにその解決につながる『承認フロー機能』がリリースされました。
今後はこの機能も活用して、さらに信頼性の高いナレッジ運用を進めていきたいと考えています。」
— 今後の展望などはありますか。

畠山様:
「弊社ではもともと、情報収集の効率化や、新入社員・キャリア採用者の教育体制に課題を感じており、その解決の手段としてナレカンを活用し始めました。
しかし、実際に導入してみると、当初想定していた課題の解決にとどまらず、突発的な異動者や退職者への対応が柔軟にできるようになりました。
さらに、情報収集の効率化によって本来の人事業務により多くの時間を割けるようになり、業務の品質向上にもつながるなど、想定以上の効果を実感しています。」
宇都宮様:
「私も、ナレカンには非常に満足しています。
RAGの検索精度や、ナレッジの視認性の高さといった基本的なスペックの良さに加えて、次々とリリースされる新機能が“現場の課題に目を向けている”と感じられる点にも好感が持てますね。
『“こういう困りごとを解決したい”という発想から作られているんだな』と思える機能が多く、実際に業務でも役立っています。
また、ナレッジデータベースというものは『放り込んで終わり』ではなく、常に更新が必要であることを前提とした設計になっているところもナレカンの強みだと感じています。
古いナレッジの通知や、類似記事の検知なども含めて、更新しやすい仕組みが整っているので非常に助かっています。
こちらからも積極的に要望を出しながら、ナレカンをもっと良いツールへと進化させていきたいと思っています。そうした“ユーザーとのサイクルが見える”という点も、他にはない魅力のひとつだと思います。」
”業務が属人化して困っているすべての企業は、一度ナレカンを使ってみていただきたいです”
— ナレカンをどんな方におすすめしたいですか。
畠山様:
「ナレカンは、『知識が属人化してしまっている』『情報にアクセスするのに時間がかかっている』と感じているすべての企業におすすめです。
特に、人事・労務・総務といった管理部門では、業務効率の向上や情報検索性の改善に大きく貢献できるはずです。
『情報を探す時間がもったいない』『イレギュラー事例を属人化させたくない』といった課題をお持ちの方には、ぜひ一度使ってみていただきたいです。」
— 最後に、一言メッセージをお願いします。
畠山様:
「人事労務業務に従事して今年で6年目になりますが、業務を進める中で、自分一人の知識や経験だけでは対応しきれないと感じる場面が多くありました。
その点、ナレカンは他の拠点で働く人事労務担当者の知識や経験もインプットできるため、人事部門全体の知見を自分の“武器”として活用できることが大きな強みだと感じています。」
伊藤様:
「私は現在入社3年目で、ナレカンを使い始めたのは2年目からでした。当時は求められる知識の幅が広く、必要な情報にたどり着くまで時間がかかり、労働時間が長くなることもありました。
ですが、ナレカンを導入してからは、就業規則や給与規程などが網羅され、すぐに事例や知識にアクセスできるようになり、業務の効率が格段に向上しました。
また、ナレカンは操作も非常にシンプルで使いやすく、『とりあえずナレカン見に行こう』と気軽にアクセスできる心理的なハードルの低さも、日々の業務に自然と溶け込む要因になっていると感じます。
そういった意味でも、誰にとっても使いやすいツールだと思います。」
宇都宮様:
「ナレカンは登録されているデータが多ければ多いほど、その真価を発揮するツールだと実感しています。
私たちも本格的に活用し始めたのが2024年の8月頃で、約1年弱でここまで成果を感じられるようになりました。
コツコツとナレッジを蓄積していけば、必要な情報にたどり着きやすくなりますし、長い目で見れば、ナレッジを登録するコストを考えても十分にペイできる価値があると感じています。」