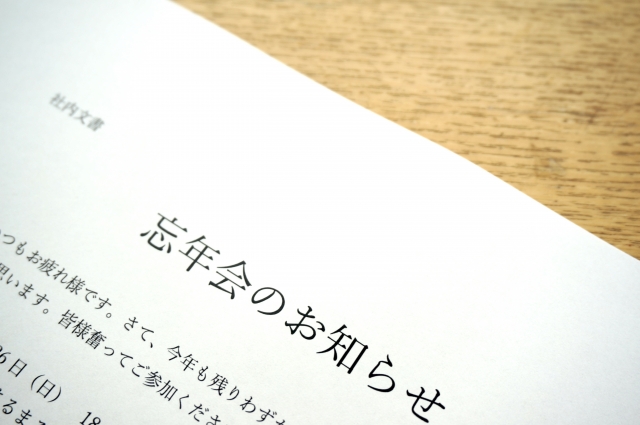紙ベースの情報管理を電子化するメリットとは?具体的な手順も解説!

紙ベースで業務を進めていると、用紙を印刷・保管する手間がかかったり、必要な情報を見つけるまでに時間がかかったりして非効率です。そこで、情報管理を電子化すると、余計なコストを削減して、社内の情報管理を徹底できます。
しかし、「紙ベースの情報管理を電子化する具体的なイメージが持てない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、紙ベースの情報管理を電子化するメリット・手順を中心にご紹介します。
- 紙ベースから情報を電子化するメリットを明確にしたい
- 情報管理の電子化が進まない理由を把握して対策したい
- 非効率な紙ベースでの管理から脱却するのに最適なツールを探している
という方はこの記事を参考にすると、紙ベースの情報管理を電子化する手順が分かり、効率的に業務を遂行できるようになります。
目次
紙ベースとは
ここでは、「紙ベース」の意味やメリット・デメリットをご紹介します。「紙ベース」の概要を押さえたうえで、紙ベースからの脱却を進めたい方は必見です。
紙ベースの意味
「紙ベース」とは、情報を紙媒体に記録・印刷して管理している状態を意味します。
紙ベースでは「印刷した書類を修正できない」「書類を配布する手間がかかる」ため、情報をスムーズに管理・共有できません。また、膨大な書類の中から必要な項目を探し出したり、都度ファイルを開いたりする手間がかかります。
したがって、紙ベースの情報管理を電子化すれば、無駄なコストを削減して、業務をストレスなく進められるようになります。
「紙ベース」と「紙媒体」の違い
「紙ベース」は、紙を使って管理や記録をする方法を指し、「紙媒体」は情報を伝達する媒体としての紙そのものを指すという違いがあります。
「紙ベース」と「紙媒体」の使い分けの具体例は以下の通りです。
- 例1:紙で提出する
- 例2:紙中心の業務を電子化する
❌紙ベースで提出する
⭕️紙媒体で提出する
⭕️紙ベースの業務を電子化する
❌紙媒体の業務を電子化する
このように、紙ベースは紙を使った業務の方法を表し、紙媒体は紙自体を示すという点で異なります。似て非なるものなので、しっかり使い分けましょう。
紙ベースで情報管理するメリット・デメリット
以下の表は、紙ベースで情報管理するメリット・デメリットをまとめたものです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
・視認性が高い
・信頼性が高い
・紙素材を活かした表現ができる
・記憶に残りやすい | ・管理コストがかかる
・情報の共有に手間がかかる
・情報を見つけづらい
・情報漏えいのリスクがある |
以上のように、紙の良さはあるものの、情報の管理・共有においては懸念が残ります。そこで、気軽に情報の整理・共有ができる「ナレカン」のようなツールで、ペーバーレス化すべきなのです。
紙ベースの情報管理を電子化する3つのメリットとは
ここでは、紙ベースの情報管理を電子化する3つのメリットについて解説します。以下のような恩恵が得られることを把握した上で電子化を進めましょう。
(1)紙を印刷・保管するコストを削減できる
メリットとして、紙を印刷・保管するコストを削減できる点が挙げられます。
紙ベースで情報を管理していると、書類を紙に印刷・配布するコストがかかります。また、膨大な書類を保管するスペースも確保しなければなりません。
そこで、情報管理を電子化すれば、紙を印刷・保管するコストを削減して、オフィススペースを有効活用できるようになります。
(2)必要な情報へすぐにアクセスできる
必要な情報へすぐにアクセスできる点も、紙ベースのデータ保管を電子化するメリットのひとつです。
情報管理を電子化すれば「キーワード」や「ファイル名」などで検索できるので、必要なデータをすぐに探し出せます。そのため、書類を探す時間を削減して、業務の停滞を防止できるのです。
したがって、紙ベースでの管理から電子化に移行すると、情報の検索性を向上させて、スピーディーに業務を進められます。
(3)情報を安全に管理できる
紙ベースによる管理を電子化すると、情報を安全に管理できるメリットがあります。
紙ベースでは、書庫の鍵さえあれば、誰でも書類の持ち出しができるため、紛失や情報漏えいのリスクが高まります。また、紙の経年劣化で読みづらくなり、情報が消失してしまう恐れもあるのです。
そこで、フォルダごとにアクセス権限を設定して情報を保護できる「ナレカン」のようなITツールを用いると、劣化や情報漏えいの心配をなくせます。
紙ベースの情報管理をデータ化する4つの手順とは
ここでは、紙ベースの情報管理をデータ化する4つの手順について解説します。具体的な手順は以下の通りです。
- ステップ1|電子化する文書を選ぶ
- ステップ2|データの解像度・形式を決める
- ステップ3|データの保管場所を決める
- 外付けハードディスク(HDD)
- 自社サーバー
- オンラインストレージ
- ステップ4|文書をスキャンする
まず、電子化する文書を選びます。
現場社員とのヒアリングを実施して「作業にミスが発生している」「情報へのアクセスに手間がかかっている」業務の文書から、優先的に電子化を進めましょう。
次に、データの解像度・形式を決めます。
解像度が高すぎるとデータ量が大きくなり、低すぎると見づらくなるので、適切な解像度を設定しましょう。また、ファイル形式を「文字情報を保持できるPDF」または「jpgやpngなどの画像ファイル」などから選択します。
解像度・形式を選択したら、データの保管場所を決めましょう。具体的な保管場所は以下の通りです。
とくに、オンラインストレージを利用すると、インターネット上にデータを一元管理できるので、情報共有の手間を削減して、いつでもどこからでも必要な情報へアクセス可能です。
最後に、文書をスキャンします。
コピー機のスキャナー機能を使ったり、スマホのカメラで撮影したりして、文書をスキャンしましょう。また、大量の文書を短期間で電子化する場合は、外部の業者に委託することも手法のひとつです。
以上より、紙ベースの情報管理を電子化するときは「あらかじめデータの解像度・形式・保管場所などのルールを決めておく」「計画的に実施する」ことがポイントです。
紙ベースの情報管理の電子化が進まない3つの理由とは
ここでは、紙ベースによる管理から電子化が進まない3つの理由について解説します。対処法も併せてご紹介しているので、担当者の方は必見です。
(1)導入コストがかかるから
1つ目の理由には、導入コストがかかる点が挙げられます。
情報管理を電子化すると、機器やツールを導入する金銭的コストだけでなく「機器の操作方法を周知する」「情報セキュリティ教育を実施する」ための時間的・人的コストが発生します。
そのため、導入コストがボトルネック(取り組みが進まない要因のこと)となって、電子化が浸透しない場合があります。そこで、長期的な視点で、情報管理を電子化する目的・メリットを周知したり、「IT導入補助金」などの補助金制度を活用したりしましょう。
(2)業務手順の変更に抵抗があるから
2つ目に、業務手順の変更に抵抗があることも、電子化が進まない理由のひとつです。
たとえば、承認が必要な業務を急に電子化してしまうと、「承認に印鑑がないと不安」といった心理的な抵抗感が生まれてしまいます。そのため、アナログに慣れている社員の中で電子化の取り組みを忌避する人が出るのです。
そこで、印鑑をもらう代わりに「承認フロー機能」を搭載した「ナレカン」のようなツールを用いれば、業務プロセスの変更を最小限に抑えられます。結果、ツール導入後も戸惑うことなく、いつも通りの手順で仕事ができるのです。
(3)上層部の問題意識が低いから
3つ目に上層部の問題意識が低いと、電子化が進みません。
近年、DXやペーパーレス化がよく取り上げられ、多くの人が存在を認識している一方で、実際に取り組みを始めている企業は少ないのが現状です。理由としては、紙ベースでも問題なく日常業務が遂行できてしまい、電子化の優先順位が低いためです。
しかし、電子化を実現した企業とそうでない企業では将来的に大きな差がつきます。そのため、会社の上層部が、現状への問題意識を持って改革を進めることが、企業間競争で生き残るために不可欠なのです。
【必見】情報管理の電子化に最適なツール
以下では、情報管理の電子化に最適なツールをご紹介します。
紙ベースで社内情報を管理すると、管理コストや共有の手間がかかります。かといって、電子化を推進しようとすると、導入に大きな負担がかかったり、アナログな方法に慣れている社員は強い抵抗感を示したりと、思うように電子化が進まないことがあります。
そこで、「業務プロセスを大幅に変えずに自然と電子化を進められるツール」を導入すれば、社員の心理的抵抗を抑えることができます。また、導入時の負荷を減らすため、充実したサポート体制があるものが望ましいです。
結論として、自社が導入すべきなのは、丁寧な導入支援制度があり、社内でも受け入れられやすいツール「ナレカン」一択です。
ナレカンでは、初期導入支援や既存データの移行支援が受けられるため、導入後すぐに運用に乗せることが可能です。また、従来の、印鑑で複数人に承認をもらうフローをツール内で実行できるため、業務プロセスを変えずに効率化が実現するのです。
徹底したサポート体制のもとスムーズに電子化できるツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
<ナレカンをおすすめするポイント>
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。
ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
紙ベースの情報管理を電子化するメリット・手順まとめ
これまで、紙ベースの情報管理を電子化するメリット・手順を中心にご紹介しました。
紙ベースの管理を電子化すると、余計なコストを削減できるうえ、必要な情報へすぐにアクセスできるようになります。また、情報管理を電子化するときは、文書をスキャンする前にデータの解像度・形式・保管場所などのルールを決めておきましょう。
ただし、「業務手順の変更」や「セキュリティ」に不安があると、情報管理の電子化が進みません。そこで、「業務プロセスの変更が少なく、誰でも安心して情報管理ができるツール」があると便利です。
したがって、情報管理を電子化するには、すべての社員が安心して使えるツール「ナレカン」が最適です。
無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、紙ベースの情報管理を電子化しましょう。