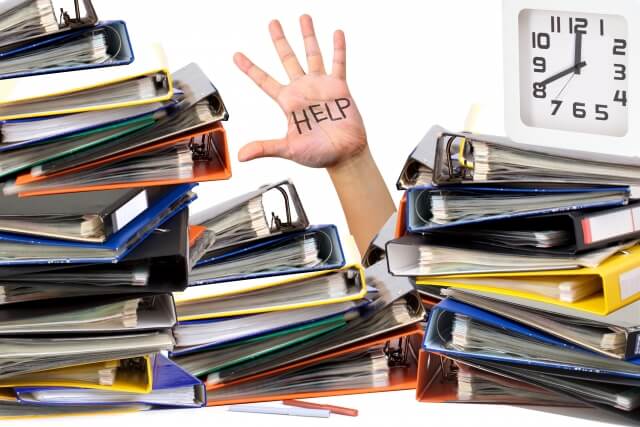ヘルプデスクに最適な情報共有ツールとは?選定ポイントも紹介

社内ヘルプデスクには、ITシステムの使い方からエラーの対処法まで、さまざまな問い合わせが寄せられます。とくに、近年では政府が「企業のDX化」を奨励しているので、新しくITツールを導入する企業が増加し、ヘルプデスクの必要性も高まりました。
一方、ヘルプデスクへのニーズの高まりに伴い、担当者が扱う情報が増えて、担当者がストレスを抱えていることも多くあります。しかし、現状を改善したいと考えていても「ヘルプデスクの情報共有を円滑する方法が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ヘルプデスクの情報共有を円滑にする方法、情報共有ツールの選定ポイントを中心に解説します。
- ヘルプデスクの情報共有を円滑にしたい
- ヘルプデスクで使う情報共有ツールの選定ポイントを知りたい
- ヘルプデスクに最適なツールを探している
という方はこの記事を参考にすると、ヘルプデスクに情報共有が最適な理由が分かり、業務の負担を大きく軽減できるようになります。
目次
ヘルプデスクとは
ここでは、ヘルプデスクの概要と課題をご紹介します。ヘルプデスクが抱える課題を知り、適切な改善をしたい方は必見です。
ヘルプデスクの概要
ヘルプデスクとは、IT機器やシステムに関する問い合わせを受ける仕事です。
ヘルプデスクの担当者は、ITツールの使い方からエラーの対応まで幅広い業務をします。しかし、情報システム部に所属する社員が兼任しており、少ない人数で多くの業務をこなしているケースも少なくありません。
そのため、ヘルプデスクに問い合わせが殺到すると、回答までに時間がかかる現状があるのです。したがって、一つひとつのトラブルへ迅速に対処できるように、問い合わせの減少に取り組むことが大切です。
ヘルプデスクの課題
ヘルプデスクの課題としては、以下の3点が挙げられます。
- 対応する範囲が定まっていない
- マニュアルが社員に活用されない
- 対応に時間がかかる
対応範囲が明確でなければ、メールの作成方法などの初歩的な質問からシステムの利用方法まで、さまざまな問い合わせが寄せられます。その結果、担当者の負担が増えてしまうのです。
ITツールのマニュアルを用意しても「必要な情報を見つけるのに時間がかかる」などの理由から、社内で活用されないケースも多いです。その結果、疑問はすべてヘルプデスクに寄せられることになり、問い合わせが増えてしまうのです。
場合によっては、担当者の知識が浅かったり意図が正しく伝わらなかったりすることもあります。その結果、トラブルの解決に無駄な時間がかかってしまうのです。
上記の課題が当てはまっているヘルプデスクは、早急に業務体制を見直しましょう。
ヘルプデスクで使う情報共有ツールの選定ポイント3選
ヘルプデスクの情報共有を円滑にするためにはITツールの導入が欠かせません。以下では、ヘルプデスクで使う情報共有ツールの選定ポイントを3つ解説します。
ポイント1|情報共有が簡単にできるか
ポイントの1つ目は、情報共有が簡単にできるツールかです。
ヘルプデスクには、日々新しい情報が集積されます。そのため情報をスムーズに共有できる仕組みが整っているかは、業務の質や生産性に向上に直結します。たとえば、FAQの作成や更新が容易に行えるか、社内の情報を共有しやすいかといった点が重要になります。
したがって、ヘルプデスクには可能な限り情報共有が簡単にできるツールを選択しましょう。
ポイント2|必要な情報に瞬時にアクセスできるか
ポイントの2つ目は、必要な情報に瞬時にアクセスできるかです。
過去のFAQや問い合わせ履歴の中から、必要な情報を迅速に見つけ出せる検索機能はヘルプデスクの業務の効率化には欠かせません。高度な検索機能や社内の情報を一元管理できるツールであれば、問い合わせ対応やFAQの作成の時間を大幅に短縮できます。


また、「キーワード検索」だけでなく、AIなどを活用した絞り込み機能があると、よりスムーズに業務に取り組むことができます。
ポイント3|サポート体制が整っているか
ポイントの3つ目は、サポート体制が整っているかです。
導入時やその後の運用において、ツールの操作方法に関する疑問やトラブルが発生する可能性は十分にあります。ツールを提供する企業のサポート体制が充実しているかが、安心してツールを利用し続けるためには重要です。
とくに、サービスを導入・移行する場合、初期設定に時間を要することが少なくありません。そこで、「導入から運用まで手厚いサポート体制が整っているツール」であるかを確認しましょう。
【必見】ヘルプデスクの抱える課題に最も効果的な情報共有ツール
以下では、ヘルプデスクの業務効率化に最適なツールをご紹介します。
ヘルプデスク担当者の業務が逼迫し、社内外からの問い合わせ対応が遅れてしまうと、業務の停滞を招き、顧客満足度の低下にも繋がりかねません。そのため、ヘルプデスクの業務効率化には、質問と回答、ノウハウの一元管理ができる仕組みを構築することが不可欠です。
そこで、「情報共有ツール」を導入し、FAQの作成や過去の問い合わせ履歴を蓄積しましょう。ただし、検索性の低いツールでは必要な情報が必要なときに見つからず、情報を探すのに時間的・人的コストがかかってしまうため注意が必要です。
結論、自社が導入するべきなのは、社内のあらゆる情報を一元的に共有・管理でき、ほしい情報を確実に絞り込めるツール「ナレカン」 一択です。
ナレカンでは、社内の情報の管理・共有だけでなく「ファイル要約機能」を使えば、FAQや過去の問い合わせ履歴の要点を自動でまとめられます。また、AIを活用した「超高精度の検索機能」で即アクセスすることが可能です。
ヘルプデスクの業務効率化に最適なツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
<ナレカンをおすすめするポイント>
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。
ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
ヘルプデスクに情報共有ツールを導入するメリット
ここでは、ヘルプデスクに情報共有ツールを導入するメリットを3つご紹介します。ヘルプデスクの業務負担を改善したいが、効果的な対策が分からない」という担当者の方は必見です。
(1)情報共有の負担が軽減する
はじめに、情報共有の負担が軽減するメリットがあります。
たとえば、社内FAQ(よくあるご質問)をツールで共有すると、社員は検索をかけるだけで必要な情報にアクセスできます。その結果、些細な疑問はすべてツール上で解消されるため、ヘルプデスクへの問い合わせが減少するのです。
さらに、クラウド型の情報共有ツールであれば、追加・修正した情報はほかの社員の端末にも瞬時に反映されます。そのため、情報の更新に手間がかかりません。
(2)対応のスピードが早まる
次に、ヘルプデスクに情報共有ツールを導入すれば、問い合わせ対応も迅速になります。
情報共有ツールであればツール上でやりとりができるので、電話やメールが不要です。そのため、メモをしたりメールファイルを毎回開いたりすることなく、スムーズに対応できるようになります。
さらに、情報共有ツールは時間や場所を問わずに使えるため、社外にいても問い合わせの状況や内容を確かめられるのです。
(3)社内にノウハウを蓄積できる
最後に、ヘルプデスクにツールを導入すればノウハウも蓄積できます。
仮に、ヘルプデスクでのやりとりが口頭であれば、ノウハウは一人ひとりに属人化されてしまい、逐一本人に聞かなければなりません。加えて、紙やメール、Excelといった方法では、目的の情報が埋もれるので探し出すのが面倒です。
しかし、情報共有ツールであればすべてのデータを一カ所に集められるので、ノウハウを残すのに大きく役立ちます。なかでも、AIを活用した高度な検索機能が備わった「ナレカン」 を使えば、目的の情報をわずかな操作で見つけられます。
ヘルプデスクに最適な情報共有ツールや選定ポイント
ここまで、ヘルプデスクに最適な情報共有ツールや選定ポイントを中心にご紹介しました。
ヘルプデスクに情報共有ツールを導入すれば、FAQの作成や過去の問い合わせ履歴を蓄積でき、業務のクオリティーや対応速度の向上につながります。また、高度な検索機能の備わったツールであれば、ヘルプデスクでの情報検索のストレスが解消されます。
ただし、新しいツールの導入や移行には、初期設定に人的・時間的コストがかかることも少なくありません。そのため、導入から運用までのサポート体制が整っているツールを選択すると、スムーズな移行と利用開始が可能になります。
結論、ヘルプデスクの情報共有には、高度な検索機能が備わっており、導入・移行サポートも充実した「ナレカン」が最適です。
無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、ヘルプデスクの悩みを解消しましょう。
この記事の監修者

株式会社Stock
代表取締役社長 澤村大輔
1986年生まれ。早稲田大学法学部卒。
新卒で、野村総合研究所(NRI)に、経営コンサルタントとして入社。
その後、株式会社リンクライブ(現:株式会社Stock)を設立。代表取締役に就任。
2018年、「世界中の『非IT企業』から、情報共有のストレスを取り除く」ことをミッションに、チームの情報を最も簡単に管理できるツール「Stock」を正式ローンチ。
2020年、DNX Ventures、East Ventures、マネーフォワード等のベンチャーキャピタル(VC)から、総額1億円の資金調達を実施。
2021年、東洋経済「すごいベンチャー100」に選出。
2024年、100名~数万名規模の企業のナレッジ管理の課題解決のために、社内のナレッジに即アクセスできるツール、「ナレカン」をαローンチ。
新卒で、野村総合研究所(NRI)に、経営コンサルタントとして入社。
その後、株式会社リンクライブ(現:株式会社Stock)を設立。代表取締役に就任。
2018年、「世界中の『非IT企業』から、情報共有のストレスを取り除く」ことをミッションに、チームの情報を最も簡単に管理できるツール「Stock」を正式ローンチ。
2020年、DNX Ventures、East Ventures、マネーフォワード等のベンチャーキャピタル(VC)から、総額1億円の資金調達を実施。
2021年、東洋経済「すごいベンチャー100」に選出。
2024年、100名~数万名規模の企業のナレッジ管理の課題解決のために、社内のナレッジに即アクセスできるツール、「ナレカン」をαローンチ。
最新の投稿
おすすめ記事