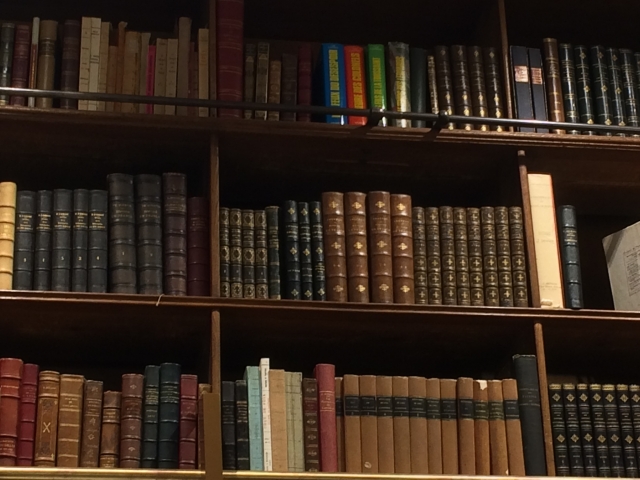【Excel/Word】分かりやすい引継ぎ書テンプレート・フォーマット5選

異動や退職時に引継ぎ書を作成すると、後任のメンバーに業務をスムーズに引き継ぐことができます。しかし、一から引継ぎ書を作るのは工数がかかるため、テンプレートやひな形を活用して、作業の負担を減らすことが推奨されます。
一方で、「引継ぎ書のテンプレートが見つからない」「見やすい引継ぎ書の構成が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、引継ぎ書の作成ポイントやテンプレートを中心にご紹介します。
- 引継ぎ書のサンプルやフォーマットを探している
- 書き方のポイントを押さえて、スムーズに引継ぎ書を作成したい
- 引継ぎ書を適切に管理・共有し、業務効率化を実現したい
という方はこの記事を参考にすると、短時間で簡単に引継ぎ書を作成し、スピーディーに情報共有する方法が見つかります。
目次
引継ぎ書とは
ここでは、引継ぎ書の概要をご説明します。引継ぎ書を作成する前に、以下で引継ぎ書の概要や目的を押さえましょう。
引継ぎ書とマニュアルの違い
引継ぎ書とマニュアルは、網羅する情報の範囲が異なります。
引継ぎ書には業務の具体的な手順や進行中の案件が記載され、業務そのものに加えて関連する情報も含まれます。一方で、マニュアルは全体の流れや手順に特化した内容で、前任者の進捗状況までは把握できません。
このように、引継ぎ書はマニュアルを補完する役割を担います。後任者がスムーズに業務を進められるよう、両方を併せて共有することが重要です。
引継ぎ書を作成する目的
引継ぎ書は、退職や異動、新人教育などのシーンで必要となり、主に以下のような目的で作成されます。
- 属人化を防ぐため
- 業務の質と効率の低下を防ぐため
- ナレッジを蓄積するため
特定の人に依存せず、業務を誰でも引き継げる状態にすることで、トラブルや業務停滞を回避できます。
引継ぎ書を活用することで、業務の質や進行状況が前任者と同じ水準で維持されます。これにより、後任者も効率よく業務を進められます。
引継ぎ書は業務のナレッジを蓄積するためにも必要です。業務のノウハウや成功・失敗事例があれば、前任者が不在になっても仕事の質を保てます。
これらのメリットを得るためにも、退職や異動、新人教育などの場面では、必ず引継ぎ書を作成し、後任者にスムーズに業務を引き継ぐ準備をしましょう。
【例文あり】引継ぎ書に記載すべき6つの項目

ここでは、引継ぎ書に必要な6つの項目について例文を用いて解説します。誰にでも分かりやすい引継ぎ書を作成するために、以下の6つの項目を漏らすことなく記載しましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 業務の概要 |
はじめに、業務の全体像を明記しましょう。これにより、後任者の業務への理解が深まります。業務の位置づけを明確にするために、関連部署や取引先の情報も記載すると良いです。 |
| スケジュール |
年間・月間・週間のスケジュールに基づいてタスクを整理します。これにより、時期による優先順位や締め切りを明確にし、後任者への伝達漏れを防ぎます。 |
| 業務内容と流れ |
業務内容や手順を具体的に記載します。前任者が知っている「コツ」や「ノウハウ」も追加しておくと、品質維持や作業効率の向上が期待できます。 |
| 進捗状況 |
前任者が完了できなかった業務について、進捗や注意点を記載します。また進捗状況の確認方法や関連資料を共有しておくと、スムーズに業務を引き継げます。 |
| トラブル発生時の対処法 |
過去のトラブルやその対処法、イレギュラーな対応例を記載しましょう。これにより、後任者はトラブルを事前に回避し、迅速な対応が可能になります。 |
| 関係者の連絡先 |
関連部署や担当者、取引先の連絡先を一覧にまとめておきます。連絡先がすぐに確認できるため、後任者が不明点を迅速に解決できます。 |
以上を参考に、前任者と後任者で認識のずれがでないよう、必要な情報を詳細に記載することが大切です。また、引き継ぐべき情報量が多い場合には、”ノート形式”で情報を整理して書き込める「ナレカン」のようなツールを活用するのも一つの手です。
【無料】おすすめの引継ぎ書テンプレート・フォーマット5選
引継ぎ書は、日常業務の合間を縫いながら作るため、短時間で完成させることが求められます。そこで、以下で紹介する5つのテンプレートを活用して、簡単に引継ぎ書を完成させましょう。
【Word】作業や業務の流れが掴める引継ぎ資料のテンプレート

こちらは、Microsoftが提供するWordで使える引継ぎ書テンプレートです。
フォーマットに沿って必要な情報を入力するだけで、簡単に引継ぎ書を作成できます。画像を添付できる欄もあるため、作業手順や資料の内容を視覚的に分かりやすく伝えられる点もメリットです。
【Word】自由度の高い引継ぎ書のサンプル

こちらは、SILAND.JPが提供するWord形式の引継ぎ書テンプレートです。
表紙や見出し用の素材があらかじめ用意されており、自分好みにカスタマイズして資料を作成できます。ただし、自由度が高い分、ITに不慣れな方には操作が難しく感じられる可能性があるため注意が必要です。
【Excel】異動・退職時の業務引継ぎの報告書類のひな形

こちらは、経費削減実行委員会が提供するExcel形式の業務引継ぎ書テンプレートです。ダウンロードするには、会員登録が必須になっています。
表があらかじめ用意されているため、項目に情報を入力するだけで引継ぎ書を作成できます。異動や転勤などで担当者が不在になる前の引継ぎ報告に便利ですが、業務の詳細な手順を記載する欄がないため、マニュアルとの併用が必要です。
【Excel】経理や会計、事務などの様々な引継ぎで使えるフォーマット

こちらは、テンプレートの無料ダウンロードが提供する、Excelで使える業務引継ぎ書のテンプレートです。
シンプルな形式の引継ぎ書なので汎用性が高く、経理や営業、事務など幅広い業務の引継ぎに利用できます。ただし、画像を挿入する欄がないため、テキストだけではやや読みづらくなる可能性があります。
【Word・Excel】シンプルで見やすい引継書の見本

こちらは、テンプレルンが提供するA4サイズの業務引継ぎ書のテンプレートです。ダウンロードするにはLINE登録が必要です。
ExcelやWordのほか、PDF形式でも配布されているため、社内共有や印刷しての配布など、さまざまな用途で活用できます。ただし、画像を挿入する欄がないため、テキストのみの資料となる点に注意が必要です。
WordやExcel資料で引継ぎ書を共有するデメリット3つ
ここでは、WordやExcel資料で引継ぎ書を共有するデメリットを3つ紹介します。WordやExcelで引継ぎ書を作成・管理している場合は、以下のデメリットを理解し、引継ぎ書の管理方法を見直しましょう。
(1)管理が煩雑化する
1つ目に、管理が煩雑化するというデメリットがあげられます。
WordやExcelのファイルは、開かないと中身を確認できないため、資料が増えるにつれて管理が複雑になります。複数の担当者が作成した資料が同じフォルダに混在すると、必要な情報がどこにあるのか分からなくなることも少なくありません。
また、メールやチャットでファイルをやり取りすると、補足情報や関連資料が分散してしまいます。その結果、「どのファイルが最新版なのか」「どのメールに情報が書いてあったのか」を探すのに無駄な時間がかかります。
(2)画像や動画を添付しにくい
2つ目に、画像や動画を添付しにくいというデメリットがあげられます。
WordやExcelでも画像・動画を添付することは可能ですが、直感的な操作ではないため、画像や動画を使って見やすく情報をまとめるのはITに不慣れなメンバーにとっては難しく感じられます。
とくに、視覚的に分かりやすい資料を作りたい場合、ExcelやWordでは画像や動画の配置やサイズ調整が複雑になりやすく、作業に時間がかかります。したがって、見やすい資料を直感的に作るには不向きなのです。
(3)情報の追加・更新が面倒
3つ目に、情報の追加・更新が面倒だというデメリットがあげられます。
WordやExcelで作業手順や連絡先を更新すると、関係者全員に最新版をメールやチャットで送り直す必要があります。もし送付漏れや混同が起こると、古い情報をもとに作業が進められ、ミスや手戻りが発生しかねません。
そこで、「ナレカン」のような情報の更新とともに即共有されるツールを導入すれば、わざわざ共有する手間を省けるうえ、一つのツールで引継ぎ書の作成・共有・管理が完結するのです。
【必見】引継ぎ書を最も簡単に作成・管理・共有できるツール
以下では、引継ぎ書を最も簡単に作成・管理・共有できるツールをご紹介します。
引継ぎ書をWordやExcelで作成すると、一から作成する手間が省けて便利です。しかし、「どこにファイルがあるかわからない」「追記・更新した後の共有が面倒」となることが多いため、引継ぎ書が有効活用されない恐れがあります。
そこで「テンプレート機能を備えた文書管理ツール」を導入すると、引継ぎ書の作成時間が短縮されるうえ、引継ぎ書の運用もしやすくなります。とくに「検索機能に優れたツール」であれば過去の引継ぎ書を最大限活用できるのです。
したがって、自社が引継ぎ書の制作・管理で導入すべきは、引継ぎ書などのあらゆる社内文書に即アクセスでき、作成・管理・共有が簡単にできるツール「ナレカン」一択です。
ナレカンの「テンプレート」で作成した引継ぎ書は、即座に任意のメンバーに共有されるうえ「ヒット率100%の検索機能」で目的の情報に即アクセスできます。そのため、引継ぎ書の作成から共有・運用までを一貫して効率化できるのです。
ナレッジを即作成・即アクセスできる「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
<ナレカンをおすすめするポイント>
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。
ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
【見本】ナレカンを使った引継ぎ書のテンプレートの作成例
ここでは、ナレカンを使った引継ぎ書の作り方を解説します。以下の手順を追えば、見やすい引継ぎ書を簡単に作成できます。
- はじめに、記載する項目を決めて、引継ぎ書のテンプレートを作成します。[+新規作成]をクリックして、作成を始めましょう。
- 画面右下の [+テンプレートから作成] をクリックし、引継ぎ書のテンプレートを選択します。
- テンプレートに沿って記載すれば、引継ぎ書の完成です。画面右上の[公開する]をクリックして共有しましょう。

テンプレートが完成したら、[保存]をクリックして作成完了です。




このように、ナレカンを使えば、必須項目を押さえた自作のテンプレートで見やすい引継ぎ書を簡単に作れます。
また、複雑な記法は必要なく、記事の下部にある[機能ボタン]をクリックすれば、表やチェックリストも簡単に「引継ぎ書テンプレート」として登録可能です。そのため、すべての社員が簡単に分かりやすい引継ぎ書を作成できるのです。
わかりやすい引継ぎ書を作成する3つのポイント
ここでは、引継ぎ書を作成するときに押さえておくべき3つのポイントを解説します。以下のポイントを守れば、後任者に滞りなく業務の引継ぎができます。
(1)頻度別にまとめる
まず、引継ぎ書には、業務を「日次」「月次」「年次」といった頻度別にまとめて記載しましょう。
たとえば、「日報」と「週次ミーティング」を混在して書くと、後任者がどの作業を優先すべきか判断しづらく、重要な作業の抜け漏れが起こる可能性があります。また、作業順序や期限も分かりにくくなるため、業務効率の低下にもつながりかねません。
そこで、頻度ごとに整理して記載すれば、後任者は重要な作業をすぐに把握できるので、抜け漏れの防止やスムーズな引き継ぎが可能になります。
(2)要点を押さえる
次に、引継ぎ書は要点を押さえて簡潔に書きましょう。
引継ぎ書で業務を詳しく説明すれば、後任のメンバーがすぐに仕事を進められますが、情報量が多すぎると、かえって資料が読みづらくなってしまうので注意が必要です。そのため、要点を押さえて業務を簡潔に説明することを意識しましょう。
そこで、必須項目を押さえた自作のテンプレートをいつでも呼び起こせて、必要に応じて項目の追記や画像添付ができる「ナレカン」などのITツールを活用すれば、誰から見ても分かりやすい引継ぎ書を作れるのです。
(3)関係者を記載する
最後に、業務に関連するメンバーの情報を記載しましょう。
業務には、社内外の担当者と連携して進めるものもあります。そのため、関係者の名前や所属先、連絡先を含めておくことで、業務に関する質問や不明点がすぐに解決できるようになります。
また、担当が変わる場合は、事前に関係者に対面でその旨を伝えることが大切です。これにより、誤解やトラブルを防ぐことができます。
【番外編】スムーズに業務を引き継ぐコツとは?
スムーズに業務を引き継ぐには以下2つのコツがあります。
- わかりやすい引継ぎ書を作る
- 日頃から情報共有を徹底する
まず誰が読んでも理解できるほど、視覚的にも内容的にもわかりやすい引継ぎ書を作成することが大切です。そのためには、一人で引継ぎ書類を完成させるのではなく、複数人で内容の確認や補填をするようにしましょう。
どんなにわかりやすい引継ぎ書であっても、業務を進めていく上で必ず不明点が生じます。そこで、普段から業務の概要を共有する仕組みを作り、業務の属人化を解消しておきましょう。
以上のように、引継ぎをスムーズに進めるには情報共有の制度を整えるといった普段からの積み重ねが重要です。そのため、正しく業務情報が共有されていない場合は、今から「ナレカン」のような情報共有ツールで今後の業務の引継ぎを円滑に進めましょう。
引継ぎ書の作成ポイントやテンプレートまとめ
ここまで、引継ぎ書の作成ポイントやテンプレートを解説しました。
引継ぎ書はテンプレートを使えば短時間で作れるものの、WordやExcelで作成するとファイルが増えて管理に手間がかかります。また、様々な業務に関する引継ぎ書やマニュアルが混在して、なかなか必要な書類に辿り着けないこともあります。
そこで、引継ぎ書の作成から管理や共有まで効率よく実行できるツールを導入しましょう。加えて、高度な検索機能を備えたものであれば、必要なファイルがストレスなく見つかります。
結論、自社で導入すべきITツールは、AIによる検索機能を備え、作成・共有・管理を一元化できるアプリ「ナレカン」一択です。
無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、スムーズな引継ぎを実現しましょう。