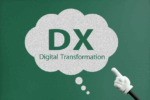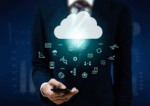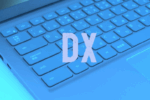DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?役立つ技術や推進事例を紹介!

今日では、社内業務をデジタル化してビジネスの変革を進めるDX(デジタルトランスフォーメーション)が推奨されています。激しい時代変化のなかで市場競争をしていくうえでも、DX化は必須のテーマとなっているのです。
しかし、実際にDX化をしようとしても「具体的にどのような取り組みをすべきか分からない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、DXの定義や役立つ技術、推進事例を中心にご紹介します。
- 企業におけるDX化について背景やメリットを理解したい
- DX化を進めるための具体的な実践方法を知りたい
- DX化に役に立つツールを教えてほしい
という方はこの記事を参考にすると、DXの明確なメリットや施策が分かり、社内のDX化を進められるようになります。
目次
DXとは?どういう意味?
ここでは、DXの概要やよくある質問をご紹介します。これまで「なぜDXが必要とされているのか」を説明できない方は必見です。
DXの概要
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術によって業務フローを改善したり新たなビジネスを生み出したりする動きを指します。
2004年にスウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱したもので「情報技術で人々の生活をあらゆる面でより良く変化させること」を意味しています。また、総務省には以下のように定義されています。
デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化なども変革していくような取組を指す概念である。
また、DXが進んでいる背景として、スマートフォンやSNSによる消費活動の変化や企業による新ビジネスの創出が挙げられます。以上のような激しい時代変化へ対応するためにも、今日においてDX化は必須のプロセスとなっているのです。
DXに関するよくある質問
ここでは、DXに関するよくある質問を表形式でご紹介します。質問ごとの回答は以下の通りです。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| DXとはどのような意味か |
「デジタル技術で人々の生活をより良く変えること」を意味します。 |
| DXは何をするものなのか |
デジタル技術によって既存の業務フローを改善したり、新たなビジネスを生み出したりします。 |
| DXは何の略か |
「デジタル変革」を意味する”Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)”の略です。 |
| DXにはどのような人材が必要か |
UXデザイナーやデータサイエンティスト、エンジニアなど、ITに詳しい人材が必要です。 |
| DXにおける「2025年の崖」とは何か |
既存のシステムが部署ごとの分断や複雑化していることによって、全社横断的なDXができないことを意味します。 |
以上のように、DXが必要とされる理由や知識を押さえて適切な取り組みをしましょう。
DXを推進するメリット
ビジネスにおいて、DX化を進めるメリットには、主に「業務効率化」と「働き方改革の促進」の2つが挙げられます。
- 業務効率化や生産性向上を実現できる
- リモートワーク促進など働き方改革につながる
これまで手作業だった業務をDXによって自動化できれば、大幅に時間を短縮できるうえに、空いたリソースを他の業務に回すことも可能になるので、職場全体の生産性を大幅に向上できます。
DXによってコミュニケーションツールや管理システムを導入すれば、オフィスや現場に行かなくても仕事ができる環境を整えられるので、リモートワークを促進し、働き方改革を実現できます。
とくに近年では、情報技術が著しく発展しており、業界職種問わずあらゆる企業でDX化が進んでいます。つまり、DX化を進めている企業では「上記のメリットを享受している」と言えるので、後れを取らないためにもDX化は必須の取り組みだと言えるのです。
DXの定義
ここではDXの定義をご紹介します。これまで、DXをIT化やほかの類義語と混同していた方は必見です。
DX化とIT化の違い
DX化とIT化には範囲の大きさに違いがあります。
DX化は社会やビジネスの仕組みそのものを変革する動きなのに対し、IT化は業務プロセスを変えずに効率化のみを図る動きです。そのため、IT化はDX化よりも影響する範囲が小さく、DX推進における手段のひとつと定義されます。
以上のように、IT化はDX化よりも限定的な範囲を指すのです。
DXの類義語との違い
DXの類義語に「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」があります。
デジタイゼーションは”業務効率化のためにデジタル技術を導入すること”を指し、DXにおける最低限のプロセスです。一方、デジタライゼーションは”業務を効率化したり新しい顧客体験を生み出したりすること”であり、ビジネスモデルの変革を指します。
以上のように、どちらもDXにおけるプロセスのひとつのため、混同しないようにすべきです。
日本企業におけるDX化推進状況とは
日本企業ではDX化が年々進みつつあります。
とくに、昨今はAIを活用したサービスが多く生まれており「三菱総合研究所のDX推進状況調査結果【2025年度速報版】」によれば、2023年と2025年を比較すると、AI技術を業務に活用している企業の割合は「20.2%」も上がっています。
しかし、同調査結果によると「業務効率化のためにデジタル技術を導入しても、思うような成果を実感できていない」との声も多く上がっていることが分かります。
つまり、むやみにDX化を進めるのではなく、自社が抱える課題に合ったものであるかという点を考慮して、サービスを選ばないといけないのです。
DXの推進方法・取り組み方

以下では、DXの推進方法・取り組み方を3段階に分けて解説します。「DX化を進めるには、何から始めればいいのかわからない」という担当者の方は必見です。
ステップ1|現状の課題を可視化する
まずは自社の現状の課題を可視化することが重要です。
業務の現状課題の中で自動化によって解決できるものはないか検討し、リストアップなどをして可視化します。さらに、社内で現在使用している既存システムや、その管理にかかっている人的リソースなども忘れずに考慮しましょう。
現状の課題を把握せず闇雲にDX化に取り掛かると、課題も解決できないまま無駄なコストを費やしてしまう恐れがあるので注意が必要です。
ステップ2|DX化に必要な人材を確保する
次にDX化を推進する人材を確保しましょう。
DXのための人材を確保するには外部から採用する方法がありますが、現状ではDXを推進できる人材が大幅に不足しています。そのため、既存社員のリスキリングによってDX推進を担えるように、スキルを開発する方法を検討する必要があります。
以上のように、人材確保だけでなく、経営層のコミットや社内理解が得られるような「DX推進に適した組織体制の構築」も重要です。
ステップ3|課題解決に合ったツールを導入する
最後に、自社の課題解決に合ったツールを導入しましょう。
ステップ1で可視化した課題を解決できるようなツールを比較検討して選定する必要があります。ただし、目先の業務効率化ばかりを考えて複数のツールを導入してしまうと、コストの増加やツールごとの情報の分断が生じてしまうので注意が必要です。
担当者だけで自社の課題に最適なツールを選ぶのは困難な場合もあるため、可能であれば無料相談サービスを受けましょう。
【担当者必見】DXの推進に最適なツール
以下では、DXの推進に最適なツールをご紹介します。
DXを推進するには、まずは情報共有や業務連携の仕組みを整える必要があります。それは、社員が社内情報にアクセスできる環境が無ければ、DXによる業務の変化を浸透させることができないからです。
しかし、DXの促進のために多機能なツールや複数のツールを導入してしまうと、かえって社員が使いこなせず形骸化してしまいます。そこで、「シンプルな操作で社内情報の蓄積から共有・管理までできる情報管理ツール」を導入しましょう。
したがって、DXの実現には、シンプルな操作で社内情報を一元管理でき、担当者が導入から定着までを手厚くサポートしてくれる情報共有ツール「ナレカン」が最適です。
ナレカンでは、社内のあらゆる情報の共有・管理が簡単にできるため、DX化が促進されます。また、「超高精度の検索機能」でIT初心者でも直感的に情報を確認できるほか、専属担当者の手厚いサポートを受けられるので、社内に確実に定着させられるのです。
社内のナレッジに直感的にアクセスできるツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
<ナレカンをおすすめするポイント>
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。
ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
日本のDX推進の成功事例7選
ここでは、実際にDXを進め、業務に活用できた成功事例を7つご紹介します。他社の事例から自社へ活かせるポイントを見つけたい方は必見です。
事例1|木村鋳造所の事例(製造)

木村鋳造所は、自動車用プレス機械や産業用機械を鋳造・販売している企業です。
当社では鋳造法のひとつに3Dプリンターを採用しており、設計から鋳造のスピードと質を両立させながらコスト削減や大量生産を実現しました。
さらに、3Dプリンターを用いた鋳造を1.5倍にして工場設備を増強するなど、リソースの有効活用もできています。
引用・参考:木村鋳造所の事例
事例2|株式会社スペースリーの事例(不動産)
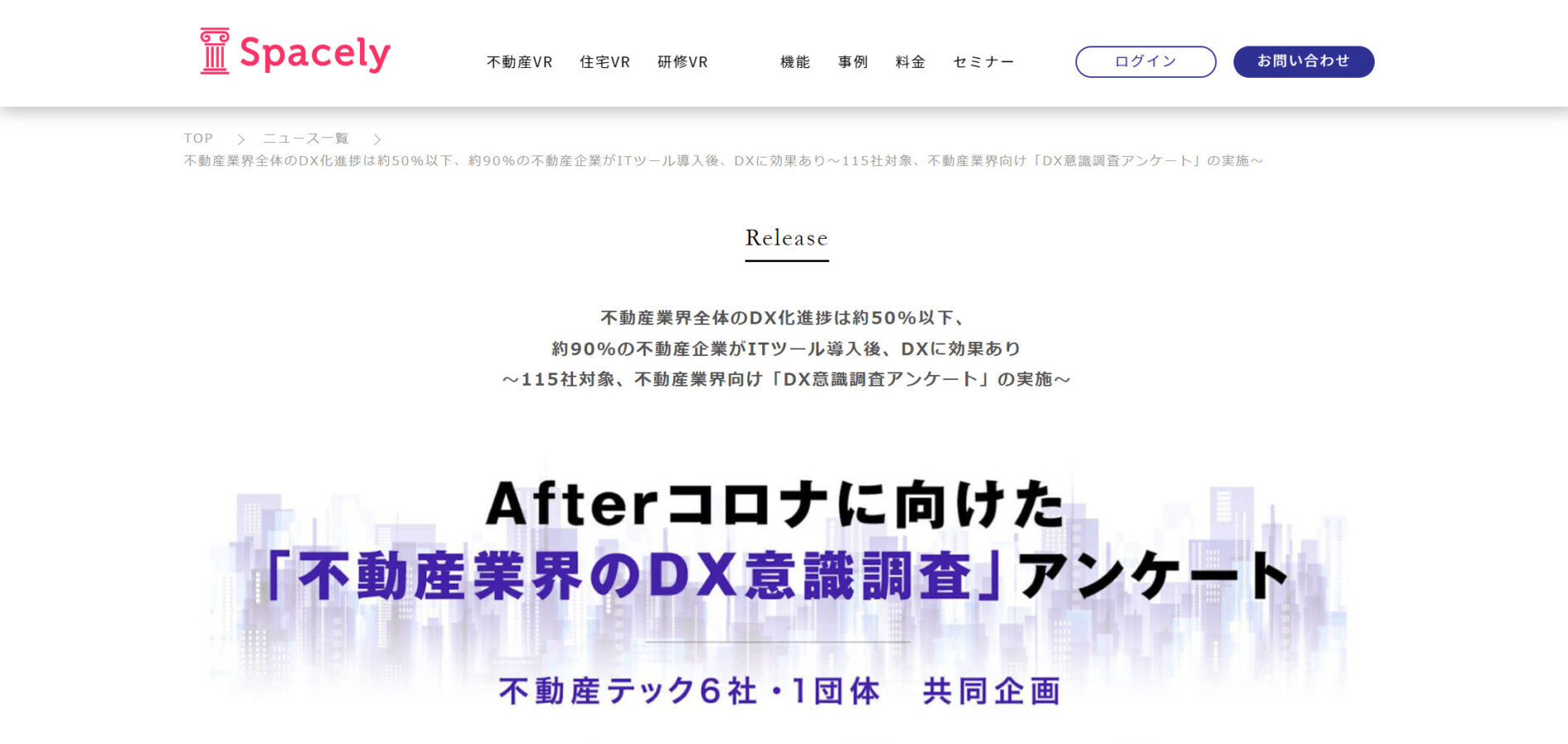
株式会社スペースリーは、VRクラウドソフト「スペースリー」を開発した企業です。
当社のソフトウェアは主に不動産業界における「オンライン内見」の発足に貢献しています。ソフトを活用すれば、VR上で部屋間を移動したり昼夜を切り替えたりできるので、サイト上の写真よりも多くの情報を得られるのです。
その結果、物件の成約数や反響も向上するなど、大幅な利益アップを実現しました。
引用・参考:株式会社スペースリーの事例
事例3|横浜銀行の事例(金融)

引用:横浜銀行の公式サイト
横浜銀行は、現在AIを用いた不正取引検知(アンチマネーロンダリング)サービスを高度化しています。
当行は、人間には気づかないような不正取引も検知するため、AIで取引のリスク度合いを可視化してセキュリティ強化を図りました。
その結果、調査対象の口座数を30~40%減少させるなど、業務負担が大幅に軽減されたのです。
参考:横浜銀行の事例
事例4|パーソルホールディングスの事例(人材)

パーソルホールディングスは、dodaやテンプスタッフなどをはじめとした人材サービスを展開する企業です。
当社では、グループのシステム統合時に研修データや人事データが活用されていない課題がありました。そこで、管理方法をスプレッドシートからBI(ビジネスインテリジェンスツール)へ変更したのです。
その結果、人事担当者の作業工数が大幅に削減され、データも正しく活用されるようになりました。
事例5|日本航空の事例(航空)

引用:日本航空の公式サイト
日本航空は、コロナウイルスによる生活様式の変革に対応するため「IoTおもてなしサービス実証」へ参画しました。
具体的には、搭乗の時間まで写真撮影ができる「笑顔写真撮影サイネージ」や、液晶ディスプレイのカメラで個人を特定し、手荷物受け取りまでの時間を表示する「手荷物待ち時間可視化サイネージ」、顔認証だけで決済が可能な「手ぶら決済」が挙げられます。
以上のようなIoTで安心・快適な旅行提供を実現できたことから、顧客満足度もアップしました。
参考:日本航空のDX事例
事例6|クオーレ労務経営の事例(社労士事務所)

クオーレ労務経営は、人事労務サービスと経営コンサルティングサービスを提供している社労士事務所です。
当社では従来ファイルサーバーで情報管理をしており、ファイルを探し出す時間の削減が課題でした。そこで、操作がシンプルな情報共有ツール「Stock」を導入したところ、ファイルのフォルダ管理機能、検索機能によって情報に簡単にアクセス可能になりました。
目的の情報を探す手間を削減できただけでなく、業務マニュアルや顧問先情報、社員同士のやりとりなどの全ての情報が一元化されたため、業務効率の向上に繋がったのです。
引用・参考:クオーレ労務経営の事例
事例7|長野県山ノ内町の事例(観光)

長野県山ノ内町周辺の志賀高原では、地域サイトから得られるデータを活用して収益アップとマーケティングを実現しています。
志賀高原では、観光協会が運営するサイト「CLUB SHIGA KOGEN」の顧客データベースをマーケティングに活用し、誘客を促進したほか、人工知能の分析によって顧客の関心に沿った検索内容をサイト上に表示するなど、効率的なプロモーションを実施しました。
DXの結果、志賀高原の観光事業ではサイトへの平均アクセス数が大幅に向上し、宿泊予約も増加し売上高の目標を達成しました。
参考:長野県山ノ内町の事例
DX推進に役立つ5つの技術
ここでは、DX推進に役立つ技術を5つご紹介します。各技術の特徴を押さえて自社に最適なものを使いましょう。
(1)IoT(アイオーティ)
まずは、DX推進に役立つ技術としてIoT(アイオーティ)が挙げられます
IoTは「Internet of Things」の略であり、モノのインターネットと言われます。具体的には、あるモノに取り付けられたセンサーが情報を収集してクラウド上にデータを蓄積したり、遠隔操作でセンサーの付いたモノ同士で情報共有をしたりする技術です。
以上のようなセンサーや通信機能を持った物体を使った情報共有により、機械の故障を未然に防いだり正確なデータ分析をしたりできるのです。
(2)AI(人工知能)
次に、AI(人工知能)もDX推進に役立つ技術です。
AIは「Artificial Intelligence」の略であり、代表的なものとしてはGoogleの検索エンジンや自動運転があります。また、”タスクを自動化するAI”や”あらゆる課題を解決させて学習させるAI”など、用途が多岐に渡るのも特徴です。
さらに、AIによって人間では危険の伴う作業ができるだけでなく、人件費も削減されるメリットもあるのです。
(3)5G
5G(第五世代移動通信システム)もDX推進では重要です。
5Gは「5th Generation」の略であり、3Gや4Gと比較すると通信速度の向上や低遅延化、多数同時接続といった点で優れています。また、2020年には各種携帯キャリアが5Gの運用をリリースするなど、今日におけるトレンドとなっているのです。
しかし、対応エリアが限られていたり端末の購入時に対応プランへ加入しなければならなかったりする点に注意しましょう。
(4)仮想現実(VR)/拡張現実(AR)
仮想現実(VR)・拡張現実(AR)もDXを推進する技術です。
VR(Virtual Reality)やAR(Augmented Reality)では、現実世界と全く異なる環境を作ったりコンピュータが生成したイメージやサウンドを知覚したりできます。
また、ビジネスシーンでは「バーチャルで販売店を映し、商品を実際に手にとっているような感覚で商品情報を取得できる」といった活用方法も挙げられます。
(5)クラウドサービス
最後に、クラウドサービスもDX推進に欠かせません。
クラウドサービスとは、インターネット経由でベンダー(販売業者)が提供しているシステムをスマホやPCで利用できるサービスです。自社サーバーのように保守・整備をする必要がないため、比較的簡単に始められます。
ただし、クラウドサービスを選ぶ時には、自社の課題解決にマッチしているか、検討する必要があります。そこで、自社に最適なツールの選び方や運用方法を無料相談できるツール「ナレカン」であれば、ミスなく情報を管理・共有できるのです。
DX推進における2つの課題
ここでは、DX推進における2つの課題をご紹介します。「DX化によりかえって業務が非効率になった」とならないためにも、以下の点に注意しましょう。
(1)システムの見直しに時間がかかる
まずは、DX推進の課題として、システムの見直しに時間がかかることがあります。
とくに、既存システムの運用期間が長ければ、柔軟な仕様変更や組み替えが難しいケースもあり得ます。さらに、通常業務と並行して進めなければならないことから、データの移行に多くの時間がかかってしまうのです。
したがって、システムの見直しに必要以上の時間をかけないためにも、専門業者に依頼したりITに詳しい人材を確保したりといった対策をしましょう。
(2)高度なITリテラシーが必要になる
高度なITリテラシーが必要なのも、DX推進の課題です。
DX推進のために既存システムをほかのツールに移行しようとしても、自社のITリテラシーが低く保守運用を外注している企業が多いのが現状です。このような状態ではコストがかさむだけでなく、システム移行のノウハウも蓄積されません。
また、導入したツールが社内に広まらない問題も発生してしまうため、導入から運用まで手厚いサポート体制が整っている「ナレカン」がおすすめです。
DXの定義や事例まとめ
ここまで、DXの定義や事例を中心にご紹介しました。
DXは”デジタル技術でより良い社会に変化させる動き”と定義されており、そのためにはあらゆる情報を1か所に集約する”情報共有ツール”が欠かせません。
ただし、導入前に「自社の課題解決にマッチしているか」「実務に活かせるか」をしっかりと検討することが重要です。またツールを形骸化させないためにも、「社員が使いこなせる操作性か」にも注意しましょう。
すなわち、DX推進を成功させるには、自社に最適なツールの選び方や運用方法を相談できる「ナレカン」が最適と言えます。
無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」でDXを実現し、自社をさらに成長させていきましょう。