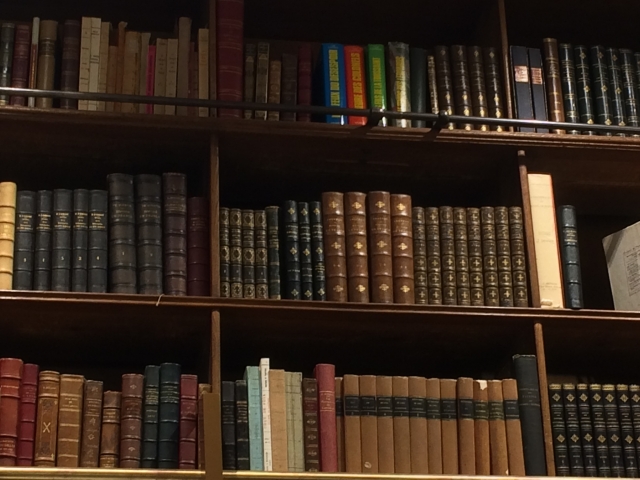コアコンピタンスとは?ケイパビリティとの違いや企業例も紹介

コアコンピタンスは、ゲイリーハメルとC・K・プラハラードの著書『コア・コンピタンス経営』によって広められた言葉です。コアコンピタンスは、今や企業の経営戦略には欠かせないキーワードとなっています。
しかし、「コアコンピタンスが具体的にどういうものか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、コアコンピタンスの意味や類語との違い、企業例を中心にご紹介します。
- コアコンピタンスの意味やケイパビリティの違いが分からない
- 企業例を参考に、コアコンピタンスの考え方を自社に取り入れたい
- 自社のコアコンピタンスの発見に役立つツールを探している
という方はこの記事を参考にすると、コアコンピタンスの意味や考え方が分かり、自社のコアコンピタンスの見極めが可能になります。
目次
コアコンピタンスとは
コアコンピタンスとは、コア(中核)とコンピタンス(能力)を組み合わせた言葉で、企業の中核となる自社ならではの強みを指します。
コアコンピタンスであるためには、単に「自社が得意」というだけでは足りず、「顧客に対して何らかの利益をもたらすこと」「競合他社が簡単に真似できないこと」「複数の市場に適応できること」の3つの要件を満たす必要があるとされています。
自社のコアコンピタンスを正しく認識すれば、顧客に自社にしかない価値を提供できます。したがって、コアコンピタンスがあると、変化の激しい競争社会において企業が継続的に成果を出し、高い競争力を保てるようになると言えるのです。
ケイパビリティとは
コアコンピタンスによく似た言葉に、ケイパビリティがあります。ケイパビリティとは、企業全体の組織的な能力という意味です。
ジョージ・ストークス、フィリップ・エバンス、ローレンス E.シュルマンの3人が1992年に発表した論文に登場する言葉ですが、コアコンピタンスが特定の技術に焦点を当てるのに対し、ケイパビリティは製品の販売や開発のプロセスに注目しています。
つまり、コアコンピタンスは組織の中核となる技術単体を指し、ケイパビリティはコアコンピタンスを実現する組織全体を指しています。
コアコンピタンス経営とは?重要視される背景を解説
コアコンピタンス経営とは、企業が他社には真似できない独自の強みであるコアコンピタンを核にして、持続的な競争優位を築く経営戦略のことです。現在では、コアコンピタンス経営が重要視されていますが、その背景には以下のような状況があります。
1980年代には、市場や競合他社の状況を考慮して、戦略的に優位に立とうとする「ポジショニング・ビュー」という考え方のもと経営をするのが一般的でした。しかし、技術革新の影響を受け、「業界内での位置取り」では競争力を維持できなくなったのです。
そこで、注目されるようになったのが、「リソース・ベースド・ビュー(RBV)」という考え方です。これは、企業内部の資源や能力を活かす考え方で、その代表例が「企業独自の強み」に着目して経営をする「コアコンピタンス経営」なのです。
要するに、市場や競合他社という「外部環境」へ適応するだけでは、競争力の維持が難しくなったため、「企業内部」に着目しようという動きの中で注目されているのが、コアコンピタンス経営だと言えます。
コアコンピタンスの企業事例
ここからはコアコンピタンスの具体的な企業事例をご紹介します。成功事例を参考に、自社のコアコンピタンスを見極めていきましょう。
事例1|本田技研工業

本田技研工業はバイクや車の製造販売のほか、小型ジェット機やロボットの開発など、幅広い事業を展開している会社です。
同社は、新型エンジンの開発によって、コアコンピタンスを確立しました。それまでは自動車メーカーとして最後発だったため、他社との差別化が難しい状況でした。
しかし、1960年代半ば、自動車の排気ガスによる大気汚染が問題視され始めたときに、他社に先駆けて大気汚染対策の厳しい基準をクリアした新型エンジンを開発したのです。
その後、新型エンジン技術はオートバイや芝刈り機など他の製品にも応用され、ブランド化に成功しました。
事例2|ソニー株式会社

ソニー株式会社は総合電機メーカーで、テレビやカメラ、スマホの開発のほか、ネットワークサービスや映像制作など、テクノロジーやエンターテインメント分野のサービスを展開する企業です。
ソニーのコアコンピタンスは、小型化技術と言えます。ポータブルで音楽を聴くことができる「ウォークマン」の発売は、コアコンピタンスの成功例です。
同社は、ウォークマンの発売前はテープレコーダーを製造販売していましたが、重さが35kgもあり持ち運べるものではなかったのです。
そこで、レコーダーの小型化に挑み、手のひらサイズの音楽再生プレイヤー「ウォークマン」を開発しました。ウォークマンはベストセラー商品になったうえ、同社はゲーム機やビデオカメラといった音楽再生プレイヤー以外の製品も小型化に成功しています。
コアコンピタンスを見極める5つの視点
ゲイリーハメルとC・K・プラハラードは著書の中で、コアコンピタンスを見極める5つの視点を紹介しています。
- 模倣可能性(Imitability)
- 移動可能性(Transferability)
- 代替可能性(Substitutability)
- 希少性(Scarcity)
- 耐久性(Durability)
自社の技術やノウハウが、競合他社は簡単には真似できないものであるかという視点です。ソニーがレコーダーの小型化を極めたように、他社が模倣しようとしてもできない高度な技術がコアコンピタンスと言えます。
自社の技術やノウハウを他分野に応用できるかという視点です。本田技研工業が車のエンジン技術をオートバイや芝刈り機に応用したように、一つの製品や分野に限らず、幅広く使用可能な技術やサービスはコアコンピタンスと言えます。
自社の技術や製品が他のものに代替できないオリジナリティがあるかという視点です。
たとえば、ソニーの「ウォークマン」は当時、小さくて持ち運べるという点でラジカセなどの他の音楽再生機器では代用できないものでした。
コアコンピタンスには、希少価値が高いかという視点もあります。
技術やサービス自体が珍しく、特定の分野に特化していることも見極めのポイントです。ただ、多くの場合は模倣可能性と代替可能性の条件を満たしていれば、希少性があると言えます。
耐久性は、長期にわたって模倣可能性、移動可能性、代替可能性、希少性を保てるかという視点です。たとえば、ソニーやホンダという名前自体にあるブランド価値が当てはまります。
耐久性が高ければ、社会環境の変化に影響を受けず、成果を上げ続けられます。
上記5つの視点を持って、自社のコアコンピタンスを見極めましょう。
自社のコアコンピタンスを見極めるステップ
自社のコアコンピタンスは以下のステップで見極めましょう。
- 自社の強みを把握する
- 自社の強みがコアコンピタンスになり得るかを評価する
- 自社のコアコンピタンスを決定する
製品やサービスだけでなく、ノウハウや技術、設備、企業文化など、さまざまな要素について考えましょう。
模倣可能性、移動可能性、代替可能性、希少性、耐久性の5つの視点から、競合他社より優れているかを比較検討していきましょう。
今までの分析や検討を踏まえながら、ターゲットとなる顧客や顧客に提供する価値を明確にし、適切に絞り込みましょう。
コアコンピタンスは、今後の経営方針に大きな影響を与えるので、慎重に決定する必要があります。
自社のコアコンピタンスの強化・活用に役立つツール
以下では、自社のコアコンピタンス発見に役立つおすすめツールをご紹介します。
コアコンピタンスは、他社が簡単に真似できない技術やノウハウの組み合わせによって生まれる自社の中核的な強みです。しかし、自社の強みが何であるかを正確に把握し、社内全体で共有・活用できていなければ、客観的な基準で判断するのは困難です。
また、ノウハウが属人化していたり、暗黙知のまま放置されていたりすると、コアコンピタンスを次世代に継承することも難しくなります。そこで、「過去の事例やノウハウを蓄積できるナレッジ管理ツール」を利用しましょう。
ITツールを利用して過去の成功事例を可視化することで、成功事例に共通する要素から自社のコアコンピタンスを導き出せます。したがって、自社のコアコンピタンスを高めるには、情報の一元化と活用ができるナレッジ管理ツール「ナレカン」一択です。
ナレカンにノウハウを共有すると、部署を超えたナレッジの活用がスムーズになります。また、継続的に情報をアップデートする仕組みが整うことで、自社の強みを未来にわたって進化させていけるのです。
自社の情報が見やすく簡単に記録できる「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
<ナレカンをおすすめするポイント>
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。
ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
コアコンピタンスの概要や企業例についてまとめ
これまで、コアコンピタンスの意味やケイパビリティとの違い、コアコンピタンスの企業例を中心にご紹介しました。
自社のコアコンピタンスを見極めるには、業務実績やノウハウから自社の強みを探すことが大切です。そのため、社内の情報は一括で管理し、いつでも閲覧できるようにしておく必要があります。
そこで、「社内の情報を簡単に管理・蓄積できるツール」が必須です。しかし、操作が複雑だと使える人が限られてしまい、十分に活用できません。
したがって、自社のコアコンピタンスを見極めるには社内のノウハウをシンプルな操作で保存できるナレッジ管理ツール「ナレカン」が最適です。
無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、自社のコアコンピタンスを見極めましょう。