【事例3選】ITリテラシーを高める方法とは?社内教育する目的を解説

近年、情報化社会が加速しており、社員のITリテラシーを高めることは不可欠です。そして、社員をサポートするためには、社内の教育体制を整備しなければなりません。
しかし、「社員を教育する具体的な方法が分からず、社員のITリテラシーが向上しない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ITリテラシー教育の目的や方法、事例を中心にご紹介します。
- ITリテラシー教育の実施にあたり、その目的を社内に浸透させたい
- ITリテラシーを高めたいが、具体的に何をすべきか分からない
- ITリテラシーの教育と並行し、社内体制を整えたい
という担当者の方はこの記事を参考にすると、社員の情報の取り扱いに対する意識を高められるだけでなく、業務を安全かつスムーズに進められる仕組みを構築できます。
目次
ITリテラシー/情報リテラシーとは
ITリテラシーとは、ネット・通信・セキュリティなどの情報技術(IT)を理解して操作する能力のことです。
よく「情報リテラシー」という言葉を耳にしますが、これはITリテラシーの要素である”情報基礎”に当てはまります。なお、ITリテラシーは、情報基礎を含む以下3種類に分類できます。
| 情報基礎リテラシー |
正しい情報を見極め、活用する能力のことです。フェイクニュースなどの嘘の情報が溢れているネット上では、必要な情報を拾い、真偽を判断する能力が必須です。 |
|---|---|
| コンピュータリテラシー |
コンピュータの仕組みを理解し、操作する能力です。キーボードやマウスの使い方だけでなく、Word、Excel、PowerPointなどを活用するための知識が必要となります。 |
| ネットワークリテラシー |
ネットワークやセキュリティに関する知識を把握する能力です。ネットワークリテラシーがあれば、ネット上での不適切な発言や情報漏洩を未然に防げます。 |
以上のように、上記の3つのITリテラシーを身につけることは、仕事の効率を上げるだけでなく、取引先企業や顧客からの信頼を得るうえで大切なのです。
ITリテラシー教育の目的
ITリテラシー教育の目的は「ITツールや情報を安全に利用できるようにすること」にあります。
ITリテラシーが欠如している職場では、誤作動などの人的ミスやサイバー攻撃による情報漏洩、SNS上での不適切な発言が起こりやすいと言えます。結果として、企業への信頼度が低下する恐れがあるのです。
そこで、ITへの理解を深め、従業員がITツールを適切に使えるようになれば、生産性の向上だけでなく企業のブランディングを守ることにつながります。したがって、企業の生産性や信頼性を損なわないために、ITリテラシーの教育が必要となるのです。
ITリテラシーが低いことで起こる5つのリスク
社員のITリテラシーが低いことで、企業の損失につながる恐れもあります。そのため、担当者は以下のリスクを念頭に置き、適切な対策を講じましょう。
(1)情報漏えいの懸念
社員のITリテラシーが低いと情報漏えいのリスクが一気に高まります。
情報の保護に対する意識や対策が足りないことが要因としてあります。例えば、メールで情報の誤送信などによる情報の流出、セキュリティの甘さゆえに外部からの情報搾取が起こり得ます。
このように、ITリテラシーは企業情報を守り、不正アクセスを防ぐために必要です。また、情報漏えいをなくすことで、会社の信頼を得ることにもつながります。
(2)生産性の低迷
ITリテラシーが低い環境では、生産性を高められません。
ITリテラシーの中には、コンピュータを適切に扱い、ツールを使いこなすことも含まれています。そのため、社員のITリテラシーが低いと業務に必要なツールの扱いに時間を要したり、ミスが生じやすくなったりしてしまいます。
特に、ExcelやPowerPointなどはどの業務においても使うことが多いため、ITに使い慣れていない社員は苦戦しやすいので注意しなければなりません。以上のように、仕事にかかる時間を減らし、生産性を上げるためにはITリテラシーが不可欠になるのです。
(3)企業のイメージダウン
ITリテラシーの低さは、企業のイメージダウンを招く恐れがあります。
ITリテラシーが低いと、ネットワークやセキュリティに関する知識が少ないため、ネット上での不祥事に繋がりやすくなります。とくに昨今では、SNSにおける情報拡散力を知らない社員が、安易に不適切な発言を書き込んでしまい、炎上するケースも多いです。
このように、一人でもITリテラシーが低い社員がいると、企業のイメージを悪化させてしまうリスクがあります。そのため、ネットの特性を理解し、適切に情報を発信できるようにひとり一人のITリテラシーを高めることが必要なのです。
(4)DXの遅れによる競争力の低下
社員のITリテラシーが低いとDXの推進に遅れが生じてしまうリスクがあります。
DXとは、デジタル技術を活用して、業務プロセスやビジネスモデル、産業構造までも変革し、競争において優位に立つことを指します。業界内でDX化に遅れをとると、顧客のニーズや市場の変化に対応しきれず、顧客満足度の低下を引き起こします。
また、DXできないていない職場では、新しい人材が集まりにくい傾向にあります。以上のように、DX推進の流れに乗れなければ、生き残り競争に勝てないため、ITリテラシー教育によってDX化の地盤を固めることは不可欠なのです。
(5)肖像権や著作権などの権利侵害
ITリテラシーが低いと、意図しないうちに権利を侵害してしまう事態になりかねません。
ChatGPTなどの普及により、情報の検索性が向上した一方、情報の出所を確認せずに引用してしまうことが懸念されます。写真や動画など、人物が映っているものを許可なくネットに載せてしまえば、肖像権の侵害になってしまいます。
そのため、権利を侵害してしまわないように、ITリテラシーを高め、情報の取り扱いに注意する必要があるのです。
【具体例あり】企業が社員のITリテラシーを高める4つの方法
ここでは、企業が社員のITリテラシーを高める方法を解説します。以下の方法を実践して、社員のITリテラシーを高めていきましょう。
社員教育の実施
従業員のITリテラシーを高めるためには、社員教育の実施が欠かせません。具体的には、社員に教えるべき基本的なIT知識として、以下の内容が挙げられます。
- ITツールの使い方
- インターネットの仕組み
- パソコン・スマホ・サーバーなどのコンピューターの仕組み
- OS・アプリケーションなどのソフトウェアの仕組み
また、社内研修では、上記の内容に加え、セキュリティリスクを周知させることも大切です。具体例を挙げると当事者意識が高まるので、総務省の【事故・被害の事例】などを利用してリスクを把握しましょう。
このように、企業が社員のために研修を用意し、実施することで、従業員全体のITリテラシーの底上げにつながるのです。
ICT環境の整備
ITリテラシー教育と並行して、順次ICT環境を整備していきましょう。
ITリテラシーを高めて、社員一人一人が情報保護の意識を持てたとしても、実際にITツールを使用しないとITリテラシーを伸ばすことはできません。しかし、ITリテラシーが十分でない状態でITツールを活用するには情報漏えいなどのリスクが伴います。
したがって、高いセキュリティを備えたシステムを導入し、安全な環境を用意しておくべきです。そこで、情報管理における国際規格の「ISO27001」を取得しているかを判断基準にシステムを選びましょう。
たとえば、ISO27001を取得し、高い安全性を誇る「ナレカン」のようなシステムを導入すれば、社員が安心して使える環境を構築できます。
資格の取得促進
ITリテラシーを高めるために、企業が社員の資格の取得を推し進めることも重要です。
いくら社内研修でITリテラシー教育を受けたとしても、自発的に勉強しようとしなければITリテラシーは向上しません。そこで、学んだことを復習し、ITに関わる知識が身についているかを確認するために資格試験を利用しましょう。
以下にITリテラシーを測るのに役立つ資格を紹介します。
- ITパスポート
- 基本情報技術者
- MOS
- P検(ICTプロフィシェンシー検定試験)
このように、資格を使って社員の自主的な学習を促すことがITリテラシーの向上に寄与します。
情報を発信する機会の提供
ITリテラシー教育を行う過程で、社員が情報を発信する機会を少しずつ増やしていきましょう。
ただ学ぶだけではなく、実践的な場を設けることは短期間でITリテラシーを上げるために有効です。情報を発信するなかで、ネット上の情報の真偽や自身が発信する情報の正確性、ネットの扱い方などを学べます。
しかし、ITリテラシーが完全ではない社員だけに情報発信させるのではなく、ITリテラシーを持つ社員が背後でサポートする必要があります。十分なサポート体制のもとで、適切な情報を発信できるような仕組みをづくりましょう。
【担当者必見】ITリテラシーに関する社内教育の事例3選
ここでは、ITリテラシーに関する社内教育の事例3選について解説します。以下の事例から得たノウハウを活用して、自社の社内教育を成功させましょう。
事例1|株式会社日本デザインセンター
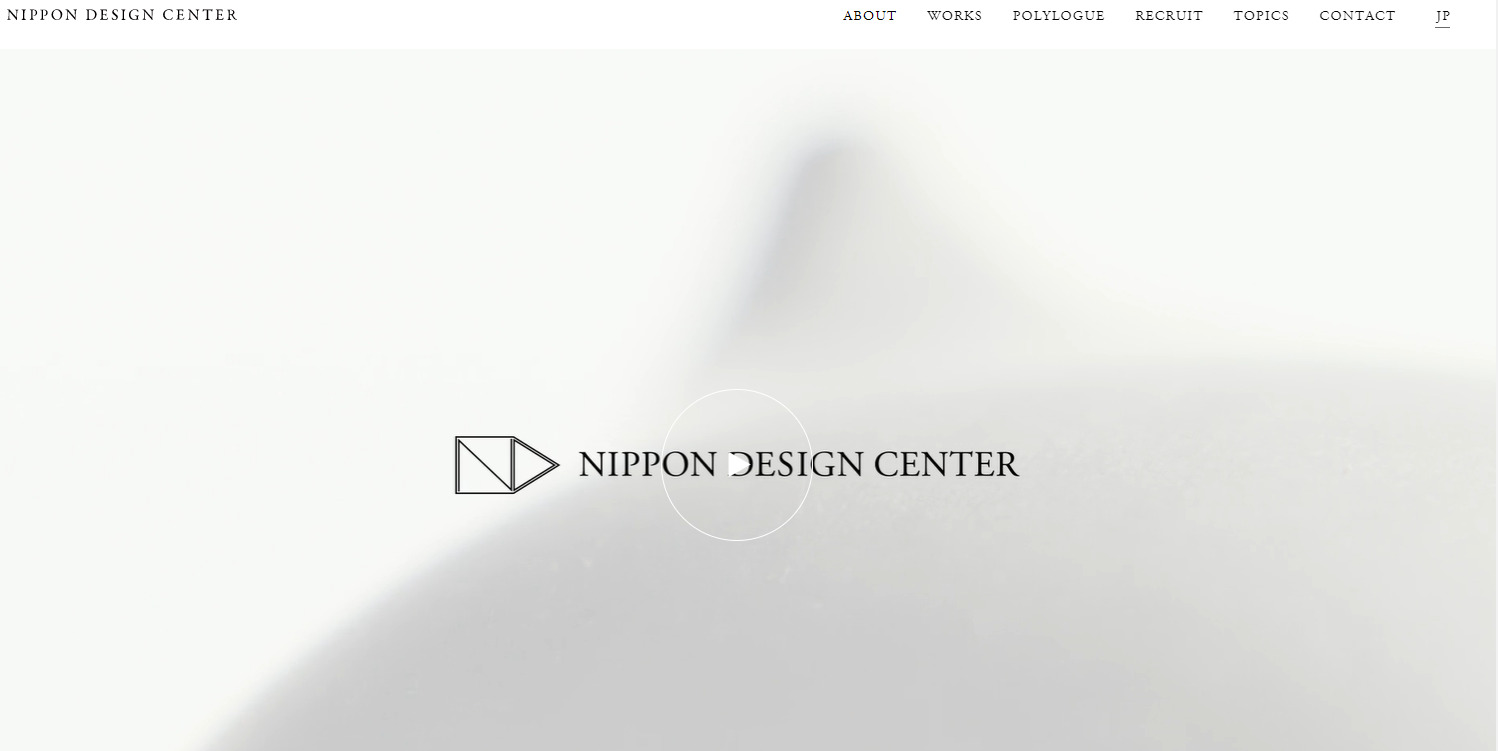
株式会社日本デザインセンターは、紙媒体のデザインを中心に制作しており、Web制作に対応できる人材が限られている課題がありました。
そこで、Web研修のサービスを利用して、全社員を対象にITリテラシー研修を実施しました。Webの仕組みを学ぶことでWebデザインへの理解が深まり、全ての社員がWeb制作スキルを身につけたのです。
その結果、既存の制作にくわえてWeb制作を含めたコミュニケーション提案が可能になり、自社の強みが強化されました。また、社員間のITリテラシーの差が埋まったため、ミーティングにおけるWebデザインの議論が活発化しました。
事例2|株式会社アントレ

株式会社アントレは、会社として独立したことで「社員研修の仕組み」や「研修を企画する知見」がない状態にありました。
そこで同社では、半期ごとに社員個々の面談をおこない、学習目標を設定しました。さらに、動画学習サービスを利用しつつ、ITツールを用いた学習共有スレッドで、学んだ授業の概要要約や感想を共有できる環境を整えたのです。
このように、学習の可視化をしたことで、社員の学習意欲が向上し、自主的な学びを促進する環境がつくられました。また、アウトプットを通して知識が定着するだけでなく、個々が学んだ内容をナレッジとして蓄積する仕組みが整備されたのです。
事例3|社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団

社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団は、対面での福祉サービスを中心に提供しているため、ITツールの活用は一部の業務に限られている課題がありました。
そこで、研修サービスを利用し、オンライン会議の実施方法やITツールの活用に関する研修を行いました。また、普段の業務でのツール活用をイメージしながら、実際にひとり一人がツールの操作を体験したのです。
このような実践的な学びによって、ツールの機能やメリットを体感でき、社員のツール活用に対する積極性が育まれました。
ITリテラシー教育中の企業でも安心して使える情報管理ツール
以下では、ITリテラシー教育中の企業でも安心して使える情報管理ツールをご紹介します。
社員ひとり一人のITリテラシーを高めるには、企業が主体となって取り組まなければなりません。しかし、ITリテラシーの定着には時間がかかるため、大企業のように人数が多いと、全員のITリテラシーを短期間で向上させるのは困難です。
そのため、企業は同時に、ITリテラシーの有無を問わず、安全に情報を管理できる環境を整えましょう。”安心して情報を管理できる仕組み”があれば、ITリテラシーの不足による情報漏洩や企業イメージの悪化を防ぐことにつながります。
結論、自社が導入すべきは、ツール本体のセキュリティ性が高く、ITリテラシーが低くても安心し使い始められる「ナレカン」一択です。
ナレカンの「記事」に書いた情報は、管理者が「フォルダ」単位でメンバーの編集/閲覧権限をコントロールできるので、情報漏えいの心配がありません。また、専属担当者が「運用設計の提案」「メンバー向けの説明会」を実施するので、ITリテラシーを教育中の企業でも安心して導入できます。
安全かつ適切に情報管理ができるツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
<ナレカンをおすすめするポイント>
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。
ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
ITリテラシー教育の目的や事例まとめ
これまで、ITリテラシー教育の目的や事例を中心にご紹介しました。
ITリテラシー教育が不足していると、ITを適切に利用できず、生産性や企業イメージへの悪影響につながります。そのため、企業はITリテラシーの教育はもちろん、ITリテラシーの有無を問わず、安全かつスムーズに作業できる環境を整えることが大切です。
とくに、業務を円滑に進めるには、情報管理の最適化が不可欠です。そこで、「すべての社員が負担なく使える情報管理ツール」を導入すると、ITリテラシー教育と並行して効率的にIT化を実現できるのです。
結論として、セキュリティ性が高く、誰でも簡単に使える「ナレカン」を使ってITリテラシーの向上と業務効率化を両立すべきです。また、ナレカンでは、専属担当者による圧倒的なサポートを受けられるので、現場に最適な環境をつくれます。
ぜひ「ナレカン」を導入して情報管理を最適化しつつ、ITリテラシー教育をおこない社員の知識を高めましょう。















