ナレッジマネジメント
お役立ちガイド
ナレッジマネジメントのノウハウや、
効率化のポイントなど、
ビジネスで役立つ情報をご紹介します。
効率化のポイントなど、
ビジネスで役立つ情報をご紹介します。

ナレッジ管理
-
 2025年03月18日ノウハウを共有しないと起こる問題とは?できない原因や解決法も解説ノウハウを共有すると、業務をスムーズに進められるようになったり、社内全体の知識レベルが向上したりするメリットがあります。しかし、組織によってはノウハウの共有がされず、属人的な業務が進行されている場合が多いのも現状です。 そのため、「ノウハウを共有しない社内文化に困っている」という方もいるのではないでしょうか。 そこで、今回はノウハウを共有しない人の特徴や、ノウハウ共有を浸透させる方法を中心に解説します。 ノウハウが共有されない組織体制なので属人化が解消されず困っている ノウハウを共有してベテランの知識を共有させたい そもそも社内に情報共有の文化がないので、今回を機に体制を変えたい という担当者の方は今回の記事を参考にすると、ノウハウ共有の重要性について理解を深めながら、すぐに社内体制を整えられる方法までわかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 社内でノウハウを共有しないことによって起こる問題1.1 社内メンバーの成長が見込めない1.2 帰属意識の低下1.3 時間を効率的に活用できない2 ノウハウ・情報共有をしない人の心理とは?2.1 ノウハウ共有の意義をわかっていない2.2 自身の評価につながらないと考えている2.3 社内でノウハウを共有する手法がない3 社内でノウハウ共有を浸透させる方法3.1 社内ミーティングで共有する3.2 ITツールを導入する4 ノウハウ共有ツールの4つの選定ポイント4.1 全ユーザーが簡単に操作できるか4.2 必要な情報へすぐにアクセスできるか4.3 情報共有できる機能があるか4.4 高いセキュリティを持っているか5 ノウハウ共有の社内文化構築におすすめなツール5.1 社内のノウハウを簡単に蓄積・共有できるツール「ナレカン」6 ノウハウ共有の概要やツール選定ポイントのまとめ 社内でノウハウを共有しないことによって起こる問題 まずは、社内でノウハウを共有しないことで発生する問題を解説します。 日常業務において、ノウハウ共有をはじめとした「情報共有」が行われていなければ、以下の問題が発生する可能性が高いので早急に見直すべきです。 社内メンバーの成長が見込めない 社内でノウハウを共有できていない場合、社員の成長が見込めなくなってしまいます。 組織では、社員同士がノウハウを共有し合うことで、新たな知識や技術を獲得でき、より質の高い成果を生み出せます。しかし、ノウハウが適切に共有されない場合、特定の社員だけが知識や情報を持ち、他の社員は新しい知識や技術を得ることができず、成長の機会を失ってしまう恐れがあるのです。 たとえば、新入社員が営業業務を進める場合、上司のノウハウを知っていれば様々な知識を得た状態で顧客にアプローチできます。一方で、ノウハウが共有されない場合、独自で知識を得なければならず、一人前に成長するまでに時間がかかってしまうのです。 このように、自社でノウハウを共有しない文化が浸透している場合、社員の成長を阻害してしまう可能性があるのです。したがって、ノウハウを「情報」として共有しやすい環境づくりが求められます。 帰属意識の低下 ノウハウを共有する環境がなければ、帰属意識の低下に繋がるリスクもあります。 ノウハウを共有していない環境は、社員同士のコミュニケーションが少ない環境ともいえます。コミュニケーションをとる機会が少ないと、信頼関係が深まらず、メンバーの帰属意識も次第に薄れてしまうのです。 また、帰属意識が薄れると、業務上共有した情報に対する認識のズレや共有漏れ、トラブルの発生などに繋がりかねません。そのため、ノウハウを共有するのはもちろん、会話の機会を増やし、帰属意識の低下を防ぐ必要があるのです。 時間を効率的に活用できない ノウハウを共有しない環境では、時間を効率的に活用できません。 ノウハウが共有されていない環境では、同じ業務に取り組んでいたとしてもベテランと経験の浅いメンバーでは作業時間に開きがでます。たとえば、タスクが並列の関係で進む業務では、ベテランが作業を完了しても経験の浅いメンバーが作業終了するまでに「待ち時間」が発生してしまうのです。 このように、ノウハウが共有されないだけで「ベテランが待つ」といった、何も成果のない時間が発生するので、スピード感が求められるビジネスにおいて非効率だといえます。効率的な時間配分で業務を進めるためにも、ノウハウは同じ業務を行うメンバーへ平等に浸透させる必要があることがわかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ・情報共有をしない人の心理とは? 社内でノウハウが共有されないことで非効率さが発生している現状は把握しつつも、ノウハウが共有される環境にならないのには原因があります。 以下でご紹介する原因が自社の現状と合致している場合は、ノウハウ共有の重要性を浸透させる必要があります。 ノウハウ共有の意義をわかっていない まず、「共有する意味がない」のように、ノウハウ共有の必要性や意義をわかっていない場合が考えられます。ノウハウ共有は日々の業務と並行して実施するものなので、メンバーは以下のように判断しがちです。 自身の作業時間を割いてまで共有する価値がない 共有するまでに手間がかかるので、ノウハウ共有が自身や企業にとってどのように役立つか理解できない そのため、ノウハウを積極的に共有してもらうためには「教育コストによって自身の業務負荷が軽くなる」「労働生産性の向上によって残業が削減できる」など、メンバー側が得られるメリットを具体的に説明する必要があります。 自身の評価につながらないと考えている ノウハウ共有の重要性は理解していても、「自身の評価にはつながらないのでやらない」というケースもあります。 このような場合、「ノウハウ共有が自社の組織力向上につながることはわかっているが、自身の評価にはつながらないので時間を割きたくない」「自身の価値を維持するのに、有益な情報を他者に伝えたくない」などのように、評価に対するデメリットを強く感じているケースが多いです。 したがって、「ナレカン」のようなノウハウの共有状況をレポートで確認できるツールを導入して、ノウハウの共有を評価制度に取り入れることで、共有を促す方法も考えられます。 社内でノウハウを共有する手法がない ノウハウ共有の重要性は理解していても、共有する手法がないケースがあります。 各メンバーが得たノウハウを共有するために、口頭や紙などのアナログな手法で伝達されがちです。しかし、このような手法では伝えるメンバーによって情報の粒度や理解度が異なるので、ノウハウを一義的に正しく共有できません。 そのため、ノウハウの共有は「ノウハウ共有ツール」を使って情報を残し、誰でも過不足なく伝わる方法で共有しなければなりません。また、ツールでノウハウを管理すると、全社員が必要な情報へすぐにアクセスできるのも特徴です。 とくに、誰でも簡単に情報を残せるツールであれば、「人によってノウハウの伝え方や粒度が異なる」といったケースも防止しつつ「言った言わない」の不毛なやりとりも発生しません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内でノウハウ共有を浸透させる方法 以下では、社内でノウハウ共有を浸透させる方法についてご紹介します。社内のノウハウ共有を定着させたいと考えている方は必見です。 社内ミーティングで共有する 社内でノウハウ共有を浸透させる方法の1つ目は、「社内ミーティングで共有する」です。 対面やオンラインでミーティングを開き、社員の日常業務における知識や最新の顧客情報などを直接交換する機会を設けます。「1週間に1回」などと開催頻度を決めれば、継続的にノウハウを共有する文化を構築できます。 一方で、社員同士での日程調整が必要なうえ、ミーティングを開くだけではノウハウの蓄積ができない点に注意が必要です。 ITツールを導入する 社内でノウハウ共有を浸透させる方法の2つ目は、「ITツールを導入する」です。 情報共有に適したITツールを使えば、時間や場所を問わず、リアルタイムでの情報共有が可能になります。また、ミーティングでの共有に比べて、情報を蓄積しやすい点もメリットと言えます。 このように、ITツールではノウハウを即座に共有して蓄積できるため、実際の業務に活用しやすいのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有ツールの4つの選定ポイント ノウハウを効率的に共有するためには、蓄積・管理するためのツールを導入することが有効です。しかし、「有名だから」「多機能だから」といった定性的な判断で自社に適さないツールを導入すると、社内に浸透しない恐れがあるのです。 そこで以下では、ノウハウ共有ツールで押さえるべき、4つの選定ポイントについて解説します。 全ユーザーが簡単に操作できるか 選定候補のツールがすべてのユーザーにとって、簡単に操作できるものであるか確認しましょう。 担当者目線では多機能で便利そうなツールを導入しても、仕組みが複雑であれば現場のメンバーが使いこなせない可能性が高く、結果として放置されてしまうからです。 また、ITリテラシーが必要なツールは設定も複雑であり、運用に乗せるまで想定以上の時間がかかってしまうこともあります。したがって、現場のメンバー全員が簡単に操作できるかは必ず確認する必要があります。 必要な情報へすぐにアクセスできるか 求めている情報へすぐにアクセスできるツールかどうかも重要なポイントです。 たとえば、ExcelやWordのように必要な情報がどれかわかりづらく、すぐに目的の情報に辿り着けないツールでは、情報を探すことに時間と手間がかかってしまいます。また、アクセス性の悪さが業務の遅れにつながる可能性もあるのです。 したがって、スピーディに業務を進めるためにも、求める情報へ迅速にアクセスできるかは押さえておくべき点です。 情報共有できる機能があるか リアルタイムで更新される機能や、メッセージなどの情報共有機能がツールにあるかも押さえましょう。 情報共有機能があれば、蓄積したノウハウを時間や場所を問わずスピーディに共有できるうえ、業務に関するコミュニケーションも円滑になります。とくに、インターネット上にデータを格納する「クラウド型」のツールであれば、リモートワークや出張時など対面で話すことが難しい場合にもやりとりができます。 また、PCだけで利用できるツールではなく、スマホやタブレットからも利用できる「マルチデバイス」のツールであると「手元にPCがなければ情報を確認できない」というストレスもなくなるのです。 高いセキュリティを持っているか 高度なセキュリティを持ち合わせているかも確認しましょう。 ノウハウ共有ツールには多くの種類がありますが、セキュリティが担保されていないツールを選んでしまった場合、ベンダーの不手際やセキュリティの脆弱さから外部に情報漏えいしてしまうリスクもあるのです。 そのため、自社の情報資産となるノウハウを守るためにも、ベンダーの公式サイトに掲載されている「セキュリティポリシー」は必ず確認し、自社のセキュリティ要件とマッチしているかの確認をすべきです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有の社内文化構築におすすめなツール 以下では、ノウハウ共有の社内文化構築におすすめのツールをご紹介します。 ノウハウを共有しない社内文化に困っている場合には、「ノウハウや情報を簡単に共有できるツール」を導入しましょう。紙や口頭での共有に比べて、印刷や会議のために集まるといった手間が省け、情報を即座に共有できます。 しかし、多機能で操作の難しいツールでは、ノウハウを共有するのが面倒になり、結局社内にノウハウ共有の文化が定着しません。そのため、「誰でも簡単にノウハウ・情報共有ができるツール」がおすすめです 結論、ノウハウ共有には、社内のあらゆる情報やノウハウを簡単に共有できるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」では、画像・ファイルを含む社内情報やノウハウをリアルタイムで任意のメンバーに共有できます。また、シンプルで直感的に操作できるので、スムーズに社内に浸透します。 社内のノウハウを簡単に蓄積・共有できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有の概要やツール選定ポイントのまとめ これまで、ノウハウ共有の重要性やツールを選定する際のポイントを中心にご紹介してきました。 ノウハウを共有しなければ社内メンバーの成長が見込めず帰属意識の低下、時間を効率的に活用できない問題点がありました。しかし、ノウハウ共有に対する意識の低さや手法が確立されていないケースもあるので、社内体制から見直す必要があります。 そのため、ノウハウ共有ツールを用いた情報管理への体制変更が必要です。ノウハウの共有機能はもちろん、情報へのアクセス性やセキュリティの高さが見るべきポイントな一方、「誰でも使える操作性」はツールを社内に浸透させるうえで大前提な点に注意です。 ご紹介した選定ポイントをすべて満たす「ナレカン」は、誰でも簡単に使えるほどシンプルなツールであり、ノウハウ共有に必要な機能が「過不足なく」備わっています。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、ノウハウが自然と共有される環境を作りましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年03月18日ノウハウを共有しないと起こる問題とは?できない原因や解決法も解説ノウハウを共有すると、業務をスムーズに進められるようになったり、社内全体の知識レベルが向上したりするメリットがあります。しかし、組織によってはノウハウの共有がされず、属人的な業務が進行されている場合が多いのも現状です。 そのため、「ノウハウを共有しない社内文化に困っている」という方もいるのではないでしょうか。 そこで、今回はノウハウを共有しない人の特徴や、ノウハウ共有を浸透させる方法を中心に解説します。 ノウハウが共有されない組織体制なので属人化が解消されず困っている ノウハウを共有してベテランの知識を共有させたい そもそも社内に情報共有の文化がないので、今回を機に体制を変えたい という担当者の方は今回の記事を参考にすると、ノウハウ共有の重要性について理解を深めながら、すぐに社内体制を整えられる方法までわかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 社内でノウハウを共有しないことによって起こる問題1.1 社内メンバーの成長が見込めない1.2 帰属意識の低下1.3 時間を効率的に活用できない2 ノウハウ・情報共有をしない人の心理とは?2.1 ノウハウ共有の意義をわかっていない2.2 自身の評価につながらないと考えている2.3 社内でノウハウを共有する手法がない3 社内でノウハウ共有を浸透させる方法3.1 社内ミーティングで共有する3.2 ITツールを導入する4 ノウハウ共有ツールの4つの選定ポイント4.1 全ユーザーが簡単に操作できるか4.2 必要な情報へすぐにアクセスできるか4.3 情報共有できる機能があるか4.4 高いセキュリティを持っているか5 ノウハウ共有の社内文化構築におすすめなツール5.1 社内のノウハウを簡単に蓄積・共有できるツール「ナレカン」6 ノウハウ共有の概要やツール選定ポイントのまとめ 社内でノウハウを共有しないことによって起こる問題 まずは、社内でノウハウを共有しないことで発生する問題を解説します。 日常業務において、ノウハウ共有をはじめとした「情報共有」が行われていなければ、以下の問題が発生する可能性が高いので早急に見直すべきです。 社内メンバーの成長が見込めない 社内でノウハウを共有できていない場合、社員の成長が見込めなくなってしまいます。 組織では、社員同士がノウハウを共有し合うことで、新たな知識や技術を獲得でき、より質の高い成果を生み出せます。しかし、ノウハウが適切に共有されない場合、特定の社員だけが知識や情報を持ち、他の社員は新しい知識や技術を得ることができず、成長の機会を失ってしまう恐れがあるのです。 たとえば、新入社員が営業業務を進める場合、上司のノウハウを知っていれば様々な知識を得た状態で顧客にアプローチできます。一方で、ノウハウが共有されない場合、独自で知識を得なければならず、一人前に成長するまでに時間がかかってしまうのです。 このように、自社でノウハウを共有しない文化が浸透している場合、社員の成長を阻害してしまう可能性があるのです。したがって、ノウハウを「情報」として共有しやすい環境づくりが求められます。 帰属意識の低下 ノウハウを共有する環境がなければ、帰属意識の低下に繋がるリスクもあります。 ノウハウを共有していない環境は、社員同士のコミュニケーションが少ない環境ともいえます。コミュニケーションをとる機会が少ないと、信頼関係が深まらず、メンバーの帰属意識も次第に薄れてしまうのです。 また、帰属意識が薄れると、業務上共有した情報に対する認識のズレや共有漏れ、トラブルの発生などに繋がりかねません。そのため、ノウハウを共有するのはもちろん、会話の機会を増やし、帰属意識の低下を防ぐ必要があるのです。 時間を効率的に活用できない ノウハウを共有しない環境では、時間を効率的に活用できません。 ノウハウが共有されていない環境では、同じ業務に取り組んでいたとしてもベテランと経験の浅いメンバーでは作業時間に開きがでます。たとえば、タスクが並列の関係で進む業務では、ベテランが作業を完了しても経験の浅いメンバーが作業終了するまでに「待ち時間」が発生してしまうのです。 このように、ノウハウが共有されないだけで「ベテランが待つ」といった、何も成果のない時間が発生するので、スピード感が求められるビジネスにおいて非効率だといえます。効率的な時間配分で業務を進めるためにも、ノウハウは同じ業務を行うメンバーへ平等に浸透させる必要があることがわかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ・情報共有をしない人の心理とは? 社内でノウハウが共有されないことで非効率さが発生している現状は把握しつつも、ノウハウが共有される環境にならないのには原因があります。 以下でご紹介する原因が自社の現状と合致している場合は、ノウハウ共有の重要性を浸透させる必要があります。 ノウハウ共有の意義をわかっていない まず、「共有する意味がない」のように、ノウハウ共有の必要性や意義をわかっていない場合が考えられます。ノウハウ共有は日々の業務と並行して実施するものなので、メンバーは以下のように判断しがちです。 自身の作業時間を割いてまで共有する価値がない 共有するまでに手間がかかるので、ノウハウ共有が自身や企業にとってどのように役立つか理解できない そのため、ノウハウを積極的に共有してもらうためには「教育コストによって自身の業務負荷が軽くなる」「労働生産性の向上によって残業が削減できる」など、メンバー側が得られるメリットを具体的に説明する必要があります。 自身の評価につながらないと考えている ノウハウ共有の重要性は理解していても、「自身の評価にはつながらないのでやらない」というケースもあります。 このような場合、「ノウハウ共有が自社の組織力向上につながることはわかっているが、自身の評価にはつながらないので時間を割きたくない」「自身の価値を維持するのに、有益な情報を他者に伝えたくない」などのように、評価に対するデメリットを強く感じているケースが多いです。 したがって、「ナレカン」のようなノウハウの共有状況をレポートで確認できるツールを導入して、ノウハウの共有を評価制度に取り入れることで、共有を促す方法も考えられます。 社内でノウハウを共有する手法がない ノウハウ共有の重要性は理解していても、共有する手法がないケースがあります。 各メンバーが得たノウハウを共有するために、口頭や紙などのアナログな手法で伝達されがちです。しかし、このような手法では伝えるメンバーによって情報の粒度や理解度が異なるので、ノウハウを一義的に正しく共有できません。 そのため、ノウハウの共有は「ノウハウ共有ツール」を使って情報を残し、誰でも過不足なく伝わる方法で共有しなければなりません。また、ツールでノウハウを管理すると、全社員が必要な情報へすぐにアクセスできるのも特徴です。 とくに、誰でも簡単に情報を残せるツールであれば、「人によってノウハウの伝え方や粒度が異なる」といったケースも防止しつつ「言った言わない」の不毛なやりとりも発生しません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内でノウハウ共有を浸透させる方法 以下では、社内でノウハウ共有を浸透させる方法についてご紹介します。社内のノウハウ共有を定着させたいと考えている方は必見です。 社内ミーティングで共有する 社内でノウハウ共有を浸透させる方法の1つ目は、「社内ミーティングで共有する」です。 対面やオンラインでミーティングを開き、社員の日常業務における知識や最新の顧客情報などを直接交換する機会を設けます。「1週間に1回」などと開催頻度を決めれば、継続的にノウハウを共有する文化を構築できます。 一方で、社員同士での日程調整が必要なうえ、ミーティングを開くだけではノウハウの蓄積ができない点に注意が必要です。 ITツールを導入する 社内でノウハウ共有を浸透させる方法の2つ目は、「ITツールを導入する」です。 情報共有に適したITツールを使えば、時間や場所を問わず、リアルタイムでの情報共有が可能になります。また、ミーティングでの共有に比べて、情報を蓄積しやすい点もメリットと言えます。 このように、ITツールではノウハウを即座に共有して蓄積できるため、実際の業務に活用しやすいのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有ツールの4つの選定ポイント ノウハウを効率的に共有するためには、蓄積・管理するためのツールを導入することが有効です。しかし、「有名だから」「多機能だから」といった定性的な判断で自社に適さないツールを導入すると、社内に浸透しない恐れがあるのです。 そこで以下では、ノウハウ共有ツールで押さえるべき、4つの選定ポイントについて解説します。 全ユーザーが簡単に操作できるか 選定候補のツールがすべてのユーザーにとって、簡単に操作できるものであるか確認しましょう。 担当者目線では多機能で便利そうなツールを導入しても、仕組みが複雑であれば現場のメンバーが使いこなせない可能性が高く、結果として放置されてしまうからです。 また、ITリテラシーが必要なツールは設定も複雑であり、運用に乗せるまで想定以上の時間がかかってしまうこともあります。したがって、現場のメンバー全員が簡単に操作できるかは必ず確認する必要があります。 必要な情報へすぐにアクセスできるか 求めている情報へすぐにアクセスできるツールかどうかも重要なポイントです。 たとえば、ExcelやWordのように必要な情報がどれかわかりづらく、すぐに目的の情報に辿り着けないツールでは、情報を探すことに時間と手間がかかってしまいます。また、アクセス性の悪さが業務の遅れにつながる可能性もあるのです。 したがって、スピーディに業務を進めるためにも、求める情報へ迅速にアクセスできるかは押さえておくべき点です。 情報共有できる機能があるか リアルタイムで更新される機能や、メッセージなどの情報共有機能がツールにあるかも押さえましょう。 情報共有機能があれば、蓄積したノウハウを時間や場所を問わずスピーディに共有できるうえ、業務に関するコミュニケーションも円滑になります。とくに、インターネット上にデータを格納する「クラウド型」のツールであれば、リモートワークや出張時など対面で話すことが難しい場合にもやりとりができます。 また、PCだけで利用できるツールではなく、スマホやタブレットからも利用できる「マルチデバイス」のツールであると「手元にPCがなければ情報を確認できない」というストレスもなくなるのです。 高いセキュリティを持っているか 高度なセキュリティを持ち合わせているかも確認しましょう。 ノウハウ共有ツールには多くの種類がありますが、セキュリティが担保されていないツールを選んでしまった場合、ベンダーの不手際やセキュリティの脆弱さから外部に情報漏えいしてしまうリスクもあるのです。 そのため、自社の情報資産となるノウハウを守るためにも、ベンダーの公式サイトに掲載されている「セキュリティポリシー」は必ず確認し、自社のセキュリティ要件とマッチしているかの確認をすべきです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有の社内文化構築におすすめなツール 以下では、ノウハウ共有の社内文化構築におすすめのツールをご紹介します。 ノウハウを共有しない社内文化に困っている場合には、「ノウハウや情報を簡単に共有できるツール」を導入しましょう。紙や口頭での共有に比べて、印刷や会議のために集まるといった手間が省け、情報を即座に共有できます。 しかし、多機能で操作の難しいツールでは、ノウハウを共有するのが面倒になり、結局社内にノウハウ共有の文化が定着しません。そのため、「誰でも簡単にノウハウ・情報共有ができるツール」がおすすめです 結論、ノウハウ共有には、社内のあらゆる情報やノウハウを簡単に共有できるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」では、画像・ファイルを含む社内情報やノウハウをリアルタイムで任意のメンバーに共有できます。また、シンプルで直感的に操作できるので、スムーズに社内に浸透します。 社内のノウハウを簡単に蓄積・共有できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有の概要やツール選定ポイントのまとめ これまで、ノウハウ共有の重要性やツールを選定する際のポイントを中心にご紹介してきました。 ノウハウを共有しなければ社内メンバーの成長が見込めず帰属意識の低下、時間を効率的に活用できない問題点がありました。しかし、ノウハウ共有に対する意識の低さや手法が確立されていないケースもあるので、社内体制から見直す必要があります。 そのため、ノウハウ共有ツールを用いた情報管理への体制変更が必要です。ノウハウの共有機能はもちろん、情報へのアクセス性やセキュリティの高さが見るべきポイントな一方、「誰でも使える操作性」はツールを社内に浸透させるうえで大前提な点に注意です。 ご紹介した選定ポイントをすべて満たす「ナレカン」は、誰でも簡単に使えるほどシンプルなツールであり、ノウハウ共有に必要な機能が「過不足なく」備わっています。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、ノウハウが自然と共有される環境を作りましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年03月18日ノウハウコレクターとは?特徴や脱出する方法を解説!知識だけがありビジネスに活かせない状態になる人を「ノウハウコレクター」と呼びます。ノウハウを蓄積する作業は大切ですが、ビジネスを成功させるには行動して情報を活かさなければなりません。 しかし、蓄積したノウハウを活用したいとは考えているものの「ノウハウを社内でうまく共有できない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ノウハウコレクターの特徴やノウハウコレクターを抜け出す方法を中心にご紹介します。 ノウハウコレクターの特徴を理解し、適切に対応できるようにしたい ノウハウコレクターの脱出方法を知り、業務を円滑に行えるようにしたい 蓄積したノウハウを効果的に活用する方法が知りたい という方は今回の記事を参考にすると、ノウハウコレクターから脱出してビジネスを成功につなげるためのヒントが得られます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ノウハウコレクターとは2 ノウハウコレクターの心理や特徴とは2.1 情報を集めないと不安2.2 ノウハウの実践を後回しにしてしまう2.3 常に受け身の姿勢3 ノウハウコレクターの失敗例4 ノウハウコレクターを脱出する方法とは4.1 ノウハウの内容を継続して実践する4.2 行動と分析を繰り返す4.3 蓄積したノウハウを共有する5 ノウハウコレクターの卒業におすすめのツール5.1 蓄積したノウハウを最も簡単に可視化できるツール「ナレカン」6 ノウハウコレクターの脱出法まとめ ノウハウコレクターとは 「ノウハウコレクター」とは、ビジネスで成功するための知識や情報を多く得ているものの、知識を集めるだけでビジネスに活用できていなかったり、収益をあげられていなかったりする人を指します。 一般的にノウハウコレクターは、ネット上の情報商材や書籍を通して多くの知識を持っているものの、思うような収益をあげられない状態にあり、情報を得るだけで満足してしまうというケースが多いです。 また、新しい情報を得ていくうちに「ノウハウを得る行為」自体が目的になり、行動を起こせなくなる場合もあります。よって、ビジネスの成功のためにはノウハウコレクターとなることを避け、情報を実際の行動に活かしていくことが重要になるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウコレクターの心理や特徴とは ここからは、ノウハウコレクターの心理や特徴を解説します。以下で紹介する特徴に当てはまる社員がいた場合は、該当社員が行動へ移せるように対処する必要があります。 情報を集めないと不安 情報を集めないと不安に感じることが、ノウハウコレクターにありがちな特徴です。 「いつか役に立つだろう」「知っておけば安心」などの理由で、優先度の高くない情報まで収集し、次第に情報の収集自体が目的になってしまうのです。 このように、情報を集めなければ不安な状態になり、情報収集のみに時間を割きすぎているケースでは、収集する情報の取捨選択が重要であることを社員自身に認識させる必要があります。 ノウハウの実践を後回しにしてしまう ノウハウの実践を後回しにしてしまうことも、ノウハウコレクターの特徴です。 ノウハウの実践よりも集めることを優先してしまい、結局集めたノウハウが活用されないケースもあります。しかし、いくらノウハウを多く持っていても、行動や業務につなげられていなければ結果は現れません。 このように、実践が後回しになっている場合は「情報を得たらすぐに行動へ移す」など、収集した情報を実際の行動と結びつけられるようにすることが重要です。 常に受け身の姿勢 常に受け身の姿勢であることも、ノウハウコレクターの特徴です。 情報を「与えられる」認識でいると、情報のインプットのみに意識が向いて行動が起こせなくなってしまいます。ノウハウコレクターを脱するには、情報は与えられるものではなく実践を通じて活用するものであると認識しなくてはなりません。 たとえば、ノウハウに対する気付きや改善策を社内で交換する場を設けるなど、アウトプットの機会を増やすことが重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウコレクターの失敗例 ノウハウコレクターの失敗例としては「ノウハウの収集」自体が目的になっているために収集したノウハウを業務に活かせず、組織全体の成長が妨げられるケースが挙げられます。 このように、ノウハウの収集が目的化している場合には、「収集したノウハウをすぐに社内に共有し、活用すること」が重要です。ノウハウを共有することで、情報の属人化を防ぎながら、社内全体で実際の業務に活用するきっかけを生み出せるのです。 しかし、ノウハウを共有できる環境が構築されていなかったり、共有できる場所はあっても簡単に共有できなかったりすると、蓄積したノウハウをアウトプットできないために知識が属人化しやすく、業務スピードの停滞を招いてしまいます。 したがって、「ナレカン」のようにシンプルで誰でも簡単に操作できるツールを使って、ノウハウ共有が活発化するような環境を構築する必要があるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウコレクターを脱出する方法とは ここからは、ノウハウコレクターを脱出する方法を解説します。以下の内容が把握できていなければ、ノウハウを適切に活用できず業務が停滞する原因になってしまうため注意しましょう。 ノウハウの内容を継続して実践する まずは、ノウハウの内容を継続して実践することが重要です。 ノウハウは実際の業務に活用して始めて成果につながるため、まずは実践してみることが重要です。しかし、どのような業務においても、結果が出るまでには時間がかかります。 よって、ノウハウコレクターを脱出するには、すぐに結果が出なくても継続して実践することが重要なのです。たとえば、一定期間でノウハウの内容を実践する計画を立て、行動してみることが有効です。 このように、ノウハウコレクターを脱出するには、すぐに結果が出ない場合でも継続性を持って行動する必要があります。 行動と分析を繰り返す 行動を起こしたら、内容を振り返り分析することも重要です。 ノウハウの活用を効果的に進めるには「ノウハウをもとにした行動が進捗にどのような影響を与えたか」などを、数値や施策の打ち方を振り返りながら分析し、改善していく必要があります。 このように、行動と分析を繰り返すと、ノウハウの内容がブラッシュアップされていくので、有効なノウハウを業務に活かせるようになります。 蓄積したノウハウを共有する ノウハウコレクターを脱出するためには、蓄積したノウハウを共有することも重要です。 ノウハウコレクターになる原因のひとつとして、蓄積した情報の活用方法がわからないことが挙げられます。このような場合には、今までに蓄積した情報を社内に共有し、社内全体で活用するのがおすすめです。 具体的な方法としては、今までに蓄積したノウハウの中から、自社の業務に活用できそうなノウハウを選んで社内に共有します。ただし、紙での共有には印刷や配付などの手間がかかるので、簡単に情報を共有できる「ナレカン」のようなツールで共有する方法がおすすめです。 このように、ノウハウを共有すると、情報の属人化を防止しながら社内全体の業務効率化に貢献できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウコレクターの卒業におすすめのツール 以下では、ノウハウコレクターの卒業におすすめのITツールをご紹介します。 ノウハウコレクターを脱出するには、蓄積したノウハウを整理して社内共有できる仕組みづくりが重要です。そこで、「収集したノウハウを簡単に共有できるツール」を導入すると、ほかのメンバーに情報共有しやすくなります。 しかし、多機能で操作が難しいツールでは、ノウハウを共有するのに時間や手間がかかり、結局ノウハウコレクターから脱却できない事態になりかねません。したがって、「誰でも簡単に操作できる情報共有ツール」を使いましょう。 結論、社内のノウハウ共有には、直感的な操作で誰でも簡単にノウハウの共有・管理ができるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」では、簡単にノウハウをまとめられるうえ、リアルタイムですぐに共有可能です。また、ノウハウを持っている社内メンバーに質問できる「質問機能」で、ノウハウが属人化する事態も防げます。 蓄積したノウハウを最も簡単に可視化できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウコレクターの脱出法まとめ これまで、ノウハウコレクターの特徴や失敗例、ノウハウコレクターから抜け出す方法を紹介しました。 蓄積した情報を活用しないままでは、知識の属人化が進み、組織全体の成長が妨げられてしまいます。そこで、ノウハウを社内で共有すると、ノウハウコレクターから脱出しながら組織力の向上にも貢献します。 しかし、ノートやメモにノウハウを書き出していると、情報がどこにあるか分からなくなったり、書き込みが面倒になったりする可能性があります。したがって、簡単に情報を書き込めて、かつ適切に共有・管理できるツールを使う必要があるのです。 ノウハウコレクターのノウハウを自社に還元するためにも、誰でも簡単にノウハウの共有・確認ができる情報共有ツール「ナレカン」を使って「社内の情報資産を構築」「ノウハウ共有の活性化」を両立すべきと言えます。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、ノウハウコレクターからの脱却を図りましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年03月18日ノウハウコレクターとは?特徴や脱出する方法を解説!知識だけがありビジネスに活かせない状態になる人を「ノウハウコレクター」と呼びます。ノウハウを蓄積する作業は大切ですが、ビジネスを成功させるには行動して情報を活かさなければなりません。 しかし、蓄積したノウハウを活用したいとは考えているものの「ノウハウを社内でうまく共有できない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ノウハウコレクターの特徴やノウハウコレクターを抜け出す方法を中心にご紹介します。 ノウハウコレクターの特徴を理解し、適切に対応できるようにしたい ノウハウコレクターの脱出方法を知り、業務を円滑に行えるようにしたい 蓄積したノウハウを効果的に活用する方法が知りたい という方は今回の記事を参考にすると、ノウハウコレクターから脱出してビジネスを成功につなげるためのヒントが得られます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ノウハウコレクターとは2 ノウハウコレクターの心理や特徴とは2.1 情報を集めないと不安2.2 ノウハウの実践を後回しにしてしまう2.3 常に受け身の姿勢3 ノウハウコレクターの失敗例4 ノウハウコレクターを脱出する方法とは4.1 ノウハウの内容を継続して実践する4.2 行動と分析を繰り返す4.3 蓄積したノウハウを共有する5 ノウハウコレクターの卒業におすすめのツール5.1 蓄積したノウハウを最も簡単に可視化できるツール「ナレカン」6 ノウハウコレクターの脱出法まとめ ノウハウコレクターとは 「ノウハウコレクター」とは、ビジネスで成功するための知識や情報を多く得ているものの、知識を集めるだけでビジネスに活用できていなかったり、収益をあげられていなかったりする人を指します。 一般的にノウハウコレクターは、ネット上の情報商材や書籍を通して多くの知識を持っているものの、思うような収益をあげられない状態にあり、情報を得るだけで満足してしまうというケースが多いです。 また、新しい情報を得ていくうちに「ノウハウを得る行為」自体が目的になり、行動を起こせなくなる場合もあります。よって、ビジネスの成功のためにはノウハウコレクターとなることを避け、情報を実際の行動に活かしていくことが重要になるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウコレクターの心理や特徴とは ここからは、ノウハウコレクターの心理や特徴を解説します。以下で紹介する特徴に当てはまる社員がいた場合は、該当社員が行動へ移せるように対処する必要があります。 情報を集めないと不安 情報を集めないと不安に感じることが、ノウハウコレクターにありがちな特徴です。 「いつか役に立つだろう」「知っておけば安心」などの理由で、優先度の高くない情報まで収集し、次第に情報の収集自体が目的になってしまうのです。 このように、情報を集めなければ不安な状態になり、情報収集のみに時間を割きすぎているケースでは、収集する情報の取捨選択が重要であることを社員自身に認識させる必要があります。 ノウハウの実践を後回しにしてしまう ノウハウの実践を後回しにしてしまうことも、ノウハウコレクターの特徴です。 ノウハウの実践よりも集めることを優先してしまい、結局集めたノウハウが活用されないケースもあります。しかし、いくらノウハウを多く持っていても、行動や業務につなげられていなければ結果は現れません。 このように、実践が後回しになっている場合は「情報を得たらすぐに行動へ移す」など、収集した情報を実際の行動と結びつけられるようにすることが重要です。 常に受け身の姿勢 常に受け身の姿勢であることも、ノウハウコレクターの特徴です。 情報を「与えられる」認識でいると、情報のインプットのみに意識が向いて行動が起こせなくなってしまいます。ノウハウコレクターを脱するには、情報は与えられるものではなく実践を通じて活用するものであると認識しなくてはなりません。 たとえば、ノウハウに対する気付きや改善策を社内で交換する場を設けるなど、アウトプットの機会を増やすことが重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウコレクターの失敗例 ノウハウコレクターの失敗例としては「ノウハウの収集」自体が目的になっているために収集したノウハウを業務に活かせず、組織全体の成長が妨げられるケースが挙げられます。 このように、ノウハウの収集が目的化している場合には、「収集したノウハウをすぐに社内に共有し、活用すること」が重要です。ノウハウを共有することで、情報の属人化を防ぎながら、社内全体で実際の業務に活用するきっかけを生み出せるのです。 しかし、ノウハウを共有できる環境が構築されていなかったり、共有できる場所はあっても簡単に共有できなかったりすると、蓄積したノウハウをアウトプットできないために知識が属人化しやすく、業務スピードの停滞を招いてしまいます。 したがって、「ナレカン」のようにシンプルで誰でも簡単に操作できるツールを使って、ノウハウ共有が活発化するような環境を構築する必要があるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウコレクターを脱出する方法とは ここからは、ノウハウコレクターを脱出する方法を解説します。以下の内容が把握できていなければ、ノウハウを適切に活用できず業務が停滞する原因になってしまうため注意しましょう。 ノウハウの内容を継続して実践する まずは、ノウハウの内容を継続して実践することが重要です。 ノウハウは実際の業務に活用して始めて成果につながるため、まずは実践してみることが重要です。しかし、どのような業務においても、結果が出るまでには時間がかかります。 よって、ノウハウコレクターを脱出するには、すぐに結果が出なくても継続して実践することが重要なのです。たとえば、一定期間でノウハウの内容を実践する計画を立て、行動してみることが有効です。 このように、ノウハウコレクターを脱出するには、すぐに結果が出ない場合でも継続性を持って行動する必要があります。 行動と分析を繰り返す 行動を起こしたら、内容を振り返り分析することも重要です。 ノウハウの活用を効果的に進めるには「ノウハウをもとにした行動が進捗にどのような影響を与えたか」などを、数値や施策の打ち方を振り返りながら分析し、改善していく必要があります。 このように、行動と分析を繰り返すと、ノウハウの内容がブラッシュアップされていくので、有効なノウハウを業務に活かせるようになります。 蓄積したノウハウを共有する ノウハウコレクターを脱出するためには、蓄積したノウハウを共有することも重要です。 ノウハウコレクターになる原因のひとつとして、蓄積した情報の活用方法がわからないことが挙げられます。このような場合には、今までに蓄積した情報を社内に共有し、社内全体で活用するのがおすすめです。 具体的な方法としては、今までに蓄積したノウハウの中から、自社の業務に活用できそうなノウハウを選んで社内に共有します。ただし、紙での共有には印刷や配付などの手間がかかるので、簡単に情報を共有できる「ナレカン」のようなツールで共有する方法がおすすめです。 このように、ノウハウを共有すると、情報の属人化を防止しながら社内全体の業務効率化に貢献できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウコレクターの卒業におすすめのツール 以下では、ノウハウコレクターの卒業におすすめのITツールをご紹介します。 ノウハウコレクターを脱出するには、蓄積したノウハウを整理して社内共有できる仕組みづくりが重要です。そこで、「収集したノウハウを簡単に共有できるツール」を導入すると、ほかのメンバーに情報共有しやすくなります。 しかし、多機能で操作が難しいツールでは、ノウハウを共有するのに時間や手間がかかり、結局ノウハウコレクターから脱却できない事態になりかねません。したがって、「誰でも簡単に操作できる情報共有ツール」を使いましょう。 結論、社内のノウハウ共有には、直感的な操作で誰でも簡単にノウハウの共有・管理ができるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」では、簡単にノウハウをまとめられるうえ、リアルタイムですぐに共有可能です。また、ノウハウを持っている社内メンバーに質問できる「質問機能」で、ノウハウが属人化する事態も防げます。 蓄積したノウハウを最も簡単に可視化できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウコレクターの脱出法まとめ これまで、ノウハウコレクターの特徴や失敗例、ノウハウコレクターから抜け出す方法を紹介しました。 蓄積した情報を活用しないままでは、知識の属人化が進み、組織全体の成長が妨げられてしまいます。そこで、ノウハウを社内で共有すると、ノウハウコレクターから脱出しながら組織力の向上にも貢献します。 しかし、ノートやメモにノウハウを書き出していると、情報がどこにあるか分からなくなったり、書き込みが面倒になったりする可能性があります。したがって、簡単に情報を書き込めて、かつ適切に共有・管理できるツールを使う必要があるのです。 ノウハウコレクターのノウハウを自社に還元するためにも、誰でも簡単にノウハウの共有・確認ができる情報共有ツール「ナレカン」を使って「社内の情報資産を構築」「ノウハウ共有の活性化」を両立すべきと言えます。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、ノウハウコレクターからの脱却を図りましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年03月18日ノウハウの蓄積・管理を成功させるには?おすすめツールも紹介自社のノウハウは適切に蓄積・管理して社内資産化すべきです。優れたノウハウが横展開・縦展開されることなく属人化すれば、社員ごとの作業クオリティに差が生じてしまい「特定の人にしか業務を任せられない」という悪循環を生み出してしまいます。 しかし、「ノウハウを社内に展開したいが、具体的に何をすれば良いか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ノウハウの蓄積・管理を成功させる方法や、ノウハウの継承におすすめのツールを中心にご紹介します。 ノウハウの蓄積や管理を効率化させる方法が知りたい ノウハウを社内に蓄積・管理できるツールを探している ノウハウの蓄積だけでなく、すぐに検索できるツールを選びたい という方はこの記事を参考にすると、簡単かつ適切にノウハウを蓄積・管理できるようになり、社内の業務負担が大幅に解消されます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ノウハウを蓄積・管理するには1.1 ノウハウの蓄積・管理が求められる理由1.2 ノウハウとナレッジの違い2 ノウハウの蓄積・管理によるメリット2.1 (1)ノウハウを継承できる2.2 (2)業務効率化につながる2.3 (3)集合知を作り出せる2.4 (4)ノウハウを改善できる2.5 (5)社員のスキルアップにつながる3 ノウハウの蓄積・管理を効率化させる方法3.1 ノウハウの重要性を周知する3.2 蓄積するノウハウを整理する3.3 ITツールを導入・運用する4 最も簡単に社内のノウハウを蓄積・管理できるツール4.1 社内のノウハウ蓄積・管理を成功させる「ナレカン」5 【担当者は必見】ノウハウ蓄積ツールにおける3つの選定ポイント5.1 (1)情報を簡単に蓄積できるか5.2 (2)情報にすぐにアクセスできるか5.3 (3)社内に定着するか6 ノウハウの蓄積・管理ができるツールの種類6.1 社内wiki6.2 ビジネスチャット6.3 オンラインストレージ6.4 ナレッジ管理ツール7 ノウハウの蓄積・管理によるメリットまとめ ノウハウを蓄積・管理するには 適切にノウハウを蓄積していくために、まずは「ノウハウを蓄積する理由」や「第一にノウハウは何を指すのか」という疑問を解消しましょう。 ノウハウの蓄積・管理が求められる理由 ノウハウの蓄積・管理をする理由は、チームの業務処理速度を上げるためです。 そもそも「ノウハウを蓄積する」とは、各社員がそれまでの業務から得た経験や教訓などの暗黙知(言語化しづらい知識)を、文書や図として社内に浸透させることを指します。 たとえば、特殊な業務を扱う部署へ新たに社員が配属されたときは、その都度取り組み方を教育しなければなりません。そこで、当該業務のノウハウが共有されれば、経験のない社員でもすぐに業務の要領をつかめます。 このように、ノウハウを蓄積・共有することは、業務の属人化を防ぎ、社内の業務水準の底上げにつながります。以上のことから、ノウハウの蓄積・管理が求められるのです。 ノウハウとナレッジの違い ノウハウと混同しやすい言葉に「ナレッジ」があります。 「ナレッジ」とは、すでに新聞や書籍としてテキスト化された情報を指します。たとえば、ビジネスにおけるナレッジでは”新サービスの開発に役立つ情報”というように、すぐに社内に共有できるのが特徴です。 社内で共有されることが多いナレッジとして以下のものが挙げられます。 業務を行うための基本的なナレッジ:メールの書き方、議事録の作成方法 業務経験から身に付くナレッジ:営業の交渉術、マーケティング戦略の立て方 限られた人のみが保有するナレッジ:共有が難しい研究内容 一方、「ノウハウ」のように、社員の経験を通じて得た知見は言語化しづらく、OJTなどの研修から学んでいくのが一般的です。しかし、それでは一部の社員にしかノウハウが引き継がれないことから、昨今ではノウハウを「ナレッジ化」する企業が増えています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウの蓄積・管理によるメリット ここでは、ノウハウの蓄積・管理によるメリットを5つご紹介します。適切なノウハウ蓄積・管理によって、以下のメリットを得ましょう。 (1)ノウハウを継承できる ノウハウが蓄積・管理されれば、ノウハウを後任に継承できるようになります。 業務担当者が培ったノウハウを誰にも共有しないまま異動になると、後任の担当者が効率的な方法を0から模索するので、非効率です。また、担当者の定性的なノウハウも自社の成長に結びつく大切な財産なので、喪失してしまう事態は避けなければなりません。 そこで、ノウハウを正しく蓄積・管理する仕組みを整備することでノウハウを後任に継承可能になり、高い生産性を維持できるのです。 (2)業務効率化につながる ノウハウが蓄積されると業務の属人化を未然に防ぎ、業務効率化につながります。 逆に、ノウハウを蓄積していない企業では業務が属人化しており、担当者によって業務の質が異なります。そのため、経験の浅い社員が担当すると、対応遅れ・漏れが生じてしまうのです。 しかし、ノウハウを蓄積・共有することで、社員の経験値の差に関わらず「業務を進めるうえで、最適な方法」が分かるので、社員全体で業務の質が担保されます。このように、業務効率を上げるためには、ノウハウや技術を蓄積できる環境が必須です。 (3)集合知を作り出せる 体系的にノウハウを蓄積することによって、集合知を作り出せます。 集合知とは、「ほかのメンバーのノウハウを集めると、より優れたノウハウ・知見が得られる」という考え方です。ノウハウを社内全体で蓄積・共有することによって、新たなノウハウの誕生に貢献するのです。 しかし、集合知を作り出すためには、ノウハウが適切に蓄積されていなければなりません。ノウハウが個人に溜まっている状態はもちろん、煩雑に蓄積されている状態では、ノウハウが活用できず集合知を作り出せないので、まずは蓄積の仕組みを整えましょう。 (4)ノウハウを改善できる ノウハウが適切に蓄積・管理されていれば、必要に応じてノウハウをより実務的に改善できます。 これまで蓄積されたノウハウであっても、時代や会社の方針の変化に伴い、乖離する可能性も考えられます。たとえば、昨今ではリモートワークの普及により働き方が多様化しており、オフラインに最適化されたノウハウを蓄積し直す必要があるのです。 そのため、都度ノウハウをアップデートし、古い知識に新たな知見を付与する必要があります。そこで、たとえば、社内のナレッジに即アクセスできる「ナレカン」のようなツールを使うと、常に最新のノウハウを集約でき、社内に浸透しやすくなります。 (5)社員のスキルアップにつながる ノウハウが蓄積されると、社員のスキルアップも実現できます。 業務で意識すべき点や効率的な作業方法が蓄積されていれば、社員は素早く業務に慣れることが可能です。また、ベテラン社員のノウハウを継承することで、より高いクオリティを目指せます。 このように、研修コストが抑えられるので、教育担当者の負担解消にもつながります。したがって、社員個人のスキルアップを通じて組織力を向上させるためにも、ノウハウは必ず蓄積・管理しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウの蓄積・管理を効率化させる方法 以下では、面倒なノウハウの蓄積や管理を効率的に行う方法を解説します。適切な方法で計画を進めなければ、最終的な運用が上手くいかなくなる可能性があるので必見です。 ノウハウの重要性を周知する はじめに、ノウハウの重要性を周知することが大切です。 ノウハウを蓄積するときは、単純に言語化するのではなく”読み手にとって分かりやすいか”を意識して書くため、労力を費やします。つまり、労力をかけてでも、得られるメリットの大きさや重要性をメンバーへ認知させることが第一歩となるのです。 また、個人成果主義の企業では、自身の評価を上げるために、ノウハウの共有を割けるケースも少なくありません。そのため、積極的なノウハウ共有をしたメンバーに対して、新たに評価項目を設けることも、ノウハウの蓄積推進に効果的です。 以上のように、ノウハウを書き起こす手間と比較して、中長期的に大きな恩恵があることを強調しましょう。 蓄積するノウハウを整理する 次に、ノウハウが散らばらないように整理しましょう。 各自で自由にノウハウを残すと探すのが困難になるうえ、活用すべき場面・業務が分からず混乱が生じかねません。そのため、ノウハウの蓄積時には、想定している場面・業務を明確にし、体系的にまとめることが重要なのです。 ノウハウを整理して体系的にまとめておけば、溜まったノウハウからマニュアルへ昇華させるときも、すぐに作成・展開ができるようになります。 ITツールを導入・運用する 最後に、ノウハウを効率的に蓄積するには、 ITツールの導入・運用も不可欠です。 ノウハウを蓄積する方法として、”Excel”や”スプレットシート”があります。しかし、これらはファイルを開く手間がかかるうえに、ファイルが増えていくにつれて管理が入り乱れてしまい、「どこに・どのノウハウがあるのか分からない」状態になってしまうのです。 そのため、ノウハウの一元管理と検索ができるようなITツールがあると便利です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 最も簡単に社内のノウハウを蓄積・管理できるツール 以下では、最も簡単にノウハウを蓄積・管理できるツールをご紹介します。 ExcelやWordでノウハウを管理すると内容の確認・更新をするために逐一ファイルを開くのが面倒だと言えます。また、ビジネスチャットやオンラインストレージでは、欲しい情報にすぐにたどり着けないので不便です。 そこで、「ノウハウを蓄積し、必要なときに即アクセスできるITツール」を活用するべきです。ただし、多機能で操作が複雑なツールでは、ITに不慣れな社員が使いこなせないので、ノウハウを蓄積する段階で頓挫してしまいます。 したがって、ITに疎い社員でも手軽に使える「シンプルなツール」を導入しましょう。結論、自社が導入すべきは、蓄積したノウハウを超高精度検索で簡単に見つけられるナレッジ管理ツール「ナレカン」が必須です。 ナレカンでは、自身の持つノウハウを「記事」にして共有したり「質問機能」で他のメンバーに情報を聞きだしたりして簡単にノウハウを蓄積できます。また、生成AIを活用した「検索機能」を使えば、蓄積したノウハウのなかから最も適切な回答を得られるので、業務の不明点も解消しやすいのです。 社内のノウハウ蓄積・管理を成功させる「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【担当者は必見】ノウハウ蓄積ツールにおける3つの選定ポイント 以下では、ノウハウ蓄積ツールの選定ポイントを3つ解説します。ツールの導入後に「適切に運用できない」とならないためにも、担当者の方は必見です。 (1)情報を簡単に蓄積できるか ツールを選定するときは、まず情報を簡単に蓄積できるかを確認しましょう。 たとえば、長く業務に携わるベテラン社員が持つノウハウはとても貴重なものです。しかし、ITに疎いベテラン社員でも簡単に使いこなせるツールでなければ、そのノウハウを共有することは難しくなってしまいます。 したがって、誰でも簡単に情報を蓄積できるツールであるかは、重要なポイントです。 (2)情報にすぐにアクセスできるか 大量のノウハウを蓄積する場合、情報へ瞬時にアクセスすることも重要です。 任意のノウハウをすぐに見つけられるツールの条件は、以下の3つになります。 キーワードを検索しただけで該当ファイルを抽出できる ノウハウが案件や作業ごとに振り分けられる 必要な業務情報がほかの情報に埋もれずに蓄積できる 以上のような条件を備えたツールを使えば、「必要な情報を探し出す手間」を軽減でき、結果として業務がより効率化されます。 (3)社内に定着するか ツールが社内に定着するかも極めて重要な点です。 ツールを導入しても社内に定着しなければ、仕事がスムーズに進まず、次第に使われなくなる恐れがあります。そのため、ツールを選定するときは社内に定着するよう「サポート体制が充実しているツール」を選びましょう。 たとえば、「運用設計の提案」や「既存データの移行支援」を実施している「ナレカン」のようなツールであれば、最初からナレッジがある状態で使い始められるので社内に定着しやすいです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウの蓄積・管理ができるツールの種類 ここでは、ノウハウの蓄積・管理ができるツールの種類をご紹介します。紙やメールでのノウハウ継承から脱却するには、以下のツールがおすすめです。 社内wiki 社内wikiは、社員が各々情報を書き込んで作成する社内の百科事典です。 分からないことがあれば社内wikiで必要な情報を確認できるようになります。また、多くのサービスでアクセス権限が設定可能なので、許可されたユーザーのみが情報を更新する使い方も可能です。 以上のように、社内wikiではセキュリティを確保しながらノウハウ蓄積ができます。 ビジネスチャット ビジネスチャットはコミュニケーションツールですが、ファイルのアップロード機能やグループ機能を利用すればノウハウ共有ツールとしても使えます。 ノウハウをメッセージで共有できるほか、不明点や該当の情報が見つからない場合は、ノウハウを持つ社員からすぐに回答を得られるのがメリットです。また、ノウハウを蓄積するためのグループを用意すれば、情報が錯綜する心配もありません。 ただし、社内SNSはメッセージが次々に流れてしまうので、あとから目的のノウハウを見つけるのが面倒な点に注意しましょう。 オンラインストレージ オンラインストレージはファイル形式の情報を保存できるツールを指します。 たとえば、ノウハウをWordなどのファイルにまとめて、ツール上に保存するという使い方です。ファイルの持ち出し制限や閲覧履歴の記録も取れるので、情報漏えいや不正アクセスへも対処できます。 以上のように、オンラインストレージは比較的強固なセキュリティ機能があります。一方、目的のファイルを探し出すのが面倒なので、運用方法も整備しなければ次第に使われなくなる可能性がある点に注意しましょう。 ナレッジ管理ツール ナレッジ管理ツールは、ノウハウや業務の知識を管理できる専用ツールを指します。 ノウハウや業務に役立つ知識、事例は、社内ナレッジとして共有しなければ業務品質の均一化につながりません。しかし、WordやExcelでまとめるとどのファイルに目的の情報が記録されているかが分からず、あとから振り返りにくくなってしまうのです。 そこで、「ナレカン」のようなナレッジ管理専用のツールを使うと、ノウハウをはじめとした情報を整理しやすいうえ、検索機能やタグで簡単に目的の情報を見つけられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウの蓄積・管理によるメリットまとめ これまで、ノウハウを蓄積・管理するメリットや方法、ツールの選定ポイントを中心にご紹介しました。 ノウハウを蓄積・共有すれば、一から教育する手間を省けるうえに、教育係によって社員のスキルがばらつく事態も防げます。つまり、蓄積されたノウハウを活用することで、製品やサービスの質が高まれば、最終的に「自社のブランドの向上」につながるのです。 そして、ノウハウを簡単かつ効率的に蓄積するには、ノウハウを一元管理しながら簡単に情報を探し出せる「ITツール」が不可欠です。ただし、ツールを選ぶときには、チーム全体のITリテラシーを考慮して「誰でもストレスなく使えるか」が必須条件となります。 結論、社内メンバーのノウハウを一元管理して超高精度検索できるツール「ナレカン」が最適です。 ぜひ「ナレカン」を導入し、ノウハウを蓄積しやすい環境を整えましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年03月18日ノウハウの蓄積・管理を成功させるには?おすすめツールも紹介自社のノウハウは適切に蓄積・管理して社内資産化すべきです。優れたノウハウが横展開・縦展開されることなく属人化すれば、社員ごとの作業クオリティに差が生じてしまい「特定の人にしか業務を任せられない」という悪循環を生み出してしまいます。 しかし、「ノウハウを社内に展開したいが、具体的に何をすれば良いか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ノウハウの蓄積・管理を成功させる方法や、ノウハウの継承におすすめのツールを中心にご紹介します。 ノウハウの蓄積や管理を効率化させる方法が知りたい ノウハウを社内に蓄積・管理できるツールを探している ノウハウの蓄積だけでなく、すぐに検索できるツールを選びたい という方はこの記事を参考にすると、簡単かつ適切にノウハウを蓄積・管理できるようになり、社内の業務負担が大幅に解消されます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ノウハウを蓄積・管理するには1.1 ノウハウの蓄積・管理が求められる理由1.2 ノウハウとナレッジの違い2 ノウハウの蓄積・管理によるメリット2.1 (1)ノウハウを継承できる2.2 (2)業務効率化につながる2.3 (3)集合知を作り出せる2.4 (4)ノウハウを改善できる2.5 (5)社員のスキルアップにつながる3 ノウハウの蓄積・管理を効率化させる方法3.1 ノウハウの重要性を周知する3.2 蓄積するノウハウを整理する3.3 ITツールを導入・運用する4 最も簡単に社内のノウハウを蓄積・管理できるツール4.1 社内のノウハウ蓄積・管理を成功させる「ナレカン」5 【担当者は必見】ノウハウ蓄積ツールにおける3つの選定ポイント5.1 (1)情報を簡単に蓄積できるか5.2 (2)情報にすぐにアクセスできるか5.3 (3)社内に定着するか6 ノウハウの蓄積・管理ができるツールの種類6.1 社内wiki6.2 ビジネスチャット6.3 オンラインストレージ6.4 ナレッジ管理ツール7 ノウハウの蓄積・管理によるメリットまとめ ノウハウを蓄積・管理するには 適切にノウハウを蓄積していくために、まずは「ノウハウを蓄積する理由」や「第一にノウハウは何を指すのか」という疑問を解消しましょう。 ノウハウの蓄積・管理が求められる理由 ノウハウの蓄積・管理をする理由は、チームの業務処理速度を上げるためです。 そもそも「ノウハウを蓄積する」とは、各社員がそれまでの業務から得た経験や教訓などの暗黙知(言語化しづらい知識)を、文書や図として社内に浸透させることを指します。 たとえば、特殊な業務を扱う部署へ新たに社員が配属されたときは、その都度取り組み方を教育しなければなりません。そこで、当該業務のノウハウが共有されれば、経験のない社員でもすぐに業務の要領をつかめます。 このように、ノウハウを蓄積・共有することは、業務の属人化を防ぎ、社内の業務水準の底上げにつながります。以上のことから、ノウハウの蓄積・管理が求められるのです。 ノウハウとナレッジの違い ノウハウと混同しやすい言葉に「ナレッジ」があります。 「ナレッジ」とは、すでに新聞や書籍としてテキスト化された情報を指します。たとえば、ビジネスにおけるナレッジでは”新サービスの開発に役立つ情報”というように、すぐに社内に共有できるのが特徴です。 社内で共有されることが多いナレッジとして以下のものが挙げられます。 業務を行うための基本的なナレッジ:メールの書き方、議事録の作成方法 業務経験から身に付くナレッジ:営業の交渉術、マーケティング戦略の立て方 限られた人のみが保有するナレッジ:共有が難しい研究内容 一方、「ノウハウ」のように、社員の経験を通じて得た知見は言語化しづらく、OJTなどの研修から学んでいくのが一般的です。しかし、それでは一部の社員にしかノウハウが引き継がれないことから、昨今ではノウハウを「ナレッジ化」する企業が増えています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウの蓄積・管理によるメリット ここでは、ノウハウの蓄積・管理によるメリットを5つご紹介します。適切なノウハウ蓄積・管理によって、以下のメリットを得ましょう。 (1)ノウハウを継承できる ノウハウが蓄積・管理されれば、ノウハウを後任に継承できるようになります。 業務担当者が培ったノウハウを誰にも共有しないまま異動になると、後任の担当者が効率的な方法を0から模索するので、非効率です。また、担当者の定性的なノウハウも自社の成長に結びつく大切な財産なので、喪失してしまう事態は避けなければなりません。 そこで、ノウハウを正しく蓄積・管理する仕組みを整備することでノウハウを後任に継承可能になり、高い生産性を維持できるのです。 (2)業務効率化につながる ノウハウが蓄積されると業務の属人化を未然に防ぎ、業務効率化につながります。 逆に、ノウハウを蓄積していない企業では業務が属人化しており、担当者によって業務の質が異なります。そのため、経験の浅い社員が担当すると、対応遅れ・漏れが生じてしまうのです。 しかし、ノウハウを蓄積・共有することで、社員の経験値の差に関わらず「業務を進めるうえで、最適な方法」が分かるので、社員全体で業務の質が担保されます。このように、業務効率を上げるためには、ノウハウや技術を蓄積できる環境が必須です。 (3)集合知を作り出せる 体系的にノウハウを蓄積することによって、集合知を作り出せます。 集合知とは、「ほかのメンバーのノウハウを集めると、より優れたノウハウ・知見が得られる」という考え方です。ノウハウを社内全体で蓄積・共有することによって、新たなノウハウの誕生に貢献するのです。 しかし、集合知を作り出すためには、ノウハウが適切に蓄積されていなければなりません。ノウハウが個人に溜まっている状態はもちろん、煩雑に蓄積されている状態では、ノウハウが活用できず集合知を作り出せないので、まずは蓄積の仕組みを整えましょう。 (4)ノウハウを改善できる ノウハウが適切に蓄積・管理されていれば、必要に応じてノウハウをより実務的に改善できます。 これまで蓄積されたノウハウであっても、時代や会社の方針の変化に伴い、乖離する可能性も考えられます。たとえば、昨今ではリモートワークの普及により働き方が多様化しており、オフラインに最適化されたノウハウを蓄積し直す必要があるのです。 そのため、都度ノウハウをアップデートし、古い知識に新たな知見を付与する必要があります。そこで、たとえば、社内のナレッジに即アクセスできる「ナレカン」のようなツールを使うと、常に最新のノウハウを集約でき、社内に浸透しやすくなります。 (5)社員のスキルアップにつながる ノウハウが蓄積されると、社員のスキルアップも実現できます。 業務で意識すべき点や効率的な作業方法が蓄積されていれば、社員は素早く業務に慣れることが可能です。また、ベテラン社員のノウハウを継承することで、より高いクオリティを目指せます。 このように、研修コストが抑えられるので、教育担当者の負担解消にもつながります。したがって、社員個人のスキルアップを通じて組織力を向上させるためにも、ノウハウは必ず蓄積・管理しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウの蓄積・管理を効率化させる方法 以下では、面倒なノウハウの蓄積や管理を効率的に行う方法を解説します。適切な方法で計画を進めなければ、最終的な運用が上手くいかなくなる可能性があるので必見です。 ノウハウの重要性を周知する はじめに、ノウハウの重要性を周知することが大切です。 ノウハウを蓄積するときは、単純に言語化するのではなく”読み手にとって分かりやすいか”を意識して書くため、労力を費やします。つまり、労力をかけてでも、得られるメリットの大きさや重要性をメンバーへ認知させることが第一歩となるのです。 また、個人成果主義の企業では、自身の評価を上げるために、ノウハウの共有を割けるケースも少なくありません。そのため、積極的なノウハウ共有をしたメンバーに対して、新たに評価項目を設けることも、ノウハウの蓄積推進に効果的です。 以上のように、ノウハウを書き起こす手間と比較して、中長期的に大きな恩恵があることを強調しましょう。 蓄積するノウハウを整理する 次に、ノウハウが散らばらないように整理しましょう。 各自で自由にノウハウを残すと探すのが困難になるうえ、活用すべき場面・業務が分からず混乱が生じかねません。そのため、ノウハウの蓄積時には、想定している場面・業務を明確にし、体系的にまとめることが重要なのです。 ノウハウを整理して体系的にまとめておけば、溜まったノウハウからマニュアルへ昇華させるときも、すぐに作成・展開ができるようになります。 ITツールを導入・運用する 最後に、ノウハウを効率的に蓄積するには、 ITツールの導入・運用も不可欠です。 ノウハウを蓄積する方法として、”Excel”や”スプレットシート”があります。しかし、これらはファイルを開く手間がかかるうえに、ファイルが増えていくにつれて管理が入り乱れてしまい、「どこに・どのノウハウがあるのか分からない」状態になってしまうのです。 そのため、ノウハウの一元管理と検索ができるようなITツールがあると便利です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 最も簡単に社内のノウハウを蓄積・管理できるツール 以下では、最も簡単にノウハウを蓄積・管理できるツールをご紹介します。 ExcelやWordでノウハウを管理すると内容の確認・更新をするために逐一ファイルを開くのが面倒だと言えます。また、ビジネスチャットやオンラインストレージでは、欲しい情報にすぐにたどり着けないので不便です。 そこで、「ノウハウを蓄積し、必要なときに即アクセスできるITツール」を活用するべきです。ただし、多機能で操作が複雑なツールでは、ITに不慣れな社員が使いこなせないので、ノウハウを蓄積する段階で頓挫してしまいます。 したがって、ITに疎い社員でも手軽に使える「シンプルなツール」を導入しましょう。結論、自社が導入すべきは、蓄積したノウハウを超高精度検索で簡単に見つけられるナレッジ管理ツール「ナレカン」が必須です。 ナレカンでは、自身の持つノウハウを「記事」にして共有したり「質問機能」で他のメンバーに情報を聞きだしたりして簡単にノウハウを蓄積できます。また、生成AIを活用した「検索機能」を使えば、蓄積したノウハウのなかから最も適切な回答を得られるので、業務の不明点も解消しやすいのです。 社内のノウハウ蓄積・管理を成功させる「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【担当者は必見】ノウハウ蓄積ツールにおける3つの選定ポイント 以下では、ノウハウ蓄積ツールの選定ポイントを3つ解説します。ツールの導入後に「適切に運用できない」とならないためにも、担当者の方は必見です。 (1)情報を簡単に蓄積できるか ツールを選定するときは、まず情報を簡単に蓄積できるかを確認しましょう。 たとえば、長く業務に携わるベテラン社員が持つノウハウはとても貴重なものです。しかし、ITに疎いベテラン社員でも簡単に使いこなせるツールでなければ、そのノウハウを共有することは難しくなってしまいます。 したがって、誰でも簡単に情報を蓄積できるツールであるかは、重要なポイントです。 (2)情報にすぐにアクセスできるか 大量のノウハウを蓄積する場合、情報へ瞬時にアクセスすることも重要です。 任意のノウハウをすぐに見つけられるツールの条件は、以下の3つになります。 キーワードを検索しただけで該当ファイルを抽出できる ノウハウが案件や作業ごとに振り分けられる 必要な業務情報がほかの情報に埋もれずに蓄積できる 以上のような条件を備えたツールを使えば、「必要な情報を探し出す手間」を軽減でき、結果として業務がより効率化されます。 (3)社内に定着するか ツールが社内に定着するかも極めて重要な点です。 ツールを導入しても社内に定着しなければ、仕事がスムーズに進まず、次第に使われなくなる恐れがあります。そのため、ツールを選定するときは社内に定着するよう「サポート体制が充実しているツール」を選びましょう。 たとえば、「運用設計の提案」や「既存データの移行支援」を実施している「ナレカン」のようなツールであれば、最初からナレッジがある状態で使い始められるので社内に定着しやすいです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウの蓄積・管理ができるツールの種類 ここでは、ノウハウの蓄積・管理ができるツールの種類をご紹介します。紙やメールでのノウハウ継承から脱却するには、以下のツールがおすすめです。 社内wiki 社内wikiは、社員が各々情報を書き込んで作成する社内の百科事典です。 分からないことがあれば社内wikiで必要な情報を確認できるようになります。また、多くのサービスでアクセス権限が設定可能なので、許可されたユーザーのみが情報を更新する使い方も可能です。 以上のように、社内wikiではセキュリティを確保しながらノウハウ蓄積ができます。 ビジネスチャット ビジネスチャットはコミュニケーションツールですが、ファイルのアップロード機能やグループ機能を利用すればノウハウ共有ツールとしても使えます。 ノウハウをメッセージで共有できるほか、不明点や該当の情報が見つからない場合は、ノウハウを持つ社員からすぐに回答を得られるのがメリットです。また、ノウハウを蓄積するためのグループを用意すれば、情報が錯綜する心配もありません。 ただし、社内SNSはメッセージが次々に流れてしまうので、あとから目的のノウハウを見つけるのが面倒な点に注意しましょう。 オンラインストレージ オンラインストレージはファイル形式の情報を保存できるツールを指します。 たとえば、ノウハウをWordなどのファイルにまとめて、ツール上に保存するという使い方です。ファイルの持ち出し制限や閲覧履歴の記録も取れるので、情報漏えいや不正アクセスへも対処できます。 以上のように、オンラインストレージは比較的強固なセキュリティ機能があります。一方、目的のファイルを探し出すのが面倒なので、運用方法も整備しなければ次第に使われなくなる可能性がある点に注意しましょう。 ナレッジ管理ツール ナレッジ管理ツールは、ノウハウや業務の知識を管理できる専用ツールを指します。 ノウハウや業務に役立つ知識、事例は、社内ナレッジとして共有しなければ業務品質の均一化につながりません。しかし、WordやExcelでまとめるとどのファイルに目的の情報が記録されているかが分からず、あとから振り返りにくくなってしまうのです。 そこで、「ナレカン」のようなナレッジ管理専用のツールを使うと、ノウハウをはじめとした情報を整理しやすいうえ、検索機能やタグで簡単に目的の情報を見つけられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウの蓄積・管理によるメリットまとめ これまで、ノウハウを蓄積・管理するメリットや方法、ツールの選定ポイントを中心にご紹介しました。 ノウハウを蓄積・共有すれば、一から教育する手間を省けるうえに、教育係によって社員のスキルがばらつく事態も防げます。つまり、蓄積されたノウハウを活用することで、製品やサービスの質が高まれば、最終的に「自社のブランドの向上」につながるのです。 そして、ノウハウを簡単かつ効率的に蓄積するには、ノウハウを一元管理しながら簡単に情報を探し出せる「ITツール」が不可欠です。ただし、ツールを選ぶときには、チーム全体のITリテラシーを考慮して「誰でもストレスなく使えるか」が必須条件となります。 結論、社内メンバーのノウハウを一元管理して超高精度検索できるツール「ナレカン」が最適です。 ぜひ「ナレカン」を導入し、ノウハウを蓄積しやすい環境を整えましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年03月18日【必見】社内のノウハウを共有・管理する方法とは?日々の業務を通して個人や組織にはノウハウが蓄積されますが、活用されなければ業務効率化や生産性の向上は実現しません。したがって、ノウハウの適切な共有が必要です。 しかし、ノウハウを共有する重要性を把握してはいるものの「社内のノウハウを共有する方法がわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ノウハウ共有・管理のメリットや正しい共有方法を中心にご紹介します。 属人化しているノウハウを社内に共有したい ノウハウを簡単に管理できる方法が知りたい 社内のノウハウを活用して業務効率化を図りたい という方はこの記事を参考にすると、効果的なノウハウ管理をベースとして、社員一人ひとりのスキルを効率的に高められます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ノウハウ共有とは2 ノウハウを共有するメリットとは2.1 必要なノウハウをすぐに得られる状態になる2.2 業務の標準化ができる2.3 ミスが起こりにくくなる3 社内でノウハウを共有する方法3.1 目的を定めて共有する内容を明確にする3.2 ノウハウを共有する手法を決める3.3 蓄積と活用のPDCAサイクルを回す4 社内のノウハウ共有・管理におすすめのツール4.1 共有されたノウハウを最も簡単に共有できるツール「ナレカン」5 ノウハウ共有を成功させるポイント3選5.1 なぜ行うべきかを周知する5.2 共有の活性化を促す施策を打つ5.3 共有方法をマニュアル化する6 ノウハウ共有ツールを使うメリット6.1 社内のノウハウが蓄積される6.2 業務効率化に繋がる6.3 秘匿性の高い情報を正しく管理できる7 効果的なノウハウ共有・管理方法のまとめ ノウハウ共有とは ノウハウ共有とは、業務で得た知識や技術を指す「ノウハウ」を、社員で共有することです。たとえば、自社製品を売る際の効果的な営業方法や、自社独自の商品製造技術などを、会社や組織全体で共有することを言います。 ノウハウ共有ができていない場合、ある特定の社員しか知識をもっていないため、そのほかの社員は業務に対応できなかったり業務を効率的に進められなかったりする恐れがあります。 そのため、ノウハウを社内全体で共有して、知識を業務に活かすことが重要なのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウを共有するメリットとは ここからは、ノウハウを共有するメリットをご紹介します。以下の内容を把握しておけば、自社でノウハウ共有が進んだ際の効果を想定しながら、導入へ向けた取り組みができます。 必要なノウハウをすぐに得られる状態になる 社内でノウハウが共有されると、業務の進め方や効率的な方法といった情報がすぐに得られるようになり、業務を停滞させることなく作業を進められます。 たとえば、作業中に不明点があった場合、ノウハウが共有されない環境ではほかの社員に質問したり調べたりする必要があります。 一方、ノウハウがすぐに閲覧できれば、問題を自己解決できるようになるのでスムーズに業務を遂行できるのです。 業務の標準化ができる 業務の標準化ができることも、ノウハウ共有によって得られる効果のひとつです。 たとえば、チーム内で知識量に差がある場合には、特定の社員に業務負担が偏ってしまい業務効率が低下する恐れがあります。そこで、ノウハウの共有をすれば、経験豊富な社員が持つ知識をチーム全体で活かせるので、業務の標準化につながるのです。 また、蓄積されたノウハウを新人教育に活用すれば、教育にかかる時間的コストを削減しながら効率よく教育ができます。 ミスが起こりにくくなる ノウハウ共有を進めると、ミスが起こりにくくなる効果もあります。 社内で共有されるノウハウには、ミスを防ぐものもあります。たとえば、特定の業務においてミスが発生しやすい部分と防止のための対策をノウハウとして共有すると、同じ箇所でミスが起こりづらくなります。 ただし、ノウハウに記載された情報と実際の業務に乖離が生じないように、ノウハウの情報は定期的に更新しなくてはなりません。実際の業務との乖離がある場合、社員がノウハウを確認しなくなる可能性があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内でノウハウを共有する方法 ここからは、ノウハウを効果的に管理して活用するための方法をご紹介します。以下の内容を把握しておけば、蓄積したノウハウを最大限に活用できます。 目的を定めて共有する内容を明確にする まずは、何を目的にノウハウを共有するか明確にします。 たとえば、「業務効率化」や「顧客満足度の向上」など、ノウハウによって実現したい内容を部署や組織単位で設定しましょう。 目的を設定したうえでノウハウを共有すれば、関係のないノウハウが蓄積されてしまう事態も防げます。 ノウハウを共有する手法を決める 次に、ノウハウを共有する手法を決定しましょう。 ノウハウ共有には、主に「ドキュメントでまとめて共有する方法」と「ツールを使って共有する方法」の2種類があります。 「ドキュメントでまとめて共有する」場合には、WordやGoogleドキュメントなどを使ってノウハウをまとめ、その後メールやチャットツールで共有する必要があります。 そのため、ノウハウのまとめから共有まで一気通貫して進められる「ノウハウ共有ツール」を使って共有する方法がおすすめです。 蓄積と活用のPDCAサイクルを回す 目標と手法の決定後は、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回し続けましょう。 PDCAサイクルを回し続ければ、新たなノウハウが蓄積され、活用される好循環が生まれます。また、常に情報がブラッシュアップされるため、現在の業務において最も有効なノウハウが蓄積されていくのです。 このように、PDCAサイクルの中でノウハウの蓄積と活用を行えば、業務効率の向上などの効果を最大限に得られます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内のノウハウ共有・管理におすすめのツール 以下では、社内のノウハウ共有・管理におすすめのツールをご紹介します。 社内のノウハウを共有する方法が分からない場合には、ノウハウを簡単に共有できるITツールの導入がおすすめです。Wordなどのドキュメントツールを使った場合、社員に共有する際にメールやチャットツールで送る手間がかかってしまいます。 そこで、「簡単に社内の情報共有ができるITツール」を利用するとノウハウのまとめ・共有が一か所で完結します。ただし、操作が複雑なツールでは社員が使いづらさを感じて利用しなくなる可能性があるため、誰でも使いこなせるツールを選ぶべきです。 結論、社内のノウハウ共有には、誰でも簡単にノウハウを共有できるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」にノウハウを残せば、リアルタイムで任意のメンバーに簡単に共有できます。また、「メール転送機能」で顧客対応した記録をナレカンに残すことも可能なので、気軽なノウハウ蓄積が実現します。 共有されたノウハウを最も簡単に共有できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有を成功させるポイント3選 ここからは、業務のノウハウ共有を成功させるための3つのポイントを解説します。 ノウハウを展開させたいと考えているものの社内で定着していない場合、以下のポイントを押さえて取り組むと成功する確率が高まります。 なぜ行うべきかを周知する まずは、なぜノウハウ共有を行うべきなのかを周知しましょう。 ノウハウ共有の重要性を理解していないままでは、社員の自発的な共有は見込めません。また、競争意識の強い企業であれば「同じ会社の社員であっても、ノウハウを共有したくない」と考える社員がいる可能性があります。 したがって、ノウハウ共有の持つメリットを社内に周知し、組織内で目的意識を統一させる必要があります。 たとえば、定期的にミーティングで周知したり、ノウハウ共有の重要性について社内報などで伝えたりするなど、自社に合った方法を利用して社内理解を得ましょう。 共有の活性化を促す施策を打つ ノウハウ共有を成功させるには、共有の活性化を促す施策を打つことも効果的です。 組織での認識は統一できているがノウハウ共有が活性化しない場合、自分の経験や知恵をノウハウとして記載する手間を面倒に感じる社員が一定数いる可能性があります。 そのため、ノウハウ共有が活性化するような施策を打ち出し、自発的な行動を促す必要があるのです。たとえば、優秀なノウハウにはインセンティブを与えたり、ノウハウ共有の機会を朝礼に盛り込んだりする施策が有効です。 共有方法をマニュアル化する 共有の手順や方法をマニュアル化するのも、ノウハウ共有を成功させるポイントです。 ノウハウ共有はトップ層だけが行うものではなく、全社で取り組むべきものです。そのため、現場の社員であっても確実に共有や活用の方法を理解し使いこなせる状況にしなくてはなりません。 したがって、共有や活用の手順は明確にマニュアル化し、マニュアルを元に運用する必要があります。マニュアルがあれば「ツールの操作方法がわからないからノウハウの蓄積ができない」といった事態を防げるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有ツールを使うメリット ここからは、ツールの導入による3つのメリットをご紹介します。以下の内容を把握せずにツールを導入すると、効果が見えづらくなるため最大限にツールを活用することが難しくなります。 社内のノウハウが蓄積される ツールを使うことで、個人が持つノウハウの蓄積が可能になります。 メモ書きや口頭でのノウハウ共有は、今までに共有された情報を蓄積することが難しく、上手く情報を活用できなかったり、特定の社員の離職とともにノウハウが消失したりする恐れがあります。 一方、ツールを使えば、属人化しがちなノウハウも一箇所に蓄積することができるため、知りたい情報をいつでも確認して活用できるようになります。また、離職した社員のノウハウが消失することもないので、過去のノウハウを振り返って活用することもできます。 業務効率化に繋がる ノウハウ共有ツールの導入により、業務効率化を実現できます。 たとえば、組み立て作業のような「同じ作業工程を繰り返す業務」にマニュアルを作成して共有しておけば、誰でも同じ作業時間・クオリティで作業できるのです。 また、ノウハウがツールによって共有されるので、引き継ぎや教育にかかる時間的コストを削減できます。そのため、自社内の業務フローが確立していない、教育コストに時間が取られすぎてしまい他業務に支障が出ている場合、ツールの導入による改善は必須です。 秘匿性の高い情報を正しく管理できる ノウハウ共有ツールの多くはセキュリティ対策がとられているため、秘匿性が高いノウハウも正しく管理できます。 たとえば、閲覧・編集権限のほか2段階認証やシングルサインオン、特定のIPアドレスの制限など、ツールによって利用できるセキュリティ機能はさまざまです。導入の際は自社の規模や使用範囲、目的と併せてツールを検討する必要があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 効果的なノウハウ共有・管理方法のまとめ これまで、効果的なノウハウの共有・管理方法をご紹介しました。 ノウハウを正しく管理し活用するには、目標を明確にしたり蓄積と活用のPDCAサイクルを回したりすることが重要です。また、ドキュメントでノウハウを管理する方法もありますが、共有に都度手間がかかるといったデメリットは無視できません。 一方、ITツールを利用してノウハウを共有・管理すれば、スムーズに社内に共有ができるうえ、アクセス性も高まります。しかし、多機能なツールではITに詳しくない社員が使いこなせないのでシンプルなツールが最適です。 結論、社内のノウハウ共有には、直感的な操作で誰でも簡単にノウハウ共有・管理ができるツール「ナレカン」が最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」で効率的なノウハウ共有・管理を実現しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む
2025年03月18日【必見】社内のノウハウを共有・管理する方法とは?日々の業務を通して個人や組織にはノウハウが蓄積されますが、活用されなければ業務効率化や生産性の向上は実現しません。したがって、ノウハウの適切な共有が必要です。 しかし、ノウハウを共有する重要性を把握してはいるものの「社内のノウハウを共有する方法がわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ノウハウ共有・管理のメリットや正しい共有方法を中心にご紹介します。 属人化しているノウハウを社内に共有したい ノウハウを簡単に管理できる方法が知りたい 社内のノウハウを活用して業務効率化を図りたい という方はこの記事を参考にすると、効果的なノウハウ管理をベースとして、社員一人ひとりのスキルを効率的に高められます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ノウハウ共有とは2 ノウハウを共有するメリットとは2.1 必要なノウハウをすぐに得られる状態になる2.2 業務の標準化ができる2.3 ミスが起こりにくくなる3 社内でノウハウを共有する方法3.1 目的を定めて共有する内容を明確にする3.2 ノウハウを共有する手法を決める3.3 蓄積と活用のPDCAサイクルを回す4 社内のノウハウ共有・管理におすすめのツール4.1 共有されたノウハウを最も簡単に共有できるツール「ナレカン」5 ノウハウ共有を成功させるポイント3選5.1 なぜ行うべきかを周知する5.2 共有の活性化を促す施策を打つ5.3 共有方法をマニュアル化する6 ノウハウ共有ツールを使うメリット6.1 社内のノウハウが蓄積される6.2 業務効率化に繋がる6.3 秘匿性の高い情報を正しく管理できる7 効果的なノウハウ共有・管理方法のまとめ ノウハウ共有とは ノウハウ共有とは、業務で得た知識や技術を指す「ノウハウ」を、社員で共有することです。たとえば、自社製品を売る際の効果的な営業方法や、自社独自の商品製造技術などを、会社や組織全体で共有することを言います。 ノウハウ共有ができていない場合、ある特定の社員しか知識をもっていないため、そのほかの社員は業務に対応できなかったり業務を効率的に進められなかったりする恐れがあります。 そのため、ノウハウを社内全体で共有して、知識を業務に活かすことが重要なのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウを共有するメリットとは ここからは、ノウハウを共有するメリットをご紹介します。以下の内容を把握しておけば、自社でノウハウ共有が進んだ際の効果を想定しながら、導入へ向けた取り組みができます。 必要なノウハウをすぐに得られる状態になる 社内でノウハウが共有されると、業務の進め方や効率的な方法といった情報がすぐに得られるようになり、業務を停滞させることなく作業を進められます。 たとえば、作業中に不明点があった場合、ノウハウが共有されない環境ではほかの社員に質問したり調べたりする必要があります。 一方、ノウハウがすぐに閲覧できれば、問題を自己解決できるようになるのでスムーズに業務を遂行できるのです。 業務の標準化ができる 業務の標準化ができることも、ノウハウ共有によって得られる効果のひとつです。 たとえば、チーム内で知識量に差がある場合には、特定の社員に業務負担が偏ってしまい業務効率が低下する恐れがあります。そこで、ノウハウの共有をすれば、経験豊富な社員が持つ知識をチーム全体で活かせるので、業務の標準化につながるのです。 また、蓄積されたノウハウを新人教育に活用すれば、教育にかかる時間的コストを削減しながら効率よく教育ができます。 ミスが起こりにくくなる ノウハウ共有を進めると、ミスが起こりにくくなる効果もあります。 社内で共有されるノウハウには、ミスを防ぐものもあります。たとえば、特定の業務においてミスが発生しやすい部分と防止のための対策をノウハウとして共有すると、同じ箇所でミスが起こりづらくなります。 ただし、ノウハウに記載された情報と実際の業務に乖離が生じないように、ノウハウの情報は定期的に更新しなくてはなりません。実際の業務との乖離がある場合、社員がノウハウを確認しなくなる可能性があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内でノウハウを共有する方法 ここからは、ノウハウを効果的に管理して活用するための方法をご紹介します。以下の内容を把握しておけば、蓄積したノウハウを最大限に活用できます。 目的を定めて共有する内容を明確にする まずは、何を目的にノウハウを共有するか明確にします。 たとえば、「業務効率化」や「顧客満足度の向上」など、ノウハウによって実現したい内容を部署や組織単位で設定しましょう。 目的を設定したうえでノウハウを共有すれば、関係のないノウハウが蓄積されてしまう事態も防げます。 ノウハウを共有する手法を決める 次に、ノウハウを共有する手法を決定しましょう。 ノウハウ共有には、主に「ドキュメントでまとめて共有する方法」と「ツールを使って共有する方法」の2種類があります。 「ドキュメントでまとめて共有する」場合には、WordやGoogleドキュメントなどを使ってノウハウをまとめ、その後メールやチャットツールで共有する必要があります。 そのため、ノウハウのまとめから共有まで一気通貫して進められる「ノウハウ共有ツール」を使って共有する方法がおすすめです。 蓄積と活用のPDCAサイクルを回す 目標と手法の決定後は、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回し続けましょう。 PDCAサイクルを回し続ければ、新たなノウハウが蓄積され、活用される好循環が生まれます。また、常に情報がブラッシュアップされるため、現在の業務において最も有効なノウハウが蓄積されていくのです。 このように、PDCAサイクルの中でノウハウの蓄積と活用を行えば、業務効率の向上などの効果を最大限に得られます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内のノウハウ共有・管理におすすめのツール 以下では、社内のノウハウ共有・管理におすすめのツールをご紹介します。 社内のノウハウを共有する方法が分からない場合には、ノウハウを簡単に共有できるITツールの導入がおすすめです。Wordなどのドキュメントツールを使った場合、社員に共有する際にメールやチャットツールで送る手間がかかってしまいます。 そこで、「簡単に社内の情報共有ができるITツール」を利用するとノウハウのまとめ・共有が一か所で完結します。ただし、操作が複雑なツールでは社員が使いづらさを感じて利用しなくなる可能性があるため、誰でも使いこなせるツールを選ぶべきです。 結論、社内のノウハウ共有には、誰でも簡単にノウハウを共有できるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」にノウハウを残せば、リアルタイムで任意のメンバーに簡単に共有できます。また、「メール転送機能」で顧客対応した記録をナレカンに残すことも可能なので、気軽なノウハウ蓄積が実現します。 共有されたノウハウを最も簡単に共有できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有を成功させるポイント3選 ここからは、業務のノウハウ共有を成功させるための3つのポイントを解説します。 ノウハウを展開させたいと考えているものの社内で定着していない場合、以下のポイントを押さえて取り組むと成功する確率が高まります。 なぜ行うべきかを周知する まずは、なぜノウハウ共有を行うべきなのかを周知しましょう。 ノウハウ共有の重要性を理解していないままでは、社員の自発的な共有は見込めません。また、競争意識の強い企業であれば「同じ会社の社員であっても、ノウハウを共有したくない」と考える社員がいる可能性があります。 したがって、ノウハウ共有の持つメリットを社内に周知し、組織内で目的意識を統一させる必要があります。 たとえば、定期的にミーティングで周知したり、ノウハウ共有の重要性について社内報などで伝えたりするなど、自社に合った方法を利用して社内理解を得ましょう。 共有の活性化を促す施策を打つ ノウハウ共有を成功させるには、共有の活性化を促す施策を打つことも効果的です。 組織での認識は統一できているがノウハウ共有が活性化しない場合、自分の経験や知恵をノウハウとして記載する手間を面倒に感じる社員が一定数いる可能性があります。 そのため、ノウハウ共有が活性化するような施策を打ち出し、自発的な行動を促す必要があるのです。たとえば、優秀なノウハウにはインセンティブを与えたり、ノウハウ共有の機会を朝礼に盛り込んだりする施策が有効です。 共有方法をマニュアル化する 共有の手順や方法をマニュアル化するのも、ノウハウ共有を成功させるポイントです。 ノウハウ共有はトップ層だけが行うものではなく、全社で取り組むべきものです。そのため、現場の社員であっても確実に共有や活用の方法を理解し使いこなせる状況にしなくてはなりません。 したがって、共有や活用の手順は明確にマニュアル化し、マニュアルを元に運用する必要があります。マニュアルがあれば「ツールの操作方法がわからないからノウハウの蓄積ができない」といった事態を防げるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有ツールを使うメリット ここからは、ツールの導入による3つのメリットをご紹介します。以下の内容を把握せずにツールを導入すると、効果が見えづらくなるため最大限にツールを活用することが難しくなります。 社内のノウハウが蓄積される ツールを使うことで、個人が持つノウハウの蓄積が可能になります。 メモ書きや口頭でのノウハウ共有は、今までに共有された情報を蓄積することが難しく、上手く情報を活用できなかったり、特定の社員の離職とともにノウハウが消失したりする恐れがあります。 一方、ツールを使えば、属人化しがちなノウハウも一箇所に蓄積することができるため、知りたい情報をいつでも確認して活用できるようになります。また、離職した社員のノウハウが消失することもないので、過去のノウハウを振り返って活用することもできます。 業務効率化に繋がる ノウハウ共有ツールの導入により、業務効率化を実現できます。 たとえば、組み立て作業のような「同じ作業工程を繰り返す業務」にマニュアルを作成して共有しておけば、誰でも同じ作業時間・クオリティで作業できるのです。 また、ノウハウがツールによって共有されるので、引き継ぎや教育にかかる時間的コストを削減できます。そのため、自社内の業務フローが確立していない、教育コストに時間が取られすぎてしまい他業務に支障が出ている場合、ツールの導入による改善は必須です。 秘匿性の高い情報を正しく管理できる ノウハウ共有ツールの多くはセキュリティ対策がとられているため、秘匿性が高いノウハウも正しく管理できます。 たとえば、閲覧・編集権限のほか2段階認証やシングルサインオン、特定のIPアドレスの制限など、ツールによって利用できるセキュリティ機能はさまざまです。導入の際は自社の規模や使用範囲、目的と併せてツールを検討する必要があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 効果的なノウハウ共有・管理方法のまとめ これまで、効果的なノウハウの共有・管理方法をご紹介しました。 ノウハウを正しく管理し活用するには、目標を明確にしたり蓄積と活用のPDCAサイクルを回したりすることが重要です。また、ドキュメントでノウハウを管理する方法もありますが、共有に都度手間がかかるといったデメリットは無視できません。 一方、ITツールを利用してノウハウを共有・管理すれば、スムーズに社内に共有ができるうえ、アクセス性も高まります。しかし、多機能なツールではITに詳しくない社員が使いこなせないのでシンプルなツールが最適です。 結論、社内のノウハウ共有には、直感的な操作で誰でも簡単にノウハウ共有・管理ができるツール「ナレカン」が最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」で効率的なノウハウ共有・管理を実現しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/続きを読む -
 2025年07月03日【無料あり】社内のノウハウ共有に役立つおすすめのツール7選!ノウハウは一般的に、社員それぞれの「頭のなか」や「PCのなか」で、属人化してしまっているケースが多いです。そこで、ノウハウを全社で統一し管理できると、社員の知識・情報が詰まった”ナレッジ”として全社に浸透させられます。 しかし、ノウハウの共有に必要な「ノウハウ共有ツール」の導入を検討していても、「どのツールが自社にマッチしているか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内の知識・ノウハウ共有におすすめのツール7選や、選定ポイントをご紹介します。 属人化しているノウハウを共有し、生産性の向上に努めたい 複数あるノウハウ共有ツールから自社に最適なツールを判断したい ITスキル問わずノウハウの蓄積から共有まで簡単にできるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、自社にマッチした最適なツールを選べるうえ、社内のノウハウ共有を活性化できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ノウハウ共有とは2 社内のノウハウ共有を成功させる方法とは3 ノウハウ共有ツールの選定ポイント3選3.1 (1)ノウハウの共有・蓄積が簡単か3.2 (2)サポートが手厚いか3.3 (3)必要な機能が備わっているか4 【無料あり】おすすめのノウハウ共有ツール7選4.1 【ナレカン】最もシンプルなナレッジ管理ツール4.2 【Stock】簡単にノウハウの蓄積・共有ができるツール4.3 【Qiita Team】Markdown形式にも対応したツール4.4 【iQube】グループウェアとしても使えるツール4.5 【Confluence】エンジニア向けの社内Wiki4.6 【kintone】自由なカスタマイズが可能なツール4.7 【Vertica】大量データ利用に最適なノウハウ蓄積ツール5 ノウハウ共有ツールの比較表6 ノウハウ共有ツールの無料と有料の違い7 ノウハウ共有ツールを導入する3つのメリット7.1 (1)ノウハウを社内のナレッジとして残せる7.2 (2)ノウハウの検索がしやすい7.3 (3)ノウハウの更新が簡単8 【見本あり】ノウハウを蓄積・共有する方法9 おすすめのノウハウ共有ツールのまとめ ノウハウ共有とは ノウハウ共有とは、”業務に関する専門的な知識や必要な情報を共有すること”です。 たとえば、「マーケティングのテクニック」「プログラム開発の知識」「自社独自の製造技術」など実体験から得た情報を、部署内や全社で伝えます。このように、ノウハウを共有することで、ばらつきやすい業務水準を社内で揃えられ、生産性を上げられるのです。 またノウハウが共有されていない状態のことを「属人化」といい、属人化が起こると業務の滞りや、自社の経営状態の悪化が起こりやすくなります。したがって、ベテランの知識を共有できる仕組みづくりが求められているのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内のノウハウ共有を成功させる方法とは 社内のノウハウ共有を成功させるには、「ノウハウを簡単に残せる仕組み」を構築する必要があります。 ノウハウの共有が社内で定着しない最も大きな理由のひとつに、「知識・情報を手動で蓄積していること」が挙げられます。したがって、社員一人ひとりが能動的に知見を教え合うような環境とシステムを整備する必要があるのです。 つまり、全メンバーが情報を記録・閲覧できるノウハウ共有ツールが不可欠になるのです。また、ノウハウ共有ツールを活用すると、情報が一か所に集約されて知識の属人化を防げます。 ただし、操作の複雑なツールを導入するとノウハウ共有が社内に浸透しづらいので、「ナレカン」のように、少ない工数で情報管理できるツールを選ぶなどの工夫が必須です。このように、ノウハウを簡単に共有できるように仕組みを整えましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有ツールの選定ポイント3選 ノウハウ共有ツールの導入・運用には教育コストや利用料金など、さまざまなコストがかかります。そのため、ツールの導入前には以下の3つの選定ポイントを事前に把握しておき、ミスマッチのないツールを選びましょう。 (1)ノウハウの共有・蓄積が簡単か とくに、非IT企業や社員のITリテラシーにばらつきのある大企業の場合、誰でも簡単にノウハウの共有・蓄積ができるかは一層注視すべきポイントです。 導入したツールの操作が複雑ではメンバーが面倒だと感じ、結果として中長期的にノウハウの蓄積・共有がされなくなってしまいます。また、「便利そう」という定性的な理由で多機能なツールを選定すると、全ての機能を使いこなせず、費用対効果は下がります。 したがって、社内のITリテラシーが異なる場合でも、誰でも簡単にノウハウ共有・蓄積できるツールの選定が大切です。 (2)サポートが手厚いか サポートの手厚さも、ノウハウ共有ツールの選定ポイントのひとつです。 ナレッジ管理ツールは全社で使うものですが、最初は限られた部署から試用を始めて、徐々に利用人数を増やしていく必要があります。また、ツールを導入するにあたり”社内稟議”や、”すでに書き溜めているノウハウを移行する”ことにも手間がかかります。 そのため、試用計画の立案や、稟議・データ移行のサポートが手厚い「ナレカン」のようなツールが適しているのです。 (3)必要な機能が備わっているか 自社に導入するツールが、ノウハウ共有に必要かつ過不足ない機能を備えているかを確認しましょう。 ノウハウ共有のほかにも多数の機能を備えたグループウェアもありますが、多機能で操作が複雑なツールの導入は控えるべきです。そのため、ツールを選ぶときは、自社のノウハウ共有における一番の課題を特定しましょう。 たとえば、ノウハウの共有が上手くいかない理由には「ノウハウを貯めるのに労力がかかる」「ほしい情報がヒットしない」などがあります。したがって、誰でも簡単にノウハウを蓄積できる機能と、優れた検索機能を兼ね備えたツールの導入が重要となります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【無料あり】おすすめのノウハウ共有ツール7選 以下では、厳選したおすすめのノウハウ共有ツール7選をご紹介します。 ノウハウ共有を実現するには、誰でも自由にノウハウを残し、蓄積されたノウハウへ簡単にアクセスできるシステムが必須です。そこで、個人のノウハウを一元管理するITツールを導入して、ナレッジ管理の体制を整えるべきと言えます。 ただし、多機能で操作が複雑なツールや検索機能が優れていないツールでは、操作に手間がかかり結局使われなくなる可能性が高いです。したがって、「高度な検索機能を備え、ノウハウの共有に必要かつ過不足のない機能を備えたツール」を選びましょう。 結論、最も簡単にノウハウ共有を進めるには、ITに不慣れでも簡単に社内のノウハウを一元管理して超高精度検索できる「ナレカン」が最適です。 ナレカンでは、生成AIを活用した「完全な自然言語」で検索できるので、情報が見つからないストレスがありません。また、ノウハウを書き込める「記事」や、知恵袋のように”特定の人・部署”に回答リクエスト可能な「質問」機能が、情報の属人化を防ぎます。 【ナレカン】最もシンプルなナレッジ管理ツール 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Stock】簡単にノウハウの蓄積・共有ができるツール 目的ごとに複数のツールを導入すると、ツールの数が多いほど社員の負担となります。そのため、ノウハウ共有に加えて「タスク管理」や「個人やグループ間のメッセージ」などの機能を備えたツールを使う選択肢もあります。 したがって、あらゆる情報を「ノート」に蓄積でき、ノートごとに「タスク」「メッセージ」を紐づけられる「Stock」の利用が適しています。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 <Stockをおすすめするポイント> ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 <Stockの口コミ・評判> 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ(栃木SC) 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 <Stockの料金> フリープラン :無料 ビジネスプラン :500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数:5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Qiita Team】Markdown形式にも対応したツール <Qiita Teamの特徴> Qiita Teamは、日報や議事録などのドキュメント作成・共有ツールです。Markdown記法で記入できるほか、入力補助やショートカットも用紙されているので、エンジニア以外のメンバーでも使いやすいです。 <Qiita:Teamの機能・使用感> 外部サービスとの連携 外部サービスとの連携により、Qiita:Team内の新しいコメントにすぐ反応できます。具体的には、「Slack」や「Chatwork」などのツールと連携可能です。 下書き機能 Qiita Teamの記事に書いた内容は「下書き保存」もしくは「グループに投稿する」を選択できます。そのため、任意のタイミングで記事を公開できる点が便利です。 <Qiita:Teamの注意点> 無料プランがない 無料利用は30日間のトライアルのみで、トライアル後は有償契約が前提となります。 非エンジニアには馴染みづらい 文章の記載にMarkdown方式を採用しているため、非エンジニアが多い企業では浸透しづらいです。 <Qiita Teamの料金体系> Personal(1人):500円/月 Micro(~3人):1,520円/月 Small(~7人):4,900円/月 Medium(~10人):7,050円/月 Large(~17人):15,300円/月 Extra(人数制限なし):15,300円/月~ Qiita Teamの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【iQube】グループウェアとしても使えるツール <iQubeの特徴> iQubeはノウハウ蓄積に特化したグループウェアです。「スケジュール」「掲示板」「タイムカード」など、15種類におよぶノウハウを蓄積するための機能が搭載されています。 <iQubeの機能・使用感> 閲覧・編集権限の設定 フォルダごとに権限の設定が可能です。編集者の設定だけではなく、閲覧可能の設定もユーザー・グループごとにできるので、機密情報の管理にも適しています。 <iQubeの注意点> 無料プランでは一部機能に制限がある ほぼ有料プランと同様の機能が利用できますが、コンテンツ登録数や利用人数には制限があります。 連携機能が不十分 利用しているユーザーからは「googleカレンダーとの連携を行った際、連携機能はあるようですが、連携されませんでした」という声もあります。(引用:ITreview) <iQubeの料金体系> 1か月無料プラン:最長1か月間無料 スタンダードプラン:440円/ユーザー/月(月払い) プレミアムプラン:770円/ユーザー/月(月払い) iQubeの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Confluence】エンジニア向けの社内Wiki <Confluenceの特徴> Confluenceは、JIRAなどのプロジェクト管理ツールを開発しているAtlassianが提供する、Wikiツールです。JIRAとの連携ができ、プロジェクト管理とドキュメント管理をシームレスに進められるのが特徴です。 <Confluenceの機能・使用感> テンプレート機能 あらかじめ複数のテンプレートを用意しておくことができます。テンプレートの検索機能もあるため、すぐに見つけられます。 <Confluenceの注意点> ビジュアルエディターが使いづらい HTMLでの記載ができず、ビジュアルエディターが使いづらいというユーザーの声があります。 検索機能が不十分 利用しているユーザーからは「ドキュメントの検索性が悪い、キーワード入力でも探したいものが見当たらないケースが多い」という声もあります。(引用:ITreview) フリーズすることがある 利用しているユーザーからは「特定のページの特定の個所の記載を修正しようとした場合フリーズしてしまうことがある」という声もあります。(引用:ITreview) <Confluenceの料金体系> Free:0円 Standard:645円/ユーザー/月(月払い) Premium:1,174円/ユーザー/月(月払い) Enterprise:要問い合わせ Confluenceの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【kintone】自由なカスタマイズが可能なツール <kintoneの特徴> kintoneは自社で必要な機能を自在にカスタマイズ可能な、サイボウズのクラウドサービスです。APIを使って他システムと連携をしたり、Javascriptを使った開発ができるのが特徴です。 <kintoneの機能・使用感> 豊富な機能 豊富な選択肢のなかから自社に必要な機能を選んで、設定することができます。自由にカスタマイズすることができますが、ITツールに不慣れな社員は使いづらいと感じる可能性が高いです。 <kintoneの注意点> プラグイン導入した機能は表示されない場合がある プラグイン(拡張機能)を導入した機能は、スマホで表示されない場合があるので注意が必要です。 検索機能が使いづらいと感じる可能性がある 利用しているユーザーからは「検索機能に対する制限があり、ちょっと使いにくいところがあります」という声もあります。(引用:ITreview) 最小契約数が10ユーザーに引き上げ Kintoneでは2024年10月以降、最小契約人数が10ユーザーに引き上げされています。そのため、少人数での利用を検討している方は注意が必要です。 <kintoneの料金体系> 以下は、2024年10月1日より適用された改定後の料金です。 ライトコース:1,000円/ユーザー/月(月払い) スタンダードコース:1,800円/ユーザー/月(月払い) ワイドコース:3,000円/ユーザー/月(月払い) kintoneの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Vertica】大量データ利用に最適なノウハウ蓄積ツール <Verticaの特徴> Verticaは次世代型データベースと呼ばれ、蓄積された大量のデータから必要な情報を抽出して分析できるのが特徴です。 <Verticaの機能・使用感> データ圧縮 最大90%のデータ圧縮によって、同じコストで10~30倍の量のデータを保存できるのです。 <Verticaの注意点> 日本での導入事例が少ない 導入事例の多くが海外のため、事例を参考にした導入が難しいです。 <Verticaの料金体系> 詳細な料金については問い合わせが必要です。 Verticaの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有ツールの比較表 以下はご紹介した7つの「ノウハウ共有ツール」の比較表です。(右にスクロールできます) ナレカン【1番おすすめ】 Stock【おすすめ】 Qiita:Team iQube Confluence kintone Vertica 特徴 最もシンプルなナレッジ管理ツール 簡単にノウハウの蓄積・共有ができるツール Markdown形式にも対応したツール グループウェアとしても使えるツール エンジニア向けの社内Wiki 自由なカスタマイズが可能なツール 大量データ利用に最適なノウハウ蓄積ツール シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単(大手~中堅企業向け) シンプルで簡単(中小規模の企業向け) 多機能 多機能 多機能 多機能 多機能 フォルダ機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 検索機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注意点 法人利用が前提なので、個人利用は不可 マークダウン方式は採用していない 非エンジニアには馴染みづらい 無料プランでは一部機能に制限がある オンプレミスとクラウドで提供機能が違う 欲しいシステムを構築するには時間がかかる 日本での導入事例が少ない 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料プランあり ・有料プランは月額500円/ユーザー/~ ・無料プランなし ・有料プランは500円/月(1名のみ)〜 ・無料プランあり ・有料プランは1ユーザーあたり645円/月(月払い)〜 ・無料プランあり ・有料プランは1ユーザーあたり790円/月(月払い)〜 ・無料プランなし ・有料プランは1ユーザーあたり1,000円/月(月払い)〜 詳細な料金は要問合せ 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「Qiita:Team」の詳細はこちら 「iQube」の詳細はこちら 「Confluence」の詳細はこちら 「kintone」の詳細はこちら 「Vertica」の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有ツールの無料と有料の違い ノウハウ共有ツールの無料と有料の違いを以下の表で紹介します。以下のように「機能面」「サポート面」「セキュリティ面」で価格の差があらわれます。 ツールを導入するうえで”予算”はつきものですが「無料であること」に軸を置いてしまうと、十分な効果を得られません。そのため、ツールを選定するときは、長期的な運用を考えて費用対効果の高いものを選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有ツールを導入する3つのメリット 以下では、ノウハウ共有ツールを導入する3つのメリットを解説します。 ツールを導入するメリットをあらかじめ社内で浸透させておくと、導入後もスムーズに定着できるため、以下の内容を確認しておきましょう。 (1)ノウハウを社内のナレッジとして残せる ノウハウ共有ツールを活用すると、ノウハウを社内のナレッジとして保管できます。 ノウハウが属人化すると特定社員にしかできない業務が増え、異動や退職時に引継ぎの手間がかかります。また、特定の社員が欠勤したときに業務が停滞する恐れもあるのです。 そこで、ノウハウ共有ツールに個人のノウハウを登録しておくと、必要に応じて任意のメンバーへ共有できます。このように、属人的なノウハウを社内のナレッジとして定着させることで、業務を円滑に進められるようになるのです。 (2)ノウハウの検索がしやすい ノウハウ共有ツールを利用すると、検索によって目的のノウハウへ素早くアクセスできます。 ノウハウを共有しても、必要なときに該当の情報をすぐに使えなければ、正しく共有できているとは言えません。そこで、キーワードやタグを検索するだけで該当のノウハウを確認できるツールを使うと、ノウハウを効率的に活用可能になります。 たとえば、「ナレカン」では超高精度の「キーワード検索」や生成AIを活用した「自然言語検索(ゆらぎ検索対応)」ができるため、必要な情報に即たどり着けます。このようなツールを使えば、検索にかかるストレスを低減でき、業務に集中しやすくなるのです。 (3)ノウハウの更新が簡単 ノウハウ共有ツールを利用すると、ノウハウを簡単に更新できます。 紙の管理では修正を重ねるたびに視認性が低下するほか、メモやエクセルを使ったノウハウ共有であっても、更新したら都度共有しなおす必要があり効率的ではありません。さらに、どのデータが最新のノウハウなのか分からなくなってしまう可能性もあるのです。 一方で、ノウハウ共有ツールでは投稿されたノウハウに追記したり、タグをつけたりすることで情報を簡単に更新できます。つまり、最新状態のノウハウが常にツール内に蓄積されるので、自由に活用可能なのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【見本あり】ノウハウを蓄積・共有する方法 ここでは、実際に「ナレカン」を使用してノウハウを蓄積・共有する方法を紹介します。 ナレカンは大きく3つのレイアウトに分かれており「①=部署」「②=業務内容」「③=ノウハウの詳細」といった形で見やすく管理できます。また、添付ファイル内まで検索できる高度な検索機能も搭載されており、情報へスムーズにたどり着けるのです。 また、ノウハウを記録する記事には「コメント」も紐づいているため、分からないことがあっても、メンバー間で素早く情報共有できる効果もあります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ おすすめのノウハウ共有ツールのまとめ ここまで、ノウハウ共有に役立つおすすめツールと、選定ポイント・メリットについて解説しました。 ノウハウを蓄積・共有すると、企業の規模を問わず業務効率化を実現でき、コスト削減にも繋がります。また、業務に関する知識のデータベースを作るためにも、ITツールを活用して”必要なときに必要なノウハウへアクセスできる環境”を作る必要があるのです。 そして、ツールの選定ポイントで一番大切なのは、サポート体制はもちろん、「誰でも簡単にノウハウの共有・蓄積ができるか」です。また、”コメント機能”で共有したノウハウに対するやりとりができるツールを使うと、より効率的に業務を進められます。 結論、自社のノウハウ共有には、ITツールに不慣れな社員でも簡単に操作できるツール『ナレカン』が最適です。 ナレカンにはコメント機能も備えたツールなので、ぜひ「ナレカン」を導入して、効率的にノウハウ蓄積・共有をしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジとは?ノウハウとの違いや社内のナレッジ運用の重要性を解説 【必見】社内のノウハウを共有・管理する方法とは? ノウハウの蓄積・管理を成功させるには?おすすめツールも紹介 ノウハウコレクターとは?特徴や脱出する方法を解説! ノウハウを共有しないと起こる問題とは?できない原因や解決法も解説 ベテラン社員のノウハウの継承が進まない?方法やメリットを解説 【簡単に解説】「ノウハウ」とは?ビジネスにおける意味や共有のメリットまで解説! ノウハウとは?使い方や類義語・共有方法を解説!続きを読む
2025年07月03日【無料あり】社内のノウハウ共有に役立つおすすめのツール7選!ノウハウは一般的に、社員それぞれの「頭のなか」や「PCのなか」で、属人化してしまっているケースが多いです。そこで、ノウハウを全社で統一し管理できると、社員の知識・情報が詰まった”ナレッジ”として全社に浸透させられます。 しかし、ノウハウの共有に必要な「ノウハウ共有ツール」の導入を検討していても、「どのツールが自社にマッチしているか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内の知識・ノウハウ共有におすすめのツール7選や、選定ポイントをご紹介します。 属人化しているノウハウを共有し、生産性の向上に努めたい 複数あるノウハウ共有ツールから自社に最適なツールを判断したい ITスキル問わずノウハウの蓄積から共有まで簡単にできるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、自社にマッチした最適なツールを選べるうえ、社内のノウハウ共有を活性化できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 ノウハウ共有とは2 社内のノウハウ共有を成功させる方法とは3 ノウハウ共有ツールの選定ポイント3選3.1 (1)ノウハウの共有・蓄積が簡単か3.2 (2)サポートが手厚いか3.3 (3)必要な機能が備わっているか4 【無料あり】おすすめのノウハウ共有ツール7選4.1 【ナレカン】最もシンプルなナレッジ管理ツール4.2 【Stock】簡単にノウハウの蓄積・共有ができるツール4.3 【Qiita Team】Markdown形式にも対応したツール4.4 【iQube】グループウェアとしても使えるツール4.5 【Confluence】エンジニア向けの社内Wiki4.6 【kintone】自由なカスタマイズが可能なツール4.7 【Vertica】大量データ利用に最適なノウハウ蓄積ツール5 ノウハウ共有ツールの比較表6 ノウハウ共有ツールの無料と有料の違い7 ノウハウ共有ツールを導入する3つのメリット7.1 (1)ノウハウを社内のナレッジとして残せる7.2 (2)ノウハウの検索がしやすい7.3 (3)ノウハウの更新が簡単8 【見本あり】ノウハウを蓄積・共有する方法9 おすすめのノウハウ共有ツールのまとめ ノウハウ共有とは ノウハウ共有とは、”業務に関する専門的な知識や必要な情報を共有すること”です。 たとえば、「マーケティングのテクニック」「プログラム開発の知識」「自社独自の製造技術」など実体験から得た情報を、部署内や全社で伝えます。このように、ノウハウを共有することで、ばらつきやすい業務水準を社内で揃えられ、生産性を上げられるのです。 またノウハウが共有されていない状態のことを「属人化」といい、属人化が起こると業務の滞りや、自社の経営状態の悪化が起こりやすくなります。したがって、ベテランの知識を共有できる仕組みづくりが求められているのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内のノウハウ共有を成功させる方法とは 社内のノウハウ共有を成功させるには、「ノウハウを簡単に残せる仕組み」を構築する必要があります。 ノウハウの共有が社内で定着しない最も大きな理由のひとつに、「知識・情報を手動で蓄積していること」が挙げられます。したがって、社員一人ひとりが能動的に知見を教え合うような環境とシステムを整備する必要があるのです。 つまり、全メンバーが情報を記録・閲覧できるノウハウ共有ツールが不可欠になるのです。また、ノウハウ共有ツールを活用すると、情報が一か所に集約されて知識の属人化を防げます。 ただし、操作の複雑なツールを導入するとノウハウ共有が社内に浸透しづらいので、「ナレカン」のように、少ない工数で情報管理できるツールを選ぶなどの工夫が必須です。このように、ノウハウを簡単に共有できるように仕組みを整えましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有ツールの選定ポイント3選 ノウハウ共有ツールの導入・運用には教育コストや利用料金など、さまざまなコストがかかります。そのため、ツールの導入前には以下の3つの選定ポイントを事前に把握しておき、ミスマッチのないツールを選びましょう。 (1)ノウハウの共有・蓄積が簡単か とくに、非IT企業や社員のITリテラシーにばらつきのある大企業の場合、誰でも簡単にノウハウの共有・蓄積ができるかは一層注視すべきポイントです。 導入したツールの操作が複雑ではメンバーが面倒だと感じ、結果として中長期的にノウハウの蓄積・共有がされなくなってしまいます。また、「便利そう」という定性的な理由で多機能なツールを選定すると、全ての機能を使いこなせず、費用対効果は下がります。 したがって、社内のITリテラシーが異なる場合でも、誰でも簡単にノウハウ共有・蓄積できるツールの選定が大切です。 (2)サポートが手厚いか サポートの手厚さも、ノウハウ共有ツールの選定ポイントのひとつです。 ナレッジ管理ツールは全社で使うものですが、最初は限られた部署から試用を始めて、徐々に利用人数を増やしていく必要があります。また、ツールを導入するにあたり”社内稟議”や、”すでに書き溜めているノウハウを移行する”ことにも手間がかかります。 そのため、試用計画の立案や、稟議・データ移行のサポートが手厚い「ナレカン」のようなツールが適しているのです。 (3)必要な機能が備わっているか 自社に導入するツールが、ノウハウ共有に必要かつ過不足ない機能を備えているかを確認しましょう。 ノウハウ共有のほかにも多数の機能を備えたグループウェアもありますが、多機能で操作が複雑なツールの導入は控えるべきです。そのため、ツールを選ぶときは、自社のノウハウ共有における一番の課題を特定しましょう。 たとえば、ノウハウの共有が上手くいかない理由には「ノウハウを貯めるのに労力がかかる」「ほしい情報がヒットしない」などがあります。したがって、誰でも簡単にノウハウを蓄積できる機能と、優れた検索機能を兼ね備えたツールの導入が重要となります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【無料あり】おすすめのノウハウ共有ツール7選 以下では、厳選したおすすめのノウハウ共有ツール7選をご紹介します。 ノウハウ共有を実現するには、誰でも自由にノウハウを残し、蓄積されたノウハウへ簡単にアクセスできるシステムが必須です。そこで、個人のノウハウを一元管理するITツールを導入して、ナレッジ管理の体制を整えるべきと言えます。 ただし、多機能で操作が複雑なツールや検索機能が優れていないツールでは、操作に手間がかかり結局使われなくなる可能性が高いです。したがって、「高度な検索機能を備え、ノウハウの共有に必要かつ過不足のない機能を備えたツール」を選びましょう。 結論、最も簡単にノウハウ共有を進めるには、ITに不慣れでも簡単に社内のノウハウを一元管理して超高精度検索できる「ナレカン」が最適です。 ナレカンでは、生成AIを活用した「完全な自然言語」で検索できるので、情報が見つからないストレスがありません。また、ノウハウを書き込める「記事」や、知恵袋のように”特定の人・部署”に回答リクエスト可能な「質問」機能が、情報の属人化を防ぎます。 【ナレカン】最もシンプルなナレッジ管理ツール 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Stock】簡単にノウハウの蓄積・共有ができるツール 目的ごとに複数のツールを導入すると、ツールの数が多いほど社員の負担となります。そのため、ノウハウ共有に加えて「タスク管理」や「個人やグループ間のメッセージ」などの機能を備えたツールを使う選択肢もあります。 したがって、あらゆる情報を「ノート」に蓄積でき、ノートごとに「タスク」「メッセージ」を紐づけられる「Stock」の利用が適しています。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 <Stockをおすすめするポイント> ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 <Stockの口コミ・評判> 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ(栃木SC) 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 <Stockの料金> フリープラン :無料 ビジネスプラン :500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数:5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Qiita Team】Markdown形式にも対応したツール <Qiita Teamの特徴> Qiita Teamは、日報や議事録などのドキュメント作成・共有ツールです。Markdown記法で記入できるほか、入力補助やショートカットも用紙されているので、エンジニア以外のメンバーでも使いやすいです。 <Qiita:Teamの機能・使用感> 外部サービスとの連携 外部サービスとの連携により、Qiita:Team内の新しいコメントにすぐ反応できます。具体的には、「Slack」や「Chatwork」などのツールと連携可能です。 下書き機能 Qiita Teamの記事に書いた内容は「下書き保存」もしくは「グループに投稿する」を選択できます。そのため、任意のタイミングで記事を公開できる点が便利です。 <Qiita:Teamの注意点> 無料プランがない 無料利用は30日間のトライアルのみで、トライアル後は有償契約が前提となります。 非エンジニアには馴染みづらい 文章の記載にMarkdown方式を採用しているため、非エンジニアが多い企業では浸透しづらいです。 <Qiita Teamの料金体系> Personal(1人):500円/月 Micro(~3人):1,520円/月 Small(~7人):4,900円/月 Medium(~10人):7,050円/月 Large(~17人):15,300円/月 Extra(人数制限なし):15,300円/月~ Qiita Teamの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【iQube】グループウェアとしても使えるツール <iQubeの特徴> iQubeはノウハウ蓄積に特化したグループウェアです。「スケジュール」「掲示板」「タイムカード」など、15種類におよぶノウハウを蓄積するための機能が搭載されています。 <iQubeの機能・使用感> 閲覧・編集権限の設定 フォルダごとに権限の設定が可能です。編集者の設定だけではなく、閲覧可能の設定もユーザー・グループごとにできるので、機密情報の管理にも適しています。 <iQubeの注意点> 無料プランでは一部機能に制限がある ほぼ有料プランと同様の機能が利用できますが、コンテンツ登録数や利用人数には制限があります。 連携機能が不十分 利用しているユーザーからは「googleカレンダーとの連携を行った際、連携機能はあるようですが、連携されませんでした」という声もあります。(引用:ITreview) <iQubeの料金体系> 1か月無料プラン:最長1か月間無料 スタンダードプラン:440円/ユーザー/月(月払い) プレミアムプラン:770円/ユーザー/月(月払い) iQubeの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Confluence】エンジニア向けの社内Wiki <Confluenceの特徴> Confluenceは、JIRAなどのプロジェクト管理ツールを開発しているAtlassianが提供する、Wikiツールです。JIRAとの連携ができ、プロジェクト管理とドキュメント管理をシームレスに進められるのが特徴です。 <Confluenceの機能・使用感> テンプレート機能 あらかじめ複数のテンプレートを用意しておくことができます。テンプレートの検索機能もあるため、すぐに見つけられます。 <Confluenceの注意点> ビジュアルエディターが使いづらい HTMLでの記載ができず、ビジュアルエディターが使いづらいというユーザーの声があります。 検索機能が不十分 利用しているユーザーからは「ドキュメントの検索性が悪い、キーワード入力でも探したいものが見当たらないケースが多い」という声もあります。(引用:ITreview) フリーズすることがある 利用しているユーザーからは「特定のページの特定の個所の記載を修正しようとした場合フリーズしてしまうことがある」という声もあります。(引用:ITreview) <Confluenceの料金体系> Free:0円 Standard:645円/ユーザー/月(月払い) Premium:1,174円/ユーザー/月(月払い) Enterprise:要問い合わせ Confluenceの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【kintone】自由なカスタマイズが可能なツール <kintoneの特徴> kintoneは自社で必要な機能を自在にカスタマイズ可能な、サイボウズのクラウドサービスです。APIを使って他システムと連携をしたり、Javascriptを使った開発ができるのが特徴です。 <kintoneの機能・使用感> 豊富な機能 豊富な選択肢のなかから自社に必要な機能を選んで、設定することができます。自由にカスタマイズすることができますが、ITツールに不慣れな社員は使いづらいと感じる可能性が高いです。 <kintoneの注意点> プラグイン導入した機能は表示されない場合がある プラグイン(拡張機能)を導入した機能は、スマホで表示されない場合があるので注意が必要です。 検索機能が使いづらいと感じる可能性がある 利用しているユーザーからは「検索機能に対する制限があり、ちょっと使いにくいところがあります」という声もあります。(引用:ITreview) 最小契約数が10ユーザーに引き上げ Kintoneでは2024年10月以降、最小契約人数が10ユーザーに引き上げされています。そのため、少人数での利用を検討している方は注意が必要です。 <kintoneの料金体系> 以下は、2024年10月1日より適用された改定後の料金です。 ライトコース:1,000円/ユーザー/月(月払い) スタンダードコース:1,800円/ユーザー/月(月払い) ワイドコース:3,000円/ユーザー/月(月払い) kintoneの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Vertica】大量データ利用に最適なノウハウ蓄積ツール <Verticaの特徴> Verticaは次世代型データベースと呼ばれ、蓄積された大量のデータから必要な情報を抽出して分析できるのが特徴です。 <Verticaの機能・使用感> データ圧縮 最大90%のデータ圧縮によって、同じコストで10~30倍の量のデータを保存できるのです。 <Verticaの注意点> 日本での導入事例が少ない 導入事例の多くが海外のため、事例を参考にした導入が難しいです。 <Verticaの料金体系> 詳細な料金については問い合わせが必要です。 Verticaの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有ツールの比較表 以下はご紹介した7つの「ノウハウ共有ツール」の比較表です。(右にスクロールできます) ナレカン【1番おすすめ】 Stock【おすすめ】 Qiita:Team iQube Confluence kintone Vertica 特徴 最もシンプルなナレッジ管理ツール 簡単にノウハウの蓄積・共有ができるツール Markdown形式にも対応したツール グループウェアとしても使えるツール エンジニア向けの社内Wiki 自由なカスタマイズが可能なツール 大量データ利用に最適なノウハウ蓄積ツール シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単(大手~中堅企業向け) シンプルで簡単(中小規模の企業向け) 多機能 多機能 多機能 多機能 多機能 フォルダ機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 検索機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注意点 法人利用が前提なので、個人利用は不可 マークダウン方式は採用していない 非エンジニアには馴染みづらい 無料プランでは一部機能に制限がある オンプレミスとクラウドで提供機能が違う 欲しいシステムを構築するには時間がかかる 日本での導入事例が少ない 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料プランあり ・有料プランは月額500円/ユーザー/~ ・無料プランなし ・有料プランは500円/月(1名のみ)〜 ・無料プランあり ・有料プランは1ユーザーあたり645円/月(月払い)〜 ・無料プランあり ・有料プランは1ユーザーあたり790円/月(月払い)〜 ・無料プランなし ・有料プランは1ユーザーあたり1,000円/月(月払い)〜 詳細な料金は要問合せ 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「Qiita:Team」の詳細はこちら 「iQube」の詳細はこちら 「Confluence」の詳細はこちら 「kintone」の詳細はこちら 「Vertica」の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有ツールの無料と有料の違い ノウハウ共有ツールの無料と有料の違いを以下の表で紹介します。以下のように「機能面」「サポート面」「セキュリティ面」で価格の差があらわれます。 ツールを導入するうえで”予算”はつきものですが「無料であること」に軸を置いてしまうと、十分な効果を得られません。そのため、ツールを選定するときは、長期的な運用を考えて費用対効果の高いものを選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ノウハウ共有ツールを導入する3つのメリット 以下では、ノウハウ共有ツールを導入する3つのメリットを解説します。 ツールを導入するメリットをあらかじめ社内で浸透させておくと、導入後もスムーズに定着できるため、以下の内容を確認しておきましょう。 (1)ノウハウを社内のナレッジとして残せる ノウハウ共有ツールを活用すると、ノウハウを社内のナレッジとして保管できます。 ノウハウが属人化すると特定社員にしかできない業務が増え、異動や退職時に引継ぎの手間がかかります。また、特定の社員が欠勤したときに業務が停滞する恐れもあるのです。 そこで、ノウハウ共有ツールに個人のノウハウを登録しておくと、必要に応じて任意のメンバーへ共有できます。このように、属人的なノウハウを社内のナレッジとして定着させることで、業務を円滑に進められるようになるのです。 (2)ノウハウの検索がしやすい ノウハウ共有ツールを利用すると、検索によって目的のノウハウへ素早くアクセスできます。 ノウハウを共有しても、必要なときに該当の情報をすぐに使えなければ、正しく共有できているとは言えません。そこで、キーワードやタグを検索するだけで該当のノウハウを確認できるツールを使うと、ノウハウを効率的に活用可能になります。 たとえば、「ナレカン」では超高精度の「キーワード検索」や生成AIを活用した「自然言語検索(ゆらぎ検索対応)」ができるため、必要な情報に即たどり着けます。このようなツールを使えば、検索にかかるストレスを低減でき、業務に集中しやすくなるのです。 (3)ノウハウの更新が簡単 ノウハウ共有ツールを利用すると、ノウハウを簡単に更新できます。 紙の管理では修正を重ねるたびに視認性が低下するほか、メモやエクセルを使ったノウハウ共有であっても、更新したら都度共有しなおす必要があり効率的ではありません。さらに、どのデータが最新のノウハウなのか分からなくなってしまう可能性もあるのです。 一方で、ノウハウ共有ツールでは投稿されたノウハウに追記したり、タグをつけたりすることで情報を簡単に更新できます。つまり、最新状態のノウハウが常にツール内に蓄積されるので、自由に活用可能なのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【見本あり】ノウハウを蓄積・共有する方法 ここでは、実際に「ナレカン」を使用してノウハウを蓄積・共有する方法を紹介します。 ナレカンは大きく3つのレイアウトに分かれており「①=部署」「②=業務内容」「③=ノウハウの詳細」といった形で見やすく管理できます。また、添付ファイル内まで検索できる高度な検索機能も搭載されており、情報へスムーズにたどり着けるのです。 また、ノウハウを記録する記事には「コメント」も紐づいているため、分からないことがあっても、メンバー間で素早く情報共有できる効果もあります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ おすすめのノウハウ共有ツールのまとめ ここまで、ノウハウ共有に役立つおすすめツールと、選定ポイント・メリットについて解説しました。 ノウハウを蓄積・共有すると、企業の規模を問わず業務効率化を実現でき、コスト削減にも繋がります。また、業務に関する知識のデータベースを作るためにも、ITツールを活用して”必要なときに必要なノウハウへアクセスできる環境”を作る必要があるのです。 そして、ツールの選定ポイントで一番大切なのは、サポート体制はもちろん、「誰でも簡単にノウハウの共有・蓄積ができるか」です。また、”コメント機能”で共有したノウハウに対するやりとりができるツールを使うと、より効率的に業務を進められます。 結論、自社のノウハウ共有には、ITツールに不慣れな社員でも簡単に操作できるツール『ナレカン』が最適です。 ナレカンにはコメント機能も備えたツールなので、ぜひ「ナレカン」を導入して、効率的にノウハウ蓄積・共有をしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ ナレッジとは?ノウハウとの違いや社内のナレッジ運用の重要性を解説 【必見】社内のノウハウを共有・管理する方法とは? ノウハウの蓄積・管理を成功させるには?おすすめツールも紹介 ノウハウコレクターとは?特徴や脱出する方法を解説! ノウハウを共有しないと起こる問題とは?できない原因や解決法も解説 ベテラン社員のノウハウの継承が進まない?方法やメリットを解説 【簡単に解説】「ノウハウ」とは?ビジネスにおける意味や共有のメリットまで解説! ノウハウとは?使い方や類義語・共有方法を解説!続きを読む -
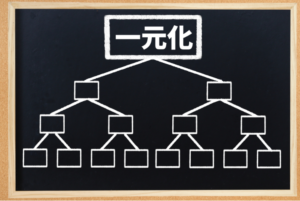 2025年03月27日情報の一元化とは?一元管理する方法やメリット、おすすめツールを紹介近年、インターネットの発達やAI技術の進歩によって、多くの情報が簡単に入手できるようになりました。企業においても社内情報のデータベースや顧客のビッグデータが積極的に活用されています。 一方で、「収集した情報を一元化したいが、どのように管理すれば良いかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、情報を一元化する方法やメリット、おすすめの情報管理ツールを中心にご紹介します。 社内情報を一元化するやり方を知りたい 情報を一元管理するメリットを把握したい 社内情報の一元管理に適したツールを探している という方はこの記事を参考にすると、社内に散在する情報を一元化して収集した情報をナレッジとして十分に活用できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 情報の一元化とは2 一元化すべき情報とは3 社内情報を一元化するメリット3.1 検索性が向上する3.2 業務の属人化を解消できる3.3 業務時間の短縮につながる4 【3ステップ】社内情報を一元管理する方法4.1 ステップ1|どこに何の情報があるのか整理する4.2 ステップ2|一元管理する情報を選定する4.3 ステップ3|ツールを選定する5 社内情報の一元化に最も適したツール5.1 社内のナレッジを一元管理して超高精度で検索できるツール「ナレカン」6 社内情報を一元管理するときの注意点7 社内情報を一元管理する方法やメリットまとめ 情報の一元化とは 情報の一元化とは、社内のあちこちに散らばっている情報を一箇所にまとめて管理することです。 顧客との商談記録や会議資料、マニュアルなど、社内情報は日々増えていきます。そのため、社員それぞれが自身のパソコンやストレージで業務情報を管理していると、担当者の不在時に対応が遅滞したり引き継ぎに時間がかかったりする恐れがあります。 また、情報を共有する場所を整備しておかないと業務ノウハウが属人化してしまい、ナレッジが社内に蓄積されていきません。したがって、社内情報を適切に管理・活用するためには情報を一元化して保管する場所を用意することが求められるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 一元化すべき情報とは 社内情報のなかでも、とくに一元化すべき情報には以下の3つがあります。 全社で共有するべき社内規定やお知らせ 社内規定の変更や社内行事のお知らせなどは、全社にすぐ共有し、常に全員が確認しやすいように管理しなくてはなりません。 顧客対応の記録や過去のトラブル事例 顧客との商談記録や過去のトラブル事例は、社内にナレッジとして蓄積し、必要なときに誰もが参考にできるようにしておきましょう。 業務に使うマニュアルや資料 頻繁に更新される業務マニュアルや社内資料は、一箇所にまとめて検索しやすいようにしておくべきです。 以上の3つを一元管理すれば、社内の情報に誰もが即アクセスできる状態になります。ただし、蓄積した情報は検索すれば確実に見つかるように「ナレカン」のような検索性に優れたツールで保管しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報を一元化するメリット 以下では、社内情報を一元化するメリットを解説します。社内情報の一元管理によって得られる効果を把握しきれていない担当者の方は必見です。 検索性が向上する 社内情報を一元化すると、検索性が向上します。 業務のマニュアルや会議資料が社内のあちこちに散在していると、どこに何を保存したかわからず、探すのに時間がかかります。また、そもそも業務ノウハウや手引書が共有されておらず、社員の頭の中や個人のパソコンの中にしか存在しない場合もあるのです。 そのため、社内の情報をまとめて保管しておく場所を決めておき、検索すれば必要な情報を必ず見つけられる状態を整備しましょう。 業務の属人化を解消できる 社内の情報を一元化すると、業務の属人化を解消できます。 社内で情報管理の方法が決まっていれば、共有や更新がしやすくなり、情報の属人化を防げるのです。ただし、ExcelやWordなどのファイル形式で共有すると、タイトルだけで中身を把握しづらくいちいちファイルを開く手間がかかります。 そのため、社内のマニュアルや過去事例などのナレッジは専用ツールで管理しましょう。たとえば、ナレッジ管理ツールの「ナレカン」は、AIによる添付ファイルの自動要約機能が備わっているので、既存のExcelファイルを貼り付けるだけで運用を始められます。 業務時間の短縮につながる 社内情報を一元管理すると、業務時間の短縮につながります。 社内文書や資料が複数のシステムやツールに分散していると、それぞれの場所をすべて検索しなくてはならず、煩わしいです。一方、社内情報を一元化して、「一箇所を検索すれば欲しい情報が必ず見つかる」という状態なら情報を探している時間を短縮できます。 そのため、本来の業務に時間をかけられるようになり、生産性が上がるのです。また、無駄な業務時間がなくなって社員の業務負担も減り、従業員満足度の向上も期待できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【3ステップ】社内情報を一元管理する方法 以下では、社内情報を一元管理する方法を3ステップでご紹介します。社内情報を一元化したいが、具体的な方法がわからないという担当者の方は必見です。 ステップ1|どこに何の情報があるのか整理する 社内情報を一元化する前に、まず「どこに何の情報があるのか」を整理しましょう。 たとえば、社内のファイルストレージや個人のパソコン、そもそもマニュアル化されていない暗黙知など、それぞれの場所にどんな情報が格納されているかを把握する必要があります。 社内に散在している情報を可視化することが、社内情報の一元化の最初のステップです。 ステップ2|一元管理する情報を選定する 次に、一元管理する情報を選定しましょう。 ステップ1で集めた社内情報にはさまざまな種類があるため、管理したい情報ごとにまとめます。たとえば、顧客データからグラフや表を作成したいのか、社内全体で活用する業務マニュアルやノウハウを蓄積したいのかによって、管理すべき情報が変わります。 また、重複していたり古くなっていたりする情報がないかも確認しておくことが重要です。 ステップ3|ツールを選定する 最後に、一元管理したい情報の種類と目的に合わせてツールを選定しましょう。 専用ツールがなくてもExcelなどで代用はできますが、運用ルールや使い方に工夫が必要です。とくに、ファイルでの管理は更新に手間がかかるうえ、タイトルからは内容を把握しづらく情報の検索性が低いので、社内でナレッジが活用されません。 そのため、顧客データの管理や売上予測にはCRMやSFAなどの専門ツール、社内全体で使うマニュアルや業務ノウハウの共有にはナレッジ管理専用ツールの利用が適しています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報の一元化に最も適したツール 以下では、社内情報の一元化に最も適したツールをご紹介します。 社内に散在する情報をナレッジ管理専用のツールで管理すれば、情報を探す時間が削減できて業務効率が上がります。また、共有ストレージや個人のパソコンに散在しているマニュアルやノウハウなどのナレッジを共有すれば、業務の属人化解消も期待できます。 ただし、ナレッジを一元管理しても社員が必要な情報に即アクセスできる検索性が備わっていなければ、「あるはずの情報が見つからない」という事態に陥ります。そこで、誰が検索しても欲しい情報へ確実にたどり着けるツールを導入しましょう。 結論、社内の情報を一元管理するなら、あらゆるファイル形式でナレッジを保管できてAIを活用したチャット形式の検索機能が備わった「ナレカン」が最適です。 ナレカンの「記事」には、ファイルやテキスト、画像などあらゆる形式の資料をまとめられ、検索すればナレカンAIが全ての資料から適切な情報を提示します。また、添付したファイルはAIが自動要約してくれるので、ファイルを開かずに内容を把握できるのです。 社内のナレッジを一元管理して超高精度で検索できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報を一元管理するときの注意点 社内情報を一元管理するときは、すでに社内に存在する情報を移管する手間がかかることに注意しましょう。 社内に散在しているマニュアルやノウハウを集めて、内容を精査・整理したうえでツールに移管しなくてはならないため、ある程度の手間と時間がかかります。そこで、既存の社内資料の移行支援をしてくれるなどのサポートがあるツールを選ぶと、導入がスムーズです。 たとえば、「ナレカン」は、社内の既存データの移行支援のほか、「メンバー登録」や「部署登録」などの初期設定支援やツールの利用状況レポートの利用が可能なので、導入・運用の負担を最小限に抑えられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報を一元管理する方法やメリットまとめ これまで、社内情報を一元管理する方法やメリットを中心にご紹介しました。 マニュアルや業務ノウハウなどの社内ナレッジを一元管理すると、社員が必要な情報を入手しやすくなり、業務効率の向上や属人化の解消に貢献します。また、社内情報の一元管理には専用ツールを使うと、管理や運用の手間が軽減されます。 ただし、大量の社内ナレッジから欲しい情報に即アクセスできるように、超高精度で検索できるツールを選びましょう。とくに、AIによるチャット形式での検索ができると、社員の検索スキルによらず思い通りの情報にたどり着けます。 したがって、社内情報を一元管理するなら、社内のあちこちに散らばったナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、スムーズに社内情報を一元化し、社内の業務効率を向上させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む
2025年03月27日情報の一元化とは?一元管理する方法やメリット、おすすめツールを紹介近年、インターネットの発達やAI技術の進歩によって、多くの情報が簡単に入手できるようになりました。企業においても社内情報のデータベースや顧客のビッグデータが積極的に活用されています。 一方で、「収集した情報を一元化したいが、どのように管理すれば良いかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、情報を一元化する方法やメリット、おすすめの情報管理ツールを中心にご紹介します。 社内情報を一元化するやり方を知りたい 情報を一元管理するメリットを把握したい 社内情報の一元管理に適したツールを探している という方はこの記事を参考にすると、社内に散在する情報を一元化して収集した情報をナレッジとして十分に活用できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 情報の一元化とは2 一元化すべき情報とは3 社内情報を一元化するメリット3.1 検索性が向上する3.2 業務の属人化を解消できる3.3 業務時間の短縮につながる4 【3ステップ】社内情報を一元管理する方法4.1 ステップ1|どこに何の情報があるのか整理する4.2 ステップ2|一元管理する情報を選定する4.3 ステップ3|ツールを選定する5 社内情報の一元化に最も適したツール5.1 社内のナレッジを一元管理して超高精度で検索できるツール「ナレカン」6 社内情報を一元管理するときの注意点7 社内情報を一元管理する方法やメリットまとめ 情報の一元化とは 情報の一元化とは、社内のあちこちに散らばっている情報を一箇所にまとめて管理することです。 顧客との商談記録や会議資料、マニュアルなど、社内情報は日々増えていきます。そのため、社員それぞれが自身のパソコンやストレージで業務情報を管理していると、担当者の不在時に対応が遅滞したり引き継ぎに時間がかかったりする恐れがあります。 また、情報を共有する場所を整備しておかないと業務ノウハウが属人化してしまい、ナレッジが社内に蓄積されていきません。したがって、社内情報を適切に管理・活用するためには情報を一元化して保管する場所を用意することが求められるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 一元化すべき情報とは 社内情報のなかでも、とくに一元化すべき情報には以下の3つがあります。 全社で共有するべき社内規定やお知らせ 社内規定の変更や社内行事のお知らせなどは、全社にすぐ共有し、常に全員が確認しやすいように管理しなくてはなりません。 顧客対応の記録や過去のトラブル事例 顧客との商談記録や過去のトラブル事例は、社内にナレッジとして蓄積し、必要なときに誰もが参考にできるようにしておきましょう。 業務に使うマニュアルや資料 頻繁に更新される業務マニュアルや社内資料は、一箇所にまとめて検索しやすいようにしておくべきです。 以上の3つを一元管理すれば、社内の情報に誰もが即アクセスできる状態になります。ただし、蓄積した情報は検索すれば確実に見つかるように「ナレカン」のような検索性に優れたツールで保管しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報を一元化するメリット 以下では、社内情報を一元化するメリットを解説します。社内情報の一元管理によって得られる効果を把握しきれていない担当者の方は必見です。 検索性が向上する 社内情報を一元化すると、検索性が向上します。 業務のマニュアルや会議資料が社内のあちこちに散在していると、どこに何を保存したかわからず、探すのに時間がかかります。また、そもそも業務ノウハウや手引書が共有されておらず、社員の頭の中や個人のパソコンの中にしか存在しない場合もあるのです。 そのため、社内の情報をまとめて保管しておく場所を決めておき、検索すれば必要な情報を必ず見つけられる状態を整備しましょう。 業務の属人化を解消できる 社内の情報を一元化すると、業務の属人化を解消できます。 社内で情報管理の方法が決まっていれば、共有や更新がしやすくなり、情報の属人化を防げるのです。ただし、ExcelやWordなどのファイル形式で共有すると、タイトルだけで中身を把握しづらくいちいちファイルを開く手間がかかります。 そのため、社内のマニュアルや過去事例などのナレッジは専用ツールで管理しましょう。たとえば、ナレッジ管理ツールの「ナレカン」は、AIによる添付ファイルの自動要約機能が備わっているので、既存のExcelファイルを貼り付けるだけで運用を始められます。 業務時間の短縮につながる 社内情報を一元管理すると、業務時間の短縮につながります。 社内文書や資料が複数のシステムやツールに分散していると、それぞれの場所をすべて検索しなくてはならず、煩わしいです。一方、社内情報を一元化して、「一箇所を検索すれば欲しい情報が必ず見つかる」という状態なら情報を探している時間を短縮できます。 そのため、本来の業務に時間をかけられるようになり、生産性が上がるのです。また、無駄な業務時間がなくなって社員の業務負担も減り、従業員満足度の向上も期待できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【3ステップ】社内情報を一元管理する方法 以下では、社内情報を一元管理する方法を3ステップでご紹介します。社内情報を一元化したいが、具体的な方法がわからないという担当者の方は必見です。 ステップ1|どこに何の情報があるのか整理する 社内情報を一元化する前に、まず「どこに何の情報があるのか」を整理しましょう。 たとえば、社内のファイルストレージや個人のパソコン、そもそもマニュアル化されていない暗黙知など、それぞれの場所にどんな情報が格納されているかを把握する必要があります。 社内に散在している情報を可視化することが、社内情報の一元化の最初のステップです。 ステップ2|一元管理する情報を選定する 次に、一元管理する情報を選定しましょう。 ステップ1で集めた社内情報にはさまざまな種類があるため、管理したい情報ごとにまとめます。たとえば、顧客データからグラフや表を作成したいのか、社内全体で活用する業務マニュアルやノウハウを蓄積したいのかによって、管理すべき情報が変わります。 また、重複していたり古くなっていたりする情報がないかも確認しておくことが重要です。 ステップ3|ツールを選定する 最後に、一元管理したい情報の種類と目的に合わせてツールを選定しましょう。 専用ツールがなくてもExcelなどで代用はできますが、運用ルールや使い方に工夫が必要です。とくに、ファイルでの管理は更新に手間がかかるうえ、タイトルからは内容を把握しづらく情報の検索性が低いので、社内でナレッジが活用されません。 そのため、顧客データの管理や売上予測にはCRMやSFAなどの専門ツール、社内全体で使うマニュアルや業務ノウハウの共有にはナレッジ管理専用ツールの利用が適しています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報の一元化に最も適したツール 以下では、社内情報の一元化に最も適したツールをご紹介します。 社内に散在する情報をナレッジ管理専用のツールで管理すれば、情報を探す時間が削減できて業務効率が上がります。また、共有ストレージや個人のパソコンに散在しているマニュアルやノウハウなどのナレッジを共有すれば、業務の属人化解消も期待できます。 ただし、ナレッジを一元管理しても社員が必要な情報に即アクセスできる検索性が備わっていなければ、「あるはずの情報が見つからない」という事態に陥ります。そこで、誰が検索しても欲しい情報へ確実にたどり着けるツールを導入しましょう。 結論、社内の情報を一元管理するなら、あらゆるファイル形式でナレッジを保管できてAIを活用したチャット形式の検索機能が備わった「ナレカン」が最適です。 ナレカンの「記事」には、ファイルやテキスト、画像などあらゆる形式の資料をまとめられ、検索すればナレカンAIが全ての資料から適切な情報を提示します。また、添付したファイルはAIが自動要約してくれるので、ファイルを開かずに内容を把握できるのです。 社内のナレッジを一元管理して超高精度で検索できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報を一元管理するときの注意点 社内情報を一元管理するときは、すでに社内に存在する情報を移管する手間がかかることに注意しましょう。 社内に散在しているマニュアルやノウハウを集めて、内容を精査・整理したうえでツールに移管しなくてはならないため、ある程度の手間と時間がかかります。そこで、既存の社内資料の移行支援をしてくれるなどのサポートがあるツールを選ぶと、導入がスムーズです。 たとえば、「ナレカン」は、社内の既存データの移行支援のほか、「メンバー登録」や「部署登録」などの初期設定支援やツールの利用状況レポートの利用が可能なので、導入・運用の負担を最小限に抑えられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内情報を一元管理する方法やメリットまとめ これまで、社内情報を一元管理する方法やメリットを中心にご紹介しました。 マニュアルや業務ノウハウなどの社内ナレッジを一元管理すると、社員が必要な情報を入手しやすくなり、業務効率の向上や属人化の解消に貢献します。また、社内情報の一元管理には専用ツールを使うと、管理や運用の手間が軽減されます。 ただし、大量の社内ナレッジから欲しい情報に即アクセスできるように、超高精度で検索できるツールを選びましょう。とくに、AIによるチャット形式での検索ができると、社員の検索スキルによらず思い通りの情報にたどり着けます。 したがって、社内情報を一元管理するなら、社内のあちこちに散らばったナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、スムーズに社内情報を一元化し、社内の業務効率を向上させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む -
 2025年03月27日社内システムとは?内製化のデメリットや解決策を紹介!DXが進む今日、業務の効率化やペーパーレス化などの目的で、あらゆる企業が社内システムを導入しています。 しかし、「社内システムを導入したいが、自社に適したものが分からず困っている」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内システムが使いづらい原因や解決策を中心にご紹介します。 新たに社内システムを導入して業務効率化を実現したい 社内システムが使いづらい原因と解決策を把握したい すぐに運用に乗せられるような社内システムを探している という方はこの記事を参考にすると、社内システムが使いづらい原因が分かるだけでなく、簡単に業務効率化をする方法までわかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 社内システムとは2 社内システムが使いづらい3つの原因2.1 (1)導入前の準備が不十分2.2 (2)システムが複雑化している2.3 (3)導入後のサポートができていない3 社内システムを内製化するデメリット3.1 (1)開発・運用コストがかかる3.2 (2)エンジニアの人員を確保する必要がある3.3 (3)システムの品質が低下する恐れがある4 【必見】開発不要で簡単に業務効率化を実現する方法4.1 誰でも簡単に社内情報を管理できるツール「ナレカン」5 社内システムの運用におけるポイント6 社内システムが使いづらい原因や解決策まとめ 社内システムとは 社内システムとは、社内で使用する業務システム全般のことです。 具体的には、販売管理システムや勤怠管理システム、顧客管理システムなどを指します。これらのシステムは利益に直結するものではありませんが、自社の業務を円滑かつ効率的に進め、生産性を向上させる点において重要な役割を果たすのです。 また、システム導入の選択肢としては、「既製品のツールを利用する」「社内でシステムを構築する」の2つが挙げられます。コストや社員のITスキルを考慮したうえで、自社に適した方を選択しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムが使いづらい3つの原因 以下では、社内システムが使いづらい3つの原因をご紹介します。社内システムが使いづらく悩んでいる方は必見です。 (1)導入前の準備が不十分 1つ目の原因は、導入前の準備が不十分である点です。 とくに準備不足になりやすい点として、必要な機能の選定が挙げられます。現場の業務を十分に理解せずに機能を選定すると、理想的なフローに合っていても実際には使いづらいシステムになってしまうのです。 また、内製する場合は開発計画が不十分であると、開発に過剰な時間がかかったりリソース不足になったりする可能性があります。したがって、システムの導入や内製にあたっては入念な準備を心掛けましょう。 (2)システムが複雑化している 2つ目の原因は、システムが複雑している点です。 システムの改良や修正を繰り返した結果、似たような機能が複数存在したり、機能が多すぎたりしてシステムが複雑化してしまう場合があります。そのため、かえって使いづらくなり、業務効率の低下を招いてしまうのです。 そのため、社員の意見を定期的に聞き、機能の重複や不要な機能を見直して必要な機能のみが搭載されたシステムを導入することが重要です。 (3)導入後のサポートができていない 3つ目の原因は、導入後のサポートができていない点です。 どれだけ高性能なシステムを導入しても、社内で定着しなければ意味がありません。システムの運用こそが本番であり、そのためにはサポートが欠かせないのです。 したがって、システムを内製する場合は社内の情報システム部や、各部署のITに強い人材を中心にサポート対応をしましょう。既存のシステムを利用する場合は、導入サポートが充実しているか十分確認しておく必要があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムを内製化するデメリット 以下では、社内システムを自社で構築するデメリットを3つご紹介します。社内システムの内製化を検討している方は、必ず確認しましょう。 (1)開発・運用コストがかかる デメリット1つ目は、開発・運用コストがかかる点です。 システム開発の場合、パソコン端末やサーバー、ネットワークなどのハードウェアや、業務管理を行うソフトウェアの準備が必要になります。また、作業場所の確保や備品の用意もしなければなりません。 そのため、「予想以上のコストが発生した」という事態を防ぐには、あらかじめ必要な設備や道具、その費用を試算しておくことが重要です。さらに、初期費用だけでなく、保守や運用にコストも考慮しておきましょう。 (2)エンジニアの人員を確保する必要がある デメリット2つ目は、エンジニアの人員確保が必要な点です。 システム開発の内製化において、必要なスキルを持つ人材を揃えることは必須です。そのためには、既存社員の育成するか、外部から人材を採用する必要があります。 しかし、外部委託が長期にわたると社内に知識を持つ人材が不足しやすく、育成に時間を要します。また、確保した人材が異動・退職するときには、引き継ぎが欠かせない点にも注意しましょう。 (3)システムの品質が低下する恐れがある デメリット3つ目は、システムの品質が低下する恐れがある点です。 内製化すると、システム開発を専門とする企業に依頼するよりも技術やノウハウが不足しやすく、システムの機能が求めていたレベルに届かない恐れがあります。結果として、システムエラーが発生したり改良・修正に手間がかかり、業務効率が下がってしまうのです。 そのため、内製化でシステムの品質を維持するには、十分なスキルを持つ人材を確保し、継続的な教育とサポート体制を整えなければなりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】開発不要で簡単に業務効率化を実現する方法 以下では、開発不要で簡単に業務効率化を実現できるITツールをご紹介します。 社内システムを導入すれば、円滑に業務を進められ業務効率の向上が期待できます。しかし、自社で開発をするとなると多大なコストがかかるうえ、検証や改修も自社で実施する必要があるため、かえって業務量が増え対応が追いつかなくなる恐れがあるのです。 そこで、「社内のあらゆる情報を一元管理できるITツール」を導入し、業務効率化を実現させましょう。しかし、多機能で複雑なツールでは使いこなせず、社内情報が散在してしまうため「シンプルな操作性で目的の情報へアクセスしやすいツール」を選ぶべきです。 結論、社内の業務効率化には、誰でも簡単に社内情報を管理でき、高精度の検索機能で目的の情報に即アクセス可能な「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、テキストやファイルを残してすばやく共有でき、「キーワード検索」やAIを活用した「自然言語検索」などの機能で欲しい情報をすぐに見つけられます。また、既存データの移行支援等のサポートによってすぐに運用に乗せられるのです。 誰でも簡単に社内情報を管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムの運用におけるポイント ここでは、社内システムの運用におけるポイントをご紹介します。システムの運用方法に不安がある方は、以下を参考にしましょう。 システムの導入目的を明確にする 社内システムの導入目的を明確にすることで、社員がその重要性を理解し、システムを活用しやすくなります。また、どの機能がどの分野の目標達成に役立つかを理解できるのです。 継続的なサポートを実施する システム導入後も、トラブルへの迅速な対応や定期的なメンテナンスなど、継続的なサポートを提供することが重要です。また、実際にシステムを使用する社員の意見も積極的に反映させましょう。 以上のように、効果的な社内システムの運用を目指しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムが使いづらい原因や解決策まとめ これまで、社内システムが使いづらい原因や内製化のデメリット、運用ポイントを中心にご紹介しました。 社内システムを活用することで、業務の効率化や生産性の向上につながります。しかし、内製化する場合、開発コストがかかるだけでなく、人材育成や定期的なサポートなどにより、業務負担が大きくなってしまうのです。 そこで、「社内のナレッジを一元管理できるITツール」を導入すれば、開発不要で業務効率化を実現できます。ただし、複雑なツールでは使いこなせず放置されてしまう恐れがあるため、「シンプルな操作性であるか」を確認しましょう。 結論、自社が導入すべきなのは、社内のあらゆる情報を一元管理でき、目的の情報がすぐに見つかる「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、社内の業務を円滑に進めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む
2025年03月27日社内システムとは?内製化のデメリットや解決策を紹介!DXが進む今日、業務の効率化やペーパーレス化などの目的で、あらゆる企業が社内システムを導入しています。 しかし、「社内システムを導入したいが、自社に適したものが分からず困っている」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内システムが使いづらい原因や解決策を中心にご紹介します。 新たに社内システムを導入して業務効率化を実現したい 社内システムが使いづらい原因と解決策を把握したい すぐに運用に乗せられるような社内システムを探している という方はこの記事を参考にすると、社内システムが使いづらい原因が分かるだけでなく、簡単に業務効率化をする方法までわかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 社内システムとは2 社内システムが使いづらい3つの原因2.1 (1)導入前の準備が不十分2.2 (2)システムが複雑化している2.3 (3)導入後のサポートができていない3 社内システムを内製化するデメリット3.1 (1)開発・運用コストがかかる3.2 (2)エンジニアの人員を確保する必要がある3.3 (3)システムの品質が低下する恐れがある4 【必見】開発不要で簡単に業務効率化を実現する方法4.1 誰でも簡単に社内情報を管理できるツール「ナレカン」5 社内システムの運用におけるポイント6 社内システムが使いづらい原因や解決策まとめ 社内システムとは 社内システムとは、社内で使用する業務システム全般のことです。 具体的には、販売管理システムや勤怠管理システム、顧客管理システムなどを指します。これらのシステムは利益に直結するものではありませんが、自社の業務を円滑かつ効率的に進め、生産性を向上させる点において重要な役割を果たすのです。 また、システム導入の選択肢としては、「既製品のツールを利用する」「社内でシステムを構築する」の2つが挙げられます。コストや社員のITスキルを考慮したうえで、自社に適した方を選択しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムが使いづらい3つの原因 以下では、社内システムが使いづらい3つの原因をご紹介します。社内システムが使いづらく悩んでいる方は必見です。 (1)導入前の準備が不十分 1つ目の原因は、導入前の準備が不十分である点です。 とくに準備不足になりやすい点として、必要な機能の選定が挙げられます。現場の業務を十分に理解せずに機能を選定すると、理想的なフローに合っていても実際には使いづらいシステムになってしまうのです。 また、内製する場合は開発計画が不十分であると、開発に過剰な時間がかかったりリソース不足になったりする可能性があります。したがって、システムの導入や内製にあたっては入念な準備を心掛けましょう。 (2)システムが複雑化している 2つ目の原因は、システムが複雑している点です。 システムの改良や修正を繰り返した結果、似たような機能が複数存在したり、機能が多すぎたりしてシステムが複雑化してしまう場合があります。そのため、かえって使いづらくなり、業務効率の低下を招いてしまうのです。 そのため、社員の意見を定期的に聞き、機能の重複や不要な機能を見直して必要な機能のみが搭載されたシステムを導入することが重要です。 (3)導入後のサポートができていない 3つ目の原因は、導入後のサポートができていない点です。 どれだけ高性能なシステムを導入しても、社内で定着しなければ意味がありません。システムの運用こそが本番であり、そのためにはサポートが欠かせないのです。 したがって、システムを内製する場合は社内の情報システム部や、各部署のITに強い人材を中心にサポート対応をしましょう。既存のシステムを利用する場合は、導入サポートが充実しているか十分確認しておく必要があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムを内製化するデメリット 以下では、社内システムを自社で構築するデメリットを3つご紹介します。社内システムの内製化を検討している方は、必ず確認しましょう。 (1)開発・運用コストがかかる デメリット1つ目は、開発・運用コストがかかる点です。 システム開発の場合、パソコン端末やサーバー、ネットワークなどのハードウェアや、業務管理を行うソフトウェアの準備が必要になります。また、作業場所の確保や備品の用意もしなければなりません。 そのため、「予想以上のコストが発生した」という事態を防ぐには、あらかじめ必要な設備や道具、その費用を試算しておくことが重要です。さらに、初期費用だけでなく、保守や運用にコストも考慮しておきましょう。 (2)エンジニアの人員を確保する必要がある デメリット2つ目は、エンジニアの人員確保が必要な点です。 システム開発の内製化において、必要なスキルを持つ人材を揃えることは必須です。そのためには、既存社員の育成するか、外部から人材を採用する必要があります。 しかし、外部委託が長期にわたると社内に知識を持つ人材が不足しやすく、育成に時間を要します。また、確保した人材が異動・退職するときには、引き継ぎが欠かせない点にも注意しましょう。 (3)システムの品質が低下する恐れがある デメリット3つ目は、システムの品質が低下する恐れがある点です。 内製化すると、システム開発を専門とする企業に依頼するよりも技術やノウハウが不足しやすく、システムの機能が求めていたレベルに届かない恐れがあります。結果として、システムエラーが発生したり改良・修正に手間がかかり、業務効率が下がってしまうのです。 そのため、内製化でシステムの品質を維持するには、十分なスキルを持つ人材を確保し、継続的な教育とサポート体制を整えなければなりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【必見】開発不要で簡単に業務効率化を実現する方法 以下では、開発不要で簡単に業務効率化を実現できるITツールをご紹介します。 社内システムを導入すれば、円滑に業務を進められ業務効率の向上が期待できます。しかし、自社で開発をするとなると多大なコストがかかるうえ、検証や改修も自社で実施する必要があるため、かえって業務量が増え対応が追いつかなくなる恐れがあるのです。 そこで、「社内のあらゆる情報を一元管理できるITツール」を導入し、業務効率化を実現させましょう。しかし、多機能で複雑なツールでは使いこなせず、社内情報が散在してしまうため「シンプルな操作性で目的の情報へアクセスしやすいツール」を選ぶべきです。 結論、社内の業務効率化には、誰でも簡単に社内情報を管理でき、高精度の検索機能で目的の情報に即アクセス可能な「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、テキストやファイルを残してすばやく共有でき、「キーワード検索」やAIを活用した「自然言語検索」などの機能で欲しい情報をすぐに見つけられます。また、既存データの移行支援等のサポートによってすぐに運用に乗せられるのです。 誰でも簡単に社内情報を管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムの運用におけるポイント ここでは、社内システムの運用におけるポイントをご紹介します。システムの運用方法に不安がある方は、以下を参考にしましょう。 システムの導入目的を明確にする 社内システムの導入目的を明確にすることで、社員がその重要性を理解し、システムを活用しやすくなります。また、どの機能がどの分野の目標達成に役立つかを理解できるのです。 継続的なサポートを実施する システム導入後も、トラブルへの迅速な対応や定期的なメンテナンスなど、継続的なサポートを提供することが重要です。また、実際にシステムを使用する社員の意見も積極的に反映させましょう。 以上のように、効果的な社内システムの運用を目指しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内システムが使いづらい原因や解決策まとめ これまで、社内システムが使いづらい原因や内製化のデメリット、運用ポイントを中心にご紹介しました。 社内システムを活用することで、業務の効率化や生産性の向上につながります。しかし、内製化する場合、開発コストがかかるだけでなく、人材育成や定期的なサポートなどにより、業務負担が大きくなってしまうのです。 そこで、「社内のナレッジを一元管理できるITツール」を導入すれば、開発不要で業務効率化を実現できます。ただし、複雑なツールでは使いこなせず放置されてしまう恐れがあるため、「シンプルな操作性であるか」を確認しましょう。 結論、自社が導入すべきなのは、社内のあらゆる情報を一元管理でき、目的の情報がすぐに見つかる「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、社内の業務を円滑に進めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む -
 2025年03月27日基幹システムとは?ERPとの違いや選定ポイントをわかりやすく解説基幹システムとは、企業の主要部分となる業務を効率化するシステムです。ただし、企業によって主要となる業務は異なるので、基幹システムと一口に言っても種類は多岐にわたります。 そのため、「基幹システムを導入したいが、具体的にどのようなシステムがあるのかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、基幹システムの概要や選定ポイントを中心にご紹介します。 基幹システムの概要を把握したい 基幹システムとERPとの違いを知りたい 導入した基幹システムを社内に浸透させる方法を探している という方はこの記事を参考にすると、基幹システムにどのような種類があるかだけでなく、導入した基幹システムを社内に浸透させる方法までわかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 基幹システムとは1.1 ERPとの違い1.2 SAPとの違い2 基幹システムの主な機能3 基幹システムの選定ポイント3選3.1 (1)クラウド型かオンプレミス型か3.2 (2)自社の業務内容に合っているか3.3 (3)導入・運用のサポートが手厚いか4 社内の基幹システムの運用を円滑にするツール4.1 基幹システムの操作マニュアルを一元管理できるツール「ナレカン」5 基幹システムの概要や選定ポイントまとめ 基幹システムとは ここでは、基幹システムの概要についてわかりやすく解説します。基幹システムが具体的にどのようなものかわからないという方は必見です。 ERPとの違い 基幹システムは、労務部や経理部などの各部署で利用される、業務を円滑化するためのシステムを指すのに対し、ERPは各部門の基幹システムを連携し、データを一元管理するシステムを指します。 そもそも、ERPとはEnterprise Resource Planningの略で、日本語では「企業資源計画」と訳されるものです。しかし近年では、企業内の資源を適切に配置するためのシステムそのものをERPと呼称しています。 つまり、基幹システムをまとめて管理しているのがERPです。 SAPとの違い SAPは、基幹システムのうちの一つです。 SAPとは、ドイツのSAP社が提供する基幹システムの名称で、多くの日本企業に導入されています。 そのため、基幹システムという意味でSAPという言葉が使われる場合もあります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 基幹システムの主な機能 基幹システムの主な機能は、以下の6つです。 生産管理 生産管理システムは、製造計画を立てたり受注状況から材料の調達量を決定したりするのに必要な機能で、主に製造業で利用されます。在庫管理システムと連携して、無駄のない事業運営に貢献します。 在庫管理 在庫管理システムは、在庫数や棚卸し業務を支援するシステムで、在庫を抱えすぎたり欠品が発生したりするのを防ぎます。会社の利益に関わる重要な業務なので、システムの導入によって人為的なミスを軽減しましょう。 販売管理 販売管理システムは、受注や売上などを管理するシステムで、製造業や流通業の会社では必須です。在庫管理システムや生産管理システムと連携して、企業の一連の業務を円滑に進めます。 労務管理 労務管理システムは、社員の給与や就労時間の管理、採用活動の支援に利用されるシステムです。業種問わず必要な業務であるため、労務管理業務を適切に実施することで、社内の人的リソースの配分や人事評価の円滑な実施に役立ちます。 財務会計 財務会計システムは、会社の財務・会計を効率化するシステムです。会計帳票や決算書の作成の一部を自動化して、業務負荷を軽減できます。 情報管理 情報管理システムは、社内の情報を一元管理し、必要なデータに即座にアクセスできるようにするシステムです。社内システムのマニュアルや業務ノウハウなどの情報資産(ナレッジ)の管理は、企業の基盤になるのでシステムで効率化しましょう。 ただし、システムによって対応している業務範囲や利用方法が異なるので、システムを導入するときは各システムを比較して慎重に検討を進めることが重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 基幹システムの選定ポイント3選 ここでは、基幹システムの選定ポイントをご紹介します。自社に基幹システムを導入するときは以下の選定ポイントを参考にしましょう。 (1)クラウド型かオンプレミス型か 基幹システムの選定ポイントの1つ目は、クラウド型かオンプレミス型かです。 オンプレミス型は、自社のサーバを利用するためセキュリティが強固ですが、ピーク時の稼働量に合わせてストレージ容量を決めるので、稼働量が少ない最初のうちは費用対効果が低くなる恐れがあります。また、メンテナンスの手間がかかる点にも注意しましょう。 一方、クラウド型はオンラインで提供されているサービスを利用するので、自社でメンテナンスする必要がありません。また、現時点で必要なストレージ容量を確保すれば良いため、費用を抑えられるのです。 そのため、費用を抑えて自社の業務効率を向上させたい場合は、クラウド型のシステムを利用するのがおすすめです。 (2)自社の業務内容に合っているか 基幹システムの選定ポイントの2つ目は、自社の業務内容に合っているかです。 基幹システムは、同じ機能を持つものでもシステムによって対応している業務や操作方法が異なります。そのため、自社の業務内容に必要な機能を見極めなければ、かえって業務が遅滞したり不要な機能に利用料金を払ったりする恐れがあるのです。 したがって、基幹システムをどのように利用したいのかを明確にしたうえで導入するシステムを決定しましょう。 (3)導入・運用のサポートが手厚いか 基幹システムの選定ポイントの3つ目は、導入・運用のサポートが手厚いかです。 基幹システムを導入しても、操作が複雑すぎて社員が使いこなせなければ社内に浸透せず、システムが形骸化してしまいます。そのため、自社に新しいシステムやツールを導入するときは、導入・運用のサポートが充実しているかを必ず確認するべきです。 たとえば、社内情報の管理には既存の社内情報のデータ移管がある「ナレカン」のようなシステムを利用すると、導入から運用までがスムーズです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内の基幹システムの運用を円滑にするツール 以下では、社内の基幹システムの運用を円滑にするツールをご紹介します。 基幹システムは、財務管理や労務管理、在庫管理など企業が事業を運営するうえで必須の機能を備えています。しかし、システムの操作方法や業務での利用方法を社内で共有しなくては、導入したシステムが現場で使われず、形骸化する恐れがあるのです。 そのため、基幹システムの機能の中でも情報管理がとくに重要です。ただし、基幹システムのマニュアルなどの社内情報をファイルストレージや操作の複雑なシステム上で共有すると他のファイルに埋もれたり、探すのに時間がかかったりします。 したがって、社内情報は誰もが即アクセスできるよう、検索性に優れたツールで保管しましょう。結論、社内のあらゆるナレッジを一元管理するなら、格納した情報をAI検索によって必要なときにすぐ確認できるツール「ナレカン」が最適です。 ナレカンの「記事」に記載した情報は、”上司に話しかけるように”口語で検索できるので、誰が検索しても欲しい情報を確実に見つけられます。また、添付画像内の文章も検索可能なので、ファイルの中身をいちいち開いて確認する手間が一切かかりません。 基幹システムの操作マニュアルを一元管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 基幹システムの概要や選定ポイントまとめ これまで、基幹システムの概要や選定ポイントを中心にご紹介しました。 基幹システムは、企業の中心となる業務を円滑に進めるために必要です。とくに、社内の情報資産(ナレッジ)の管理は業種・業態問わず重要なので、検索性に優れたシステムで情報を一元管理しましょう。 なかでも、AIによるチャット形式での検索が可能なシステムであれば、検索したいキーワードを一字一句覚えていなくてもあいまい検索で欲しい情報にたどり着けます。 したがって、情報管理機能を備えた基幹システムを導入するなら、社内の情報資産を守りつつ、欲しい情報にストレスなく即アクセスできるシステム「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、誰もが必要なときに欲しい社内情報を見つけられるようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む
2025年03月27日基幹システムとは?ERPとの違いや選定ポイントをわかりやすく解説基幹システムとは、企業の主要部分となる業務を効率化するシステムです。ただし、企業によって主要となる業務は異なるので、基幹システムと一口に言っても種類は多岐にわたります。 そのため、「基幹システムを導入したいが、具体的にどのようなシステムがあるのかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、基幹システムの概要や選定ポイントを中心にご紹介します。 基幹システムの概要を把握したい 基幹システムとERPとの違いを知りたい 導入した基幹システムを社内に浸透させる方法を探している という方はこの記事を参考にすると、基幹システムにどのような種類があるかだけでなく、導入した基幹システムを社内に浸透させる方法までわかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 基幹システムとは1.1 ERPとの違い1.2 SAPとの違い2 基幹システムの主な機能3 基幹システムの選定ポイント3選3.1 (1)クラウド型かオンプレミス型か3.2 (2)自社の業務内容に合っているか3.3 (3)導入・運用のサポートが手厚いか4 社内の基幹システムの運用を円滑にするツール4.1 基幹システムの操作マニュアルを一元管理できるツール「ナレカン」5 基幹システムの概要や選定ポイントまとめ 基幹システムとは ここでは、基幹システムの概要についてわかりやすく解説します。基幹システムが具体的にどのようなものかわからないという方は必見です。 ERPとの違い 基幹システムは、労務部や経理部などの各部署で利用される、業務を円滑化するためのシステムを指すのに対し、ERPは各部門の基幹システムを連携し、データを一元管理するシステムを指します。 そもそも、ERPとはEnterprise Resource Planningの略で、日本語では「企業資源計画」と訳されるものです。しかし近年では、企業内の資源を適切に配置するためのシステムそのものをERPと呼称しています。 つまり、基幹システムをまとめて管理しているのがERPです。 SAPとの違い SAPは、基幹システムのうちの一つです。 SAPとは、ドイツのSAP社が提供する基幹システムの名称で、多くの日本企業に導入されています。 そのため、基幹システムという意味でSAPという言葉が使われる場合もあります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 基幹システムの主な機能 基幹システムの主な機能は、以下の6つです。 生産管理 生産管理システムは、製造計画を立てたり受注状況から材料の調達量を決定したりするのに必要な機能で、主に製造業で利用されます。在庫管理システムと連携して、無駄のない事業運営に貢献します。 在庫管理 在庫管理システムは、在庫数や棚卸し業務を支援するシステムで、在庫を抱えすぎたり欠品が発生したりするのを防ぎます。会社の利益に関わる重要な業務なので、システムの導入によって人為的なミスを軽減しましょう。 販売管理 販売管理システムは、受注や売上などを管理するシステムで、製造業や流通業の会社では必須です。在庫管理システムや生産管理システムと連携して、企業の一連の業務を円滑に進めます。 労務管理 労務管理システムは、社員の給与や就労時間の管理、採用活動の支援に利用されるシステムです。業種問わず必要な業務であるため、労務管理業務を適切に実施することで、社内の人的リソースの配分や人事評価の円滑な実施に役立ちます。 財務会計 財務会計システムは、会社の財務・会計を効率化するシステムです。会計帳票や決算書の作成の一部を自動化して、業務負荷を軽減できます。 情報管理 情報管理システムは、社内の情報を一元管理し、必要なデータに即座にアクセスできるようにするシステムです。社内システムのマニュアルや業務ノウハウなどの情報資産(ナレッジ)の管理は、企業の基盤になるのでシステムで効率化しましょう。 ただし、システムによって対応している業務範囲や利用方法が異なるので、システムを導入するときは各システムを比較して慎重に検討を進めることが重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 基幹システムの選定ポイント3選 ここでは、基幹システムの選定ポイントをご紹介します。自社に基幹システムを導入するときは以下の選定ポイントを参考にしましょう。 (1)クラウド型かオンプレミス型か 基幹システムの選定ポイントの1つ目は、クラウド型かオンプレミス型かです。 オンプレミス型は、自社のサーバを利用するためセキュリティが強固ですが、ピーク時の稼働量に合わせてストレージ容量を決めるので、稼働量が少ない最初のうちは費用対効果が低くなる恐れがあります。また、メンテナンスの手間がかかる点にも注意しましょう。 一方、クラウド型はオンラインで提供されているサービスを利用するので、自社でメンテナンスする必要がありません。また、現時点で必要なストレージ容量を確保すれば良いため、費用を抑えられるのです。 そのため、費用を抑えて自社の業務効率を向上させたい場合は、クラウド型のシステムを利用するのがおすすめです。 (2)自社の業務内容に合っているか 基幹システムの選定ポイントの2つ目は、自社の業務内容に合っているかです。 基幹システムは、同じ機能を持つものでもシステムによって対応している業務や操作方法が異なります。そのため、自社の業務内容に必要な機能を見極めなければ、かえって業務が遅滞したり不要な機能に利用料金を払ったりする恐れがあるのです。 したがって、基幹システムをどのように利用したいのかを明確にしたうえで導入するシステムを決定しましょう。 (3)導入・運用のサポートが手厚いか 基幹システムの選定ポイントの3つ目は、導入・運用のサポートが手厚いかです。 基幹システムを導入しても、操作が複雑すぎて社員が使いこなせなければ社内に浸透せず、システムが形骸化してしまいます。そのため、自社に新しいシステムやツールを導入するときは、導入・運用のサポートが充実しているかを必ず確認するべきです。 たとえば、社内情報の管理には既存の社内情報のデータ移管がある「ナレカン」のようなシステムを利用すると、導入から運用までがスムーズです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内の基幹システムの運用を円滑にするツール 以下では、社内の基幹システムの運用を円滑にするツールをご紹介します。 基幹システムは、財務管理や労務管理、在庫管理など企業が事業を運営するうえで必須の機能を備えています。しかし、システムの操作方法や業務での利用方法を社内で共有しなくては、導入したシステムが現場で使われず、形骸化する恐れがあるのです。 そのため、基幹システムの機能の中でも情報管理がとくに重要です。ただし、基幹システムのマニュアルなどの社内情報をファイルストレージや操作の複雑なシステム上で共有すると他のファイルに埋もれたり、探すのに時間がかかったりします。 したがって、社内情報は誰もが即アクセスできるよう、検索性に優れたツールで保管しましょう。結論、社内のあらゆるナレッジを一元管理するなら、格納した情報をAI検索によって必要なときにすぐ確認できるツール「ナレカン」が最適です。 ナレカンの「記事」に記載した情報は、”上司に話しかけるように”口語で検索できるので、誰が検索しても欲しい情報を確実に見つけられます。また、添付画像内の文章も検索可能なので、ファイルの中身をいちいち開いて確認する手間が一切かかりません。 基幹システムの操作マニュアルを一元管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 基幹システムの概要や選定ポイントまとめ これまで、基幹システムの概要や選定ポイントを中心にご紹介しました。 基幹システムは、企業の中心となる業務を円滑に進めるために必要です。とくに、社内の情報資産(ナレッジ)の管理は業種・業態問わず重要なので、検索性に優れたシステムで情報を一元管理しましょう。 なかでも、AIによるチャット形式での検索が可能なシステムであれば、検索したいキーワードを一字一句覚えていなくてもあいまい検索で欲しい情報にたどり着けます。 したがって、情報管理機能を備えた基幹システムを導入するなら、社内の情報資産を守りつつ、欲しい情報にストレスなく即アクセスできるシステム「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、誰もが必要なときに欲しい社内情報を見つけられるようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む -
 2025年03月27日【事例あり】社内イントラとは?導入する目的や作成方法を解説!社内イントラとは、「組織内の情報通信網」のことを指します。社内イントラを構築することで、迅速な情報共有が可能となり、業務効率化が実現できます。 とはいえ、「社内イントラをどのように構築すればいいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内イントラの目的や作成方法を中心にご紹介します。 社内イントラの作成方法を知りたい 事例を参考にして社内イントラを構築したい 業務を効率化できる社内イントラツールを探している という方はこの記事を参考にすると、社内イントラの構築方法が分かり、組織全体の生産性向上が期待できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 社内イントラとは1.1 社内イントラの概要1.2 社内イントラと社内ポータルサイトの違い2 社内イントラを作成するメリット2.1 (1)迅速な情報共有が実現できる2.2 (2)社内コミュニケーションが円滑になる2.3 (3)コストを削減できる3 社内イントラの作り方4 最も簡単に社内イントラを構築できるツール4.1 必要な社内情報が即見つかるようになるツール「ナレカン」5 社内イントラネットの活用事例6 社内イントラを導入する目的や作成方法まとめ 社内イントラとは ここでは、社内イントラの概要や社内ポータルサイトとの違いを解説します。「社内イントラが何か分からない」という方は必見です。 社内イントラの概要 社内イントラとは、社内イントラネット(intranet)の略語で、社内のみで使えるネットワークのことです。 社内イントラを活用すれば、社内文書やファイルを安全に共有できます。また、場所や時間を問わず作業が可能になるほか、社員同士の情報共有や連携がスムーズになるのです。 社内イントラと社内ポータルサイトの違い 社内イントラと社内ポータルサイトは、閲覧制限の厳しさが異なります。 社内ポータルサイトは、「URLを知っている社員なら誰でも社内向けのサービスや社内情報を検索・閲覧できる」のに対し、社内イントラは「社内の限られた空間、あるいは端末からのみアクセスできる情報通信網」です。 一方で、社内イントラも社内ポータルサイトも「社内の情報を一元管理してアクセスしやすくしている」点は同じです。 社内で情報が散在していると、必要な情報を探すのに手間がかかり、業務の対応漏れや作業効率の低下につながります。そのため、社内イントラを活用して、社内文書やマニュアルなどのナレッジに即アクセスできるようにしておきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラを作成するメリット ここでは、社内イントラを作成するメリットについて解説します。社内イントラを作成するかを悩んでいる方は必見です。 (1)迅速な情報共有が実現できる 1つ目のメリットは、迅速な情報共有が実現できる点です。 社内イントラにより、「ツールを見れば全ての社内情報を確認できる」といった環境を整えられます。そのため、特定の社員や個人に情報や業務が偏ってしまう課題を解消できます。 このように、社内イントラを作ると、迅速な情報共有が可能となり、業務の属人化防止につながるのです。 (2)社内コミュニケーションが円滑になる 2つ目のメリットは、社内コミュニケーションが円滑になる点です。 社内イントラを構築することで、部署を超えた情報共有が容易になります。そのため、業務連携が取りやすくなるほか、企業としての一体感も生まれます。 また、社内の情報共有がツール上で可能になれば、リモートワークやフレックスタイム制などの多様な働き方にも対応できます。以上のように、社内イントラを導入することで社内での業務連携がスムーズになるのです。 (3)コストを削減できる 3つ目のメリットは、費用や教育コストを削減できる点です。 社内イントラを構築すると、いちいち書類を印刷したりファイリングして保管したりする必要がなくなり、管理費用を抑えられます。また、マニュアルをツール内に共有すれば業務上の不明点を社員が自分で解消できるので、教育コストの削減も可能です。 このように社内イントラを作ることで、管理費用や教育コストの削減が実現します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラの作り方 ここでは、社内イントラの作り方を解説します。ポイントも解説しているので、社内イントラ作成に役立てましょう。 目的を明確化する まず、社内イントラの導入目的を明確にします。社内イントラ導入後の理想を掲げ、現在の課題を考えることで、ツール選定の方向性が定まります。 ツールを選定する 次に、現在の課題をカバーするのに必要な機能を検討し、ツールを選定します。無料トライアル期間を設けているツールでは、無料トライアルで使い勝手を確認してみましょう。 運用ルールを決める 続いて、運用ルールを決めていきます。多岐にわたる部署のメンバーがツールを適切に活用できるように、マニュアルを作成したり、ツールのカスタマイズや拡張性を検討する必要があります。 ツールを運用する 続いて、全社員に周知し、運用を開始します。とくに、導入して間もないうちは社員からフィードバックを収集し、改善をしていくことが重要です。 定期的に振り返る 最後に、ツールの運用においてはPDCAサイクルを回すことが重要です。定期的にツールの使用状況や効果を振り返り、必要に応じて運用ルールを改善をしていきます。 このように、社内イントラをより効果的に活用するために、適切な手順に則って導入していきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 最も簡単に社内イントラを構築できるツール 以下では、最も簡単に社内イントラを構築できるツールをご紹介します。 社内イントラとは、社員同士の情報共有を円滑にし、社内のコミュニケーションを促進する社内情報通信網です。社内イントラツールに、社内に散在しがちな業務マニュアルや共有事項などのナレッジを一元管理すれば、必要な情報をすぐ見つけられます。 ただし、社員全員が思い通りに情報を検索できるように検索機能の優れたツールを導入しましょう。とくに、生成AIによって口語での検索に対応していると欲しい情報を誰もが見つけられます。 結論、社内イントラの構築に最適なツールは、社内の情報を一元管理し、AIを活用した超高精度検索で簡単に情報へアクセスできる「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、あらゆる形式のファイルを添付して任意のメンバーと共有できます。また、生成AIを活用した超高精度の「自然言語検索」が備わっているので、検索スキルに依存せず、誰もが目的の情報にたどり着けます。 必要な社内情報が即見つかるようになるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラネットの活用事例 KOKUYOは、日本を代表する文具やオフィス家具メーカーの企業です。 同社では新規事業を立ち上げるにあたって、他部門との連携が取りづらい階層構造の組織体系が課題でした。多くの新規事業を円滑に進めるためには、部門を横断して情報を共有しながら業務に取り組むことが重要です。 そこで、部門を超えたコミュニケーションを取るためにITツールを導入したところ、自然に業務ノウハウが共有されるようになりました。結果として、上から言われたことをやるだけではなく、社員が主体性を持ってプロジェクトを進められるようになったのです。 参考:「自律的に動く組織へ。Slack 活用で目指すコクヨ式ハイブリッドワーク」│KOKUYO 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラを導入する目的や作成方法まとめ これまで、社内イントラの目的や作成方法を中心に解説してきました。 社内のノウハウやマニュアルなどのナレッジを適切に共有して活用するためには、社内に散在する情報を一元管理する社内イントラツールが必須です。また、社内イントラツールには、必要な情報を確実に見つけられる超高精度の機能が求められます。 そのため、「蓄積したナレッジを超高精度検索機能で簡単にアクセスできるITツール」を利用しましょう。とくに、生成AIによるチャット形式で検索できる検索機能があると便利です。 結論、社内イントラに利用すべきなのは、あらゆる情報を一元化し、生成AIを活用した「自然言語検索」が備わったツール「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、社内情報を共有・管理しやすい体制をつくりましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む
2025年03月27日【事例あり】社内イントラとは?導入する目的や作成方法を解説!社内イントラとは、「組織内の情報通信網」のことを指します。社内イントラを構築することで、迅速な情報共有が可能となり、業務効率化が実現できます。 とはいえ、「社内イントラをどのように構築すればいいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内イントラの目的や作成方法を中心にご紹介します。 社内イントラの作成方法を知りたい 事例を参考にして社内イントラを構築したい 業務を効率化できる社内イントラツールを探している という方はこの記事を参考にすると、社内イントラの構築方法が分かり、組織全体の生産性向上が期待できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 社内イントラとは1.1 社内イントラの概要1.2 社内イントラと社内ポータルサイトの違い2 社内イントラを作成するメリット2.1 (1)迅速な情報共有が実現できる2.2 (2)社内コミュニケーションが円滑になる2.3 (3)コストを削減できる3 社内イントラの作り方4 最も簡単に社内イントラを構築できるツール4.1 必要な社内情報が即見つかるようになるツール「ナレカン」5 社内イントラネットの活用事例6 社内イントラを導入する目的や作成方法まとめ 社内イントラとは ここでは、社内イントラの概要や社内ポータルサイトとの違いを解説します。「社内イントラが何か分からない」という方は必見です。 社内イントラの概要 社内イントラとは、社内イントラネット(intranet)の略語で、社内のみで使えるネットワークのことです。 社内イントラを活用すれば、社内文書やファイルを安全に共有できます。また、場所や時間を問わず作業が可能になるほか、社員同士の情報共有や連携がスムーズになるのです。 社内イントラと社内ポータルサイトの違い 社内イントラと社内ポータルサイトは、閲覧制限の厳しさが異なります。 社内ポータルサイトは、「URLを知っている社員なら誰でも社内向けのサービスや社内情報を検索・閲覧できる」のに対し、社内イントラは「社内の限られた空間、あるいは端末からのみアクセスできる情報通信網」です。 一方で、社内イントラも社内ポータルサイトも「社内の情報を一元管理してアクセスしやすくしている」点は同じです。 社内で情報が散在していると、必要な情報を探すのに手間がかかり、業務の対応漏れや作業効率の低下につながります。そのため、社内イントラを活用して、社内文書やマニュアルなどのナレッジに即アクセスできるようにしておきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラを作成するメリット ここでは、社内イントラを作成するメリットについて解説します。社内イントラを作成するかを悩んでいる方は必見です。 (1)迅速な情報共有が実現できる 1つ目のメリットは、迅速な情報共有が実現できる点です。 社内イントラにより、「ツールを見れば全ての社内情報を確認できる」といった環境を整えられます。そのため、特定の社員や個人に情報や業務が偏ってしまう課題を解消できます。 このように、社内イントラを作ると、迅速な情報共有が可能となり、業務の属人化防止につながるのです。 (2)社内コミュニケーションが円滑になる 2つ目のメリットは、社内コミュニケーションが円滑になる点です。 社内イントラを構築することで、部署を超えた情報共有が容易になります。そのため、業務連携が取りやすくなるほか、企業としての一体感も生まれます。 また、社内の情報共有がツール上で可能になれば、リモートワークやフレックスタイム制などの多様な働き方にも対応できます。以上のように、社内イントラを導入することで社内での業務連携がスムーズになるのです。 (3)コストを削減できる 3つ目のメリットは、費用や教育コストを削減できる点です。 社内イントラを構築すると、いちいち書類を印刷したりファイリングして保管したりする必要がなくなり、管理費用を抑えられます。また、マニュアルをツール内に共有すれば業務上の不明点を社員が自分で解消できるので、教育コストの削減も可能です。 このように社内イントラを作ることで、管理費用や教育コストの削減が実現します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラの作り方 ここでは、社内イントラの作り方を解説します。ポイントも解説しているので、社内イントラ作成に役立てましょう。 目的を明確化する まず、社内イントラの導入目的を明確にします。社内イントラ導入後の理想を掲げ、現在の課題を考えることで、ツール選定の方向性が定まります。 ツールを選定する 次に、現在の課題をカバーするのに必要な機能を検討し、ツールを選定します。無料トライアル期間を設けているツールでは、無料トライアルで使い勝手を確認してみましょう。 運用ルールを決める 続いて、運用ルールを決めていきます。多岐にわたる部署のメンバーがツールを適切に活用できるように、マニュアルを作成したり、ツールのカスタマイズや拡張性を検討する必要があります。 ツールを運用する 続いて、全社員に周知し、運用を開始します。とくに、導入して間もないうちは社員からフィードバックを収集し、改善をしていくことが重要です。 定期的に振り返る 最後に、ツールの運用においてはPDCAサイクルを回すことが重要です。定期的にツールの使用状況や効果を振り返り、必要に応じて運用ルールを改善をしていきます。 このように、社内イントラをより効果的に活用するために、適切な手順に則って導入していきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 最も簡単に社内イントラを構築できるツール 以下では、最も簡単に社内イントラを構築できるツールをご紹介します。 社内イントラとは、社員同士の情報共有を円滑にし、社内のコミュニケーションを促進する社内情報通信網です。社内イントラツールに、社内に散在しがちな業務マニュアルや共有事項などのナレッジを一元管理すれば、必要な情報をすぐ見つけられます。 ただし、社員全員が思い通りに情報を検索できるように検索機能の優れたツールを導入しましょう。とくに、生成AIによって口語での検索に対応していると欲しい情報を誰もが見つけられます。 結論、社内イントラの構築に最適なツールは、社内の情報を一元管理し、AIを活用した超高精度検索で簡単に情報へアクセスできる「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、あらゆる形式のファイルを添付して任意のメンバーと共有できます。また、生成AIを活用した超高精度の「自然言語検索」が備わっているので、検索スキルに依存せず、誰もが目的の情報にたどり着けます。 必要な社内情報が即見つかるようになるツール「ナレカン」 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラネットの活用事例 KOKUYOは、日本を代表する文具やオフィス家具メーカーの企業です。 同社では新規事業を立ち上げるにあたって、他部門との連携が取りづらい階層構造の組織体系が課題でした。多くの新規事業を円滑に進めるためには、部門を横断して情報を共有しながら業務に取り組むことが重要です。 そこで、部門を超えたコミュニケーションを取るためにITツールを導入したところ、自然に業務ノウハウが共有されるようになりました。結果として、上から言われたことをやるだけではなく、社員が主体性を持ってプロジェクトを進められるようになったのです。 参考:「自律的に動く組織へ。Slack 活用で目指すコクヨ式ハイブリッドワーク」│KOKUYO 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内イントラを導入する目的や作成方法まとめ これまで、社内イントラの目的や作成方法を中心に解説してきました。 社内のノウハウやマニュアルなどのナレッジを適切に共有して活用するためには、社内に散在する情報を一元管理する社内イントラツールが必須です。また、社内イントラツールには、必要な情報を確実に見つけられる超高精度の機能が求められます。 そのため、「蓄積したナレッジを超高精度検索機能で簡単にアクセスできるITツール」を利用しましょう。とくに、生成AIによるチャット形式で検索できる検索機能があると便利です。 結論、社内イントラに利用すべきなのは、あらゆる情報を一元化し、生成AIを活用した「自然言語検索」が備わったツール「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、社内情報を共有・管理しやすい体制をつくりましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む -
 2025年10月03日【最新版】人気のクラウド型社内ポータルサイト7選を徹底比較!昨今、社内向けのWebサイトである「社内ポータルサイト」を介して情報共有をする企業が増えています。とくに、クラウド型は自社で開発したりサーバ等を管理したりする必要がないので、ITに関する知識がない企業でも手軽に使い始められる点が人気です。 しかし、「クラウド型の社内ポータルサイトを導入したいが、どのように選定したらよいか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、おすすめのクラウド型社内ポータルサイト7選と選定ポイントを中心に解説します。 自社に適した社内ポータルサイトを選定するポイントを知りたい 社内の総合ポータルサイトを作れるツールを比較検討したい 誰でも簡単に「社内お知らせ」ができるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、自社にマッチする社内ポータルサイトが見つかるだけでなく、運用のポイントまで押さえられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 クラウド型社内ポータルサイトの導入メリット2 社内ポータルサイトの選定ポイント4選2.1 (1)簡単に操作できるか2.2 (2)スムーズに導入できるか2.3 (3)セキュリティ対策が万全か2.4 (4)スマホからでも確認しやすいか3 人気あり!おすすめのクラウド型社内ポータルサイト7選3.1 【ナレカン】100人以上の大企業のナレッジ管理に特化したツール3.2 【Stock】100人以下の中小企業の情報管理・共有に最適のツール3.3 【Garoon】サイボウズが提供する大企業向けグループウェア3.4 【kintone】サイボウズが提供する多機能なクラウドサービス3.5 【Concrete CMS】オープンソースのポータルソフト3.6 【Notion】デザイン性の高い社内ポータルを作成できるツール3.7 【SharePoint】社内メンバーとの”情報共有”に使えるポータルサイト4 無料から試せる!クラウド型社内ポータルサイトの比較表5 社内ポータルサイトの基本的な使い方3選5.1 (1)社内掲示板にお知らせを掲載する5.2 (2)マニュアルや社内情報を検索する5.3 (3)コメントを残してコミュニケーションを取る6 社内ポータルサイトを導入すべき企業の特徴7 【解決策あり】ポータルサイトの運用が上手くいかない3つの原因7.1 (1)欲しい情報が見つからない7.2 (2)明確な運用ルールがない7.3 (3)設計が合っていない8 おすすめのクラウド型社内ポータルサイトまとめ クラウド型社内ポータルサイトの導入メリット クラウド型社内ポータルサイトの導入メリットは、おもに以下の2つです。 業務効率が上がる 社内ポータルサイトには、情報を整理できる「管理機能」や、欲しい情報がすぐに見つかる「検索機能」などが豊富に備わっています。そのため、社内ポータルで情報連携を改善することで、業務スピードの向上や業務品質の均一化が期待できるのです。 ナレッジ(知識・経験)が蓄積される 社内ポータルサイトは、あらゆるナレッジ(知識・経験)が蓄積される場所になります。社内ポータルを通して社内wikiや業務ノウハウを共有することで、ナレッジが蓄積され、属人化防止につながるのです。 開発・運用コストを抑えられる クラウド型のポータルサイトでは、サービスに不具合があった場合にベンダー(システム提供者)が対応します。そのため、ITに詳しい人材のいない「非IT企業」であっても、開発・運用コストを抑えてスムーズに導入できる点がメリットです。 以上のように、社内ポータルサイトはあらゆる情報を蓄積でき、属人化の防止や業務効率の向上につながります。有効活用するために、業務にどのような利益をもたらすのかを把握し、具体的なイメージを持っておきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルサイトの選定ポイント4選 以下では、社内ポータルサイトを選定するときに押さえるべきポイントを4つご紹介します。ポータルサイトの導入に失敗したくない方は必見です。 (1)簡単に操作できるか 1つ目のポイントは、「ITに詳しくないメンバーでも簡単に操作できるか」です。 社内ポータルサイトは全社員が利用するので、誰でも簡単に使いこなせるシンプルなツールが理想です。とくに、従業員数が多い企業では「年齢層」や「ITリテラシー」を考慮して選定しなければ、情報の更新や閲覧がされなくなってしまいます。 したがって、「便利そうだから」と多機能なツールを選ぶのではなく、必要な機能に過不足のないツールを選びましょう。 (2)スムーズに導入できるか 2つ目のポイントは、「スムーズに導入できるか」です。 社内ポータルサイトの導入には、様々な作業が伴います。具体的には、サイトの初期セットアップや運用ルールの制定、既存データの移行など、複雑で時間のかかる初期設定をしなければなりません。 また、運営元のサポート体制が手厚いかは、ツール運用の成功を左右するため、決裁者の承認を得るうえでも重要です。一方、サイト導入時に初期設定に関するサポートを受けられれば、担当者の負担を最小限に抑えつつ、スムーズな運用が開始できます。 (3)セキュリティ対策が万全か 3つ目のポイントは、「セキュリティ対策が万全であるか」です。 社内ポータルサイトは、自社が保有する様々な情報にアクセスすることができるサイトです。そのため、セキュリティ対策が不完全だと、不正アクセスによって社外秘の情報が漏えいしてしまう危険性もあります。 したがって、社内ポータルサイトを導入するときは、高セキュアなツールを選ぶようにしましょう。 (4)スマホからでも確認しやすいか 4つ目のポイントは、「スマホでも確認しやすいか」です。 職種によっては、オフィス外で社内ポータルサイトにアクセスする機会も少なくありません。たとえば、商談や営業で社外に出ている場合、スマホに対応していないツールでは社内ポータルサイトにアクセスするのに手間がかかってしまいます。 したがって、オフィス外でも快適に情報を参照できるよう、「ナレカン」のようにスマホでの利用にも最適化されたツールを選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 人気あり!おすすめのクラウド型社内ポータルサイト7選 以下では、おすすめのクラウド型社内ポータルサイトをご紹介します。 社内ポータルはあらゆる情報の入り口になるため、社内の重要なお知らせを常に掲示できなくてはなりません。また、社内で活用されるポータルサイトにするには、「知りたい情報に簡単にアクセスできること」を重視して構築しましょう。 そこで、「高精度の検索機能」を備えたサービスを選べば、情報を振り返りやすい体制が整います。とくに、どこに何の情報があるのかが分からなければ閲覧しないメンバーが出るため、「検索しやすい操作性やUI(画面デザイン)であるか」も重要なポイントです。 結論、社内ポータルサイトに最適なのは、社内のナレッジを簡単に一元管理でき、超高精度の検索機能で目的の情報に即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンでは「社内お知らせ」機能で全社へ簡単に情報を共有し、「ヒット率100%」の超高精度の検索機能で必要な情報をすぐに見つけられます。また、どのナレッジがどの程度活用されているかを把握できる機能もあり、効果的なナレッジ活用が実現可能です。 【ナレカン】100人以上の大企業のナレッジ管理に特化したツール 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンで社内ポータル(社内お知らせ)を作成する手順 ナレカンでは、下記のように、重要な情報をアナウンスできます。 また、管理画面から、社内お知らせの「レイアウト」や「公開/非公開」も簡単に調整できます。 そのため、わずかな工数で全社員向けにアナウンスできるので、担当者の負担を最小限に抑えられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Stock】100人以下の中小企業の情報管理・共有に最適のツール Stockは、非IT企業の65歳の方でも即日使いこなせるシンプルなツールです。 「Stock」の「ノート」にはあらゆる情報を残せるだけでなく、任意のメンバーにリアルタイムで共有できます。また、ノートには「メッセージ」や「タスク」を紐づけられるので、情報が分散する煩わしさを解消できるのです。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 <Stockをおすすめするポイント> ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 <Stockの口コミ・評判> 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ(栃木SC) 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 <Stockの料金> フリープラン :無料 ビジネスプラン :500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数:5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Garoon】サイボウズが提供する大企業向けグループウェア <Garoonの特徴> 社内ポータルを手軽に作成できる ドラッグ&ドロップやテンプレート機能で、誰でも手間をかけずに社内ポータルを作成できます。 大規模企業向け 同社が運営している「サイボウズOffice」と比較して、Garoonは、”企業規模が100名以上の企業向けツール”になっています。 <Garoonの機能・使用感> お知らせ機能が充実している 掲示板の”掲載期間設定”や”閲覧確認機能”を活用すれば、メールを使わずに全社へ周知できます。そのため、社員数が多い企業や掲示期間を設定して投稿したい場合に便利です。 kintoneと連携して使える Garoonのポータル上に、kintoneアプリで作成した案件管理や売上管理などのグラフを表示し、ダッシュボードのように利用できます。また、kintoneの通知や未処理アプリの一覧もGaroon上で表示できるため、必要な情報をすぐに確認するのに便利です。 <Garoonの注意点> スケジュールが外部サービスと連携できない Garoonには、スケジュール機能が備わっている一方、outlookやGoogleのカレンダーと連携できないため、予定が重複しない様に注意が必要です。 直感的に利用できない 利用しているユーザーからは「もう少し直感的な使い方が出来れば良い。若干昔のデザインや動作がある。特にデザインは今風に刷新してほしい。」との声があります。(引用:ITトレンド) <Garoonの料金> 以下は、クラウド版の価格です。 900円/ユーザー/月(1,000ユーザー以上の場合は、要問合せ) 以下は、パッケージ版の新規ライセンスの料金です。 ランクA:600,000円/50ユーザー ランクB:11,000円/1ユーザー(51~249ユーザー) ランクC:10,000円/1ユーザー(250~499ユーザー) ランクD:9,000円/1ユーザー(500~999ユーザー) ランクE:8,000円/1ユーザー(1,000~2,499ユーザー) ランクF:7,500円/1ユーザー(2,500~4,999ユーザー) ランクG:要問合わせ(5,000~9,999ユーザー) ランクH:要問合わせ(10,000ユーザー~) Garoonの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【kintone】サイボウズが提供する多機能なクラウドサービス <kintoneの特徴> 独自の業務アプリを作成できる プログラミングの知識を問わず、ノーコードで業務アプリを作ることが可能です。自社の業務内容や課題に合わせたアプリを作れるため、業務の効率化を図れます。 多言語に対応 表示言語は、日本語・英語・中国語・スペイン語・韓国語など、さまざまな言語に切り替えることができ、グローバル企業にも適しています。 <kintoneの機能・使用感> データをグラフ化できる 記入したデータをグラフ化する「レポート機能」が備わっています。リアルタイムでデータがグラフに反映されるため、更新の手間がかかりません。 全文検索ができる タイトルや条件、キーワードを絞り込んで全文検索が可能です。さらに、文字情報以外にも添付ファイルの中身まで検索対象となるため、必要な情報まで迅速にたどり着けます。 <kintoneの注意点> 一定以上のITリテラシーが必要 アプリを自由にカスタマイズできる一方、高いITリテラシーがないと上手く活用できない可能性があります。 バックアップが取りにくい ユーザーからは「もし間違えてデータを消してしまっても元に戻せない。データはcsvに出力することは可能だが、戻す場合、項目によってはそのまま戻せないものもあり、非常に手間がかかる。」といった声が寄せられています。(参考:ITreview) 直感的に使えない 「複雑なカスタマイズを行う際にもう少し直感的なUIが欲しいと感じました。特に、フォームの設計やフィールドの配置において、ドラッグ&ドロップ操作の精度や柔軟性が向上するとより使いやすくなります。」という声が寄せられています。(参考:ITトレンド) <kintoneの料金体系> ライトコース:1,000円/ユーザー/月 スタンダードコース:1,800円/ユーザー/月 ワイドコース:3,000円/ユーザー/月 kintoneの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Concrete CMS】オープンソースのポータルソフト <Concrete CMSの特徴> 誰でも無料で使える Concrete CMSは、誰でも簡単にHPの運用ができるCMS(コンテンツ・マネージメント・システム)です。オープンソースなので誰でも無料で使えます。 ページの編集がしやすい 編集したい部分をクリックするだけで編集できるので、ページを行き来する手間がかかりません。 <Concrete CMSの機能・使用感> 使い方が詳しく記載されている バージョンごとの勉強会の解説録画がアップロードされているため、難しい操作でも理解しやすいです。 セキュリティ対策が高い IPアドレスブロック機能の搭載や暗号化して復号できない形式のパスワード設定など、万全のセキュリティ対策によって大企業でも安心して利用できます。 <Concrete CMSの注意点> 運用に関する情報が少ない Concrete CMSは国内利用者が少ないため、ほかのツールに比べて情報が少なく、コミュニティーで情報を調べる必要があります。 インストールするのに手間がかかる Concrete CMSは、ホスティング環境もしくはローカル環境にインストール可能です。ただし、設定に手間がかかる点に注意しましょう。 動作が重くなることがある 利用しているユーザーからは「ドラッグ&ドロップで直感的に編集ができるというメリットが有る一方で、この機能を優先したため、読み込み速度が遅くなるケースが多々あります」との意見が挙がっています。(参考:ITreview) <Concrete CMSの料金> オープンソースのサービスなので、完全無料で利用できます。 Concrete CMSの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Notion】デザイン性の高い社内ポータルを作成できるツール Notionの特徴 かっこいいサイトを作れる Notionは画像やページの編集の自由度が高い点が特徴です。そのため、かっこいい社内ポータルサイトを作りたい場合に役立ちます。 ポータル以外の機能も充実している 社内ポータルを作るだけでなく、タスクやプロジェクト管理・データベース作成にも活用可能です。したがって、ひとつのツールであらゆる用途に活用したいという方に適しています。 Notionの機能・使用感 テンプレート機能が充実している Notionには豊富なテンプレートが用意されています。そのため、社内ポータルのトップページを作ったり、お知らせや社内wikiなどの体裁を整えたりするのに便利です。 動作が重くなる場合がある オリジナリティのあるページを自由に作成できる一方で、複雑な構造を作ると動作が重くなり、開くまでに時間がかかる点に注意が必要です。読み込みが遅いときは、履歴を削除すると解消できる場合があります。 Notionの注意点 直感的に使いこなせない Notionは構造化したサイトを作れるように、さまざまな編集機能が備わっています。一方で、「各機能がどのように使えるのかが分かりにくい」ため、ITに不慣れな場合は直感的に使いこなせない可能性があります。 検索機能が使いづらい ユーザーからは「まだページが増えてくると検索に時間がかかることがあり、タグやリンクの運用ルールをチームで統一する必要があります。AI機能による自動要約や検索補助がもう少し強化されると、大量情報でも迷わずアクセスできると思います。」という声があります。(参考:ITreview) Notionの料金体系 フリー:無料 プラス:2,000円/ユーザー/月 ビジネス:3,800円/ユーザー/月 エンタープライズ:要問合わせ Notionの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【SharePoint】社内メンバーとの”情報共有”に使えるポータルサイト SharePointの特徴 社内ポータルを自由に構築できる SharePointは、目的に応じて社内ポータルを自由に構築できます。たとえば、チームで完結するファイル共有には「チームサイト」、全社向けには掲示板のように使える「コミュニケーションサイト」と、利用用途に合わせて展開可能です。 Microsoft製品と連携できる SharePoint上でWordやExcelのファイルを編集したり、Outlookのスケジュールと連携させたりできるので、Microsoft社の製品を多用している会社に向いています。 SharePointの機能・使用感 サイトを簡単に作成できる SharePointはMicrosoft社の製品であるため、AIデジタルアシスタントである「Copilot」を連携して利用できます。Copilotを使えば、数個のプロンプトとクリック操作だけで目的のサイトを作成可能なため、手間がかからず便利です。 必要なファイルがすぐに見つかる 全文検索機能がついているので、ファイルの中身を開くことなく検索をかけることができます。そのため、スピーディーに情報へアクセスするのに役立ちます。 SharePointの注意点 教育コストがかかる SharePointでは、管理者が作成したサイト上にページを用意し、コンテンツを配置することで情報共有をします。つまり、情報共有のために自社独自の使い方を「全メンバーに教育する必要がある」のです。 自由度が低い 利用しているユーザーからは「ある程度フォーマット化されている分、自由度が高くないことが多い。」という声があります。(参考:ITreview) SharePointの料金体系 SharePoint (プラン 1):749円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Basic:899円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月 また、Microsoft 365 Copilot(4,497円/ユーザー/月)を追加すれば、 SharePointサイトやライブラリ、フォルダー内の情報を駆使して、簡単にエージェントを作成できるようになります。さまざまなエージェントを作ることで、生産性の向上が図れます。 SharePointの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 無料から試せる!クラウド型社内ポータルサイトの比較表 以下は、クラウド型社内ポータルサイトの比較表です。(左右にスクロールできます。)なかには、無料から利用できるものもあるので、担当者の方は必見です。 ナレカン【一番おすすめ】 Stock【おすすめ】 Garoon kintone Concrete CMS Notion SharePoint 特徴 100人以上の大企業のナレッジ管理に特化したツール 100人以下の中小企業の情報管理・共有に最適のツール サイボウズが提供する大企業向けグループウェア サイボウズが提供する多機能なクラウドサービス オープンソースのポータルソフト デザイン性の高い社内ポータルを作成できるツール 社内メンバーとの”情報共有”に使えるポータルサイト シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単(大手~中堅企業向け) シンプルで簡単(中小規模の企業向け) 多機能 多機能 多機能 多機能 多機能 既読機能 【〇】 【×】 【〇】 【〇】 【×】 【×】 【〇】 コメント機能 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】 【×】 【〇】 【〇】 注意点 法人利用が前提なので、個人利用は不可 5名以上での利用が前提 スケジュールが外部サービスと連携できない 一定以上のITリテラシーが必要 運用に関する情報が少ない 直感的に使いこなせない 教育コストがかかる 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料プランあり ・有料プランでも1人あたり500円/月〜 ・無料プランなし ・有料プラン(クラウド版)は900円/ユーザー/月~ ・無料プランなし ・有料プランは1,000円/ユーザー/月~ 完全無料で利用できます ・無料プランあり ・有料プランは2,000円/ユーザー/月~ ・無料プランなし ・有料プランは749円/ユーザー/月~ 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「Garoon」の詳細はこちら 「kintone」の詳細はこちら 「Concrete CMS」の詳細はこちら 「Notion」の詳細はこちら 「SharePoint」の詳細はこちら 以上のように、ツールによって機能性や価格帯が大きく異なる点に注意しましょう。また、社内ポータルサイトは全社で使われるものなので、「何名規模で使うか」を想定して導入を検討するのがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルサイトの基本的な使い方3選 以下では、社内ポータルサイトの使い方を3つ解説します。サイト導入後のイメージができていない方は、以下を参考にしましょう。 (1)社内掲示板にお知らせを掲載する 1つ目は、「社内掲示板へのお知らせ掲載」です。 社内ポータルサイトの「社内掲示板機能」を活用すると、共有したい情報を「お知らせ」として迅速に社員へ共有可能です。一般的には「企業情報」や「社内イベント」「社内FAQ」などが対象になります。 社内掲示板を通じて情報をリアルタイムで共有することで、情報共有のスピードが向上し、認識の齟齬も防げます。さらに、「お知らせ」として掲載した情報はサイト内に蓄積されて重要な社内資産となるため、「ナレッジ」として活用できるのです。 (2)マニュアルや社内情報を検索する 2つ目は、「マニュアルや社内情報の検索」です。 社内ポータルサイトには膨大な量の社内情報が保管されています。それらの情報を活用するためには、検索機能を使って目当ての情報を素早く抽出する必要があるのです。 しかし、精度の低い検索機能では、一度の検索で情報を絞りきることができない可能性があります。したがって、”複数キーワード検索”や”ファイル内検索”など、超高精度な検索機能が備わった「ナレカン」のようなサービスを選択しましょう。 (3)コメントを残してコミュニケーションを取る 3つ目は、「コメントを通じたコミュニケーション」です。 「コメント機能」があるポータルサイトでは、メールのように形式に縛られたやりとりではなく、対面に近い感覚でスピーディーに会話を進めることが可能です。一方で、他の話題と混ざって重要な情報が埋もれたり、確認漏れが生じたりするケースも少なくありません。 そこで、「共有したい情報」と「コメント機能」が紐づいたサービスを使えば、話題が入り乱れずにスムーズなコミュニケーションが実現します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルサイトを導入すべき企業の特徴 社内ポータルサイトを導入すべき企業の特徴は、以下の通りです。 社員数が多い企業 社員数が多いと、一人一人の質問や問合せへの対応に多くの時間と手間がかかってしまいます。そのため、社内ポータルサイトで社員が自ら調べ、疑問を解決できる体制を整える必要があるのです。 ナレッジやスキルが属人化している企業 業務に関するナレッジやスキルが属人化していると、「○○さんがいないからこの業務が進められない」という状況になりかねません。そのため、個人が有するナレッジやスキルをマニュアル化し、誰でも閲覧できる体制を整える必要があります。 上記の点を踏まえて、社内の情報共有に困っている場合は社内ポータルサイトの導入を検討しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【解決策あり】ポータルサイトの運用が上手くいかない3つの原因 社内ポータルの運用が上手くいかない原因として、以下が挙げられます。事前に原因と解決策を押さえて、迅速に対応できるようにしましょう。 (1)欲しい情報が見つからない 1つ目の原因として、「目的の情報がすぐに見つからない」ことが挙げられます。 社内ポータルサイトに蓄積した情報は、活用されなければ意味がありません。しかし、検索機能が乏しかったり、情報の整理ができていなかったりすると「どこに、何の情報があるのか分からない」という問題に直面するのです。 したがって、誰でも簡単に欲しい情報にアクセスできる体制に改善していきましょう。具体的には、高精度の検索機能やフォルダ機能が備わっているツールの導入が効果的です。 (2)明確な運用ルールがない 2つ目の原因として、「明確な運用ルールがない」ことが挙げられます。 運用ルールが明確でないと、メンバーによって情報の共有方法が異なったり、情報が散乱したりする事態につながります。したがって、ポータルサイトの作成や管理に関するルールを策定して、情報を見やすく管理しましょう。 また、運用ルールだけでなく、テンプレートを活用する方法も効果的です。社内ポータルで文書を共有する場合、テンプレートを使えば項目に従って情報を入力するだけで文書を作れるうえ、体裁も統一できます。 (3)設計が合っていない 3つ目の原因として、「自社に合った設計になっていない」ことが挙げられます。 たとえば、一から社内ポータルを構築した場合「情報がどこにあるのか分かりづらい」「情報にたどり着くのに工数がかかる」といったトラブルが起こりがちです。以上のように、情報へのアクセス性が悪ければ、サイトを構築しても使われなくなってしまいます。 したがって、自力で社内ポータルを構築するのに不安がある場合は、「自社に合わせたフォルダ・ルール設計」を支援する「ナレカン」のような、手厚いサポート体制が整ったサービスがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ おすすめのクラウド型社内ポータルサイトまとめ ここまで、おすすめのクラウド型社内ポータルサイトや選定ポイント、上手く運用できない原因をご紹介しました。 クラウド型社内ポータルサイトで社内情報を一元化すれば、格納場所が分散していた資料やデータを体系的にまとめられ、仕事で活用しやすくなります。また、全社共通で周知したい情報もスムーズに共有できるので、業務効率の向上が期待できるのです。 なかでも「検索性の高いサービス」であれば、共有した情報をあとから簡単に振り返ることができます。一方、多機能で複雑な操作性の社内ポータルを導入すると、社員が使いこなせないため「誰でも簡単に使える操作性やデザインのサービス」を選びましょう。 結論、社内ポータルサイトの構築には、シンプルな操作性で簡単に情報共有ができ、高精度の検索機能で欲しい情報がすぐに見つかるツール「ナレカン」が最適です 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、ナレッジ管理・共有のストレスを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む
2025年10月03日【最新版】人気のクラウド型社内ポータルサイト7選を徹底比較!昨今、社内向けのWebサイトである「社内ポータルサイト」を介して情報共有をする企業が増えています。とくに、クラウド型は自社で開発したりサーバ等を管理したりする必要がないので、ITに関する知識がない企業でも手軽に使い始められる点が人気です。 しかし、「クラウド型の社内ポータルサイトを導入したいが、どのように選定したらよいか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、おすすめのクラウド型社内ポータルサイト7選と選定ポイントを中心に解説します。 自社に適した社内ポータルサイトを選定するポイントを知りたい 社内の総合ポータルサイトを作れるツールを比較検討したい 誰でも簡単に「社内お知らせ」ができるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、自社にマッチする社内ポータルサイトが見つかるだけでなく、運用のポイントまで押さえられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 目次1 クラウド型社内ポータルサイトの導入メリット2 社内ポータルサイトの選定ポイント4選2.1 (1)簡単に操作できるか2.2 (2)スムーズに導入できるか2.3 (3)セキュリティ対策が万全か2.4 (4)スマホからでも確認しやすいか3 人気あり!おすすめのクラウド型社内ポータルサイト7選3.1 【ナレカン】100人以上の大企業のナレッジ管理に特化したツール3.2 【Stock】100人以下の中小企業の情報管理・共有に最適のツール3.3 【Garoon】サイボウズが提供する大企業向けグループウェア3.4 【kintone】サイボウズが提供する多機能なクラウドサービス3.5 【Concrete CMS】オープンソースのポータルソフト3.6 【Notion】デザイン性の高い社内ポータルを作成できるツール3.7 【SharePoint】社内メンバーとの”情報共有”に使えるポータルサイト4 無料から試せる!クラウド型社内ポータルサイトの比較表5 社内ポータルサイトの基本的な使い方3選5.1 (1)社内掲示板にお知らせを掲載する5.2 (2)マニュアルや社内情報を検索する5.3 (3)コメントを残してコミュニケーションを取る6 社内ポータルサイトを導入すべき企業の特徴7 【解決策あり】ポータルサイトの運用が上手くいかない3つの原因7.1 (1)欲しい情報が見つからない7.2 (2)明確な運用ルールがない7.3 (3)設計が合っていない8 おすすめのクラウド型社内ポータルサイトまとめ クラウド型社内ポータルサイトの導入メリット クラウド型社内ポータルサイトの導入メリットは、おもに以下の2つです。 業務効率が上がる 社内ポータルサイトには、情報を整理できる「管理機能」や、欲しい情報がすぐに見つかる「検索機能」などが豊富に備わっています。そのため、社内ポータルで情報連携を改善することで、業務スピードの向上や業務品質の均一化が期待できるのです。 ナレッジ(知識・経験)が蓄積される 社内ポータルサイトは、あらゆるナレッジ(知識・経験)が蓄積される場所になります。社内ポータルを通して社内wikiや業務ノウハウを共有することで、ナレッジが蓄積され、属人化防止につながるのです。 開発・運用コストを抑えられる クラウド型のポータルサイトでは、サービスに不具合があった場合にベンダー(システム提供者)が対応します。そのため、ITに詳しい人材のいない「非IT企業」であっても、開発・運用コストを抑えてスムーズに導入できる点がメリットです。 以上のように、社内ポータルサイトはあらゆる情報を蓄積でき、属人化の防止や業務効率の向上につながります。有効活用するために、業務にどのような利益をもたらすのかを把握し、具体的なイメージを持っておきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルサイトの選定ポイント4選 以下では、社内ポータルサイトを選定するときに押さえるべきポイントを4つご紹介します。ポータルサイトの導入に失敗したくない方は必見です。 (1)簡単に操作できるか 1つ目のポイントは、「ITに詳しくないメンバーでも簡単に操作できるか」です。 社内ポータルサイトは全社員が利用するので、誰でも簡単に使いこなせるシンプルなツールが理想です。とくに、従業員数が多い企業では「年齢層」や「ITリテラシー」を考慮して選定しなければ、情報の更新や閲覧がされなくなってしまいます。 したがって、「便利そうだから」と多機能なツールを選ぶのではなく、必要な機能に過不足のないツールを選びましょう。 (2)スムーズに導入できるか 2つ目のポイントは、「スムーズに導入できるか」です。 社内ポータルサイトの導入には、様々な作業が伴います。具体的には、サイトの初期セットアップや運用ルールの制定、既存データの移行など、複雑で時間のかかる初期設定をしなければなりません。 また、運営元のサポート体制が手厚いかは、ツール運用の成功を左右するため、決裁者の承認を得るうえでも重要です。一方、サイト導入時に初期設定に関するサポートを受けられれば、担当者の負担を最小限に抑えつつ、スムーズな運用が開始できます。 (3)セキュリティ対策が万全か 3つ目のポイントは、「セキュリティ対策が万全であるか」です。 社内ポータルサイトは、自社が保有する様々な情報にアクセスすることができるサイトです。そのため、セキュリティ対策が不完全だと、不正アクセスによって社外秘の情報が漏えいしてしまう危険性もあります。 したがって、社内ポータルサイトを導入するときは、高セキュアなツールを選ぶようにしましょう。 (4)スマホからでも確認しやすいか 4つ目のポイントは、「スマホでも確認しやすいか」です。 職種によっては、オフィス外で社内ポータルサイトにアクセスする機会も少なくありません。たとえば、商談や営業で社外に出ている場合、スマホに対応していないツールでは社内ポータルサイトにアクセスするのに手間がかかってしまいます。 したがって、オフィス外でも快適に情報を参照できるよう、「ナレカン」のようにスマホでの利用にも最適化されたツールを選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 人気あり!おすすめのクラウド型社内ポータルサイト7選 以下では、おすすめのクラウド型社内ポータルサイトをご紹介します。 社内ポータルはあらゆる情報の入り口になるため、社内の重要なお知らせを常に掲示できなくてはなりません。また、社内で活用されるポータルサイトにするには、「知りたい情報に簡単にアクセスできること」を重視して構築しましょう。 そこで、「高精度の検索機能」を備えたサービスを選べば、情報を振り返りやすい体制が整います。とくに、どこに何の情報があるのかが分からなければ閲覧しないメンバーが出るため、「検索しやすい操作性やUI(画面デザイン)であるか」も重要なポイントです。 結論、社内ポータルサイトに最適なのは、社内のナレッジを簡単に一元管理でき、超高精度の検索機能で目的の情報に即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンでは「社内お知らせ」機能で全社へ簡単に情報を共有し、「ヒット率100%」の超高精度の検索機能で必要な情報をすぐに見つけられます。また、どのナレッジがどの程度活用されているかを把握できる機能もあり、効果的なナレッジ活用が実現可能です。 【ナレカン】100人以上の大企業のナレッジ管理に特化したツール 「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 <ナレカンをおすすめするポイント> 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 <ナレカンの料金> ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンで社内ポータル(社内お知らせ)を作成する手順 ナレカンでは、下記のように、重要な情報をアナウンスできます。 また、管理画面から、社内お知らせの「レイアウト」や「公開/非公開」も簡単に調整できます。 そのため、わずかな工数で全社員向けにアナウンスできるので、担当者の負担を最小限に抑えられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Stock】100人以下の中小企業の情報管理・共有に最適のツール Stockは、非IT企業の65歳の方でも即日使いこなせるシンプルなツールです。 「Stock」の「ノート」にはあらゆる情報を残せるだけでなく、任意のメンバーにリアルタイムで共有できます。また、ノートには「メッセージ」や「タスク」を紐づけられるので、情報が分散する煩わしさを解消できるのです。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 <Stockをおすすめするポイント> ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 <Stockの口コミ・評判> 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ(栃木SC) 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 <Stockの料金> フリープラン :無料 ビジネスプラン :500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数:5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Garoon】サイボウズが提供する大企業向けグループウェア <Garoonの特徴> 社内ポータルを手軽に作成できる ドラッグ&ドロップやテンプレート機能で、誰でも手間をかけずに社内ポータルを作成できます。 大規模企業向け 同社が運営している「サイボウズOffice」と比較して、Garoonは、”企業規模が100名以上の企業向けツール”になっています。 <Garoonの機能・使用感> お知らせ機能が充実している 掲示板の”掲載期間設定”や”閲覧確認機能”を活用すれば、メールを使わずに全社へ周知できます。そのため、社員数が多い企業や掲示期間を設定して投稿したい場合に便利です。 kintoneと連携して使える Garoonのポータル上に、kintoneアプリで作成した案件管理や売上管理などのグラフを表示し、ダッシュボードのように利用できます。また、kintoneの通知や未処理アプリの一覧もGaroon上で表示できるため、必要な情報をすぐに確認するのに便利です。 <Garoonの注意点> スケジュールが外部サービスと連携できない Garoonには、スケジュール機能が備わっている一方、outlookやGoogleのカレンダーと連携できないため、予定が重複しない様に注意が必要です。 直感的に利用できない 利用しているユーザーからは「もう少し直感的な使い方が出来れば良い。若干昔のデザインや動作がある。特にデザインは今風に刷新してほしい。」との声があります。(引用:ITトレンド) <Garoonの料金> 以下は、クラウド版の価格です。 900円/ユーザー/月(1,000ユーザー以上の場合は、要問合せ) 以下は、パッケージ版の新規ライセンスの料金です。 ランクA:600,000円/50ユーザー ランクB:11,000円/1ユーザー(51~249ユーザー) ランクC:10,000円/1ユーザー(250~499ユーザー) ランクD:9,000円/1ユーザー(500~999ユーザー) ランクE:8,000円/1ユーザー(1,000~2,499ユーザー) ランクF:7,500円/1ユーザー(2,500~4,999ユーザー) ランクG:要問合わせ(5,000~9,999ユーザー) ランクH:要問合わせ(10,000ユーザー~) Garoonの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【kintone】サイボウズが提供する多機能なクラウドサービス <kintoneの特徴> 独自の業務アプリを作成できる プログラミングの知識を問わず、ノーコードで業務アプリを作ることが可能です。自社の業務内容や課題に合わせたアプリを作れるため、業務の効率化を図れます。 多言語に対応 表示言語は、日本語・英語・中国語・スペイン語・韓国語など、さまざまな言語に切り替えることができ、グローバル企業にも適しています。 <kintoneの機能・使用感> データをグラフ化できる 記入したデータをグラフ化する「レポート機能」が備わっています。リアルタイムでデータがグラフに反映されるため、更新の手間がかかりません。 全文検索ができる タイトルや条件、キーワードを絞り込んで全文検索が可能です。さらに、文字情報以外にも添付ファイルの中身まで検索対象となるため、必要な情報まで迅速にたどり着けます。 <kintoneの注意点> 一定以上のITリテラシーが必要 アプリを自由にカスタマイズできる一方、高いITリテラシーがないと上手く活用できない可能性があります。 バックアップが取りにくい ユーザーからは「もし間違えてデータを消してしまっても元に戻せない。データはcsvに出力することは可能だが、戻す場合、項目によってはそのまま戻せないものもあり、非常に手間がかかる。」といった声が寄せられています。(参考:ITreview) 直感的に使えない 「複雑なカスタマイズを行う際にもう少し直感的なUIが欲しいと感じました。特に、フォームの設計やフィールドの配置において、ドラッグ&ドロップ操作の精度や柔軟性が向上するとより使いやすくなります。」という声が寄せられています。(参考:ITトレンド) <kintoneの料金体系> ライトコース:1,000円/ユーザー/月 スタンダードコース:1,800円/ユーザー/月 ワイドコース:3,000円/ユーザー/月 kintoneの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Concrete CMS】オープンソースのポータルソフト <Concrete CMSの特徴> 誰でも無料で使える Concrete CMSは、誰でも簡単にHPの運用ができるCMS(コンテンツ・マネージメント・システム)です。オープンソースなので誰でも無料で使えます。 ページの編集がしやすい 編集したい部分をクリックするだけで編集できるので、ページを行き来する手間がかかりません。 <Concrete CMSの機能・使用感> 使い方が詳しく記載されている バージョンごとの勉強会の解説録画がアップロードされているため、難しい操作でも理解しやすいです。 セキュリティ対策が高い IPアドレスブロック機能の搭載や暗号化して復号できない形式のパスワード設定など、万全のセキュリティ対策によって大企業でも安心して利用できます。 <Concrete CMSの注意点> 運用に関する情報が少ない Concrete CMSは国内利用者が少ないため、ほかのツールに比べて情報が少なく、コミュニティーで情報を調べる必要があります。 インストールするのに手間がかかる Concrete CMSは、ホスティング環境もしくはローカル環境にインストール可能です。ただし、設定に手間がかかる点に注意しましょう。 動作が重くなることがある 利用しているユーザーからは「ドラッグ&ドロップで直感的に編集ができるというメリットが有る一方で、この機能を優先したため、読み込み速度が遅くなるケースが多々あります」との意見が挙がっています。(参考:ITreview) <Concrete CMSの料金> オープンソースのサービスなので、完全無料で利用できます。 Concrete CMSの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【Notion】デザイン性の高い社内ポータルを作成できるツール Notionの特徴 かっこいいサイトを作れる Notionは画像やページの編集の自由度が高い点が特徴です。そのため、かっこいい社内ポータルサイトを作りたい場合に役立ちます。 ポータル以外の機能も充実している 社内ポータルを作るだけでなく、タスクやプロジェクト管理・データベース作成にも活用可能です。したがって、ひとつのツールであらゆる用途に活用したいという方に適しています。 Notionの機能・使用感 テンプレート機能が充実している Notionには豊富なテンプレートが用意されています。そのため、社内ポータルのトップページを作ったり、お知らせや社内wikiなどの体裁を整えたりするのに便利です。 動作が重くなる場合がある オリジナリティのあるページを自由に作成できる一方で、複雑な構造を作ると動作が重くなり、開くまでに時間がかかる点に注意が必要です。読み込みが遅いときは、履歴を削除すると解消できる場合があります。 Notionの注意点 直感的に使いこなせない Notionは構造化したサイトを作れるように、さまざまな編集機能が備わっています。一方で、「各機能がどのように使えるのかが分かりにくい」ため、ITに不慣れな場合は直感的に使いこなせない可能性があります。 検索機能が使いづらい ユーザーからは「まだページが増えてくると検索に時間がかかることがあり、タグやリンクの運用ルールをチームで統一する必要があります。AI機能による自動要約や検索補助がもう少し強化されると、大量情報でも迷わずアクセスできると思います。」という声があります。(参考:ITreview) Notionの料金体系 フリー:無料 プラス:2,000円/ユーザー/月 ビジネス:3,800円/ユーザー/月 エンタープライズ:要問合わせ Notionの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【SharePoint】社内メンバーとの”情報共有”に使えるポータルサイト SharePointの特徴 社内ポータルを自由に構築できる SharePointは、目的に応じて社内ポータルを自由に構築できます。たとえば、チームで完結するファイル共有には「チームサイト」、全社向けには掲示板のように使える「コミュニケーションサイト」と、利用用途に合わせて展開可能です。 Microsoft製品と連携できる SharePoint上でWordやExcelのファイルを編集したり、Outlookのスケジュールと連携させたりできるので、Microsoft社の製品を多用している会社に向いています。 SharePointの機能・使用感 サイトを簡単に作成できる SharePointはMicrosoft社の製品であるため、AIデジタルアシスタントである「Copilot」を連携して利用できます。Copilotを使えば、数個のプロンプトとクリック操作だけで目的のサイトを作成可能なため、手間がかからず便利です。 必要なファイルがすぐに見つかる 全文検索機能がついているので、ファイルの中身を開くことなく検索をかけることができます。そのため、スピーディーに情報へアクセスするのに役立ちます。 SharePointの注意点 教育コストがかかる SharePointでは、管理者が作成したサイト上にページを用意し、コンテンツを配置することで情報共有をします。つまり、情報共有のために自社独自の使い方を「全メンバーに教育する必要がある」のです。 自由度が低い 利用しているユーザーからは「ある程度フォーマット化されている分、自由度が高くないことが多い。」という声があります。(参考:ITreview) SharePointの料金体系 SharePoint (プラン 1):749円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Basic:899円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月 また、Microsoft 365 Copilot(4,497円/ユーザー/月)を追加すれば、 SharePointサイトやライブラリ、フォルダー内の情報を駆使して、簡単にエージェントを作成できるようになります。さまざまなエージェントを作ることで、生産性の向上が図れます。 SharePointの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 無料から試せる!クラウド型社内ポータルサイトの比較表 以下は、クラウド型社内ポータルサイトの比較表です。(左右にスクロールできます。)なかには、無料から利用できるものもあるので、担当者の方は必見です。 ナレカン【一番おすすめ】 Stock【おすすめ】 Garoon kintone Concrete CMS Notion SharePoint 特徴 100人以上の大企業のナレッジ管理に特化したツール 100人以下の中小企業の情報管理・共有に最適のツール サイボウズが提供する大企業向けグループウェア サイボウズが提供する多機能なクラウドサービス オープンソースのポータルソフト デザイン性の高い社内ポータルを作成できるツール 社内メンバーとの”情報共有”に使えるポータルサイト シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単(大手~中堅企業向け) シンプルで簡単(中小規模の企業向け) 多機能 多機能 多機能 多機能 多機能 既読機能 【〇】 【×】 【〇】 【〇】 【×】 【×】 【〇】 コメント機能 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】 【×】 【〇】 【〇】 注意点 法人利用が前提なので、個人利用は不可 5名以上での利用が前提 スケジュールが外部サービスと連携できない 一定以上のITリテラシーが必要 運用に関する情報が少ない 直感的に使いこなせない 教育コストがかかる 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料プランあり ・有料プランでも1人あたり500円/月〜 ・無料プランなし ・有料プラン(クラウド版)は900円/ユーザー/月~ ・無料プランなし ・有料プランは1,000円/ユーザー/月~ 完全無料で利用できます ・無料プランあり ・有料プランは2,000円/ユーザー/月~ ・無料プランなし ・有料プランは749円/ユーザー/月~ 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「Garoon」の詳細はこちら 「kintone」の詳細はこちら 「Concrete CMS」の詳細はこちら 「Notion」の詳細はこちら 「SharePoint」の詳細はこちら 以上のように、ツールによって機能性や価格帯が大きく異なる点に注意しましょう。また、社内ポータルサイトは全社で使われるものなので、「何名規模で使うか」を想定して導入を検討するのがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルサイトの基本的な使い方3選 以下では、社内ポータルサイトの使い方を3つ解説します。サイト導入後のイメージができていない方は、以下を参考にしましょう。 (1)社内掲示板にお知らせを掲載する 1つ目は、「社内掲示板へのお知らせ掲載」です。 社内ポータルサイトの「社内掲示板機能」を活用すると、共有したい情報を「お知らせ」として迅速に社員へ共有可能です。一般的には「企業情報」や「社内イベント」「社内FAQ」などが対象になります。 社内掲示板を通じて情報をリアルタイムで共有することで、情報共有のスピードが向上し、認識の齟齬も防げます。さらに、「お知らせ」として掲載した情報はサイト内に蓄積されて重要な社内資産となるため、「ナレッジ」として活用できるのです。 (2)マニュアルや社内情報を検索する 2つ目は、「マニュアルや社内情報の検索」です。 社内ポータルサイトには膨大な量の社内情報が保管されています。それらの情報を活用するためには、検索機能を使って目当ての情報を素早く抽出する必要があるのです。 しかし、精度の低い検索機能では、一度の検索で情報を絞りきることができない可能性があります。したがって、”複数キーワード検索”や”ファイル内検索”など、超高精度な検索機能が備わった「ナレカン」のようなサービスを選択しましょう。 (3)コメントを残してコミュニケーションを取る 3つ目は、「コメントを通じたコミュニケーション」です。 「コメント機能」があるポータルサイトでは、メールのように形式に縛られたやりとりではなく、対面に近い感覚でスピーディーに会話を進めることが可能です。一方で、他の話題と混ざって重要な情報が埋もれたり、確認漏れが生じたりするケースも少なくありません。 そこで、「共有したい情報」と「コメント機能」が紐づいたサービスを使えば、話題が入り乱れずにスムーズなコミュニケーションが実現します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 社内ポータルサイトを導入すべき企業の特徴 社内ポータルサイトを導入すべき企業の特徴は、以下の通りです。 社員数が多い企業 社員数が多いと、一人一人の質問や問合せへの対応に多くの時間と手間がかかってしまいます。そのため、社内ポータルサイトで社員が自ら調べ、疑問を解決できる体制を整える必要があるのです。 ナレッジやスキルが属人化している企業 業務に関するナレッジやスキルが属人化していると、「○○さんがいないからこの業務が進められない」という状況になりかねません。そのため、個人が有するナレッジやスキルをマニュアル化し、誰でも閲覧できる体制を整える必要があります。 上記の点を踏まえて、社内の情報共有に困っている場合は社内ポータルサイトの導入を検討しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ 【解決策あり】ポータルサイトの運用が上手くいかない3つの原因 社内ポータルの運用が上手くいかない原因として、以下が挙げられます。事前に原因と解決策を押さえて、迅速に対応できるようにしましょう。 (1)欲しい情報が見つからない 1つ目の原因として、「目的の情報がすぐに見つからない」ことが挙げられます。 社内ポータルサイトに蓄積した情報は、活用されなければ意味がありません。しかし、検索機能が乏しかったり、情報の整理ができていなかったりすると「どこに、何の情報があるのか分からない」という問題に直面するのです。 したがって、誰でも簡単に欲しい情報にアクセスできる体制に改善していきましょう。具体的には、高精度の検索機能やフォルダ機能が備わっているツールの導入が効果的です。 (2)明確な運用ルールがない 2つ目の原因として、「明確な運用ルールがない」ことが挙げられます。 運用ルールが明確でないと、メンバーによって情報の共有方法が異なったり、情報が散乱したりする事態につながります。したがって、ポータルサイトの作成や管理に関するルールを策定して、情報を見やすく管理しましょう。 また、運用ルールだけでなく、テンプレートを活用する方法も効果的です。社内ポータルで文書を共有する場合、テンプレートを使えば項目に従って情報を入力するだけで文書を作れるうえ、体裁も統一できます。 (3)設計が合っていない 3つ目の原因として、「自社に合った設計になっていない」ことが挙げられます。 たとえば、一から社内ポータルを構築した場合「情報がどこにあるのか分かりづらい」「情報にたどり着くのに工数がかかる」といったトラブルが起こりがちです。以上のように、情報へのアクセス性が悪ければ、サイトを構築しても使われなくなってしまいます。 したがって、自力で社内ポータルを構築するのに不安がある場合は、「自社に合わせたフォルダ・ルール設計」を支援する「ナレカン」のような、手厚いサポート体制が整ったサービスがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ おすすめのクラウド型社内ポータルサイトまとめ ここまで、おすすめのクラウド型社内ポータルサイトや選定ポイント、上手く運用できない原因をご紹介しました。 クラウド型社内ポータルサイトで社内情報を一元化すれば、格納場所が分散していた資料やデータを体系的にまとめられ、仕事で活用しやすくなります。また、全社共通で周知したい情報もスムーズに共有できるので、業務効率の向上が期待できるのです。 なかでも「検索性の高いサービス」であれば、共有した情報をあとから簡単に振り返ることができます。一方、多機能で複雑な操作性の社内ポータルを導入すると、社員が使いこなせないため「誰でも簡単に使える操作性やデザインのサービス」を選びましょう。 結論、社内ポータルサイトの構築には、シンプルな操作性で簡単に情報共有ができ、高精度の検索機能で欲しい情報がすぐに見つかるツール「ナレカン」が最適です 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、ナレッジ管理・共有のストレスを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 <100人~数万名規模>の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します!https://www.narekan.info/ Googleサイト|社内ポータルの作り方と活用事例を解説!続きを読む
最新の投稿
おすすめ記事

